Page 1
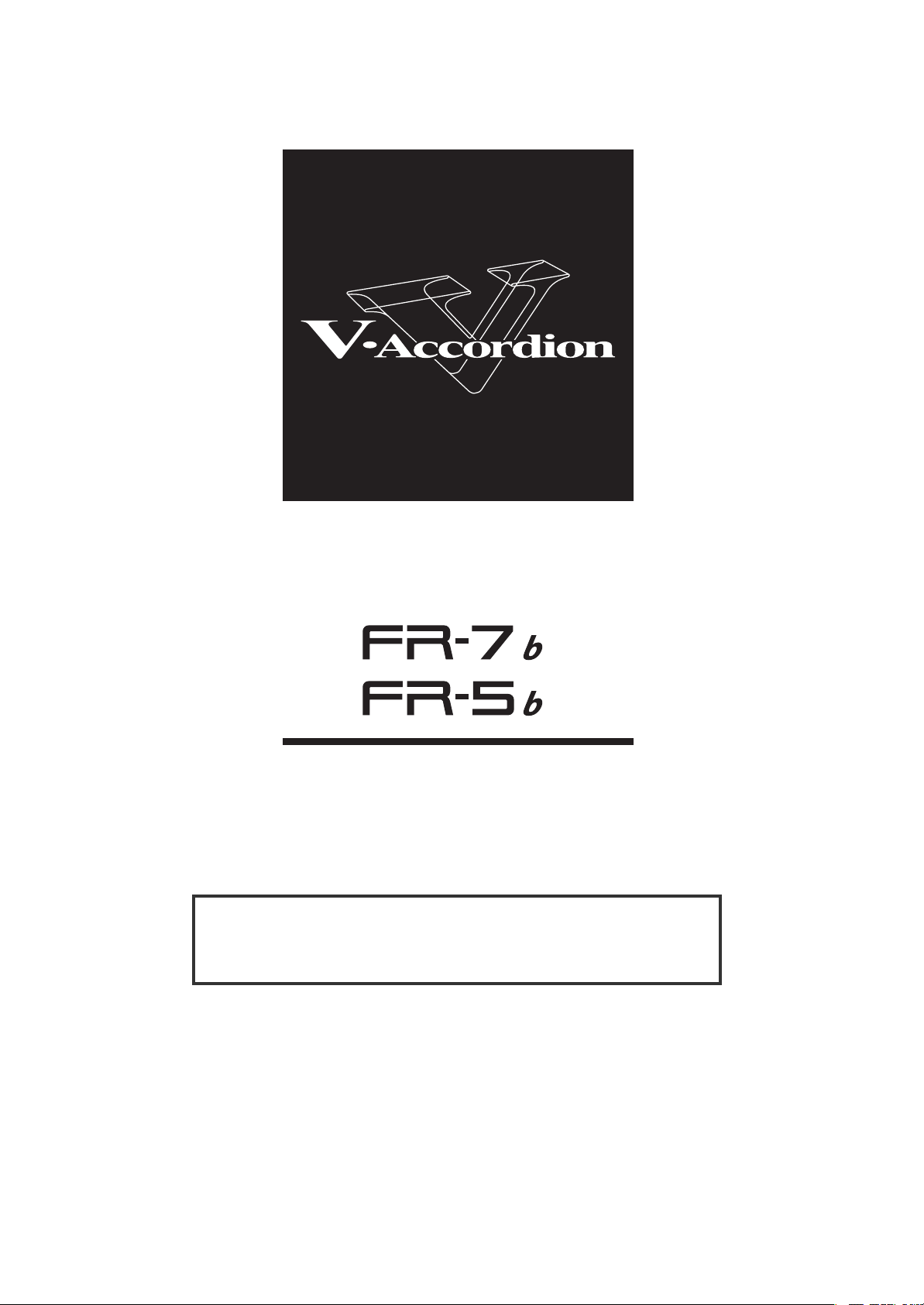
取扱説明書
この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)と
「使用上のご注意」(P.5)をよくお読みください。また、この機器の優れた機能を十分
ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なと
きにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。
©
2006 ローランド株式会社
本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。
Page 2
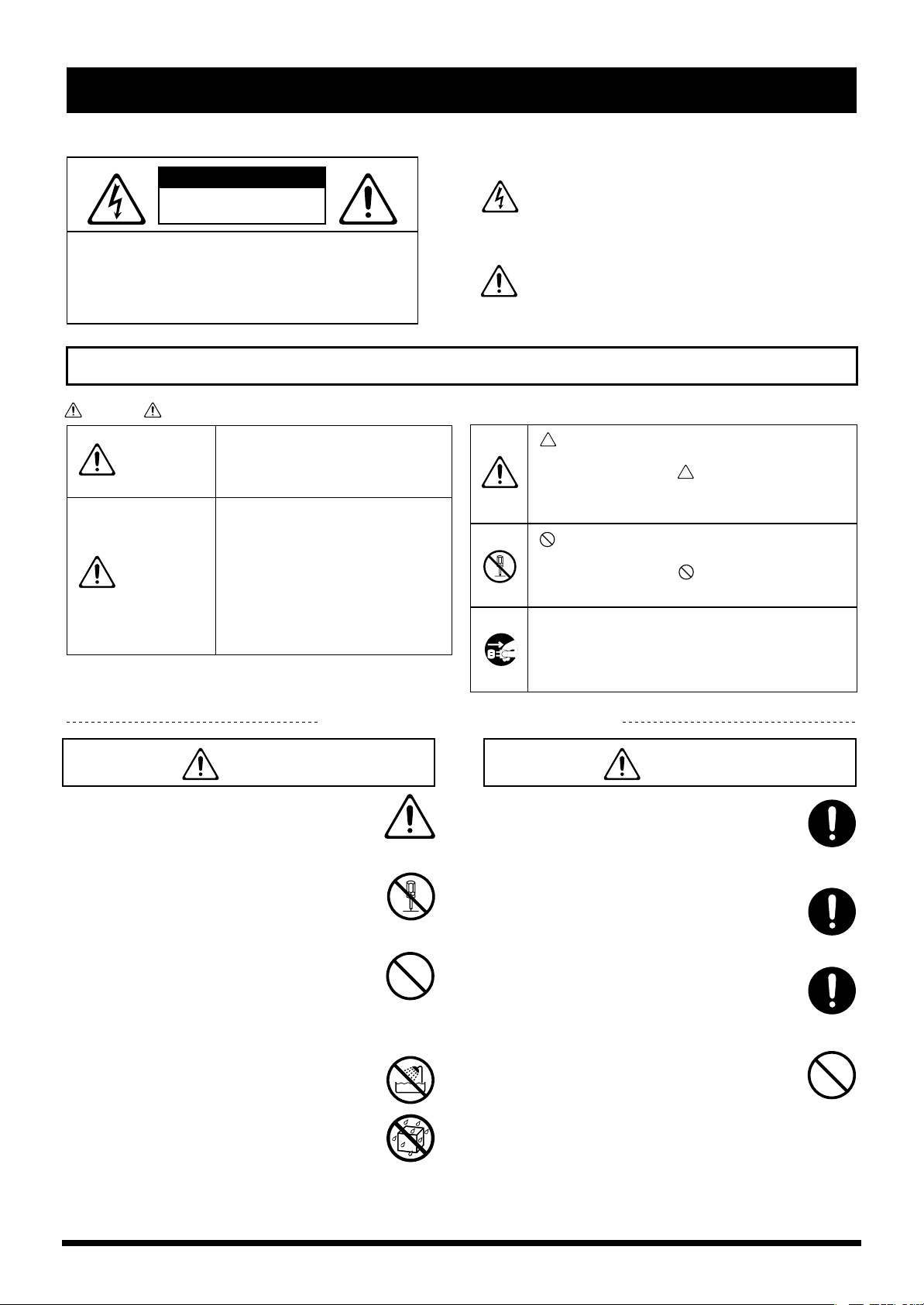
安全上のご注意
安全上のご注意
火災・感電・傷害を防止するには
このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書
などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ
れていることを表わしています。
このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危
険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警
告しています。
マークについて この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。
以下の指示を必ず守ってください
図記号の例
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。
※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
●は、強制(必ずすること)を表わしています。
具体的な強制内容は、
●の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。
警告
注意
注意の意味について警告と
は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。
は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。
注意:
感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。
この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品
はありません。
修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに
依頼してください。
注意
感電の恐れがあります。
キャビネットをあけないでください。
警告
● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書を
よく読んでください。
..............................................................................................................
002c
● この機器および DC パワーユニット(FBC-7)を分解
したり、改造しないでください。
..............................................................................................................
003
● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていな
いことは、絶対にしないでください。必ずお買い上げ
店またはローランド・サービスに相談してください。
..............................................................................................................
004
● 次のような場所での使用や保存はしないでください。
○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、
暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や
湿度の高い場所
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
..............................................................................................................
警告
2
007
● この機器を、ぐらつく台の上や傾いた場所に設置しな
いでください。必ず安定した水平な場所に設置してく
ださい。
..............................................................................................................
008c
● 必ず付属の DC パワーユニット(FBC-7)を AC100V
の電源で使用してください。
..............................................................................................................
008e
● 電源コードは、必ず付属のものを使用してください。
また、付属の電源コードを他の製品に使用しないでく
ださい。
..............................................................................................................
009
● DC パワーユニット(FBC-7 )の電源コードや 19 ピ
ン・ケーブルを無理に曲げたり、これらケーブル類の
上に重いものを載せたりしないでください。ケーブル
類に傷がつき、ショートや断線の結果、火災や感電の
恐れがあります。
..............................................................................................................
Page 3
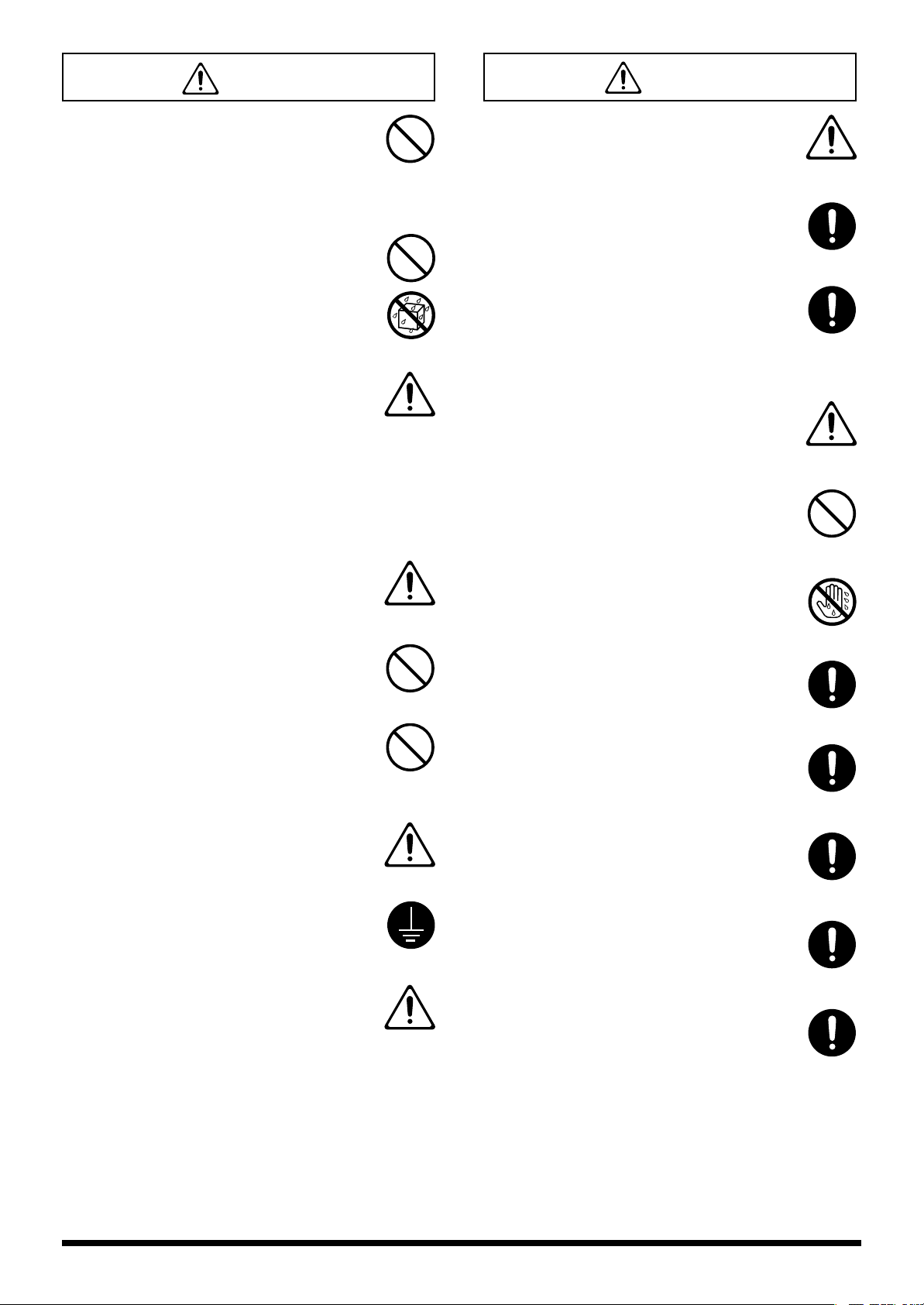
警告
注意
010
● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、ス
ピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によって
は永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量
で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や
耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に
相談してください。
..............................................................................................................
011
● この機器と DC パワーユニット(FBC-7)に、異物(燃
えやすいもの、硬貨、針金など)や液体(水、ジュー
スなど)を絶対に入れないでください。
..............................................................................................................
012b
● 次のような場合は、直ちに電源を切って電源コードを
コンセントから外し、お買い上げ店またはローラン
ド・サービスに修理を依頼してください。
○ DC パワーユニット(FBC-7)本体、電源コード、
またはプラグが破損したとき
○ 煙が出たり、異臭がしたとき
○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたと
き
○ 機器が(雨などで)濡れたとき
○ 機器に異常や故障が生じたとき
..............................................................................................................
013
● お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱
いやいたずらに注意してください。必ず大人のかた
が、監視/指導してあげてください。
..............................................................................................................
014
● この機器や DC パワーユニット(FBC-7)を落とした
り、この機器に強い衝撃を与えないでください。
..............................................................................................................
015
● 電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでくだ
さい。特に、電源タップを使用している場合、電源
タップの容量(ワット/アンペア)を超えると発熱し、
コードの被覆が溶けることがあります。
..............................................................................................................
016
● 外国で使用する場合は、お買い上げ店またはローラン
ド・サービスに相談してください。
..............................................................................................................
024
● DC パワーユニット( FBC-7)の電源コードのアース
を確実に取り付けてください。感電の恐れがあります
(P.19 )。
..............................................................................................................
026
● この機器と DC パワーユニット(FBC-7)の上に水の
入った容器(花びんなど)、殺虫剤、香水、アルコー
ル類、マニキュア、スプレー缶などを置かないでくだ
さい。また、表面に付着した液体は、すみやかに乾い
た柔らかい布で拭き取ってください。
..............................................................................................................
101b
● この機器と DC パワーユニット(FBC-7)は、風通し
のよい、正常な通気が保たれている場所に設置して、
使用してください。
..............................................................................................................
102c
● DC パワーユニット(FBC-7)の電源コードを機器本
体やコンセントに抜き差しするときは、必ずプラグを
持ってください。
..............................................................................................................
103b
● 定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でゴミやほこり
を拭き取ってください。また、長時間使用しないとき
は、電源プラグをコンセントから外してください。電
源プラグとコンセントの間にゴミやほこりがたまる
と、絶縁不良を起こして火災の原因になります。
..............................................................................................................
104
● 接続したコードやケーブル類は、繁雑にならないよう
に配慮してください。特に、コードやケーブル類は、
お子様の手が届かないように配慮してください。
..............................................................................................................
106
● この機器や DC パワーユニット(FBC-7)の上に乗っ
たり、機器の上に重いものを置かないでください。
..............................................................................................................
107c
● 濡れた手で DC パワーユニット(FBC-7)の電源コー
ドのプラグを持って、機器本体やコンセントに抜き差
ししないでください。
..............................................................................................................
108b
● この機器を移動するときは、DC パワーユニット(FBC7)の電源コードをコンセントから外し、外部機器と
の接続を外してください。
..............................................................................................................
109b
● お手入れをするときには、電源を切って DC パワーユ
ニット(FBC-7)の電源コードをコンセントから外し
てください(P.19 )。
..............................................................................................................
110b
● 落雷の恐れがあるときは、早めに DC パワーユニット
(FBC-7)の電源コードをコンセントから外してくだ
さい。
..............................................................................................................
● この機器を使用していないときは、不安定になります
ので縦に(ボタン鍵盤を上に)置かないでください。
もし、縦に置く場合は、壁や重量のある機材など、安
定した面にもたれるように置いてください。
..............................................................................................................
118c
● 取り外したリファレンス・キャップ(ボタン)やバッ
テリー・カバーのネジは、小さなお子様が誤って飲み
込んだりすることのないようお子様の手の届かない
ところへ保管してください。
..............................................................................................................
3
Page 4
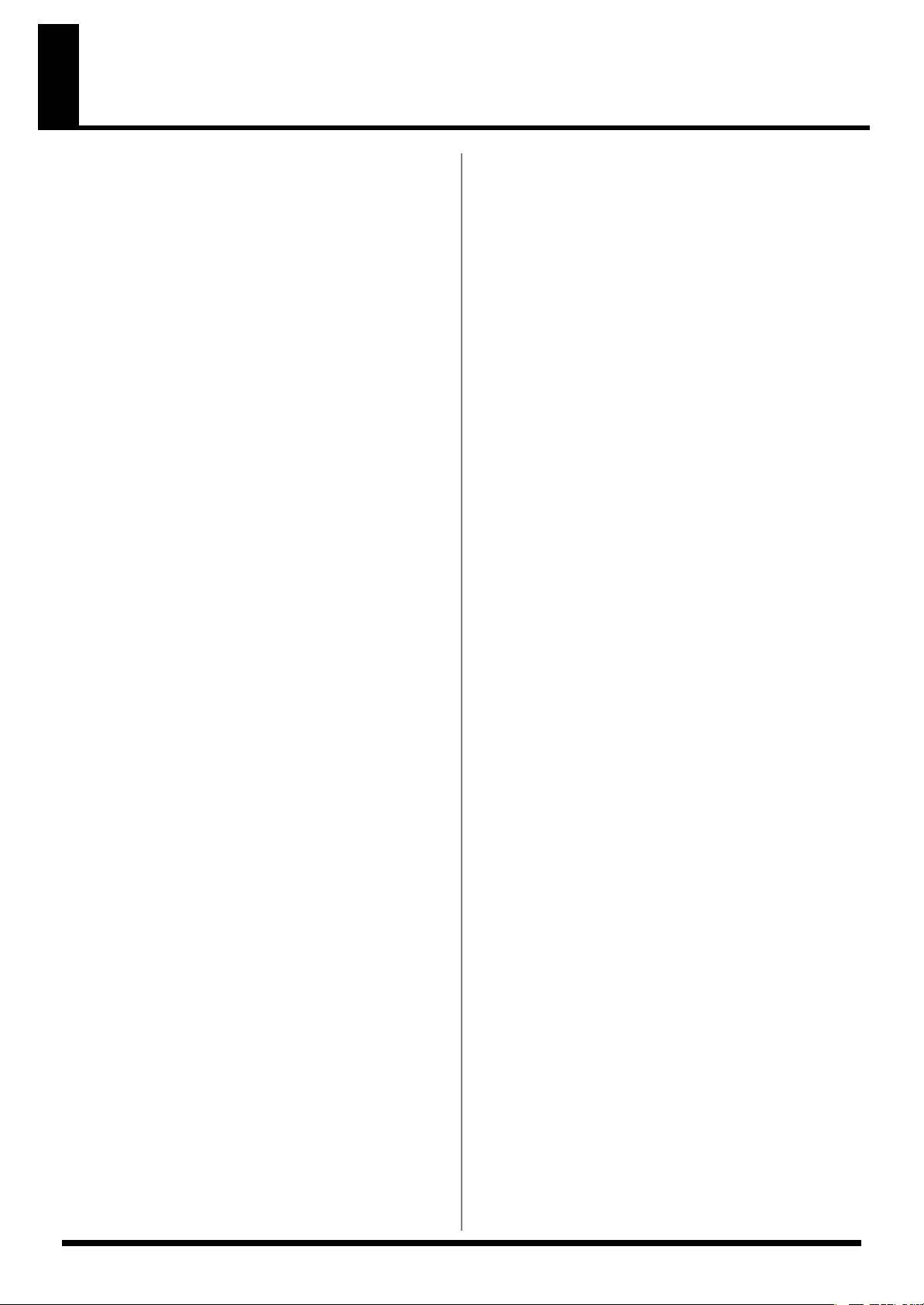
使用上のご注意
291a
2 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次の
ことに注意してください。
電源、電池のセットや交換について
301
● 本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどのイ
ンバーター制御の製品やモーターを使った電気製品が接
続されているコンセントと同じコンセントに接続しない
でください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイ
ズにより本機が誤動作したり、雑音が発生する恐れがあ
ります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、
電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。
304a
● 電池のセットや交換は、誤動作やスピーカーなどの破損
を防ぐため、他の機器と接続する前にこの機器の電源を
切った状態で行なってください。
307
● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ
ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。
308
● 電源スイッチを切った後、FR-7b / 5b 本体や DC パ
ワーユニット(FBC-7)の LCD や LED などは消えます
が、これは主電源から完全に遮断されているわけではあ
りません。完全に電源を切る必要があるときは、これら
の機器の電源スイッチを切った後、コンセントからプラ
グを抜いてください。そのため、電源コ−ドのプラグを
差し込むコンセントは、これらの機器にできるだけ近い、
すぐ手の届くところのものを使用してください。
設置について
352b
● 携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着
信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあり
ます。この場合は、それらの機器を本機から遠ざけるか、
もしくは電源を切ってください。
354a
● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め
切った車内などに放置しないでください。変形、変色す
ることがあります。
355b
● 極端に温湿度の違う場所に移動すると、内部に水滴がつ
く(結露)ことがあります。そのまま使用すると故障の
原因になりますので、数時間放置し、結露がなくなって
から使用してください。
358
● ボタン鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。
発音しなくなるなどの故障の原因になります。
● 湿気の多い場所や雨のあたる場所で使用しないでくださ
い。故障の原因になります。
● 本機の上に、ゴムやビニール素材などのものを置かない
でください。変形、変色することがあります。
● 花びんなどの水が入ったものを置かないでください。ま
たベンジン、シンナーおよびアルコール類などを本機に
つけないようにしてください。ついてしまった場合は、
柔らかい布で乾拭きしてください。
● ステッカーやシール、テープなど強力な粘着力のあるも
のを貼らないでください。変形、変色することがありま
す。
お手入れについて
401a
● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く
絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいと
きは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔
らかい布で乾拭きしてください。
402
● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル
コール類は、使用しないでください。
修理について
451a
● お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能
について保証できなくなります。また、修理をお断りす
る場合もあります。
452
● 修理に出される場合、記憶した内容が失われることがあ
ります。大切な記憶内容は、バルク・ダンプ機能
(P.104)を使って外部 MIDI 機器に保存するか、記憶内
容をメモしておいてください。修理するときには記憶内
容の保存に細心の注意を払っておりますが、メモリー部
の故障などで記憶内容が復元できない場合もあります。
失われた記録内容の修復に関しましては、補償も含めご
容赦願います。
453a
● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維
持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し
ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて
いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇
所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上
げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く
ださい。
● パワー・アンプなどの、高出力機器の近くでは、雑音が
発生する恐れがあります。その場合は、それらの機器か
ら離してお使いください。
● テレビやラジオの近くでは、それらの電波によって雑音
が発生する恐れがあります。その場合は、それらの機器
から離してお使いください。
● スピーカーなどの強い磁気を発生するものの近くでは使
用しないでください。
4
その他の注意について
551
● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、
失われることがあります。失っても困らないように、大
切な記憶内容は、バックアップとしてバルク・ダンプ機
能(P.104)を使って外部 MIDI 機器に保存しておいてく
ださい。
● 本体メモリーの失われた記憶内容の修復に関しましては、
補償を含めご容赦願います。
Page 5
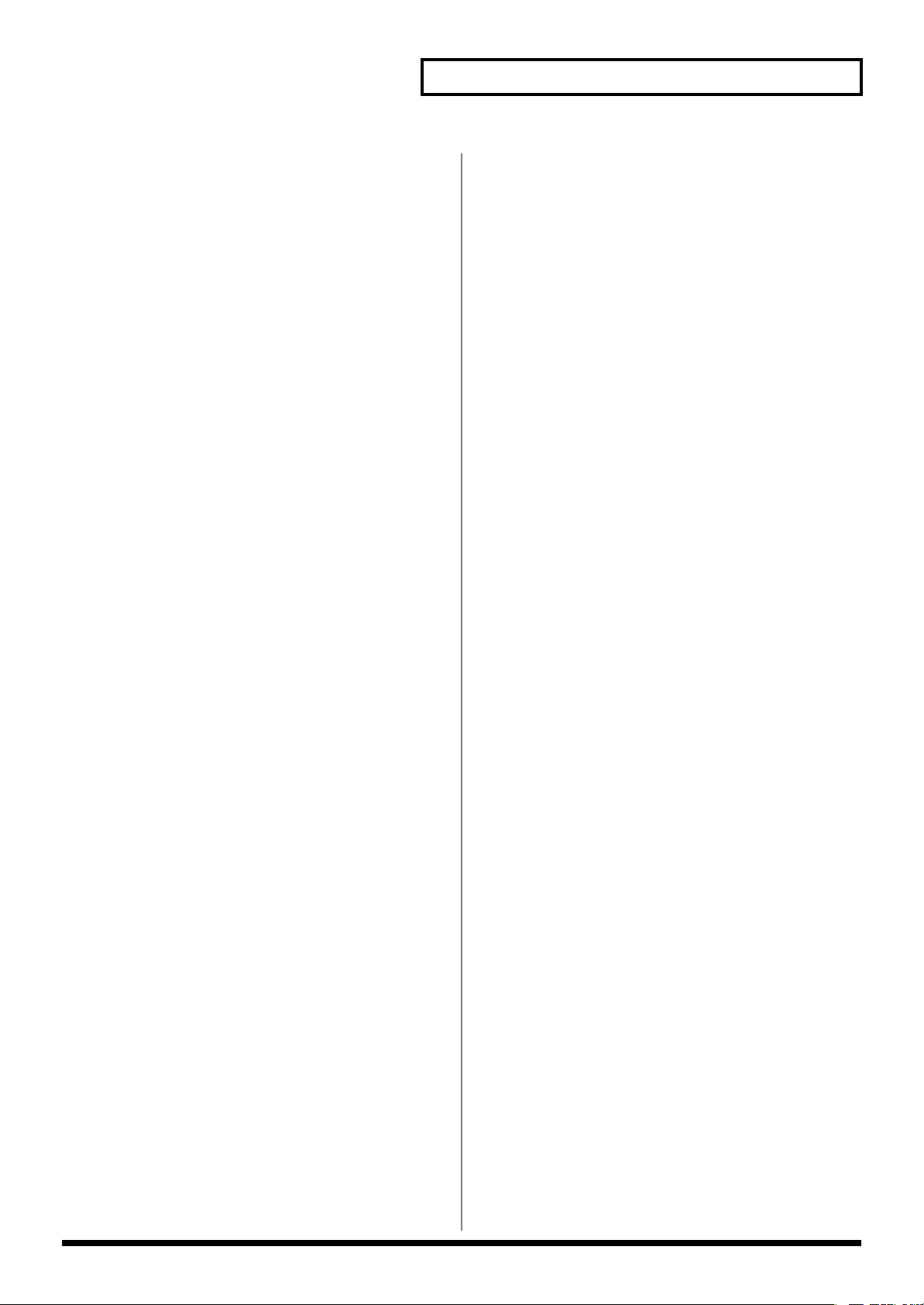
使用上のご注意
553
● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端
子などに過度の力を加えないでください。
556
● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ
ラグを持ってください。
557
● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあ
りません。
558a
● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない
ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。
ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ
ます。
559a
● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダ
ンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
559c
● この機器が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄する場合、
各市町村のゴミの分別基準に従って行ってください。
561
● エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの(別
売:EV シリーズ)をお使いください。他社製品を接続
すると、本体の故障の原因になる場合があります。
● 故障の原因になりますので、ディスプレイをたたいたり、
過度の力を加えないでください。
● 接続には、当社ケーブルをご使用ください。他社製の接
続ケーブルをご使用になる場合は、次の点にご注意くだ
さい。
● 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本機と
の接続には、抵抗入りのケーブルを使用しないでくださ
い。音が極端に小さくなったり、全く聞こえなくなる場
合があります。ケーブルの仕様につきましては、ケーブ
ルのメーカーにお問い合わせください。
バッテリー(FR-7b のみ付属)につ
いて
● バッテリーを使用、保管、充電する場合は、以下の温度
範囲で行ってください。
使用する場合(充電は行わない):0 〜 50 度
保管する場合:マイナス 20 〜 30 度
充電する場合:0 〜 40 度
● 範囲外の温度でご使用になると、性能や寿命を低下させ
る原因となります。
● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め
切った車内などで使用しないでください。液漏れや性能、
寿命を低下させる原因となります。
● 0 度以下、または温度の低い屋外で充電を行わないでく
ださい。液漏れや性能、寿命を低下させる原因となりま
す。
● 水をかけたり、端子部を濡らさないでください。発熱や
さびの原因となります。
● 指定以外の充電器(FBC-7、付属)を使用しないでくだ
さい。未充電、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となり
ます。
● バッテリーの充電のしかたについて詳細は、「バッテリー
を充電する」(P.23)をご覧ください。
● 直接電源コンセントや車の電源に接続しないでください。
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
● お買い上げ後に初めてご使用になるときに、発熱したり、
異常がみられる場合は、お買い上げ店またはローラン
ド・サービスにご相談ください。
● 初めて充電する場合は、バッテリーの残電池を使い切っ
てから充電を行ってください。
● お子様の手が届かないように保管してください。また充
電はお子様の手が届かない場所で行ってください。
● ご使用方法にしたがって、正しくご使用ください。
● 火の中へ入れたり、温めないでください。化学反応を起
こし、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
● プラス(+)とマイナス(−)を逆にして使用、充電し
ないでください。消耗や異常反応の原因になります。通
常の使用、充電では、逆にすることができないように
なっています。
● バッテリーの外側の被覆をはがしたり、破損させないで
ください。
● たたいたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでく
ださい。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
● 並列に 2 つ以上のバッテリーを接続しないでください。
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
5
Page 6
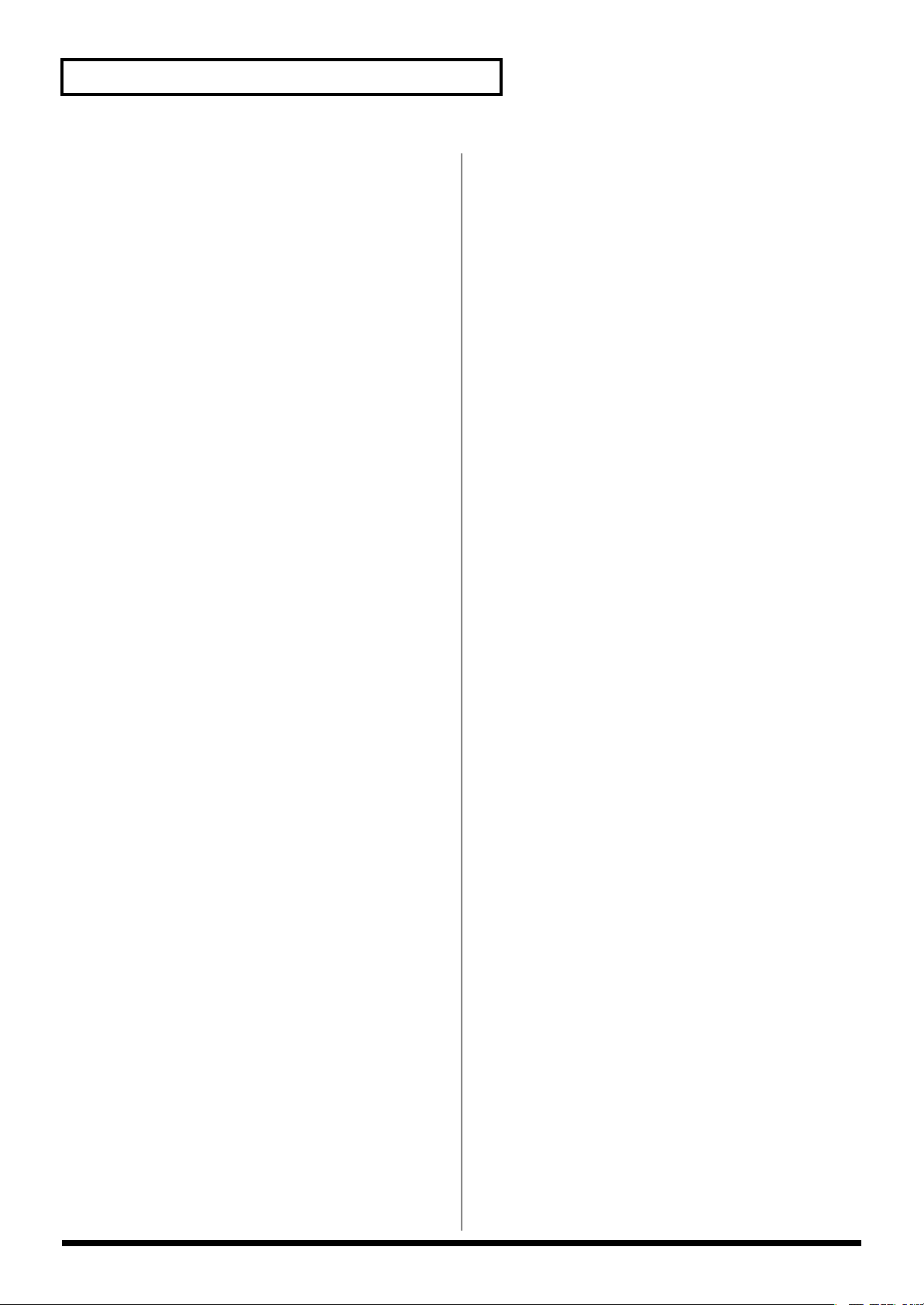
使用上のご注意
● 分解、改造をしないでください。
● 端子のプラス側には通気孔がありますが、変型させたり、
ふさがないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原
因となります。
● 充電中、充電器(FBC-7、付属)のランプが緑色に点灯
したら、充電完了です。そのまま続けて過充電しないで
ください。また充電済みのバッテリーを充電しないでく
ださい。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
● 充電中、充電器(FBC-7、付属)のランプが緑色に点灯
したあと、フル充電されない場合でも、一度充電を中断
してください。続けて充電しないでください。液漏れ、
発熱、破裂、発火の原因となります。
● バッテリーの液が漏れて目に入った場合、すぐにきれい
な水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてく
ださい。強アルカリ性ですので、目に障害を与え、失明
するおそれがあります。
● バッテリーの液が漏れて衣服や身体についた場合、すぐ
にきれいな水でよく洗い流してください。身体に障害を
与えるおそれがあります。
● バッテリーを廃棄する場合、各市町村のゴミの分別基準
に従ってください。
● 液漏れ、変色、変型したバッテリーを使用しないでくだ
さい。発熱、破裂、発火の原因となります。
● 電池のショートは、絶対に避けてください。金属製の
ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管
しないでください。ショートさせた場合、過大な電流が
流れ、電池を漏液、発熱、破裂、発火させる原因となり、
機器を損傷させたり、やけど等人体に傷害をおよぼすお
それがあります。
● 電池を本製品以外の機器に使わないでください。誤用に
よって電池性能を劣化させたり、機器を損傷させたりす
ることがあります。場合によっては異常な電流が流れ、
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。
ストラップ・ホルダーに関する注意
● ストラップ・ホルダーと本体を固定しているネジは、絶
対に外さないでください。ネジを着脱した結果、本体の
プラスチック・ケースが破損し、最悪の場合、本体が落
下する恐れがあります。
6
Page 7
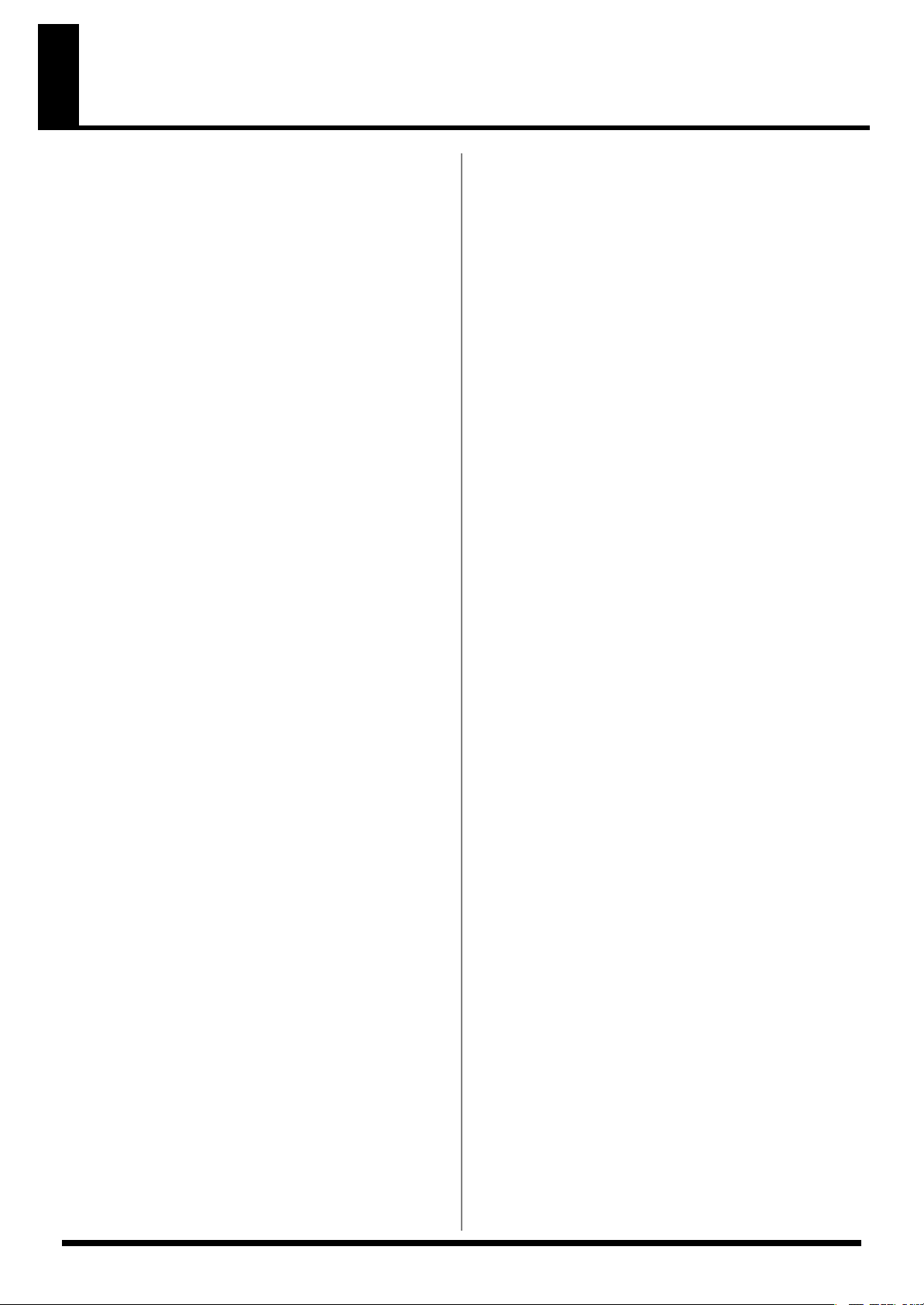
主な特長
●アコーディオンの豊かな表現力を受け継いだ PBM
音源
新たなアコーディオンの世界を生みだすために、最新のローランド
音源テクノロジーをベースに、発音原理そのものからアコース
ティック・アコーディオン各部の振る舞いを精密にモデリングした
PBM(Physical Behavior Modeling) 音源を搭載。アコーディオン
の奏法を最大限に活した演奏が可能です。
たとえば、ベローズ(蛇腹)による微妙な空気の動きを感知し、各
リードの反応も個別にモデリングして発音。ベローズの動きに応じ
て音量・音色・音程もダイナミックかつナチュラルに変化します。
さらに、ボタン演奏時に生じるパーカッシブなタッチ・ノイズや、
ボタンを離した時の微妙なリード・ノイズ、ベローズの弁開閉ノイ
ズといった音楽的に重要なノイズも再現します。
●プロ用高級モデルをも超える驚異の表現力
アコーディオン音色を生みだすトレブル(右手ボタン)リードは最
大 7 リード。幅広いジャンルで好まれる HMML タイプから、流行
のミュゼット・トーンが得られる MMML タイプも一台で表現する
ことができます。さらに、プロ・モデル級の HMMML に加え、本
機ならではの 2-2/3'、5-1/3' も組み合わせることができます。
トレブル・レジスターは 14 種類を搭載。また、ベース用 5 リード、
コード用 3 リードの組み合わせが可能なベース・レジスターも 7 種
類を搭載。
さらに、チャンバー(木製共鳴室)の開口部を閉じて音をこもら
せ、丸みのある音色が得られる高級アコースティック・アコーディ
オンの特徴的な機構もモデリング。しかも、各リードやフッテージ
ごとにそれぞれ個別に設定できる CASSOTTO と、スイッチのオン
/ オフだけでトレブル・セクション全体に設定できる SORDINA を
装備しています。
●フル・カスタマイズによる自分だけの夢の一台
バンドネオンやテックスメックス、アルペンなど世界各地の個性的
なアコーディオンも再現。ブライトで金属的な響きのリードや、メ
ローで優しい響きのリード、さらには個性的な 16 フィートのリー
ドを重ねたダブル・バスーンや 32 フィートの音域までサポートし
ています。これらのリードの組み合わせやチャンバーの有無など、
プロがメーカーにカスタム・モデルをオーダーする感覚で音づくり
が楽しめます。
また、ミュゼット・チューニングにより、懐かしの曲ならデチュー
ンの多い豊かな響きに、今風の音色ならうねりの少ないインチュー
ンにするなど、チューニングを自在に設定でき、ワンタッチで選択
も可能です。これらの設定は、40 種類の「セット」として本体に
保存することができます。
●オーケストラ音色やエフェクトを組み合わせた多彩
な演奏
トレブル・セクションには、アコーディオンの音色だけでなく、22
種類のオーケストラ音色を内蔵しています。フルートやサックス、
オルガンなどベローズの表現力を最大限に活かせる音色と、ピアノ
やギターなどベローズを使用しなくとも発音できる音色の 2 タイプ
で構成、多彩な楽器音で個性的な表現が楽しめます。
ベース・セクションには、さまざまな奏法のアコースティック・
ベースやエレクトリック・ベースといった 7 種類のオーケストラ・
ベース・サウンドをはじめ、トロンボーン、クラリネット、オルガ
ン、アコースティック・ギターなど 7 種類のオーケストラ・コー
ド・サウンド、オーケストラ・フリー・ベース・サウンドも搭載し
ています。
さらに、音に空間的な広がりを与えるリバーブやコーラス、ディレ
イを内蔵。メロディを引き立て、ホールのような演奏感も演出でき
ます。
●デジタル・アコーディオンならではの使いやすさ
音量調節が自由自在で、ヘッドホンを使えば、夜間の練習なども気
兼ねなく行えます。さらに、アコースティック・アコーディオンの
ように定期的なリードのメンテナンスなども必要なく、安定した
チューニングが持続します。
また、アンプやミキサーに直結できるため、ステージではマイクを
使用した時のようにハウリングを心配することがなく、右手と左手
の演奏を鮮やかなセパレーションで表現できるステレオ出力が可
能。さらに、ギター用のワイヤレス・システムを使えば、自由なス
テージングを実現することができます。
●スタンドアローン・タイプの電子楽器
小さな会場やレストランなどでは必要十分なパワーを持つアンプと
スピーカーを内蔵しています(FR-7b のみ)。
さらに、充電タイプのバッテリー(最大 8 時間使用可)を搭載でき
るので、ケーブルなしで、演奏しながら自由に動き回ることができ
ます。
●フット・スイッチ / バッテリー・チャージャー
(FBC-7)を標準装備
フット操作でレジスターの切り替えやサスティン効果のオン / オ
フ、さらにステレオ・ライン出力や MIDI 送受信、製品への電源供
給やバッテリー充電機能などを可能にします。ステージなどでは、
FBC-7 が専用ケーブルにより本体に電源を供給するためバッテリー
は必要ありません。また音声出力も FBC-7 経由でアンプや PA シ
ステムなどに送ることができます。
●高度な奏法に対応するベース & コード・セクション
左手ボタン配列は、奏法に合わせて多彩な切り替えを実現。通常の
ストラデラ・ベース・モードでは、ベースを 2 列にするか 3 列にす
るかを選択可能。さらに高度なフリー・ベース・モードへ切り替え
もでき、Minor 3rd、Bajan、5th、N.Europe、Finnish の 5 配列を
サポート。
●洗練された MIDI コントロール機能
FBC-7 を経由して、MIDI 接続による外部シーケンサーとの連携プ
レイや、他の音源を従えた重厚な演奏も実現します。ピアノ・タイ
プのトレブル・キーボードはアフタータッチ・メッセージも送信可
能です。
7
Page 8
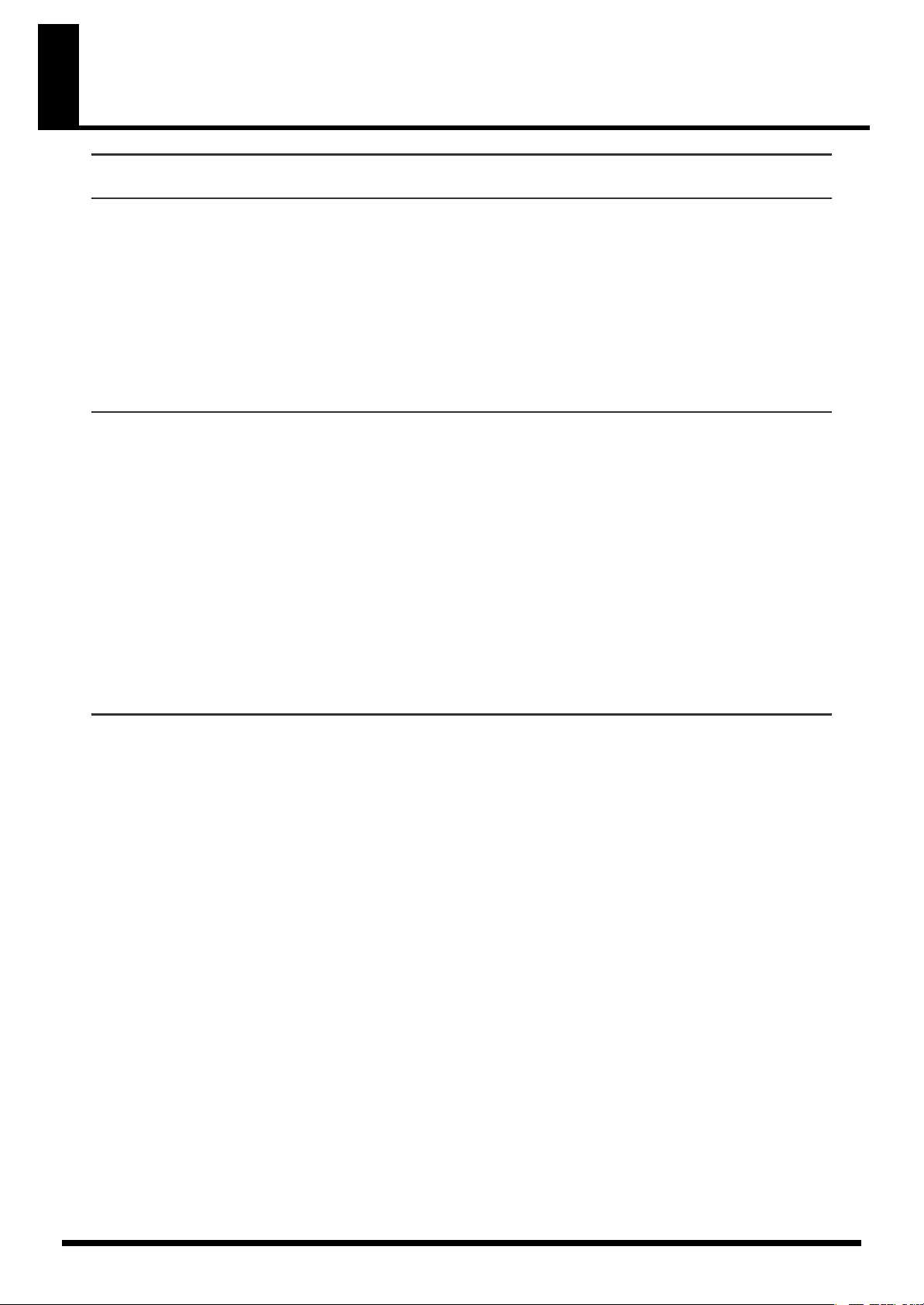
目次
主な特長 ...................................................................................... 7
はじめに ....................................................................................10
V-Accordion(V- アコーディオン)とは .................................................................................. 10
本機の構成について............................................................................................................................................ 11
各部名称とはたらき................................................................................................................... 12
トレブル・セクション .......................................................................................................................................12
ベース・セクション............................................................................................................................................ 14
マスター・バー、ディスプレイ.......................................................................................................................15
接続パネル ............................................................................................................................................................15
フット・スイッチ(FBC-7)背面...................................................................................................................16
準備する ....................................................................................17
接続する................................................................................................................................... 17
FBC-7、外部オーディオ機器を接続する ......................................................................................................17
本体の OUTPUT ジャックを使う(バッテリーを使用した場合)............................................................18
電源コードの接続................................................................................................................................................18
電源を入れる、電源を切る ......................................................................................................... 19
FBC-7 を使用する場合 ...................................................................................................................................... 19
バッテリーを使用し、アンプなどに接続しない場合(FR-7b のみ)...................................................... 20
バッテリーを使用し外部オーディオ機器に接続する場合 .........................................................................20
デモ・ソングを聴く................................................................................................................... 21
バッテリー(FR-7b のみ付属)の準備をする .............................................................................. 21
バッテリーを本機に内蔵する........................................................................................................................... 22
バッテリーを充電する .......................................................................................................................................23
演奏する ....................................................................................24
演奏の前に................................................................................................................................ 24
ディスプレイについて .......................................................................................................................................24
イージー・モードとフル・モードを選択する..............................................................................................25
アコーディオンの音色で演奏する................................................................................................ 26
セットを選ぶ........................................................................................................................................................ 26
トレブル・セクションを演奏する(トレブル・パート)........................................................................... 26
ベース・セクションを演奏する(ベース・パート)....................................................................................28
オーケストラの音色で演奏する................................................................................................... 31
トレブル・セクションでオーケストラ音色を使う(オーケストラ・パート)......................................31
ベース・セクションでオーケストラ音色を使う(オーケストラ・ベース・パート)..........................34
コード・セクションでオーケストラ音色を使う(オーケストラ・コード・パート)..........................35
フリー・ベース・セクションでオーケストラ音色を使う
(オーケストラ・フリー・ベース・パート).................................................................................................. 36
デジタル・エフェクトを使う ...................................................................................................... 37
その他の実践的な機能................................................................................................................ 38
ピッチに関係した機能 .......................................................................................................................................38
音量に関係した機能............................................................................................................................................ 40
フット・スイッチ(FBC-7、付属)について .............................................................................. 41
[SET]スイッチを使う .....................................................................................................................................41
[REGISTER]スイッチを使う.........................................................................................................................41
[SUSTAIN]スイッチを使う...........................................................................................................................41
エクスプレッション・ペダル(別売)を使う..............................................................................................41
各スイッチにいろいろな機能を割り当てる.................................................................................................. 41
8
Page 9
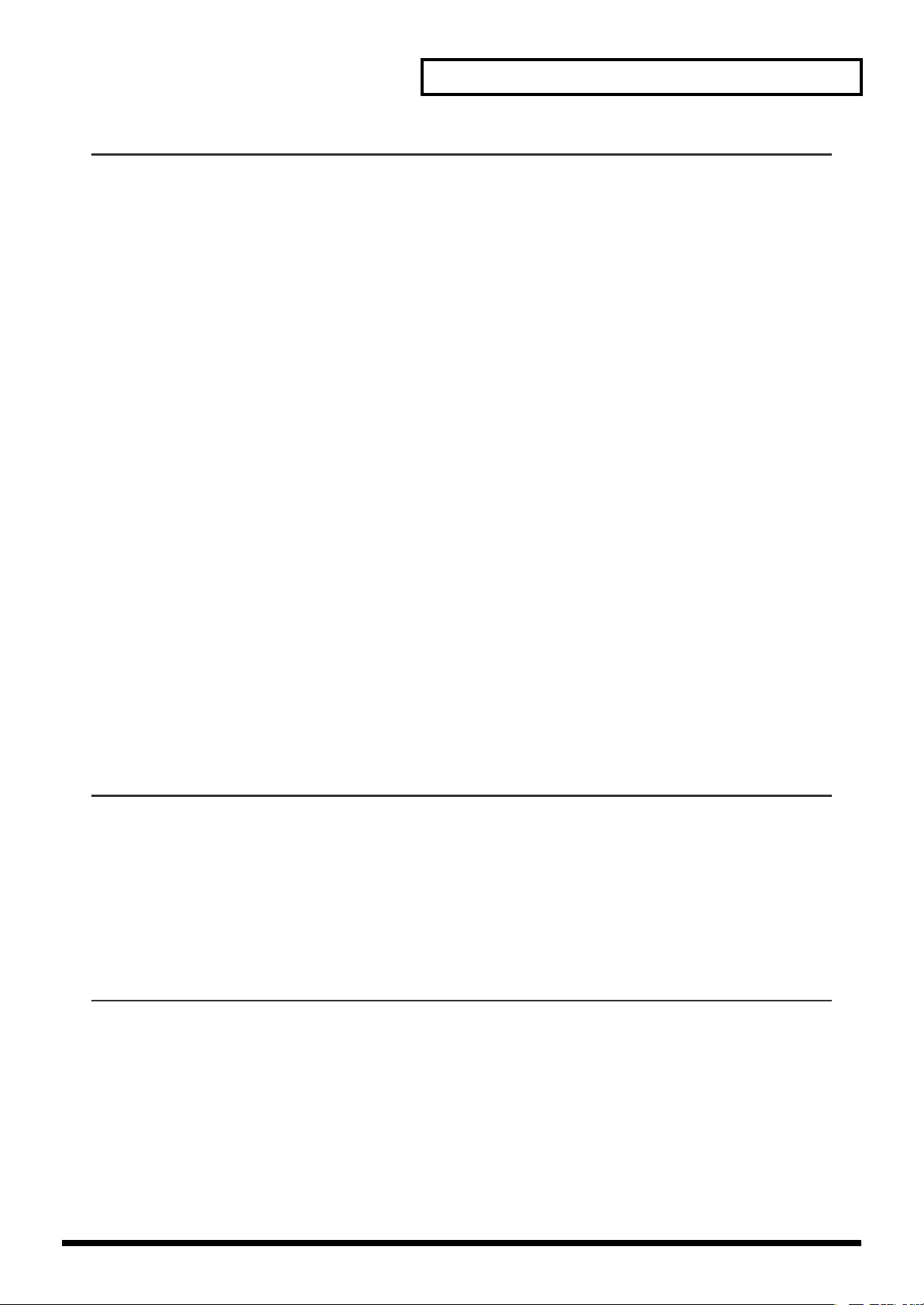
本機の設定をする........................................................................42
設定できる項目について............................................................................................................. 42
設定のしかた ............................................................................................................................ 44
パラメーターを選択する ...................................................................................................................................44
パラメーターの設定を変更する.......................................................................................................................45
「1 TUNING」チューニングの設定をする................................................................................... 46
「2 TREBLE EDIT」トレブル・パートの音色の設定をする......................................................... 48
「3 BASS EDIT」ベース・パート(ストラデラ・ベース・モード)の音色の設定をする ................ 55
「4 FREE BS EDIT」ベース・パート(フリー・ベース・モード)の音色の設定をする .................. 59
「5 ORC.BASS EDIT」オーケストラ・ベース・パートの音色の設定をする ................................. 63
「6 ORCH. EDIT」オーケストラ・パートの音色の設定をする ..................................................... 65
「7 ORC CHD EDIT」オーケストラ・コード・パート音色の設定をする ...................................... 67
「8 ORC FBS EDIT」オーケストラ・フリー・ベース・パート音色の設定をする........................... 69
「9 SET COMMON」セット全体の設定をする .......................................................................... 71
エフェクトの設定をする ...................................................................................................................................72
その他の設定をする............................................................................................................................................ 77
「10 SYSTEM」システムの設定をする ..................................................................................... 78
「11 UTILITY」ユーティリティー設定をする ............................................................................. 89
「12 MIDI」MIDI 設定をする.................................................................................................... 97
MIDI について.......................................................................................................................................................97
MIDI 接続をする ..................................................................................................................................................98
MIDI の使用例.......................................................................................................................................................98
本機の MIDI 設定をする .....................................................................................................................................99
各パートで送信する MIDI の設定をする..................................................................................................... 102
本機の設定を外部 MIDI 機器に保存する(バルク・ダンプ).................................................................. 104
各機能の概要 ..........................................................................................................................107
WRITE(ライト)機能で保存できる設定 ..................................................................................................107
工場出荷時の設定に戻す...........................................................................................................109
目次
資料........................................................................................ 110
故障かな?と思ったら.............................................................................................................. 110
主な仕様.................................................................................................................................112
パラメーター・リスト.............................................................................................................. 114
MIDI インプリメンテーション .................................................................................................. 119
メニュー一覧 ..........................................................................................................................122
セット一覧..............................................................................................................................124
デモ曲一覧..............................................................................................................................124
索引........................................................................................ 125
9
Page 10
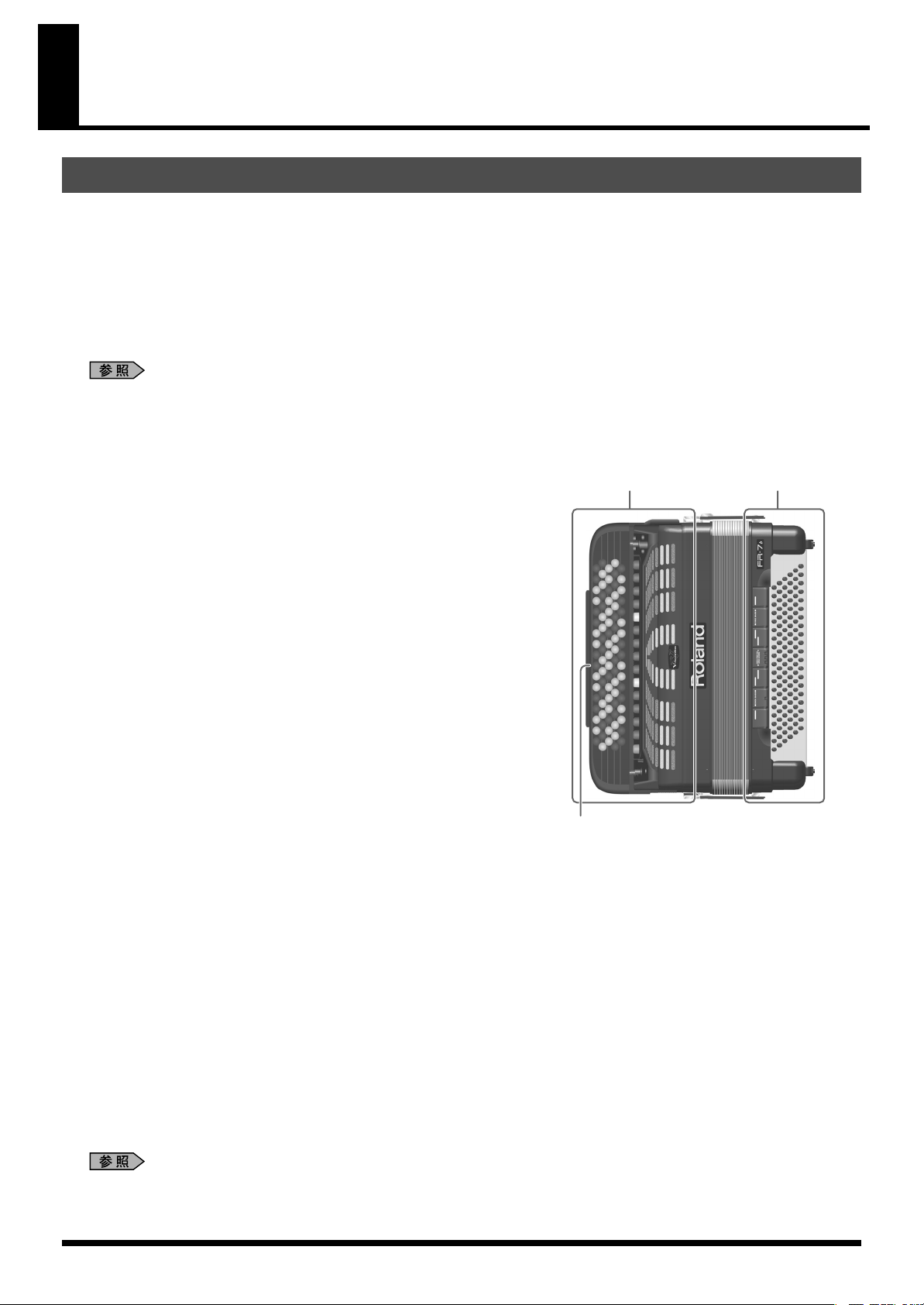
はじめに
トレブル・セクション
マスター・バー
ベース・セクション
V-Accordion(V- アコーディオン)とは
V- アコーディオンは、最新のローランド音源技術をベースに生み出されるさまざまな種類の高品位アコーディオン・サウンドに加え、アコー
ディオンの特徴でもあるベローズ(蛇腹)やリードなどの振る舞いも精密に再現します。
これによって、アコーディオンの奏法を最大限に活かしながら、これまで1台のアコーディオンでは考えられなかったデジタルならではの多彩
な演奏表現が可能になります。
たとえば、いろいろな種類のアコーディオンのリードを組み合わせたり、チューニングを変えたりと、自在にカスタマイズすることができま
す。さらに、トランペットやフルートといったオーケストラ楽器の音色も同時に操ることができます。また、内蔵のリバーブ、コーラス、ディ
レイといったデジタル・エフェクトを使って独自のサウンド、空間を演出することも可能です。
これらの設定は、本体のメモリーに保存しておくことができ、いつでもお好みの音色、設定を使って演奏することができます。
本機を使うための準備をする → 「準備する」(P.17)
本機を演奏する → 「演奏する」(P.24)
本機をカスタマイズする → 「本機の設定をする」(P.42)
トレブル・セクション
右手で演奏する部分です。以下のパートで演奏することができます。
●トレブル・パート(P.26)
アコーディオンの音色で演奏します。トレブル・レジスター・スイッチで音色を選
ぶことができます。
●オーケストラ・パート(P.31)
ピアノや管楽器などのオーケストラ音色で演奏します。トレブル・レジスター・ス
イッチで音色を選ぶことができます。
どちらか一つのパートで演奏することもできますし、同時に演奏することもできます
(オーケストラ・モード、P.32)。
ベース・セクション
左手で演奏する部分です。以下のパートで演奏することができます。
●ベース・パート(P.28)
アコーディオンの音色で演奏します。以下の 2 種類のモードがあります。
ストラデラ・ベース・モード(P.28)
•
左手のボタンの配列方法がストラデラ・ベース配列になります。
フリー・ベース・モード(P.30)
•
左手のボタンの配列方法がフリー・ベース配列になります。
●オーケストラ・ベース・パート(P.34)
オーケストラ・ベースの音色で演奏します。(ストラデラ・ベース・モードとフリー・ベース・モードのどちらでも音色を使うことができま
す。)
●オーケストラ・コード・パート(P.35)
ストラデラ・ベース・モードのときに、オーケストラ・コードの音色で演奏します。
●オーケストラ・フリーベース・パート(P.37)
ストラデラ・ベース・モードのときに、オーケストラ・コードの音色で演奏します。
マスター・バー
お好みの音色をワンタッチで呼び出すことができます(P.28)。また設定によって、さまざまな操作をマスター・バーに割り当てることがで
きます(P.77)。
その他各部の名称、はたらきなどの詳細は「各部名称とはたらき」(P.12)をご覧ください。
10
Page 11
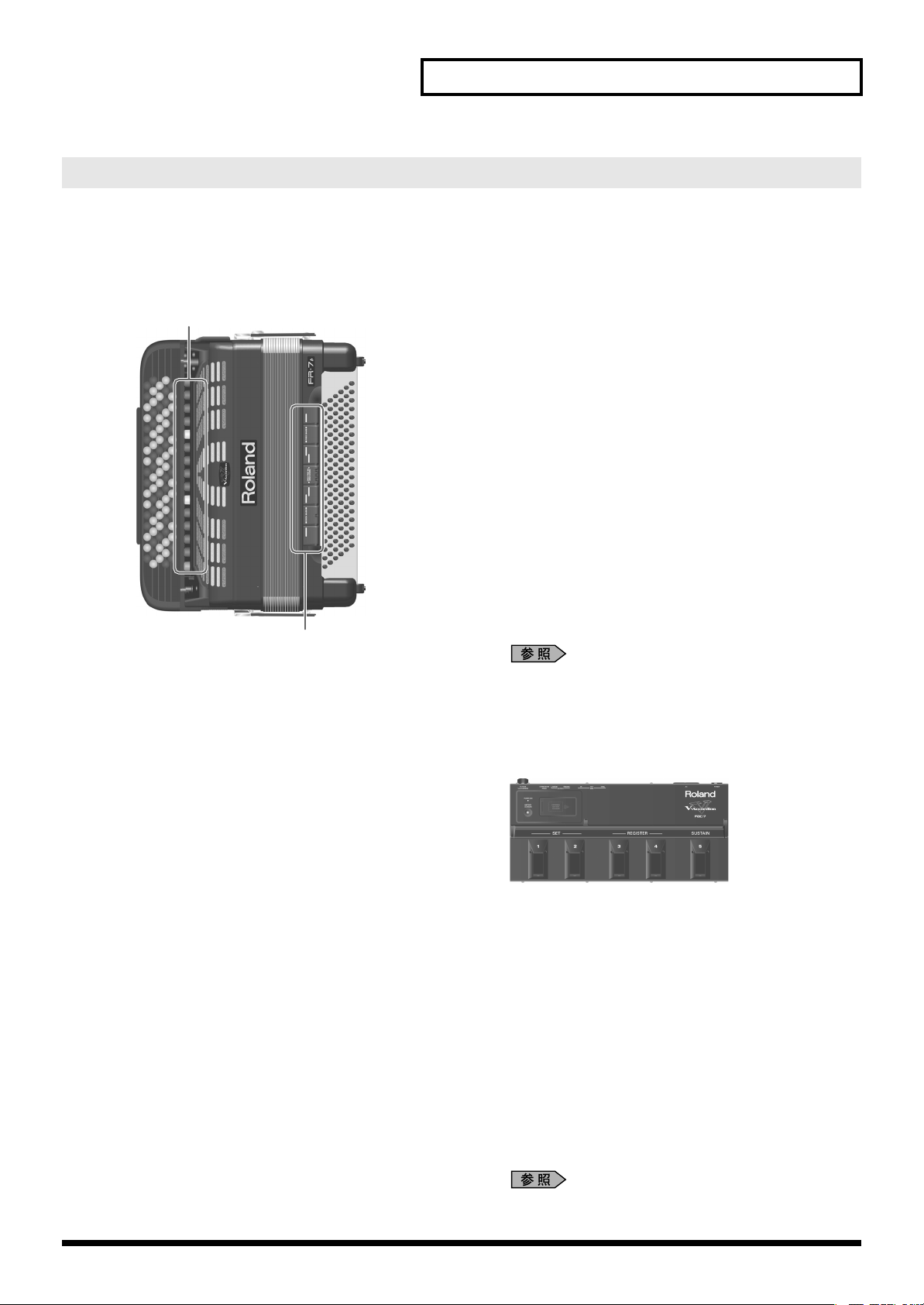
本機の構成について
トレブル・レジスター・スイッチ
ベース・レジスター・スイッチ
はじめに
演奏時に選ぶことができる音色
本機ではアコーディオンのようにトレブル・セクション、ベース・
セクションにレジスター・スイッチが装備されています。
トレブル・レジスター・スイッチでトレブル・セクションの音色、
ベース・レジスター・スイッチでベース・セクションの音色をワン
タッチで選ぶことができます。
また本機はピアノや管楽器などオーケストラのような音色を演奏す
ることができます。その場合、演奏したい音色を、各レジスター・
スイッチでワンタッチに呼び出すことができます。
レジスター・スイッチによって選ぶことができる音色は、どのパー
トを選んでいるかで変わります。
●オーケストラ・コード・パート
ストラデラ・ベース・モードのときに、サックスやアコース
ティック・ギターなどの音色を選ぶことができます。
●オーケストラ・フリー・ベース・パート
フリー・ベース・モードのときにオーボエやオルガンなどの音色
を選ぶことができます。
設定できること
各音色はお好みに合わせていろいろな設定をすることができます。
たとえば、トレブル・レジスター・スイッチの[1]を押して選ん
だ音色のみオクターブをあげたり、ディレイ、リバーブなどのエ
フェクトをかけたり、リードのピッチをずらしたりなど、各レジス
ター・スイッチに登録されている音色に対してそれぞれ違う設定を
することができます。
音色は、トレブル・パート、オーケストラ・パートなど、すべての
パートで独立して設定でき、その状態をまとめて「セット」として
保存することができます。
「セット」は 40 種類まで保存することができ、簡単に呼び出すこと
ができますので、あたかも 40 種類のアコーディオンを持っている
感覚でお使いになれます。
セットについての詳細は、「セットについて」(P.71) をご覧くださ
い。
フット・スイッチ
フット・スイッチ(FBC-7)が付属されています。
各パートで選ぶことができる音色は以下のようになります。
トレブル・セクション
●トレブル・パート
通常のアコーディオンに装備されているような音色を選ぶことが
できます。
●オーケストラ・パート
ピアノや管楽器などの音色を選ぶことができます。
ベース・セクション
●ベース・パート
ストラデラ・ベース・モードとフリー・ベース・モードがあり、
通常のアコーディオンに装備されているような音色を選ぶことが
できます。
●オーケストラ・ベース・パート
アコースティック・ベースやチューバなどの音色を選ぶことがで
きます。
本機に接続すると、以下のように機能します。
•
本機に電源を供給します。
•
セットを切り換えます。
•
トレブル・パート、ベース・パートの音色を選びます。*
•
本機にバッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵した場合、
バッテリーを充電します。
•
MIDI コネクターを装備しており、外部 MIDI 機器を接続する
ことによって MIDI機能が使えます。
•
サスティン・ペダル(ホールド機能)として使えます。
エクスプレッション・ペダル(別売:EV シリーズ)を接続
•
すると、ペダルで音量を調節することができます。
※ ベース・パートの音色は、トレブル・パートと
のリンク時のみ選ぶことができます(P.52)。
フット・スイッチについての詳細は、「フット・スイッチ(FBC-7、
付属)について」(P.41)をご覧ください。
11
Page 12
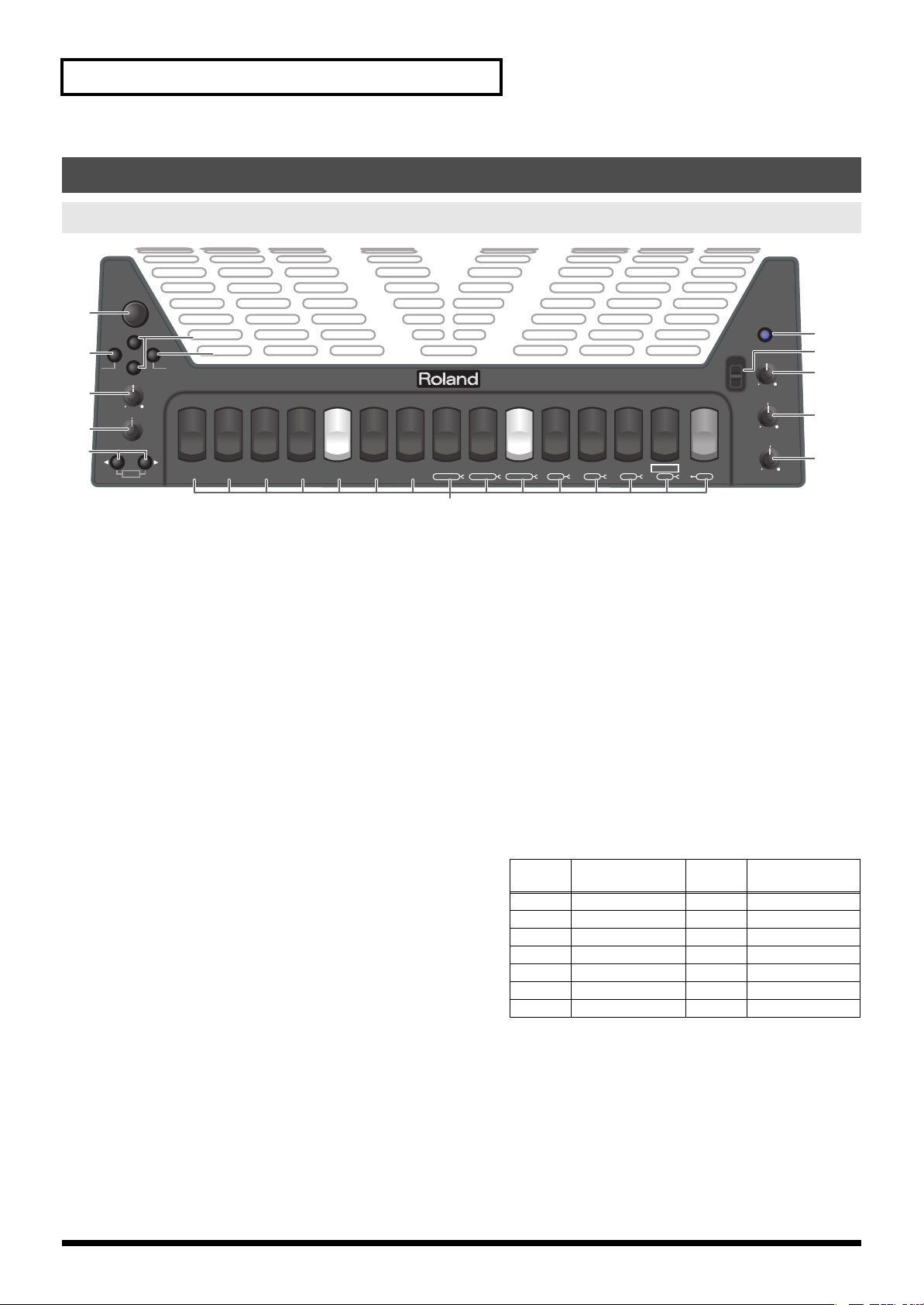
はじめに
各部名称とはたらき
トレブル・セクション
DATA /
ENTER
1
UP
MENU
EXIT
3
JUMP
DOWN
VOLUME
5
BALANCE
6
TREBLE
BASS
7
SET
DEMO
WRITE
2
4
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BRASS
SAX
WIND
HARMON
VIOLIN
FLUTE
BAG PIPE
JAZZ ORG
SEND PC
8
BLUES ORG
BASS LINK
SCAT VOICE
ORCH LINK
MANDOLIN
LOW
AC GUITAR
HIGH
13
AC PIANO
DUAL
14
CANCEL
SOLO
OFF
ORCHESTRA
MODE
ON
SORDINA
POWER
DELAY
CHORUS
REVERB
9
10
11
12
13
DATA / ENTER つまみ
1.
つまみを回すと設定値の変更やメニューの選択を行うことがで
きます。つまみを押すと設定したいパラメーターの選択をする
ことができます。
2.
UP ボタン、DOWN ボタン
メイン画面(本機を演奏しているときに表示される画面、
P.24)上で、以下の機能を素早く選択します。
Transpose(トランスポーズ機能):[UP]ボタンを 1 回押し
ます。(P.38)
Musette Detune(ミュゼット・デチューン機能):[UP]ボタ
ンを 2 回押します。(P.38 )
Scale(音階機能):[UP]ボタンを 3 回押します。(P.39)
Noise Edit (Valve, Button)(ノイズ・エディット機能):
[UP]ボタンを 4 回押します。(P.40)
Orchestra Volume(オーケストラ・ボリューム機能):
[DOWN]ボタンを 1 回押します。(P.34)
Orc.Bass Volume(オーケストラ・ベース・ボリューム機能):
[DOWN]ボタンを 2 回押します。(P.35)
Orch.Chord Volume(オーケストラ・コード・ボリューム機
能):[DOWN]ボタンを 3 回押します。(P.36)
Orch.Free Bass Volume(オーケストラ・フリー・ベース・ボ
リューム機能):[DOWN]ボタンを 4 回押します。(P.37)
メニュー画面では、設定値を変更するときに使います
([DATA / ENTER]つまみを回すのと同じ機能です)。
3.
EXIT / JUMP ボタン
メイン画面(本機を演奏しているときに表示される画面、
P.24)に戻ります。メニュー画面では、1 回押すと上位階層に
戻り、もう一度押すとメイン画面に戻ります。
メイン画面が表示されているときに[EXIT / JUMP]ボタン
を押し続けるとジャンプ機能(P.44)を使うことができます。
4.
MENU / WRITE ボタン
メニューを選択します。また、[NEMU / WRITE]ボタンを押
し続けると設定を保存することができます(ライト機能、
P.108)。
VOLUME つまみ
5.
全体の音量を調節します。
BALANCE つまみ
6.
ベース・セクションとトレブル・セクションの音量バランスを
調節します。「BASS」の方へ回すとトレブル・セクションの
音量が小さくなり、「TREBLE」の方へ回すとベース・セク
ションの音量が小さくなります。
7.
SET ボタン
セットを切り換えます。各セットには、トレブル・パート 14
種類、ベース・パート(ストラデラ・ベース・モード 7 種類と
フリー・ベース・モード 7 種類)、オーケストラ・パート 22
種類、オーケストラ・ベース・パート 7 種類、オーケストラ・
コード・パート 7 種類、オーケストラ・フリー・ベース・パー
ト 7 種類の各音色とそれぞれの設定がまとめて保存されていま
す。[SET]ボタンを押すことによって、簡単にセットを呼び
出すことができます。
8.
トレブル・レジスター・スイッチ
トレブル・パートでは各トレブル・レジスター・スイッチに、
以下の 14 種類の音色が登録されています。
スイッチ
の番号
音色
スイッチ
の番号
音色
1 Bassoon 8 Master
2 Bandon 9 Musette
3 Cello 10 Celeste
4 Harmon 11 Tremolo
5 Organ 12 Clarinet
6 Accord 13 Oboe
7 Violin 14 Piccolo
[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押すとオーケスト
ラ・パートに切り換わり、トレブル・レジスター・スイッチに
22 種類のオーケストラ・パートの音色を割り当てます。
[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押した後、[1]〜
[13]のレジスター・スイッチを押して音色(「BRASS」、
「SAX」、「WIND」、「HARMONICA」、「VIOLIN」など)を選択
します。[1]〜[14]のレジスター・スイッチに登録された
音色をトレブル・パートに戻すには、[ORCHESTRA]レジス
ター・スイッチを押します。
12
Page 13
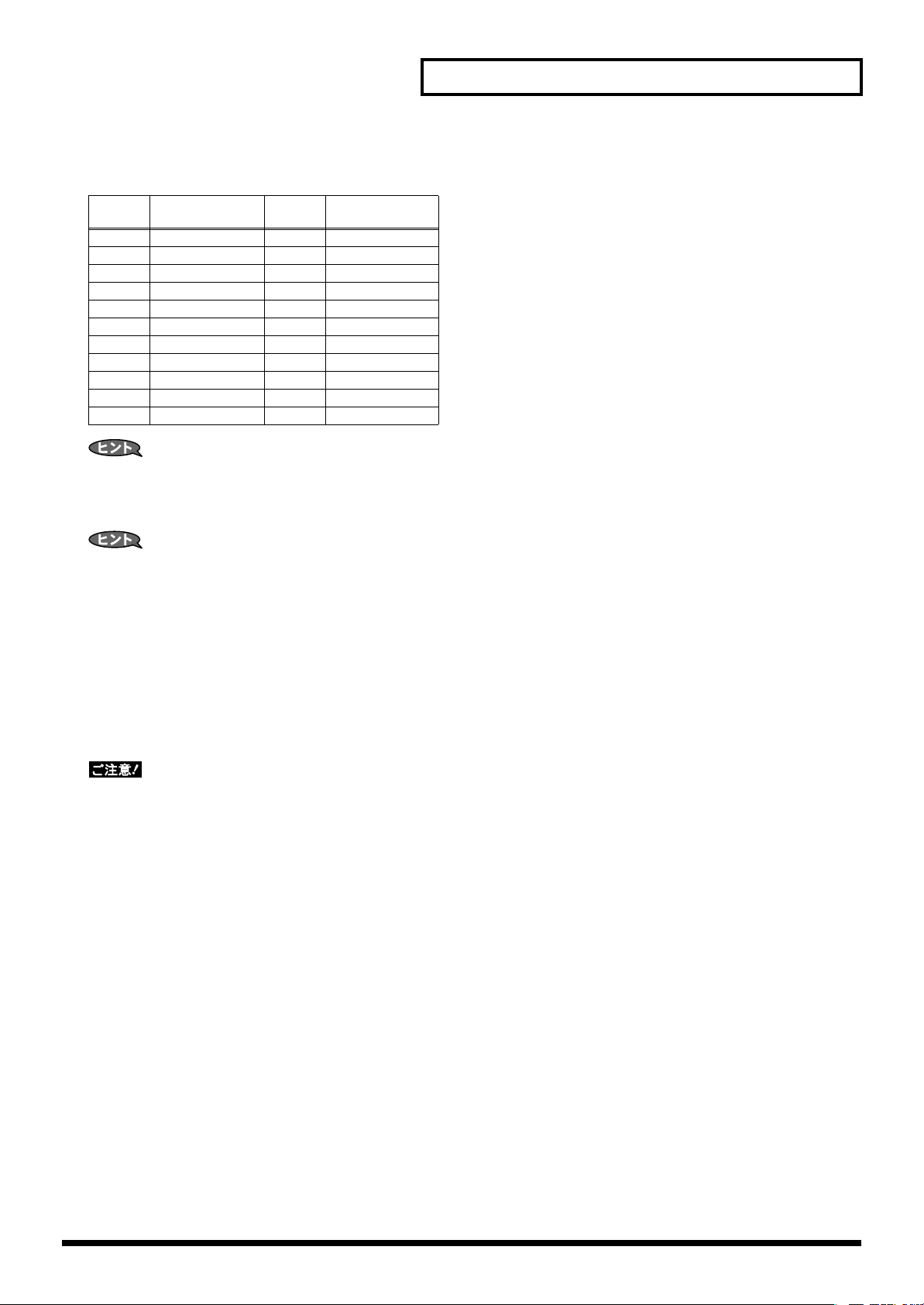
オーケストラ・パートでは以下の 22 種類の音色が登録されて
います。
はじめに
スイッチ
の番号
1A Trombone 6B PanFlute
1B Trumpet 7A HighLand
2A Tenor Sax 7B Zampogna
2B Alto Sax 8A PercOrgan
3A Clarinet 8B JazzOrgan
3B Oboe 9A RotOrgan
4A Harmonica 9B TermOrg
4B Mute Harm 10 ScatVoice
5A Violin 11 Mandolin
5B Pizzicato 12 AcGuitar
6A Flute 13 AcPiano
オーケストラ・パートでは、[1]〜[9]のレジスター・スイッチ
には 2 種類の音色(A / B)が登録されています(音色の種類はレ
ジスター・スイッチの下に印刷されています)。B の音色を選択す
るにはそのレジスター・スイッチを 2 回押します。
[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押し続けながら[9]〜
[14]のレジスター・スイッチを押すと、リンク機能(P.52)をオ
ンにしたりオーケストラ・モード(P.32)を選択したりすることが
できます。
[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押し続けながら[8]
のレジスター・スイッチを押すと、「Send PC(センド PC)」
機能(P.101)を呼び出すことができます。
9.
POWER ボタン
電源のオン(ボタンが点灯)/オフ(ボタンが消灯)を切り換
えます。
音色
スイッチ
の番号
音色
本機は 10 分間何も操作をしないと、バッテリー節約のために電源
が自動的にオフになります。電源が切れるまでの時間はお好みに設
定することもできます(P.81)。
10.
SORDINA スイッチ
チャンバー(ソルディナ)機能(チャンバー(共鳴箱)による
効果のシミュレート、P.28)のオン/オフを切り換えます。
11.
DELAY つまみ
エフェクトのディレイ(エコー)のレベルを調節します
(P.37)。
CHORUS つまみ
12.
エフェクトのコーラスのレベルを調節します(P.37)。
REVERB つまみ
13.
エフェクトのリバーブのレベルを調節します(P.37)。
13
Page 14
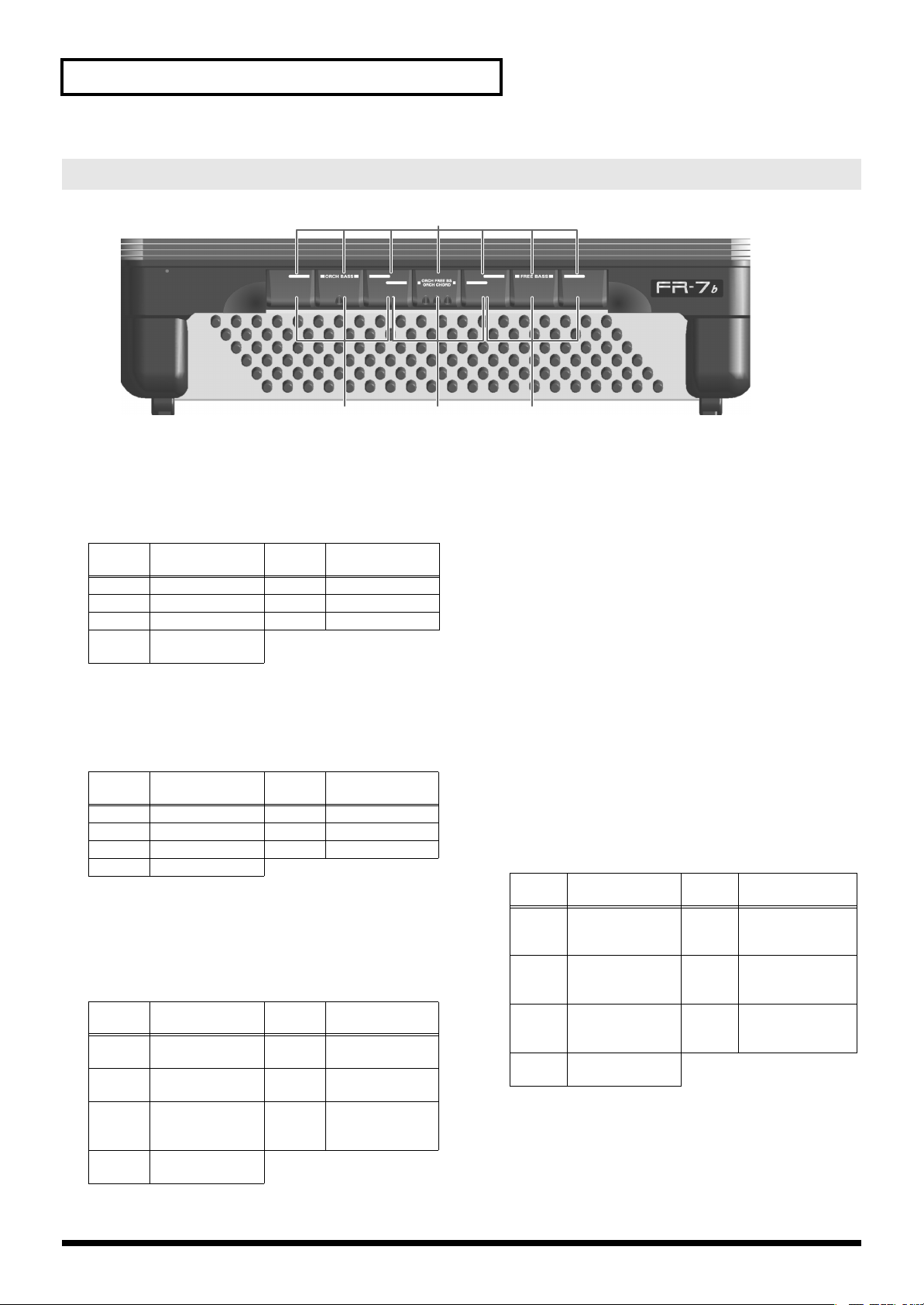
はじめに
ベース・セクション
※上記のベース・レジスター・スイッチ図に表記されているような番号は実際にはありません。
14
16 1715
14.
ベース・レジスター・スイッチ
ベース・パートのストラデラ・ベース・モード(P.28)では以
下の 7 種類の音色が登録されています。
スイッチ
の番号
本体上部から見て上 3 つのレジスター・スイッチ([FREE BASS]
レジスター・スイッチ)を同時に押すと、フリー・ベース・モー
ド(P.30)のオン/オフを切り換えることができます。
ベース・パートのフリー・ベース・モードでは以下の 7 種類の
音色が登録されています。
スイッチ
の番号
本体上部から見て下 3 つのレジスター・スイッチ([ORCH
BASS]レジスター・スイッチ)を同時に押すと、オーケスト
ラ・ベース・パート(P.34)のオン/オフを切り換えることが
できます。
オーケストラ・ベース・パートでは以下の 7 種類の音色が登録
されています。
スイッチ
の番号
音色
1 2' 5 8' / 4' / 2'
2 4' 6 16' / 8' / 8-4'
3 8- 4' 7 16' / 2'
4 16' / 8' / 8-4'
/4'/2'
音色
1 low 5 lwlow+hi
2 high 6 highlw+h
3 low+high 7 lowhigh
4 lw+hglow
音色
1 Acoustic
(アコースティック)
2 Bowed
(バウド)
3 Fingered
(フィンガー)
4 Fretless
(フレットレス)
スイッチ
の番号
スイッチ
の番号
スイッチ
の番号
音色
音色
音色
5 Picked
(ピック)
6 Tuba
(チューバ)
7 Tuba Mix
(チューバ・ミッ
クス)
15.
オーケストラ・ベース・レジスター・スイッチ
本体上部から見て下 3 つのレジスター・スイッチ([ORCH
BASS]レジスター・スイッチ)を同時に押すと、オーケスト
ラ・ベース・モード(P.34)になります。
アコーディオン・ベース音色がオフになり、オーケストラ・
ベース音が選択されます。
もう一度 3 つのレジスター・スイッチを同時に押すと、通常の
ベース・モードに戻ります。
16.
オーケストラ・フリー・ベース/オーケストラ・コー
ド・レジスター・スイッチ
これら 3 つのスイッチを同時に押すと、オーケストラ・コード
(フリー・ベース・セクションがオフの時)またはオーケスト
ラ・フリー・ベース(フリー・ベース・セクションがオンの
時)のオン/オフを切り換えることができます。
オーケストラ・コードはコード・ボタンのオーケストラ音色
を、オーケストラ・フリー・ベースはフリー・ベース・セク
ションのオーケストラ・ベース音色を選択することができま
す。
詳細は P.35 と P.37 をご覧ください。
ORCH FREE BS sounds
(オーケストラ・フリー・ベース音色)
スイッチ
の番号
音色
1* Trombone
(トロンボーン)
2* Clarinet
(クラリネット)
3* Oboe
(オーボエ)
4* Flute
(フルート)
スイッチ
の番号
音色
5* Perc Organ
(パーカッション・
オルガン)
6 Ac Guitar
(アコースティッ
ク・ギター)
7 Ac Piano
(アコースティッ
ク・ピアノ)
14
Page 15
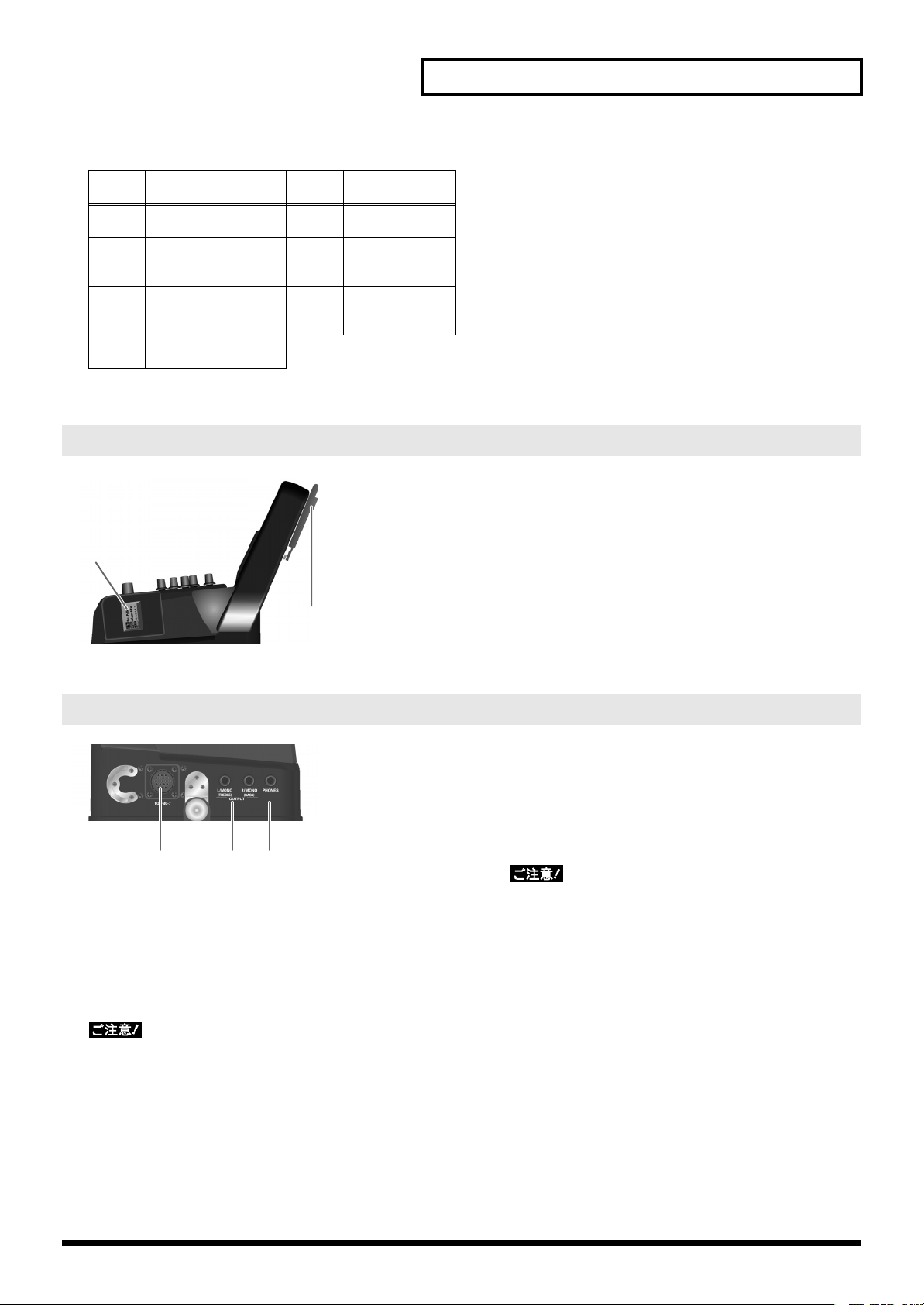
はじめに
ORCH CHORD sound(オーケストラ・コード音色)
スイッチ
の番号
※「*」のついた音色の音量は、蛇腹の動きのみで変化します。
これらの音色はベロシティには対応していません。
音色
1* Trombone
(トロンボーン)
2* Tenor Sax
(テナー・サックス)
3* Clarinet
(クラリネット)
4* Trem Organ
(トレモロ・オルガン)
スイッチ
の番号
音色
5* Voice(ボイス)
6 Ac Guitar
(アコースティッ
ク・ギター)
7 Ac Piano
(アコースティッ
ク・ピアノ)
マスター・バー、ディスプレイ
19
18
フリー・ベース・レジスター・スイッチ
17.
本体上部から見て上 3 つのレジスター・スイッチ([ORCH
BASS]レジスター・スイッチ)を同時に押すと、フリー・
ベース・モードになります。
フリー・ベース・モードは、システムの設定をすることができ
ます(P.81)。
もう一度同じ 3 つのレジスター・スイッチを同時に押すと、通
常のベース・モードに戻ります。
18.
マスター・バー
指定したトレブル・レジスター・スイッチの音色を呼び出しま
す(P.28)。また、デュアル、ハイ、ローの各オーケストラ・
モード(P.32)ではオーケストラ・パートのオン/オフを切り
換えます。
ディスプレイ
19.
本機のさまざまな情報を表示します。
接続パネル
20 21 22
20.
TO FBC-7 ジャック
付属のケーブルを使って付属の FBC-7(電源ユニット/フッ
ト・スイッチ/バッテリー充電器)を接続します。
以下の場合に FBC-7 を接続します。
付属のバッテリー(FR-7b のみ)を使わずに本機に電源を
•
供給する場合(付属のバッテリーを使った場合は、約 8 時
間電源を供給することができます)。
バッテリーの最長供給時間に関する詳細は「バッテリー(FR-
7b のみ付属)の準備をする」(P.21)をご覧ください。
フット・スイッチで操作を行う場合(FBC-7 をフット・ス
•
イッチとして使います)。
本機を MIDI コントローラー(MIDI コネクターは FBC-7 のみ
•
に装備されています)としてお使いになる場合。
OUTPUT L / MONO ジャック、OUTPUT R / MONO
21.
ジャック
アンプ、ミキサー、ワイヤレス・システムなどへ接続します。
本機の出力をステレオにするときは両方のジャックを接続しま
す。L がトレブル・パート、R がベース・パート側の出力にな
ります。本機の出力をモノラルにするときはどちらか一方の
ジャック(L または R ジャック)を接続します。
OUTPUT L / MONO ジャックと OUTPUT R / MONO ジャック
に接続しても内部スピーカーはミュートされません(FR-7b のみ)。
22.
PHONES ジャック
ステレオ・ヘッドホン(ローランド RH-25、RH-50、RH200、RH-200S、RH-300)を接続します。
ヘッドホンを接続すると内部スピーカーがミュートされます
(FR-7b のみ)。
15
Page 16

はじめに
フット・スイッチ(FBC-7)背面
23 24 25 26 27 28
POWER ON スイッチ
23.
FBC-7 の電源のオン/オフを切り換えます。
AC ジャック
24.
電源コードを接続します(P.18)。
25.
MIDI コネクター
MIDI ケーブルを接続します(P.98)。
26.
OUTPUT ジャック
アンプ、ミキサーなどへ接続します。
本機の出力をステレオにするときは両方のジャックを接続しま
す。本機の出力をモノラルにするときはどちらか一方のジャッ
ク(L または R ジャック)を接続します(P.17)。
EXPRESSION PEDAL ジャック
27.
エクスプレッション・ペダル(別売:EV シリーズ)を接続し
ます(P.41)。
TO FR7/5 V-ACCORDION ジャック
28.
付属のケーブルを使って FR-7b /5 b と接続します(P.17)。
フット・スイッチ(FBC-7)について詳細は「フット・スイッチ
(FBC-7、付属)について」(P.41)をご覧ください。
16
Page 17
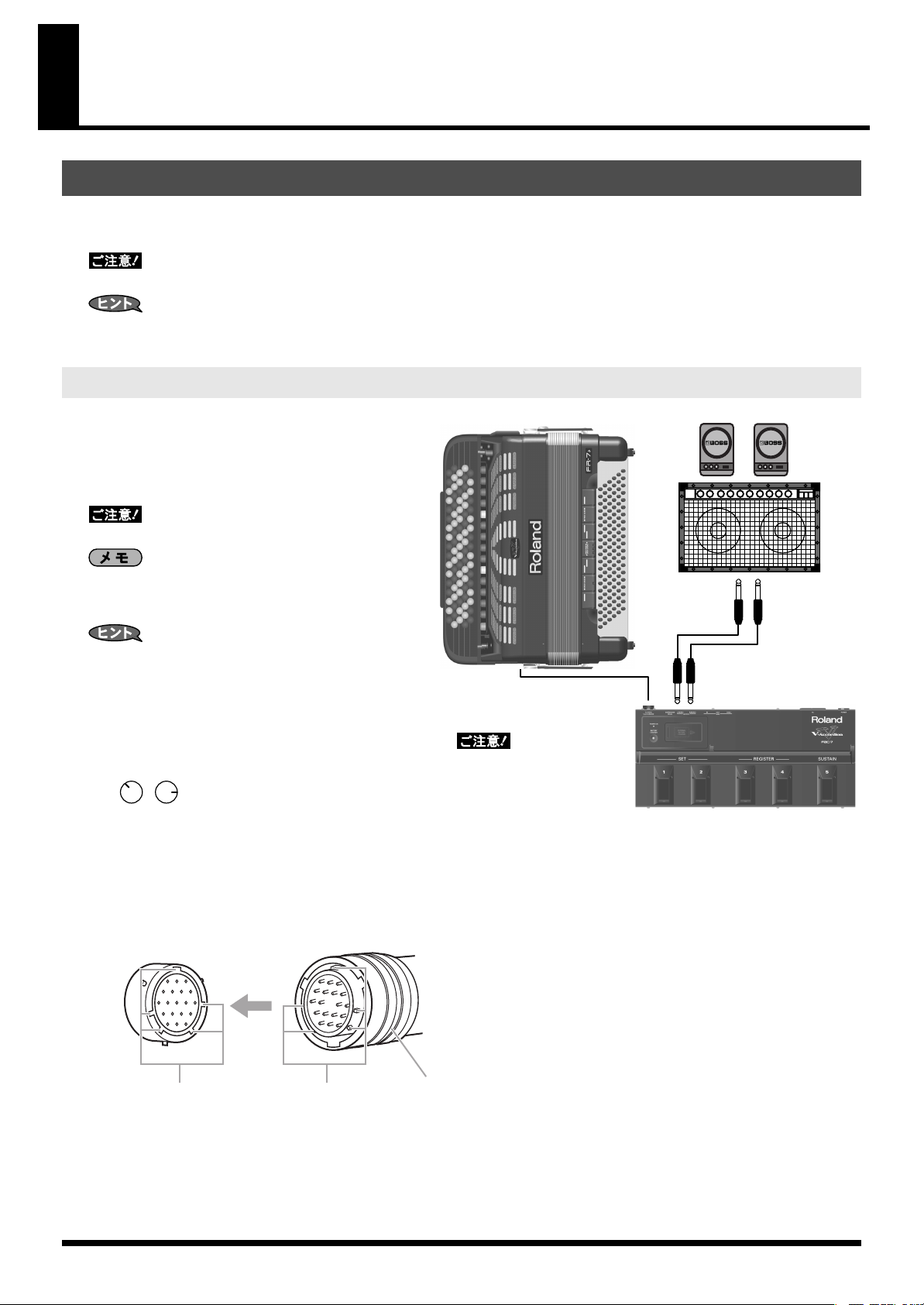
準備する
OUTPUT
L/MONO+R/MONO
INPUT
L+R
19 ピン・ケーブル(付属)
接続する
フット・スイッチ(FBC-7、付属)やアンプなどを本機と接続します。
FBC-7 は本機の電源ユニットであり、フット・スイッチにもなります。またバッテリー(FR-7b のみ付属)を充電することもできます。
他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。
FR-7b にはバッテリーが付属されており、スピーカーを内蔵していますので、バッテリーを本機に内蔵して充電しておけば、アンプや FBC-7 に接
続しなくてもお使いになれます(P.20)。
FBC-7、外部オーディオ機器を接続する
本機を FBC-7 に接続して、FBC-7 をアンプなどの外部オーディ
オ機器に接続します。
FBC-7 を接続すると、FBC-7 は電源、フット・スイッチ、音声
出力ジャックとして機能します。
MIDI 機能(P.97)は、FBC-7 を接続したときに機能します。
FBC-7 の OUTPUT ジャックを外部オーディオ機器と接続すれ
ば、本体の OUTPUT ジャックとアンプを接続する必要はあり
ません。
本機のサウンドはステレオ出力した際、自然なステレオ・サウ
ンドとなるようにアレンジされています。ミキサーに接続する
場合はバランスを保つために、OUTPUT L / MONO ジャック
(トレブル・セクションが出力されます)を接続したチャンネル
の P AN コントロールを 11 時の位置に、OUTPUT R / MONO
ジャック(ベース・セクションが出力されます)を接続した
チャンネルの PAN コントロールを3 時の位置にセットしてく
ださい。
(例: )
T
B/C
この設定は変更することもできます(P.81)。
FBC-7 の AC ジャックとコンセ
ントを接続してください。
19 ピン・ケーブルの接続のしかた
19 ピン・ケーブルのコネクターの突起(5 ケ所)を、本機または FBC-7 のコネクターのくぼみに合わせて差し込んでから、リングを時計回り
に回してロックします。
本機または FBC-7 のコネクター
19 ピン・ケーブルのコネクター
くぼみ 突起
リング
17
Page 18
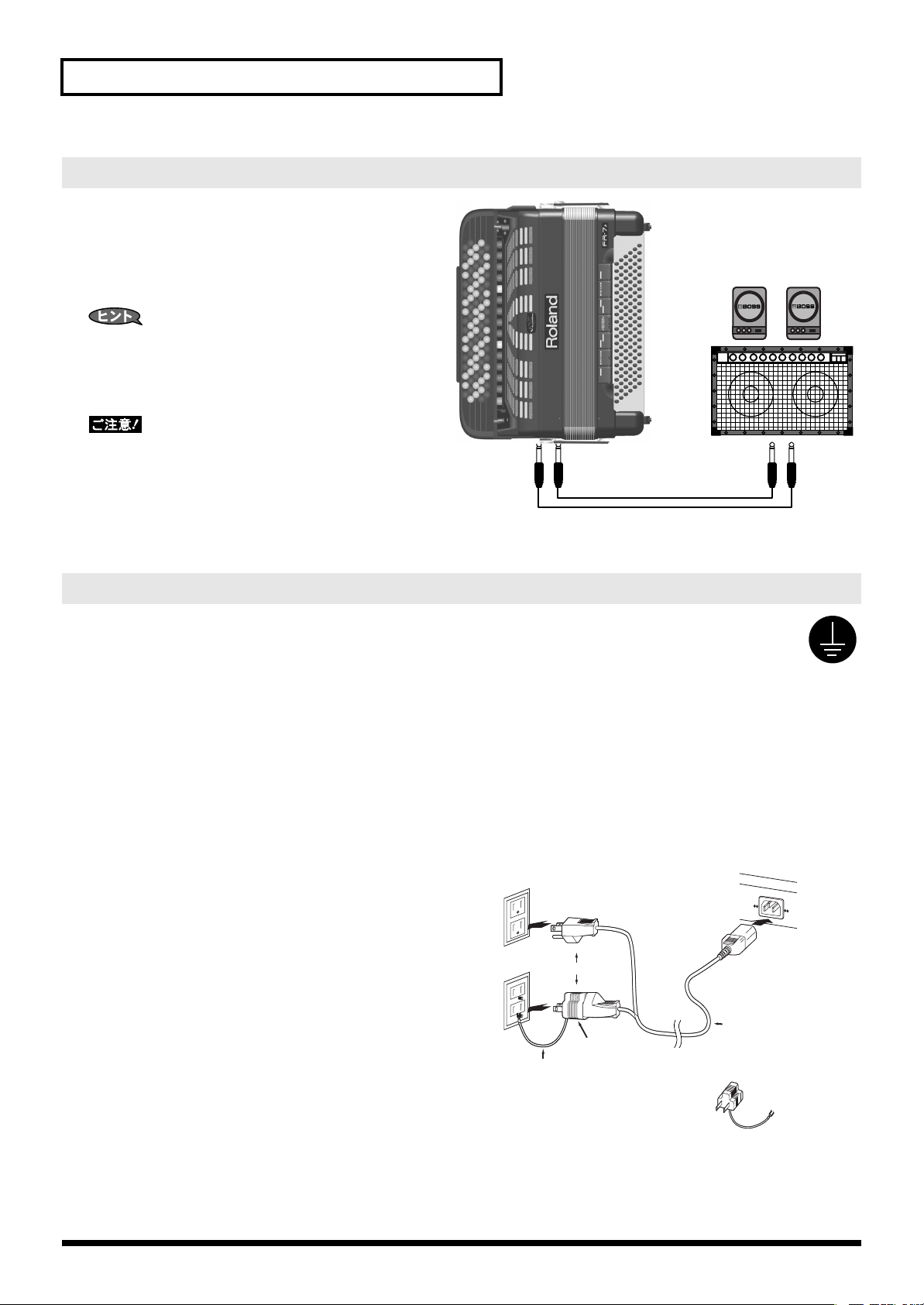
準備する
本体の OUTPUT ジャックを使う(バッテリーを使用した場合)
バッテリー(FR-7b のみ付属)で電源を供給し、本機を直接外部
オーディオ機器(PA システムやミキサーなど)に接続することも
できます。
ワイヤレス・システムなどをご使用になれば、PA システムやミキ
サーから離れて本機を演奏することができます。
PHONES ジャックにヘッドホン(ローランド RH-25、RH-50、
RH-200)を接続することもできます。この場合はオーディオ機器
に接続する必要はありません。
FR-7b では、ヘッドホンを接続すると内部スピーカーがオフになり
ます。
本機を FBC-7 に接続しても本体の OUTPUT ジャックから音声が
出力されます。
OUTPUT
L/MONO(Treble)
OUTPUT
R/MONO(Bass)
INPUT
L
INPUT
電源コードの接続
感電を防ぐために付属の電源コードを使用し、アースを確実に取り付けてください。
付属の電源コードには、感電と機器の損傷を防ぐためにアース用電極端子を加えた 3 端子のプラグがついています。
○ コンセントが接地コンセント(端子穴が 3 個)の場合そのままコンセントにプラグを挿し込んでください。
○ コンセントがアースターミナル付コンセント(端子穴が 2 個)の場合プラグに 2P-3P 変換器をつけ、アース接続後コンセントに挿し込
みます。
※ アース接続は必ず、電源プラグをコンセントに挿し込む前に行なってください。
※ アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。
コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店に接地工事を依頼してください。
なお、接続方法がわからないときは、ローランド・サービスにご相談ください。
fig.connection
※ 設置条件によっては本体に触れると、違和感を覚えたりざ
らつくような感じになるときがあります。これは人体に全
く害のない極微量の帯電によるものですが、気になる方は、
必要に応じ、接地端子(上図参照)を使って外部のアース
か大地に接地してご使用ください。接地した場合、設置条
件によってはわずかにハム(うなり)が混じる場合があり
ます。なお接続方法がわからないときはローランド・サー
ビスにご相談ください。
接地コンセント
ターミナル付き
コンセント
または
フット・スイッチ(FBC-7)
リアパネル
R
接続してはいけないところ
水道管(感電の原因になります)
•
ガス管(爆発や引火の原因になります)
•
電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)
•
18
アース接続
2P-3P変換器
(付属)
電源コード
(付属)
2P-3P変換器
Page 19
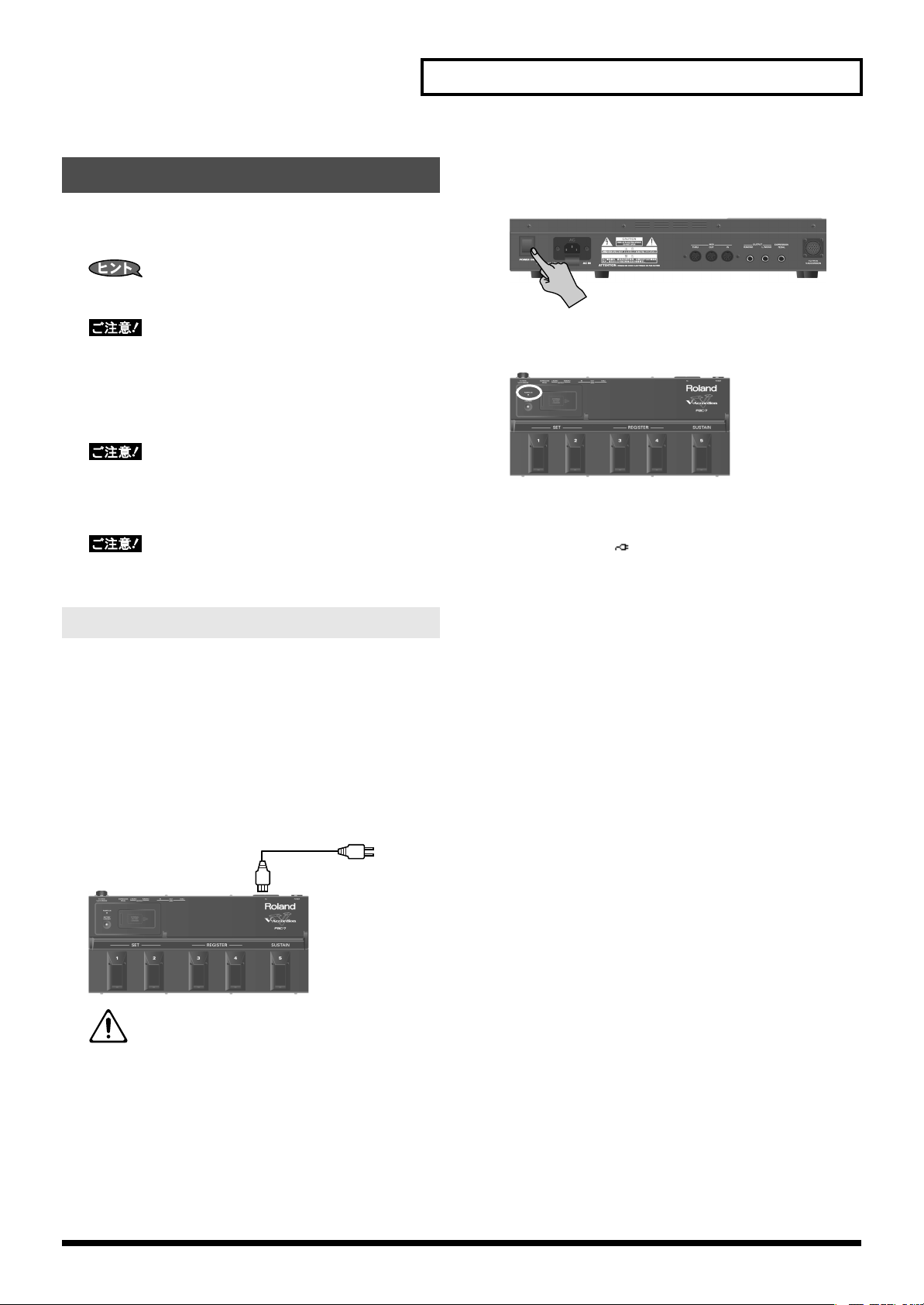
電源を入れる、電源を切る
バッテリー(FR-7b のみ付属)をお使いになっている場合と FBC7 を接続して電源を供給している場合で、電源の入れ方が変わりま
す。
電源を入れるたびに、ディスプレイにお好みの短いメッセージを表
示させることができます(P.82)。
バッテリーは必ず FR-7b に付属のものかローランド製品の取り扱
い販売店で購入したものをお使いください。その他のバッテリーを
お使いになると本機や FBC-7 に深刻な損傷を加える可能性があり
ます。指定外のバッテリーが原因による損傷にはローランドは一切
の責任を負いかねます。そのような損傷はローランドの保証の対象
外となります。
正しく接続したら(P.19)、必ず次の手順で電源を投入してくださ
い。手順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する
恐れがあります。
接続されている機器 → 本機 → アンプ等
この機器は回路保護のため、電源をオンしてからしばらくは動作し
ません。
FBC-7 を使用する場合
付属の FBC-7 で本機に電源を供給する場合は以下のように操作を
します。
接続をする前に、すべての機器の音量を絞り電源を切っ
1.
ておきます。
2.
付属の 19 ピン・ケーブルで本機を FBC-7 に接続します
(P.17)。
3.
FBC-7 の AC ジャックとコンセントを接続します。
コンセントへ
AC
準備する
FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して電源を入れま
5.
す。
FBC-7 のトップ・パネル上にある[POWER ON]インジケー
ターが赤く点灯します。
本体の[POWER]ボタンを押して電源を入れます。
6.
ボタンが点灯します。
ディスプレイ上に
電源が供給されていることを示します。
7.
外部オーディオ機器の電源を入れ、演奏しながら本体と
外部オーディオ機器のボリュームを徐々に上げ適当な音
量にします。
電源を切るには
1.
すべての機器の音量を絞り、外部機器の電源を切りま
す。
2.
本体の[POWER]ボタンを再び押すと、電源が切れま
す。
ボタンが消灯します。
FBC-7 の電源を切ります。
3.
FBC-7 のトップ・パネル上にある[POWER ON]インジケー
ターが消灯します。
アイコンが表示され FBC-7 から本機に
FBC-7 の裏面に記載されている電源のコンセントに接続し
てください。本機の電源について詳しくは、「主な仕様」
(P.112)をご覧ください。
FBC-7 の OUTPUTジャックと外部オーディオ機器(アン
4.
プ、ミキサーなど)を接続します。
本体の OUTPUT ジャックからも出力されますが、本体の
OUTPUT ジャックは主にワイヤレス・システムに接続すると
きなどに使用します。
19
Page 20
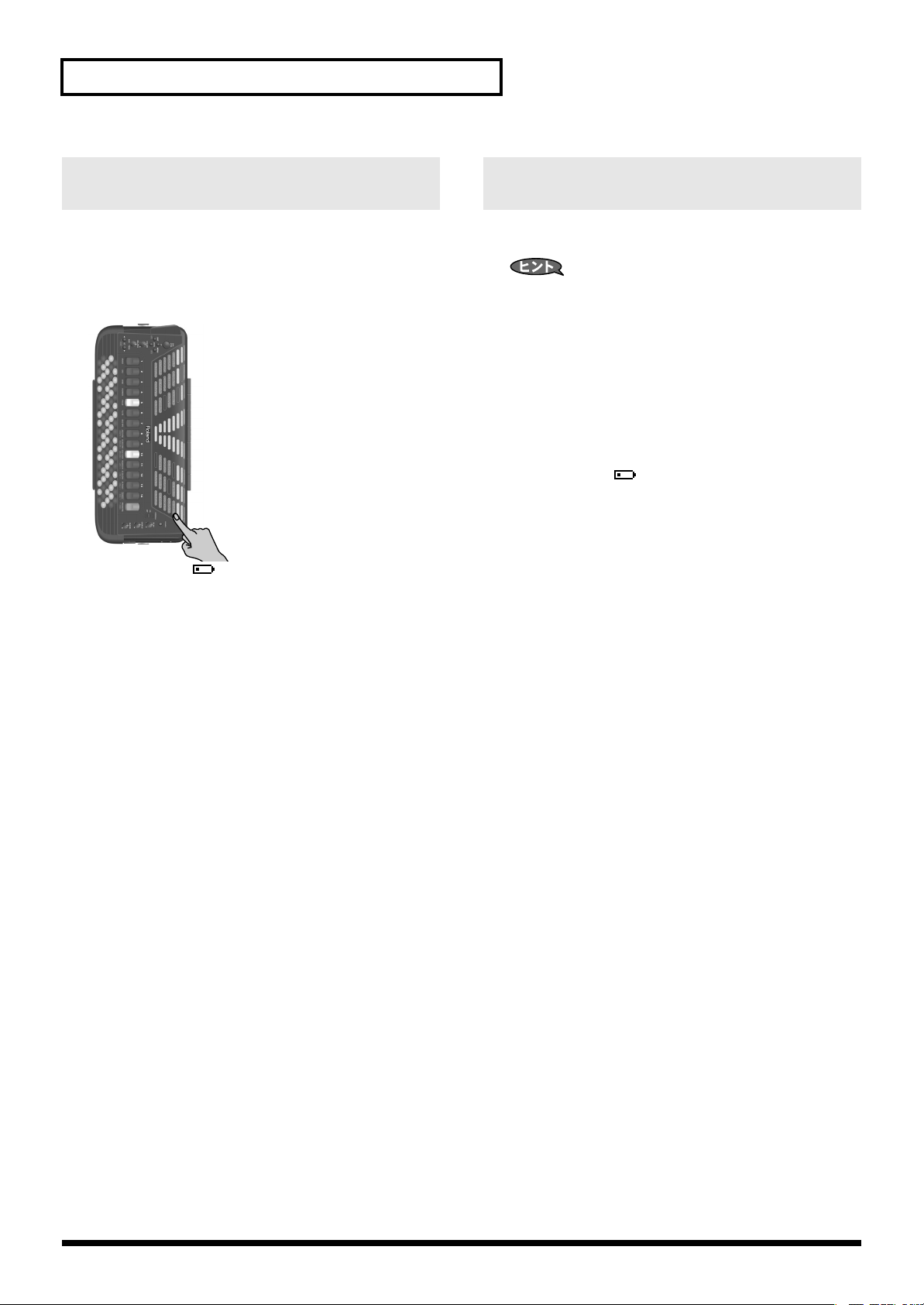
準備する
バッテリーを使用し、アンプなどに接続 しない場合(FR-7b のみ)
バッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵し充電をすれば(P.21)、本
機のみで演奏することができます。
[POWER]ボタンを押して電源を入れます。
1.
ボタンが点灯します。
ディスプレイ上に アイコンが表示されバッテリーで電源
を供給していることを示します(このアイコンはバッテリーの
残量も表示します)。
演奏を始めます(「演奏する」(P.24)をご覧ください)。
2.
3.
[POWER]ボタンを再び押すと、電源が切れます。
ボタンが消灯します。
バッテリーを使用し外部オーディオ機器 に接続する場合
バッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵し充電をすれば(P.21)、本
機を直接外部オーディオ機器と接続し、演奏することができます。
ワイヤレス・システムを本機の OUTPUT ジャックと接続すること
もできます。
1.
接続をする前に、すべての機器の音量を絞り電源を切っ
ておきます。
2.
標準タイプのケーブル(2 本)で本機の OUTPUT ジャッ
クと外部オーディオ機器を接続します。
[POWER]ボタンを押して電源を入れます。
3.
ボタンが点灯します。
ディスプレイ上に アイコンが表示されバッテリーで電源
を供給していることをお知らせします(このアイコンはバッテ
リーの残量も表示します)。
外部オーディオ機器の電源を入れ、演奏しながら本体と
4.
外部オーディオ機器のボリュームを徐々に上げ適当な音
量にします。
電源を切るには
すべての機器の音量を絞り、外部機器の電源を切りま
1.
す。
2.
[POWER]ボタンを再び押すと、電源が切れます。
ボタンが消灯します。
20
Page 21
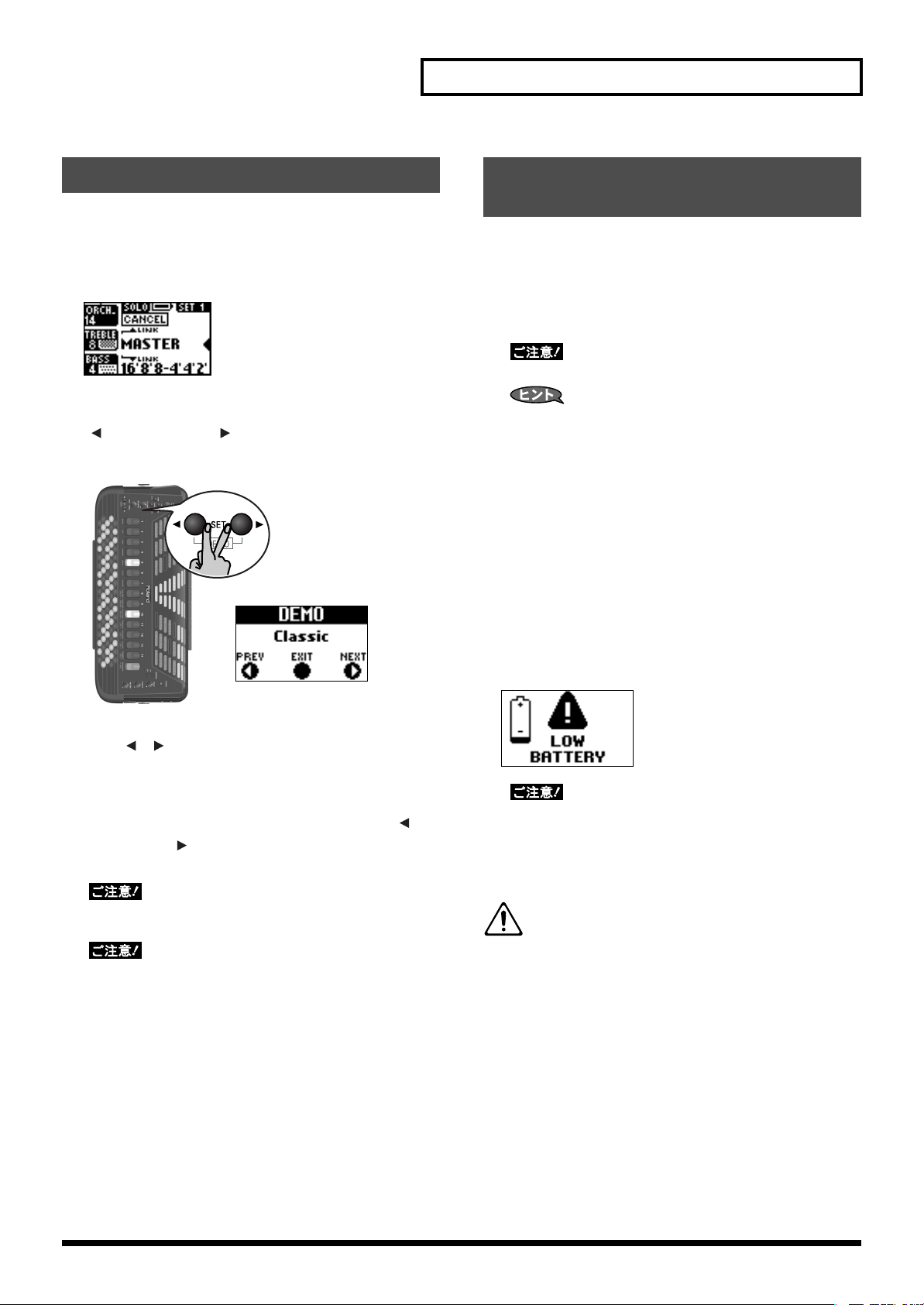
準備する
デモ・ソングを聴く バッテリー(FR-7b のみ付属)
本機にはいくつかのデモ・ソングが内蔵されています。本機の多彩
なサウンドや機能を確認することができます。
本機の電源を入れます(P.19)。
1.
ディスプレイに以下のように表示されます。
ディスプレイに以下のように表示されるまで、[SET
2.
]ボタンと[SET ]ボタンを同時に押しつづけま
す。
の準備をする
本機にバッテリー(FR-7b のみ付属)を内蔵すると、FBC-7 を接
続しなくでも本機を使用することができます。また FR-7b はスピー
カーを内蔵していますので、通常のアコーディオンと同じように本
機のみで使うこともできます。
バッテリーは本機に内蔵したまま充電したり、本機から取り外した
状態で充電することができます。
バッテリーを使用するには、バッテリーの充電が必要です。
バッテリーを 2 本以上お持ちの場合は、本機をバッテリーで使用し
ている間に、FBC-7 で使用していないバッテリーを充電すること
ができます。
バッテリー(FR-7b のみ付属)について
●バッテリーを廃棄する場合、各市町村のゴミの分別基準に従って
ください。
●お使いになる前に「バッテリー(FR-7b のみ付属)について」
(P.5)をよくお読みください。
●初めて充電する場合は、バッテリーの残量を使い切ってから充電
を行ってください。
●フル充電されたバッテリーは約 8 時間お使いになれます。
●バッテリーの残量がなくなると、ディスプレイに以下のように表
示され、電源が切れます。
最初のデモ・ソングの演奏が自動的に始まります。
[SET / ]ボタンを押して別のデモ・ ソングを選択するこ
ともできます。
3.
[VOLUME]つまみを使って音量を調節します。
[EXIT / JUMP]ボタンを押して(または[SET ]ボ
4.
タンと[SET ]ボタンを同時に押して)デモ・ソン
グを終了します。
デモ・ソングを個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく使用すること
は、法律で禁じられています。
デモ・ソングの演奏データは MIDI OUT コネクターからは出力され
ません。
本機は 10 分間何も操作をしないと、バッテリー節約のために電源
が自動的にオフになります。電源が切れるまでの時間はお好みに設
定することもできます(P.81)。
●付属または指定のバッテリー(BP-24-45)以外は使用しないで
ください。
警告:
充電後のバッテリーは熱を持つことがありますので、取
り扱いには十分ご注意ください。
21
Page 22
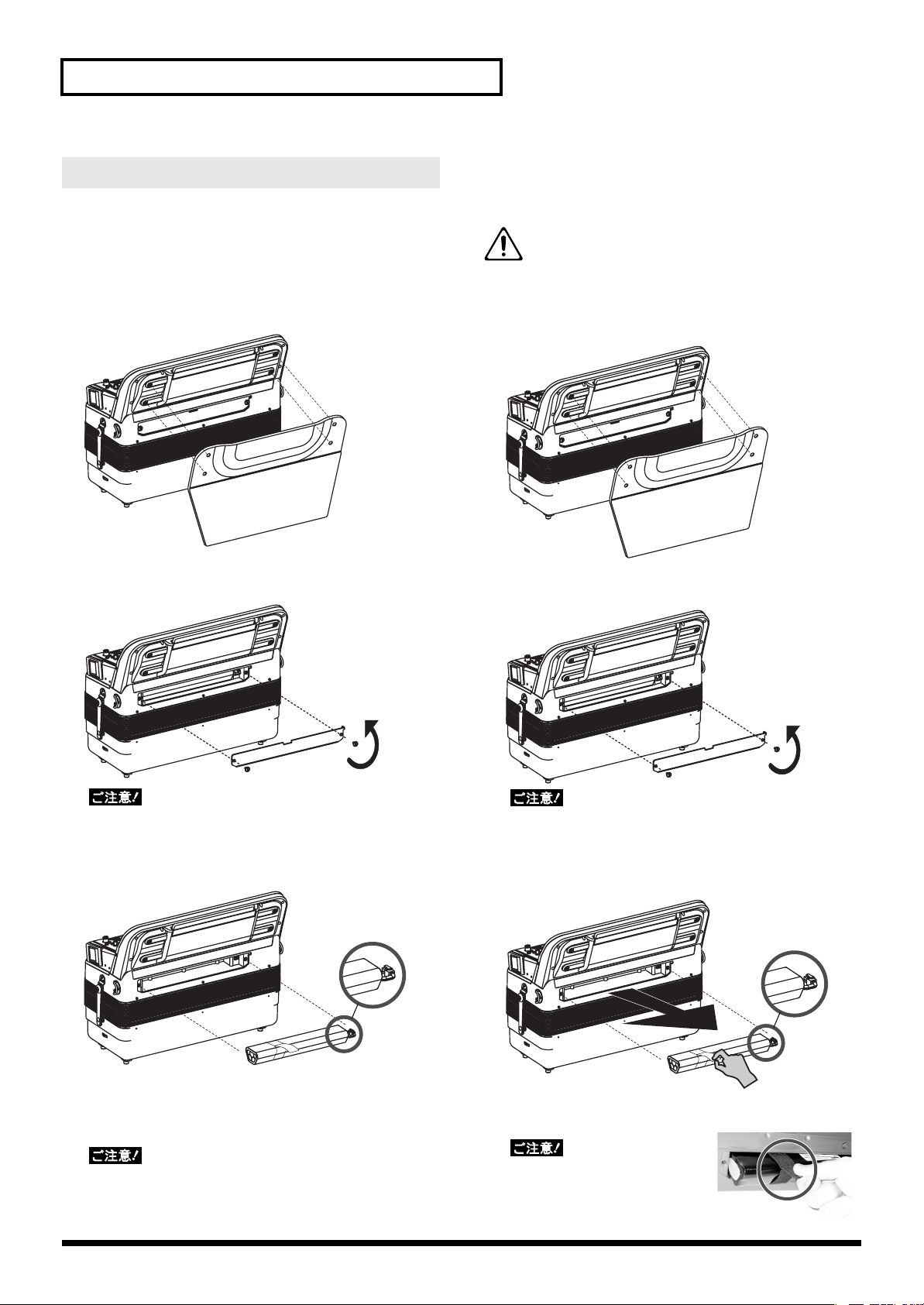
準備する
バッテリーを本機に内蔵する
充電したバッテリーを使用する、またはバッテリーを本機に内蔵し
てから充電する場合は、以下の手順でバッテリーを本機に内蔵しま
す。
本機の電源を切ります。
1.
2.
本機裏側のクッションをはずします。
ボタンをはずして、クッションをはずします。
コインなどを使ってネジ(2 本)をはずし、バッテ
3.
リー・ケース・カバーをはずします。
バッテリーを本機からはずすには
バッテリーを交換する、またはバッテリーをはずしてから充電する
場合は、以下の手順でバッテリーをはずします。
警告:
バッテリーをはずすときは、必ず本機の電源をオフにし
てください([POWER]ボタンが消灯しているのを確認してく
ださい)。
本機の電源を切ります。
1.
2.
本機裏側のクッションをはずします。
ボタンをはずして、クッションをはずします。
3.
コインなどを使ってネジ(2 本)をはずし、バッテ
リー・ケース・カバーをはずします。
バッテリー・ケース・カバーをはずした状態では、本機の電源をオ
ンにすることはできません。
バッテリーをバッテリー・ケースに入れ、コネクターを
4.
接続します。
5.
バッテリー・ケース・カバーを取り付け、コインなどを
使ってネジ(2 本)を締めて、バッテリー・ケース・カ
バーを固定します。
バッテリー・ケース・カバーは必ずネジで固定してください。ネジ
がゆるい状態では本機の電源をオンにすることはできません。
クッションを本機に取り付けます。
6.
22
バッテリー・ケース・カバーをはずした状態では、本機の電源をオ
ンにすることはできません。
4.
リボンを引っ張ってバッテリーをバッテリー・ケースか
ら少し取り出し、コネクターをはずしてから、バッテ
リーをバッテリー・ケースから取り出します。
コネクターのつまみを押しながら、コネクターを引っ張っては
ずします。
必ずバッテリーに取り付けられてい
るリボンを引っ張ってバッテリーを
取り出してください。
Page 23
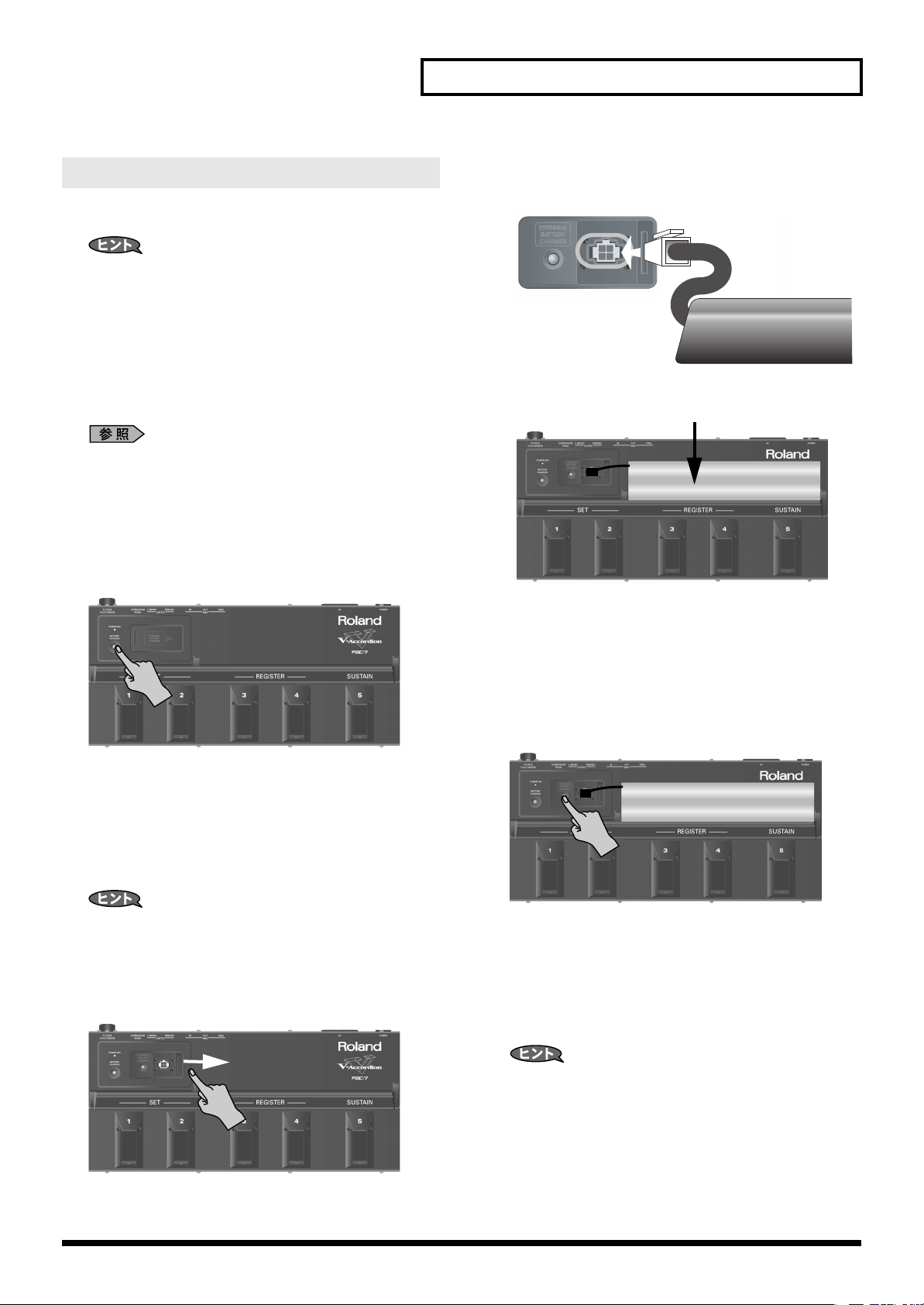
バッテリーを充電する
充電器カバーを開けた状態
バッテリーのコネクター
バッテリーは本機に内蔵したまま充電することもできますし、本機
から取り外して FBC-7 で充電することもできます。
バッテリーを 2 本以上お持ちの場合は、本機をバッテリーで使用し
ている間に、FBC-7 で使用していないバッテリーを充電すること
ができます。
本機に内蔵したまま充電する
バッテリーを本機に内蔵します。
1.
本機と FBC-7 を接続します。
2.
準備する
バッテリーのコネクターを充電器のコネクターに接続し
2.
ます。
バッテリーを FBC-7 の上に置きます。
3.
バッテリー
接続のしかたについては「接続する」(P.17)をご覧ください。
FBC-7 の AC ジャックとコンセントを接続します。
3.
4.
FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、FBC-7 の電
源を入れます。
[POWER ON]ランプが点灯します。
5.
FBC-7 の[BATTERY CHARGER]ボタンをおします。
[BATTERY CHARGER]ボタンが赤色に点灯し、充電を開始
します。
[BATTERY CHARGER]ボタンが緑色に点灯したら充電
6.
完了です。
充電が完了したら、FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、
FBC-7 の電源を切ります。
4.
FBC-7 の AC ジャックとコンセントを接続します。
FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、FBC-7 の電
5.
源を入れます。
[POWER ON]ランプが点灯します。
FBC-7 の[EXTERNAL BATTERY CHARGER]ボタンを
6.
おします。
バッテリー充電中も本機を演奏することができます。
FBC-7 で充電する
充電器カバーをスライドさせて開きます。
1.
[EXTERNAL BATTERY CHARGER]ボタンが赤色に点灯し、
充電を開始します。
[EXTERNAL BATTERY CHARGER]ボタンが緑色に点
7.
灯したら充電完了です。
充電が完了したら、FBC-7 の[POWER ON]ボタンを押して、
FBC-7 の電源を切ります。
本機が FBC-7 に接続されているときは、バッテリー充電中も本機
を演奏することができます。
バッテリーの持ち時間が短くなったら
バッテリーは約 300 回充電して使用することができます。 使用して
いるうちにだんだん持ち時間が短くなりますので、そうなった場合
は新しいものと交換してください。
23
Page 24
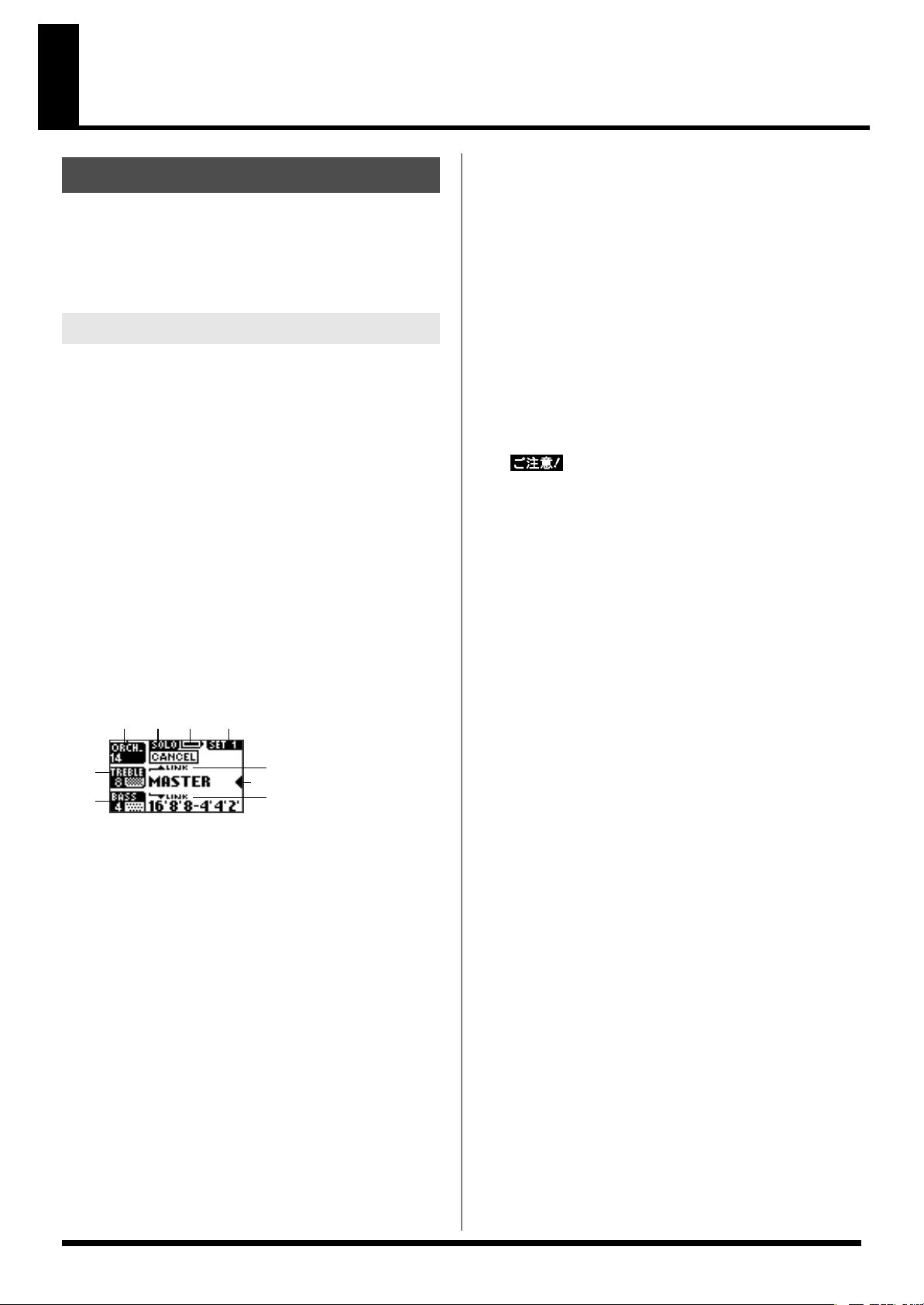
演奏する
演奏の前に
設定や現在の状態などは、ディスプレイに表示されます。ここで
は、そのディスプレイの見かたを説明します。
また、本機には、手軽に演奏を楽しむ「イージー・モード」と、細
かな設定をして演奏ができる「フル・モード」の 2 種類が用意され
ていますので、演奏するモードについて説明します。
ディスプレイについて
本機の設定はディスプレイを見ながら行います。また設定された項
目はディスプレイで確認することができます。
本機の電源を入れたとき、または演奏中など、ディスプレイにはメ
イン画面が表示され、音色や設定などを確認することができます。
メイン画面について
ディスプレイやボタンとつまみが付いている以外は、伝統的なア
コーディオンと変りません。
ディスプレイには現在の設定が表示されます。
ディスプレイの表示内容は、選択している機能によって異なりま
す。本機の電源を入れたときや[EXIT / JUMP]ボタンを何度か
押したときには、メイン画面が表示されます。パラメーターの値を
変更した後は自動的にメイン画面になる場合があります。内部パラ
メーターを変更しているときを除き、演奏中はメイン画面が表示さ
れています。
メイン画面は基本的に以下のように表示されます。
ベース、フリー・ベース、オーケストラ・ベース、オー
6.
ケストラ・コード、オーケストラ・フリーベース・レジ
スター(図では 4 番)
2 つのベース・セクション(フリー・ベースまたはベース)の
うち 1 つだけを選ぶことができます。
7.
リンク・シンボル
トレブル・レジスターを選択したとき、オーケストラ・レジス
ターやベース・レジスターが変わることを意味します。
ベース・リンク機能はオーケストラ・コード・セクションや
オーケストラ・フリー・ベース・セクションにも対応していま
す。
8.
パート選択表示
トレブル・ボタンをトレブル・パートの音色で演奏しているの
かオーケストラ・パートの音色で演奏しているのかを表示しま
す。
つまみを回したりボタンを押すと画面に表示される情報が変ります
が、このような場合しばらくするとメイン画面が再び現れます。
その他の画面について
ディスプレイに表示されるものは、選択した機能によって変わりま
す。本機の電源を入れたときや、[EXIT / JUMP]ボタンを数回押
したときはメイン画面が表示されます。また、あるパラメーターの
設定を変更した後にメイン画面が自動的に再表示されることもあり
ます。
また、各種設定中は、設定用の画面が表示されます。設定中の画面
については、各設定のしかたをご覧ください(P.42)。
123 4
5
6
実際の表示は、選択されているセットやセクションと演奏機能の設
定によって変わります。1 〜 8 の部分には常に以下の内容が表示さ
れます。
オーケストラ・レジスター(図では 14 番)
1.
オーケストラ・パートが選択されているときは、ボタン鍵盤ア
イコンが表示されます。
オーケストラ・モード
2.
3.
電源の種類(図ではバッテリー)
バッテリーで電源を供給している場合は、バッテリーの残量も
表示されます。
4.
セット番号
5.
トレブル・レジスター番号(図では 8 番)
トレブル・パートが選択されているときは、ボタン鍵盤アイコ
ンが表示されます。
7
8
7
24
Page 25
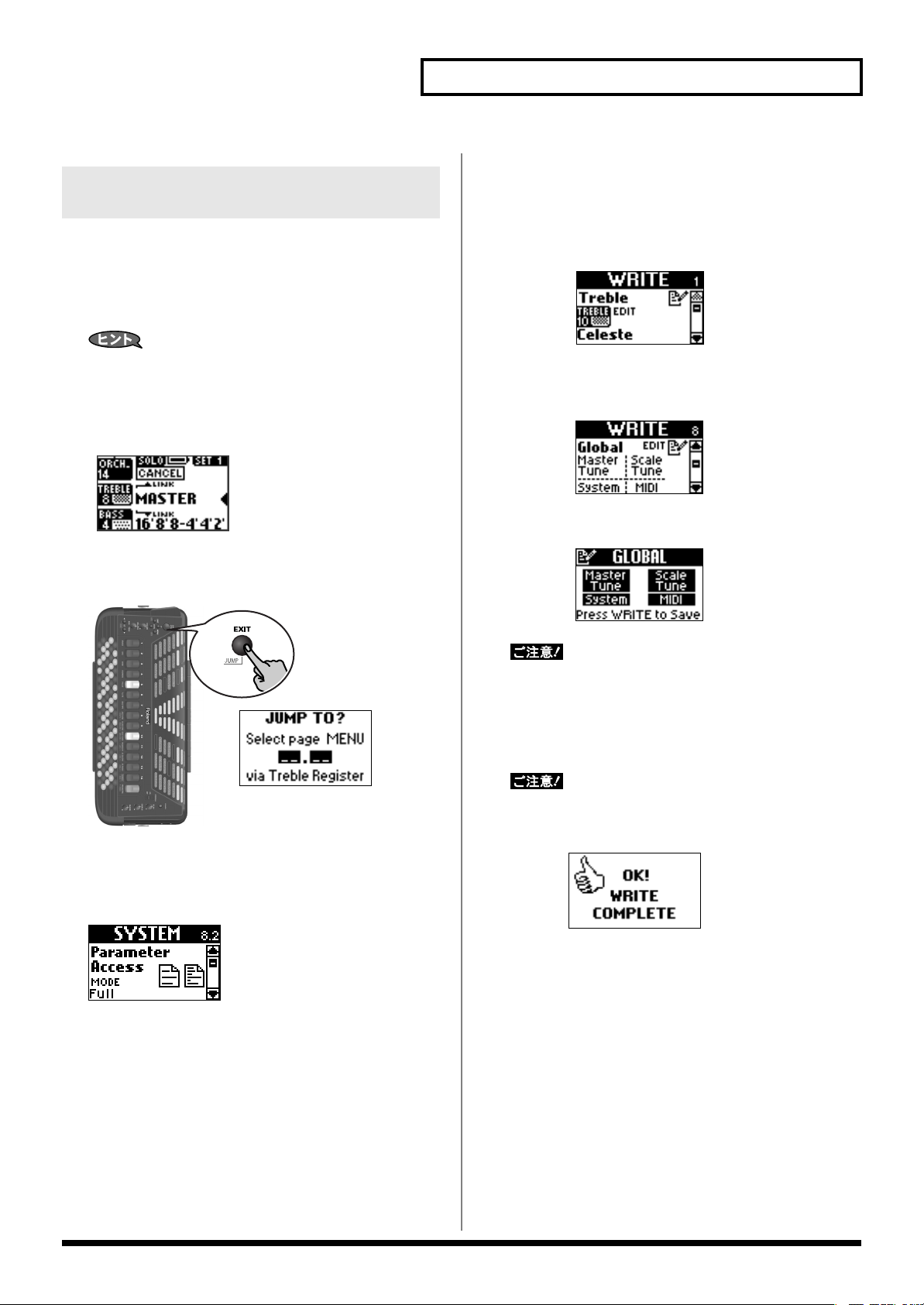
イージー・モードとフル・モードを選択 する
初めて電源を入れたとき、本機はイージー・モードで起動します。
このモードでは主要なパラメーターのみを選択することができ、手
軽に本機をお使いいただけます。またフル・モードを選択すると、
リードの種類や微妙なチューニングの設定など、より細かな設定を
することができます。
本機のすべての機能をお使いになる場合は、フル・モードに変更す
る必要があります。
1.
本機の電源を入れます(P.19)。
メイン画面が表示されます。
演奏する
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
6.
電源をオフにした後もこの設定を記憶させておきたい場合は、
続けて次の操作を行ってください。
7.
ディスプレイに以下のように表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
8.
ボタンを押して「Global」を選択します。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
9.
2.
ディスプレイに以下のように表示されるまで[EXIT /
JUMP]ボタンを押し続けます。
[8]と[2]のトレブル・レジスター・スイッチを押し
3.
ます。
ディスプレイに以下のように表示されます。
グローバル画面には、グローバル・メモリーに保存されるすべての
パラメーターが表示されます。1 セットのみ保存できます。
[MENU / WRITE]ボタンを押して設定を保存します。
10.
ディスプレイにしばらくの間、保存完了メッセージが表
示されます。
グローバル・セッティングを保存しない場合でも、電源を切った
り、設定を変更しなければ、その設定のまま使用することができま
す。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
11.
[DATA / ENTER]ボタンを押します。
4.
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
5.
ボタンを押して「Full」または「Easy」を選択します。
•
Full(フル・モード):全パラメーターをご使用になれます。
•
Easy(イージー・モード):主要なパラメーターのみご使用
になれます。
25
Page 26
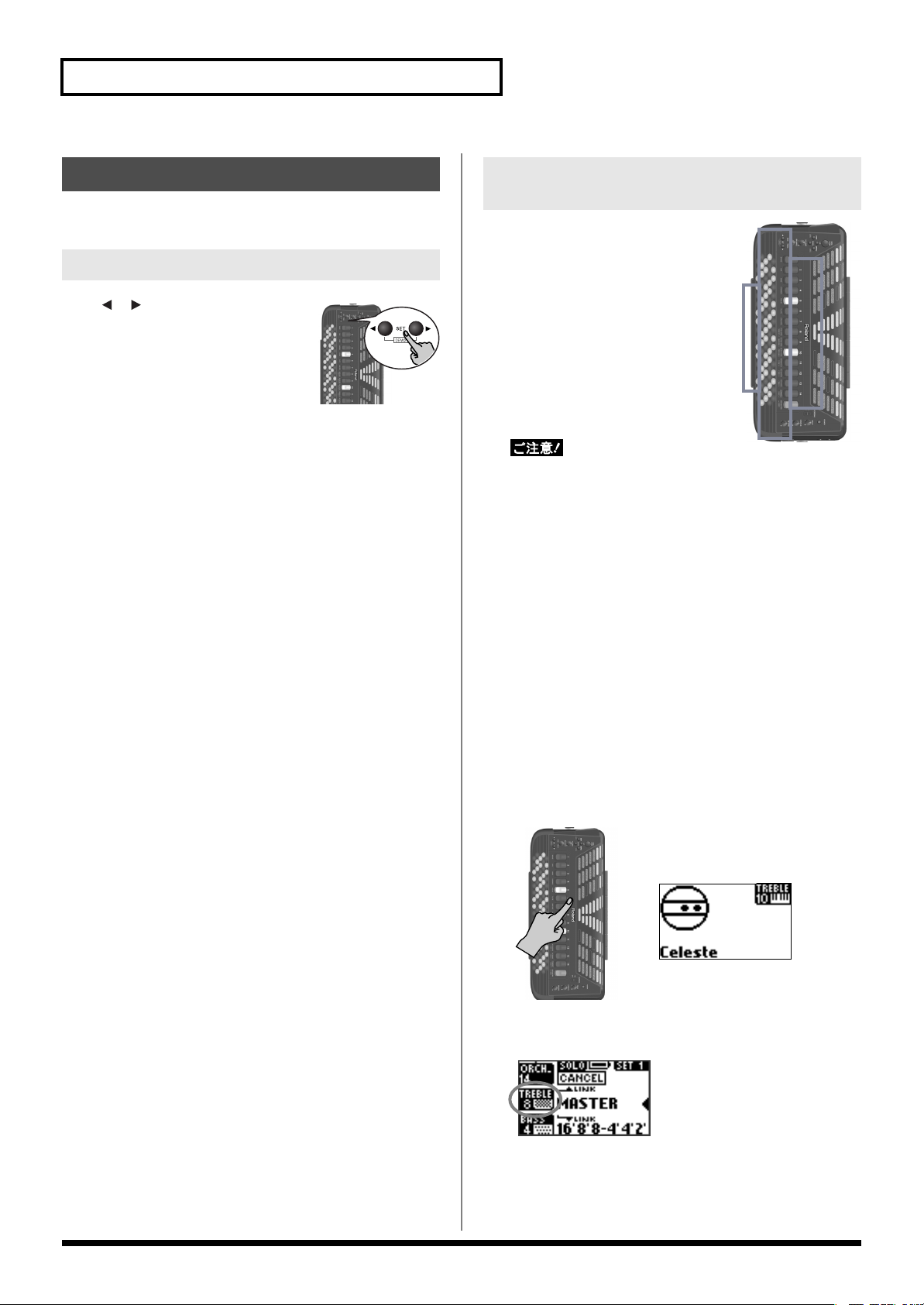
演奏する
アコーディオンの音色で演奏する
それでは実際に演奏してみましょう。
まず、アコーディオンの音色で演奏する場合の説明をします。
セットを選ぶ
[SET / ]ボタンを押して、セットを
切り換えます(P.12)。
「セット」には、各パートの音色や設定が保
存されていますので、あたかも 40 種類の
アコーディオンを持っている感覚でお使い
になれます(セット一覧 P.124)。
※ セットに関して詳しくは P.71 をご覧ください。
※ セットはフット・スイッチでも切り替え可能です(P.41)。
トレブル・セクションを演奏する
(トレブル・パート)
トレブル・セクションは 92 個のボタン鍵盤
(トレブル・ボタン)を使って演奏します。
トレブル・ボタンを弾くと、現在押されてい
るトレブル・レジスター・スイッチ([1]〜
[14])に登録されている音色が鳴ります。ト
レブル・セクションは「アコーディオン」と
してお使いになることもできますし、オーケ
ストラ音色で演奏することもできます。ここ
ではアコーディオンの音色で演奏する場合を
説明します。
レジスター・スイッチを押し続けると、トレブル・セクションを切
り替えることができます。このとき、トレブル・セクションは
MIDI コマンドを送信し続けます。別のレジスター・スイッチを押
すとトレブル・セクションに戻ります。
1.
必要に応じて各接続を行い(P.17)、電源を入れます
(P.19)。
2.
本機を抱え、お好みのトレブル・レジスター・スイッチ
を押して蛇腹を動かしながらトレブル・ボタンで演奏し
ます。
システム設定「10.3 Bellows Curve(ベローズ・カーブ)」
(P.79)を「Fixed Low」、「Fixed Med」、「Fixed High」のいず
れかに設定した場合は、ダイナミクスは一定となり、蛇腹の動
かし具合に関係なく音量は一定になります。
3.
別のトレブル・レジスター・スイッチを押して音色を変
更します。
ディスプレイには選択した音色と、その音色のリード設定を確
認する画面がしばらくの間表示されます。リード設定の見かた
については「各音色で使用されているリードについて」(P.27)
をご覧ください。
26
メイン画面の「TREBLE」のエリアに、選択したトレブル・レ
ジスター・スイッチの番号が表示されます。
Page 27
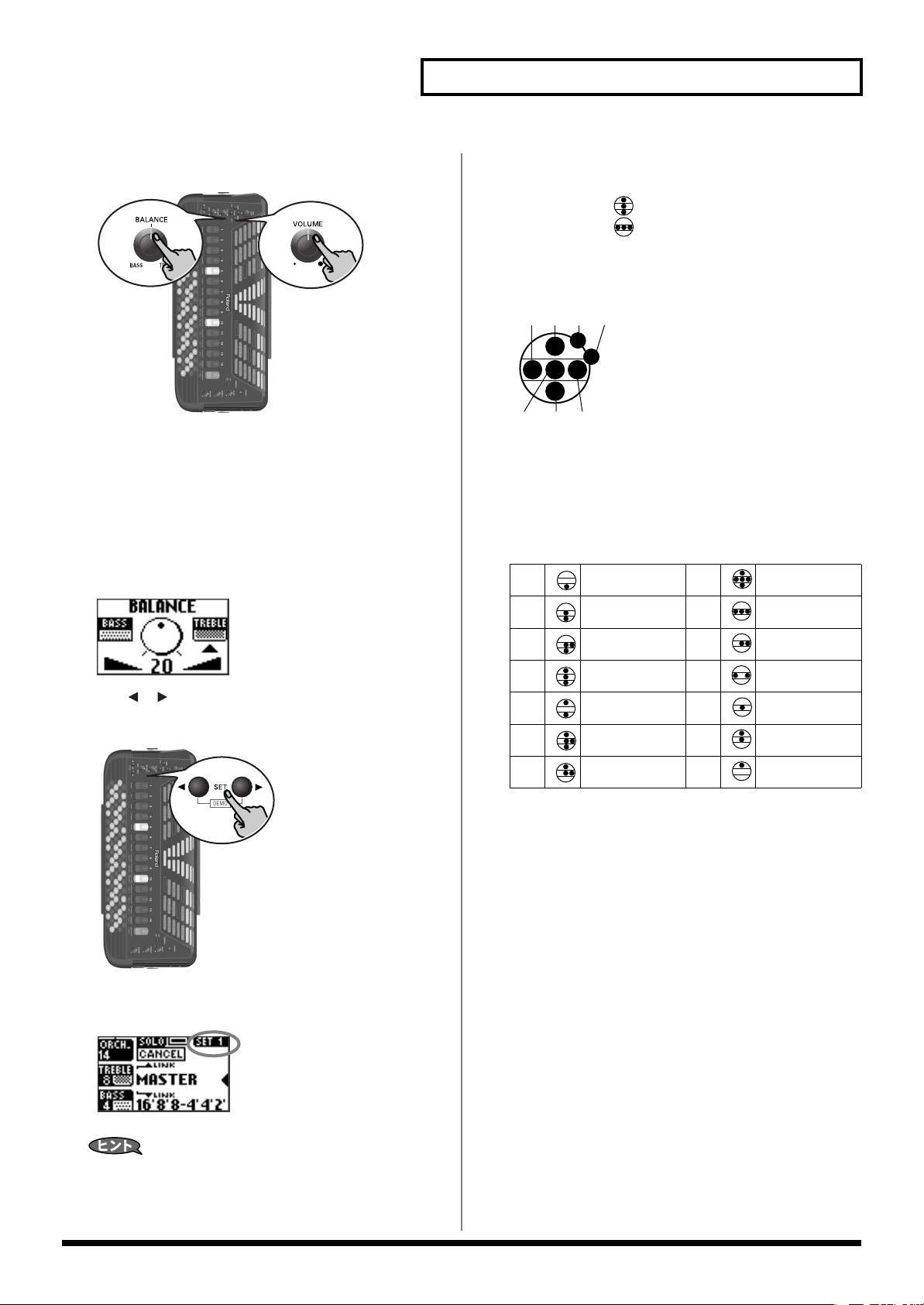
[VOLUME]つまみを回して音量を調節します。
4'8-'
16'
22/3' 51/3'
8+'8'
4.
音が聞こえない場合は[BALANCE]つまみを中央の位
5.
置まで回します。
[BALANCE]つまみはトレブル・セクションとベース・セク
ションの音量バランスを調節するときに使います。「BASS」
の方へいっぱいに回すとトレブル・セクションの音は聞こえな
くなります。音量バランスの設定を変えると、ディスプレイに
以下の設定を確認する画面がしばらくの間表示されます。
演奏する
各音色で使用されているリードについて
ディスプレイにはその音色で使用されているリードが表示され
ます。垂直方向( )の表示は、オクターブの違うリードを
表し、水平方向( )の表示は、わずかにピッチの違うリー
ドを表しています。わずかにピッチの違うリードは中音域の
リード(8' リード)でのみ使用可能です。
使用されているリードは以下のように表示されます。
リードは白または黒のドットで表示されます。
白いドットはカソット機能(P.50)がオン、黒いドットはオフ
になっていることを意味します。
トレブル・パートで各トレブル・レジスター・スイッチに登録
されている音色とそのリード設定は以下のようになります。
1 Bassoon 8 Master
6.
[SET / ]ボタンを押して別のセットを選択しま
す。
選択されたセットの番号がディスプレイの右上隅に表示されま
す。
2 Bandon 9 Musette
3 Cello 10 Celeste
4 Harmon 11 Tremolo
5 Organ 12 Clarinet
6 Accord 13 Oboe
7 Violin 14 Piccolo
FBC-7 の[SET]フット・スイッチでもセットを選択することが
できます(P.41)。
27
Page 28
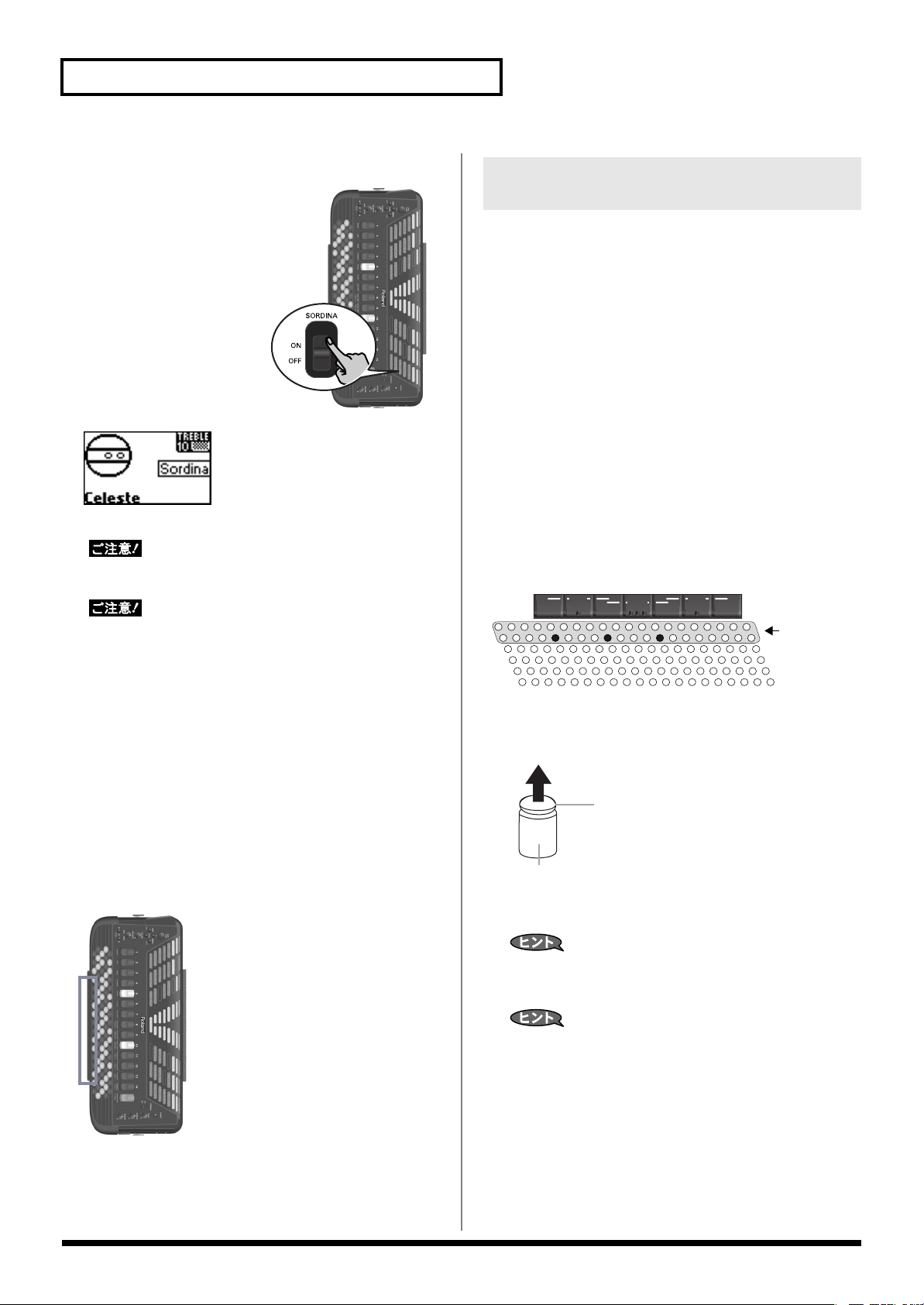
演奏する
Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3
E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3
EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM CM GM DM AM EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM
Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm
E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7 C7 G7 D7 A7 E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7
Edim
Bdim F#dim C#dim Abdim Ebdim Bbdim Fdim Cdim Gdim Ddim Adim Edim Bdim F#dim C#dim Abdim Abdim Bbdim Fdim
FREE BASSORCH BASS
ORCH CHORD
ORCH FREE BS
コード・ボタン
ベース・
チャンバー(ソルディナ)機能を使う
[SORDINA]スイッチを[ON]に
すると、音をやや弱く(ソフトに)
することができます。
通常のアコーディオンでは楽器内部
のチャンバー(共鳴箱)でこの効果
を作り出します。本機ではこの効果
を電子的にシミュレートします。
[SORDINA]スイッチを[ON]に
すると、ディスプレイに以下の設定
を確認する画面がしばらくの間表示
されます。
チャンバー(ソルディナ)機能はトレブル・パートのみ機能しま
す。
ベース・セクションを演奏する
(ベース・パート)
ベース・セクションでは、ストラデラ・ベース・モードとフリー・
ベース・モードのどちらかを選ぶことができます。各モードでは、
ベース・ボタンの配列が違います。
通常は「ストラデラ」のボタン配列で演奏します(ストラデラ・
ベース・モード)。
フリー・ベース・モードはより上級者向けになります。
ストラデラ・ベース・モードで演奏する
ベース・セクションのボタンはベースとコードを演奏します。ベー
スの音は円で囲まれている 2 列に割り当てられ、残りのボタンは
コードを演奏するのに使われます。コードはベース・パートで選択
しているベース・レジスター・スイッチに登録された音色が鳴りま
す。
本機には、ベースとコードのボタンの位置がわかるようにリファレ
ンス・キャップ(凹面のもの)がいくつか付属しています。工場出
荷時には、下図の黒いボタンに 3 個のキャップが取り付けられてい
ますが、別のボタンに取り付けた方が演奏しやすい場合は移動させ
ることもできます。
オルガンの音色(8A 〜 9B)での演奏時は、スピーカー・キャビ
ネットをシミュレートしたロータリー効果がオンになりますので、
チャンバー(ソルディナ)機能は無効になります。その場合、アフ
タータッチ機能を使ってロータリー効果のスピードを変えることが
できます。
アフタータッチは、
マスター・バーを使用します。マスター.
バーを押す強さによってピッチを一時的に変えることができま
す。
マスター・バーを使って音色を切り換える
オーケストラ・パートがオフ(「CANCEL」に設定されている)の
場合(P.34)、マスター・バーを押すことによって、ワンタッチで
お好みの音色を呼び出すことができます。お好みの音色の設定のし
かたについては(「9.8 Master Bar Recall (マスター・バー・リコー
ル)」(P.77)をご覧ください)。
ボタン
リファレンス・キャップをつまんで矢印の方向に引っ張れば外
れます。
リファレンス・キャップ
ベース・ボタン
ボタンを押すと、最後に押したベース・レジスター・スイッチに登
録されている音色が鳴ります。
3 ベース・3 コードの配列に変更することもできます。「10.5
Bass&Chord Mode (ベース &コード・モード)」(P.81)をご覧
ください。
ベース・セクションはオーケストラ音色で演奏することもできます
(P.34)。
1.
必要に応じて各接続を行い(P.17)、電源を入れます
(P.19)。
28
2.
本機を抱え、お好みのベース・レジスター・スイッチを
押してベース・ボタンで演奏します。
本機は電子楽器ですが、蛇腹を動かして音を鳴らします。ア
コースティック・アコーディオンと同じように蛇腹を動かさな
いと音は鳴りません。
Page 29
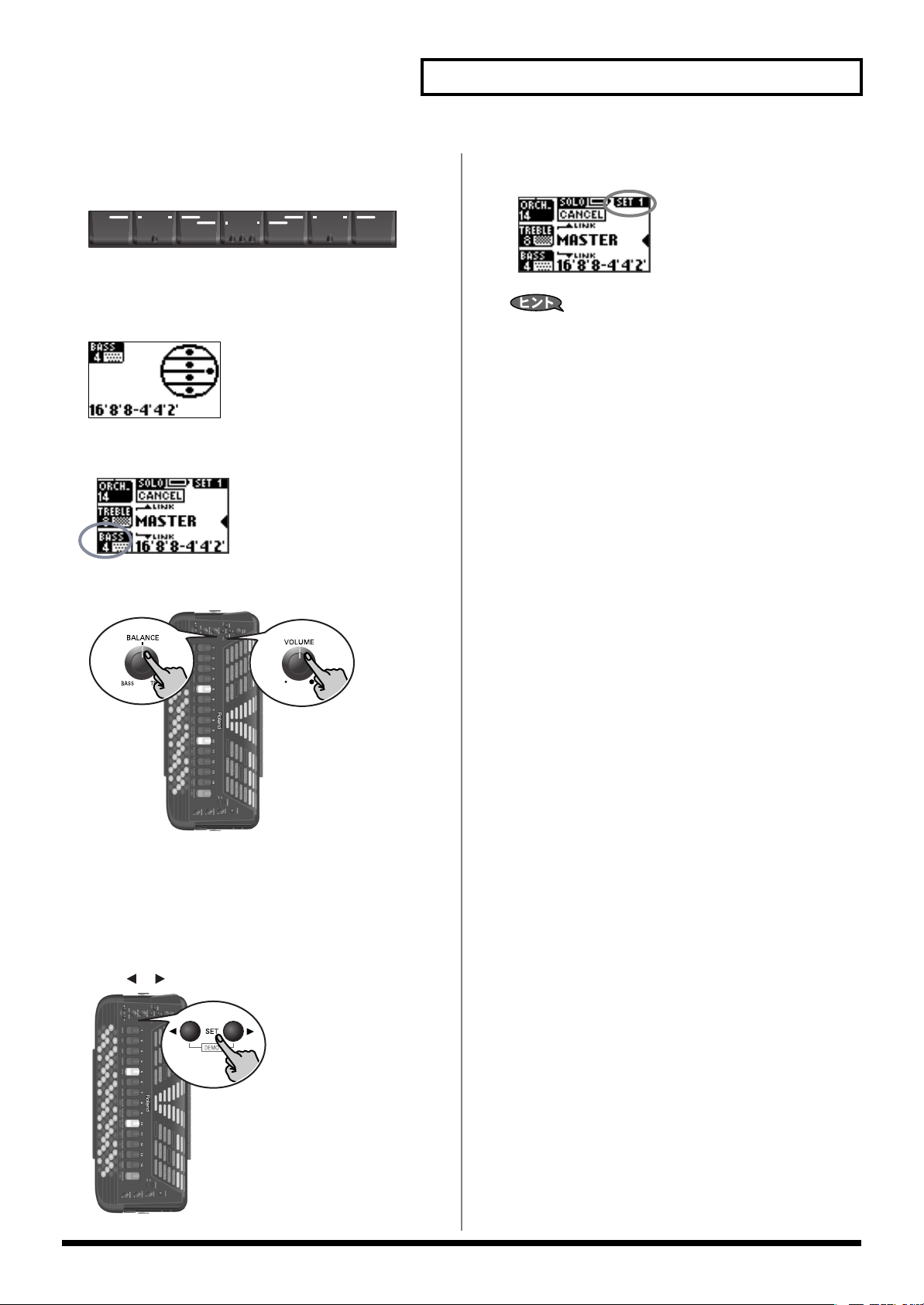
演奏する
別のベース・レジスター・スイッチを押して音色を変更
3.
します。
ORCH FREE BS
ORCH CHORD
ディスプレイには選択した音色と、その音色のリード設定を確
認する画面がしばらくの間表示されます。リード設定の見かた
については「各音色で使用されているリードについて」(P.30)
をご覧ください。
メイン画面の「BASS」のエリアに、選択したベース・レジス
ター・スイッチの番号が表示されます。
[VOLUME]つまみを回して音量を調節します。
4.
FREE BASSORCH BASS
選択されたセットの番号がディスプレイの右上隅に表示されま
す。
FBC-7 の[SET]フット・スイッチでもセットを選択することが
できます(P.41)。
音が聞こえない場合は[BALANCE]つまみを中央の位
5.
置までに回します。
[BALANCE]つまみはトレブル・セクションとベース・セク
ションの音量バランスを調節するときに使います。「TREBLE」
の方へいっぱいに回すとベース・セクションの音は聞こえなく
なります。
6.
[SET / ]ボタンを押して別のセットを選択します。
29
Page 30
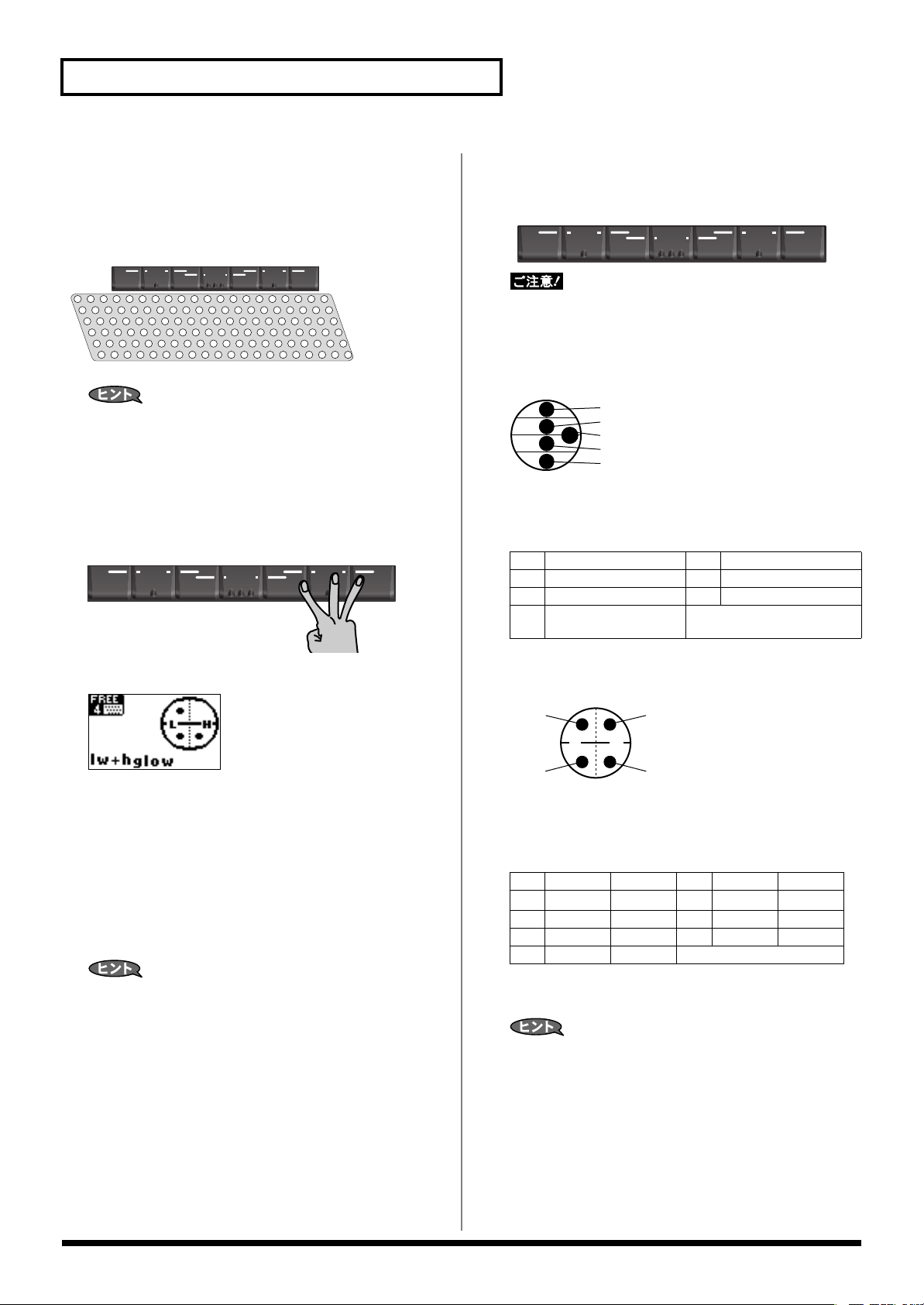
演奏する
FREE BASSORCH BASS
ORCH CHORD
ORCH FREE BS
FREE BASSORCH BASS
ORCH CHORD
ORCH FREE BS
[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
2'
4'
8-4'
8'
16'
L H
8'
16'
8'
ロー側
ハイ側
16'
フリー・ベース・モードで演奏する
本機はフリー・ベース・モードを使うこともできます。フリー・
ベース・モードでは、ストラデラ・ベース・モードと違って、一つ
のボタンに一つの音を割り当てます。各ボタンに対する音の配列を
変えることもできる上級者向けのモードです。
ORCH FREE BS
ORCH CHORD
各ボタンに割り当てられる音階は、ボタン配列によって変わりま
す。ボタン配列の選択方法については「10.6 Free Bass Mode (フ
リー・ベース・モード)」(P.81)、各ベース・ボタンの音階につい
ては「ボタン配列 2(フリー・ベース・モード)」(P.85)をご覧く
ださい。
1.
[FREE BASS]と表記された 3 つのベース・レジス
ター・スイッチを同時に押します。
FREE BASSORCH BASS
E3
ベース・ボタン
各音色で使用されているリードについて
表中の番号は、以下のベース・レジスター・スイッチを示していま
す。
上記のベース・レジスター・スイッチ図に表記されているような番
号は実際にはありません。
ストラデラ・ベース・モードの場合
使用されているリードは以下のように表示されます。
ベース・パートのストラデラ・ベース・モードで各ベース・レ
ジスター・スイッチに登録されているリード設定は以下のとお
りです。
1 2' 5 8 / '4' / 2'
2 4' 6 16' / 8' / 8-4'
3 8-4' 7 16' / 2'
4 16' / 8'/ 8-4' / 4'
/2'
ディスプレイに以下のようにしばらくの間表示されます。
ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま
2.
す。
ディスプレイには選択した音色と、その音色のリード設定を確
認する画面がしばらくの間表示されます。リード設定の見かた
については「各音色で使用されているリードについて」(P.30)
をご覧ください。
3 つの[FREE BASS]レジスター・スイッチを再び押す
3.
とストラデラ・ベース・モードに戻ります。
オーケストラ・ベース・パートの音色はストラデラ・ベース・モー
ド、フリー・ベース・モードのどちらでも使うことができます。詳
しくは「ベース・セクションでオーケストラ音色を使う (オーケ
ストラ・ベース・パート)」(P.34)をご覧ください。
フリー・ベース・モードの場合
使用されているリードは以下のように表示されます。
ベース・パートのフリー・ベース・モードで各ベース・レジス
ター・スイッチに登録されているリード設定は以下のとおりで
す。
ロー側 ハイ側 ロー側 ハイ側
1 16' 16' 5 16' 16' / 8'
2 8' 8' 6 8' 16' / 8'
3 16' / 8' 16' / 8' 7 16' 8'
4 16' / 8' 16'
ロー側のボタンとハイ側でそれぞれ上記のような設定になりま
す。
ロー側のボタンとハイ側のボタンは、ベース・ボタンの配列によっ
て変わります。ボタン配列の選択方法については「10.6 Free Bass
Mode (フリー・ベース・モード)」(P.81)、ロー側、ハイ側のボ
タンの位置については「ボタン配列 2(フリー・ベース・モード)」
(P.85)をご覧ください。
30
Page 31

オーケストラの音色で演奏する
本機は PCM 音源を搭載しており、アコーディオンの音色とは違う
様々な楽器の音色で演奏することができます。外部 MIDI 機器を使
わなくても、いろいろな音色で演奏することができます。
オーケストラ音色はトレブル・セクション、ベース・セクションど
ちらでも演奏できます。トレブル・セクションでオーケストラ音色
を演奏する場合は「オーケストラ・パート」、ベース・セクション
でオーケストラ音色を演奏する場合は「オーケストラ・ベース・
パート/オーケストラ・コード・パート/オーケストラ・フリー・
ベース・パート」と呼びます。
外部 MIDI 機器を使って演奏する場合は「「12 MIDI」MIDI 設定をす
る」(P.97) をご覧ください。
トレブル・セクションとベース・セクションのどちらか一方でオー
ケストラ音色を演奏する(アコーディオンの音色+オーケストラ音
色)こともできますし、両方ともオーケストラ音色で演奏すること
もできます。
トレブル・セクションでオーケストラ音 色を使う(オーケストラ・パート)
トレブル・セクションでオーケストラ音色を演奏します。
音色はひとつだけ選択することができます。
1.
[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押します。
演奏する
トレブル・レジスター・スイッチを押して、オーケスト
2.
ラ・パートの音色を選択します(各音色の種類はトレブ
ル・レジスター・スイッチの下に表記してあります)。
オーケストラ・パートがオンになり、ディスプレイに選択した
音色名が表示されます。
オーケストラ・パートでは各トレブル・レジスター・スイッチ
に以下の 22 種類の音色が登録されています。
スイッチ
の番号
1A Trombone 6B PanFlute
1B Trumpet 7A
2A Tenor Sax 7B
2B Alto Sax 8A PercOrgan
3A Clarinet 8B JazzOrgan
3B Oboe 9A RotOrgan
4A Harmonica 9B TermOrg
4B Mute Harm 10 ScatVoice
5A Violin 11
5B Pizzicato 12
6A Flute 13
*1持続低音機能に対応しています。詳しくは「「HighLand」、
「Zampogna」の音色について」(P.32)をご覧ください。
2
ベロシティ対応の音色です。音量や音質は蛇腹ではなくボ
*
タンをどれくらい強く、速く弾いたかで調整します。
[1]〜[9]のトレブル・レジスター・スイッチでは 2 種類の
音色(A と B)を選択することができます。同じスイッチを押
すことで A と B を切り替えることができます。
音色
スイッチ
の番号
音色
HighLand*
Zampogna*
Mandolin*
AcGuitar*
AcPiano*
1
1
2
2
2
ディスプレイに以下のように表示されます(メイン画面、
P.24)。
パート選択表示が「TREBLE」から「ORCH.」に移動します。
たとえば、B の音色(例:5B Pizzicato)を選択した場合、別のレ
ジスター・スイッチ(12 AcGuitar)を押して、再び最初に押した
レジスター・スイッチ([5])押すと、B の音色(Pizzicato)を呼
び出します。この状態は電源を切るまで記憶されます。演奏してい
るときに A の音色(Violin)の音色が必要なときは、[5]のレジス
ター・スイッチをもう一度押します。
ディスプレイには以下の選択した音色名とトレブル・レジス
ター・スイッチの番号を確認する画面がしばらくの間表示され
ます。
[CANCEL]レジスター・スイッチを押すと、オーケストラ・
パートがオフになります(メイン画面に「CANCEL]が表示さ
れます)。
31
Page 32

演奏する
トレブル・ボタンを演奏します。
3.
トレブル・パート(アコーディオンの音色)はベロシティ対応では
ありません。アコースティック・アコーディオンと同じように蛇腹
の動かし方で音量や音質に変化を加えます。
トレブル・ボタンはアフタータッチ機能に対応しています。ア
フタータッチとは、ボタンを押したあとにそのボタンをさらに
強く押し込むことを言います。トレブル・パートの音色だけで
なく、いくつかのオーケストラ・パートの音色(ギターや、フ
ルートなど)でも、アフタータッチの効果によって音をベン
ド・ダウン(一時的にピッチを下げる)やベンド・アップ(一
時的にピッチを上げる)することができます。オルガンの音色
を選択した場合は、ロータリー効果のスピードをアフタータッ
チで切り換えることもできます。
また外部 MIDI 機器に対して、アフタータッチ情報を送信する
こともできます。
アフタータッチによる効果は同時に鳴っているすべての音に適応さ
れます。コードを弾いた後、そのコード構成音のボタンをひとつだ
け押し込んでも、すべての音が同じようにベンドされます(MIDI
ではこれを「チャンネル・アフタータッチ」と呼びます)。
「HighLand」、「Zampogna」の音色につ
いて
本機には「HighLand」(ハイランド)と「Zampogna」(ザンポー
ニャ)の 2 種類のバグパイプの音色があります。これらは、単音ま
たは複数音の持続低音を鳴らし、その上でメロディーを演奏しま
す。
本機で同じ効果を作り出すために、「HighLand」、「Zampogna」の
どちらかを選択すると、トレブル・ボタンの一番低い 1 オクターブ
の部分に持続低音が割り当てられます。
トレブル・パートとオーケストラ・パー
トを同時に演奏する(オーケストラ・
モード)
トレブル・セクションを演奏したときに、オーケストラ・パートと
トレブル・パートの音色を同時に鳴らすことができます(オーケス
トラ・モード)。
オーケストラ・モードには以下の 4 つのモードがあります。
•
SOLO(ソロ・モード)
オーケストラ・パートの音色だけが鳴ります。[CANCEL]レジ
スター・スイッチを押すとトレブル・パートの音色に戻ります。
•
DUAL(デュアル・モード)
トレブル・パートの音色にオーケスト
ラ・パートの音色を加えます。アコー
ディオンとオーケストラ・パートで選択
した楽器がユニゾンで演奏しているよう
なサウンドになります。ディスプレイに
は、「ORCH.」と「TREBLE」両方のスペースにボタン鍵盤アイ
コンが表示され、2 つの音色が同時になっていることを示しま
す。
•
HIGH(ハイ・モード)
ひとつのボタンを押すとオーケストラ・パートの音色が鳴ります
が、そのボタンを押したままそれよりも低いボタンを押すとトレ
ブル・パートの音色が鳴ります(下図参照)。異なる音色でコー
ドやソロを演奏するときなどに有効です。
オーケストラ・パートの音色
トレブル・パートの音色
メロディーを弾くボタン
E4
E4
持続低音を弾くボタン
持続低音機能について説明します。
グレー部分のボタン(上図参照)を押すとボタンから指を離して
•
もこの音は無限に持続します。2 音(またはそれ以上)同時に押
してもそれらの音は無限に持続します
鳴っている持続低音を止めるには、別のグレーのボタンを押すか
•
(別の持続低音に変わります)、または同じボタンをもう一度押し
ます(持続低音が止まります)。
持続低音機能は「HighLand」と「Zampogna」の音色でのみ使う
ことができます。
32
LOW(ロー・モード)
•
ひとつのボタンを押すとオーケストラ・パートの音色が鳴ります
が、そのボタンを押したままそれよりも高いボタンを押すとトレ
ブル・パートの音色が鳴ります(下図参照)。最初に弾いた音よ
りも高い音程域でメロディー(またはオブリガード)を演奏する
ときなどに有効です。
トレブル・パートの音色
オーケストラ・パートの音色
Page 33

[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押しながら、
1.
[11]、[12]、[13]、[14]のいずれかのトレブル・レジ
スター・スイッチを押してオーケストラ・モードを選択
します。
[11]:LOW(ロー・モード)を選択します。
•
[12]:HIGH(ハイ・モード)を選択します。
•
[13]:DUAL(デュアル・モード)を選択します。
•
•
[14]:SOLO(ソロ・モード)を選択します。
ディスプレイに以下の選択を確認する画面がしばらくの間表示
されます(以下のうちのひとつが表示されます)。
演奏する
マスター・バーを使ってオーケストラ・
パートをミュートする
オーケストラ・パートがオンのとき(メイン画面のオーケストラ・
パート部分が「CANCEL」以外の表示になっているとき)、マス
ター・バーを使ってオーケストラ・パートのミュートのオン/オフ
をワンタッチで切り換えることができます。あるフレーズをトレブ
ル・パートの音色だけで演奏し、ワンタッチでオーケストラ・パー
トを加えるような演奏をすることができます。
マスター・バーを押すたびに、オーケストラ・パートのミュートの
オン/オフが切り換わります。
マスター・バーを押したときの効果は、以下のように変わります。
•
オーケストラ・モード(P.32)がデュアル・モード、ハイ・モー
ドまたはロー・モードの場合
オーケストラ・パートの音色のみミュートします(トレブル・
パートの音色はオンのままです)。
オーケストラ・モード(P.32)がソロ・モードの場合
•
トレブル・パートとオーケストラ・パートが交互に切り換わりま
す。
演奏して確認します。
2.
オーケストラ・モードの設定はセットに保存されます(「2.13
Orchestra Link (オーケストラ・リンク)」(P.53)をご覧くださ
い)。保存したモードはオーケストラ・パートをオンにしたときに
呼び出されます。
オーケストラ・パートをミュートするとディスプレイには以下のよ
うに表示されます(「ORCH.」のスペースからボタン鍵盤アイコン
が消えます)。
再びマスター・バーを押してオーケストラ・パートのミュートを解
除すると、「ORCH.」のスペースにもボタン鍵盤アイコンが表示さ
れます。
33
Page 34

演奏する
FREE BASS
ORCH BASS
ORCH CHORD
ORCH FREE BS
[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
オーケストラ・パートの音量を設定する
(オーケストラ・ボリューム機能)
デュアル、ハイ、ローの各オーケストラ・モード(P.32)で、トレ
ブル・パートに比べてオーケストラ・パートの音色の音量が大きす
ぎたり、または小さすぎたりする場合は音量を調節することができ
ます。
[DOWN]ボタンを 1 回押します。
1.
ディスプレイに以下のように表示されます。
ベース・セクションでオーケストラ音色
を使う
(オーケストラ・ベース・パート)
オーケストラ・ベース・パートの音色はストラデラ・ベース・モー
ド(P.28)とフリー・ベース・モード(P.30)のどちらでも使うこ
とができます。
オーケストラ・ベース・パートの音色はベース音のボタン列(蛇腹
に近い側)のみに適用されます。コード音のボタンはオーケスト
ラ・ベース音色では鳴りません。
ベース・セクションでは、マスター・バーを使ってパートを切り換
えることはできません。
1.
[ORCH BASS]と表記された 3 つのベース・レジス
ター・スイッチを同時に押します。
※ 上記のベース・レジスター・スイッチの図に表記されているよ
うな番号は実際にはありません。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。
「Off」、「-40」〜「Std」〜「40」の範囲で音量のバランスを
調節します。「Std」でオーケストラ・パートは標準的な音量に
なり、設定値を下げると小さく、上げると大きくなります。
「Off」にするとオーケストラ・パートの音量がゼロになりま
す。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
変更した設定は保存することができます(P.108)。
オーケストラ・パートをオフにする
トレブル・パートの音色だけが鳴る状態にするには、[CANCEL]
レジスター・スイッチを押します。
再びオーケストラ・パートをオンにする場合は、P.31 の手順 1と
2
の操作をもう一度行ってください。
ディスプレイに以下のようにしばらくの間表示されます。
2.
ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま
す。
オーケストラ・ベース・パートでは各ベース・レジスター・ス
イッチに以下の 7 種類の音色が登録されています。
スイッチ
の番号
音色
1 Acoustic 5 Picked
2 Bowed 6 Tuba
3 Fingered 7 Tuba Mix
4 Fretless
スイッチ
の番号
音色
34
Page 35

演奏する
オーケストラ・ベース・パートの音量を
設定する(オーケストラ・ベース・ボ
リューム機能)
ベース・パートに比べてオーケストラ・ベース・パートの音色の音
量が大きすぎたり、または小さすぎたりする場合は音量を調節する
ことができます。
[DOWN]ボタンを 2 回押します。
1.
ディスプレイに以下のように表示されます。
コード・セクションでオーケストラ音色
を使う
(オーケストラ・コード・パート)
オーケストラ・コード・パートは、ベース・セクションのコード列
にオーケストラ音色を設定することができます。
オーケストラ・コード・パートはコード・ボタンのみで使用できま
す。ただし、フリー・ベース・モードでは、すべてがベース・ボタ
ンになるため、オーケストラ・コード・パートを使うことはできま
せん。
ベース・レジスター・スイッチの中央 3 つのボタンを同
1.
時に押します。
ORCH BASS
ディスプレイにしばらくの間次のように表示されます。
ORCH FREE BS
ORCH CHORD
FREE BASS
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。
「Off」、「-40」〜「Std」〜「40」の範囲で音量のバランスを
調節します。「Std」でオーケストラ・ベース・パートは標準的
な音量になり、設定値を下げると小さく、上げると音大きくな
ります。「Off」にするとオーケストラ・ベース・パートの音量
がゼロになります。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
この設定は保存することができます(P.108)。
オーケストラ・ベース・パートをオフに
する
ベース・パートの音色だけが鳴る状態にするには、3 つの[ORCH
BASS]レジスター・スイッチを同時に押します。
再びオーケストラ・ベース・パートをオンにする場合は、P.34 の
手順 1と 2の操作をもう一度行ってください。
2.
ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま
す。
ORCH CHORD sound(オーケストラ・コード音色)
スイッチ
の番号
1* Trombone
2* Tenor Sax(テ
3* Clarinet
4* Trem Organ(
* の付いた音色の音量は蛇腹の動きのみで変化します。これらの音
色はベロシティには対応していません。
音色
(トロンボーン)
ナー・サックス)
(クラリネット)
トレモロ・オル
ガン)
スイッチ
の番号
音色
5* Voice(ボイス)
6 Ac Guitar
(アコースティッ
ク・ギター)
7 Ac Piano(
アコースティッ
ク・ピアノ)
35
Page 36

演奏する
オーケストラ・コード・パートの音量を
設定する
他のパートに対してオーケストラ・コード・パートの音量が大きす
ぎたり、または小さすぎたりする場合は音量を調節することができ
ます。
[DOWN]ボタンを 3 回押します。
3.
ディスプレイに以下のように表示されます。
フリー・ベース・セクションでオーケス トラ音色を使う(オーケストラ・フ リー・ベース・パート)
オーケストラ・フリー・ベース・パートは、フリー・ベース・モー
ドが選ばれている時、ベース・ボタンにオーケストラ音色を設定す
ることができます。このときすべてのボタンはベース・ボタンとな
り、コード・ボタンとしては機能しません。
[FREE BASS]と表記された 3 つのベース・レジス
1.
ター・スイッチを同時に押し、同名のアコーディオン・
モードにします。
ORCH BASS
[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
既にフリー・ベース・モードの場合は、この操作は必要ありま
せん。
[ORCH FREE BS]と表記された 3 つのベース・レジス
2.
ORCH FREE BS
ORCH CHORD
ター・スイッチを同時に押します。
ORCH BASS
[7] [6] [5] [4] [3] [2] [1]
ORCH FREE BS
ORCH CHORD
FREE BASS
FREE BASS
4.
[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。
「Off」、「-40」〜「Std」〜「+40」の範囲で音量のバランスを
調節します。オーケストラ・コード・パートは「Std」で標準
的な音量になり、値を下げると小さくなり、上げると大きくな
ります。「Off」にするとオーケストラ・コード・パートの音量
がゼロになります。
設定した値を保存することができます。(P.108)
5.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
オーケストラ・コード・パートをオフに
する
6.
もう一度、ベース・レジスター・スイッチの中央 3 つの
ボタンを同時に押すと、通常の(アコーディオン)コー
ド・モードに戻ります。
ORCH BASS
ORCH FREE BS
ORCH CHORD
FREE BASS
ディスプレイに以下のようにしばらくの間表示されます。
ベース・レジスター・スイッチを押して音色を選択しま
3.
す。
ORCH FREE BS sounds
(オーケストラ・フリー・ベース音色)
スイッチ
の番号
※ ベース・レジスター・スイッチの図に表記されているような番
号は実際にはありません。
音色
1* Trombone(ト
ロンボーン)
2* Tenor Sax(テ
ナー・サックス)
3* Clarinet(クラリ
ネット)
4* Trem Organ(ト
レモロ・オルガ
ン)
スイッチ
の番号
音色
5* Voice(ボイス)
6 Ac Guitar(ア
コースティッ
ク・ギター)
7 Ac Piano(ア
コースティッ
ク・ピアノ)
36
* の付いた音色の音量は蛇腹の動きのみで変化します。これらの音
色はベロシティには対応していません。
Page 37

演奏する
オーケストラ・フリー・ベース・パート
の音量を設定する(オーケストラ・フ
リー・ベース・ボリューム機能)
トレブル・パートやオーケストラ・パートに比べてオーケストラ・
フリー・ベース・パートの音色の音量が大きすぎたり、または小さ
すぎたりする場合は音量を調節することができます。
[DOWN]ボタンを 4 回押します。
4.
ディスプレイに以下のように表示されます。
デジタル・エフェクトを使う
アコーディオンやオーケストラの音色にリバーブやコーラス、ディ
レイなどのデジタル・エフェクトを加えることができます。
本機には 3 種類のデジタル・エフェクトが搭
載されています。
•
REVERB(リバーブ):コンサート・ホー
ル、教会、部屋で演奏しているような効果
を作り出します。音色に「深み」を加えま
す。
•
CHORUS(コーラス):複数の同じ楽器が
同時に演奏されているような効果を作り出
します(ピッチのわずかに違うリードが複
数ある音色に似ています)。
•
DELAY(ディレイ):エコー効果を作り出
します。音を遅らせる時間が短い(「ス
ラップバック」と呼びます)ときはリバー
ブに似た効果を作り出します。音を遅らせる時間が長いときはエ
コーのような効果を作り出します。
[DELAY]、[CHORUS]、[REVERB]の各つまみを使ってエフェク
トの量を調節します。エフェクトが必要でない場合は、該当するつ
まみを左いっぱいまで(小さいドットの方へ)回します。つまみを
右(大きいドットの方へ)に回すとエフェクトの音が多くなりま
す。
[DATA / ENTER]つまみを回して音量を調節します。
5.
「Off」、「-40」〜「Std」〜「+40」の範囲で音量のバランスを
調節します。オーケストラ・フリー・ベース・パートは「Std」
で標準的な音量になり、値を下げると小さくなり、上げると大
きくなります。「Off」にするとオーケストラ・フリー・ベー
ス・パートの音量がゼロになります。
設定した値を保存することができます。(P.108)
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
6.
オーケストラ・フリー・ベース・パート
をオフにする
もう一度[ORCH FREE BS]と表記された 3 つのベー
7.
ス・レジスター・スイッチを同時に押すと、フリー・
ベース・モードに戻ります。
更にもう一度これらのスイッチを同時に押すと、フリー・ベー
ス・モードからベース・モードに戻ります。
つまみの値は、左いっぱいまで回した状態で「0」、右いっぱいまで
回した状態で「127」になります。つまみを 12 時方向(中央点)
にしたときの値は、それぞれお好みの値を設定することができま
す。詳しくは、以下のページを参照ください。
「9.1 Reverb Macro(リバーブ・マクロ)」(P.72)、「9.3 Chorus
Macro(コーラス・マクロ)」(P.74)、「9.5 Delay Macro(ディレ
イ・マクロ)」(P.75)
各エフェクトはより詳細な設定をすることができます。詳細は「エ
フェクトの設定をする」(P.72)をご覧ください。
エフェクトのつまみの設定は全セクション、全セットに適用されま
す。
デジタル・エフェクトの設定は、各セットで保存した音色ごとに保
存することができます。セットを選んで、音色を選んだときに、あ
らかじめ設定されたエフェクトを加えたい場合は、各エフェクトの
つまみを中央の位置にしておきます。
つまみを回してもそのエフェクトの効果を確認することができない
場合があります。これはその音色で設定された各エフェクトのセン
ド・レベルによるもので(「2.8 Reverb Send(リバーブ・センド)
2.9 Chorus Send(コーラス・センド)2.10Delay Send(ディレ
イ・センド)」(P.51))などをご覧ください)、そのエフェクトへ信
号を送らないように設定されているからです。その場合は、つまみ
を最大にしても効果が変わりません。
37
Page 38

演奏する
その他の実践的な機能
本機は電子楽器であり、その外見はアコースティック・アコーディ
オンと変わらないものの、それとはまったく異なった技術に基づい
て設計されています。ここでは電子楽器ならではの使いかたを説明
します。
これらの機能は、フロント・パネルの操作子を使ってワンタッチで
選択することができるようになっています。
これらの機能は主に一時的な調節のために使われる機能であるた
め、ここで行った設定の変更は自動的に保存されません。これらの
設定を保存するには、P.108 をご覧ください。
[DATA / ENTER]つまみを回してキーを選択します。
2.
このキーの表示(上図では C#)は元となるキーが常に C のと
きの階名ですので、たとえば、Bb で演奏中に F# にトランス
ポーズする場合などは多少複雑に感じるかもしれません。その
場合、数値の方をガイドとしてお使いください。この数値は半
音が 1 単位になっています。たとえば、以下のようになりま
す。
•
曲のキーが E メジャーで、演奏するのに使いたいキーが C メ
ジャーの場合
シフトする半音数が[C# → D → Eb → E]と 4 段階になり
ますので、設定値は 4 になります。
3.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
以下の機能はメニューから設定することもできます。
ピッチに関係した機能
Transpose(トランスポーズ機能)
トランスポーズ機能はあなたが演奏している曲のキーを変えるとき
に使います。この機能を使うと、たとえば、C メジャーの運指で E
メジャーの曲を演奏することができます。あるキーで演奏してい
て、突然別のキーに変える必要があるときに便利な機能です。
例:
このように演奏しているときに
Transpose
音はこのように鳴ります。
「Transpose」の設定は保存されません。電源を切ると元に戻りま
す。
Musette Detune
(ミュゼット・デチューン機能)
アコーディオンのトレブル・セクションで使う 8' のリードは、2 枚
ないし 3 枚のピッチがわずかに違う別々のリードを組み合わせて豊
潤な音色(「ミュゼット・トーン」)を作り出します。一方のリード
はピッチをわずかに高く、もう一方のリードはピッチをわずかに低
く、それぞれチューニングされています(3 枚目のリードはピッチ
をずらさないダイレクトな音が鳴ります)。
本機ではその「リード」(実際には存在しませんが)を「チューニ
ング」することができます。
メイン画面(P.24)が表示されているときに[UP]ボ
1.
タンを 2 回押します。
メイン画面(P.24)が表示されているときに[UP]ボ
1.
タンを 1 回押します。
38
[DATA / ENTER]つまみを回してトレブル・セクショ
2.
ンのリードのチューニングのタイプを以下の中から選択
します。
Page 39

演奏する
TYPE
(タイプ)
「Off」を選ぶと、ミュゼット・デチューン機能はオフになりま
す。
3.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
Off(オフ)
Dry(ドライ)
Classic(クラシック)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
AmericanL(アメリカン L)
AmericanH(アメリカン H)
NorthEur(ノース・ヨーロッパ)
GermanL(ジャーマン L)
D-FolkL(ジャーマン・フォーク L)
ItalianL(イタリアン L)
GermanH(ジャーマン H)
Alpine(アルペン)
ItalianH(イタリアン H)
D-FolkH(ジャーマン・フォーク H)
French(フレンチ)
Scottish(スコティッシュ)
Scale(音階機能)
音階機能は演奏する音楽に最適な音階を選択するときに使います。
欧米を中心に使用されている平均律や、アラブやインドネシアなど
の音楽文化圏で使用されている音階などを選ぶことができます。
また、必要とする音階が初期設定にない場合は、新たに音階を設定
し(「1.4 Scale Edit(スケール・エディット)」(P.47))、それを選
択することもできます。
メイン画面が表示されているときに[UP]ボタンを 3 回
1.
押します。
TYPE(タイプ) 説明
Arabic 1
(アラビック 1)
Arabic 2
(アラビック 2)
Just Major
(ジャスト・メ
ジャー)
Just Minor
(ジャスト・マイ
ナー)
Pythagorean
(ピタゴリアン)
Mean-Tone
(ミーン・トーン)
Werckmeister
(ヴェルクマイス
ター)
Kirnberger
(キルンベルガー)
「Equal (Off)」以外では、演奏する曲のキーに合った基音を指
定する必要があります。
[DATA / ENTER]つまみを押すと「KEY」のところが
3.
アラビア音階です。「Arabic 1」は
E と B が 1 / 4 音(-50 CENT)低
くなっており、「Arabic 2」は E と
A が 1 / 4 音低くなっています。
完全 5 度と長 3 度を純正な音程に
した(純正律の)長音階です。コー
ドを弾くと非常に美しい響きを作り
出しますが、バランスが悪いため、
メロディーの演奏には適しません。
マイナー・キーの曲を演奏するのに
適した音階です。
古代ギリシャで考案されたピタゴラ
ス音律による音階です。4 度と 5 度
が純正な音程になります。3 度がい
くらか濁り気味ではあるものの、メ
ロディーがより鮮明なものになりま
す。
純正律の欠点をいくつか補った中全
音律による音階で、転調をスムーズ
にします。
中全音律とピタゴラス音律を組み合
わせた音階で、あらゆるキーで演奏
することができます。
中全音律と純正律に改善を加えた結
果による音階で、転調がスムーズに
なり、また、あらゆるキーで演奏す
ることができます。
反転します。
[DATA / ENTER]つまみを回して以下の中から音階を
2.
選択します。
TYPE(タイプ) 説明
Equal (Off)
(イコール)
User 1
(ユーザー 1)
User 2
(ユーザー 2)
User 3
(ユーザー 3)
平均律です。1 オクターブを 12 分
割した最も一般的な音律です。
新たに作成した音階を呼び出しま
す。詳細は「1.4 Scale Edit(ス
ケール・エディット)」(P.47)をご
覧ください。
4.
[DATA / ENTER]つまみを回して基音(C 〜 B)を選択
します。
5.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
39
Page 40

演奏する
音量に関係した機能
Orchestra Volume / Orc.Bass Volume
/ Orc. Chord Volume / Orc. FBass
Volume(オーケストラ・ボリューム機能
/オーケストラ・ベース・ボリューム機
能/オーケストラ・コード・ボリューム
機能/オーケストラ・フリー・ベース・
ボリューム機能)
この 4 つのパラメーターを使ってトレブル、ベースの各パートに対
する、オーケストラ・パート、オーケストラ・ベース・パート、
オーケストラ・コード・パート、オーケストラ・フリー・ベース・
パートの音色の音量を設定します。詳しくは「オーケストラ・パー
トの音量を設定する(オーケストラ・ボリューム機能)」(P.34)、
「オーケストラ・ベース・パートの音量を設定する(オーケストラ・
ベース・ボリューム機能)」(P.35)、「オーケストラ・コード・パー
トの音量を設定する」(P.36)、「オーケストラ・フリー・ベース・
パートの音量を設定する(オーケストラ・フリー・ベース・ボ
リューム機能)」(P.37)をご覧ください。
NOISE EDIT (Valve, Button)
(ノイズ・エディット機能)
本機の音色は、実際の楽器が鳴っているかのように、その音色をシ
ミュレートするだけでなく、楽器自体の動きやその結果生じる「ノ
イズ」も再現しています。たとえばギターの音色には運指したとき
の音も含まれています。一方、アコーディオンの音色では、実際の
アコーディオンでは消すことのできないバルブやボタンの音までシ
ミュレートしています。
これらのノイズが目立ちすぎたりまたは小さすぎたりする場合に
は、音量を調節することができます。
メイン画面が表示されているときに[DOWN]ボタンを
1.
3 回押します。
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して「Valve LEVEL」と
「Button LEVEL」のいずれかを選択します。
Valve LEVEL:トレブル・セクションのボタン(バルブ)
•
のノイズの音量を調節します。
Button LEVEL:ベース・セクションのボタンのノイズの音
•
量を調節します。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
3.
ボタンを押してノイズの音量(「Off」、「-40」〜「Std」
〜「40」)を設定します。
設定値を下げると小さく、上げると大きくなります。「Std」に
すると初期設定となり、「Off」にするとノイズの音は消えま
す。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
4.
40
Page 41

演奏する
Roland
エクスプレッション・ペダル
フット・スイッチ(FBC-7、付 属)について
FBC-7 は本機の電源ユニットであり、フット・スイッチにもなりま
す。またバッテリー(FR-7b のみ付属)を充電することもできま
す。
ここでは、FBC-7 を本機に接続して、フット・スイッチとして使う
場合の説明をします。
FBC-7 の電源ユニットとしての使いかたについては「FBC-7 を使
用する場合」(P.19)をご覧ください。また充電器としてお使いに
なる場合は「バッテリーを充電する」(P.23)をご覧ください。
FBC-7 を本機に接続するには「FBC-7、外部オーディオ機器を接
続する」(P.17)をご覧ください。
FBC-7 には以下の 5 つのフット・スイッチがあります。
[SET(1、2)]スイッチ
1.
2.
[REGISTER(3、4)]スイッチ
3.
[SUSTAIN(5)]スイッチ
ベース・リンク機能(P.52)やオーケストラ・リンク機能(P.53)
がオンになっていると、リンクされているパートの音色も同時に変
わります。
[SUSTAIN]スイッチを使う
トレブル・セクションで、オーケストラ・パートを演奏していると
き[SUSTAIN]スイッチを踏んでいる間は、トレブル・ボタンを
離しても音を持続(サステイン)させることができます。ピアノの
音色などで、レガート演奏をするときに使用します。
また FBC-7 に外部 MIDI機器を接続しているときは、[SUSTAIN]
スイッチを踏んでいる間、MIDI メッセージのホールド 1(コント
ローラー・ナンバー 64)を送信します。
エクスプレッション・ペダル(別売)を 使う
エクスプレッション・ペダル(別売:EV シリーズ)を FBC-7 の
EXPRESSION PEDAL ジャックに接続すると、ペダルを使ってオー
ケストラ・パートの「11 Mandolin」「12 AcGuitar」「13 AcPiano」
の音色の音量を変化させることができます。
[SET]スイッチを使う
「セット」(P.71)を選ぶことができます。[SET 1]スイッチを踏
むと一つ前のセット、[SET 2]スイッチを踏むと一つあとのセット
を選ぶことができます。
セットは 40 セットあります。「セット 1」を選んでいるときに
[SET 1]スイッチを踏むと、「セット 40」になります。同じように
「セット 40」を選んでいるときに[SET 2]スイッチを踏むと、
「セット 1」になります。
[REGISTER]スイッチを使う
トレブル・セクションの音色(トレブル・パート、P.26 /オーケ
ストラ・パート、P.31)を選ぶことができます。[REGISTER]ス
イッチを踏むたびに、トレブル・レジスター・スイッチに登録され
ている音色の順番で、音色が変わります。
[REGISTER 3]スイッチを踏むと一つ前の音色、[REGISTER 4]
スイッチを踏むと一つあとの音色を選ぶことができます。
最初のトレブル・レジスター・スイッチに登録されている音色を選
んでいるときに[REGISTER 3]スイッチを踏むと、最後の音色に
なります。同じように最後のトレブル・レジスター・スイッチに登
録されている音色を選んでいるときに[REGISTER 4]スイッチを
踏むと、最初の音色になります。
ペダルを踏むと音量が大きく、戻すと音量が小さくなります。
デュアル・モード(P.32)で演奏時に、トレブル・パートを演奏し
ながら、オーケストラ・パート(「11 Mandolin」「12 AcGuitar」
「13 AcPiano」)だけの音量を調節するといった使いかたができま
す。
また FBC-7 に外部 MIDI機器を接続しているときは、ペダルの操作
によって、MIDI メッセージのエクスプレッション(コントロー
ラー・ナンバー 11)を送信します。
エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの(別売:EV シ
リーズ)をお使いください。他社製品を接続すると、本体の故障の
原因になる場合があります。
各スイッチにいろいろな機能を割り当て る
各スイッチにいろいろな機能を割り当てることができます。お好み
の機能をスイッチに割り当てて、ワンタッチで操作を行うことがで
きます。
機能の割り当てかたについて詳細は「10.4 Pedal Controller (ペダ
ル・コントローラー)」(P.79)をご覧ください。
41
Page 42

本機の設定をする
本機では、音色の細かな設定や、チューニング、音階などさまざま
な設定をすることができます。
設定できる項目について
以下の項目を設定することができます。設定項目をパラメーターと
呼び、各パラメーターは設定の種類によって以下のように大きく別
れています(パラメーター・グループ)。
イージー・モードでは、下表の●印が表示されているパラメーター
のみ選択することができます。すべてのパラメーターを選択するに
はフル・モードにしてください(P.25)。
設定内容の詳細については、それぞれの参照ページをご覧くださ
い。
本機全体に適用される設定と、セットごとに保存される設定があり
ます。
「*」マークのついた設定はセットには保存されません。これらは本
機の全般的なパラメーターですので別のメモリーに保存されます。
1.
TUNING*(チューニングに関する設定、P.46)
番号 メニュー名 概要
1.1 Master Tune 全体的なチューニング ●
1.2 Transpose トランスポーズ ●
1.3 Scale スケール ●
1.4 Scale Edit スケールの編集
1.5 Scale Assign パートのスケール ●
本機の音程に関するパラメーターです。本機全体に適用されま
す。
レジスター単位での音程に関するパラメーターは、各パートの
設定をご覧ください。
「Transpose」の設定は保存されません。電源を切ると元に戻りま
す。
TREBLE EDIT(トレブル・パートに関する設定、P.48)
2.
番号 メニュー名 概要
2.1 Reed Type リードのタイプ
2.2 Register レジスター
2.3 Reed Volume リードの音量
2.4 Treble Octave オクターブ ●
2.5 Valve Noise バルブのノイズ
2.6 Musette Detune ミュゼット・ デチューン ●
2.7 Bellows Detune 蛇腹の設定
2.8 Reverb Send リバーブ量 ●
2.9 Chorus Send コーラス量 ●
2.10 Delay Send ディレイ量 ●
2.11 Aftertouch Pitch アフタータッチ ●
2.12 Bass Link ベース・リンク ●
2.13 Orchestra Link オーケストラ・リンク ●
2.14 Orchestra Chord Link オーケストラ・ コード・
リンク
2.15 Treble MIDI TX MIDI 設定
イージー
モード
イージー
モード
BASS EDIT(ベース・パート(ストラデラ・ベース・
3.
モード)に関する設定、P.55)
番号 メニュー名 概要
3.1 Reed Type リードのタイプ
3.2 Register レジスター
3.3 Reed Volume リードの音量
3.4 Button Noise ボタンのノイズ
3.5 Reed Growl ベース・リードのノイズ
3.6 Bellows Detune 蛇腹の設定
3.7 Reverb Send リバーブ量 ●
3.8 Chorus Send コーラス量 ●
3.9 Delay Send ディレイ量 ●
3.10 Bass MIDI TX MIDI設定
3.11 Chord MIDI TX MIDI設定
ベース・パートのストラデラ・ベース・モードに関するパラ
メーターで、レジスターごとに設定できます。セットごとに保
存されます。
4.
FREE BS EDIT(ベース・パート(フリー・ベース・
モード)に関する設定、P.59)
番号 メニュー名 概要
4.1 Reed Type リードのタイプ
4.2 Register レジスター
4.3 Reed Volume リードの音量
4.4 Button Noise ボタンのノイズ
4.5 Reed Growl ベース・リードのノイズ
4.6 Bellows Detune 蛇腹の設定
4.7 Reverb Send リバーブ量 ●
4.8 Chorus Send コーラス量 ●
4.9 Delay Send ディレイ量 ●
4.10 Free Bass MIDI TX MIDI 設定
ベース・パートのフリー・ベース・モードに関するパラメー
ターで、レジスターごとに設定できます。セットごとに保存さ
れます。
ORC.BASS EDIT(オーケストラ・ベース・パートに関
5.
イージー
モード
イージー
モード
する設定、P.63)
番号 メニュー名 概要
5.1 Lowest Note 最低音の設定
5.2 Orc.Bass Release T. 離鍵後の減衰 ●
5.3 Orc.Bass Volume 音量 ●
5.4 Reverb Send リバーブ量 ●
5.5 Chorus Send コーラス量 ●
5.6 Delay Send ディレイ量 ●
5.7 Orchest. MIDI TX MIDI設定
オーケストラ・ベース・パートに関するパラメーターで、レジ
スターごとに設定できます。セットごとに保存されます。
●
イージー
モード
トレブル・パートに関するパラメーターで、レジスターごとに
設定できます。セットごとに保存されます。
42
Page 43

本機の設定をする
ORCH. EDIT(オーケストラ・パートに関する設定、
6.
P.65)
番号 メニュー名 概要
6.1 Orchestra Octave オクターブ ●
6.2 Orchestra Volume 音量 ●
6.3 Bellows Detune 蛇腹の設定
6.4 Reverb Send リバーブ量 ●
6.5 Chorus Send コーラス量 ●
6.6 Delay Send ディレイ量 ●
6.7 Aftertouch Pitch アフタータッチ ●
6.8 Orchest. MIDI TX MIDI 設定
オーケストラ・パートに関するパラメーターで、レジスターご
とに設定できます。セットごとに保存されます。
ORCH CHORD EDIT(オーケストラ・コード・パート
7.
に関する設定、P.67)
番号 メニュー名 概要
7.1 Orc. Chord Volume 音量 ●
7.2 Reverb Send リバーブ量 ●
7.3 Chorus Send コーラス量 ●
7.4 Delay Send ディレイ量 ●
7.5 Orc. Chord MIDI TX MIDI 設定
ORC. FBS EDIT(オーケストラ・フリー・ベース・パー
8.
トに関する設定、P.69)
番号 メニュー名 概要
8.1 ORC. FreeBs Volume 音量 ●
8.2 Reverb Send リバーブ量 ●
8.3 Chorus Send コーラス量 ●
8.4 Delay Send ディレイ量 ●
8.5 Orc. FreeBs MIDI TX MIDI 設定
SET COMMON(セット全般の設定、P.71)
9.
番号 メニュー名 概要
9.1 Reverb Macro リバーブのタイプ ●
9.2 Reverb Parameters リバーブの詳細設定
9.3 Chorus Macro コーラスのタイプ ●
9.4 Chorus Parameters コーラスの詳細設定
9.5 Delay Macro ディレイのタイプ ●
9.6 Delay Parameters ディレイの詳細設定
9.7 Name セットの名前 ●
9.8 Master Bar Recall マスター・バーの設定 ●
9.9 Icon 表示されるアイコン ●
セットの全般的な設定に関するパラメーターです(エフェク
ト、セットの名前、マスター・バーの機能など)。セットごと
に保存されます。
イージー
モード
イージー
モード
イージー
モード
イージー
モード
SYSTEM*(システムに関する設定、P.78)
10.
番号 メニュー名 概要
10.1 LCD Contrast 表示コントラスト ●
10.2 Parameter Access イージー/フル・モード ●
10.3 Bellows Curve 蛇腹の設定 ●
10.4 Pedal Controller フット・スイッチの設定 ●
10.5 Bass&Chord Mode ストラデラ・ベース配列 ●
10.6 Free Bass Mode フリー・ベース配列 ●
10.7 Stereo Width ステレオ設定 ●
10.8 Auto Power Off 自動電源オフ機能 ●
10.9 Startup 起動時の設定 ●
Startup Name 起動時の表示 ●
10.10
Orchestra Touch オーケストラ・パートの
10.11
キーボード感度
Orch. Bs&Ch Touch オーケストラ・ベース&
10.12
コードのボタン感度
Start / Stop MIDI TX MIDI 設定 ●
10.13
Treble Release T. トレブル・パート離鍵後
10.14
の減衰
Treble Mode トレブル・ボタン配列 ●
10.15
本機全体に適用されるパラメーターです。
11.
UTILITY(ユーティリティー設定、P.89)
番号 メニュー名 概要
11.1 Battery Status バッテリーの状態 ●
11.2 Copy ALL Effects エフェクト設定のコピー
11.3 Copy Reverb リバーブ設定のコピー
11.4 Copy Chorus コーラス設定のコピー
11.5 Copy Delay ディレイ設定のコピー
11.6 Copy SET セットのコピー ●
11.7 Bulk Dump ALL 全設定のバルク・ダンプ ●
11.8 Bulk Dump SET セットのバルク・ダンプ ●
11.9 Restore SET 初期セットの呼び出し ●
11.10
Treble Reg. On
トレブル・レジスタ設定 ●
Current Set
11.11
Bass Reg. On
ベース・レジスタ設定 ●
Current Set
Free Bass Reg. On
11.12
Current Set
フリー・ベース・レジス
タ設定
バッテリーのチェックや、設定のコピーなどのパラメーターで
す。また、工場出荷時のセットをロードすることもできます。
MIDI*(MIDI に関する設定、P.97)
12.
番号 メニュー名 概要
12.1 RealTime RX-TX 送受信する MIDI 設定 ●
12.2 Ext. Seq. Playback シーケンサーで演奏する ●
12.3
Bellows TX Resolution
蛇腹操作の MIDI 設定 ●
12.4 Bank forSend PC バンク・ナンバーの設定 ●
イージー
モード
●
●
●
イージー
モード
●
イージー
モード
本機には、メニューからパラメーターを選択しなくても設定を変更
することのできる機能がいくつかあります(P.38)。これらには、
保存を行わなくても、本機の電源を切るまではその設定のままで演
奏することができるという便利な点があります。保存を行う場合は
ライト機能(P.108)を使います。
43
Page 44

本機の設定をする
設定のしかた
設定は「設定できる項目について」(P.42)にある設定項目(パラ
メーター)を選択してから、設定を変更して行います。
イージー・モードとフル・モード
本機をイージー・モードでお使いのときには、選択することのでき
ないパラメーターがいくつかあります。それらのパラメーターを選
択する場合は、フル・モードに切り換える必要があります(P.25)。
パラメーターを選択する
パラメーターの番号を直接入力して選択する方法(ジャンプ機能)
と、メニュー画面から選択する方法があります。
ディスプレイに以下のように表示されるまで[EXIT /
3.
JUMP]ボタンを押し続けます。
各パートの設定を行う場合、パラメーターはオンになっているパー
ト(トレブル・セクションやベース・セクションで選択している音
色のパート)に関するパラメーターのみ選択することができます。
オフになっているパートのパラメーターを選択すると、そのパラ
メーターが変更不可であることを知らせる画面がディスプレイに表
示されます。この場合は、該当するパートをオンにするか、別のパ
ラメーターを選択してください。
このメッセージは、オーケストラ・パートがオフになっているため
に設定を変更することができないということを示しています。
ジャンプ機能を使ってパラメーターを選
択する
パラメーターの番号を入力してパラメーターを選択します。
本機の電源を入れます(P.19)。
1.
メイン画面が表示されます。
10 秒以内にトレブル・レジスター・スイッチを押さなかった場合
は、自動的にメイン画面に戻ります。
4.
[1]〜[12]のトレブル・レジスター・スイッチを使っ
てパラメーター・グループの番号を入力します。
例:「1.2 Transpose」を選択する場合、[1]のレジスター・
スイッチを押します。
トレブル・レジスター・スイッチ([1]〜[14]、
5.
[ORCHESTRA](15))を使って、選択したパラメー
ター・グループ内のパラメーター番号を入力します。
例:「1.2 Transpose」を選択する場合、[2]のレジスター・
スイッチを押します。
「パラメーターの設定を変更する」(P.45)へ進みます。
6.
[EXIT / JUMP]ボタンを数回押すとメイン画面に戻ります。
設定したいパラメーターとその番号を確認します。
2.
パラメーター番号については、「設定できる項目について」
(P.42)をご覧ください。
44
Page 45

本機の設定をする
「MENU(メニュー)」からパラメーター
を選択する
メニュー画面からパラメーターを選択します。
[MENU / WRITE]ボタンを押します。
1.
メニュー画面が表示されます。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
ボタンを押してパラメーター・グループを選択します。
[DATA / ENTER]つまみを押してパラメーター・グ
3.
ループを決定します。
パラメーターの設定を変更する
「パラメーターを選択する」(P.44)で選択したパラメーター設定を
変更します。
設定を変更するパラメーターを選択します。
1.
2.
[DATA / ENTER]つまみを押します。
画面右端のガイドが「EDIT」に変わり、パラメーターの設定値
が反転します。
ひとつの画面に複数のパラメーターがある場合は、[DATA /
ENTER]つまみを繰り返し押して変更するパラメーターを選
択します。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
3.
ボタンを押して設定値を変更します。
ディスプレイに以下のように表示されます(選択したパラメー
ター・グループによって異なります)。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
4.
ボタンを押して変更するパラメーターを選択します。
「パラメーターの設定を変更する」(P.45)へ進みます。
5.
[EXIT / JUMP]ボタンを 1 回押すとパラメーター・グループ
のトップ画面(例では「1 TUNING」)に戻り、もう一度押すと
メイン画面に戻ります。
設定を保存する場合
設定によって保存のしかたが違います。保存のしかたについては、
各設定をご覧ください。
設定を保存しない場合
[EXIT / JUMP]ボタンを 1 回押すとパラメーターの選択が解除さ
れ、もう一度押すとパラメーター・グループのトップ画面に戻りま
す。
45
Page 46

本機の設定をする
「1 TUNING」
チューニングの設定をする
本機のチューニングに関する設定をします。全体
のピッチを半音ずつ変えたり、アラビア音階など
のスケール設定にしたりなどの設定をすることが
できます。
ここでのパラメーターの設定は本機全体に適用されます。セットご
とで保存することはできません。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべて保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で電源を切ると、変更した
設定は失われます。ご注意ください。
以下の手順に従って、保存を行ってください。
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
1.
WRITE]ボタンを押し続けます。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
2.
ボタンを押して「Global」を選択します。
1.1 Master Tune(マスター・チューン)
本機の全体的なチューニングを変更しま
す。ピアノなどのアコースティック楽器と
一緒に演奏するときや、CD やカセット・
テープを伴奏としてお使いになるときなど
に便利です。ほとんどの電子楽器は初期設
定の「440.0Hz」を基準に設定されています。
415.3 〜 466.2Hz(初期設定:440.0Hz)
1.2 Transpose(トランスポーズ)
本機全体のキーを変更します。トランス
ポーズについての詳細は「Transpose(ト
ランスポーズ機能)」(P.38)をご覧くださ
い。
-6 / F# 〜 4 / E
「Transpose」の設定は保存されません。電源を切ると元に戻りま
す。
1.3 Scale(スケール)
本機で演奏する音階を選ぶことができます。
「TYPE」は音階を選択し、「KEY」は演奏す
るキーのルートを指定します。
音階についての詳細は「Scale(音階機能)」
(P.39)をご覧ください。
3.
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
グローバル画面には、グローバル・メモリーに保存されるすべての
パラメーターが表示されます。1 セットのみ保存できます。
4.
[MENU / WRITE]ボタンを押して設定を保存します。
ディスプレイに保存完了メッセージがしばらくの間表示
されます。
グローバル・セッティングを保存しない場合でも、電源を切った
り、設定を変更しなければ、その設定のまま使用することができま
す。
TYPE
(タイプ)
KEY
(キー)
Equal (Off)(イコール)
User 1(ユーザー 1)
User 2(ユーザー 2)
User 3(ユーザー 3)
Arabic 1(アラビック 1)
Arabic 2(アラビック 2)
Just Major(ジャスト・メジャー)
Just Minor(ジャスト・マイナー)
Pythagorean(ピタゴリアン)
Mean-Tone(ミーン・トーン)
Werckmeister(ヴェルクマイスター)
Kirnberger(キルンベルガー)
C〜B
46
Page 47

1.4 Scale Edit(スケール・エディット)
「1.3 Scale」の「TYPE」で選択すること
ができる「User 1」、「User 2」、「User 3」
には、新たに編集した音階を記憶させるこ
とができます。本機に用意されていない音
階をお使いになる場合(たとえばガムラン
音階で演奏するときなど)に便利です。
音階を編集する手順は、他のパラメーターの設定のしかたと異な
り、以下のように設定します。
「1.4 Scale Edit」を選択し、[DATA / ENTER]つまみを
1.
押すとディスプレイに以下のように表示されます。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
ボタンを押して、編集した音階を記憶させたい場所を選
択します。
TYPE
(タイプ)
[DATA / ENTER]つまみをもう一度押すとディスプレ
3.
イに以下のように表示されます。
User 1(ユーザー 1)
User 2(ユーザー 2)
User 3(ユーザー 3)
本機の設定をする
保存中(砂時計表示中)は絶対に電源を切らないでください。故障
の原因になります。
[EXIT / JUMP]ボタンを押すとひとつ前の設定画面に戻りま
す。この場合は保存されません。
1.5 Scale Assign(スケール・アサイン)
「1.3 Scale」で選択した音階をどのパート
に適用するかを指定します。各パートで
違った音階を選択することができます。
PART
(パート)
「ALL」を選ぶと全パートに適用されます。
トレブル・セクションとベース・セクションを一緒に演奏したとき
に音が濁って聞こえるときは、「ALL」に設定して演奏してみてく
ださい。
Treble(トレブル)
Orchestra(オーケストラ)
Treb&Orch(トレブル & オーケストラ)
Bass&Chord(ベース & コード)
ALL(オール)
[DATA / ENTER]つまみを押して音名(左側)か
4.
チューニング値(右側)を選択し、[DATA / ENTER]
つまみを回すか[UP]/[DOWN]ボタンを押して設
定を変更します。
TUNE
(チューン)
音名を選んでから、そのチューニング値を変更します。
(「C」のピッチを変更した場合、その設定値はすべての C
(C1、C2、C3 など)のピッチに適用されます。)
チューニング値を「50」(または「-50」)にすると、1 / 4 音
上げた(または下げた)ことになります。
5.
[MENU / WRITE]ボタンを押して編集した音階を保存
C〜B
-64 〜 63
します。
保存終了後に、ディスプレイに以下の保存完了メッセージ画面
がしばらくの間表示されます。
47
Page 48

本機の設定をする
「2 TREBLE EDIT」
トレブル・パートの音色の設定
をする
トレブル・パートの音色の設定をします。
リードのタイプや、音量、ミュゼット・
デチューンなどのリードの設定、蛇腹の
設定、エフェクトの設定など、トレブル・
パートの音色に関する設定をすることが
できます。
ここでの設定は、セットごとに保存されます。また、設定は現在選
択されているセットに対して行います。設定を変更する前に、
[SET ]または[SET ]ボタンを使って、あらかじめ設定し
たいセットを選択してください。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
3.
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
ター
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
4.
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きます。
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
Current または Current
+ SCom の場合
ALL の場合
→ 手順 7 へ
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
ここでの設定の変更は、現在選択しているトレブル・パートの音色
に適用されます。トレブル・パートにしてから、設定を変更したい
トレブル・レジスター・スイッチ([1]〜[14])を押して設定を
始めてください。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべて保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
•
以下の手順に従って、保存を行ってください。
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
1.
WRITE]ボタンを押し続けます。
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
保存するレジスターの名前をつけます。
5.
ディスプレイに表示されている名前を変更したい場合に
行ってください。
•
[UP]/[DOWN]ボタンまたは[DATA / ENTER]つまみを
押して、点滅しているカーソルを動かしながら、変更したい文
字に合わせます。
•
[DATA / ENTER]つまみを回して文字を選択します。
•
文字を消去してスペースを入れたい場合は、[UP]ボタンと
[DOWN]ボタンを同時に押します。
例:
「Celeste」の「s」の文字の上にカーソルを合わせ[UP]ボタ
ンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、「Cele ta」となりま
す。
•
スペースを挿入する場合は、スペースを挿入したい場所にカー
ソルを合わせ「UP」ボタンを押し続けます。このときスペー
スより後ろの文字は 1 文字ずつ右にずれます。
例:
「Celeste」の「s」の文字の上にカーソルを合わせ[UP]ボタ
ンを押し続けると、「Cele sta」となります。
文字数が既に 8 文字の場合、最後の 1 文字は消去されます。
たとえば、「Bandoneo」にスペースを挿入すると「Band
one」となります。
•
文字を消去しそれより後ろの文字を前につめる場合は、消した
い文字にカーソルを合わせて「DOWN」ボタンを押し続けま
す。
例:
「Celeste」の「s」の文字の上にカーソルを合わせ[DOWN]
ボタンを押し続けると、「Celete」となります。
48
Page 49

「MENU / WRITE」ボタンを押し、以下のようなページ
6.
に移動します。
Current が選ばれている場合
7.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありませ
ん。
8.
「Current」または「Current + Current SCow」の場合
は、[DATA / ENTER]つまみを押して「REGISTER」
を選択し、[DATA / ENTER]つまみを回して保存した
い番号を 1 〜 14 の範囲で選択します。
9.
「MENU / WRITE」ボタンを押して保存を実行します。
ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしばらくの間
表示されます。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
10.
本機の設定をする
2.1 Reed Type(リード・タイプ)
本機では、いくつかのリード(電子的にシ
ミュレートされた仮想リード)が用意され
ています。それぞれのリードのタイプを選
択することができます。
実際に鳴らすリードの設定に関しては、
「2.2 Register(レジスター)」(P.50)をご覧ください。
各リードに割り当てることのできるタイプはひとつだけです。
「FOOT」でリードを選択して、「TYPE」でリードのタイプを選択
します。
FOOT
(フィート)
TYPE
(タイプ)
ALL(オール)、16'、8'、8'-、8'+、4'、
5 1/3'、2 2/3'
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
OldItaly(オールド・イタリアン)
TexMex(テックス
Trikitixa(トリキティシャ)
・メックス
)
パラメーターの選択、設定方法については P.44 、P.45 をご覧くだ
さい。
「FOOT」で「ALL」を選択すると、すべてのリードに設定を適用し
ます。
「TYPE」の設定を変更するときに以下のような手順で行うと時間を
短縮できて便利です。たとえば、設定したすべてのリードの
「TYPE」が気に入らず、「16'」、「8'」、「4'」を「Bandoneon」に
設定し直したい、というような場合には、まず「FOOT」を
「ALL」に、「TYPE」を「Bandoneon」にします。次に、「2.2
Register(レジスター)」(P.50)の「STATUS」で必要のないリー
ドをオフにします。
「FOOT」を「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、「2.5
Valve Noise(バルブ・ノイズ)」(P.51)の設定は、自動的に選択
したリードのタイプに合った設定になります。異なるノイズのタイ
プを使う場合は後で設定を変更する必要があります。
49
Page 50

本機の設定をする
2.2 Register(レジスター)
どのリードの音を鳴らし、どのように鳴ら
すかを設定します。「2.1 Reed Type(リー
ド・タイプ)」(P.49)と組み合わせて使い
ます。
Bandoneon
Buga
Cajun
Mauge
Steierische
TexMex
<16'> <8'> <8'–> <8'+> <4'> <5-1/3'> <2-2/3'>
On Off Off
この例では、「16'」、「8'+」、「5 1/3'」のリードだけが使われていま
す。「8'+」はカソット機能がオンになっていて、他のリードよりも
少しソフトな音になります。カソット機能は、チャンバー(ソル
ディナ)機能(P.28)と似ていますが、指定したピッチのリードだ
けをソフトな音にします。
「FOOT」でリードを選択して、「STATUS」で鳴らしかたを選択し
ます。
FOOT
(フィート)
STATUS
(ステイタ
ス)
On-
Cassotto
16'、8'、8'-、8'+、4'、5 1/3'、2 2/3'
Off(オフ)
On(オン)
On-Cassotto(オンーカソット機能オン)
Off On Off
Triktxa
2.3 Reed Volume(リード・ボリューム)
各リードの音量を調節します。「2.2
Register(レジスター)」(P.50)でオンに
したリードの音量バランスを調節すること
ができます。
「FOOT」で音量設定したいリードを選んで
から、「LEVEL」で音量を調節します。
FOOT
(フィート)
LEVEL
(レベル)
「ALL」を選択した場合は、16'、8'、8'-、8'+、4'、5 1/3'、2 2/3'
すべての音量を同時に調節できます。
「Std」を基準に音量を調節します。
最も重要なリードを決めてその音量を「Std」に設定し、その他の
補助的なリードの音量を必要に応じて調節するとよいでしょう。
トレブル・セクションの全体的な音量を調節するには
[BALANCE]つまみを使います(P.27)。
ALL、16'、8'、8'-、8'+、4'、5 1/3'、
2 2/3'
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
2.4 Treble Octave
(トレブル・オクターブ)
選択した音色を 1 オクターブ上げたり下げ
たりすることができます。「-1」にすると 1
オクターブ低く、「1」にすると高くなりま
す。
VALUE
(バリュー)
-1〜0〜1
(初期設定:0)
「On-Cassotto」を選択すると、カソット機能オンで鳴らすことが
できます。
50
Page 51

本機の設定をする
2.5 Valve Noise(バルブ・ノイズ)
バルブのノイズ音の設定をします。
「NOISE EDIT (Valve, Button)(ノイズ・
エディット機能)」(P.40)では、バルブや
ボタンのノイズの音量しか調節できません
でしたが、ここではノイズのタイプまで指
定することができます。
「TYPE」でノイズのタイプを選択し、「LEVEL」でノイズの音量を
調節します。
TYPE
(タイプ)
LEVEL
(レベル)
「LEVEL」で「Off」を選択するとノイズ音はオフになります。
各音色で選択できる「TYPE」はひとつです(リードごとに設定は
できません)。
「2.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.49)の「FOOT」を
「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、バルブ・ノイズの設
定は、自動的に選択したリードのタイプに合った設定になります。
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
OldItaly(オールド・イタリアン)
TexMex(テックス
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
・メックス
)
TYPE
(タイプ)
「Off」を選択すると、ミュゼット・デチューン機能がオフになりま
す。
Off(オフ)
Dry(ドライ)
Classic(クラシック)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
AmericanL(アメリカン L)
AmericanH(アメリカン H)
NorthEur(ノース・ヨーロッパ)
GermanL(ジャーマン L)
D-FolkL(ジャーマン・フォーク L)
ItalianL(イタリアン L)
GermanH(ジャーマン H)
Alpine(アルペン)
ItalianH(イタリアン H)
D-FolkH(ジャーマン・フォーク H)
French(フレンチ)
Scottish(スコティッシュ)
2.7 Bellows Detune
(ベローズ・デチューン)
蛇腹をより速く開閉したときに、トレブ
ル・リードのピッチがどれくらい強く変わ
るかをシミュレートします。これによって
本機はよりリアルな音色を作り出すことが
できます。
TYPE
(タイプ)
「Standard」で効果が弱いと感じたら「High」に、強すぎると感じ
たら「Low」にしてみてください。この効果が必要ないときは
「Off」に設定します。リードのタイプ(P.49)によって、効果が変
わります。
Off(オフ)
Low(ロー)
Standard(スタンダード)
High(ハイ)
(初期設定:Standard)
「2.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.49)の「TYPE」で選択し
たものと同じタイプのノイズを使うとよりリアルになります。
2.6 Musette Detune
(ミュゼット・デチューン)
音程がわずかに違う 8' リードのタイプを選
択します。詳しくは「Musette Detune
(ミュゼット・デチューン機能)」(P.38)
をご覧ください。
2.8 Reverb Send(リバーブ・センド)
2.9 Chorus Send(コーラス・センド)
2.10 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
他のパートでも同様のパラメーターがあり、それぞれで設定する
•
ことができます。
各エフェクトはそれぞれ設定を変更することができます。「エ
•
フェクトの設定をする」(P.72)の各設定をご覧ください。
0〜127
51
Page 52

本機の設定をする
2.11 Aftertouch Pitch
(アフタータッチ・ピッチ)
アフタータッチ操作をしたときのピッチの
変わり具合を設定します。
アフタータッチは、マスター・バーを使用
します。マスター.バーを押す強さによっ
てピッチを一時的に変えることができま
す。
•
現在選択しているトレブル・パートの音色にベース・パートまた
はオーケストラ・ベース・パートの音色をリンクさせない場合
は、「No Link」を選択してください。
•
ベース・リンクの設定をしてもベース・リンク機能がオンになら
ない場合は、[ORCHESTRA]レジスター・スイッチを押しなが
ら[9]トレブル・レジスター・スイッチを押すと、ベース・リ
ンク機能がオンになります。
MODE
(モード)
「1/4 Down」または「1/2 Down」を選択すると、1 / 4 音または
半音ベンド・ダウン(一時的にピッチを下げる)することができま
す。「1/4 Up」または「1/2 Up」を選択すると、1 / 4 音または半
音ベンド・アップ(一時的にピッチを上げる)することができま
す。「Off」を選択すると、アフタータッチは機能しません。
アフタータッチ効果は同時に鳴っているすべての音に適応されま
す。
外部 MIDI 機器を接続した場合、アフタータッチ情報を送信します。
Off(オフ)
1/4 Down(1 / 4 ダウン)
1/2 Down(1 / 2 ダウン)
1/4 Up(1 / 4 アップ)
1/2 Up(1 / 2 アップ)
(初期設定:Off)
2.12 Bass Link(ベース・リンク)
トレブル・レジスター・スイッチを押した
ときに、自動的に任意のベース・パート/
オーケストラ・ベース・パートの音色を選
ぶことができます(ベース・リンク機能)。
トレブル/ベースのレジスター・スイッチ
を別々に押さなくても、ひとつのトレブル・レジスター・スイッチ
を押すだけでベース・セクションの音色を選択することができま
す。
「BASS」でベース・パート、「ORC.BASS」でオーケストラ・ベー
ス・パートの音色を選びます。
ベース・リンクを設定するとメイン画面に以下のように表示されま
す。
リンクを設定するだけではストラデラ・ベース・モード/フリー・
ベース・モード/オーケストラ・コード・パートまたはオーケスト
ラ・ベース・パート/オーケストラ・フリー・ベース・パートの音
色は変わりません。リンクを有効にするには、ベース・リンク機能
をオンにした別のトレブル・パートの音色を選択する必要がありま
す。
本機の電源を入れるたときに、ベース・リンク機能が自動的にオン
になるように設定することもできます(P.82)。
BASS
(ベース)
ORC.BASS
(オーケスト
ラ・ベース)
「BASS」で「Free 1」〜「Free 7」を選択した場合は、ベース・
•
リンク機能をオンにした音色が登録されているトレブル・レジス
ター・スイッチを押すと、自動的にフリー・ベース・モードにな
ります(「BASS」に「Bass 1」〜「Bass 7」を選択した場合は
ストラデラ・ベース・モードになります)。
「ORC.BASS」で「No Link」以外を選択した場合、ベース・リン
•
ク機能をオンにした音色が登録されているトレブル・レジス
ター・スイッチを押すと、ベース・セクションは自動的にオーケ
ストラ・ベース・パートがオンになります
No Link(ノー・リンク)、
Bass 1 〜 Bass 7、Free 1 〜 Free 7
No Link(ノー・リンク)、Acoustic、
Bowed、Fingered、Fretless、Picked、
Tuba、Tuba Mix
52
Page 53

本機の設定をする
2.13 Orchestra Link
(オーケストラ・リンク)
トレブル・レジスター・スイッチを押した
ときに、自動的にオーケストラ・パートの
音色と、オーケストラ・モード(P.32)を
選ぶことができます(オーケストラ・リン
ク機能)。
「REGISTER」でオーケストラ・パートの音色を選んで、「MODE」
でオーケストラ・モードを選びます。
REGISTER
(レジス
ター)
MODE
(モード)
•
現在選択しているトレブル・パートの音色にオーケストラ・パー
トの音色をリンクさせない場合は、「REGISTER」で「No Link」
を選択してください。
•
「MODE」を「----」にすると、オーケストラ・モードは、現在選
択されているものになります。つまり、あるオーケストラ・パー
トの音色でロー・モードが選択されている場合は、オーケスト
ラ・リンク機能でオーケストラ・パートを選ぶと、オーケスト
ラ・モードは自動的にロー・モードになります。
オーケストラ・リンクの設定をしてもオーケストラ・リンク機能
がオンにならない場合は、[ORCHESTRA]レジスター・スイッ
チを押しながら[10]トレブル・レジスター・スイッチを押す
と、オーケストラ・リンク機能がオンになります。
No Link(ノー・リンク)、1A Trombone、
1B Trumpet、2A TenorSax、2B AltoSax、
3A Clarinet、3B Oboe、4A Harmonica、
4B MuteHarm、5A Violin、5B Pizzicato、
6A Flute、6B PanFlute、7A HighLand、
7B Zampogna、8A PercOrgan、8B
JazzOrgan、9A RotOrgan、9B TremOgr、
10 ScatVoice、11 Mandolin、
12 AcGuitar、13 AcPiano
----、Solo、Solo M、Dual、Dual M、
High、High M、Low、Low M
※ M が付いたモードを選択した場合は、
オーケストラ・パートがオフの状態でレ
ジスターが切り替わります。
オーケストラ・リンクを設定するとメイン画面に以下のように表示
されます。
リンクを設定するだけではオーケストラ・パートの音色は変わりま
せん。リンクを有効にするには、オーケストラ・リンク機能をオン
にした別のトレブル・パートの音色を選択する必要があります。
本機の電源を入れたときに、オーケストラ・リンク機能が自動的に
オンになるように設定することもできます(P.82)。
2.14 Orchestra Chord Link
(オーケストラ・コード・リンク)
トレブル・レジスター・スイッチを押した
ときに、任意のオーケストラ・コードまた
はオーケストラ・フリー・ベースの音色を
選ぶことができます。トレブル/ベースの
レジスター・スイッチを別々に押さなくて
も、ひとつのトレブル・レジスター・スイッチを押すだけでオーケ
ストラ・コード/オーケストラ・フリー・ベースの音色を選択する
ことができます。オーケストラ・コード・セクションとオーケスト
ラ・フリー・ベース・セクションはどちらかひとつだけを選ぶこと
ができます。フリー・ベース・モードのときコード・ボタンはあり
ません。
CHORDFREEBS
(コード−フ
リーベース)
No Link(ノー・リンク)、
CHD-Trombone(コード‐トロンボーン)、
CHD-TenorSax(コード‐テナーサックス)、
CHD-Clarinet(コード‐クラリネット)、
CHD-TremOrg(コード‐トレモロオルガ
ン)、CHD-Voice(コード‐ボイス)、
CHD-AcGuitar(コード‐アコースティック
ギター)、CHD-AcPiano(コード‐アコース
ティックピアノ)、FBS-Trombone(フリー
ベース‐トロンボーン)、FBS-Clarinet(フ
リーベース‐クラリネット)、
FBS-Oboe(フリーベース‐オーボエ)、
FBS-Flute(フリーベース‐フルート)、
FBS-PercOrgan(フリーベース‐パーカッ
ションオルガン)、FBS-AcGuitar(フリー
ベース‐アコースティックギター)、FBSAcPiano(フリーベース‐アコースティック
ピアノ)
53
Page 54

本機の設定をする
CHORD-FREEBS(コード−フリーベース)は、「2.12 ベース・リ
ンク」の設定によって異なります。
「2.12 ベース・
リンク」設定
No Link
(ノー・リンク)
Bass 1 〜 7
(ベース 1 〜 7)
Free 1 〜 7
(フリー 1 〜 7)
「ベース」と「フリー・ベース」はモードが異なります。フリー・
ベース・モードは、すべてのベース・ボタンでベース・アコーディ
オンを演奏します。「CHD」オプションは選べません。
同様に、ベース・モードで、「2.12 ベース・リンク」でベースに
[Bass 1]〜[Bass 7]のいずれかが選択されている場合、オーケ
ストラ・フリー・ベース音色は選べません。
「2.14 オーケストラ・コード・リンク」で
可能な設定
No Link(ノー・リンク)、
CHD-Trombone
(コード‐トロンボーン)、
CHD-TenorSax
(コード‐テナーサックス)、
CHD-Clarinet(コード‐クラリネット)、
CHD-TremOrg
(コード‐トレモロオルガン)、
CHD-Voice(コード‐ボイス)、
CHD-AcGuitar
(コード‐アコースティックギター)、
CHD-AcPiano
(コード‐アコースティックピアノ)、
FBS-Trombone
(フリーベース‐トロンボーン)、
FBS-Clarinet
(フリーベース‐クラリネット)、
FBS-Oboe(フリーベース‐オーボエ)、
FBS-Flute(フリーベース‐フルート)、
FBS-PercOrgan(フリーベース‐パー
カッションオルガン)、
FBS-AcGuitar(フリーベース‐アコース
ティックギター)、
FBS-AcPiano(フリーベース‐アコース
ティックピアノ)
No Link(ノー・リンク)、
CHD-Trombone
(コード‐トロンボーン)、
CHD-TenorSax
(コード‐テナーサックス)、
CHD-Clarinet(コード‐クラリネット)、
CHD-TremOrg
(コード‐トレモロオルガン)、
CHD-Voice(コード‐ボイス)、CHDAcGuitar
(コード‐アコースティックギター)、
CHD-AcPiano
(コード‐アコースティックピアノ)
No Link(ノー・リンク)、
FBS-Trombone
(フリーベース‐トロンボーン)、
FBS-Clarinet(フリーベース‐クラリ
ネット)、
FBS-Oboe(フリーベース‐オーボエ)、
FBS-Flute(フリーベース‐フルート)、
FBS-PercOrgan(フリーベース‐パー
カッションオルガン)、
FBS-AcGuitar(フリーベース‐アコース
ティックギター)、
FBS-AcPiano(フリーベース‐アコース
ティックピアノ)
「2.12 ベース・リンク」の設定によって「2.14 オーケストラ・コー
ド・リンク」の設定を変更することが可能かどうかが決まります。
たとえば、「2.12 ベース・リンク」で「No Link」のときに「2.14
オーケストラ・コード・リンク」で「FBS-Flute」を設定した後、
「2.12 ベース・リンク」で「Bass 6」に変更しようとした場合、
「FBS-Flute」はベース・モードでフリー・ベース・オーケストラ音
色のため設定できません。「FBS-Flute」の設定は無効となります。
この場合「2.14 オーケストラ・コード・リンク」の設定は「No
Link」に変更されます。
したがって、ベース・モードにする必要がある場合は、初めに
「2.12 ベース・リンク」で「Bass」を選択してから「2.14 オーケ
ストラ・コード・リンク」を設定してください。
「2.12 ベース・リンク」で「ORC.BASS」を設定した場合は、
「2.14 オーケストラ・コード・リンク」の設定には影響しません。
オーケストラ・コード・リンクの設定をしてもオーケストラ・コー
ド・リンク機能がオンにならない場合は、[ORCHESTRA]レジス
ター・スイッチを押しながら[9]トレブル・レジスター・スイッ
チを押すと、オーケストラ・コード・リンク機能がオンになりま
す。
リンクを設定するだけではオーケストラ・コード音色/オーケスト
ラ・フリー・ベース音色は変わりません。リンクを有効にするため
には、ベース・リンク機能をオンにした別のトレブル・パートの音
色を選択する必要があります。
オーケストラ・コード・リンク機能とオーケストラ・フリー・ベー
ス・リンク機能のオン/オフは、ベース・リンクの手順に従って切
り替える必要があります。オーケストラ・コード・セクションと
オーケストラ・フリー・ベース・セクションのための独立した切り
替えの機能はありません。
ベース・リンク機能を抜けるためには、この手順を繰り返します。
または、他のトレブル・レジスター・スイッチに「CANCEL」をア
サインし、そのスイッチを押してください。
54
Page 55

本機の設定をする
2.15 Treble MIDI TX(トレブル MIDI TX)
現在選択しているトレブル・パートの音色
の MIDI に関するパラメーターです。詳し
くは「各パートで送信する MIDI の設定を
する」(P.102)をご覧ください。これらの
設定はセットごとに保存され、そのセット
に含まれる音色ごとに異なる MIDI の設定を使うことができます。
「3 BASS EDIT」
ベース・パート(ストラデラ・
ベース・モード)の音色の設定
をする
ベース・パートでストラデラ・ベース・モードを
選んでいるときの音色の設定をします。
リードのタイプや、音量などのリードの設定、蛇
腹の設定、エフェクトの設定など、ベース・パー
ト(ストラデラ・ベース・モード)の音色に関する設定をすること
ができます。
ここでの設定は、セットごとに保存されます。また、設定は現在選
択されているセットに対して行います。設定を変更する前に、
[SET ]または[SET ]ボタンを使って、あらかじめ設定し
たいセットを選択してください。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
ここでの設定の変更は、現在選択しているベース・パート(ストラ
デラ・ベース・モード)の音色に適用されます。設定を変更したい
ベース・レジスター・スイッチ([1]〜[7])を押して設定を始
めてください。
ストラデラ・ベース・モードでは、ベースとコードのボタンの配列
方法を変更することができます。ボタン配列の選択方法については
「10.5 Bass&Chord Mode (ベース & コード・モード)」(P.81)を
ご覧ください。この設定は本機全体に適用されます(セットごとに
保存することはできません)。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべて保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
•
以下の手順に従って、保存を行ってください。
1.
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
55
Page 56

本機の設定をする
Current または Current
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
2.
ボタンを押して「Bass」を選びます。
3.
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
4.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
ター
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きるので、最も確実です。
[DATA / ENTER]つまみを回して保存したい番号を 1
〜 7 の範囲で選択します。
[MANU / WRITE]ボタンを押して変更した内容を保存
10.
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
.
11.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
5.
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
+ SCom の場合
6.
保存するレジスターの名前をつけます。
ALL の場合
→手順 8 へ
詳細は P.48 をご覧ください。名前の変更は現在ディス
プレイに表示されている名前を変更したい時のみ必要で
す。
7.
「MENU / WRITE」ボタンを押し、以下のようなページ
に移動します。
Current または Current +SCom の場合
8.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありませ
ん。
9.
「Current」または「Current+SCom」の場合は、[DATA
/ ENTER]つまみを押して「REGISTER」を選択し、
56
Page 57

本機の設定をする
3.1 Reed Type(リード・タイプ)
本機では、いくつかのリード(電子的にシ
ミュレートされた仮想リード)が用意され
ていますが、それぞれのリードに対して、
リードのタイプを選択することができま
す。
実際に鳴らすリードの設定に関しては、「3.2 Register(レジス
ター)」(P.57)をご覧ください。
各リードに割り当てることのできるタイプはひとつだけです。
「FOOT」でリードを選択して、「TYPE」でリードのタイプを選択
します。
FOOT
(フィート)
TYPE
(タイプ)
ALL(オール)、16'、8'、8'-4'、4'、2'
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
3.2 Register(レジスター)
どのリードの音を鳴らし、どのように鳴ら
すかを設定します。「3.1 Reed Type(リー
ド・タイプ)」(P.57)と組み合わせて使い
ます。
「FOOT」でリードを選択して、
「STATUS」でどのように鳴らすかを選択します。
FOOT
(フィート)
STATUS
(ステイタ
ス)
「Bass」を選ぶとベース・ボタン、「Chord 」を選ぶとコード・ボタ
ン、「Bass&Chord」を選ぶとベース・ボタンとコード・ボタンの
両方で鳴らすことができます。
各ステイタスで設定できるリード
ステイタス 16'、 8' 8'-4' 4' 2'
Off ○ ○ ○ ○ ○
Bass ○ ○ × × ×
Chord × × ○ ○ ○
Bass&Chord × × ○ ○ ○
「8'-4'」、「4'」、「2'」のリードは、まとめて「Chord」か
「Bass&Chord」を選択します。それぞれのリードでどちらかを選
択することはできません。たとえば、「4'」に「Bass&Chord」を
選択し、「2'」に「Chord」を選択することはできません。この場
合、「4'」は自動的に「Chord」が選択されます。だたし、「Off」は
個別に選択することができます。
16'、8'、8'-4'、4'、2'
Off(オフ)
Bass(ベース)
Chord(コード)
Bass&Chord(ベース & コード)
「TYPE」の設定を変更するときに以下のような手順で行うと時間を
短縮できて便利です。たとえば、設定したすべてのリードの
「TYPE」が気に入らず、「16'」、「8'」、「4'」を「Bandoneon」に
設定し直したい、というような場合には、まず「FOOT」を
「ALL」に、「TYPE」を「Bandoneon」にします。次に、「3.2
Register(レジスター)」(P.57)の「STATUS」で必要のないリー
ドをオフにします。
「FOOT」を「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、「3.4
Button Noise(ボタン・ノイズ)」(P.58)と「3.5 Reed Growl
(リード・グロール)」(P.58)の設定は、自動的に選択したリード
のタイプに合った設定になります。異なるノイズのタイプを使う場
合は後で設定を変更する必要があります。
3.3 Reed Volume(リード・ボリューム)
各リードの音量を調節します。「3.2
Register(レジスター)」(P.57)でオンに
したリードの音量バランスを調節すること
ができます。
「FOOT」で音量設定したいリードを選んで
から、「LEVEL」で音量を調節します。
FOOT
(フィート)
LEVEL
(レベル)
「ALL」を選択した場合は、16'、8'、8'-4'、4'、2 すべての音量を
同時に調節することができます。
「Std」を基準に音量を調節します。
最も重要なリードを決めてその音量を「Std」に設定し、その他の
補助的なリードの音量を必要に応じて調節するとよいでしょう。
ベース・セクションの全体的な音量を調節するには[BALANCE]
つまみを使います(P.29)。
AlLL、16'、8'、8'-4'、4'、2'
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
57
Page 58

本機の設定をする
3.4 Button Noise(ボタン・ノイズ)
ボタンのノイズ音を設定します。「NOISE
EDIT (Valve, Button)(ノイズ・エディッ
ト機能)」(P.40)ではバルブやボタンのノ
イズの音量しか調節できませんでしたが、
ここではノイズのタイプまで指定すること
ができます。
「TYPE」でノイズのタイプを選択し、「LEVEL」でノイズの音量を
調節します。
TYPE
(タイプ)
LEVEL
(レベル)
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
3.5 Reed Growl(リード・グロール)
ベース・リードが一斉に振動を止めるとき
に出るノイズ(リード・グロール)のタイ
プを設定します。
「TYPE」でリード・グロールのタイプを選
択し、「LEVEL」でリード・グロールの音
量を調節します。
TYPE
(タイプ)
LEVEL
(レベル)
「Off」を選択するとノイズ音はオフになります。
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
「LEVEL」で「Off」を選択するとノイズ音はオフになります。
各音色で選択できる「TYPE」はひとつです(リードごとに設定は
できません)。
「3.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.57)の「FOOT」を
「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、ボタン・ノイズの設
定は自動的に選択したリードのタイプに合った設定になります。
「3.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.57)の「TYPE」で選択し
たものと同じタイプのノイズを使うとよりリアルになります。
「3.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.57)の「FOOT」を
「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、リード・グロールの
設定は自動的に選択したリードのタイプに合った設定になります。
「3.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.57)の「TYPE」で選択し
たものと同じタイプのノイズを使うとよりリアルになります。
3.6 Bellows Detune
(ベローズ・デチューン)
蛇腹をより速く開閉したときに、ベースと
コードのリードのピッチがどれくらい強く
変わるかをシミュレートします。これに
よって本機はよりリアルな音色を作り出す
ことができます。
TYPE
(タイプ)
「Standard」で効果が弱いと感じたら「High」に、強すぎると感じ
たら「Low」にしてみてください。この効果が必要ないときは
「Off」に設定します。リードのタイプ(P.57)によって、効果が変
わります。
Off(オフ)
Low(ロー)
Standard(スタンダード)
High(ハイ)
(初期設定:Standard)
58
Page 59

本機の設定をする
3.7 Reverb Send(リバーブ・センド)
3.8 Chorus Send(コーラス・センド)
3.9 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
他のパートでも同様のパラメーターがあり、それぞれで設定する
•
ことができます。
各エフェクトはそれぞれ設定を変更することができます。「エ
•
フェクトの設定をする」(P.72)の各設定をご覧ください。
0〜127
3.10 Bass MIDI TX(ベース MIDI TX)
3.11 Chord MIDI TX(コード MIDI TX)
現在選択しているストラデラ・ベース・
モードの音色の MIDI に関するパラメー
ターです。ベース(蛇腹側の 2 列ないし 3
列のボタン)とコード(その他のボタン)
の MIDI 情報をそれぞれ設定します。詳し
くは「各パートで送信する MIDI の設定を
する」(P.102)をご覧ください。これらの
設定はセットごとに保存され、そのセット
に含まれる音色ごとに異なる MIDI の設定
を使うことができます。
「4 FREE BS EDIT」
ベース・パート(フリー・ベー
ス・モード)の音色の設定をす
る
ベース・パートでフリー・ベース・モードを選ん
でいるときの音色の設定をします。
リードのタイプや、音量などのリードの設定、蛇
腹の設定、エフェクトの設定など、ベース・パー
ト(フリー・ベース・モード)の音色に関する設定をすることがで
きます。
ここでの設定は、セットごとに保存されます。また、設定は現在選
択されているセットに対して行います。設定を変更する前に、
[SET / ]ボタンを使って、あらかじめ設定したいセットを
選択してください。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
ここでの設定の変更は、現在選択しているベース・パート(フ
リー・ベース・モード)の音色に適用されます。設定を変更したい
ベース・レジスター・スイッチ([1]〜[7])を押して設定を始
めてください。
フリー・ベース・モードでは、ボタンの配列方法を変更することが
できます。ボタン配列の選択方法については「10.6 Free Bass
Mode (フリー・ベース・モード)」(P.81)をご覧ください。この
設定は本機全体に適用されます(セットごとに保存することはでき
ません)。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべてライト機能で保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
•
以下の手順に従って、保存を行ってください。
1.
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
59
Page 60

本機の設定をする
Current または Current
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
2.
で「Free Bass」を選択します。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
3.
4.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
ター
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
5.
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きるので、最も確実です。
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
+ Scom の場合 ALL の場合
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
10.
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
11.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
パラメーターの選択、設定方法については P.44、P.45 をご覧くだ
さい。
4.1 Reed Type(リード・タイプ)
本機では、いくつかのリード(電子的にシ
ミュレートされた仮想リード)が用意され
ていますが、それぞれのリードに対して、
リードのタイプを選択することができま
す。
実際に鳴らすリードの設定に関しては、「4.2 Register(レジス
ター)」(P.61)をご覧ください。
各リードに割り当てることのできるタイプはひとつだけです。
フリー・ベース・モードではコードは演奏できないため、ストラデ
ラ・ベース・モードの場合より選択できるリードは少なくなりま
す。
「FOOT」でリードを選択して、「TYPE」でリードのタイプを選択
します。
6.
保存するレジスターの名前をつけます。
詳細は P.48 をご覧ください。名前の変更は現在ディス
プレイに表示されている名前を変更したいときのみ必要
です。
「MENU / WRITE」ボタンを押し、以下のようなページ
7.
に移動します。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
8.
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありません。
「Current」または「Current+SCom」の場合は[DATA
9.
/ ENTER]つまみを押して「REGISTER」を選択し、
[DATA / ENTER]つまみを回して保存したい番号を 1
〜 7 の範囲で選択します。
→手順 8 へ
Current または Current+ SCom の場合
FOOT
(フィート)
TYPE
(タイプ)
「ALL」を選択すると、すべてのリードに設定を適用します。
「FOOT」を「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、「4.4
Button Noise(ボタン・ノイズ)」(P.61)と「4.5 Reed Growl
(リード・グロール)」(P.62)の設定は、自動的に選択したリード
のタイプに合った設定になります。異なるノイズのタイプを使う場
合は後で設定を変更する必要があります。
ALL(オール)、16'、8'
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
60
Page 61

本機の設定をする
4.2 Register(レジスター)
どのリードの音を鳴らし、どのように鳴ら
すかを設定します。「4.1 Reed Type(リー
ド・タイプ)」(P.60)と組み合わせて使い
ます。
「FOOT」でリードを選択して、
「STATUS」でどのように鳴らすかを選択します。
FOOT
(フィート)
STATUS
(ステイタ
ス)
「Off」ではオフ、「Low」ではロー側のボタンでオン、「High」ではハイ
側のボタンでオン、「Whole」では全体のボタンでオンになります。
16'、8'
Off(オフ)
Low(ロー)
High(ハイ)
Whole(ホール)
4.3 Reed Volume(リード・ボリューム)
各リードの音量を調節します。「4.2
Register(レジスター)」(P.61)でオンに
したリードの音量バランスを調節すること
ができます。
「FOOT」で音量設定したいリードを選んで
から、「LEVEL」で音量を調節します。
FOOT
(フィート)
LEVEL
(レベル)
ALL、16'、8'
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
4.4 Button Noise(ボタン・ノイズ)
ボタンのノイズ音を設定します。「NOISE
EDIT (Valve, Button)(ノイズ・エディッ
ト機能)」(P.40)ではバルブやボタンのノ
イズの音量しか調節できませんでしたが、
ここではノイズのタイプまで指定すること
ができます。
「TYPE」でノイズのタイプを選択し、「LEVEL」でノイズの音量を
調節します。
TYPE
(タイプ)
LEVEL
(レベル)
「LEVEL」で「Off」を選択するとノイズ音はオフになります。
各音色で選択できる「TYPE」はひとつです(リードごとに設定は
できません)。
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
「ALL」を選択した場合は、
できます。
最も重要なリードを決めてその音量を「Std」に設定し、その他の
補助的なリードの音量を必要に応じて調節するとよいでしょう。
ベース・セクションの全体的な音量を調節するには[BALANCE]
つまみを使います(P.29)。
16' と 8'の音量を同時に調整することが
「4.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.60)の「FOOT」を
「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、ボタン・ノイズの設
定は自動的に選択したリードのタイプに合った設定になります。
「4.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.60)の「TYPE」で選択し
たものと同じタイプのノイズを使うとよりリアルになります。
61
Page 62

本機の設定をする
4.5 Reed Growl(リード・グロール)
ベース・リードが一斉に振動を止めるとき
に出るノイズ(リード・グロール)のタイ
プを設定します。
「TYPE」でリード・グロールのタイプを選
択し、「LEVEL」でリード・グロールの音
量を調節します。
TYPE
(タイプ)
LEVEL
(レベル)
「Off」を選択するとノイズ音はオフになります。
「4.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.60)の「FOOT」を
「ALL」にしてリードのタイプを選択すると、リード・グロールの
設定は自動的に選択したリードのタイプに合った設定になります。
「4.1 Reed Type(リード・タイプ)」(P.60)の「TYPE」で選択し
たものと同じタイプのノイズを使うとよりリアルになります。
Bandoneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
4.7 Reverb Send(リバーブ・センド)
4.8 Chorus Send(コーラス・センド)
4.9 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
他のパートでも同様のパラメーターがあり、それぞれで設定する
•
ことができます。
各エフェクトはそれぞれ設定を変更することができます。「エ
•
フェクトの設定をする」(P.72)の各設定をご覧ください。
0〜127
4.10 Free Bass MIDI TX
(フリー・ベース MIDI TX)
現在選択しているフリー・ベース・モード
の音色の MIDI に関するパラメーターです。
詳しくは「各パートで送信する MIDI の設
定をする」(P.102)をご覧ください。これ
らの設定はセットごとに保存され、その
セットに含まれる音色ごとに異なる MIDI の設定を使うことができ
ます。
4.6 Bellows Detune
(ベローズ・デチューン)
蛇腹をより速く開閉したときに、ベースの
リードのピッチがどれくらい強く変わるか
をシミュレートします。これによって、本
機はよりリアルな音色を作り出すことがで
きます。
TYPE
(タイプ)
「Standard」で効果が弱いと感じたら「High」に、強すぎると感じ
たら「Low」にしてみてください。この効果が必要ないときは
「Off」に設定します。リードのタイプ(P.60)によって、効果が変
わります。
Off(オフ)
Low(ロー)
Standard(スタンダード)
High(ハイ)
(初期設定:Standard)
62
Page 63

「5 ORC.BASS EDIT」
Current または Current
+ Scom の場合
ALL の場合
違うレジスターを選択したり、
名前を変更することはできませ
ん。
オーケストラ・ベース・パート
の音色の設定をする
オーケストラ・ベース・パートの音色の設定をし
ます。
最低音の設定、音の減衰や、音量などの設定、エ
フェクトの設定など、オーケストラ・ベース・
パートの音色の関する設定をすることができます。
ここでの設定は、セットごとに保存されます。また、設定は現在選
択されているセットに対して行います。設定を変更する前に、
[SET / ]ボタンを使って、あらかじめ設定したいセットを
選択してください。
本機の設定をする
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
3.
4.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
ター
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きるので、最も確実です。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
ここでの設定の変更は、現在選択しているオーケストラ・ベース・
パートの音色に適用されます。設定を変更したいベース・レジス
ター・スイッチ([1]〜[7])を押して設定を始めてください。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべてライト機能で保存することができます。設定
を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更した
設定は失われます。ご注意ください。
•
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
以下の手順に従って、保存を行ってください。
1.
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
5.
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
6.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありませ
ん。
7.
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
2.
ボタンを押して「Orch. Bass」を選びます。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
8.
パラメーターの選択、設定方法については P.44、P.45 をご覧くだ
さい。
63
Page 64

本機の設定をする
5.1 Lowest Note(ローエスト・ノート)
オーケストラ・ベース・パートの音色で演
奏するときの最も低い音を設定します。
オーケストラ・ベース・パートの音色は
PCM 音源から作り出されており、ほぼ無
限にピッチを下げることができますが、あ
まり自然な音とは言えません。ここではその音色で使う最も低い
ピッチを設定します。ベース・ボタンで設定より低い音を弾くと、
その音は 1 オクターブ上になります。
たとえば以下のようになります。
ベース・ボタンでこのように弾いたとき・・・
・・・と選択すると・・・
・・・1 オクターブ上がります
このようにオーケストラ・ベース・パートの音色のオクターブが変
わると、演奏する曲によっては初期設定(E 28)のままだと都合が
悪い場合があるかもしれません(特にウォーキング・ベースを弾く
ときなど)。この場合は、「NOTE」の設定(最低音の設定)をお好
みに変更してください。
NOTE
(ノート)
Lowest Note= E (28)
E 28、F 29、F# 30、G 31、Ab 32、
A 33、Bb 34、B 35、C 36
(初期設定:E 28)
5.2 Orc.Bass Release T.
(オーケストラ・ベース・リリース・タイム)
ベース・ボタンから指を離して音が止まる
までの時間を調節します。ベース・ボタン
から指を離したときに自然な音の減衰を得
られるように調節します。
5.4 Reverb Send(リバーブ・センド)
5.5 Chorus Send(コーラス・センド)
5.6 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
他のパートでも同様のパラメーターがあり、それぞれで設定する
•
ことができます。
各エフェクトはそれぞれ設定を変更することができます。「エ
•
フェクトの設定をする」(P.72)の各設定をご覧ください。
0〜127
5.7 Orchest. MIDI TX
(オーケストラ・ベース MIDI TX)
現在選択しているオーケストラ・ベース・
パートの音色の MIDI に関するパラメー
ターです。詳しくは「各パートで送信する
MIDI の設定をする」(P.102)をご覧くだ
さい。これらの設定はセットごとに保存さ
れ、そのセットに含まれる音色ごとに異なる MIDI の設定を使うこ
とができます。
VALUE
(バリュー)
音が突然止まるように感じられる場合は、「VALUE」の設定値を上
げます。「0」で各音色のあらかじめ設定されている減衰時間(リ
リース・タイム)となり、設定値を上げると減衰する時間は長くな
ります。
0〜63
(初期設定:0)
5.3 Orc.Bass Volume
(オーケストラ・ベース・ボリューム)
オーケストラ・ベース・パートの音量を調
節します。詳しくは「オーケストラ・ベー
ス・パートの音量を設定する(オーケスト
ラ・ベース・ボリューム機能)」(P.35)を
ご覧ください。
LEVEL
(レベル)
64
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:-10)
Page 65

「6 ORCH. EDIT」
Current または Current
+ Scom の場合 ALL の場合
違うレジスターを選択したり、
名前を変更することはできませ
ん。
オーケストラ・パートの音色の
設定をする
オーケストラ・パートの音色の設定をしま
す。音量やエフェクトの設定など、オーケス
トラ・パートの音色の関する設定をすること
ができます。
ここでの設定は、セットごとに保存されます。また、設定は現在選
択されているセットに対して行います。設定を変更する前に、
[SET / ]ボタンを使って、あらかじめ設定したいセットを
選択してください。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
本機の設定をする
[MENU / WRITE]ボタンを押して保存を実行します。
4.
保存終了後に、ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
保存中(砂時計表示中)は絶対に電源を切らないでください。故障
の原因になります。
5.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
ター
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きるので、最も確実です。
ここでの設定の変更は、現在選択しているオーケストラ・パートの
音色に適用されます。設定を変更したいレジスター・スイッチ
([1]〜[13])を押して設定を始めてください。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべてライト機能で保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
•
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
以下の手順に従って、保存を行ってください。
1.
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]
2.
ボタンを押して「Orchestra」を選びます。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
6.
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
7.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありませ
ん。
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
8.
します。ディスプレイに以下の保存完了メッセージ画面
がしばらくの間表示されます。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
3.
9.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
パラメーターの選択、設定方法については P.44、P.45 をご覧くだ
さい。
65
Page 66

本機の設定をする
6.1 Orchestra Octave
(オーケストラ・オクターブ)
選択したオーケストラ・パートの音色を 1
オクターブ上げたり下げたりすることがで
きます。「-1」にすると 1 オクターブ低く、
「1」にすると高くなります。
VALUE
(バリュー)
オーケストラ・モードをデュアル・モードにしたとき(P.32)、
オーケストラ・パートの音色をトレブル・パートの音色より 1 オク
ターブ上、または 1 オクターブ下にすると面白い効果を得ることが
できます。
-1〜0〜1
(初期設定:0)
6.2 Orchestra Volume
(オーケストラ・ボリューム)
オーケストラ・パートの音量を調節しま
す。詳しくは「オーケストラ・パートの音
量を設定する(オーケストラ・ボリューム
機能)」(P.34)をご覧ください。
6.4 Reverb Send(リバーブ・センド)
6.5 Chorus Send(コーラス・センド)
6.6 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
他のパートでも同様のパラメーターがあり、それぞれで設定する
•
ことができます。
各エフェクトはそれぞれ設定を変更することができます。「エ
•
フェクトの設定をする」(P.72)の各設定をご覧ください。
0〜127
LEVEL
(レベル)
Off(オフ)、-40 〜 Std 〜 40
(初期設定:Std)
6.3 Bellows Detune
(ベローズ・デチューン)
蛇腹をより速く開閉したときに、オーケス
トラ・パートの音色のピッチがどれくらい
強く変わるかをシミュレートします。これ
によって、オーケストラ・パートの音色は
よりリアルになります。
TYPE
(タイプ)
「Standard」で効果が弱いと感じたら「High」に、強すぎると感じ
たら「Low」にしてみてください。この効果をお使いにならないと
きは「Off」に設定してください。音色によって、効果が変わりま
す。
音色によって機能しない場合があります。
Off(オフ)
Low(ロー)
Standard(スタンダード)
High(ハイ)
(初期設定:Low)
66
Page 67

本機の設定をする
6.7 Aftertouch Pitch
(アフタータッチ・ピッチ)
アフタータッチ操作をしたときのピッチを
設定します。
アフタータッチは、
します。マスター.バーを押す強さによっ
てピッチを一時的に変えることができま
す。
MODE
(モード)
「1/4 Down」または「1/2 Down」を選択すると、1 / 4 音または
半音ベンド・ダウン(一時的にピッチを下げる)することができま
す。「1/4 Up」または「1/2 Up」を選択すると、1 / 4 音または半
音ベンド・アップ(一時的にピッチを上げる)することができま
す。「Off」を選択すると、アフタータッチは機能しません。
トレブル・パートの音色にもアフタータッチの設定を行うパラメー
ターがあります(P.52)。それぞれ独立して設定をすることができ
ます。
アフタータッチ効果は同時に鳴っているすべての音に適応されま
す。
オルガンの音色(「8A PercOrgan」、「8B JazzOrgan」、「9A
RotOrgan」、「9B TermOrg」)を選択しているときは、ロータリー
効果(オルガンの音色を選択すると自動的に適用されます)のス
ピードをアフタータッチで切り換えることができます。これはオフ
にすることができませんが、ここで説明したピッチ・コントロール
と同時に使うことができます。
外部 MIDI 機器を接続した場合、アフタータッチ情報を送信します。
マスター・バーを使用
Off(オフ)
1/4 Down(1 / 4 ダウン)
1/2 Down(1 / 2 ダウン)
1/4 Up(1 / 4 アップ)
1/2 Up(1 / 2 アップ)
(初期設定:Off)
「7 ORC CHD EDIT」
オーケストラ・コード・パート
音色の設定をする
オーケストラ・コード音色の設定をします。音量やエフェクトの設
定など、オーケストラ・コード・パートの音色に関する設定をする
ことができます。
本機は、ベース列でアコーディオン音色、コード列でオーケストラ
音色を、またはその逆を演奏することができます。オーケストラ・
コード・セクションについての詳細は P.35 をご覧ください。オー
ケストラ・コード音色とオーケストラ・ベース音色とを併せること
もできます。パラメーターの選択、設定方法については P.44、
P.45 をご覧ください。
[UP]/[DOWN]ボタンを同時に押すと、初期設定値に戻すこと
ができます。
注意
「2.14 Orchestra Chord Link (オーケストラ・コード・リンク)」
(P.53)を使って、それぞれのトレブル・レジスターでオーケスト
ラ・コードを自動的に選択することができます。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべて保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
•
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
以下の手順に従って、保存を行ってください。
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
1.
WRITE]ボタンを押し続けます。
6.8 Orchest. MIDI TX
(オーケストラ MIDI TX)
現在選択しているオーケストラ・パートの
音色の MIDI に関するパラメーターです。
詳しくは「各パートで送信する MIDI の設
定をする」(P.102)をご覧ください。これ
らの設定はセットごとに保存され、その
セットに含まれる音色ごとに異なる MIDI の設定を使うことができ
ます。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
2.
を押して「Orc. Chord」を選びます。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
3.
67
Page 68

本機の設定をする
Current または Current
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
4.
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
ター
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
5.
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きるので、最も確実です。
7.1 Orc Chord Volume
(オーケストラ・コード・ボリューム)
オーケストラ・コード・セクションと他の
セクションとのミックス(ボリューム・バ
ランス)を行うパラメーターです。ボ
リュームの標準値(Std)からの増減の相
対値を設定します。
LEVEL
(レベル)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
(初期設定値:Std)
+ Scom の場合 ALLの場合
違うレジスターを選択したり、
名前を変更することはできませ
ん。
6.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありませ
ん。
7.
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
8.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
パラメーターの選択、設定方法については P.44 、P.45 をご覧くだ
さい。
7.2 Reverb Send(リバーブ・センド)
7.3 Chorus Send(コーラス・センド)
7.4 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
0〜127
7.5 Orc Chord MIDI TX
(オーケストラ・コード MIDI TX)
オーケストラ・セクションの MIDI に関す
るパラメーターです。これらの設定は他の
セット・パラメーターと共に保存され、
セットごとに異なる MIDI の設定を行えま
す。
68
Page 69

「8 ORC FBS EDIT」
Current または Current
オーケストラ・フリー・ベース・
パート音色の設定をする
オーケストラ・フリー・ベース音色の設定をします。音量やエフェ
クトの設定などオーケストラ・フリー・ベース音色に関する設定を
することができます。
オーケストラ・フリー・ベース・セクションについての詳細は
P.36 をご覧ください。ベース・モード時はこの項目は有効ではあ
りません。
パラメーターの選択、設定方法については P.44、P.45 をご覧くだ
さい。
[UP]/[DOWN]ボタンを同時に押すと、初期設定値に戻すこと
ができます
注意
『2.5 Valve Noise(バルブ・ノイズ)』(P.51)のパラメーターを
使って、それぞれのトレブル・レジスターでオーケストラ・フ
リー・ベースを自動的に選択することができます。
本機の設定をする
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
4.
で保存したい項目を選択します。
Current 現在エディットしているトレブル・レジス
ター
Current +
SCom
ALL すべてのレジスター。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
5.
手順 3 で選択した項目にあわせてディスプレイに以下の
ように表示されます。
+ Scom の場合 ALL の場合
違うレジスターを選択したり、
名前を変更することはできませ
ん。
現在エディットしているトレブル・レジス
ターとセット・コモンの設定(P.71)。
それぞれのレジスターごとに保存する必要
がなく、一括ですべてを保存することがで
きるので、最も確実です。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべてライト機能で保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
•
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
以下の手順に従って、保存を行ってください。
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
1.
WRITE]ボタンを押し続けます。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
2.
を押して「Orc.FBass」を選びます。
6.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
で保存するセットの番号を選択します。現在のセットに
上書きする場合はこの番号を変更する必要はありませ
ん。
7.
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
8.
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
パラメーターの選択、設定方法については P.44、P.45 をご覧くだ
さい。
[DATA / E 。NTER]つまみを押して設定を確認します
3.
69
Page 70

本機の設定をする
8.1 Orc FreeBs Volume
(オーケストラ・フリーベース・ボリュー
ム)
オーケストラ・コード・セクションと他の
セクションとのミックス(ボリューム・バ
ランス)を行うパラメーターです。ボ
リュームの標準値(Std)からの増減の相
対値を設定します。
LEVEL
(レベル)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
(初期設定値:Std)
8.2 Reverb Send(リバーブ・センド)
8.3 Chorus Send(コーラス・センド)
8.4 Delay Send(ディレイ・センド)
リバーブ、コーラス、ディレイなどのエフェクト
へのセンド・レベル(各エフェクトをどれぐらい
かけるか)を調節します。設定値を高くすると、
選択している音色にかかる各エフェクトがより深
くなります。
LEVEL
(レベル)
0〜127
8.5 Orc FreeBs MIDI TX
(オーケストラ・フリーベース MIDI TX)
オーケストラ・セクションの MIDI に関す
るパラメーターです。これらの設定は他の
セット・パラメーターと共に保存され、
セットごとに異なる MIDI 設定を行えます。
70
Page 71

本機の設定をする
「9 SET COMMON」
セット全体の設定をする
セットの設定をします。ここでの設定は、セット
内の全パートに適用されます。リバーブ、コーラ
ス、ディレイなどのエフェクトのより細かな設
定、マスター・バーの設定やセットに名前を付け
たりします。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
セットについて
本機の構成は、大きく分けて、トレブル・パート(右手のトレブ
ル・ボタン部分でアコーディオンの音色)、オーケストラ・パート
(右手のトレブル・ボタン部分でオーケストラの音色)、ベース・
パート(左手のベース・ボタン部分でアコーディオンの音色)、
オーケストラ・ベース・パート(左手のベース・ボタン部分でオー
ケストラの音色)、オーケストラ・コード・パート(左手のベース・
ボタン部分でオーケストラ・コードの音色)、オーケストラ・フ
リー・ベース・パート(左手のベース・ボタン部分でオーケスト
ラ・フリー・ベース音色)となっています。各パートで独立して音
色を設定することができ、その状態をまとめて「セット」と呼びま
す。
また「セット」は音色だけでなく、エフェクトやマスター・バーの
設定も保存することができ、40 種類まで保存することができます。
「セット」を切り換えると、各パートに設定された音色や設定も同
じように切り換わります。「セット」は簡単に切り換えることがで
きますので、あたかも 40 種類のアコーディオンを持っている感覚
でお使いになれます。
以下の設定がセットごとに保存されます。
「「2 TREBLE EDIT」トレブル・パートの音色の設定をする」
•
(P.48)、「「3 BASS EDIT」ベース・パート(ストラデラ・ ベー
ス・モード)の音色の設定をする」(P.55)、「「4 FREE BS EDIT」
ベース・パート(フリー・ベース・モード)の音色の設定をす
る」(P.59)、「「5 ORC.BASS EDIT」オーケストラ・ベース・
パートの音色の設定をする」(P.63)、「「6 ORCH. EDIT」オーケ
ストラ・パートの音色の設定をする」(P.65)での各設定
「「9 SET COMMON」セット全体の設定をする」(P.71)での設定
•
変更した設定を保存する
変更した設定はすべてライト機能で保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で以下の操作を行うと変更
した設定は失われます。ご注意ください。
•
他のセットを選択したとき
•
本機の電源を切ったとき
以下の手順に従って、保存を行ってください。
1.
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
2.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
を押して「Set Com」を選びます。
[DATA / E 。NTER]つまみを押して設定を確認します
3.
もし必要であれば、[DATA / ENTER]つまみを回して
4.
他のセットを選びます。
誤ってセット・コモン設定を上書きしてしまわないため
に、ディスプレイに保存先のセットの名前も表示されま
す。(矢印の下)
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
5.
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
保存を行う前に本機の電源を切ったり別のセットを選択したりする
と、変更した設定は失われます。
以下に説明する保存の手順は「7 SET COMMON」のパラメーター
の設定を保存するもので、各パートの音色の設定は保存されませ
ん。各パートの設定の保存については、それぞれの項目をご覧くだ
さい。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
6.
71
Page 72

本機の設定をする
エフェクトの設定をする
エフェクトの設定について
ここでは主にエフェクトの詳細設定を行います。ここでのエフェク
ト設定は、セット内の全パートの音色に適用されます。各パートで
は、各エフェクトの量のみ調節することができます。
各パートの音色がエフェクトを経由したときのシステム図は以下の
ようになります。
Chorus
Send
Reverb
Send
Delay
パート
Volume
エフェクトの設定は別のセットからコピーすることができます。
(全エフェクトをコピーする場合→「11.2 Copy ALL Effects (コ
ピー・オール・エフェクト)」(P.89)、リバーブ→「11.3 Copy
Reverb(コピー・リバーブ)」(P.90)、コーラス→「11.4 Copy
Chorus(コピー・コーラス)」(P.90)、ディレイ→「11.5 Copy
Delay(コピー・ディレイ)」(P.90)。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、現在選択してい
るパラメーターが初期設定に戻ります。
Send
Chorus
Reverb
Delay
Level
Level
Level
L
R
9.1 Reverb Macro(リバーブ・マクロ)
リバーブのタイプを選択し、リバーブ音の
音量を調節します。
[DATA / ENTER]つまみを押して「TYPE」を選択し、
1.
[DATA / ENTER]つまみを回してリバーブのタイプを
選択します。
「TYPE」でリバーブのタイプを選択すると、「9.2 Reverb
Parameters (リバーブ・パラメーター)」(P.73)の「Pre-
LPF」、「Time」、「Level」、「Dly Fback」、「Pre-Dly T.」の各設
定は、そのリバーブのタイプに最適な設定になります(マクロ
操作)。さらに詳しくリバーブの設定を行いたいときは「9.2
Reverb Parameters (リバーブ・パラメーター)」(P.73)の各
設定を変更します。
TYPE(タイプ)
Hall 1(ホール 1)
Hall 2(ホール 2)
Plate(プレート) プレート・リバーブ(金属板の振動
Delay(ディレイ) エコー効果を作り出す通常のディレ
Panning Dly
(パンニング・ディ
レイ)
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して「LEVEL」を選択し、
コンサート・ホールでの残響音をシ
ミュレートしたリバーブです。
「Room(1 〜 3)」よりも深い残響
音が得られます。
を利用したリバーブ・ユニット)を
シミュレートしたリバーブです。高
音が伸びた金属的な響きが得られま
す。
イです。
ディレイ音が L / R チャンネル間
で交互に鳴る、ステレオ出力時専用
のディレイです。
[DATA / ENTER]つまみを回してリバーブ音の音量を
調節します。
LEVEL
(レベル)
このレベル「LEVEL」は、[REVERB]つまみ(P.13)を 12
時方向(中央点)にしたときの値になります。つまみの値は、
左いっぱいまで回した状態で「0」、右いっぱいまで回した状態
で「127」になります。お好みのリバーブ・レベルを設定して
おくと、つまみを 12 時方向(中央点)にすることで素早くお
好みの値にすることができます。
通常、つまみの位置は 12 時方向(設定値)で使用し、演奏時にリ
バーブをより深くかけたい場合は右に回し、浅くかけたい場合は左
に回します。
リバーブ音の音量は、1. 各パートの音色ごとに設定するリバー
ブのセンド・レベル(P.51、59、62、64、66)、2. セットご
とに設定するリバーブ音の出力音量(ここで説明している
「LEVEL」)、3. そして本機の全体的なリバーブ音の音量を決定
する[REVERB]つまみの設定(P.37)の 3 つよって決まり
ます。
3. のつまみの位置がセンターの場合は、1. あるいは 2. のどち
らかを「0」にするとリバーブの効果はなくなります。各パー
トの音色ごとに設定するリバーブのセンド・レベルを「0」に
すると、その選択した音色だけリバーブの効果がなくなりま
す。ここで説明している「LEVEL」を「0」にすると、選択し
たセットを構成する全パートの音色のリバーブ効果がなくなり
ます。
0〜127
TYPE(タイプ)
Room 1(ルーム 1)
Room 2(ルーム 2)
Room 3(ルーム 3)
72
室内での残響音をシミュレートした
リバーブです。ライブな部屋をイ
メージした明るい音色の残響音が得
られます。
Page 73

9.2 Reverb Parameters
(リバーブ・パラメーター)
リバーブの詳しい設定を行います。
1.
[DATA / ENTER]つまみを押し
て「TYPE」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを回してパラメー
ターを選択します。
以下のパラメーターを選択することができます。
•
リバーブのタイプ
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
リバーブのタイプを選択します。ただし、ここでリバーブのタ
イプを変更しても「Pre-LPF」、「Time」、「Level」、「Dly
Fback」、「Pre-Dly T.」の各設定は変わりません(一方、「9.1
Reverb Macro(リバーブ・マクロ)」(P.72)の「TYPE」を変
更すると、各設定はあらかじめ用意されたそのリバーブのタイ
プに最適な設定になります)。
「VALUE」の設定値はそれぞれ以下のリバーブのタイプに対応しま
す。
0:Room 1、1:Room 2、2:Room 3、3:Hall 1、4:Hall 2、
5:Plate、6:Delay、7:Panning Dly
Character(キャラクター)
0〜7
本機の設定をする
•
フィードバック
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
このパラメーターは「Character」で「6」か「7」を選択して
いるときのみ有効です。フィードバックとは、ディレイ信号を
ディレイの入力に戻すことを言い、ここでは入力に戻す量を調
節します。「VALUE」を大きくするほどディレイの繰り返し回
数が多くなります。
•
プリ・ディレイ・タイム
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
ダイレクト音(元の音色)が出力されてからリバーブ音が出力
されるまでの時間を調節します。「VALUE」を大きくするほど
より大きな残響空間をシミュレートします。
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して「VALUE」を選択し、
[DATA / ENTER]つまみを回して設定値を変更します。
パラメーターの設定値を変更すると、「TYPE」の横に「(E)」
と表示され、その設定があらかじめ用意されたものから変更さ
れていることを示します。
Dly Fback(ディレイ・フィードバック)
0〜127
Pre-Dly T.(プリ・ディレイ・タイム)
0〜127
ロー・パス・フィルター
•
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
リバーブに送る音色のロー・パス・フィルターを設定します。
「VALUE」を大きくするほどその音色はより暗いものとなり、
その結果、柔らかい残響効果を作り出します。このロー・パ
ス・フィルターはリバーブに送る音色にかかるものであり、実
際に鳴っている音色に変化を加えるものではありません。
リバーブの長さ
•
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
リバーブ音の長さ(時間)を調節します。「VALUE」を大きく
するほどリバーブ音の継続時間が長くなります。
リバーブの音量
•
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
リバーブ音の音量を調節します。「9.1 Reverb Macro(リバー
ブ・マクロ)」(P.72)の「LEVEL」と連動します。
Pre-LPF(プリ・ロー・パス・フィルター)
0〜7
Time(タイム)
0〜127
Level(レベル)
0〜127
「9.1 Reverb Macro(リバーブ・マクロ)」(P.72)で別の「TYPE」
を選択すると、変更した設定は失われて、そのリバーブのタイプに
最適な設定になります。
73
Page 74

本機の設定をする
9.3 Chorus Macro(コーラス・マクロ)
コーラスのタイプを設定し、コーラス音の
音量を調節します。
1.
[DATA / ENTER]つまみを押し
て「TYPE」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを回してコーラスのタイプを選択しま
す。
「TYPE」でコーラスのタイプを選択すると、「9.4 Chorus
Parameters (コーラス・パラメーター)」(P.74)の全パラ
メーターの各設定はあらかじめ用意されたそのコーラスのタイ
プに最適な設定になります(マクロ操作)。さらに詳しくコー
ラスの設定を行いたいときは「9.4 Chorus Parameters (コー
ラス・パラメーター)」(P.74)の各設定を変更します。
TYPE(タイプ)
Chorus 1
(コーラス 1)
Chorus 2
(コーラス 2)
Chorus 3
(コーラス 3)
Chorus 4
(コーラス 4)
FBack Chr
(フィードバック・
コーラス)
Flanger
(フランジャー)
Short Delay
(ショート・ディレ
イ)
Short Dly FB
(ショート・ディレ
イ・フィードバッ
ク)
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して「LEVEL」を選択し、
[DATA / ENTER]つまみを回してコーラス音の音量を
調節します。
LEVEL
(レベル)
このレベル「LEVEL」は、[CHORUS]つまみ(P.13)を 12
時方向(中央点)にしたときの値になります。つまみの値は、
左いっぱいまで回した状態で「0」、右いっぱいまで回した状態
で「127」になります。お好みのコーラス・レベルを設定して
おくと、つまみを 12 時方向(中央点)にすることで素早くお
好みの値にすることができます。
音色に空間的な拡がりと深みを加え
る通常のコーラスです。
フランジャーのような効果があり、
柔らかい音のコーラスです。
音に「うねり」を与えるフランジン
グ効果を作り出します。
ディレイ・タイムの短いディレイで
す。
ディレイ・タイムの短いディレイで
す。
0〜127
各パートの音色ごとに設定するコーラスのセンド・レベルを
「0」にすると、その選択した音色だけコーラスの効果がなくな
ります。ここで説明している「LEVEL」を「0」にすると、選
択したセットを構成する全パートの音色のコーラス効果がなく
なります。
9.4 Chorus Parameters
(コーラス・パラメーター)
コーラスの詳しい設定を行います。
[DATA / ENTER]つまみを押し
1.
て「TYPE」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを回してパラメー
ターを選択します。
以下のパラメーターを選択することができます。
•
ロー・パス・フィルター
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
コーラスに送る音色のロー・パス・フィルターを設定します。
「VALUE」を大きくするほどその音色はより暗いものとなり、
その結果、柔らかいコーラス音を作り出します。このロー・パ
ス・フィルターはコーラスに送る音色にかかるものであり、実
際に鳴っている音色に変化を加えるものではありません。
•
コーラスの音量
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
コーラス音の音量を調節します。「9.3 Chorus Macro(コーラ
ス・マクロ)」(P.74)の「LEVEL」と連動します。
•
フィードバック
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
コーラス信号をコーラスの入力に戻す(フィードバック)とき
のレベルを調節します。これによってより密度の高いコーラス
音を作り出すことができます。「VALUE」を大きくするほど
フィードバックのレベルが大きくなります。
•
コーラス音が出力されるまでの時間
Pre-LPF(プリ・ロー・パス・フィルター)
0〜7
Level(レベル)
0〜127
Feedback(フィードバック)
0〜127
通常、つまみの位置は 12 時方向(設定値)で使用し、演奏時に
コーラスをより深くかけたい場合は右に回し、浅くかけたい場合は
左に回します。
コーラス音の音量は、1. 各パートの音色ごとに設定するコーラ
スのセンド・レベル(P.51、59、62、64、66)、2. セットご
とに設定するコーラス音の出力音量(ここで説明している
「LEVEL」)、3. そして本機の全体的なコーラス音の音量を決定
する[CHORUS]つまみの設定(P.37)の 3 つよって決まり
ます。3. のつまみの位置がセンターの場合は、1. あるいは 2.
のどちらかを「0」にするとコーラスの効果はなくなります。
74
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
ダイレクト音が出力されてから、コーラス音が出力されるまで
の時間を調節します。「VALUE」を大きくするほどコーラス音
が遅れて鳴ります。
Delay(ディレイ)
0〜127
Page 75

本機の設定をする
Chorus
Level
Volume
Chorus
Send
Reverb
Send
Delay
Send
Level
Level
Reverb
Delay
L
R
パート
•
コーラス効果の速さ
TYPE
Rate(レイト)
(タイプ)
VALUE
0〜127
(バリュー)
コーラス効果の速さを調節します。「VALUE」を大きくするほ
ど変調周期が速くなります。
•
コーラス効果の深さ
TYPE
Depth(デプス)
(タイプ)
VALUE
0〜127
(バリュー)
コーラス効果の深さを調節します。「VALUE」を大きくするほ
ど変調が大きくなります。
•
コーラスのリバーブ送り
TYPE
Chr Rev(コーラス リバーブ)
(タイプ)
VALUE
0〜127
(バリュー)
リバーブへ送るコーラス音の量を調節します。「VALUE」を
「127」にするとコーラスとリバーブを直列に接続した状態に
なります(リバーブの前にコーラスを接続した状態)。コーラ
ス信号をリバーブに送らない場合は、「VALUE」を「0」にし
ます。
[DATA / ENTER]つまみを押して「VALUE」を選択し、
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して設定値を変更しま
す。
パラメーターの設定値を変更すると、「TYPE」の横に「(E)」
と表示され、その設定があらかじめ用意されたものから変更さ
れていることを示します。
「9.3 Chorus Macro(コーラス・マクロ)」(P.74)で別の「TYPE」
を選択すると、変更した設定は失われて、そのコーラスのタイプに
最適な設定になります。
9.5 Delay Macro(ディレイ・マクロ)
ディレイのタイプを設定し、ディレイ音の
音量を調節します。
[DATA / ENTER]つまみを押し
1.
て「TYPE」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを回してディレイのタイプを選択しま
す。
「TYPE」でディレイのタイプを選択すると、「9.6 Delay
Parameters (ディレイ・パラメーター)」(P.76)の全パラ
メーターの各設定はあらかじめ用意されたそのディレイのタイ
プに最適な設定になります(マクロ操作)。さらに詳しくディ
レイの設定を行いたいときは「9.6 Delay Parameters (ディレ
イ・パラメーター)」(P.76)の各設定を変更します。
コーラスのディレイ送り
•
TYPE
Chr Dly(コーラス ディレイ)
(タイプ)
VALUE
0〜127
(バリュー)
ディレイへ送るコーラス音の量を調節します。「VALUE」を
「127」にするとコーラスとディレイを直列に接続した状態に
なります(ディレイの前にコーラスを接続した状態)。コーラ
ス信号をディレイに送らない場合は、「VALUE」を「0」にし
ます。
Level
Level
Level
パート
Chorus
Send
Volume
Reverb
Send
Delay
Send
Chorus
Reverb
Delay
TYPE(タイプ)
Delay 1
(ディレイ 1)
Delay 2
(ディレイ 2)
通常のディレイです。「Delay 1」、
「Delay 2」、「Delay 3」の順にディ
レイ・タイム(音を遅らせる時間)
が長くなります。
Delay 3
(ディレイ 3)
Delay 4
(ディレイ 4)
Pan Delay 1
(パン・ディレイ 1)
Pan Delay 2
(パン・ディレイ 2)
Pan Delay 3
(パン・ディレイ 3)
Pan Delay 4
(パン・ディレイ 4)
ディレイ・タイムの短いショート・
ディレイです。
ディレイ音が L / R チャンネル間
で交互に鳴る、ステレオ出力時専用
のディレイです。「Pan Delay 1」、
「Pan Delay 2」、「Pan Delay 3」の
順にディレイ・タイムが長くなりま
す。
ディレイ・タイムの短いショート・
ディレイで、ディレイ音が L / R
チャンネル間で交互に鳴ります。ス
テレオ出力時専用のディレイです。
Delay Rev
(ディレイ リバー
ブ)
Pan Repeat
(パン・リピート)
ディレイ音にリバーブがかけられ、
L / R チャンネル間で交互に鳴りま
す。ステレオ出力時専用のディレイ
です。
ディレイ音が L / R チャンネル間
で交互に鳴る、ステレオ出力時専用
のディレイですが、上記のものとは
ステレオ位置が異なります。
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して「LEVEL」を選択し、
[DATA / ENTER]つまみを回してディレイ音の音量を
調節します。
L
R
LEVEL
(レベル)
0〜127
75
Page 76

本機の設定をする
このレベル「LEVEL」は、[DELAY]つまみ(P.13 )を 12 時
方向(中央点)にしたときの値になります。つまみの値は、左
いっぱいまで回した状態で「0」、右いっぱいまで回した状態で
「127」になります。お好みのディレイ・レベルを設定してお
くと、つまみを 12 時方向(中央点)にすることで素早くお好
みの値にすることができます。
通常、つまみの位置は左いっぱいまで回した状態(「0」)で使用し、
ディレイ音が必要な場合に右に回して使用します。
ディレイ音の音量は、1. 各パートの音色ごとに設定するディレ
イのセンド・レベル(P.51、59、62、64、66)、2. セットご
とに設定するディレイ音の出力音量(ここで説明している
「LEVEL」)、3. そして本機の全体的なディレイ音の音量を決定
する[DELAY]つまみの設定(P.37)の 3 つよって決まりま
す。3. のつまみの位置がセンターの場合は、1. あるいは 2. の
どちらかを「0」にするとディレイの効果はなくなります。各
パートの音色ごとに設定するディレイのセンド・レベルを「0」
にすると、その選択した音色だけディレイの効果がなくなりま
す。ここで説明している「LEVEL」を「0」にすると、選択し
たセットを構成する全パートの音色のディレイ効果がなくなり
ます。
9.6 Delay Parameters
(ディレイ・パラメーター)
ディレイの詳しい設定を行います。
1.
[DATA / ENTER]つまみを押し
て「TYPE」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを回してパラメー
ターを選択します。
以下のパラメーターを選択することができます。
ロー・パス・フィルター
•
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
ディレイに送る音色のロー・パス・フィルターを設定します。
「VALUE」を大きくするほどその音色はより暗いものとなり、
その結果、柔らかいディレイ音を作り出します。このロー・パ
ス・フィルターはディレイに送る音色にかかるものであり、実
際に鳴っている音色に変化を加えるものではありません。
Pre-LPF(プリ・ロー・パス・フィルター)
0〜7
センター(C)・チャンネル、レフト(L)・チャンネル、ライ
ト(R)・チャンネルのディレイ・タイム(音を遅らせる時間)
を調節します。「Time L」と「Time R」はセンター(C)・チャ
ンネル(「Time C」)との比率(%)で調節します。「VALUE」
を「100%」にすると左右両チャンネルのディレイ・タイムが
センター・チャンネルと同じになります。
•
各チャンネルのディレイの音量
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
センター(C)、レフト(L)、ライト(R)各チャンネルのディ
レイ音の音量を別々に調節します。お好みの音量バランスにす
ることができます。
•
フィードバック
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
ディレイ信号をディレイの入力に戻す量(フィードバック)を
調節します。「VALUE」を「0」にするとディレイの繰り返し
がなくなります。「VALUE」を大きくするほどディレイの繰り
返し回数が多くなります。「VALUE」の値をマイナス(「−」)
にすると、センター(C)・チャンネルのフィードバックの位相
が逆になります。これは「Time C」の「VALUE」を小さくす
ると特にその効果が顕著になります。
•
ディレイのリバーブ送り
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
リバーブへ送るディレイ音の量を調節します。「VALUE」を大
きくするほどディレイ音にリバーブがかかります。
Level L(レベル L)
Level C(レベル C)
Level R(レベル R)
0〜127
Feedback(フィードバック)
-64〜0〜63
Dly Rev(ディレイ リバーブ)
0〜127
Chorus
Send
Reverb
Send
Delay
パート
Volume
Send
Chorus
Reverb
Delay
Level
Level
Level
ディレイの音量
•
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
ディレイ音全体の音量を調節します。「9.5 Delay Macro(ディ
レイ・マクロ)」(P.75)の「LEVEL」と連動します。
ディレイ・タイム
•
TYPE
(タイプ)
VALUE
(バリュー)
Level(レベル)
0〜127
Time L(%)(タイム L)
Time C(ms 〜 s )(タイム C)
Time R(%)(タイム R)
4 〜 500(Time L / Time R の場合:%)
0.1 〜 1000(Time C の場合:1s)
76
[DATA / ENTER]つまみを押して「VALUE」を選択し、
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して設定値を変更します。
パラメーターの設定値を変更すると、「TYPE」の横に「(E)」
と表示され、その設定があらかじめ用意されたものから変更さ
れていることを示します。
「9.5 Delay Macro(ディレイ・マクロ)」(P.75)で別の「TYPE」
を選択すると、変更した設定は失われて、そのディレイのタイプに
最適な設定になります。
L
R
Page 77

本機の設定をする
その他の設定をする
9.7 Name(ネーム)
選択したセットに最大 8 文字までの名前を
つけることができます。各パートのパラ
メーターを使って作り上げた楽器の名前
や、そのセットで演奏する曲名などにする
と良いでしょう。
[UP]ボタン(右に進む)、[DOWN]ボタン(左に戻
1.
る)、または[DATA / ENTER]つまみ(右に進む)を
押してカーソル(黒い四角)を移動します。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して文字を変更します。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと現在カー
•
ソルのある文字が消去されて空白になります。
例:「Fr.Folk」の「o」を空白にする(「Fr.F lk」)場合は、
「o」にカーソルを移動して、[UP]ボタンと[DOWN]ボ
タンを同時に押します。
[UP]ボタンを押し続けると現在カーソルがある文字の前
•
に空白が入り、その後の文字はすべて右にずれます。
例:「Fr.Folk」の「o」の前に空白を入れる(「Fr.F olk」)場
合は、「o」にカーソルを移動して、[UP]ボタンを押し続
けます。
9.9 Icon(アイコン)
各セットにアイコンを割り当てます。アイ
コンは、セットを切り換えたときにディス
プレイに表示されます。本機には 40 種類
のアイコン(1 〜 40)があらかじめ用意さ
れていますので、その中から選択します。
ICON
(アイコン)
1〜40
名前がすでに 8 文字ある場合(「Bandoneo」)は最後の文字が消去
されます(「Band one」)。
[DOWN]ボタンを押し続けると現在カーソルのある文字が
•
消去され、その後の文字はすべて左にずれます。
例:「Fr.Folk」の「o」を消去する(「Fr.Flk」)場合は、「o」
にカーソルを移動して、[DOWN]ボタンを押し続けます。
9.8 Master Bar Recall
(マスター・バー・リコール)
マスター・バーを押したときに呼び出すト
レブル・パートの音色([1]〜[14]のト
レブル・レジスター・スイッチ)を指定し
ます。オーケストラ・パートがオフになっ
ている場合(「CANCEL」が表示)は、マ
スター・バーを押すと指定したトレブル・パートの音色に切り換わ
ります。
TREBLE
REGISTER
(トレブル・
レジスター)
オーケストラ・パートがオンになっていて、デュアル・モード、ハ
イ・モード、ロー・モードのオーケストラ・モードで演奏している
場合(P.32)は、マスター・バーを押すとオーケストラ・パートの
音色をミュートします(もう一度押すとオーケストラ・パートの音
色が戻ります)。ソロ・モードではトレブル・パートとオーケスト
ラ・パートの音色が交互に切り換わります。
1〜14
77
Page 78

本機の設定をする
「10 SYSTEM」
システムの設定をする
システムの設定をします。ここでの設定は本
機全体に適用されます。ディスプレイのコン
トラスト、蛇腹の設定、フット・スイッチの
設定、ベース・ボタンの設定、起動時の設定
など、本機のシステムに関する設定をしま
す。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
4.
します。ディスプレイに保存完了メッセージ画面がしば
らくの間表示されます。
グローバル・セッティングを保存しない場合でも、電源を切った
り、設定を変更しなければ、その設定のまま使用することができま
す。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
変更した設定を保存する
変更した設定はすべてライト機能で保存することができます。
設定を変更した後、保存を行わない状態で電源を切ると、変更した
設定は失われます。ご注意ください。
以下の手順に従って、保存を行ってください。
1.
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
2.
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
を押して「Grobal」を選びます。
3.
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
ここでの設定の変更を保存しなかった場合、本機の電源を切るまで
(または再び設定を変更するまで)その設定で演奏することができ
ます。
10.1 LCD Contrast(LCD コントラスト)
本機のディスプレイは、見る角度や明かり
の状態などによって表示が見えにくくなる
ことがあります。その場合は、ディスプレ
イのコントラスト(明瞭度)を調節しま
す。「VALUE」を小さくするほど背景が暗
くなります。
VALUE
(バリュー)
1〜7
(初期設定:4)
10.2 Parameter Access
(パラメーター・アクセス)
イージー・モードとフル・モードを選択し
ます。フル・モードではすべてのパラメー
ターを選択することができますが、イー
ジー・モードでは主要なパラメーターのみ
を選択することができます。詳しくは
「イージー・モードとフル・モードを選択する」(P.25)をご覧くだ
さい。
グローバル画面には、グローバル・メモリーに保存されるすべての
パラメーターが表示されます。1 セットのみ保存できます。
78
MODE
(モード)
Easy(イージー・モード)
Full(フル・モード)
(初期設定:Easy)
Page 79

10.3 Bellows Curve(ベローズ・カーブ)
蛇腹の動かし具合に対する音量の変化のし
かた(ダイナミクスの変化量)を設定しま
す。「2.7 Bellows Detune ( ベローズ・デ
チューン)」(P.51)、「3.5 Reed Growl
(リード・グロール)」(P.58)、「3.6
Bellows Detune (ベローズ・デチューン)」(P.58)、「4.5 Reed
Growl(リード・グロール)」(P.62)、「4.6 Bellows Detune (ベ
ローズ・デチューン)」(P.62)、「6.3 Bellows Detune (ベローズ・
デチューン)」(P.66)で設定する効果は、蛇腹を動かしたときの強
さや速さによって音色をコントロールします。
これらが思うように反応しない場合は、蛇腹の動きがより伝わるよ
うに別の音量カーブのタイプを選択します。
TYPE
(タイプ)
「Fixed Low」、「Fixed Med」、「Fixed High」を選択した場合は、ダ
イナミクスは一定となり、蛇腹の動かし具合に関係なく音量は一定
となります。「Fixed Low」は設定値を低く、「Fixed High」は高く、
「Fixed Med」はその中間に設定してあります。
「Light」を選択した場合は、それほど強く蛇腹を動かさなくてもそ
の効果を得ることができます。「X-Light」はさらに弱い動きにする
場合に選択します。「Standard」では通常の反応になります。
「Heavy」にすると最大の効果が得られるまでにより強い蛇腹の動
かし方が必要になりますが、それだけ幅の広いニュアンス付けが可
能となり、「X-Heavy」ではさらにその傾向が強まります。「Fixed
Low」、「Fixed Med」、「Fixed High」以外を選択した場合は、少し
弾いてみて、それを基準に思うような反応が得られるタイプを見つ
けていくのが良いでしょう。
Fixed Low(フィックスド・ロー)
Fixed Med(フィックスド・ミディアム)
Fixed High(フィックスド・ハイ)
X-Light(エクストラ・ライト)
Light(ライト)
Standard(スタンダード)
Heavy(ヘヴィー)
X-Heavy(エクストラ・ヘヴィー)
(初期設定:Standard)
10.4 Pedal Controller
(ペダル・コントローラー)
FBC-7 の各フット・スイッチに割り当てる
機能を設定します。アレンジャー機能のつ
いた音源モジュールなどの外部機器を MIDI
経由でコントロールする機能もあります。
本機を FBC-7 に接続した場合(P.17)のみ、ここでの設定は有効
になります。
FBC-7 について詳細は、「フット・スイッチ(FBC-7、付属)につ
いて」(P.41)をご覧ください。
本機の設定をする
[DATA / ENTER]つまみを押して「SWITCH」を選択
1.
し、[DATA / ENTER]つまみを回してフット・スイッ
チの番号を選択します。
SWITCH
(フット・ス
イッチ)
機能を割り当てたいスイッチの番号を選びます。
[DATA / ENTER]つまみを押して「ASSIGN」を選択
2.
し、[DATA / ENTER]つまみを回して以下の中から機
能を選択します。
ASSIGN
(アサイン)
Set Up
(セット・アップ)
Set Down
(セット・ダウン)
Regist Up
(レジスター・アッ
プ)
Regist Dwn
(レジスター・ダウ
ン)
Treble Sust*
(トレブル・サス
ティーン)
Bass Sust*
(ベース・サス
ティーン)
1
1
1〜5
セットの切り換えに使用します。
「Set Up」は次の番号のセットへ進
み、「Set Down」は前の番号のセッ
トに戻ります。セット 40 を選択し
て「Set Up」を割り当てたフット・
スイッチを踏むとセット 1 に戻り、
セット 1 を選択して「Set Down」
を割り当てたフット・スイッチを踏
むとセット 40 に移動します。初期
設定では[1]スイッチに「Set
Down」が、[2]スイッチに「Set
Up」が割り当てられています。
トレブル・レジスター・スイッチに
登録されている音色の切り換えに使
用します。「Regist Up」は次の番号
のトレブル・レジスター・スイッチ
に登録されている音色に進み、
「Regist Dwn」は前の番号のトレブ
ル・レジスター・スイッチに登録さ
れている音色に戻ります。「2.12
Bass Link(ベース・リンク)」
(P.52)や「2.13 Orchestra Link
(オーケストラ・リンク)」(P.53)
の設定と組み合わせると、この機能
を割り当てたフット・スイッチを踏
むことで簡単にすべてのパートを切
り換えることができます。
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間トレブル・
パートで鳴らしている外部 MIDI 音
源の音をホールドします。本機で鳴
る音はホールドされません。トレブ
ル・ボタンから手を離しても、フッ
ト・スイッチから足を離すまで音は
鳴り続けます。
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間ベース・パー
トのベース・ボタンで鳴らしている
外部 MIDI 音源の音をホールドしま
す。本機で鳴る音はホールドされま
せん。ボタンから手を離しても、
フット・スイッチから足を離すまで
音は鳴り続けます。
79
Page 80

本機の設定をする
ASSIGN
(アサイン)
Chord Sust*
1
(コード・サス
ティーン)
Orch. Sust*
2
(オーケストラ・サ
スティーン)
OrchBs Sust*
1
(オーケストラ・
ベース・サスティー
ン)
OrchFB Sust
(オーケストラ・フ
リーベース・サス
ティーン)
OrchCh Sust
(オーケストラ・
コード・サスティー
ン)
Orch.On/Off
(オーケストラ・オ
ン/オフ)
Start/Stop
(スタート/ストッ
プ)
3
Intro*
(イントロ)
3
Fill Up*
(フィル・アップ)
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間ベース・パー
トのコード・ボタンで鳴らしている
外部 MIDI 音源の音をホールドしま
す。本機で鳴る音はホールドされま
せん。ボタンから手を離しても、
フット・スイッチから足を離すまで
音は鳴り続けます。
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間本機で鳴らし
ているオーケストラ音と外部 MIDI
音源の音をホールドします。トレブ
ル・ボタンから手を離しても、フッ
ト・スイッチから足を離すまで音は
鳴り続けます。
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間オーケスト
ラ・ベース・パートで鳴らしている
外部 MIDI 音源の音をホールドしま
す。本機で鳴る音はホールドされま
せん。ボタンから手を離しても、
フット・スイッチから足を離すまで
音は鳴り続けます。
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間 MIDI 経由で
送信されているフリーベース・パー
トのオーケストラ音をホールドしま
す。MIDI でのみコントロールしま
す。
この機能を割り当てるとフット・ス
イッチを踏んでいる間 MIDI 経由で
送信されているコードのオーケスト
ラ音をホールドします。MIDI での
みコントロールします。
オーケストラ・パートのオン/オフ
を切り換えます。オーケストラ・リ
ンク機能(P.53)のように音色や
オーケストラ・モードを設定するこ
とはできません。
FBC-7 に外部 MIDI 機器を接続して
いるときに、MIDI メッセージの開
始/停止情報を送信します。シーケ
ンサーやドラム・マシン、アレン
ジャー機能のついた音源モジュール
などをコントロールします。
FBC-7 にアレンジャー機能のつい
た音源モジュールなどを接続してい
るときに、イントロ機能を呼び出し
ます(イントロを演奏します)。
(MIDI メッセージ PC83 を MIDI
チャンネル 10 で送信します。)
FBC-7 にアレンジャー機能のつい
た音源モジュールなどを接続してい
るときに、フィルイン機能を呼び出
します(フィルインを演奏します)。
フィルインを演奏したあと、オリジ
ナルを演奏します。(MIDI メッセー
ジ PC81 を MIDI チャンネル 10 で
送信します。)
ASSIGN
(アサイン)
Fill Down*
3
(フィル・ダウン)
FBC-7 にアレンジャー機能のつい
た音源モジュールなどを接続してい
るときに、フィルイン機能を呼び出
します(フィルインを演奏します)。
フィルインを演奏したあと、バリ
エーションを演奏します。(MIDI
メッセージ PC82 を MIDI チャンネ
ル 10 で送信します。)
Ending*
3
(エンディング)
FBC-7 にアレンジャー機能のつい
た音源モジュールなどを接続してい
るときに、エンディング機能を呼び
出します(エンディングを演奏しま
す)。(MIDI メッセージ PC84 を
MIDI チャンネル 10 で送信します。)
Set 1 〜 Set 40
(セット 1 〜セット
40)
Register 1 〜
Register 14
(レジスター 1 〜レ
ジスター 14)
任意のセットを呼び出します(選択
した番号のセットが呼び出されま
す)。
任意のトレブル・レジスター・ス
イッチに登録されている音色を呼び
出します(選択した番号のトレブ
ル・レジスター・スイッチに登録さ
れている音色が呼び出されます)。
*1 外部 MIDI 機器に対して、MIDI メッセージのホールド 1(コント
ローラー・ナンバー 64)を送信します。本機で鳴る各音色には効果
はかかりません。
*2 外部 MIDI 機器に対して、MIDI メッセージのホールド 1(コント
ローラー・ナンバー 64)を送信します。
*3 ローランド製品以外のアレンジャー機能をお使いになるとき、うま
く機能しないことがあります。その場合は、お使いの製品の MIDI イ
ンプリメンテーションをご覧になり、MIDI 設定を行ってください。
80
Page 81

本機の設定をする
10.5 Bass&Chord Mode
(ベース & コード・モード)
ベース音を弾くボタンの列数を設定しま
す。初期設定ではベースが 2 列、コードが
4 列になっています。「3 Bs Rows」を選択
するとベース・ボタンが 20 個(1 列)増
え、ディミニッシュ・コードのボタンがな
くなりますが、より使いやすくなるでしょう。
「ボタン配列 1(ベース&コード・モード)」(P.84)をご覧くださ
い。
「3 Bs Rows」オプションが 4 つあります。「A-7th」と「B-7th」
とは 6 列目のコード列が、5th のないセブンス・コード(7)とな
ります。C7 コードの場合、C-E-Bb(G は無し)音が鳴ります。
「A-7th」と「B-7th」とはベース音のアレンジが異なります。
「Bx-7th」は、「B-7th」のポジションが左右が逆になったものです。
「A-5dim」と「B-5dim」とはセブンス・コードのルート音が鳴らな
いものです。C7 コードでは E-G-Bb(C は無し)音が鳴ります。
「A-5dim」と「B-5dim」とはベース音のアレンジが異なります。
TYPE
(タイプ)
2 Bs rows(2 ベース・ロウ)
3 Bass rows A-7Th(3 ベース・ロウ A-7th)
3 Bass rows A-5dim(3 ベース・ロウ A-5dim)
3 Bass rows B-7th(3 ベース・ロウ B-7th)
3 Bass rows B-5dim(3 ベース・ロウ B-5dim)
3 Bass Rows Bx-7th(3 ベース・ロウ Bx-7th)
(初期設定:2 Bs rows)
10.7 Stereo Width(ステレオ・ウィドス)
本機ではアコーディオンの音色が自然なス
テレオ・サウンドになるように設定されて
いますが(P.17)、ステレオの幅が広く感
じる場合は、このパラメーターを使ってス
テレオの幅を狭くします。
VALUE
(バリュー)
「Full」で初期設定のステレオの幅となり、「-63」で最も狭くなりま
す。
-63 〜 -1、Full(フル)
(初期設定:-15)
10.8 Auto Power OFF
(オート・パワー・オフ)
本機は、バッテリー節約のために、一定時
間何も操作しないと自動的に電源が切れま
す。ここでは自動的に電源が切れるまでの
時間を設定します。この機能は、本機を
FBC-7 に接続している場合は適用されませ
ん。
TYPE
(タイプ)
Disabled(ディセイブルド)
10 min.(10 分)
15 min.(15 分)
20 min.(20 分)
(初期設定:10 min.)
本機を見なくてもベースとコードのボタンの位置がわかるようにデ
ザインされたリファレンス・キャップが付属しています。P.28 を
ご覧ください。
10.6 Free Bass Mode
(フリー・ベース・モード)
フリー・ベース・モードで使うボタン配列
を設定します。フリー・ベースのボタン配
列には多様なバラエティーがありますが、
本機にはその中の最も代表的なものを用意
しました。ここで選択したボタン配列はフ
リー・ベース・モードにしたときのみ使うことができます。「ボタ
ン配列 2(フリー・ベース・モード)」(P.85)をご覧ください。
TYPE
(タイプ)
本機には見なくてもベースとコードのボタンの位置がわかるように
デザインされたリファレンス・キャップがいくつか付属していま
す。詳細は「ベース・セクションを演奏する (ベース・パート)」
(P.28)をご覧ください。
minor 3rd(マイナー・サード)
Bajan(バヤン)
Fifth(フィフス)
N.Europe(ノース・ヨーロッパ)
Finnish (フィニッシュ)
(初期設定:minor 3rd)
「Disabled」を選択すると、この機能はオフになります。
バッテリーについて詳細は「バッテリー(FR-7b のみ付属)の準備
をする」(P.21)をご覧ください。
81
Page 82

本機の設定をする
10.9 Startup(スタートアップ)
本機の電源を入れたときの状態を設定しま
す。
[DATA / ENTER]つまみを押し
1.
て「TYPE」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを回して設定するパラメーターを選択
します。
TYPE
(タイプ)
ASSIGN
(アサイン)
電源を入れたときに選択するセットを指定します。
TYPE
(タイプ)
ASSIGN
(アサイン)
電源を入れたときのオーケストラ・リンク機能(P.53)のオン
/オフを設定します。
TYPE
(タイプ)
ASSIGN
(アサイン)
電源を入れたときのベース・リンク機能(P.52)のオン/オフ
を設定します。
2.
[DATA / ENTER]つまみを押して「ASSIGN」を選択
し、[DATA / ENTER]つまみを回して設定を変更しま
す。
Set(セット)
1〜40
Orch Link(オーケストラ・リンク)
ON(オン)、Off(オフ)
Bass Link(ベース・リンク)
ON(オン)、Off(オフ)
10.11 Orchestra Touch
(オーケストラ・タッチ)
このパラメーターは、オーケストラ音色の
AcPiano、AcGuitar、Mandolin の音色を
トレブル・ボタンで演奏する場合の、トレ
ブル・ボタンのベロシティー・センスを設
定します。
ボタンを強くまたは軽く押してもダイナミック・コントロールの効
かない、常に同じ値の「Fixed」カーブが 3 つあります。「Low」は
低い値、「Med」は中間、「High」は高い値となります。
「Low」はボタンを軽く押しても大きな音で演奏されます。
「High」はフォルティッシモのように非常に強い音を弾きたいとき
に、最も反応のよいベロシティー・カーブです。
さらに表現力のあるオプションとして、「Fixed L + Bellow」と
「Fixed H + Bellow」 はオーケストラ音色をベロシティー固定で弾
きながら、蛇腹の動きでベロシティーの変化をつけることができま
す。また、「Bellows」は選択しているオーケストラ音色を蛇腹の動
きでコントロールします。ボタンではベロシティー値は変化しませ
ん。
VALUE
(バリュー)
Fixed Low(ロー固定)
Fixed Med(ミディアム固定)
Fixed High(ハイ固定)
Low(ロー)
Medium(ミディアム)
High(ハイ)
Fixed L + Bellows(ロー固定+蛇腹)
Fixed M + Bellows(ミディアム固定+蛇
腹)
Fixed H + Bellows(ハイ固定+蛇腹)
Bellows(蛇腹)
(初期設定値:Medium)
10.10 Startup Name
(スタートアップ・ネーム)
本機の電源を入れたときに表示される短い
メッセージを入力します。メッセージは最
大 8 文字まで入力できます。入力の方法に
ついては「9.7 Name(ネーム)」(P.77)
の手順 1、 2をご覧ください。
入力したメッセージは右図のように表示さ
れます(この画面は、本機の電源を入れる
と約 2 秒間表示されます)。
「10.3 Bellows Curve(ベローズ・カーブ)」(P.79)で「Fixed」を
選んでいる場合は、本機は蛇腹の動きに反応しなくなるため、上記
で「Bellows」を含む VALUE(バリュー)はすべて無効になりま
す。
82
Page 83

本機の設定をする
10.12 Orch. Bs&Ch Touch
(オーケストラ・ベース&コード・タッチ)
このパラメーターは、オーケストラ音色の
AcPiano、AcGuitar の音色をベース・ボタ
ンやコード・ボタンで弾く場合の、ベロシ
ティー・センスに関する設定です。
VALUE
(バリュー)
「10.3 Bellows Curve(ベローズ・カーブ)」(P.79)で「Fixed」を
選んでいる場合は、本機は蛇腹の動きに反応しなくなるため、上記
で「Bellows」を含む VALUE(バリュー)はすべて無効になりま
す。
Fixed Low(ロー固定)
Fixed Med(ミディアム固定)
Fixed High(ハイ固定)
Low(ロー)
Medium(ミディアム)
High(ハイ)
Fixed L + Bellows(ロー固定+蛇腹)
Fixed M + Bellows(ミディアム固定+蛇
腹)
Fixed H + Bellows(ハイ固定+蛇腹)
Bellows(蛇腹)
(初期設定値:Medium)
次に[DATA / ENTER]つまみを押すと、ディスプレイにはしば
らくの間以下のように表示されます。
[DATA / ENTER]つまみで MIDI スタート/ストップ・メッセー
ジの送信を行いたくない場合、このパラメーターを「オフ」に設定
してください。
MIDI スタート/ストップ機能を FBC-7のフット・スイッチのひと
つに割り当てることができます。「10.4 Pedal Controller (ペダル・
コントローラー)」(P.79) を参照してください。
10.14 Treble Release T.
ボタンを離した後のトレブル・アコーディ
オン音色の音が減衰するまでの時間(トレ
ブル・リリース・タイム)が実際のリード
よりも長いと感じた場合、それを短くする
ことができます。その場合、設定値を小さ
くします。
10.13 Start/Stop MIDI TX
(スタート/ストップ・MIDI TX)
このパラメーターは、メイン画面が表示さ
れている時に[DATA / ENTER]つまみ
を押して、MIDI スタート/ストップ・メッ
セージを送るかどうかを設定します。
VALUE
(バリュー)
本機と MIDI シーケンサーやリズム・マシンのような音源とをあわ
せて使う場合に便利です。この機能は本機と FBC-7、そして FBC7 の MIDI OUT とシーケンサーや音源の MIDI IN とを接続した場合
にのみ有効です。
「オン」を設定し、メイン画面に戻ると次のようになります。初め
に[DATA / ENTER]つまみを押すと、ディスプレイにはしばら
くの間以下のように表示されます。
これは、MIDI スタート・メッセージが外部のシーケンサーなどに送
られたことを意味します。
Off(オフ)
On(オン)
(初期設定値:Off)
VALUE
(バリュー)
「リリース・タイム」とは、ボタンから指を離したとき、弾いてい
た音が消えるまでの時間を表します。
ミュートした状態としていない状態でシンバルを叩いた場合の違い
を考えてみましょう。
シンバルを叩いた場所
音がだんだんと消えていく
もっと音を長く伸ばしたい場合は、設定値を大きくします。
ゼロは工場出荷時のリリース・タイムを意味します。
-64〜0〜63
(初期設定値:0)
リリース・タイム
シンバルを叩いた場所
シンバルをミュートした
場所
リリース・
タイム
短い音
83
Page 84

本機の設定をする
Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3
E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3
EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM CM GM DM AM EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM
Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm
E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7 C7 G7 D7 A7 E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7
FREE BASS
ORCH BASS
Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3
E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3
EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM CM GM DM AM EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM
Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm
E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7 C7 G7 D7 A7 E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7
Edim
Bdim F#dim C#dim Abdim Ebdim Bbdim Fdim Cdim Gdim Ddim Adim Edim Bdim F#dim C#dim Abdim Abdim Bbdim Fdim
2ベース・ボタン列
FREE BASS
ORCH BASS
C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 C3 G3 D3 A3 E3 F#3 C#3
3ベース・ボタン列A
Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3
E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3
EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM CM GM DM AM EM BM F#M C#M AbM EbM BbM FM
Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm Cm Gm Dm Am Em Bm F#m C#m Abm Ebm Bbm Fm
E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7 C7 G7 D7 A7 E7 B7 F#7 C#7 Ab7 Eb7 Bb7 F7
FREE BASS
ORCH BASS
Ab3G3 D3 A3 E3 B3 F#3 C#3 Ab3 Eb3 Bb3 F3 C3 G3 D3 A3 B3E3 F#3 C#3
3ベース・ボタン列B
“7 th”=1-3-7
“5 dim”=3-5-7
“7 th”=1-3-7
“5 dim”=3-5-7
FREE BASS
ORCH BASS
Ab3Eb3Bb3
F3
C3G3
D3 A3
E3B3F#3C#3Ab3Eb3Bb3F3C3G3D3A3
E3B3F#3C#3Ab3Eb3Bb3F3C3G3D3A3E3B3F#3C#3Ab3Eb3Bb3F3
EMBMF#MC#MAbMEbMBbMFMCMGMDMAMEMBMF#MC#MAbMEbMBbMFM
EmBmF#mC#mAbmEbmBbmFmCmGmDmAmEmBmF#mC#mAbmEbmBbmFm
E7B7F#7C#7Ab7Eb7Bb7F7C7G7D7A7E7B7F#7C#7Ab7Eb7Bb7F7
Ab3 G3D3A3E3B3F#3C#3Ab3Eb3Bb3F3C3G3D3A3E3B3F#3C#3
3ベース・ボタン列Bx
“7 th”=1-3-7
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ボタン配列 1(ベース&コード・モード)
コード・ボタンについて
ストラデラ・ベース・モードでのボタン配列です。かこまれている
ボタンはベース・ボタン、それ以外のボタンがコード・ボタンにな
ります。コード・ボタンを押すと、上記のコードを演奏します。
84
ベース・ボタンについて
ベースの音域は 1 オクターブです。実際に発音される音域はリード
の種類によって異なります。また、ボタン上の音名は、MIDI ノー
ト・ナンバーに対応しています。
Page 85

ボタン配列 2(フリー・ベース・モード)
FREE BASS
ORCH BASS
Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2
E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2
F#3 Eb3 C3 A2 F#2
F3 D3 B2 Ab2 F2
E3 C#3 Bb2 G2 E2
F#3 Eb3 C3 A2 F#2 Eb2
Minor 3rd
FREE BASS
ORCH BASS
Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2
E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2
D2 F2 Ab2 B2 D3 F3
Eb2 F#2 A2 C3 Eb3 F#3
E2 G2 Bb2 C#3 E3
F2
Ab2 B2 D3 F3
Bajan
FREE BASS
ORCH BASS
Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2
E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2
5th
ORCH BASS
Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#2 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2
E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2
F3 D3 B2 Ab2
F#3 Eb3 C3 A2 F#2
E3 C#3 Bb2 G2 E2
F3 D3 B2 Ab2 F2 D2
N. Europe
(C3=ノート・ナンバー48)
Eb7 C7 A6 C5 A4 F#4 Eb4 C4 A3
D7 B6 Ab6 B4 Ab4 F4 D4 B3 Ab3
C#7 Bb6 G6 Bb4 G4 E4 C#4 Bb3 G3
C7
A6 F#6 A4 F#4 Eb4 C4 A3
F#6 Eb6 C6 A5 F#5 Eb5
F6 D6 B5 Ab5 F5 D5
E6 C#6 Bb5 G5 E5 C#5
Eb6 C6 A5 F#5 Eb5 C5
D5 F5 Ab5 B5 D6 F6 Ab6 B6
Eb5 F#5 A5 C6 Eb6 F#6 A6 C7
E5 G5 Bb5 C#6 E6 G6 Bb6 C#7
F5 Ab5 B5 D6 F6 Ab6 B6 D7
Ab3 B3 D4 F4 Ab4 B4
A3 C4 Eb4 F#4 A4 C5
G3 Bb3 C#4 E4 G4 Bb4 C#5
Ab3 B3 D4 F4 Ab4 B4 D5
Ab4 Eb4 Bb4 F4 C4 G4 D4 A4 E4 B4 F#4 C#4 Ab4 Eb4 Bb4 F4 C4 G4 D4 A4
E4 B4 F#4 C#4 Ab4 Eb4 Bb4 F4 C4 G4 D4 A4 E4 B4 F#4 C#4 Ab4 Eb4 Bb4 F4
Ab5 Eb5 Bb5 F5 C5 G5 D5 A5 E5 B5 F#5 C#5 Ab5 Eb5 Bb5 F5 C5 G5 D5 A5
E5
B5 F#5 C#5 Ab5 Eb5 Bb5 F5 C5 G5 D5 A5 E5 B5 F#5 C#5 Ab5 Eb5 Bb5 F5
Ab3
A3
G3
Ab3
F7 D7 B6 Ab6 F6 D6 B5 Ab5 F5 D5 B4 Ab4 F4 D4 B3
Eb7 C7 A6 F#6 Eb6 C6 A5 F#5 Eb5 C5 A4 F#4 Eb4 C4
C#7 Bb6 G6 E6 C#6 Bb5 G5 E5 C#5 Bb4 G4 E4 C#4 Bb3
B6
Ab6 F6 D6 B5 Ab5 F5 D5 B4 Ab4 F4 D4 B3
ORCH BASS
Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#2 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2
E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2 C3 G2 D3 A2 E2 B2 F#2 C#3 Ab2 Eb2 Bb2 F2
F2
F3 D3 B2 Ab2
E3 C#3 Bb2 G2 E2
Eb3 C3 A2 F#2 Eb2
F3 D3 B2 Ab2 F2 D2
Finnish
Ab3
G3
F#3
Ab3
D7 B6 Ab6 F6 D6 B5 Ab5 F5 D5 B4 Ab4 F4 D4 B3
C#7 Bb6 G6 E6 C#6 Bb5 G5 E5 E#5 Bb4 G4 E4 C#4 Bb3
C7 A6 F#6 Eb6 C6 A5 F#5 Eb5 C5 A4 F#4 Eb4 C4 A3
B6
Ab6 F6 D6 B5 Ab5 F5 D5 B4 Ab4 F4 D4 B3
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
ORCH CHORD
ORCH FREE BSORCH FREE BS
本機の設定をする
85
Page 86

本機の設定をする
ベース・ボタンのハイ側、ロー側について
フリー・ベース・モードでのボタン配列です。黒いボタン(字が白
抜きになっているボタン)がハイ側、白いボタン(字が黒になって
いるボタン)がロー側のボタンになります。
ボタンの配列の選択のしかたについては「10.6 Free Bass Mode
(フリー・ベース・モード)」(P.81)をご覧ください。
10.15 Treble Mode(トレブル・モード)
演奏スタイルに合わせて、トレブル・ボタ
ンへの音階の割り当てかた(配列)を変更
することができます。
TYPE
(タイプ)
各配列について詳しくは、次ページの図をご覧ください。「C」のボ
タンは灰色に塗られています。音名の後ろの数字はオクターブを、
下の数字は対応する MIDI ノート・ナンバーを表しています。
配列を切り替えても、トレブル・ボタンの白(#/b の付かない音)
と黒(#/b の付いた音)の色分けは変わりません。
ボタンの白黒を入れ替えることができます。ボタンのネジをゆるめ
て取り外し、実際に鳴る音に合わせて取り付け直してください。
C-Griff Europe,
C-Griff 2,
B-Griff Bajan,
B-Griff Fin,
D-Griff 1,
D Griff 2
(初期設定値:C-Griff Europe)
本機には予備のボタン(白黒)が付属しています。白色のボタンに
は、表面に突起のあるものと無いものの 2 種類があります。突起の
あるボタンは、一般的に「C」のボタンとして使います。
86
Page 87

ボタン配列 1(トレブル・モード)
C-Giff Europe C-Griff 2 B-Griff Bajan
本機の設定をする
87
Page 88

本機の設定をする
B-Giff Fin D-Griff 1 D-Griff 2
ボタン配列 2(トレブル・モード)
88
Page 89

本機の設定をする
「11 UTILITY」
ユーティリティー設定をする
バッテリー状態のチェック、設定のコピーなどを
します。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
11.1 Battery Status
(バッテリー・ステイタス)
バッテリー(FR-7b のみ付属)の状態を表
示します。ここでは設定を変更するための
パラメーターはありません。
本機への電源供給方法によって、表示される画面が異なります。
この画面は、バッテリーによって本機に電源が供
給されている場合に表示されます。バッテリーの
アイコンはバッテリー残量を示します。
ステージで演奏する前などにこの画面をチェック
すると良いでしょう。
11.2 Copy ALL Effects
(コピー・オール・エフェクト)
3 種類のエフェクトの全設定を、別のセッ
トにコピーします。同じ設定を使う場合
(またはその設定を元に変更を加える場合)
には、各エフェクトの設定をひとつひとつ
変更しなくても済むので非常に便利です。
リバーブ、コーラス、ディレイの各エフェクトの設定だけを別の
セットにコピーすることもできます(P.90)。
設定をコピーすると、コピー先の設定を上書きします。コピー先の
設定が上書きされてよいかどうか確認してください。
1.
[DATA / ENTER]つまみを押すとディスプレイに以下
のように表示されます。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して、コピー元のセット
を選択し、[DATA / ENTER]つまみを押します。
コピー元のセット番号は「FROM」の下に表示されます。
この画面は、バッテリーが FBC-7 を通じて充電さ
れている場合に表示されます。充電中はバッテ
リーのアイコンはすでに充電された量を示しま
す。充電が完了すると、ディスプレイに充電完了
のメッセージがしばらくの間表示されます。
バッテリーの充電のしかたについて詳細は「バッテリーを充電す
る」(P.23) をご覧ください。
この画面は、本機と FBC-7 が接続されていて、
FBC-7 によって電源が供給されているため、
バッテリー・ケース内にあるバッテリーからは電
源供給が行われていない場合に表示されます。
この画面は、本機にバッテリーが入っていない場
合で FBC-7 は接続されている場合に表示されま
す。FR-5b で別売のバッテリーをお使いでない
場合は、この画面だけが表示されます。
3.
[DATA / ENTER]つまみを回して「TO」を選択し、コ
ピー先のセットを選択します。
コピー先のセット番号は「TO」の下に表示されます。
[MENU / WRITE]ボタンを押してコピーを実行します。
4.
コピー中は、ディスプレイに以下の画面が表示されます。
保存中(砂時計表示中)は絶対に電源を切らないでください。故障
の原因になります。
89
Page 90

本機の設定をする
11.3 Copy Reverb(コピー・リバーブ)
11.4 Copy Chorus(コピー・コーラス)
11.5 Copy Delay(コピー・ディレイ)
リバーブ、コーラス、ディレイの各エフェクトの
設定をコピーします。全エフェクトの設定をコ
ピーする「11.2 Copy ALL Effects ( コピー・
オール・エフェクト)」(P.89)と違い、選択し
たひとつのエフェクトの設定だけをコピーしま
す。
設定をコピーすると、コピー先の設定を上書き
します。コピー先の設定が上書きされてよいか
どうか確認してください。
「9.3 Copy Reverb」、「9.4 Copy Chorus」、「9.5 Copy
1.
Delay」のいずれかを選択し、[DATA / ENTER]つま
みを押すとディスプレイに以下のように表示されます
(選択したエフェクトによって異なります)。
11.6 Copy SET(コピー・セット)
セットの設定を別のセットにコピーしま
す。「「9 SET COMMON」セット全体の設定
をする」(P.71)の設定と、そのセットに
含まれる各パートの全音色と設定をコピー
します。
コピー先のセットの設定はすべて上書きされます。保存しておきた
いセットはあらかじめ「本機の設定を外部 MIDI 機器に保存する
(バルク・ダンプ)」(P.104)の機能を使って、外部 MIDI 機器など
に保存しておいてください。
1.
[DATA / ENTER]つまみを押すとディスプレイに以下
のように表示されます。
[DATA / ENTER]つまみを回して、コピー元のセット
2.
を選択し、[DATA / ENTER]つまみを押します。
コピー元のセット番号は「FROM」の下に表示されます。
3.
[DATA / ENTER]つまみを回して「TO」を選択し、コ
ピー先のセットを選択します。
コピー先のセット番号は「TO」の下に表示されます。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回して、コピー元のセット
を選択し、[DATA / ENTER]つまみを押します。
コピー元のセット番号は「FROM」の下に表示されます。
[DATA / ENTER]つまみを回して「TO」を選択し、コ
3.
ピー先のセットを選択します。
コピー先のセット番号は「TO」の下に表示されます。
[MENU / WRITE]ボタンを押してコピーを実行します。
4.
コピー中は、ディスプレイに以下の画面が表示されます。
保存中(砂時計表示中)は絶対に電源を切らないでください。故障
の原因になります。
4.
[MENU / WRITE]ボタンを押してコピーを実行します。
コピー中は、ディスプレイに以下の画面が表示されます。
保存中(砂時計表示中)は絶対に電源を切らないでください。故障
の原因になります。
11.7 Bulk Dump ALL
(バルク・ダンプ・オール)
11.8 Bulk Dump SET
(バルク・ダンプ・セット)
本機の全設定、または現在選択しているセットの設定を外部 MIDI
機器に送信して保存することができます(バルク・ダンプ)。詳し
くは「本機の設定を外部 MIDI 機器に保存する (バルク・ダンプ)」
(P.104)をご覧ください。
90
Page 91

本機の設定をする
11.9 Restore SET(リストア・セット)
工場出荷時のセットのひとつをロードしま
す。
現在のセットの設定は上書きされます。
[DATA / ENTER]つまみを押すとディスプレイに以下
1.
のように表示されます。
2.
[DATA / ENTER]つまみを回してロードする工場出荷
時のセットを選択します。
[MENU / WRITE]ボタンを押してロードを実行します。
3.
ロード中は、ディスプレイに以下の画面が表示されます。
保存中(砂時計表示中)は絶対に電源を切らないでください。故障
の原因になります。
本機全体を工場出荷時の状態に戻すには、「工場出荷時の設定に戻
す」(P.109)をご覧ください。
11.10 Treble Reg. on current Set
(現在のセットのトレブル・レジスター)
現在選ばれているセットの全トレブル・レジスターの 5 種類のパラ
メーター(「Reed」、「Vol」、「Noise」、「Noise Vol」、
「MusDetune」)を同時に設定します。
複数のリードのボリュームを上げ下げする
場合や、異なるノイズ・タイプを選択する
場合にとても便利です。
エディットしたいトレブル・レジ
1.
スターを同時に選択します。
2.
パラメーターを選びます(11.10 現在のセットのトレブ
ル・レジスター)。ジャンプ・メニューから入る方法と
レジスターを使う、2 つの方法があります。詳しくは
「パラメーターを選択する」(P.44)をご覧ください。
3.
[DATA / ENTER]つまみを回して全トレブル・レジス
ターにエディットするパラメーターを選択します。
選択可能なパラメーター
Reed
(リード・タ
イプ)
Volume
(リード・ボ
リューム)
Others
(その他)
この設定には 2 つの動作があります。
a. 初めにどのパラメーター・タイプをエディットするのかを決
めます。
(「Reed」、「Vol」、「Noise」、「Noise Vol」、「MusDetune」)
b. 変更を反映させるリードを選びます。
(「リード」または「ボリューム」のみ)
たとえば、現在のセットの全 5 − 1 / 3' リード(レジスター
毎 1 つ)のボリュームを 10 に設定し、ディスプレイに「Vol 5
− 1 / 3」と表示されるまで[DATA / ENTER]つまみを回
します。そして次のステップに進みます。
Reed ALL(全リード)
Reed 16'(リード 16')
Reed 8'(リード 8')
Reed 8'-(リード 8' −)
Reed 8'+(リード 8' +)
Reed 4'(リード 4')
Reed 5-1/3(リード 5-1/3)
Reed 2-2/3(リード 2-2/3)
Vol ALL(全ボリューム)
Vol 16'(ボリューム 16')
Vol 8'(ボリューム 8')
Vol 8'-(ボリューム 8' −)
Vol 8'+(ボリューム 8' +)
Vol 4'(ボリューム 4')
Vol 5-1/3(ボリューム 5-1/3)
Vol 2-2/3(ボリューム 2-2/3)
Noise(ノイズ)
Noise Vol(ノイズ・ボリューム)
MusDetune(マスター・デチューン)
91
Page 92

本機の設定をする
警告メッセージの意味
「Reed All」か「Vol All」を選んだ場合に以下のような警告が表
示されます。
これはセット内のリードが異なるセッティングを使っているときに
起こります。
「ALL」を実行すると、現在のセットのすべてのレジスターを同じ
値に設定できます。[UP]/[DOWN]ボタンか[DATA /
ENTER]つまみを回し、すべてのリードを同じ設定にする場合は
「YES」を、そうでない場合は「NO」を選択し、[DATA /
ENTER]つまみを押して決定してください。
ここで設定した「Vol」の値は、それぞれのエディット・モードの
ボリューム・パラメーターに作用します。たとえば、ここで 5 を設
定すると、関連するリードのボリュームが 5 に設定されます。
4.
[DATA / ENTER]つまみを押して「VALUE」を選択し、
[DATA / ENTER]つまみを回して設定値を選びます。
設定できる内容は手順 3 で選択した値により異なりま
す。
パラメーター 設定値
Reed
(リード)
Vol
(ボリューム)
Noise
(ノイズ)
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
OldItaly(オールドイタリー)
TexMex(テックスメックス)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
OldItaly(オールドイタリー)
TexMex(テックスメックス)
Trikitixa(トリキティシャ)
Noise Vol
(ノイズ・ボ
リューム)
Detune
(デチューン)
現在オフになっているリードの設定(「2.2 Register(レジスター)」
(P.50))にも反映されます。ただし、この操作によってオンにはな
りません。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻って、
5.
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40
Off(オフ)
Dry(ドライ)
Classic(クラシック)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
AmericanL(アメリカン L)
AmericanH(アメリカン H)
NorthEur(ノースヨーロッパ)
GermanL(ジャーマン L)
D-FolkL(ジャーマン・フォーク L)
ItalianL(イタリアン L)
GermanH(ジャーマン H)
Alpine(アルペン)
ItalianH(イタリアン H)
D-FolkH(ジャーマン・フォーク H)
French(フレンチ)
Scottish(スコティッシュ)
トレブル・レジスターの変更内容を確認することができ
ます。
ここでセットを変更すると、設定した内容が消えてしまいますので
ご注意ください。
6.
この設定でよければ、この設定を保存します。
•
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
•
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタンで
•
[ALL]を選択します。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
•
ディスプレイに次のような画面が表示されます。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタンで変更
•
を保存する先のセットを選びます。変更した設定を現在のセッ
トに保存したくない場合のみ、ここの値を変更します。
92
Page 93

•
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を保存します。
ディスプレイに次のような画面がしばらくの間表示されます。
[EXIT / JUMP]を押してメイン画面に戻ります。
•
11.11 Bass Reg. on current Set
(現在のセットのベース・レジスター)
現在選ばれているセットの全ベース・レジ
スターの 6 種類のパラメーターを同時に設
定します。
この機能は、複数のリードのボリュームを
上げ下げする場合や、異なるノイズ・タイ
プを選ぶ場合にとても便利です。
エディットしたいベース・レジスターを同時に選びま
1.
す。
パラメーター(11.11 現在のセットのベース・レジス
2.
ター)を選びます。
ジャンプ・メニューから入る方法とレジスターを使う、
2 つの方法があります。詳しくは「パラメーターを選択
する」(P.44)をご覧ください。
3.
[DATA / ENTER]つまみを回して全ベース・レジス
ターでエディットするパラメーターを選択します。
パラメーター 設定値
Reed
(リード・タ
イプ)
Vol
(リード・ボ
リューム)
Others
(その他)
この設定には 2 つのステップがあります。
a. 初めにどのパラメーター・タイプをエディットするのかを決
めます。
(「Reed」または「Vol」、「Noise」、「Noise Vol」、「Reed
Growl」、「Growl Vol」)
b. 変更を反映させるリードを選びます。
(「Reed または「Vol」のみ)
たとえば、現在のセットの各レジスターの、全 16' リードの
リード・タイプを変更したい場合、ディスプレイに「Reed
16'」と表示されるまで[DATA / ENTER]つまみを回し、次
のステップに進みます。
Reed ALL(全リード)
Reed 16'(リード 16')
Reed 8'(リード 8')
Reed 8'-4'(リード 8'-4')
Reed 4'(リード 4')
Reed 2'(リード 2')
Vol ALL(全ボリューム)
Vol 16'(ボリューム 16')
Vol 8'(ボリューム 8')
Vol 8'-4'(ボリューム 8'-4')
Vol 4'(ボリューム 4')
Vol 2'(ボリューム 2')
Noise(ノイズ)
Noise Vol(ノイズ・ボリューム)
Reed Growl(ノイズ・グロウ)
Growl Vol( グロウ・ボリューム)
本機の設定をする
「警告メッセージの意味」については P.92 を参照してください。
DATA / ENTER]つまみを押して「VALUE」を選択し、
4.
[DATA / ENTER]つまみを回して設定値を選びます。
設定できる内容は 3 で選択した値により異なります。
パラメーター 設定値
Reed
(リード)
Vol
(ボリューム)
Noise
(ノイズ)
Noise Vol
(ノイズ・ボ
リューム)
Reed Growl
(リード・グ
ロウ)
Growl Vol
(グロウ・ボ
リューム)
現在オフになっているリードの設定(「3.2 Register(レジスター)」
(P.57))にも反映されますが、この操作によってオンにはなりませ
ん。
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
93
Page 94

本機の設定をする
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻って、
5.
ベース・レジスターの変更内容を確認することができま
す。
ここでセットを変更すると、設定した内容が消えてしまいますので
ご注意ください。
6.
この設定でよければ、この設定を保存します。
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
•
WRITE]ボタンを押し続けます。
•
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]ボタン
で[Bass]を選択します。
•
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタンで
•
[ALL]を選択します。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
•
ディスプレイに以下の画面が表示されます。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタンで変更
•
を保存する先のセットを選びます。変更した設定を現在のセッ
トに保存したくない場合のみ、ここの値を変更します。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を保存します。
•
ディスプレイに以下の画面がしばらくの間表示されます。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
•
94
Page 95

本機の設定をする
11.12 FreeBass Reg. on current Set
(現在のセットのフリーベース・レジス
ター)
これはパラメーターというよりは環境その
ものです。現在選ばれているセットの全フ
リー・ベース・レジスターの 6 種類のパラ
メーターを同時に設定します。これは「現
在のセットのベース・レジスター」パラ
メーターと、リードの数が少ないことを除いて非常に似ています。
以下がこの環境の使い方です。
同時にエディットしたいフリー・ベース・レジスターを
1.
選びます
2.
このパラメーター(11.12 現在のセットのフリーベー
ス・レジスター)を選びます。
ジャンプ・メニューから入る方法とレジスターを使う、
2 つの方法があります。詳しくは「パラメーターを選択
する」(P.44)をご覧ください。
3.
[DATA / ENTER]つまみを回して全フリー・ベース・
レジスターでエディットするパラメーターを選択しま
す。
選択可能なパラメーター
Reed
(リード・タ
イプ)
Volume
(リード・ボ
リューム)
Others
(その他)
このステップには 2 つの動作が含まれます。
a. 初めにどのパラメーター・タイプをエディットするのかを決
めます。(「Reed」または「Vol」、「Noise」、「Noise Vol」、
「Reed Growl」、「Growl Vol」)
b. 変更を反映させるリードを選びます。(「Reed」または
「Vol」のみ)
たとえば、現在のセットの各レジスターの、全 16' リードの
リード・タイプを変更したい場合、ディスプレイに「Reed
16'」と表示されるまで[DATA / ENTER]つまみを回し、次
のステップに進みます。
「警告メッセージの意味」については P.92 を参照してください。
[DATA / ENTER]つまみを押して「VALUE」を選択し、
4.
[DATA / ENTER]つまみを回して設定値を選びます。
設定できる内容は 3 で選択した値により異なります。
Reed ALL(全リード)
Reed 16'(リード 16')
Reed 8'(リード 8')
Vol ALL(全ボリューム)
Vol 16'(ボリューム 16')
Vol 8'(ボリューム 8')
Noise(ノイズ)
Noise Vol(ノイズ・ボリューム)
Reed Growl(ノイズ・グロウ)
Growl Vol(グロウ・ボリューム)
パラメーター 設定値
Reed
(リード)
Vol
(ボリューム)
Noise
(ノイズ)
Noise Vol
(ノイズ・ボ
リューム)
Reed Growl
(リード・グ
ロウ)
Growl Vol
(グロウ・ボ
リューム)
現在オフになっているリードの設定(「2.2 Register(レジスター)」
(P.50))にも反映されます。ただし、この操作によってオンにはな
りません。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻って、フ
5.
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
Bandneon(バンドネオン)
I-Folk(イタリアン・フォーク)
I-Folk2(イタリアン・フォーク 2)
Classic(クラシック)
Cajun(ケージャン)
Jazz(ジャズ)
F-Folk(フレンチ・フォーク)
D-Folk(ジャーマン・フォーク)
Organetto(オルガネット)
F-Folk2(フレンチ・フォーク 2)
Classic2(クラシック 2)
Studio(スタジオ)
Tradition(トラディション)
Steierische(ステイリッシュ)
Trikitixa(トリキティシャ)
Off(オフ)
-40 〜 Std 〜 40
(-40 〜スタンダード〜 40)
リー・ベース・レジスターの変更内容を確認することがで
きます。
変更した設定が消えてしまうため、ここでセットを変更しないでく
ださい。
95
Page 96

本機の設定をする
この設定でよければ、この設定を保存します。
6.
•
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
WRITE]ボタンを押し続けます。
•
[DATA / ENTER]つまみを回すか[UP]/[DOWN]ボタン
で[Free Bass]を選択します。
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
•
•
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタンで
[ALL]を選択します。
•
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
ディスプレイに以下の画面が表示されます。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタンで変更
•
を保存する先のセットを選びます。変更した設定を現在のセッ
トに保存したくない場合のみ、ここの値を変更します。
[MENU/WRITE]ボタンを押して変更の内容を保存します。
•
ディスプレイに以下の画面が表示されます。
•
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
96
Page 97

本機の設定をする
「12 MIDI」
MIDI 設定をする
本機は MIDI 対応で、外部 MIDI 機器をコントロールすることができ
ます。音源モジュールなどを MIDI 接続すれば、本機から音源モ
ジュールを鳴らすことができ、アレンジャー機能付きの音源モ
ジュールを接続すれば、再生の開始/停止やイントロ機能などをコ
ントロールすることができます。また、本機の設定を外部 MIDI 機
器に保存することもできます。
MIDI 機能を使うには、本機と FBC-7 との接続が必要です(P.17)。
MIDI コネクターは FBC-7にありますので、外部 MIDI 機器は FBC-
7 と MIDI 接続してください(P.98)。
以下のような使いかたができます
自動伴奏といっしょに演奏する
1.
アレンジャー機能(自動伴奏機能)対応の音源モジュールを
MIDI 接続すると、本機でアレンジャー機能をコントロールす
ることができます。本機でコードを押さえることによって、自
動伴奏をすることができ、フット・スイッチ(FBC-7)で自動
伴奏の開始/停止やフィルインなどの機能を操作することがで
きます。
シーケンサーを鳴らしながら演奏する
2.
MIDI シーケンサーなどを MIDI 接続すればフット・スイッチ
(FBC-7)でシーケンサーの再生 / 停 止をコントロールするこ
とができます。
3.
他の音源を鳴らす
MIDI 対応音源モジュールを MIDI 接続すると、本機で音源モ
ジュールを鳴らすことができます。本機にはない音色で演奏す
ることができます。
4.
本機の設定を保存する
コンピューターやシーケンサーなどを MIDI 接続すると、本機
の設定を送信して保存することができます(バルク・ダンプ)。
フット・スイッチによるコントロールについては「10.4 Pedal
Controller (ペダル・コントローラー)」(P.79)をご覧下さい。
MIDI について
MIDI とは、MIDI メッセージを MIDI ケーブル経由で送受信すること
によって、MIDI 対応機器をコントロールすることができる規格で
す。ここでは MIDI についての説明をします。
MIDI で使用するコネクター
•
MIDI IN コネクター
他の MIDI 機器からの MIDI メッセージを受信します。
•
MIDI OUT コネクター
本機から MIDI メッセージを送信します。
•
MIDI THRU コネクター
MIDI IN コネクターから受信した MIDI メッセージをそのまま送信
します。
本機からの MIDI メッセージは MIDI THRU コネクターからは送信
されません。MIDI OUT コネクターからのみ送信されます。
MIDI チャンネルについて
MIDI では同時に 16 チャンネル(16 種類)の MIDI メッセージを送
受信することができますので、16 個の楽器(音色)をコントロー
ルすることができます。ほとんどの音源モジュールは、違う音色を
たくさんのパートで演奏できるマルチ・ティンバー機能に対応して
いますので、同時にいろいろな音色を鳴らして演奏することができ
ます。
本機では「トレブル・パート」、「ストラデラ・ベース・モードの
ベース・ボタンで演奏するパートまたはフリー・ベース・モード」、
「ストラデラ・ベース・モードのコード・ボタンで演奏するパー
ト」、「オーケストラ・パート」、「オーケストラ・ベース・パート」、
「オーケストラ・コート・パート」、「オーケストラ・フリー・ベー
ス・パート」で、それぞれ違う MIDI チャンネルのメッセージを送
信できますので、それぞれのパートで違う音色を演奏することがで
きます。セットの切り替えには「ベーシック・チャンネル」を使用
します。
たとえば、トレブル・ボタンでピアノの音色、ベース・ボタンで
ウッド・ベースの音色、コード・ボタンでオルガンの音色といった
ような演奏をすることができます。
本機のそれぞれのパートで送受信される MIDI チャンネルは以下の
通りです(初期設定)。
パート チャンネル
トレブル・パート 1
ストラデラ・ベース・モードのベース・ボタンで
演奏するパートまたはフリー・ベース・モード
ストラデラ・ベース・モードのコード・ボタンで
演奏するパート
オーケストラ・パート 4
オーケストラ・ベース・パート 5
オーケストラ・コード・パート 6
オーケストラ・フリー・ベース・パート 7
ベーシック・チャンネル(セット) 13
コントロール・チャンネル(送信のみ) 13
上記の MIDI チャンネル番号は初期設定です。お好みの MIDI チャン
ネルに設定することもできます(P.99)。
2
3
97
Page 98

本機の設定をする
MIDI 接続をする
MIDI コネクターは FBC-7 にあります。MIDI 接続をする前に、本機と FBC-7 を接続します(P.17)。
外部 MIDI 機器を FBC-7 の MIDI コネクターに接続してください。
外部機器の MIDI IN コネクターを本機の MIDI OUT コネクター、外部機器の MIDI OUT コネクターを本機の MIDI IN コネクターに MIDI ケーブル
を使って接続します。
外部 MIDI機器
MIDI OUT MIDI IN
MIDI IN MIDI OUT
MIDI の使用例
音源モジュールを使う
外部音源モジュールを接続して、本機といっしょに演奏するときなどは、
以下のように接続します。
本機をマスター・キーボードとして使う
シーケンサーなどと接続して、本機を MID 入力用マスター・キーボード
として使う場合は、以下のように接続します。
外部 MIDI 機器
MIDI IN MIDI OUT
本機の内蔵音源
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI OUT
FBC-7
外部 MIDI 機器
FBC-7
MIDI IN
シーケンサー
MIDI OUT
本機の内蔵音源
98
Page 99

本機の MIDI 設定をする
本機から送受信する MIDI メッセージのチャンネルや、シーケン
サーなどと同時に演奏する場合の MIDI メッセージの出力設定をし
ます。
ここでのパラメーターの設定は本機全体に適用されます。セットご
とで保存することはできません。
パラメーターの選択、変更の方法については「設定のしかた」
(P.44)をご覧ください。
各パートの音色の設定は『「2 TREBLE EDIT」トレブル・パートの
音色の設定をする』(P.48)、『「3 BASS EDIT」ベース・パート(ス
トラデラ・ベース・モード)の音色の設定をする』(P.55)、『「4
FREE BS EDIT」ベース・パート(フリー・ベース・モード)の音
色の設定をする』(P.59)、『「5 ORC.BASS EDIT」オーケストラ・
ベース・パートの音色の設定をする』(P.63)、『「6 ORCH. EDIT」
オーケストラ・パートの音色の設定をする』(P.65)、『「7 ORC
CHD EDIT」オーケストラ・コード・パート音色の設定をする』
(P.67)、『「8 ORC FBS EDIT」オーケストラ・フリー・ベース・
パート音色の設定をする』(P.69)をご覧ください。
[UP]ボタンと[DOWN]ボタンを同時に押すと、選択したパラ
メーターが初期設定に戻ります。
変更した設定を保存する
ディスプレイに以下の画面が表示されるまで[MENU /
1.
WRITE]ボタンを押し続けます。
[DATA / ENTER]つまみか[UP]/[DOWN]ボタン
2.
を押して「Global」を選びます。
本機の設定をする
「MENU / WRITE」ボタンを押して変更した内容を保存
4.
します。ディスプレイに以下の保存完了メッセージ画面
がしばらくの間表示されます。
[EXIT / JUMP]ボタンを押してメイン画面に戻ります。
5.
本機から送受信する MIDI メッセージの設
定をする(12.1 RealTime RX-TX)
本機の各パートで送受信する MIDI チャンネ
ルの設定をします。
以下のパートごとに設定することができま
す。
•
トレブル・パート
•
ストラデラ・ベース・モードのベース・ボタンで演奏するパート
またはフリー・ベース・モード
•
ストラデラ・ベース・モードのコード・ボタンで演奏するパート
•
オーケストラ・パート
•
オーケストラ・ベース・パート
オーケストラ・コード・パート
•
オーケストラ・フリー・ベース・パート
•
ベーシック・チャンネル(セット)
•
外部 MIDI 音源モジュールの MIDI 設定をすることによって、トレブ
ル・ボタンでピアノの音色、ベース・ボタンでウッド・ベースの音
色、コード・ボタンでオルガンの音色といったような演奏をするこ
とができます。
また、受信チャンネルも設定されますので、外部シーケンサーなど
を使って、本機の各パートをそれぞれ独立して鳴らすことができま
す。
初期設定は P.97 の表をご覧ください。
GM(General MIDI)対応の音源モジュールなどは、あらかじめ各
MIDI チャンネルに役割が割り当てられています。たとえば MIDI
チャンネルの 4 にはメロディーが割り当てられていますので、トレ
ブル・パートの MIDI チャンネルを 4 に変更して演奏をするという
ように、設定を変えるとよいでしょう。
3.
[DATA / ENTER]つまみを押して設定を確認します。
グローバル画面には、グローバル・メモリーに保存されるすべての
パラメーターが表示されます。1 セットのみ保存できます。
各パートで同じ MIDI チャンネルを設定することもできますが、各
パート(たとえばトレブル・パートとオーケストラ・パート)で同
じチャンネルの音色を演奏することになります。演奏中、不具合が
生じるようでしたら、どちらかのパートの MIDI チャンネルを変え
てください。
デュアル、ハイ、ローの各オーケストラ・モード(P.32)では、ト
レブル・ボタンで演奏すると、トレブル・パートとオーケストラ・
パートで設定した各 MIDI チャンネルを同時に送信します。また同
じようにベース・セクションで演奏すると、ベース・パートとオー
ケストラ・ベース・パートで設定した各 MIDI チャンネルを同時に
送信します。
99
Page 100

本機の設定をする
「PART」で MIDI メッセージを送信するパートを選択して、
「CHANNEL」で MIDI チャンネルを選択します。
PART
(パート)
CHANNEL
(チャンネル)
「CHANNEL」で「Off」を選択すると、そのパートは MIDI メッセー
ジの送受信をしません。
Treble トレブル・パート
Bass/Free ストラデラ・ ベース・モー
ドのベース・ボタンで演奏
するパートまたはフリー・
ベース・モード
Chord ストラデラ・ ベース・モー
ドのコード・ボタンで演奏
するパート
OrchBass オーケストラ・ベース・
パート
Orchestra オーケストラ・ パート
Orc Chord オーケストラ・コード・
パート
Orc Free
Bs
Basic Ch ベーシック・チャンネル
Control Ch コントロール・チャンネル
Off、1 〜 16
オーケストラ・フリー・
ベース・パート
(セット)
(送信のみ)
ず、MIDI メッセージも送信されなくなります。
•
「Bass-Chord」には、オーケストラ・コード・パート、オーケス
トラ・フリー・ベース・パートも含まれます。
•
[ORCHESTRA/MODE]ボタンを押しながら、[1]レジスター・
ボタンを押すと ALL のオン/オフを切り替えることができます。
「ON」に設定したパートは、メイン画面で以下のように表示されま
す(パート表示の右側に「EXT MIDI」が表示されます)。
蛇腹操作の MIDI 設定をする
(12.3 Bellows TX Resolution)
本機は蛇腹の操作も MIDI メッセージとして送信
します(エクスプレッション・メッセージ
(P.103)として送信します)。各パート同時に送
信しますので、送信メッセージの量が多くなり、
受信側の機器や設定によっては、うまく MIDI メッセージを受信で
きないときがあります。この場合、蛇腹操作による MIDI メッセー
ジの量を調節することができます。
ここでの設定は MIDI 受信には影響しません。
シーケンサーや外部 MIDI 機器を使って演
奏する(12.2 Ext. Seq. Playback)
MIDI 受信でのみ演奏することができるようにな
ります(本体で演奏しても、発音、MIDI 送信さ
れません)。
以下のパートごとに設定することができます。
•
トレブル・パート
•
ベース・セクションで演奏するパート
•
オーケストラ・パート
シーケンサーと同時に演奏していて、シーケンサーの演奏と本機の
演奏がかぶってしまうときなどに、演奏したくないパートをオフに
することができます。オフにしたパートは本機で演奏しても出力さ
れず、また MIDI メッセージも送信しません。受信はしますので、
シーケンサーから MIDI メッセージを受信して本機を再生すること
はできます。
「PART」でパートを選択して、「VALUE」でオン/オフを選択しま
す。
PART
(パート)
VALUE
(バリュー)
Treble トレブル・パート
Bass-Chord ベース・セクションで演
奏するパート
Orchestra オーケストラ・パート
ALL すべてのパート
ON MIDI 受信でのみ演奏でき
ます。本体で演奏しても、
発音、MIDI 送信されませ
ん。
Off 本体でのみ演奏できます
(MIDI 送信されます)。
VALUE
(バリュー)
「Medium」は初期設定です。外部 MIDI 機器がうまく受信できない
場合は「Low」に設定します(「Low」では、送信メッセージの量
が一番少なくなります)。
「High」では MIDI 送信メッセージの量は多くなりますが、表現の幅
は広くなります。
High
Medium
Low
「VALUE」で「ON」を選択すると、そのパートの演奏は出力され
100
 Loading...
Loading...