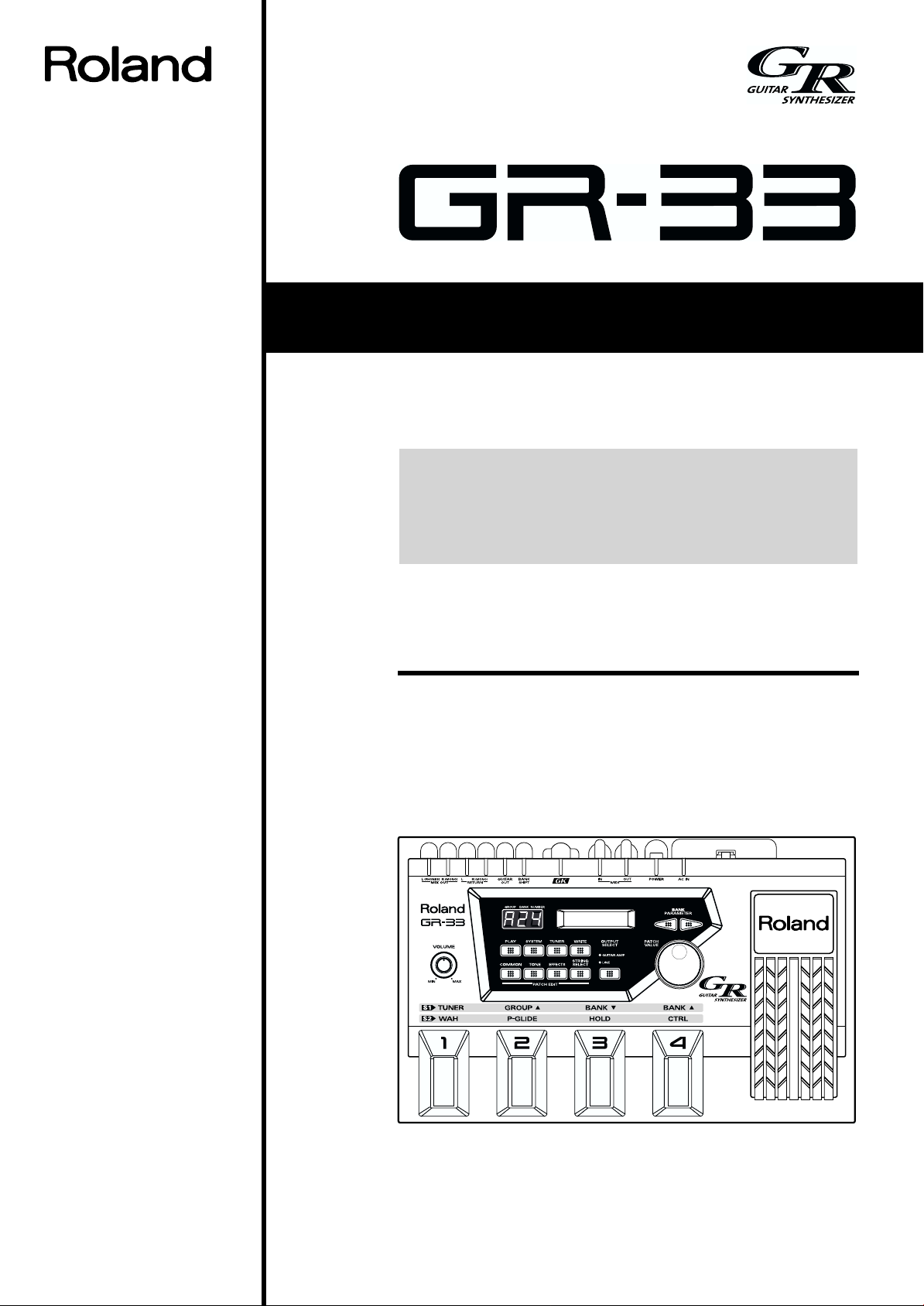
取扱説明書
このたびは、ローランド・ギター・シンセサイザー GR-33をお買
い上げいただきまして、ありがとうございます。
この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に
・ 安全上のご注意(P.2 〜 3)
・ 使用上のご注意(P.9)
をよくお読みください。
また、この機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、この
取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は必要なときにすぐ
に見ることができるよう、手元に置いてください。
2000 ©ローランド株式会社
本書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
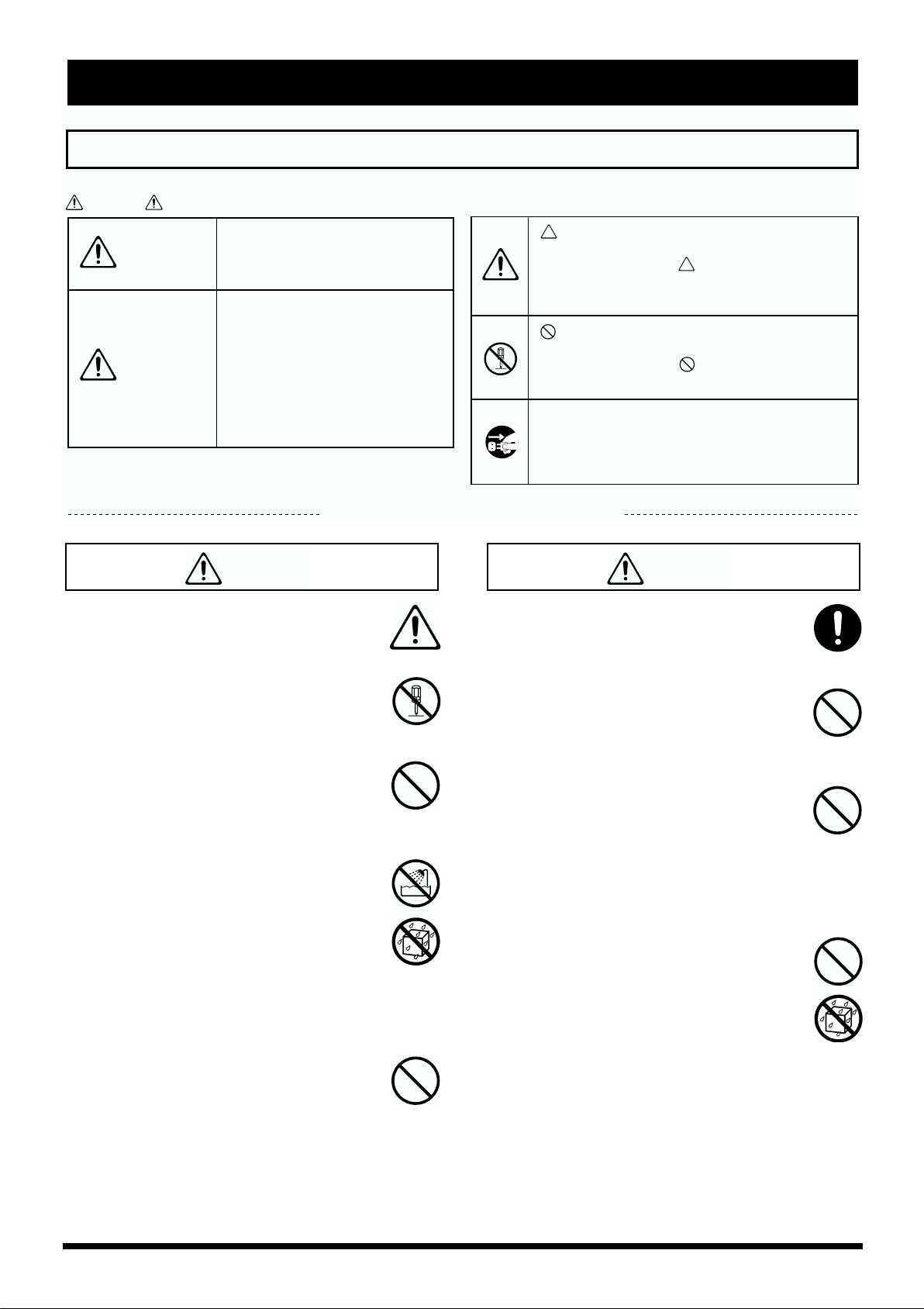
安全上のご注意
安全上のご注意
火災・感電・傷害を防止するには
注意の意味について警告と
取扱いを誤った場合に、使用者が
警告
注意
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。
※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。
以下の指示を必ず守ってください
警告 警告
001
● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説
明書をよく読んでください。
図記号の例
は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。
は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。
●は、強制(必ずすること)を表わしています。
具体的な強制内容は、●の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。
008c
● AC アダプターは、必ず付属のものを、AC 100
Vの電源で使用してください。
..............................................................................................................
002c
● この機器および AC アダプターを分解したり、改
造したりしないでください。
..............................................................................................................
003
● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれ
ていないことは、絶対にしないでください。必
ずお買い上げ店またはローランド・サービスに
相談してください。
..............................................................................................................
004
● 次のような場所での使用や保存はしないでくだ
さい。
○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場
所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)
や湿度の高い場所
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
..............................................................................................................
007
● この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に
設置しないでください。必ず安定した水平な場
所に設置してください。
..............................................................................................................
..............................................................................................................
009
● 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上
に重いものを載せたりしないでください。電源
コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火
災や感電の恐れがあります。
..............................................................................................................
010
● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アン
プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設
定によっては永久的な難聴になる程度の音量に
なります。大音量で、長時間使用しないでくだ
さい。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直
ちに使用をやめて専門の医師に相談してくださ
い。
..............................................................................................................
011
● この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針
金など)や液体(水、ジュースなど)を絶対に
入れないでください。
..............................................................................................................
2
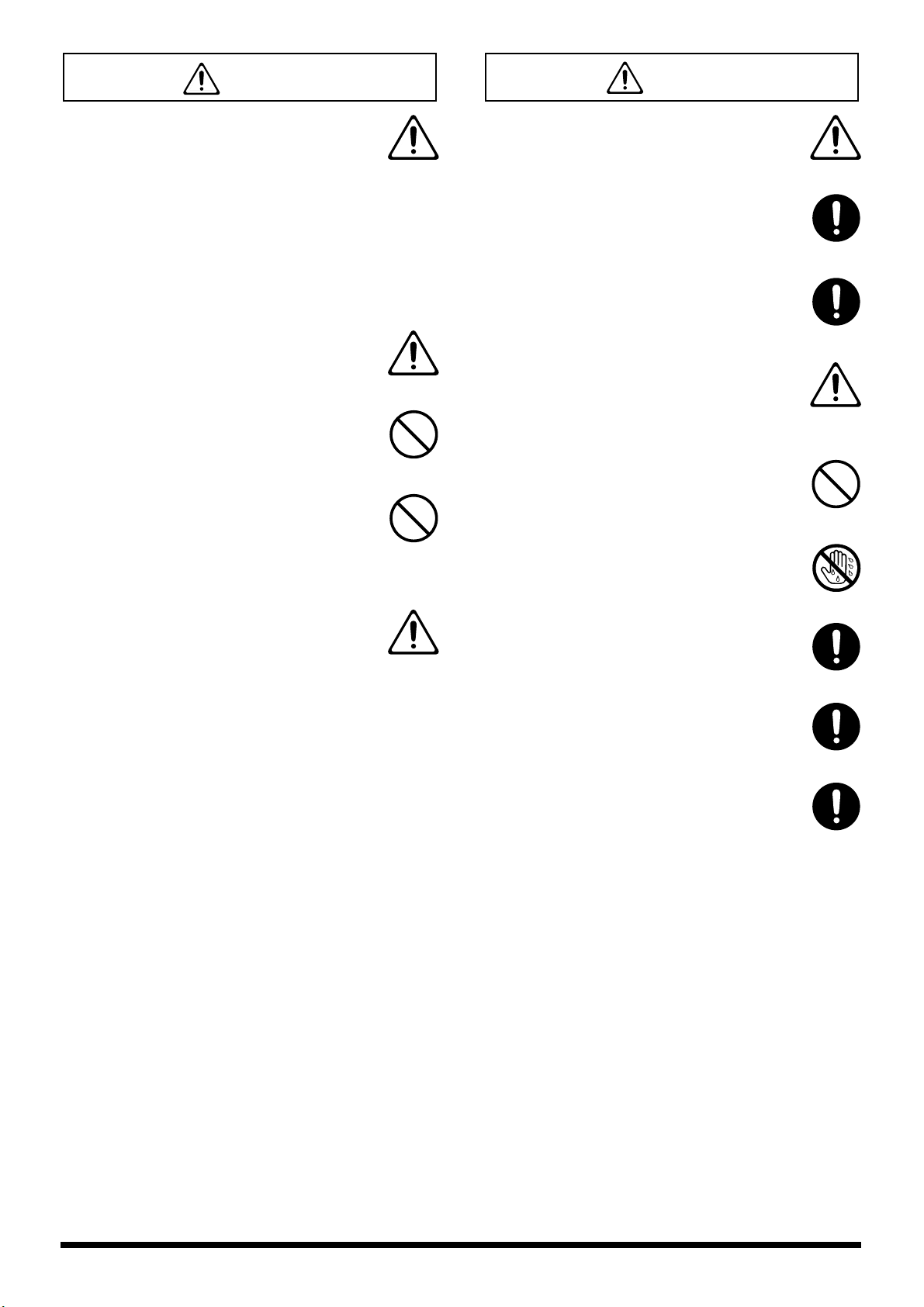
警告
注意
012b
● 次のような場合は、直ちに電源を切って AC ア
ダプターをコン セントか ら外し、お買い上げ店
またはローラン ド・サービス に修理を依頼して
ください。
○ AC アダプター本体、電源コード、またはプ
ラグが破損したとき
○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし
たとき
○ 機器が(雨などで)濡れたとき
○ 機器に異常や故障が生じたとき
..............................................................................................................
013
● お子様のいるご 家庭で使 用する場合、お子様の
取り扱いやいた ずらに注 意してください。必ず
大人のかたが、監視/指導してあげてください。
..............................................................................................................
014
● この機器を落と したり、この 機器に強い衝撃を
与えないでください。
..............................................................................................................
015
● 電源は、タコ足配線 などの無 理な配線をしない
でください。特に、電 源タップ を使用している
場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を
超えると発熱し、コ ードの被 覆が溶けることが
あります。
..............................................................................................................
016
● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または
ローランド・サービスに相談してください。
..............................................................................................................
101b
● この機器と AC アダプターは、風通しのよい、正
常な通気が保 たれている 場所に設置して、使用
してください。
..............................................................................................................
102c
●
AC アダプターを機器本体やコンセントに抜き差
しするときは、必ずプラグを持ってください。
..............................................................................................................
103b
● 長時間使用しないときは、AC アダプターをコン
セントから外してください。
..............................................................................................................
104
● 接続したコー ドやケーブ ル類は、繁雑にならな
いように配慮してください。特に、コードやケー
ブル類は、お子様 の手が届か ないように配慮し
てください。
..............................................................................................................
106
● この機器の上 に乗ったり、機 器の上に重いもの
を置かないでください。
..............................................................................................................
107c
● 濡れた手で AC アダプターのプラグを持って、機
器本体やコンセ ントに抜き 差ししないでくださ
い。
..............................................................................................................
108b
● この機器を移動するときは、AC アダプターをコ
ンセントから 外し、外部機器 との接続を外して
ください。
..............................................................................................................
109b
● お手入れをするときには、電源を切って AC ア
ダプターをコ ンセントか ら外してください
(P.12)。
..............................................................................................................
110b
● 落雷の恐れがあるときは、早めに AC アダプター
をコンセントから外してください。
..............................................................................................................
3

目次
はじめに....................................................................................................8
ギター・シンセサイザーのしくみ ........................................................................................ 8
GR-33 でできること(主なもの).......................................................................................... 8
使用上のご注意 .........................................................................................9
各部の名称と働き ...................................................................................10
第 1 章 音を出す...................................................................................13
用意するもの....................................................................................................................... 13
GK-2A の取り付け ............................................................................................................................13
接続のしかた....................................................................................................................... 14
電源オン〜演奏前に必要なこと ..........................................................................................15
「プレイ・モード」とは?...............................................................................................................15
工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)........................................................ 16
全体に関わる設定をする(SYSTEM).................................................................................17
画面の明るさを調節する(LCD コントラスト)........................................................................17
入力感度を設定する(PICKUP SENS).......................................................................................17
他の楽器にピッチを合わせる.........................................................................................................18
ギターのチューニングをする(チューナー機能)......................................................................18
出力する機器を設定する(OUTPUT SELECT)..................................................................19
ギター・アンプ・シミュレーターを OFF にする(G.AMP SIM).........................................19
ギターを弾いてシンセ音を鳴らす ...................................................................................... 20
音が出ない場合は............................................................................................................. 20
第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する ....................................21
パッチとは?....................................................................................................................... 21
書き替え可能なパッチ(ユーザー・パッチ)..............................................................................21
読み出し専用のパッチ(プリセット・パッチ)..........................................................................21
パッチを選ぶ....................................................................................................................... 21
ギター(GK-2A)側で選ぶ ............................................................................................................21
本体の操作で選ぶ..............................................................................................................................22
本体とフット・スイッチの操作で選ぶ ........................................................................................23
外部 MIDI フット・コントローラーで選ぶ..................................................................................24
パッチの並び順を変える..................................................................................................... 25
第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す........................................26
「ペダル効果モード」とその呼び出しかた.......................................................................... 26
プレイ・モードのまま同じ効果を得るには................................................................................26
MULTI-FX、アルペジエーター/ハーモニストをオン/オフする ..................................... 27
本体のペダルで音を変化させる ..........................................................................................28
ペダル・ワウのような効果を得る(ワウ)..................................................................................28
4

音高をダイナミックに変化させる(ピッチ・グライド).........................................................28
弦が止まってもシンセ音を保持させる(ホールド).................................................................28
チューナー機能をペダルで呼び出す................................................................................... 29
第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作........................................30
プレイ・モードでの操作..................................................................................................... 30
ペダル効果モードでの操作 ................................................................................................. 31
パッチ・エディット・モードの意味とその操作 .................................................................32
システム・モードでの操作 ................................................................................................. 33
チューナー・モードでの操作.............................................................................................. 33
各モード間の行き来のしかた.............................................................................................. 34
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する ...........................................35
パッチの詳しい構成 ............................................................................................................35
「トーン」とは?................................................................................................................................35
パッチごとに記憶できるその他の設定 ........................................................................................35
弦ごとに異なる設定を行う(STRING SELECT).....................................................................35
アルペジエーター/ハーモニストとパッチの関係 ...................................................................36
目次
パッチの保存のしかた ........................................................................................................36
保存に関する注意事項 .....................................................................................................................36
本体のパッチをシーケンサーなどに保存する(バルク・ダンプ)........................................37
保存したシステムやパッチのデータを受信する(バルク・ロード)....................................37
パッチに名前をつける(PATCH NAME)........................................................................... 38
パッチごとに音量を記憶させる(PATCH LEVEL)............................................................. 38
演奏感を変える(PLAY FEEL)........................................................................................... 39
エンベロープ・フォロー機能について ........................................................................................40
発音速度をさらにアップするには(アクセル機能)........................................................... 40
音の定位を変える(PAN)................................................................................................... 41
連続的な音高変化を半音刻みにする(CHROMATIC)........................................................ 42
和音を美しく響かせたい場合.........................................................................................................42
ピアノなどの音高変化を再現する場合 ........................................................................................42
ワウの効き方を選ぶ(WAH TYPE).................................................................................... 43
ピッチ・グライドの効き方を選ぶ(GLIDE TYPE)............................................................ 44
ホールドの効き方を選ぶ(HOLD TYPE)........................................................................... 45
CTRL ペダルを使う............................................................................................................. 46
エクスプレッション・ペダルを使う................................................................................... 47
効果をかけるには..............................................................................................................................47
効果を選ぶには(EXP PEDAL)....................................................................................................47
シンセ音を加工する ............................................................................................................49
素材になる音(トーン)を選ぶ(SELECT)..............................................................................49
音の立ち上がりを遅く/速くする(ATTACK).........................................................................49
余韻の長さを変える(RELEASE)................................................................................................50
5
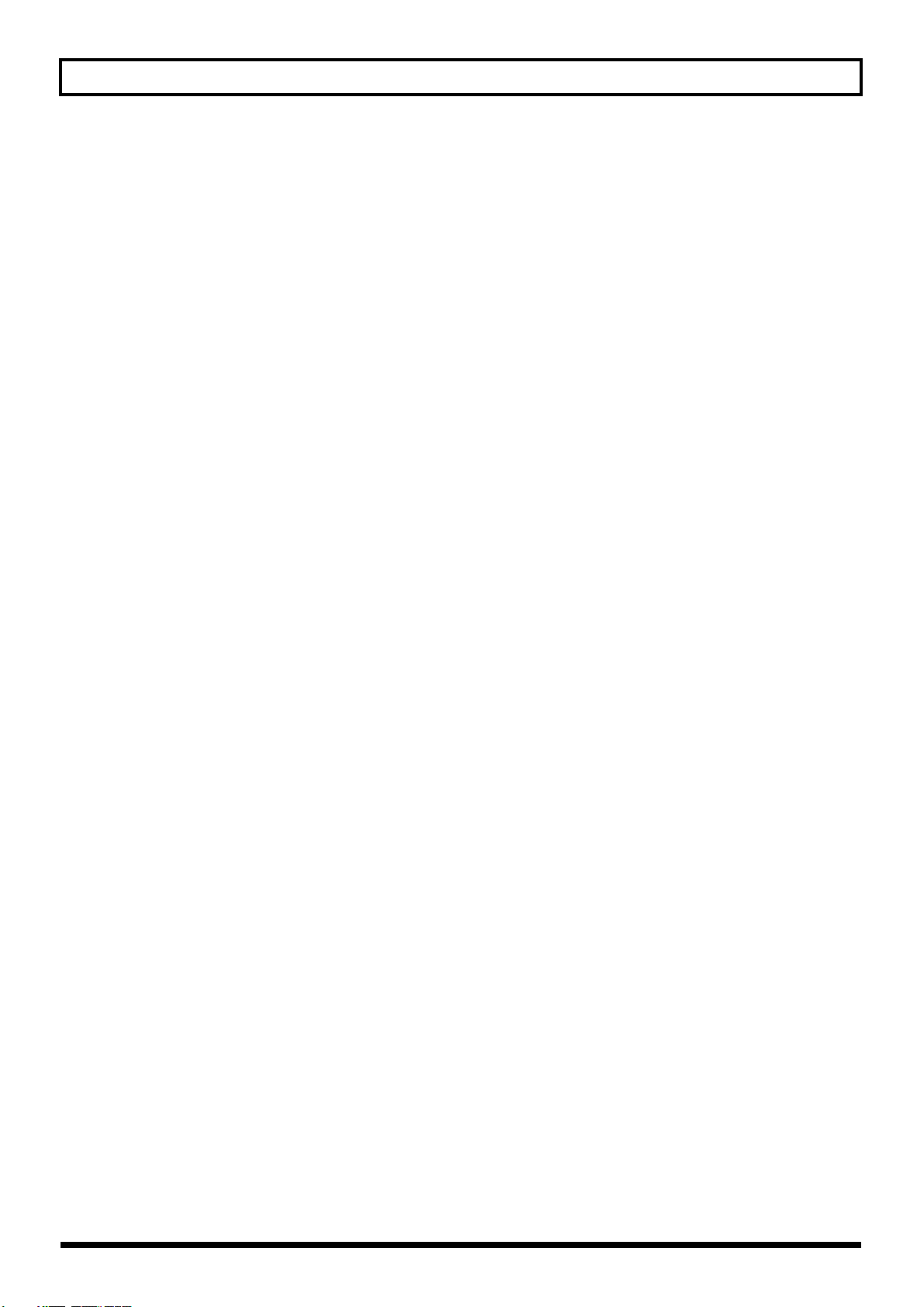
目次
音の明るさを変える(BRIGHTNESS)........................................................................................50
2 つの音(トーン)を重ねる .............................................................................................. 51
各弦でどちらのトーンを鳴らすかを決める(LAYER)............................................................51
デチューン(微妙な音高のずれ)を与える................................................................................51
音程を半音単位でずらす(TRANSPOSE).................................................................................51
2 つのトーンの音量バランスを決める(1:2 BALANCE).......................................................52
鳴るはずのトーンが鳴らない時は? ............................................................................................52
第 6 章 内蔵エフェクトを使う .............................................................53
エフェクトの構成と得られる効果 ...................................................................................... 53
マルチ・エフェクトの設定をする ...................................................................................... 53
マルチ・エフェクトをオン/オフする(MULTI-FX SW)......................................................53
種類を選ぶ(MULTI-FX TYPE)...................................................................................................54
マルチ・エフェクトのパラメーターについて............................................................................55
コーラスの設定をする ........................................................................................................74
リバーブ(残響)の設定をする ..........................................................................................74
エフェクトの一時オフについて(EFFECT BYPASS)........................................................ 75
内蔵エフェクトが効かない時は ..........................................................................................75
第 7 章 和音演奏を分散和音に展開する〜アルペジエーター...............76
アルペジエーターのしくみ ................................................................................................. 76
「アルペジオ・パターン」について ..............................................................................................76
アルペジオ中のホールド機能の有効な使い方 .................................................................... 76
アルペジオの鳴りかたを変える ..........................................................................................77
アルペジエーターのオン/オフを切り替える(HAR/ARP CONTROL)............................77
アルペジオさせるトーンを選択する(HAR/ARP SELECT).................................................78
アルペジオのパターンを選択する(ARP PATTERN)............................................................78
テンポを設定する(ARP TEMPO)..............................................................................................79
ペダルを使ってテンポを設定する(タップ・テンポ・ティーチ機能)................................79
第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト...............80
ハーモニストのしくみ ........................................................................................................80
ハーモニストでできること ................................................................................................. 80
ギター音にシンセ音でハーモニーをつける................................................................................80
シンセ音同士でハーモニーを作る ................................................................................................80
6
操作のしかた....................................................................................................................... 81
ハーモニストをオン/オフする(HAR/ARP CONTROL)....................................................81
ハーモニー音を鳴らすトーンを選択する(HAR/ARP SELECT)........................................82
副旋律の音程を設定する(HARMONY STYLE)......................................................................82
トランスポーズの設定と「HARMONY STYLE」の関係........................................................83
キー(調性)を設定する(HARMONY KEY)............................................................................84
MIDI ノート情報で外部ペダルなどからキーを変える(HARMONY REMOTE)...............84
曲中でメジャー/マイナーを切り替える....................................................................................85

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する........................................86
MIDI について ..................................................................................................................... 86
外部 MIDI 音源を鳴らす ...................................................................................................... 86
外部 MIDI 音源との接続...................................................................................................................86
MIDI チャンネル/ベンド・レンジを設定する(BASIC CHANNEL、BEND RANGE)..86
GR-33 から MIDI 情報を送って音色などを選ぶ(MIDI[PC])................................................88
弦別に異なる音色を選ぶ .................................................................................................................89
128 個を越える音色を選ぶ(MIDI[CC0]、MIDI[CC32]).......................................................89
アルペジエーター、ハーモニストを外部音源に使う ...............................................................90
エンベロープ・フォロー機能と MIDI データの関係.................................................................91
外部 MIDI 機器を本体ペダルでコントロールする .....................................................................91
外部音源への演奏情報を平行移調する(MIDI [TRANSPOSE]).........................................92
うまく外部音源が鳴らないときは ...................................................................................... 92
外部シーケンサーの入力ツールとして使う ........................................................................93
シーケンサーと接続する .................................................................................................................93
入力の手順と各機器の設定.............................................................................................................93
「ローカル・コントロール・オフ」について..............................................................................94
撥弦楽器のリアルなデータをつくる ............................................................................................94
アルペジエーター、ハーモニストの演奏を記録する ...............................................................94
ピッチ・ベンド・データの送信量を減らす................................................................................95
使用するチャンネル数を節約する ................................................................................................96
目次
うまく記録できないときは ................................................................................................. 96
第 10 章 その他の便利な機能 ...............................................................97
プログラム・チェンジ番号をパッチの順に振り直す.......................................................... 97
MIDI コントローラー 7 番(音量)の送信を止める............................................................ 97
ベンド・レンジのリクエスト情報の送信を止める ............................................................. 98
第 11 章 資料 ........................................................................................99
故障と思う前に ................................................................................................................... 99
エラー・メッセージ一覧................................................................................................... 102
ローランドのエクスクルーシブ・メッセージについて ....................................................103
MIDI インプリメンテーション ..........................................................................................105
MIDI インプリメンテーション・チャート ........................................................................ 119
主な仕様............................................................................................................................ 120
索引 .......................................................................................................121
トーン・リスト .....................................................................................124
パッチ・リスト .....................................................................................126
7
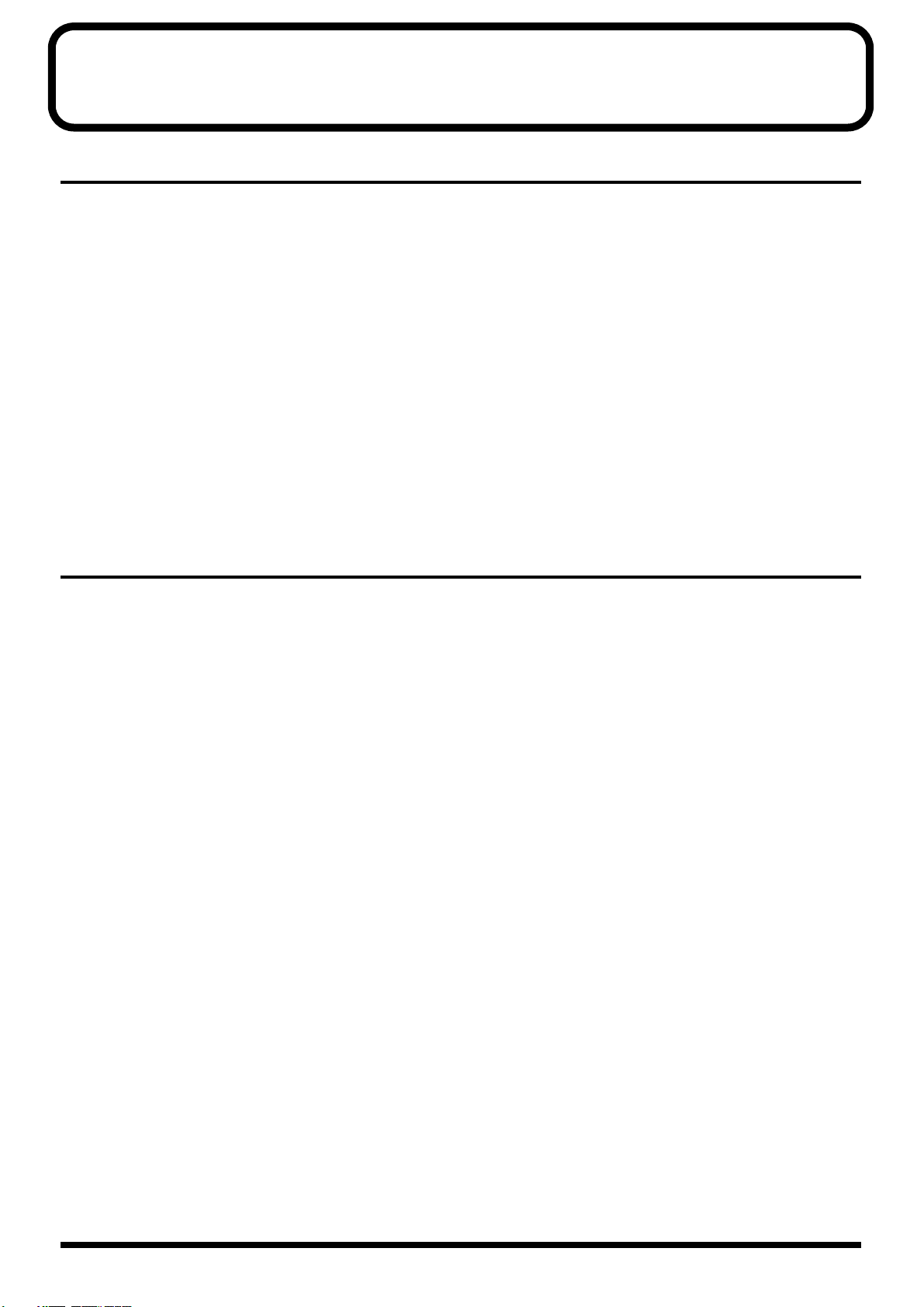
はじめに
ギター・シンセサイザーのしくみ
GR-33 は多機能で高音質、かつ小型軽量な「ギター・シンセ
サイザー」(以下ギター・シンセ)です。
通常シンセサイザーというと鍵盤コントローラー式が一般的
です。しかし鍵盤のしくみは ON/OFF スイッチの延長線にあ
り、必ずしも弦楽器や管楽器ほど表現力が高いとはいえませ
ん。
これに対してギターは、振動部(弦)に直接触れられるため、
半音以下の細かい音高変化やビブラート、ミュートのニュア
ンスなどの表現力に非常に長けています。またその手軽さか
ら、演奏人口もキーボード奏者の数を上回っています。
ギター・シンセは、これらの点に注目して開発された、ギター
を弾くことでシンセサイザー音源を鳴らすことができる楽器
です。
GR-33 でできること(主なもの)
● 通常のギター演奏と同じ感覚で、384 種もの膨大なシン
セ・サウンドを自在に操ることができます。
→ シンセ音のみで、あるいはギター音にシンセ 音を重ねて
ソロをとったり、両者を切り替えても鳴らせます。
→ 和音で演奏すれば、シンセならではの壮大な アンサンブ
ル・サウンドが表現できます。
→ エレクトリック・ギターから他の楽器(アコー スティッ
ク・ギター、ベース、オルガン、管楽器、民族楽器・・)
に持ち替えることなく、瞬時にそれらの音に 切り替えら
れます。
● 金属弦で、GK-2A(ディバイデッド・ピックアップ:別
売)が正し く取 り付けられ るも のであれば、ア コー ス
ティック・ギターとの組み合わせでも使えます。
● 2 種類のシンセ音色を重ねたり、各弦に自由に割り当て
られる他、音の明るさや立ち上がり、ギター音 との音の
高さの差などを細かく調整して記憶させてお くことがで
きます。(P.49 〜 P.52)
● シンセ・ハーモニスト機能により、ギター音に シンセ音
で(またはシンセ音同士で)あらかじめ設定し たキーの
美しいハーモニーをつけることができます(P.80)。
● 内蔵のアルペジエーターにより、様々なアル ペジオ効果
を得ることができます(P.76)。
金属弦のギターに各弦独立式のピックアップを取り付け、弦
別に拾っ た振 動からその周波 数や 振幅を抽出し、それ らに
従った高さ、音量、音色のシンセ音を発音させる...という
しくみになっています。
また内蔵音源を 鳴らすと同 時に、MIDI ア ウト端子から外部
MIDI 機器(音源など)に対しても、ギターの演奏情報を送出
するようになっています。
● シンセ音 用のエフ ェクター(リバーブ系、コー ラス系、
マルチ・エフェクト)を搭載、豊かな広がり が得られま
す(P.53)。
● 2 種類のシンセ音をステレオ(左右)に振り分けて鳴ら
したり、1 〜 6 弦に対応するシンセ音を左から右に順に
並べて発 音させる など、様々なシンセ音の 定位(パン)
が得られます(P.41)。
● 本体の 4 つの音色切替ペダルは、ワウワウ風やアーミン
グ風など、様々な効果を得るためにも使えます(P.28 〜
P.29)。
● エクスプレッション・ペダルが装備さ れているため、音
量や音の高さ等まで、様々な変化を本体の みで得ること
ができます(P.47)。
● ギターの演奏を MIDI 情報に変換し、外部音源を鳴らすこ
ともできます(P. 86 〜)。
● MIDI シーケンサーの入力用に使えば、鍵盤では再現しき
れない リア ルな撥弦楽器 パー トや、表現に富ん だメ ロ
ディ・パートを作成できます(P.93)。
● ギター・チューナーを搭載、すばやく正し くチューニン
グできます(P. 18)。
※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
8

使用上のご注意
291a
2 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。
電源について
301
● 雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電力
の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。
302
● AC アダプターを長時間使用すると AC アダプター本体が
多少発熱しますが、故障ではありません。
307
● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐた
め、必ずすべての機器の電源を切ってください。
設置について
351
● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持
つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがありま
す。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてくださ
い。
352
● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ
画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあり
ます。この場合は、この機器を遠ざけて使用してください。
354a
● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め切っ
た車内などに放置しないでください。変形、変色すること
があります。
355
● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用し
ないでください。
お手入れについて
401a
● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞っ
た布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、
中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らかい布
で乾拭きしてください。
402
● 変色や変形の原 因となる ベンジン、シンナーおよびアル
コール類は、使用しないでください。
修理について
451c
● お客様がこの機器や AC アダプターを分解、改造された場
合、以後の性能について保証できなくなります。また、修
理をお断りする場合もあります。
452
● 修理に出される場合、記憶した内容が失われることがあり
ます。大切な記憶内容は、他の MIDI 機器(シーケンサー
など)に保存する か、記憶内容 をメモしておいてくださ
い。修理するときには記憶内容の保存に細心の注意を払っ
ておりますが、メモリー部の故障などで記憶内容が復元で
きない場合もあります。失われた記録内容の修復に関しま
しては、補償も含めご容赦願います。
453
● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持
するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有して
います。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていた
だきます。なお、保 有期間が 経過した後も、故障箇所に
よっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店、
または最寄りのローランド・サービスにご相談ください。
メモリー・バックアップについて
501b
● 本体内には、電源を切った後も記憶した内容を保持するた
めの電池を装備しています。電池が消耗してくると、ディ
スプレイに次のように表示されます。電池が消耗すると記
憶した内容が失われますので、早めに交換してください。
交換するときは、必ずローランド・サービスに相談してく
ださい。
「Battery Low!」
その他の注意について
551
● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、失
われることがあります。失っても困らないように、大切な
記憶内容はバックアップとして他の MIDI 機器(シーケン
サーなど)に保存しておいてください。
552(
● 本体メモリーの失われた記憶内容の修復に関しましては、
補償を含めご容赦願います。
553
● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子
などに過度の力を加えないでください。
554
● ディスプレイ を強く押し たり、叩いたりしないでくださ
い。
556
● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プラ
グを持ってください。
558a
● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないよ
うに、特に夜間は、音量に十分注意してください。ヘッド
ホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけます。
559a
● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダン
ボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
562
● 接続には、当社ケーブル(PCS シリーズなど)をご使用
ください。他社製の接続ケーブルをご使用になる場合は、
次の点にご注意ください。
○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本
機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しない
でください。音が極端に小さくなったり、全く聞こ
えなくなる場合があります。ケーブルの仕様につき
ましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせくだ
さい。
9
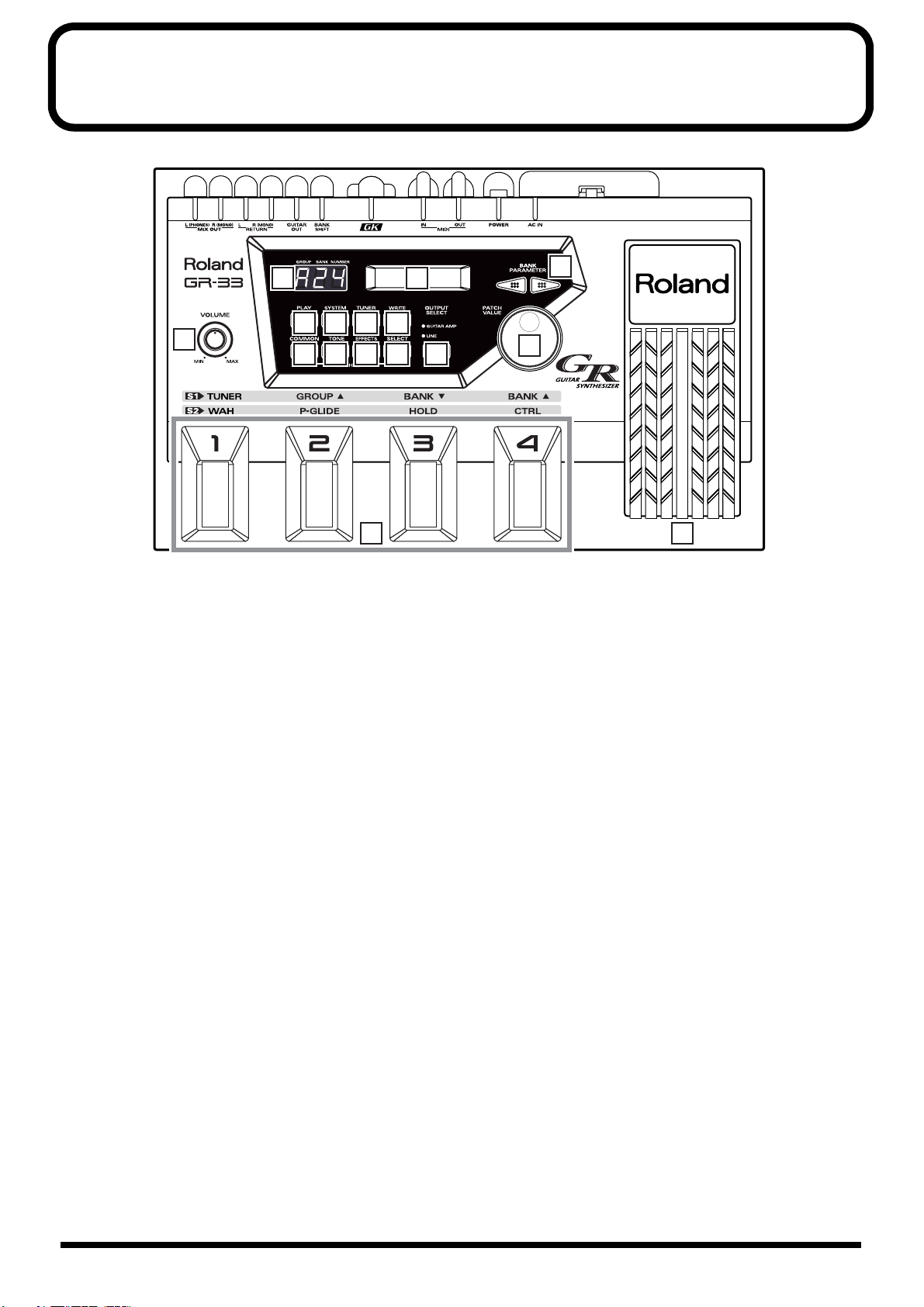
各部の名称と働き
fig.0-01(各部の名称と働き 1)
13 14
2 3 4 5
1
6 7 8 9
1 VOLUME(ボリューム)つまみ
ミックス・アウトから出力される信号の音量を調節しま
す。中央付近が、楽器用アンプやミキサーに接続する際
の目安の位置です。
※ ギター・アウト・ジャックからの出力レベルには関係し
ません。
10
11
12
1615
6 COMMON(コモン)ボタン
パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設
定関連)に切り替えるボタンです。
このボタンを押 してパ ッチ・エディット・モードに入
り、パッチの名前やペダルの効果などのパッチの設定を
行います。
2 PLAY(プレイ)ボタン
プレイ・モードに切り替えるボタンです。
演奏する時はこのボタンを押してプレイ・モード(起動
時の状態)にします。
3 SYSTEM(システム)ボタン
システム・モードに切り替えるボタンです。
このボタンを押し てシステ ム・モードに入り、GR-33
本体に関する設定を行います。
4 TUNER(チューナー)ボタン
チューナー・モードに切り替えるボタンです。
このボタンを押すとチューナー機能がオンになり、
チューニングを行うことができます。
5 WRITE(ライト)ボタン
パッチの書き込み(パッチ・ライト)に使います。
また、ファクトリー・リセットやバルク・ダンプで、確
認用ボタンとしても使います。
7 TONE(トーン)ボタン
パッチ・エディット・モードの TONE(パッチの音色関
連)に切り替えるボタンです。
このボタンを押 してパ ッチ・エディット・モードに入
り、シンセ音の基本となる音色(トーン)の設定を行い
ます。
8 EFFECTS(エフェクト)ボタン
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエ
フェクト関連)に切り替えるボタンです。
このボタンを押 してパ ッチ・エディット・モードに入
り、リバーブ、コーラス、マルチ・エフェクトなどのエ
フェクト関連の設定を行います。
9 STRING SELECT
(ストリング・セレクト)ボタン
1st / 2nd トーンの割り当て(LAYER)や移 調
(TRANSPOSE)など、弦ごとに設定を変えられる項目
で、弦番号の指定に使います。
10
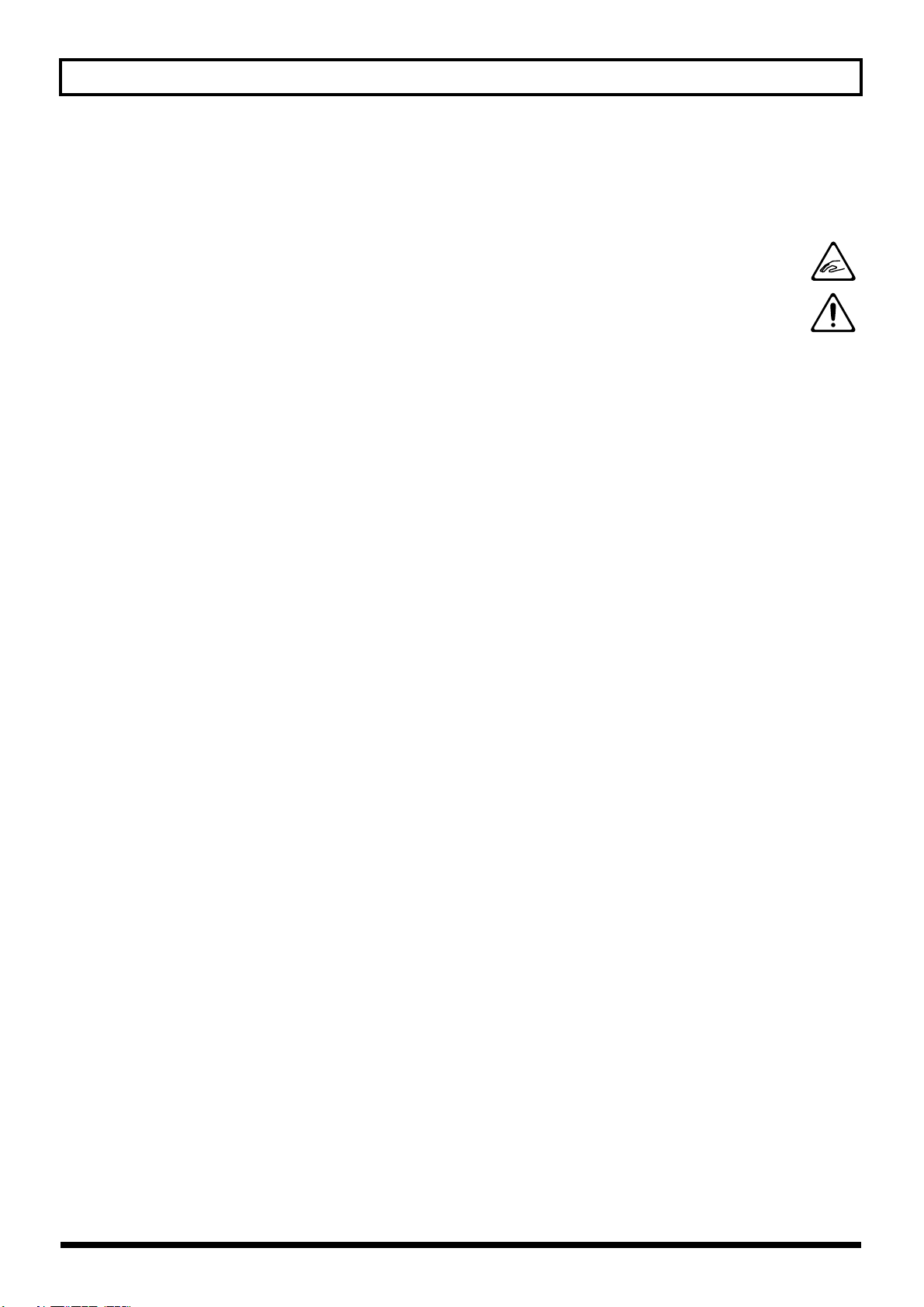
各部の名称と働き
10 OUTPUT SELECT
(アウトプット・セレクト)ボタン
MIX OUT につながれる出力機器の選択に使います。
11 BANK/PARAMETER
(バンク/パラメーター)ボタン
プレイ・モード時にこのボタンを押すと、バンクが切り
替わります。
システム・モード、パッチ・エディット・モードの時に
は、設定項目が変わります。
12 PATCH/VALUE(パッチ/バリュー)
ダイヤル
プレイ・モード時にこのダイヤルを回すと、パッチが順
次切り替わります。
システム・モード、パッチ・エディット・モードの時に
は、設定項目の設定値が変更できます。
13 3 桁表示器
プレイ・モード時はパッチ番号を表示します。
システム・モード、パッチ・エディット・モード、ペダ
ル効果モ ード では、それぞれ モー ドを表わすSYS
EdtPdLが表示されます。また弦ごとに設定がで
きる項目などでは、弦番号が表示されます。
16 エクスプレッション・ペダル
シンセ音の音量、音色、音程、アルペジエーターのテン
ポなど、様々なコントロールを行うことができます。
● エクスプレッション・ペダルを操作するときは、
可動部とパネル の間に指を 挟まないように注意
してください。
お子様のいる ご家庭で使 用する場合、お子様の
取り扱いやい たずらに注 意してください。必ず
大人のかたが、監視/指導してあげてください。
14 ディスプレイ
プレイ・モード時はパッチネームやハーモニスト/アル
ペジエーターの状態などが表示されます。
その他のモードでは、選ばれている設定項目の状態や値
を表示します。また、様々なメッセージがここに表示さ
れます。
15 フット・ペダル
4 個の足踏みスイッチです。プレイ・モードでは、GK2A の[S1]と併せて、主にパッチの切り替えに使いま
す。また GK-2A の[S2]を押し、ペダル効果モードに
入ってから踏めば、ワウ、ピッチ・グライド、ホールド
などの演奏効果が得られます。
11
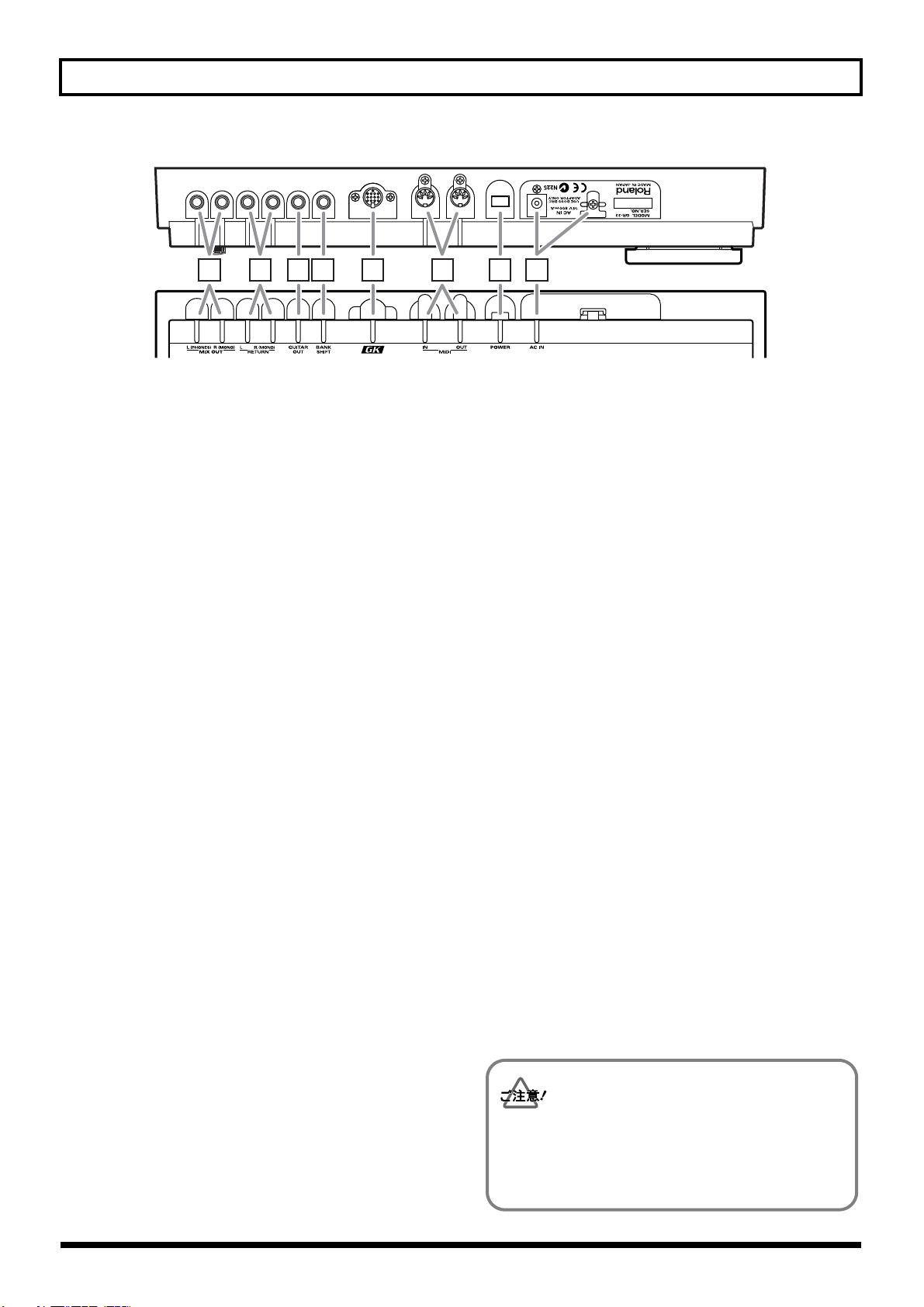
各部の名称と働き
fig.0-02(各部の名称と働き 2)
17 18 19 20 21 22 23 24
17 MIX OUT
(ミックス・アウト)ジャック
L (PHONES) /R (MONO)
シンセ音が出力されます。通常は、L / R から 2 本の
ケーブルで出力し、ステレオ構成のアンプに繋ぎます。
なお L (PHONES) 側は、ステレオ標準プラグにも対応
していますので、ヘッドホン・ジャックとしても使用で
きます。(ただし L (PHONES) をヘッドホン・アウトと
して使用している時に、R (MONO) をライン・アウト
として同時使用することはできません。)
GUITAR OUT ジャックに何も接続しないと、ギター本
体の音もここにミックスされて出力されます。
※ 出荷時のパッチを正しく鳴らすため、できる だけステレ
オ・アンプか、ステレオ・ヘッドホンでご使用ください。
モノラル・アンプにつなぐ時は、R (MONO) に接続して
ください。
18 GUITAR RETURN(ギター・リターン)
ジャック L/R(MONO)
GUITAR OUT ジャック(次項)を外部エフェクターの
センド(送り出力)として使う場合、このジャックへリ
ターン(受け入力)させます。MIX OUT からシンセ音
とエフェクトのかか ったギタ ー音がいっしょに出力さ
れます。
GUITAR OUT(ギター・アウト)ジャック
19
ギター音のみをシン セ音とは 別に出力させる場合に使
用します。お手持ち のギター 専用アンプやギター・エ
フェクターに接続します。
BANK SHIFT(バンク・シフト)ジャック
20
パッチのバンク切り替え専用の増設フット・スイッチを
接続するジャックです。フット・スイッチ BOSS FS5U を 2個、PCS-31 ケーブルを使って接続します(各
別売)。増設したフット・スイッチは、プレイ・モード
以外では異なる機能を担当します。
21 GK IN コネクター
付属の 13 ピン専用ケーブルで、ディバイデッド・ピッ
クアップ GK-2A(別売)と接続します。
※ 市販のギタ ー・シンセ 対応ギターとの接続に ついては、
各ギター・メーカーや販売店にお問い合わせください。
22 MIDI コネクター(MIDI IN/OUT)
MIDI ケーブルにより、外部機器との接続をするための
コネクターです。外 部音源モ ジュールを本機のコント
ロールで鳴らしたり、MIDI を使って音色データのやり
とりを行う場合に使用します。
23 パワー・スイッチ
機器全体の電源をオン/オフするためのスイッチです。
24 電源ジャック/コード・フック
付属の AC ア ダプターを接続しま す。また、コード・
フックにアダプターのコードを引っかけておくと、演奏
中にコードが抜ける事故を防ぐことができます。
※ 付属の AC アダプター以外は絶対に使用しないでくださ
い。
12
本書では、ディスプレイ/画面を使用して機能説明をし
ていますが、工場出荷時の設定(音色名など)と本文中
のディスプレイ/画面上の設定は一致していません。あ
らかじめご了承ください。
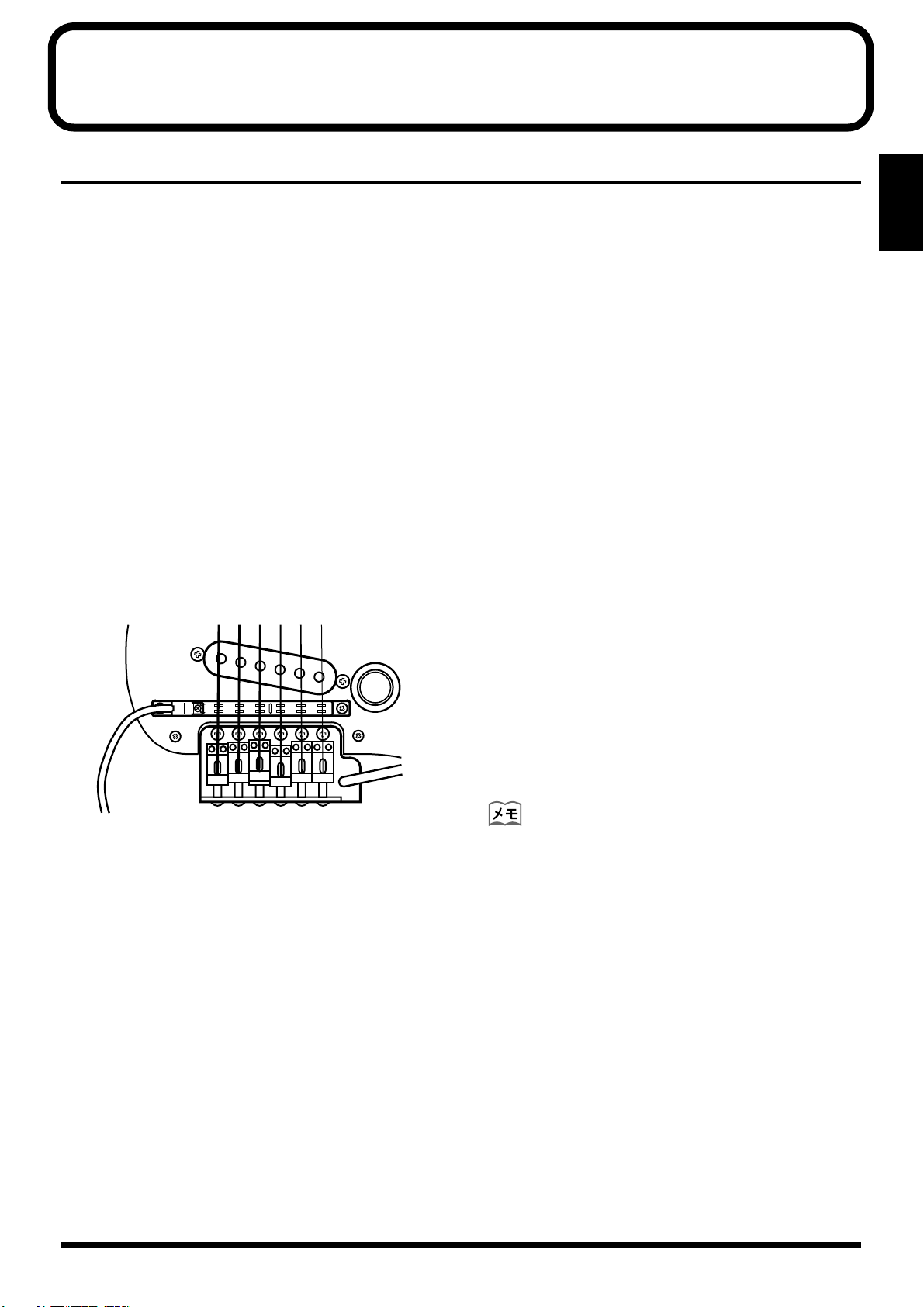
第 1 章 音を出す
用意するもの
GR-33 を鳴らすには、次のものが必要です。
● GR-33 本体、付属品(AC アダプター、13 ピン・ケーブル)
● アンプ、スピーカー、ケーブル類(なるべくステレオ構成のもの)、またはステレオ・ヘッドホン
● ディバイデッド・ピックアップ GK-2A
● GK-2A が正しく取り付けられる金属弦のギター
上記の他、次のものも必要に応じてご用意ください。
● ギター専用アンプ、ギター・エフェクター(ギター音を併用するとき)
● 外付けバンク・シフト・スイッチ(BOSS FS-5U × 2 個、PCS-31 ケーブル× 1 本:各別売)(P.23)
● MIDI フット・コントローラー(FC-200 など:別売)(P.24)
GK-2A の取り付け
各機器を接続する前に、ギターに GK-2A を取り付けます。
GK-2A の取扱説明書に記載されている手順に従って、図のよ
うに GK-2A のピックアップを取り付けてください。
fig.1-20
< GK-2A が使用できないギター>
GK-2A は多 くのギターに取り付けるこ とができるよう小型
に設計されていますが、次の様なギターでは使用できません
のでご注意ください。
1章
※ ピックアップには取り付け方向がありま す。コードが出
ているほうが 6 弦側です。
※ GK-2A の取扱説明書では、他の機器との組み合わせで説
明が書かれている場合がありますが、そのまま GR-33 に
置き替えてお考えください。
GK-2A の取り付け状態については、特に以下の点に注意しま
す。
● 最高フレットを押さえた時、弦とピックアッ プの一番狭
い点での間隔が 1mm になっていること(近すぎても不
可)。
● ギターのブリッジと、GK-2Aのピックアップ部の間隔が、
20mm を超えないこと。
a. 12 弦ギターやペダル・スティールなど弦構成が特殊なギ
ター、ナイロン弦、ガット弦などのギター、及びベース・
ギター。(取り付けても正常に動作しません。)
b. 構造上、GK-2A のピックアップを正しく装着するスペー
スがないギター。
上記 b. の場合、ギター側の比較的簡単な改造で取り付けられ
ることもあります。お買い上げの楽器店にご相談ください。
現在ギター・メーカー各社から、GK-2A なしで GR シリーズ
の 13 ピン・ケーブルを直接接続できる、ギター・シンセ対
応ギターが発売されています。詳しくはギター販売店、また
は各ギター・メーカーにお問い合わせください。
※ フレット数が 25 を超える特殊なギターや、通常より高い
チューニングが施されたギターでは、最高 フレット付近
での発音が制限される場合がありますの でご注意くださ
い。
● ピックアップ部の 6 つのヨーク(ポールピース)と、各
弦の位置関係が正しいこと。
詳しくは GK-2A の取扱説明書をご覧ください。
13
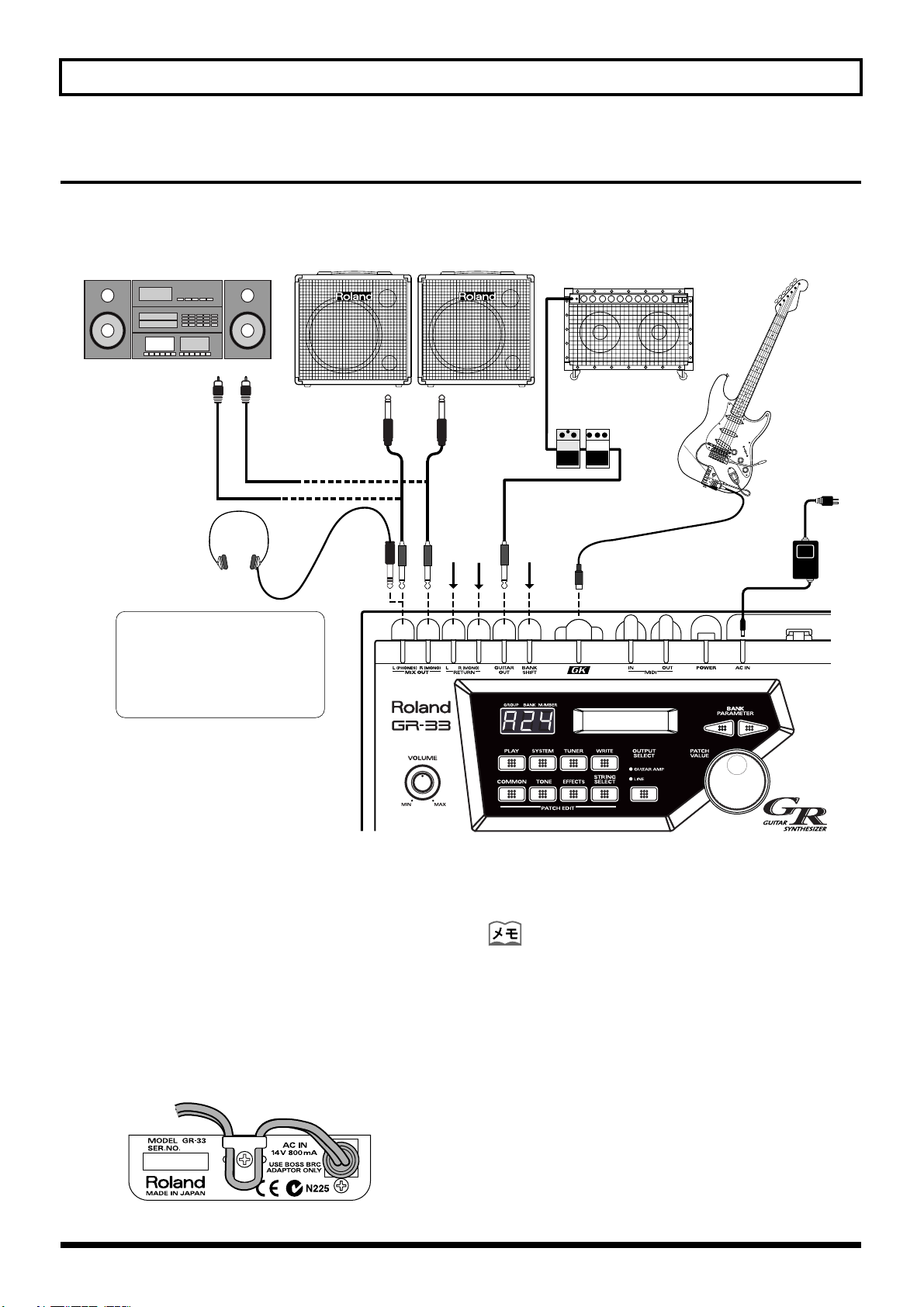
第 1 章 音を出す
接続のしかた
ギター側(GK-2A)の準備ができたら、図の接続例に従って各機器を接続します。
fig.1-01(接続図)
シンセ音用アンプ
ギター音用アンプ/
ギター・エフェクター
LR
ステレオ・セット、ラジカセなど
AUX、LINEIN端子へ
L
R
(キーボード用アンプ、PAシステムなど)
GK-2A付きギター
/市販のGR対応ギター
DOWN/S1
SYNTHVOL
UP/S2
ステレオ・ヘッドホン
MIXOUTジャック(L)は、ステレ
オ・ヘッドホン・ジャックとしても
使用できます。
一方をライン・アウト、他方をヘッ
ドホン・アウトとして同時使用する
こと(モノラル・プラグとステレ
オ・プラグの併用)はできません。
※ 他の機器と接続するときは、誤動作やスピー カーなどの
破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を 絞った状態
で、電源を切って行なってください。
※ アンプのボリュームは、すべての機器の電源 をオンにし
たあとに上げてください。
※ AC アダプターのコードは図のようにコード・フックに固
定してください。誤ってコードを引っ張ってしまっても、
プラグが抜けて電源が切 れてしまうことや、AC アダプ
ター・ジャックに無理な力が加わることを防 ぐことがで
きます。
fig.1-02(コード・フック)
P.15
参照
P.23
参照
ACアダプター
(BRC-100)
※ モノラルで出力する場合は、MIX OUT ジャックの R
(MONO)側にケーブルを接続してください。
<ステレオ・アウト>
GR-33 の機能を十分に引き出し、お買い上げ時に用意されて
いる音色を正しく鳴らすには、ステレオ構成のアンプ、スピー
カー(またはス テレオ・ヘッ ドホン)への接続が必要です。
ぜひステレオ(2 チャンネル構成)の機器をご用意ください。
14
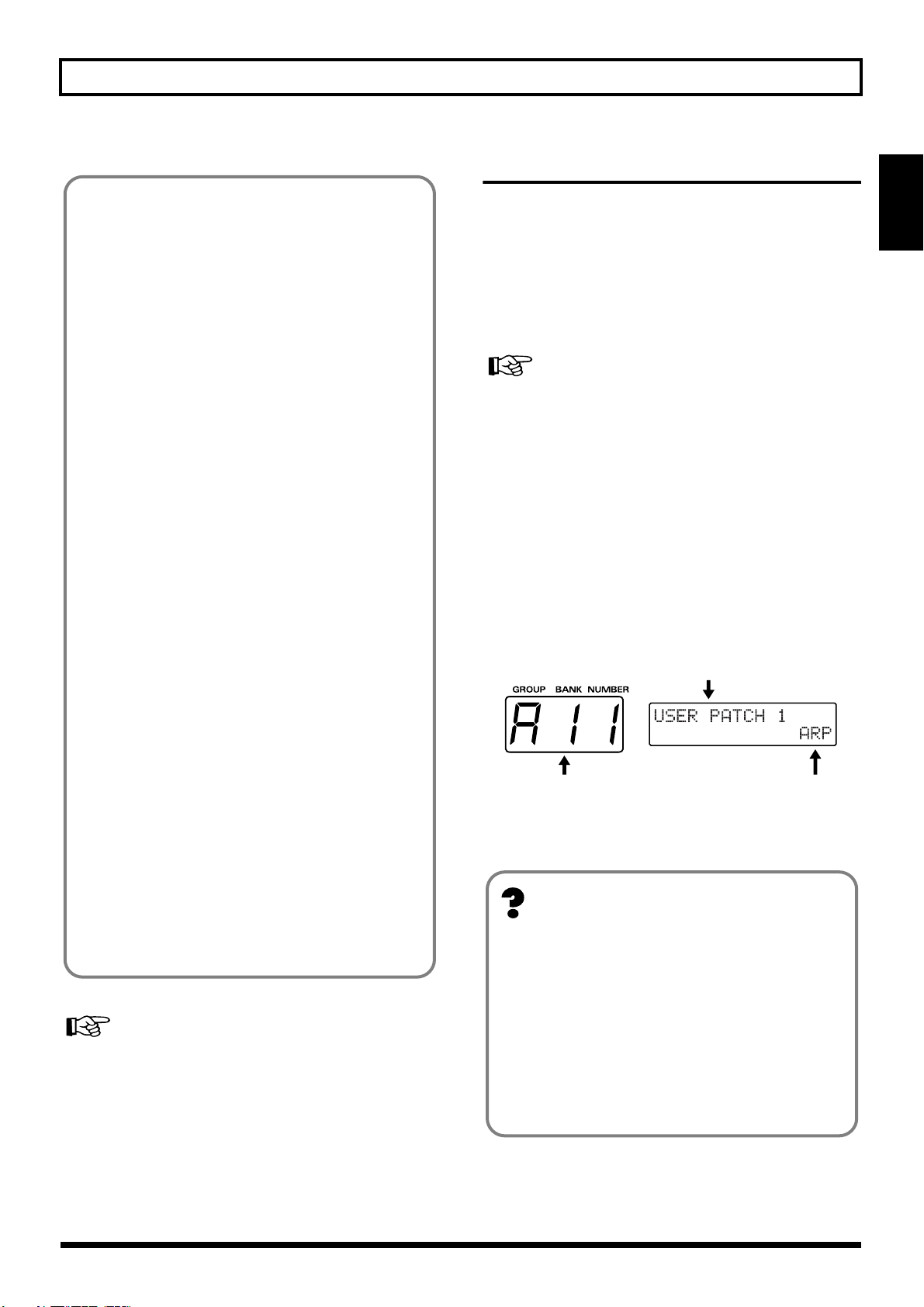
第 1 章 音を出す
現在呼ばれている
パッチ(A11)
パッチ名
ハーモニスト(HAR)
または
アルペジエーター(ARP)
<出力方法>
ギター音とシンセ音を別々に出力する
GUITAR OUT(ギター・アウト)ジャックに汎用シール
ド・ケーブルを接続し、ギター用外部エフェクターやお
手持ちのギター・アンプと接続します。これによりギター
自体の音は、GR-33 を使う前と 全く同じ感覚で コント
ロールできます。MIX OUT からはシンセ音のみが出力さ
れます。
ギター音とシンセ音をいっしょに出力する
GUITAR OUT ジャックにケーブルを接続しないで、MIX
OUT のみにケーブルを接続します。ギター本体の音はシ
ンセ音といっしょに、MIX OUT から出力されます。
これにより、アンプ 1 台でシンセ音とギター音を出力で
きます。
ギター音 のみ に外部エフェ クタ ーをかけ、シンセ 音と
いっしょに出力する
次のように接続します。
GR-33 の GUITAR OUTジャック
↓
外部エフェクターの入力
外部エフェクターの出力
電源オン〜演奏前に必要なこと
※ 正しく接続したら(P.14)、必ず次の手順で電源を投入し
てください。手順を間違えると、誤動作を したりスピー
カーなどが破損する恐れがあります。
接続の確認が終わったら本体上の VOLUME(ボリューム)つ
まみを左いっぱいに絞 った状態で、リア・パネ ルのパワー・
スイッチ(POWER)を押し、電源を入れます。
(もう一度押すと電源は切れます。)
必要な場合は、「工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・
リセット)(P.16)の手順に従って、お買い上げ時の設定状
態に戻してから使いはじめましょう。
※ この機器は回路保護のため、電源をオンし てから数秒の
間は動作しません。
「プレイ・モード」とは?
GR-33 が起動し、3 桁表示器に「A11」と表示されているの
を確認します。(これは現在選ばれている「パッチ」を示すも
のです。パッチとは、演奏中にペダルなどで自由に切り替え
ることができる音色の単位です。(→ P.21 に詳細)
fig.1-03(プレイ・モード)
1章
↓
GR-33 の GUITAR RETURNジャック
MIX OUT から、シンセ音とエフェクトのかかったギター
音がいっしょに出力されます。
ヘッドホンで聴く
MIX OUT ジャックの L (PHONES) 側に、ステレオ・ヘッ
ドホンを接続します。
※ 一方をライン・アウト、他方をヘッ ドホン・アウト
として同時使用すること(モノラ ル・プラグとステ
レオ・プラグの併用)はできません。
出力する機器による設定は「出力する機器を設定する
(OUTPUT SELECT)(P.19)を参照してください。
<プレイ・モードとは>
電源投入直後の「A11」のように、パッチ番号を表示し
ている状態が「プレイ・モード」です。通常はこのモー
ドで演奏します。またプレイ・モードは、全ての操作の
基本となる状態でもあります。
操作に慣 れな いうちに、意味の 分か らない表示状 態に
なってしまっても、電源を入れ直せば必ずプレイ・モー
ドに復帰できます。(プレイ・モードでのつまみやボタン
の働きについては、P.30 をご覧ください)。
15
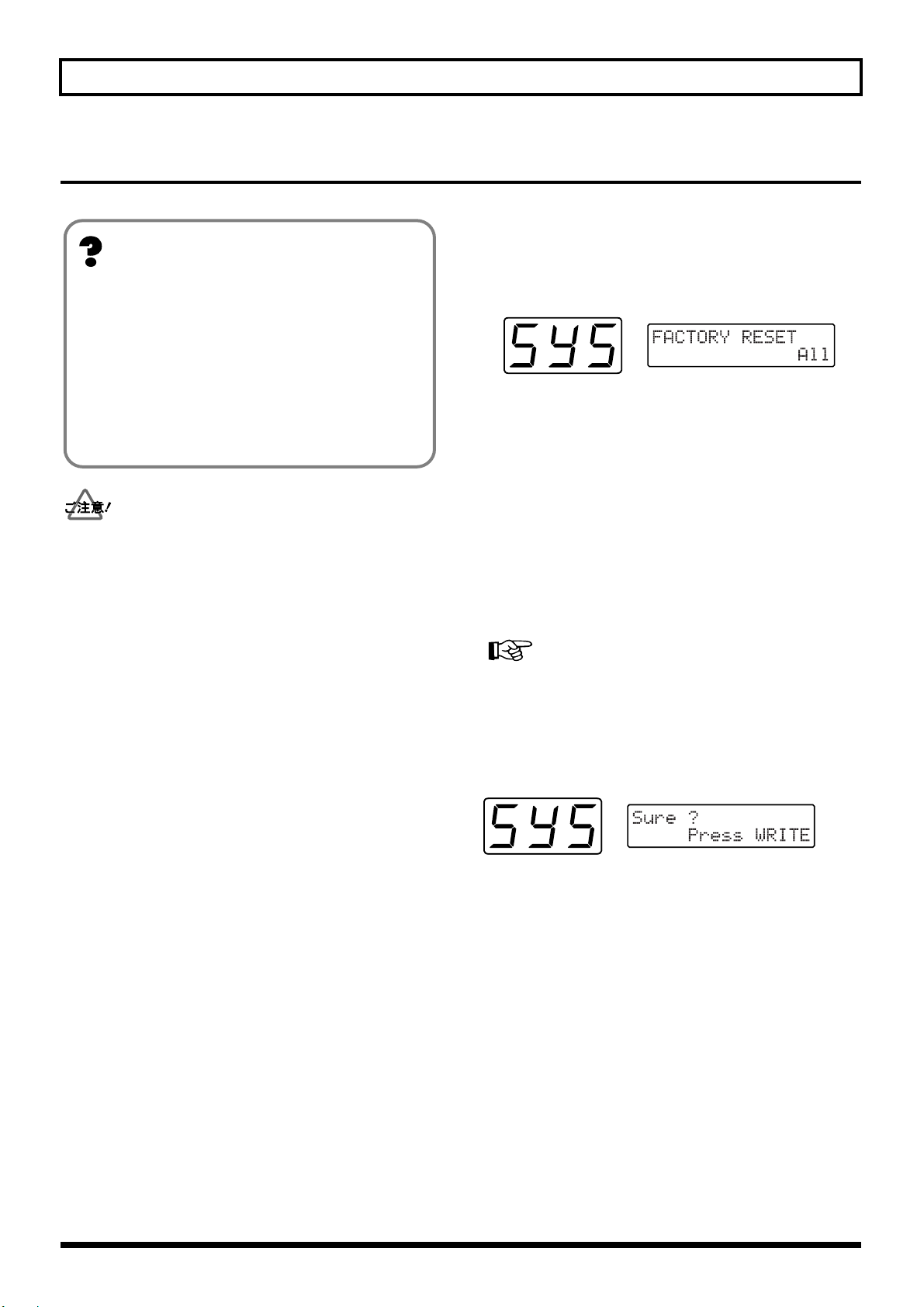
第 1 章 音を出す
工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)
■ ファクトリー・リセットを行う手順
1.
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
[PARAMETER]を押して、FACTORY RESETを選び
<ファクトリー・リセットとは>
本体の設定などを、工場出荷時(お買い上げ時)の状態
に戻すことを「ファクトリー・リセット」といいます。
GR-33 のユーザー・パッチ(A11 〜 D84)には、製品
出荷時、E11 〜 H84 のプリセット・パッチと同じものが
入っています。これをはじめ、ピックアップの感度設定
や送/受信 MIDI チャンネルなどのシステム項目も、製品
出荷時の状態に戻すことができます。
ファクトリー・リセットの操作を行うと、記憶されているデー
タを製品出荷時の設定に戻します。既に大切なデータが記憶
されている時は、バルク・ダンプ(P.37)で外部 MIDI 機器
(シーケンサーなど)に保存してからファクトリー・リセット
を行ってください。
2.
ます。
fig.1-04(ファクトリー・リセット 1)
3.
[VALUE]で製品出荷時に戻す設定を選びます。
•
All:
全ての設定を製品出荷時の状態に戻します。
System:
•
システム関連の設定を製品出荷時の状態に戻します。
User Patch:
•
パッチの内容を製品出荷時の状態に戻します。
•
PC Number:
プログラム・チェンジ番号をパッチの順に振り直します。
「PC Number」の詳細については、「プログラム・チェンジ
番号をパッチの順に振り直す」(P.97)をご覧ください。
設定が決まったら、[WRITE]を押します。
4.
Sure ?とファクトリー・リセットを実行してもよいか
を確認するメッセージが表示されます。
fig.1-05(ファクトリー・リセット 2)
5.
実行する時は、もう一度[WRITE]を押します。
Now Writing...と表示 され、プレイ・モードに 戻った
ら、ファクトリー・リセットの完了です。
中止する時は[PLAY]を押してください。
※ [WRITE]を押して からプレイ・モ ードに戻 るまでは、
パッチ・データを展開中ですので、電源を 切らないでく
ださい。
16
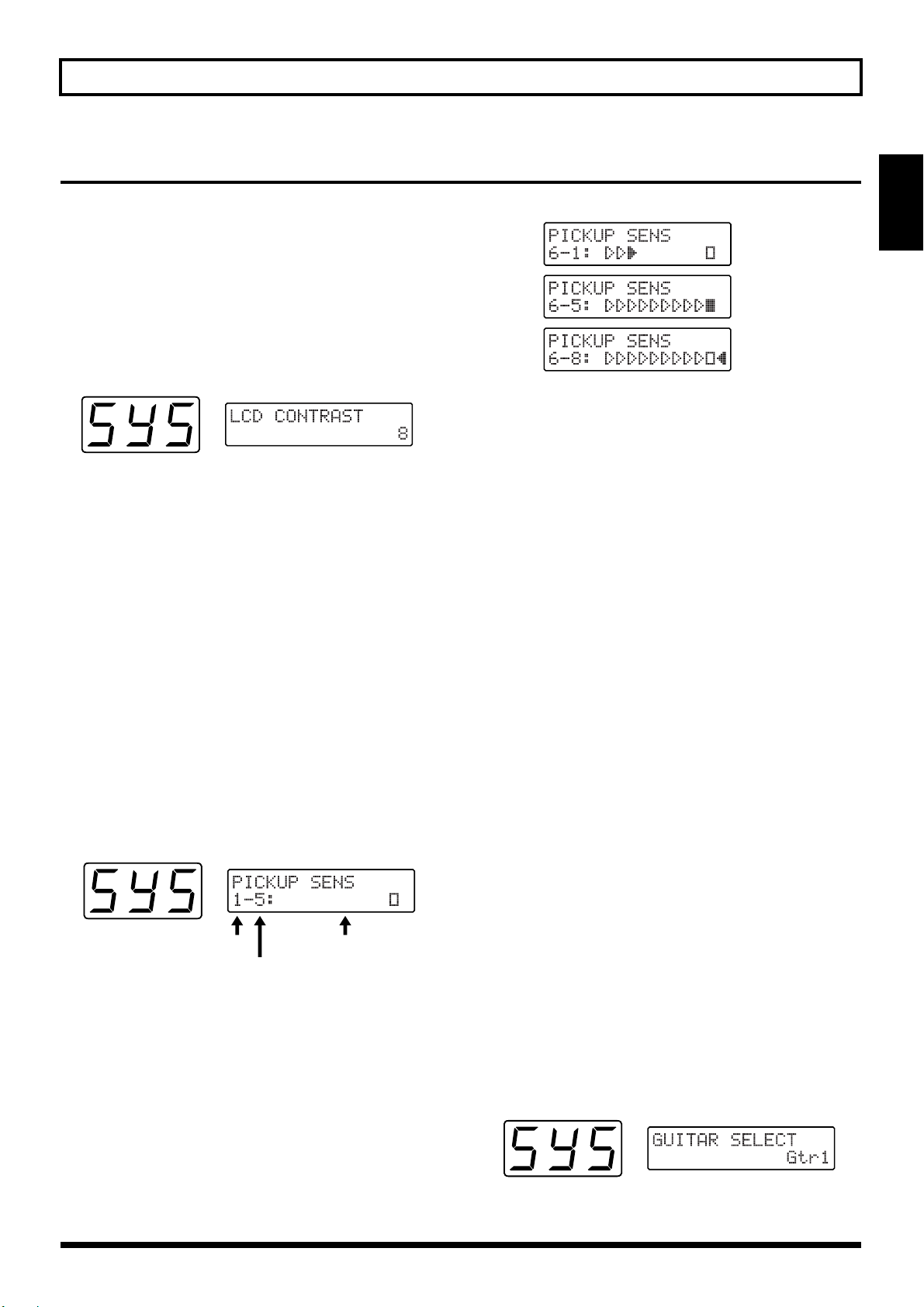
第 1 章 音を出す
全体に関わる設定をする(SYSTEM)
画面の明るさを調節する(LCD コン トラスト)
■ 画面(ディスプレイ)の明るさを調節する手順
1.
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
[PARAMETER]を押して、LCD CONTRASTを選び
2.
ます。
fig.1-06(LCD コントラスト)
3.
[VALUE]でコントラストを調節します。
調節を終えたら、[PLAY]を押してプレ イ・モードに戻
4.
ります。
入力感度を設定する(PICKUP SENS)
fig.1-21
※ 感度が高すぎると音抜けが起こったり、強 弱表現ができ
5.
6.
1章
感度が低い
感度が高い
弾いた時の最大レベルが点灯します。右端 のインジケー
ターが点灯 した場合 はレベル・オーバーですので、
[VALUE]を回して感度を下げます。
なくなったりします。また低すぎても正常 に動作しませ
んのでご注意ください。
同様に 5 〜 1 弦の感度を調整します。
設定が終わったら[PLAY]を押して、プレイ・モードに
戻ります。
電源が入ったら、GK-2A の取り付け状態やあなたのピッキン
グの強さに合わせて、各弦の入力感度を調整します。この項
での設定は自動的に記憶され、電源を切っても失われません
ので、演奏のたびに感度設定をやり直す必要はありません。
■ 入力感度を設定する手順
1.
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
[PARAMETER]を押して、PICKUP SENSを選びます。
2.
感度調整機能が呼び出され、図のような表示になります。
fig.1-07(PICKUP SENS)
弦番号
入力感度
ギターの 6 弦を弾くと、弦番号が6に自動的に切り替
3.
わります。
ディスプレイに表示されたレベル・メータ ーが、弦を弾
く強さに応じて左から順に点灯します。ま た、弦番号の
となりに、その弦の現在の入力感度が表示されます。
4.
実際の 演奏 で一番強く弾 いた 時に、四角のイン ジケ ー
ターが点灯するように、[VALUE]で感度を調整します。
レベル・メーター
次の場合には、感度調整をやり直してください!
まだ感度設定を行っていないギターを使う時。
•
•
工場出荷時の設定へ戻す操作(P.16)を行なった時。
ギター側の弦高調整などに伴い、GK-2A の取り付け状態
•
が変わった時。
•
弦の太さを変えた時など。
ギターによっては、まれに感度を最低にしてもメーターが振
り切れてしまう場合があ ります。このようなと きには、GK-
2A のデバイデッド・ピックア ップと弦との間隔を、規定よ
りもやや広めになるように調整してください。
複数のギターを使う場合(GUITAR SELECT)
GR-33 は、各弦の感度設定を最大 4 通りまで記憶でき、ギ
ター交換に合わせてそれらを呼び出せます。
■ 異なる感度設定を呼び出す手順
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
2.
[PARAMETER]を押して、GUITAR SELECTを選び
ます。
fig.1-08(GUITAR SELECT)
17
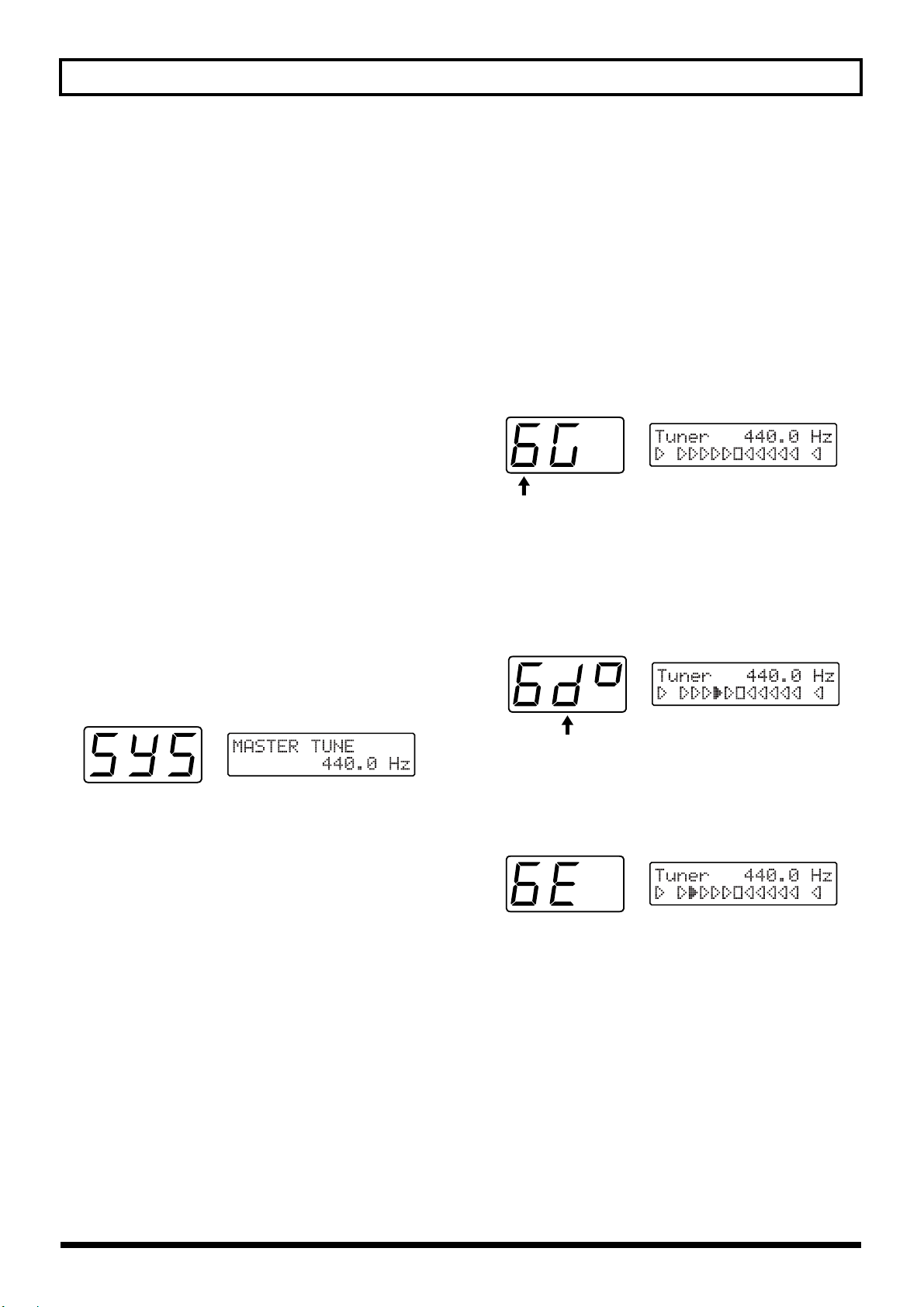
第 1 章 音を出す
1〜6の弦番号
音名
(D#。3桁目が#の意)
[VALUE]で Gtr1 〜 Gtr4 を選びます。
3.
選ばれた設定が呼び出されます。
※ 工場出荷時は「Gtr1」になっています。
新たに入力感度の設定を行う場合は、[PARAMETER]を
押してPICKUP SENSを選び、設定を行ってください。
選択が終了したら、[PLAY]を押してプ レイ・モードに
4.
戻ります。
Gtr1 〜 Gtr4 のそれぞれで入力感度の設定を行えば、4通
りの感度設定が記憶できます。
※ GUITAR SELECT 画面で一番最後に選ばれていた設定が
有効になります。
他の楽器にピッチを合わせる
工場出荷時のシンセ音と内蔵チューナーのマスター・チュー
ン(基準ピッチ)は、A=440.0 Hz です。
他の楽器のピッチと合わせる時など、マスター・チューンを
変更したい場合は、次の手順で変更します。
ギターのチューニングをする(チュー ナー機能)
正確な音程を得るため、本体内蔵のギター・チューナー機能
で、使用するギタ ーをチュ ーニングしましょう。使い方は、
市販の自動式ギター・チューナーとほぼ同じです。
■ チューニングをする手順
1.
GK-2A の[S1]を押しながら、フットペダル[1](TUNER)
を踏みます。または[TUNER]を押します。
チューナー機能が呼び出され、図のような表示になります。
fig.1-09(TUNER1)
ギターの 6 弦を弾きます。
2.
弦番号が6に自動的に切り替わります。
■ マスター・チューンを変更する手順
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
2.
[PARAMETER]を押して、MASTER TUNEを選びま
す。
fig.1-13(MASTER TUNE)
3.
[VALUE]で希望するピッチに変更します。
(変化幅 427.4 〜 452.6 Hz)
4.
[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。
※ マスター・チューンの設定を変更しても、GR-33 本体の
シンセ音の高さは直ちには変わりません。シ ンセ音はマ
スター・チューンと関係なく、ギターの実際の ピッチを
追従します。
マスター・チューンの変更後、内蔵チューナー でギター
のチューニングをやり直すことにより、シン セ音を含め
る全てのピッチが正しく調律されます。
表示器の下 2 桁に、6 弦の現在のおよその音名が、半音
刻みで表示されます。(図の例では D#。)
fig.1-10(TUNER2)
6弦を弾きながらギターのペグを回し、その弦を合わせる
3.
音名を表示させます。
fig.1-11(TUNER3)
4.
さらにギターのペグを微調整し、ディスプ レイ上の点灯
しているマークが中央に来るように合わせ込みます。
中央のインジケーターとその両側が点灯したら、6 弦 =E
にチューニングできたことになります。
18
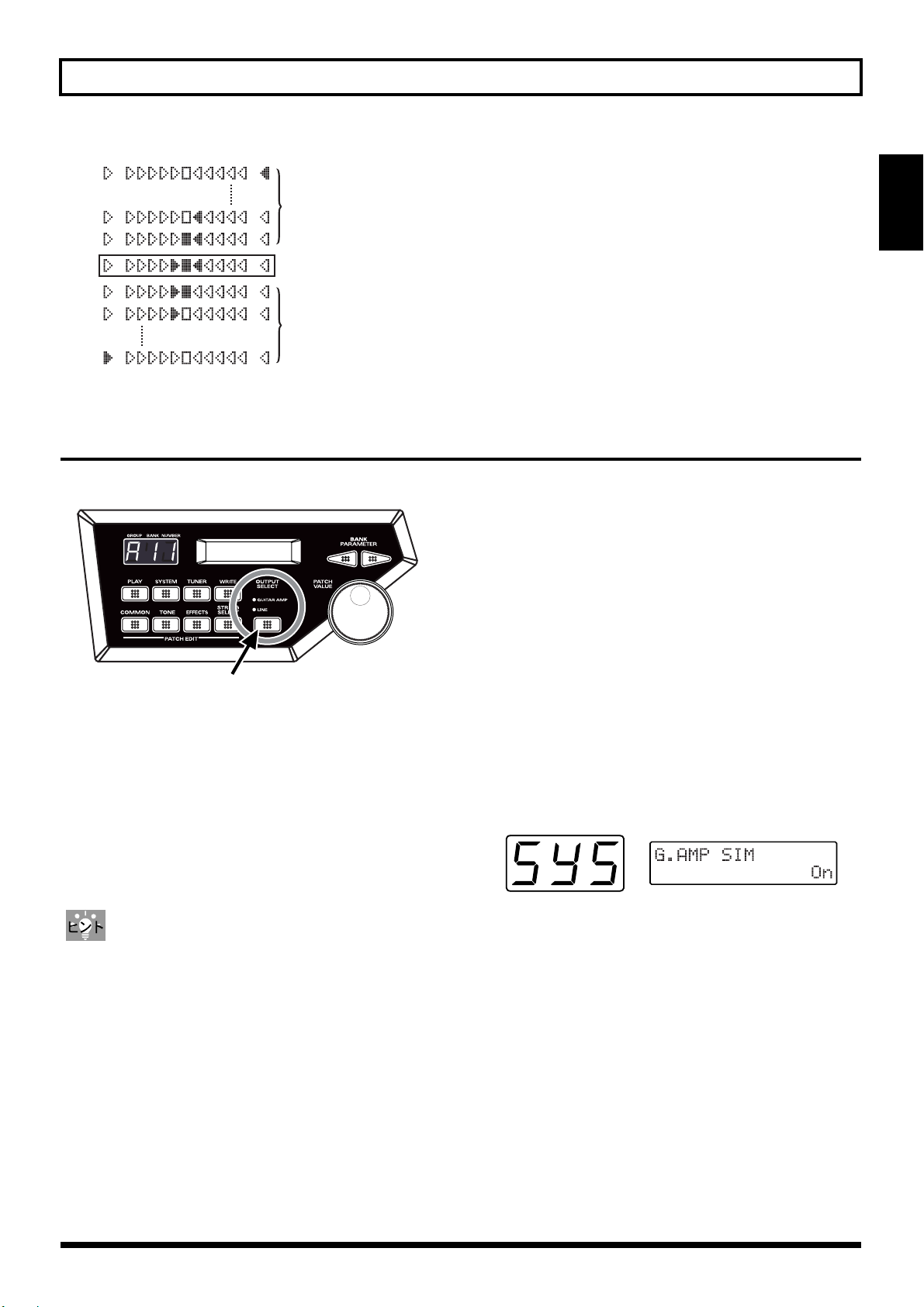
第 1 章 音を出す
fig.1-12(TUNER4)
高い状態
ジャスト・チューン
低い状態
同様にして、5 〜 1 弦をそれぞれ A、D、G、B、E にチュー
5.
ニングします。
チューニングが済んだら、任意のフッ ト・ペダルを踏む
6.
か、GK-2A の[S1]または[S2]を押すか、[PLAY]を
押して、プレイ・モードに戻ります。
出力する機器を設定する(OUTPUT SELECT)
出力(MIX OUT)に使用する機器を設定します。
fig.1-14(OUTPUT SELECT)
ギター・アンプ・シミュレーターを OFF にする(G.AMP SIM)
GR-33 にはギター・アンプ・シミュレーター(G.AMP SIM)
が内蔵されています。OUTPUT SELECT で「LINE」を選択
した場合は、ギター音のみにギター・アンプ・シミュレーター
がかかります。これによりギター本来の音は、ギター・アン
プで鳴らしているような効果を得ることができます。
1章
1.
[OUTPUT SELECT]を押して、設定を選択します。
現在選択されている設定が点灯します。
GUITAR AMP:
•
ギター専用アンプを接続する時に使います。
LINE:
•
キーボード用アンプ、汎用の楽器アンプ、ミキサー、
MTR、ヘッドホン等を接続する時に使います。
GR-33 の音源は幅広い音色を再現する PCM シンセサイザー
です。豊かなシンセ音を完全に再現するにはギター専用アン
プよりも、キーボード用や汎用の楽器アンプ、PA スピーカー
などを用いる方が有利です。
※ OUTPUT SELECT を変更しても、各パッチに記憶されて
いる設定内容が変更されることはありません。
外部エフェクターでアンプ・シミュレーターを使う時などで、
GR-33 に内蔵されているギター・アンプ・シミュレーターを
使わない場合は、以下の設定をしてください。
■ アンプ・シミュレーターをオフにする手順
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
[PARAMETER]を押して、G.AMP SIMを選びます。
2.
fig.1-15(G.AMP SIM.)
3.
[VALUE]でOffを選びます。
•
Off:
アンプ・シミュレーターを使いません。
On:
•
OUTPUT SELECT が「LINE」の時にアンプ・シミュレー
ターを使います。
[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。
4.
※ 再びアンプ・シミュレーターを使用するよ うに設定する
時は、手順 3. で「On」を選択してください。
19
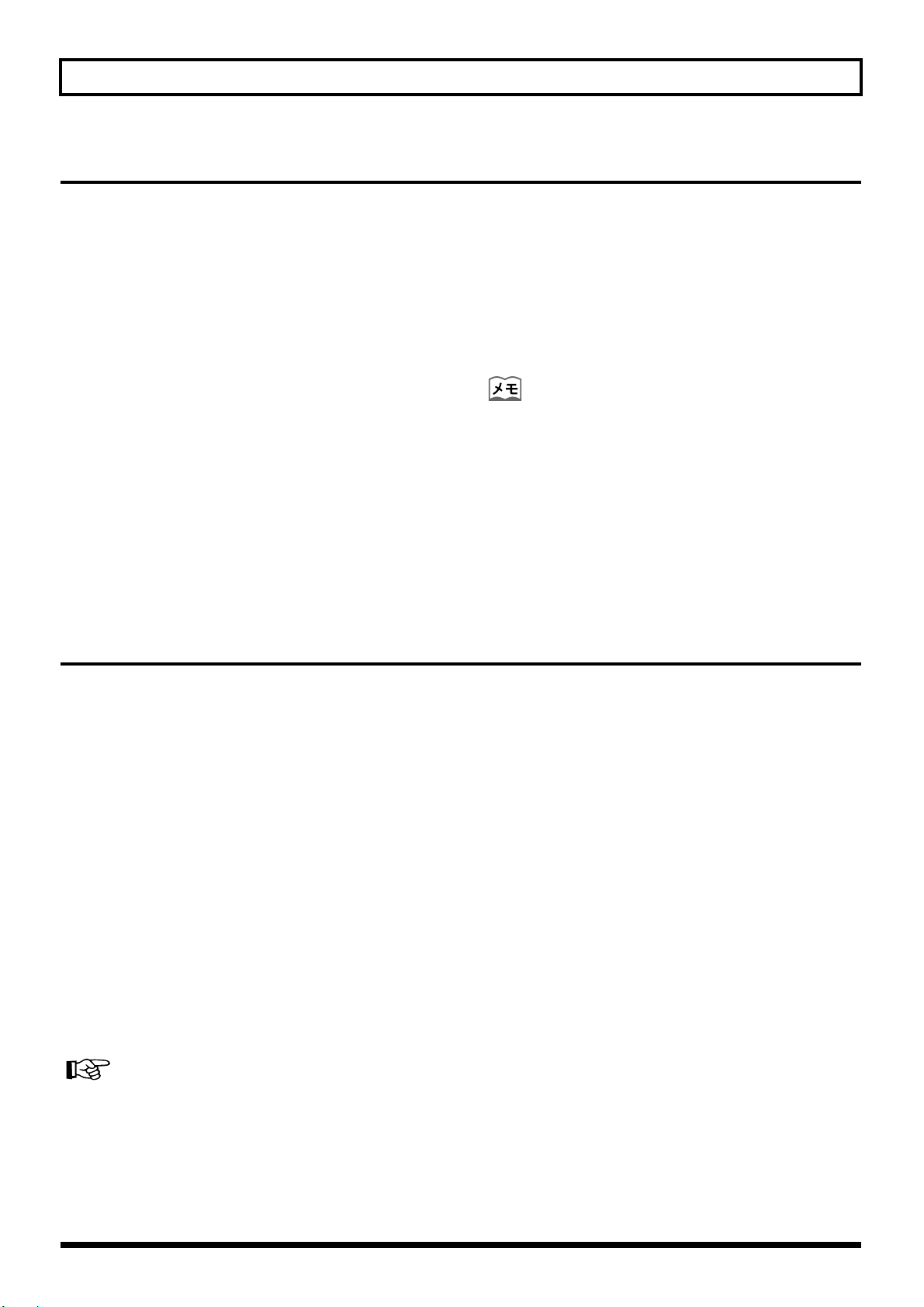
第 1 章 音を出す
ギターを弾いてシンセ音を鳴らす
アンプ類への接続を確認し、感度設定、ギターのチューニン
グが完了したら、ギターを弾いて音を出してみましょう。
■ ギターを弾いてシンセ音を鳴らす手順
1.
表示が電 源投 入時の状態(プレイ・モー ド)(P.15)に
なっているのを確認します。
GK-2A の切り替えスイッチを「SYNTH」に設定します。
2.
GK-2A のボリューム(SYNTH VOL)を右に回し、十分に
3.
上げます。
4.
GR-33 の本体ボリューム(VOLUME)を、真ん中付近に
合わせます。
ペダル 3 を踏むと表示が「A13」に変わり、パッチ(音色)
5.
が切り替わります。
以上で演奏の準備は整いました。アンプ側のボリュームつま
みを徐々に上げながらギターを弾けば、パッチ「A13」に設
定されている音色で、GR-33 の内蔵シンセ音源が鳴ります。
音が出ない場合は...
○ 通常のギターサウンドも出すには・・
GK-2A の切り替えスイッチを「MIX」に設定します。さ
らに「GUITAR」にする とシンセ音源側は消 音され、ギ
ター音だけになります。
○ シンセ音源の音量を変えるには・・
GK-2A の SYNTH VOL つまみ、または GR-33 本体の
VOLUME つまみで調整します。
GR-33 側の VOLUME つまみを操作すると、ミックス・アウ
トの全音量が変わります。従って、ミックス・アウトからギ
ター音も出力されている場合、ギター側の音量もシンセ音と
ともに変化します。(ギター・アウト・ジャックからの出力音
量は変化しません。またGK-2A のSYNTH VOL.つまみでは、
ギターの音量は一切変化しません。)
まず次の項目を再度確認してください。
•
アンプなどのボリューム、各機器間の接続(P.14)が正
しくまた確実か。
本体ボリューム、GK-2A のボリュームが下がっていない
•
か。また、ギター/シンセ切り替えスイッチが
「GUITAR」になっていないか。
○ 特定のパッチで全弦(または特定の弦)の音が 鳴らない
時は・・
•
エクスプレッション・ペダル(P.11)を、一番踏み込ん
だ状態にしてみる。
•
アンプにモノラル接続する場合は、必ず MIX OUT
ジャックの R (MONO) 側に接続する。
パッチ・エディット・モードの TONE の設定項目
•
「LAYER」で、全弦のシンセ音が消音されていないか
(P.51)。
弦によって音量がばらつく場合は、入力感度(PICKUP
SENS)の設定を再確認してください(P.17)。
20
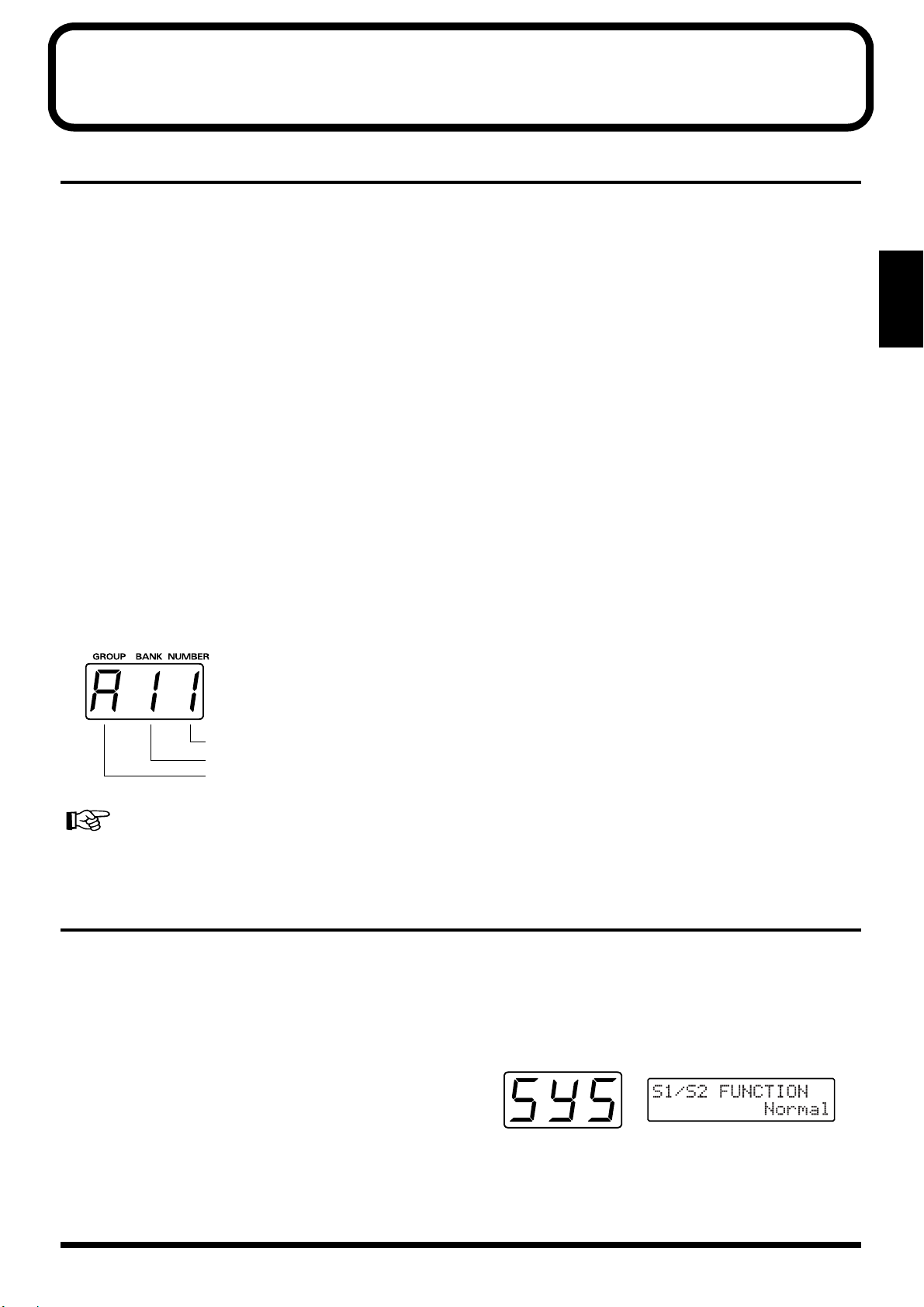
第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する
パッチとは?
「パッチ」は、ペダル・スイッチなどでいつでも呼び出し可能
な、GR-33 の音色の単位で、本体上に 256 個記憶されてい
ます。例えば電源投入直後の「A11」という表示は、パッチ
「A11」が呼び出されており、演奏可能な状態であることを示
しています。
本機の一番元になる音の単位は「トーン」です。トーンには
「GR Piano」「Pipe Organ 1」「Nylon Gtr mp 」といった様々
な音色波形があり、384 種類内蔵されています。(トーンの
選びかた→ P.49、トーン・リスト→ P.124)
パッチは、これらのトーンから 2 つまでを選んで組み合わせ、
音の明るさや立ち上がり、ギターとの音の高さの差など、各
種の設定や調整を加えたものです。設定や調整はユーザーが
曲に合うように自由に行うことができます。
また変更した結果は、128 パッチ(前半のパッチ)に書き込
んで保存することができます。(パッチについての 詳細→ P.
35 参照)
パッチ番号は「A 〜 H のアルファベット(グループ)」+「1
〜 8 の数字(バンク)」+「1 〜 4 の数字(ペダル上の番号)」
という 3 桁で表されます。
(例...A83、d24、F61 など)
fig.2-01(パッチ)
書き替え可能なパッチ(ユーザー・パッチ)
グループ A 〜 d のパッチ
(A11 〜 A84、b11 〜 b84、C11 〜 C84、d11 〜 d84)
ここには、演奏する曲や目的に合わせて、独自に作成したパッ
チを、記憶させておくことができます。
(お買い上げ時には、次項のプリセット・パッチと同じ内容の
128 パッチが書き込まれています。この状態に戻したい時は、
「工場出荷時の設定に戻す」の操作をしてください。→ P.16)
読み出し専用のパッチ(プリセット・パッチ)
グループ E 〜 H のパッチ
(E11 〜 E84、F11 〜 F84、G11 〜 G84、H11 〜 H84)
ここには、プリセット・パッチ(ローランドが用意した 128
個のパッチ)が収められています。読み出し専用なので、変
更しても同じパッチへは上書きできませんが、誤消去の心配
もありません。
プリセット・パッチは前半のユーザー・パッチと同じ感覚で
呼び出して使えます。またユーザー独自のパッチを作る参考
用や変更元としても便利です。
2章
1〜4までの数字(ペダル上の番号)
1〜8までの数字(バンク)
A,b,C,d,E,F,G,Hのアルファベット
(グループ)
001 〜 256 の通し番号表示にも切り替えられます。(P.24)
パッチを選ぶ
ギター(GK-2A)側で選ぶ
全パッチを順に聴いていきたい場合などでは、次の操作によ
り、ギター(GK-2A)側のスイッチ操作だけでパッチを選ぶ
ことができます。(本体のペダルなどに触れる必要はありませ
ん。)
■ ギター側でパッチを選ぶ手順
「SYSTEM」を押して、システム・モードに入ります。
1.
2.
[PARAMETER]を押して、S1/S2 FUNCTIONを選び
ます。
fig.2-02(S1/S2 FUNCTION1)
21
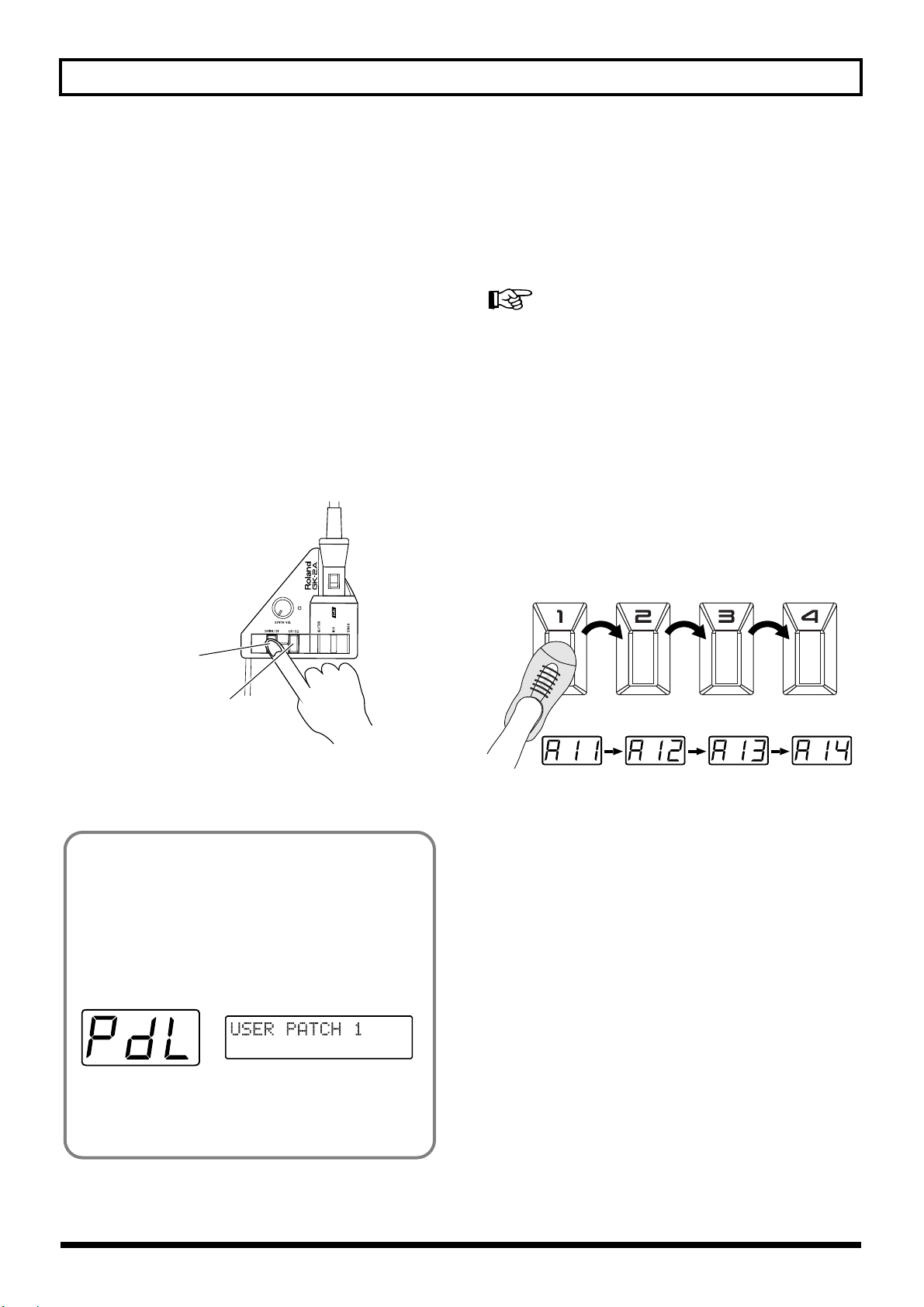
第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する
[VALUE]でPatch Selectを選びます。
3.
•
Patch Select:
GK-2A の[S1][S2]でパッチを連続的に切り替えるこ
とができます。
Normal:
•
通常の状態です。GK-2A でのパッチの切り替えはできま
せん。
4.
[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。
GK-2A の[UP/S2]を一回押す度に次のパッチへ進み、
5.
押さえたままにすると連続して切り替わ ります。さらに
他方(ここでは[DOWN/S1])のボタンを加えて押すと、
切り替わるスピード が早くなりま す。[S1]と[S2]の
ボタン操作を逆にすると、同様の動作で前の パッチに戻
ります。
fig.2-03(S1/S2 FUNCTION2)
本体の操作で選ぶ
ペダルで選ぶには
ペダルでパッチを選ぶには、「S1/S2 FUNCTION」が
「Normal」になっていないと選ぶことができません。
「S1/S2 FUNCTION」の設定は P.21 を参照してください。
○ 同じグ ルー プ/バンクのパ ッチ をペダルで呼 び出す に
は・・
ライブやスタジオ演奏の際は、本体上のペダルで、同じグルー
プ/バンク内の 4 つのパッチからひとつを瞬時に選ぶことが
できます。
プレイ・モードであることを確認します。
1.
プレイ・モードでない時は、[PLAY]を押します。
(パッチ番号ダウン)
S1
S2
(パッチ番号アップ)
それでは GK-2A のボタンを押してパッチを切り替え、ギター
を弾いて順に聴いてみましょう。
<この時ペダルを踏むと>
上記の状態で、本体の 4 つのペダルを踏むと、後述のペ
ダル効果、例えばホールドやピッチ・グライドなどが得
られます。(詳細 → P.28)こ れ を示す ため「S1/S2
FUNCTION」が「Patch Select」に選ばれている時には、
3 桁表示器に、パッチ番号と合わせて(約 4 秒に 1 回)、
PdLという表示が出ています。
fig.2-04(PdL)
またこの状態の時、外部バンク・シフト・ペダル(P.23)
の機能は、GK-2A の[S1][S2]と同じ「パッチ番号の
アップ/ダウン」に変わります。
2.
ペダル1 〜 4を踏むと、表示の一番下の桁が踏んだペダル
の数字に変わり、同グループ・同バンクの 4 個のパッチ
から、ひとつが瞬時に選ばれます。
fig.2-05(パッチ・チェンジ 1)
○ 他のグ ルー プ/バンクのパ ッチ をペダルで呼 び出す に
は・・
GK-2A の[S1]を併用し、ペダルの機能を 切り替えながら
行います。
プレイ・モードであることを確認します。
1.
プレイ・モードでない時は、[PLAY]を押します。
2.
GK-2A の[S1]を押したたまま、[GROUP ▲](ペダル
2)を踏みます。
[S1]を押さえている間だけ、ペダル 2 が次のグループ
へ進ませる働きに変わり、ペダルを踏むと 次のグループ
へ進みます。
※ グループを替えずに バンクだけを切 り替える場合は、2.
の操作は行わずに、3. の操作に進んでください。
22
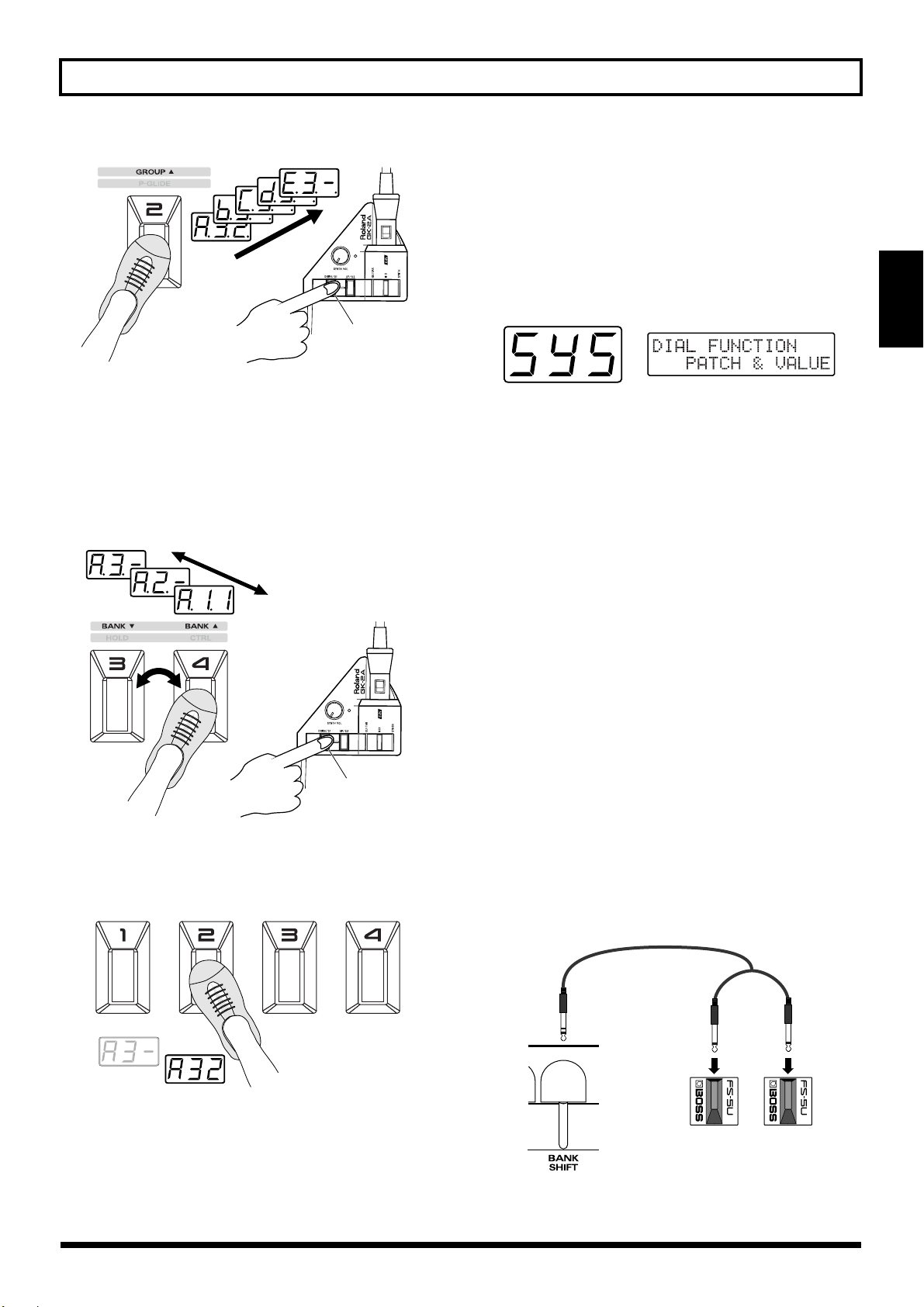
第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する
fig.2-06(パッチ・チェンジ 2)
S1を押したまま
3.
GK-2A の[S1]を押したたまま、[BANK ▲](ペダル 4)
または[BANK ▼](ペダル 3)を踏みます。
[S1]を押さえている間だけ、ペダル 4 が[BANK ▲]
(バンク・アップ)、ペダル 3 が[BANK ▼](バンク・ダ
ウン)の働きになります。表示が点滅に変 わり、ペダル
3、4 を踏むとバンク表示(2 桁目)がアップ、またはダ
ウンします。
fig.2-07(パッチ・チェンジ 3)
ダイヤルで選ぶには
ダイヤルでパッチを選ぶようにするには、以下のダイヤルの
設定が必要です。
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
[PARAMETER]を押して、DIAL FUNCTIONを選び
2.
ます。
fig.2-09(パッチ・チェンジ 5)
[VALUE]でPATCH&VALUEを選びます。
3.
•
PATCH&VALUE:
パッチ・ナンバーの切り替えと、エディッ ト中の設定の
変更の両方に使用します。
VALUE Only:
•
エディット中の設定の変更だけに使用します。
設定が終了したら、[PLAY]を押して プレイ・モードに
4.
戻ります。
プレイ・モ ード で、[VALUE]ダイヤル を回すこ とで、
A11 〜 H84 の 256 種類の全パッチを選ぶことができま
す。
2章
S1を押したまま
希望するグル ープ、バンク が選べたら、[S1]から手を
4.
離し、ペダルを踏みます。
踏むと同時にパッチが確定し、音色が切り替わります。
fig.2-08(パッチ・チェンジ 4)
また、[BANK/PARAMETER]で、バンクを順送り/順
戻しすることができます。
本体とフット・スイッチの操作で選ぶ
リア・パネルの BANK SHIFT ジャックに、フット・スイッ
チを接続すると、GK-2A の[S1]を押さずにバンクの切り
替えができます。
DP-5(別売)ではバンクのアップのみが、また 2 個の BOSS
FS-5U と分岐ケーブル PCS-31(別売)を併用すればアップ
とダウンの両方が、足元だけの操作で可能になります。
fig.2-10(フット・スイッチ)
PCS-31
赤
BANK
DOWN
白
BANK
UP
23
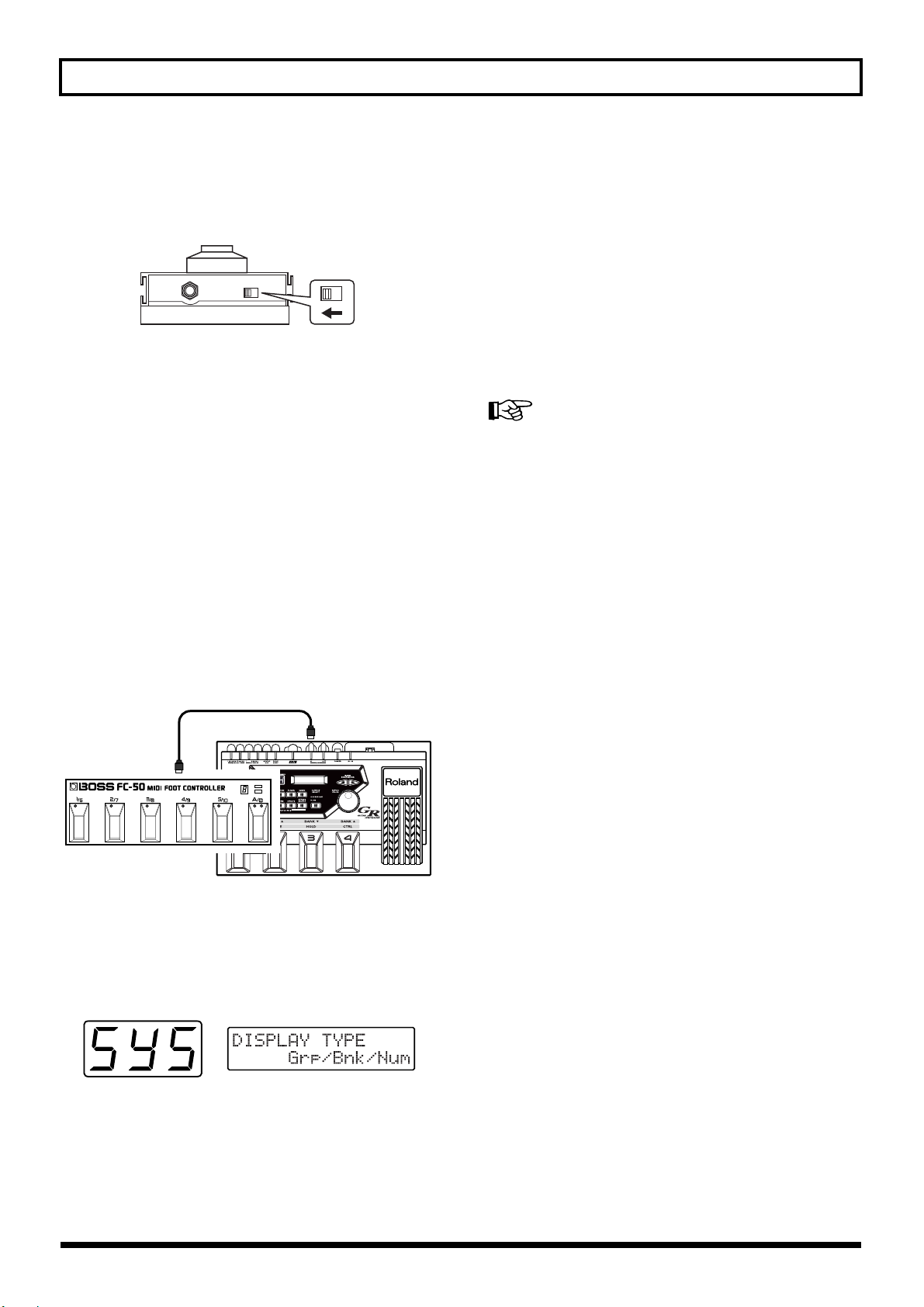
第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する
※ フット・スイッチをつけ外しする際、バンクが 切り替わ
り、パッチ番号が保留(点滅)状態になる場合 がありま
すが、故障ではありません。また、FS-5U のポラリティー・
スイッチは図のように設定してください。
fig.2-11(ポラリティー・スイッチ)
ポラリティー・スイッチ
※ 「S1/S2 FUNCTION」が「Patch Select」に合わされてい
る場合、上記のフット・スイッチの働きはパッ チのアッ
プ/ダウンに変わります(P.21)。
外部 MIDI フット・コントローラーで 選ぶ
本体の 4 つのペダルはホールドやワウなどのペダル効果(P.
26)専用にし、さらにパッチの切り替えも足で操作したい場
合があります。
この時 は、外 部 MIDI フット・コ ン トロー ラー(FC-200、
BOSS FC-50 など)と組み合わせると良いでしょう。
次の手順で設定してください。
1.
図に従って機器を接続します。
fig.2-12(MIDI フット・コントローラー)
MIDIIN
MIDIOUT
MIDIフット・
コントローラー
[VALUE]でDecimalを選びます。
4.
•
Decimal:
001 〜 256 の 10 進数でパッチ・ナンバーを表示します。
•
Grp/Bnk/Num:
A11 〜 H84 のグループ/バンク/ナンバーでパッチ・ナ
ンバーを表示します。
[PARAMETER]を押して、S1/S2 FUNCTIONを選び
5.
ます。
6.
[VALUE]でPatch Selectを選びます。
詳しい内容は、「パッチを選ぶ/ギター(GK-2A)側で選
ぶ」を参照してください。
[PLAY]ボタンを押して、プレイ・モードに戻ります。
7.
パッチ番号表示がA11でなく、001になります。
8.
MIDI フット・コントローラーの送信MIDI チャンネルを、
GR-33 側のチャンネル(P.86、お買い上げ時は「Mono11」)
に合わせます。
MIDI フット・コントローラーを取扱説明書に従って操作
9.
し、外部からパッチを切り替えます。
※ 手順 4. で設定した「パッチの通し番号表示」は、電源を
切っても記憶されています。必要な場 合は、パッチ番号
の表示をグループ/バンク/ナンバー式 に戻してくださ
い。
※ GR-33 が受信する MIDI プログラム・チェンジ番号と、そ
れによって呼び出されるパッチ(001 〜 128、A11 〜 d84)
は、先頭から順に 1 対 1 の対応に固定されており、変更
できません。(逆に、GR-33 側でパッチを選んだ時に外部
に送信される MIDI プログラム・チェンジ番号は、自由に
変更して各パッチに記憶させることができます(P.88)。
2.
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
パッチ番号の表示を、MIDI フット・コントローラー側の
表示に合わせて、001 〜 256 の通し番号にします。
3.
[PARAMETER]を押して、DISPLAY TYPEを選びます。
fig.2-13(DISPLAY MODE)
24
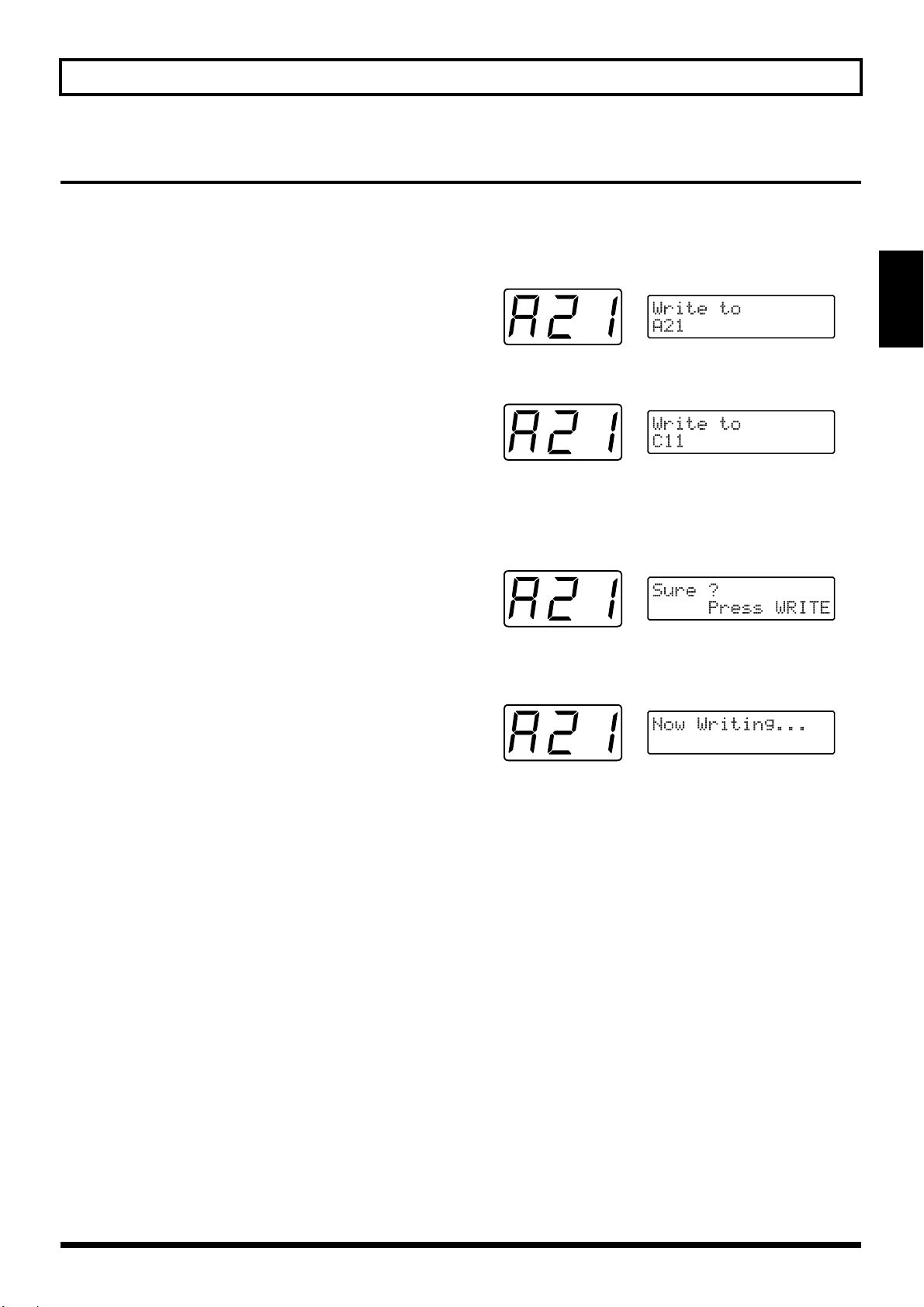
パッチの並び順を変える
第 2 章 音色(パッチ)を切り替えて演奏する
曲中やステージ中に切り替えて使うパッチを、同じグループ
/バンク上(例えば A11 〜 A14)に並べておけば、本体ペ
ダルを 1 回踏 むだけでスムーズに切り替えることがで きま
す。
パッチを並び変えるには、パッチ・ライト(書き込み)操作
(P.36)を使います。これは、現在選択中(または変更中)の
パッチの内容を、どのパッチ番号に書き込むかを指定するも
のです。
例:「A21」と「B62」の内容を入れ替えるには...
まずパッチ A21 の内容が失われない よう、使われていない
パッチ番号に退避します。(お買い上げ時、A 〜 d グループの
ユーザー・パッチは、E 〜 H グループのプリセット・パッチ
と同じ物ですので消してかまいません。)
その後、B62 → A21、待避先→ B62 と書き込む ことで、
「A21」と「B62」が入れ替わります。
1.
パッチ「A21」を選びます。
[WRITE]を押します。
2.
ライト・モードになり、次のような画面になります。
fig.2-14(WRITE TO1)
[VALUE]で書き込み先のパッチを選びます。
3.
fig.2-15(WRITE TO2)
ここでは書き込み先パッチを「C11」とした例です。
書き込み先パッチが決まったら、[WRITE]を押します。
4.
次のような確認の画面になります。
fig.2-16(WIRTE TO3)
2章
5.
確認をして問題がなければ、もう一度[WIRTE]を押し
ます。
fig.2-17(WRITE TO4)
Now Writing...と表示され、自動的にプレ イ・モード
に戻ると書き込み終了です。
上記の 1 〜 5 の、A21 →待避先(C11)と同じ要領で、B62
6.
→ A21 の書き込みをします。
7. さらに同様に待避先(C11)→ B62 の書き込みをすれば、
並べ替えは完了です。
※ パッチ・グループ E 〜 H は読み出し専用なので、並び替
えたり、待避先にすることはできません。(コピー元にす
ることはできます。)
25
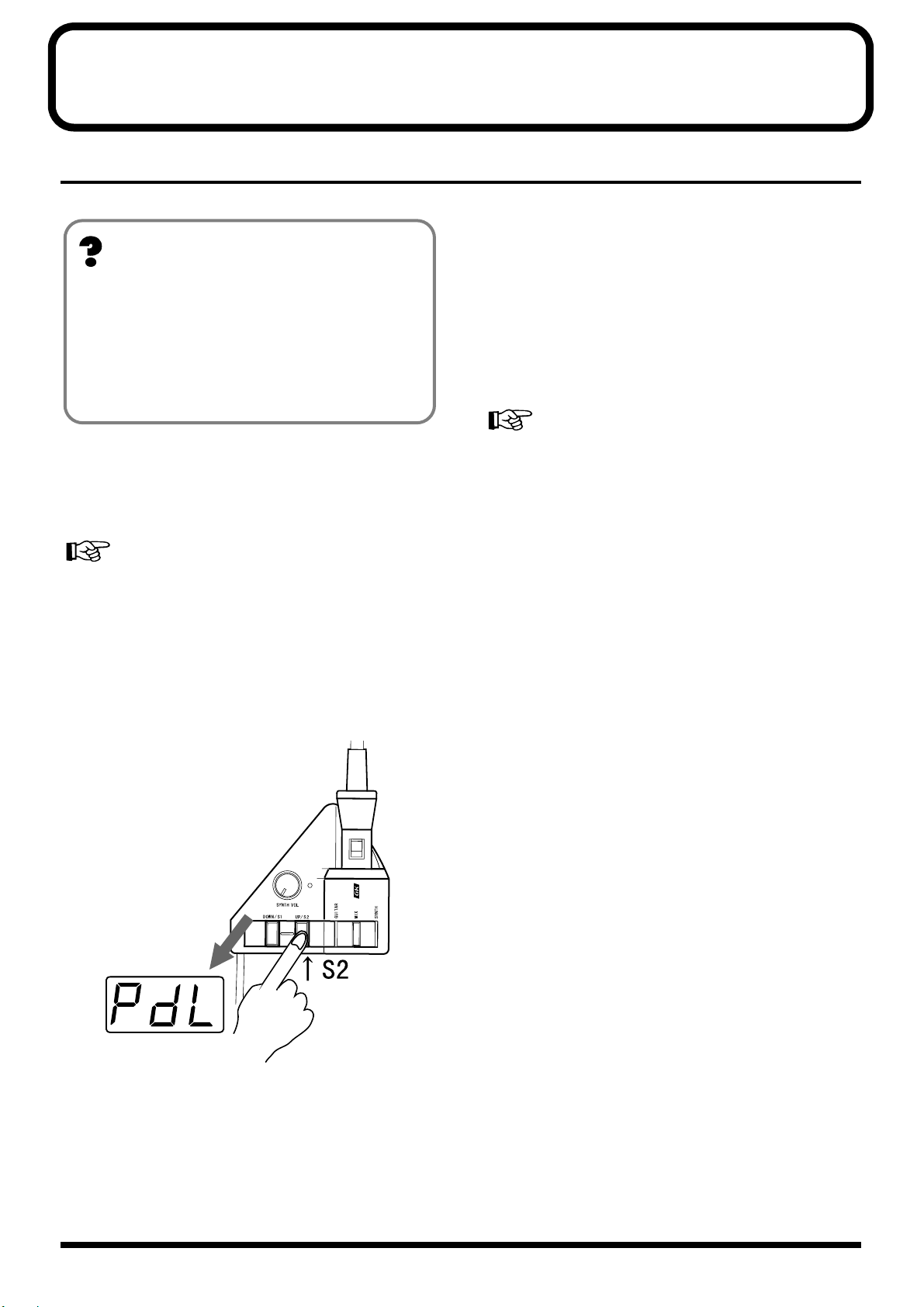
第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す
「ペダル効果モード」とその呼び出しかた
プレイ・モードのまま同じ効果を得る には
システム・モードの「S1/S2 FUNCTION」を「Patch Select」
ペダル効果モードとは
本体の 4 つのペダルで、アルペジエーター(またはハー
モニスト)をオン/オフしたり、シンセ音にホールドや
ワウ・ペダル風の効果を与えることができます。
この状態を「ペダル効果モード」といい、プレイ・モー
ドと切り替えながら、通常の演奏で使います。
■ ペダル効果モードにする手順
1.
[SYSTEM]を押してシス テム・モードに入り、「S1/S2
FUNCTION」を「Normal」にします。
にして、パッチ選択を GK-2A 側のボタンで行うようにした
場合は、プレイ・モードのままペダル効果を得ることができ
ます。この状態の場合、本体の 4 つのペダルの働きは、パッ
チ・チェンジでな く、ペダル効 果モードと同じになります。
(約 4 秒に 1 回「PdL」と表示され、ペダル効果も得られる
ことが示されます。)
詳しい操作方法は「パッチを選ぶ/ギター(GK-2A 側)で
選ぶ」(P.21)をご覧ください。
※ アルペジオのラッチ式ホールド(P.77)を除き、複数の
効果ペダルを同時に踏んだ場合の動作は 正常に行われな
い場合がありますのでご注意ください。
詳しい操作方法は「パッチを選ぶ/ギター(GK-2A 側)で
選ぶ」(P.21)をご覧ください。
[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。
2.
3.
GK-2A の[S2]を 1 回押します。
ペダル効果モードに移行し、3 桁表示器の表示がPdL
(ペダル)の点滅に変わります。
fig.3-01(ペダル効果モード)
プレイ・モードに戻るには、GK-2A の[S1]、[S2]の
いずれかを押します。
同じペ ダル を踏んでも、効果 のか かり具合はパ ッチ に
よって異なります。これらは曲や目的に合わせて変更し、
パッチに記憶させておくことができます。
各機能の詳細やかかり具合の変更のしかたについては、5
章(P.35 〜 P.52)をご覧ください。
26
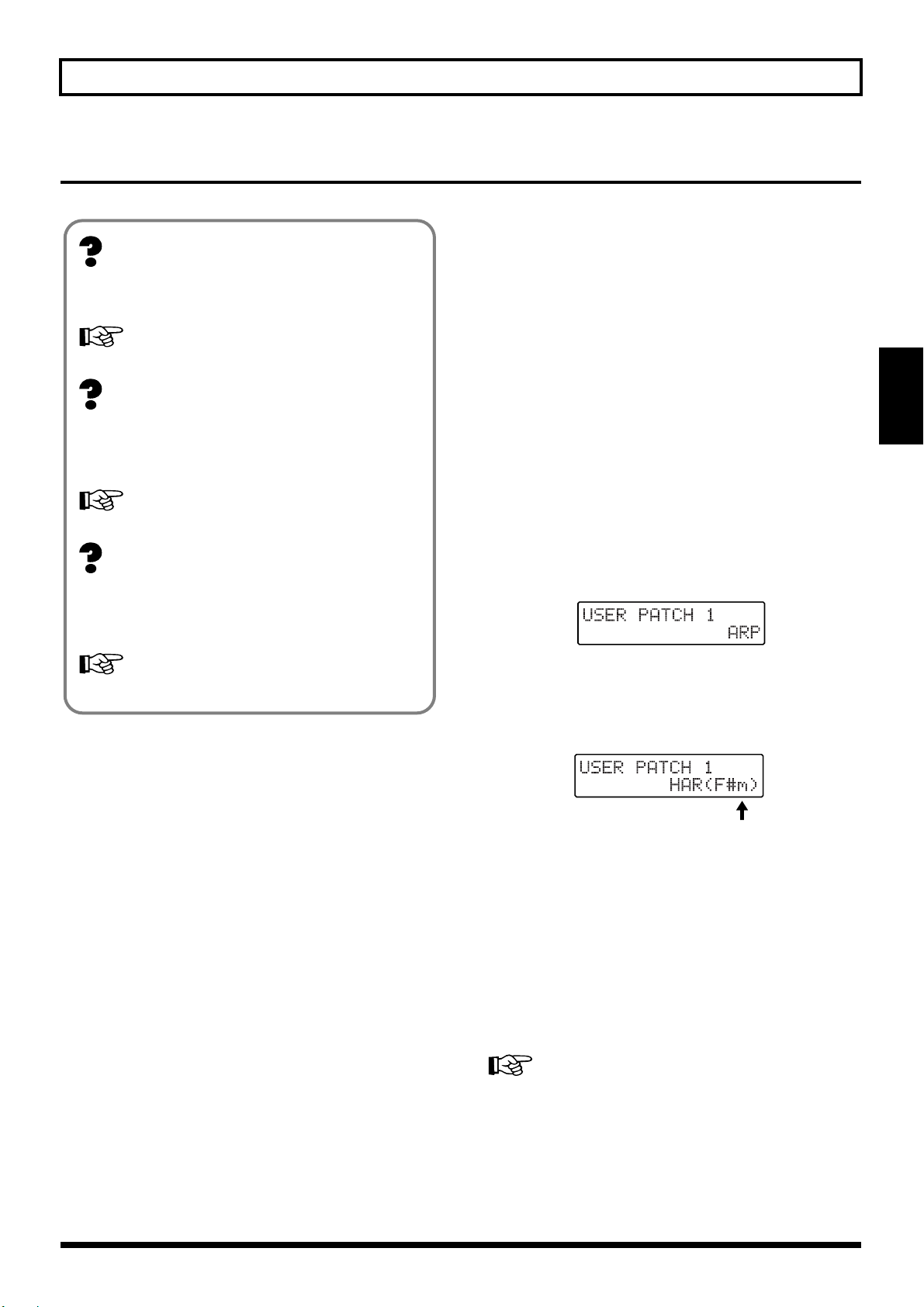
第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す
MULTI-FX、アルペジエーター/ハーモニストをオン/オフする
■ ペダルでオン/オフする手順
1.
ペダル効果モードに入ります(P.26)。(またはシステム・
モードの「S1/S2 FUNCTION」を「Patch Select」にし
MULTI-FX とは
てプレイ・モードに戻ります。)
シンセ音のための内蔵エフェクトです。
詳細については P.53 をご覧ください。
アルペジエーターとは
和音を演奏する だけで 自動的にアルペジオ(分散 和音)
効果が得られる機能です。
詳細については P.76 をご覧ください。
ハーモニストとは
ギター音とシンセ音(またはシンセ音同士)で、設定し
たキーのハーモニーを作れる機能です。
詳細については P.80 をご覧ください。
GR-33 には、MULTI-FX およびアルペジエーター機能とハー
モニスト機能が備わっており、これらのオン/オフをペダル
で行うことができます。
ペダル 4(CTRL)を踏みます。
2.
MULTI-FX BYPASS、アルペジエーター/ハーモニスト
のいずれか の設定さ れている機能がオン/オ フします。
設定は、パッ チ・エディ ット・モード「COMMON」の
「CTRL PEDAL」で行います(P.46)。
<表示の詳細について>
MULTI-FX BYPASS のオン/オフ
3 桁表示器に「bYP」/「oFF」が約 1 秒間表示されます。
アルペジエーターのオン/オフ
3 桁表示器に「Arp」/「oFF」が約 1 秒間表示されます。
オンの状態の時のディスプレイは次のようになります。
fig.3-10
ハーモニストのオン/オフ
3 桁表示器に「HAr」/「oFF」が約 1 秒間表示されます。
オンの状態の時のディスプレイは次のようになります。
fig.3-02
3章
※ パッチごとに、MULTI-FX BYPASS(マルチ・エフェク
トのバイパス機能)のオン/オフか、アルペジ エーター
/ハーモニストのオン/オフのどちらかを設 定すること
ができます。設定方法については、P.46 をご覧ください。
※ MULTI-FX BYPASS をオン/オフしたときにノイズが聞
こえる場合がありますが、故障ではありません。
キー
アルペジエーターとハーモニストはパッ チごとにどちら
か一方だけが選べるようになっていま す。オフのパッチ
も、内部ではアルペジエーターかハーモニ ストのどちら
かが選ばれています。オンの状態の時 に、ディスプレイ
で選ばれている機能が確認できます。ハー モニストが選
ばれている時は、キーも表示されます。
※ アルペジエーターのパッチをハーモニ ストに(またはそ
の逆に)切り替えたい時は、[EFFECTS]を押して「HAR/
ARP SELECT」を変更してください。
詳しい操作方法は、(P.78、82)をご覧ください。
27
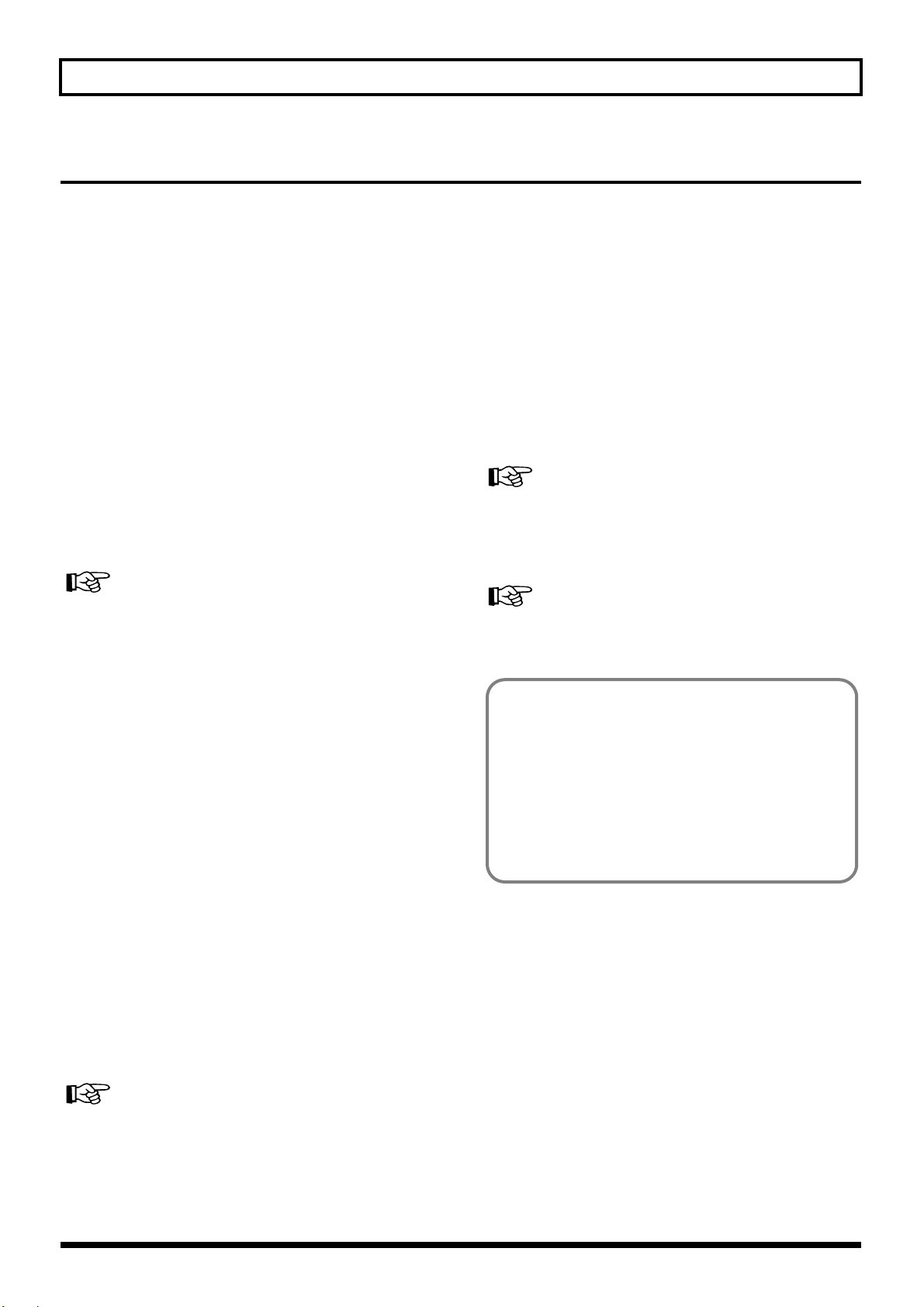
第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す
本体のペダルで音を変化させる
ペダル効果モード(P.26)で 1 〜 4 の各ペダルを踏むと、次のような効果が得られます。
ペダル・ワウのような効果を得る(ワウ)
ペダル 1(WAH)を踏むと「ワウ」に代表される数種類の効
果が得られます。ペダルの「踏む/離す」を繰り返すことに
より、ギター用のワウワウ・ペダルと似たような音色変化を、
シンセ音に与えることができます。
音色変化の速度、幅、方向、音のクセの強さなどの組み合わ
せは、用意されたバリエーションから選択し、パッチごとに
保存できます。
なお「WAH TYPE」で「Modulation」を 選ぶと、ワウ系 の
効果ではなく、ペダルを踏んでいる間、深いビブラート(ピッ
チのうねり)が得られます。この機能では、いかにもシンセ
サイザーらしい機械的なビブラートが得られるので、フィン
ガー・ビブラート奏法をした時に得られる人間的な揺らぎと
使い分けることができます。
詳しい操作方法は「ワウの効き方を選ぶ(WAH TYPE)」
(P.43)をご覧ください。
※ ペダル 1(WAH)を 1 度踏むと、以後ペダルを離した状
態の時、パッチ呼び出し時の状態と異なる音 になる場合
があります。(音がこもったり、音にクセがついたりしま
す。)これを元の音に戻すには、一度他のパッチに切り替
えてから、元のパッチを呼び出し直し ます。バンク・シ
フト・ペダルが接続されている時は、そのダウ ン側をペ
ダル効果モード中に踏むことでも、元の音に戻せます。
弦が止まってもシンセ音を保持させる
(ホールド)
ペダル 3(HOLD)を踏むと、「ホールド」効果が得られます。
この効果を使うと、ギター弦の振動が止まっても、シンセ音
を鳴らし続けることができます。
「シンセ音の和音をホールドし、ギター音でメロディを弾く」
「重なった 2 音色(トーン)の一方だけをホールド」「5、6 弦
だけホールド」などの、目的に合ったものを、用意されたバ
リエーションから選び、パッチごとに保存できます。
詳しい操作方法は「ホールドの効き方を選ぶ(HOLD
TYPE)」(P.45)をご覧ください。
※ アルペジエーターがオンの時のホール ドは、挙動や選べ
るバリエーションが、通常と異なります。
詳しい操作方法は「アルペジオ中のホールド機能の有効な使
い方」(P.76)をご覧ください。
<表示の詳細について>
ペダル 1(WAH)を踏むと
3 桁表示器に「UAH」または「Mod」と表示されます。
ペダル 2(P-GLIDE)を踏むと
3 桁表示器に「P.GL」と表示されます。
音高をダイナミックに変化させる
(ピッチ・グライド)
ペダル 2(P-GLIDE)を踏むと、「ピッチ・グライド」効果が
得られます。この 効果では、長 短様々な変化時間をかけた、
連続的な音高変化が得られます。
和音時、各音間の音程を保ったままピッチを大きく変化でき
るので、ギターのビブラート・アームのアップ/ダウンとも
異なった、独得の効果が得られます。
「どの位の時間をかけて、どれだけピッチを変化させるか」は、
ピッチの上昇/下降に各 7 種類用意されたパターンから選択
し、パッチごとに保存できます。
詳しい操作方法は「ピッチ・グライドの効き方を選ぶ
(GLIDE TYPE)」(P.44)をご覧ください。
※ 選ばれた音色やその設定、演奏状況などに よっては、変
化幅が制限される場合があります。
28
ペダル 3(HOLD)を踏むと
3 桁表示器に「HLd」と表示されます。
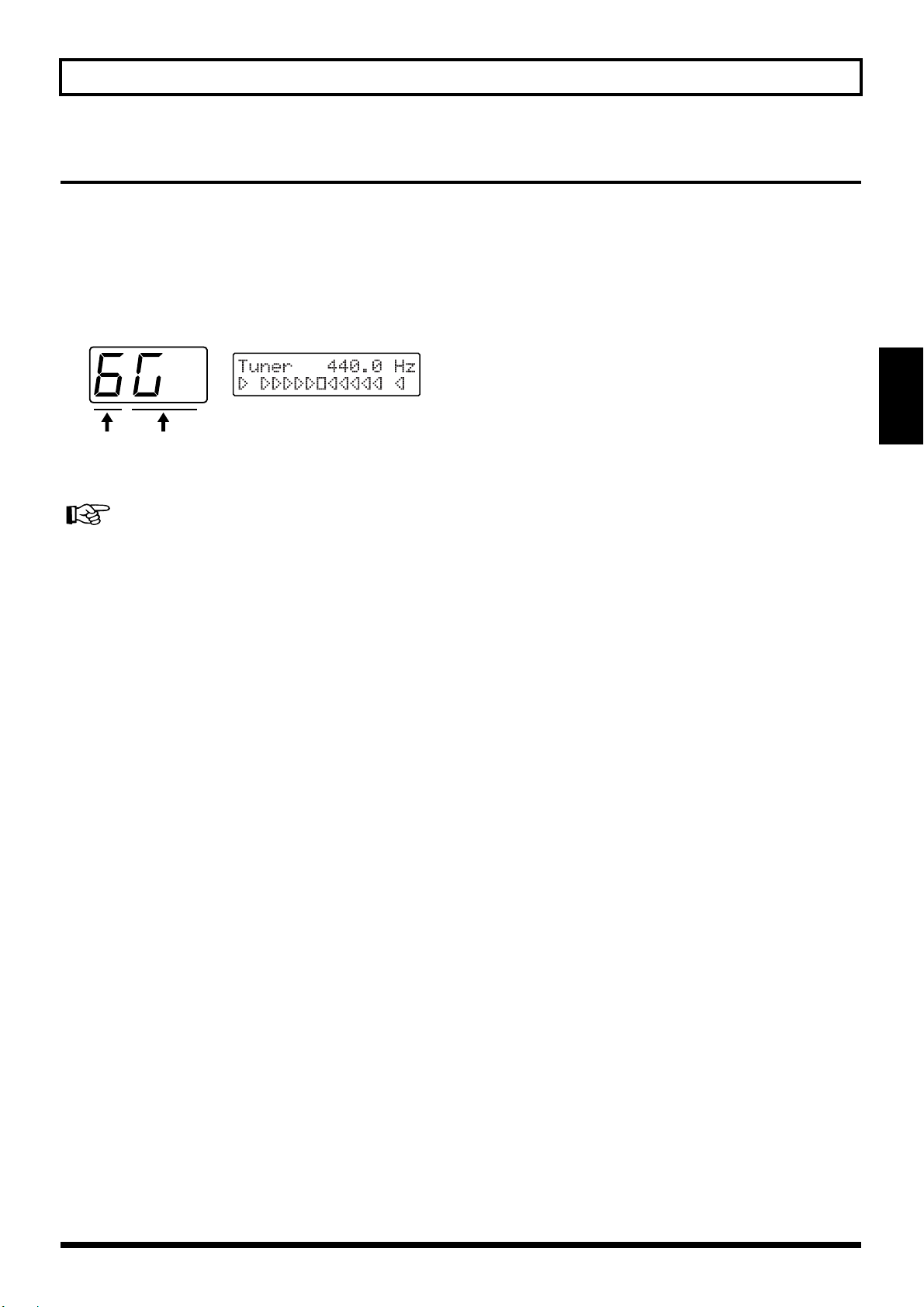
チューナー機能をペダルで呼び出す
1.
GK-2A の[S1]を押しながら、ペダル 1(TUNER)を踏
みます。
※ 「S1/S2 FUNCTION」が「Normal」の状態で、操作を行っ
てください。
チューナー機能が呼び出され、図のような表 示になりま
す。
fig.3-03(TUNER)
音名弦番号
2.
チューニングをします。
第 3 章 本体ペダルによる機能や効果を試す
3章
チューニングの操作方法は、「ギターのチューニングをする
(チューナー機能)」(P.18)をご覧ください。
3.
チューニングが終わったら、任意のフット・ペ ダルを踏
むか、GK-2A の[S1]または[S2]を押します。
プレイ・モードに戻ります。
29
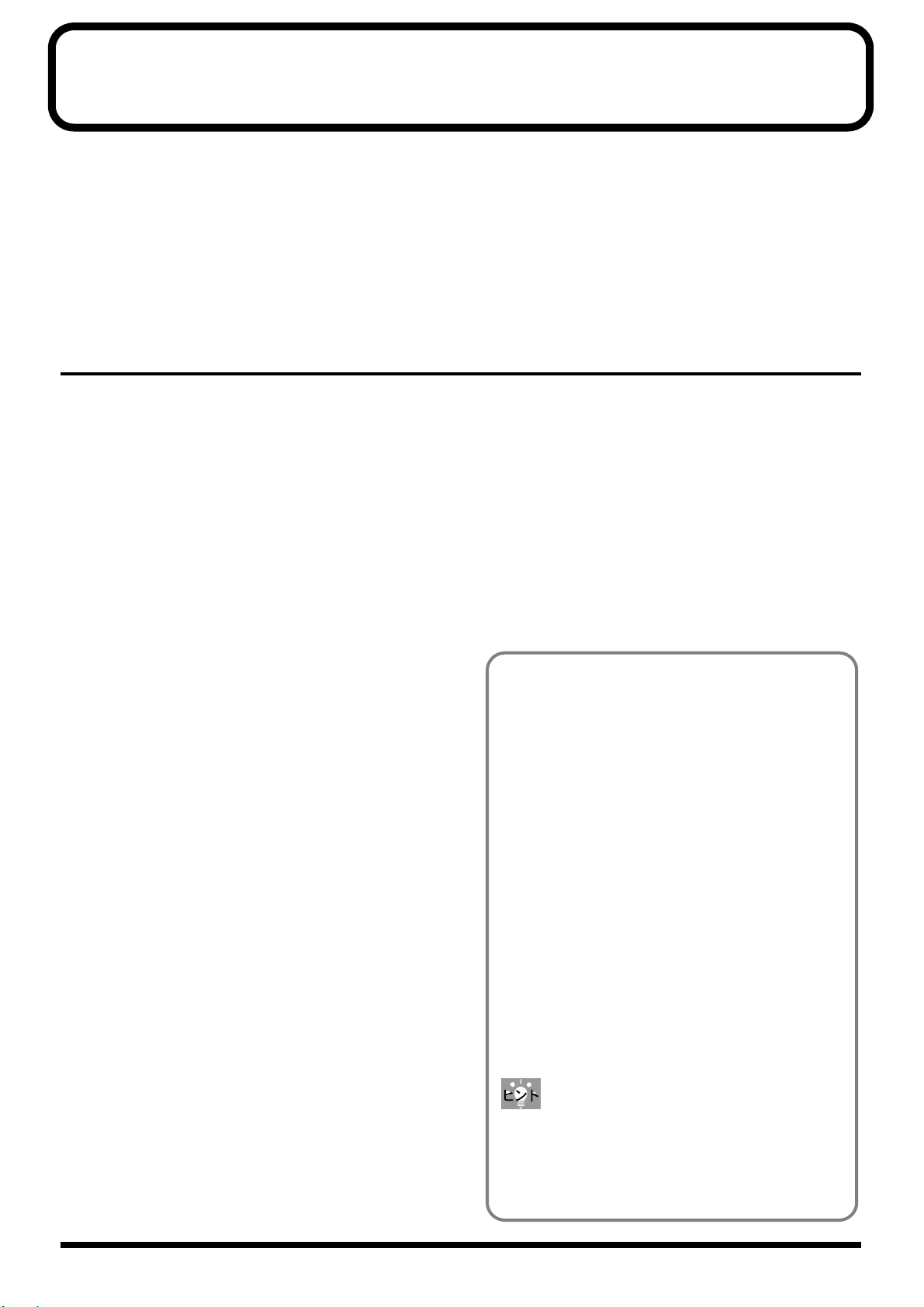
第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作
GR-33 本体の主な動作状態には、
•
音色を選んで演奏する「プレイ・モード」
•
本体上のペダルでワウやホールドの効果を得る「ペダル
効果モード」
•
パッチを作成/修正したり、書き込んだりする「パッチ・
エディット・モード」
プレイ・モードでの操作
プレイ・モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通りで
す。
[BANK/PARAMETER]ボタン
バンクの順送り/順戻し。
[PLAY]ボタン
原則として、無視される。
[SYSTEM]ボタン
システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。
[TUNER]ボタン
チューナー・モードに変わる(P.18)。
GR-33 本体の設定をする「システム・モード」
•
チューニングをする「チューナー・モード」
•
の 5 つがあり、それぞれによってボタンやつまみの働きが変
化します。
エクスプレッション・ペダル
設定されている項目の値を変化させる(P.47)。
GK-2A の[S1]
押さえている間ペダルの働きが変化する(P.22、29)。
(TUNER、GROUP ▲、BANK ▲、BANK ▼)
GK-2A の[S2]
ペダル効果モードに変わる(P.26)。
外部バンク・シフト・ペダル
パッチのバンクを切り替える。
(BANK ▼、BANK ▲と同じ働き)
[WRITE]ボタン
パッチの内容を書き込む(P.36)。
[COMMON]ボタン
パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関
連)に変わる。
[TONE]ボタン
パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)
に変わる。
[EFFECTS]ボタン
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ
クト関連)に変わる。
[STRING SELECT]ボタン
原則として、無視される。
[OUTPUT SELECT]ボタン
出力機器の設定を切り替える(P.19)。
[PATCH/VALUE]ダイヤル
パッチの順送り/順戻し(P.23)。
「S1/S2 FUNCTION」で「Patch Select」を選んで
いる場合
「S1/S2 FUNCTION」で「Patch Select」を選んでいる
状態にすると、パッチ番号が GK-2A の S1/S2 ボタンだ
けで順送り/順戻しができるようになります。以下のボ
タンの働きは、通常のプレイ・モードから次のように変
わります。
※ 記述されていないボタンやダイ ヤルの働きは、通常
のプレイ・モードと同じ働きです。
ペダル 1 〜 4
ペダル効果モード(P.31)と同じ効果が得られる。
GK-2A の[S1]
パッチの順戻し。
GK-2A の[S2]
パッチの順送り。
外部バンクシフト・ペダル
パッチの順送り/順戻し。
※ 「DIAL FUNCTION」が「VALUE Only」に設定されてい
る場合は、無視されます。
ペダル 1 〜 4
パッチを切り替える(P.22)。
30
この設定は、パッチを順に聴いて確認したい時や、ホー
ルドなどのペダル効果とパッチ切り替えの両方を、モー
ド切り替えせずに行いたい時に選ぶと便利です。この状
態の時、3 桁表示器にはパッチ番号に併せて、約 4 秒に
1 回PdLと表示されます。

ペダル効果モードでの操作
第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作
ペダル効果モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通り
です。
なおペダル 1 〜 4 を踏んで得られる効果の詳細はパッチごと
に変えることができます。ユーザー・パッチ(A11 〜 d84)
では効き方を変更し、記憶させ直すこともできます。
[BANK/PARAMETER]ボタン
バンクの順送り/順戻し。
[PLAY]ボタン
プレイ・モードに戻る。
[SYSTEM]ボタン
システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。
[TUNER]ボタン
チューナー・モードに変わる(P.18)。
[WRITE]ボタン
パッチの内容を書き込む(P.36)。
[COMMON]ボタン
パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関
連)に変わる。
[TONE]ボタン
パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)
に変わる。
[EFFECTS]ボタン
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ
クト関連)に変わる。
[STRING SELECT]ボタン
原則として、無視される。
ペダル 1
WAH →ワウ・ペダルに似た効果や機械的な ビブラートなど
がかかる。
ペダル 2
P-GLIDE →ピッチ・グライド(音高を大幅かつ滑らかに変え
る効果)をかける。
ペダル 3
HOLD →ギター弦の振動が止まってもシンセ音が鳴り続ける
効果をかける。
ペダル 4
CTRL → MULTI-FX BYPASS のオン/オフ、またはアルペ
ジエーター(P.76)/ハーモニス ト(P. 80)をオン/オフ
する。またアルペジオのホールド時(P. 76)、その補助的な
ペダルとして使う。
エクスプレッション・ペダル
設定されている項目の値を変化させる(P.47)。
GK-2A の[S1]と[S2]
押すとプレイ・モードに戻る。
外部バンクシフト・ペダル(アップ側)
アルペジエーターのタップ・テンポ・ティーチ機能に使う(P.
79)。またはハーモニストのメジャー/マイナーを切り替え
る(P.85)。
外部バンク・シフト・ペダル(ダウン側)
ワウ機能で変化したままになった音をパッチ呼び出し時の音
に戻す。(通常のパッチ切り替え操作によっても元の音に戻り
ます。)
4章
[OUTPUT SELECT]ボタン
出力機器の設定を切り替える(P.19)。
[PATCH/VALUE]ダイヤル
パッチの順送り/順戻し(P.23)。
※ 「DIAL FUNCTION」が「VALUE Only」に設定されてい
る場合は、無視されます。
31

第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作
パッチ・エディット・モードの意味とその操作
各パッチの設定や音作りなどをするモードです。
パッチ・エディット・モードは、COMMON、TONE、EFFECTS
の 3 つのカテゴリーに分類されています。
fig.4-01(パッチ・エディット・モード)
パッチ・エディット・モード
EFFECTSTONECOMMON
•
COMMON
パッチの名前やペダルの効果などの設定をします。
TONE
•
シンセ音の基本となる音色(トーン)を設定します。
EFFECTS
•
リバーブ、コーラス、マルチ・エフェクトなど のエフェ
クトの設定をします。
アルペジエーター/ハーモニストの設定もこ こで行いま
す。
パッチ・エディット・モードでの各ボタン/つまみの働きは、
次の通りです。
[BANK/PARAMETER]ボタン
設定項目(パラメーター)が順送り/順戻しで変わる。
[PLAY]ボタン
プレイ・モードに戻る。
[SYSTEM]ボタン
システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。
[TUNER]ボタン
チューナー・モードに変わる(P.18)。
[EFFECTS]ボタン
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ
クト関連)に変わる。
※ EFFECTS(パ ッ チのエフェクト関連)の状態で、
[EFFECTS]を押した場合は、バイパス機能がオン/オ
フします(P.75)。
[STRING SELECT]ボタン
各弦で設定を変更できる設定項目の場合は、設定対象となる
弦を選ぶ。
※ 各弦で設定を変更できない設定項目の 場合は、無視され
ます。
[OUTPUT SELECT]ボタン
出力機器の設定を切り替える(P.19)。
[PATCH/VALUE]ダイヤル
選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。
ペダル 1 〜 4
いくつかの設定項目において、効果の確認などに補助的に使
われる。
エクスプレッション・ペダル
いくつかの設定項目において、効果の確認などに補助的に使
われる(P.47)。
GK-2A の[S1]と[S2]
選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。
外部バンク・シフト・ペダル
選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。
[WRITE]ボタン
パッチの内容を書き込む(P.36)。
[COMMON]ボタン
パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関
連)に変わる。
※ COMMON(パッチの設定関連)のパッチネーム設定画面
では、大文字/小文字の切り替えをします(P.38)。
[TONE]ボタン
パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)
に変わる。
※ TONE(パッチの音色関係)の状態で、[TONE] を押した
場合は、設定項目の 1ST / 2ND の切り替えをします。
32
エディット・モードで、呼び出されているパッチの設定を 1ヶ
所でも変更すると、3 桁表示器の表示が変化します。下 1 桁
目のポイントが点灯し、設定が変更されていることを示しま
す。
fig.4-02(エディット中)
パッチ・エディット・モード時の場合
ポイント
新しい設定を記憶させる時は、ライト(書き込 み)操作(P.
36)を行ってください。
※ ライト(書き込み)操作を行わずにパッチ を切り替える
と、変更内容が失われます。
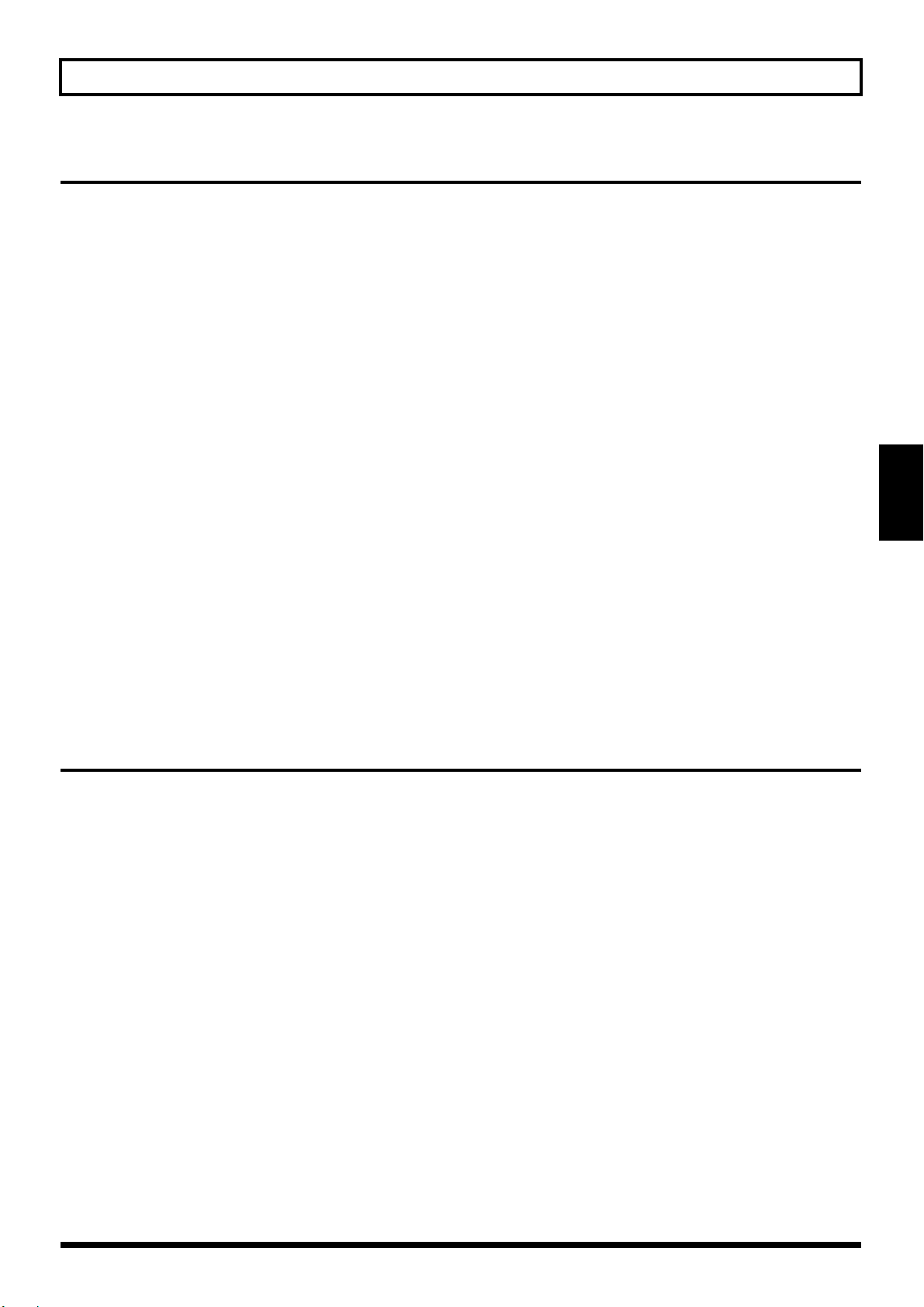
システム・モードでの操作
第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作
GR-33 本体の設定をするモードです。入力感度やディスプレ
イの明るさなど、パッチを切り替えても変更しない全体の設
定をします。
システム・モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通り
です。
[BANK/PARAMETER]ボタン
設定項目(パラメーター)が順送り/順戻しで変わる。
[PLAY]ボタン
プレイ・モードに戻る。
[SYSTEM]ボタン
原則として、無視される。
[TUNER]ボタン
チューナー・モードに変わる(P.18)。
[WRITE]ボタン
パッチの内容を書き込む。「BULK LOAD」では無視する
(P.37)。「BULK DUMP」、「FACTORY RESET」では実行開
始や確認に使用する(P.37、16)。
[COMMON]ボタン
パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関
連)に変わる。
[TONE]ボタン
パッチ・エディット・モー ドの TONE(パッ チの音色関連)
に変わる。
[EFFECTS]ボタン
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ
クト関連)に変わる。
[STRING SELECT]ボタン
原則として、無視される。
[OUTPUT SELECT]ボタン
出力機器の設定を切り替える(P.19)。
[PATCH/VALUE]ダイヤル
選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。
ペダル 1 〜 4
原則として、無視される。
エクスプレッション・ペダル
原則として、設定されている項目の値を変化させる(P.47)。
GK-2A の[S1]と[S2]
選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。
外部バンクシフト・ペダル
選ばれている設定項目(パラメーター)の値を変える。
4章
チューナー・モードでの操作
チューナー・モードでの各ボタン/つまみの働きは、次の通
りです。
[BANK/PARAMETER]ボタン
原則として、無視される。
[PLAY]ボタン
プレイ・モードに戻る。
[SYSTEM]ボタン
システム・モード(GR-33 本体の設定関連)に変わる。
[TUNER]ボタン
原則として、無視される。
[WRITE]ボタン
原則として、無視される。
[COMMON]ボタン
パッチ・エディット・モードの COMMON(パッチの設定関
連)に変わる。
[TONE]ボタン
パッチ・エディット・モード の TONE(パッチ の音色関連)
に変わる。
[EFFECTS]ボタン
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(パッチのエフェ
クト関連)に変わる。
[STRING SELECT]ボタン
原則として、無視される。
[OUTPUT SELECT]ボタン
出力機器の設定を切り替える(P.19)。
[PATCH/VALUE]ダイヤル
「MASTER TUNE」の値を変える。
ペダル 1 〜 4
チューナー・モードを抜けて、プレイ・モードに戻ります。
エクスプレッション・ペダル
原則として、設定されている項目の値を変化させる(P.47)。
GK-2A の[S1]と[S2]
チューナー・モードを抜けて、プレイ・モードに戻ります。
外部バンクシフト・ペダル
チューナー・モードを抜けて、プレイ・モードに戻ります。
33
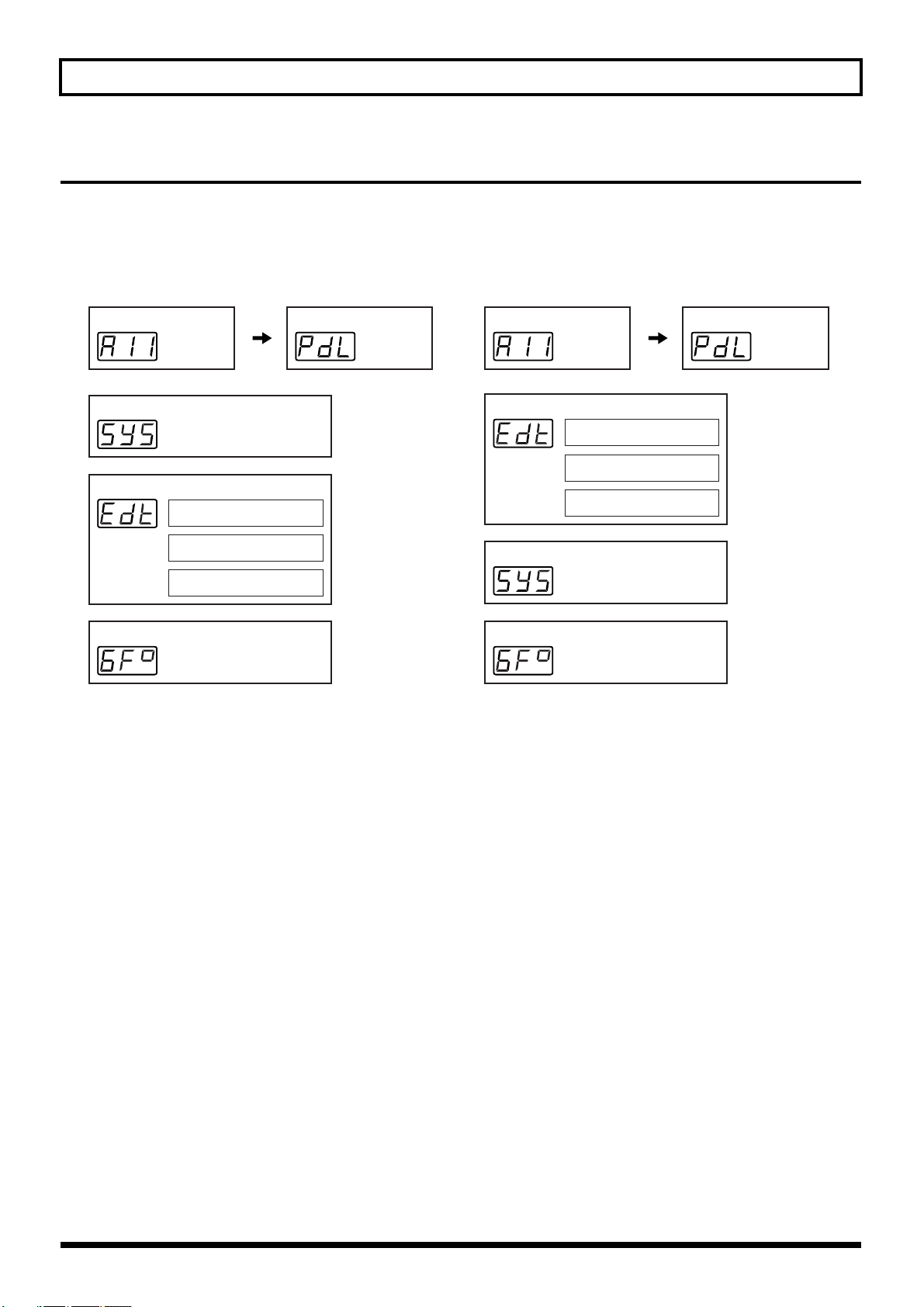
第 4 章 基本となる 5 つのモードとその操作
各モード間の行き来のしかた
ここで はプ レイ・モード、ペダ ル効 果モード、パッ チ・エ
ディット・モード、システム・モード、チューナー・モード
の 5 つのモードの行き来について説明します。
fig.4-03(モード間の行き来)
[S2]
プレイ・モード[PLAY
システム・モード
パッチ・エディット・モード
COMMON[COMMON
TONE
EFFECTS[EFFECTS
チューナー・モード
]
ペダル効果モード
[
SYSTEM
[
TONE
[
TUNER
]
]
]
]
]
ペダル効果モード以外のモードは、GR-33 本体のボタン一つ
で、どのモードからでも目的のモードに入ることができます。
次の図に、それぞれのモードに対応しているボタンと、各モー
ドの 3 桁表示器の状態を示します。
GK-2Aの
[S2]
プレイ・モード[PLAY
パッチ・エディット・モード
COMMON[COMMON
TONE
EFFECTS[EFFECTS
システム・モード
チューナー・モード
][
ペダル効果モード
]
[
]
TONE
]
[
SYSTEM
[
TUNER
]
]
S2
]
※ ペダル効果モードには、プレイ・モードからし か入るこ
とはできません。
※ 「S1/S2 FUNCTION」が「Normal」に設定されていない
と、ペダル効果モードに入ることはできません。
34

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
パッチの詳しい構成
ひとつひとつのパッチは、図のような内容で構成されています。
fig.5-01(パッチの構成)
プリセットパッチ128個
...
H84
・レイヤー
1st,2ndトーンの重ね方
・トランスポーズ1st
・トランスポーズ2nd
・1:2BALANCE
1st/2ndのレベルバランス
TONE
TONE MIX
各弦独立に
設定可能
・アルペジオやハーモニーの設定
・リバーブ系/コーラス系の設定
・MultiFXの設定
COMMON
・
パッチネーム、レベルの設定など
・PANの設定
・ペダルの設定
・MIDIの設定
EFFECTS
ユーザーパッチ128個
...
A11
D84
A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11
2nd TONE
1st TONE
トーンの選択
#1〜#384
(ピアノ、オルガン...)
トーンの調節
・アタック
・リリース
・ブライトネス
E11
「トーン」とは?
上図のようにパッチには、内蔵されている 384 のトーン(元
となるシンセ音)から、任意の 2 つを選んで使えます。
選ばれている 2 つのトーンを、そのパッチの「1st(ファー
スト)トーン」「2nd(セカンド)トーン」と呼びます。
1st トーンと 2nd トーンは、弦別に一方を割り当てたり両方
を重ねたりできます(P.51)。また両トーン別々に、音の立
ち上がり(ATTACK/P.49)、余韻(RELEASE/P.50)、明る
さ(BRIGHTNESS/P.50)、平行移調(TRANSPOSE/P.51)
などの調整を加えることができます。平行移調
(TRANSPOSE)に関しては、弦別に設定 することもできま
す。
これらの調整内容や設定はトーンの選択同様、全てパッチに
記憶できます。
パッチごとに記憶できるその他の設定
パッチにはトー ンの選択 や弦への割り当て、その調整の他、
次の項目などを記憶させておくことができます。
パッチの名前(P.38)
•
•
エフェクトのかかり方(P.53 〜)
•
アルペジエーターのパターンと関連する設定(P.76)
ハーモニストの設定(P.80)
•
ペダル操作に対する反応のしかた(P.43)
•
•
外部 MIDI 機器に送られるプログラム番号(P.88)
外部音源の平行移調(トランスポーズ)(P.51)
•
設定の手順など詳しくは、それぞれの参照ページをご覧くだ
さい。
弦ごとに異なる設定を行う
(STRING SELECT)
設定項目のうち、TONE の「LAYER」、「1ST TRANSPOSE」、
「2ND TRANSPOSE」の 3 つと、COMMON の「MIDI [PC]」、
「MIDI [CC0]」、「MIDI [CC32]」、「MIDI [TRANSPOSE]」の
4 つは、[STRING SELECT]ボタンの併用により、弦ごとに
異なる設定を行うこともできます。
[STRING SELECT]を押した時の、弦の選択と 3 桁表示器
の表示は次のようになります。
fig.5-02(STRING SELECT)
全弦を選択
5,6弦を選択
6弦を選択
5弦を選択 4弦を選択
各弦独立で設定したい場合は、[VALUE]ダイヤルで設定値
を変える前に、[STRING SELECT]ボタンを押して弦を選択
します。例えば[STRING SELECT]ボタン で「5」に合わ
せてから[VALUE]ダイヤルを回せば、5 弦についてのみ設
定が変わります。続けて同様に他の弦の設定もできます。
※ [STRING SELECT]ボタンで「ALL」または「6-5」を選
ぶと、パラメーターの値が点滅表示される 事があります
が、これは各弦 で設定 が異なっていることを 示します。
この状態で[VALUE]により値を変更すると、値は確定
されますが、「ALL」なら全弦同じ設定に、「6-5」なら 5、
6 弦が同じ設定になります。
1弦を選択
2弦を選択
3弦を選択
5章
35
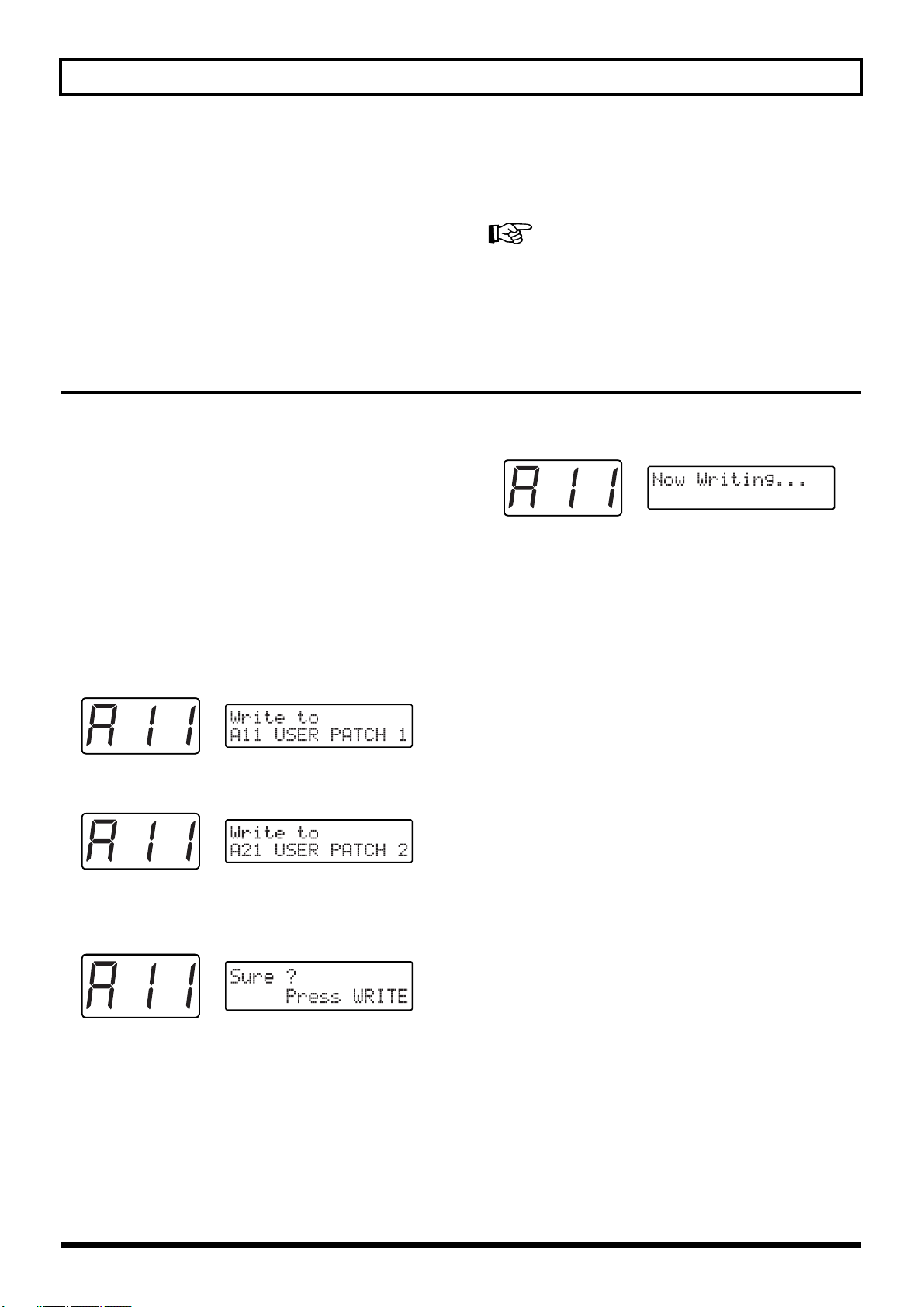
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
アルペジエーター/ハーモニストと パッチの関係
演奏時には、アルペジエーターとハーモニストの 2 機能のう
ち、どちらか一方を使用できます。どちらを使用するかの選
択(P.78、P.82)や、それがパッチ呼び出し時にオンになっ
ているかどうか(P.77、P.81)も、パッチひとつひとつに独
立で設定できます。
パッチの保存のしかた
一般に、パッチ・エディット・モー ド中で[PARAMETER]
により設定項目を選び、[VALUE]で値を設定すればパッチ
の修正ができます。
しかしそのままでは、他のパッチに切り替えると同時に修正
/変更の内容は無効になり、変更前の状態に戻ってしまいま
す。(3 桁表示器の下一桁目に、ポイントが点灯する(P.32)
のはこれを警告しています。)変更内容を保存するには、次の
手順でパッチ・ライト(書き込み)を行いましょう。
■ パッチ・ライトの手順
[WRITE]を押します。
1.
ライト・モードになり、次のような画面になります。
fig.5-04(PATCH WRITE 1)
また、アルペジオ・パターン(アルペジエーター機能が作り
出す弾弦の順)も、あらかじめ用意されている 50 種類のパ
ターンから、パッチごとに選ぶことができます。
詳しい設定方法は、「アルペジオのパターンを選択する(ARP
PATTERN)」(P.78)をご覧ください。
確認をして問題がなければ、もう一度[WIRTE]を押し
4.
ます。
fig.5-07(PATCH WRITE 4)
Now Writing...と表示され、自動的にプレ イ・モード
に戻ると書き込み終了です。
※ 中止する時は[PLAY]を押してください。
以上により、他のパッチに切り替えたり、電源を切った後で
もパッチの変更内容が再現できます。
※ 保存先の指定をせずに書き込みをする と、上書き処理に
より、そのパッチの変更前の内容は失われます。
※ パッチ・グループ E 〜 H は読み出し専用なので、保存先
の指定無しに書き込みすることはできません。
2.
[VALUE]で書き込み先のパッチを選びます。
fig.5-05(PATCH WRITE 2)
書き込み先パッチが決まったら、[WRITE]を押します。
3.
次のような確認の画面になります。
fig.5-06(PATCH WRITE 3)
保存に関する注意事項
パッチ・ライトでは、アルペジエーター/ハーモニストのオ
ン/オフも含め、その時に実際に鳴っている音の状態がその
まま書き込まれます。ただ し、本体ペダルのワ ウやピッチ・
グライド、またエクスプレッション・ペダルなどで、一時的
に得られている音色の変化は記憶されません。内蔵エフェク
トの一時オフ(エフェクト・バイパス機能/ P.75)も同様で
す。
※ システム全体でひとつだけ記憶される 設定項目(システ
ム・モードでの設定)では、パッチ・ライト の必要はあ
りません。設定を変更するだけでその内容 は自動的に保
存され、電源オフ後も記憶されています。
36

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
本体のパッチをシーケンサーなどに保 存する(バルク・ダンプ)
全ユーザー・パッチの設定内容、及びシステム設定の内容は、
MIDI を通じて外部とやりとりできます。MIDI データを記録
できる外部機器を用いれば、パッチを外部に保存することが
できます。これには、エクスクルーシブ・メッセージと呼ば
れる、データ上に指定された機種のみが解釈できる MIDI 情
報が用いられます。
例えば MIDI シーケンサーのリアルタイム・レコーディング
機能やバルク・ライブラリアン機能を用いれば、GR-33 から
送られてきたデータを、フロッピー・ディスクなどに保存で
きます。2 台の GR-33 同士をつないで、直接データをやりと
りすることも可能です。
■ 外部MIDI機器にシステム設定の内容やパッチ・デ ー
タを送信する手順
1.
GR-33 の電源を切ります。
2.
GR-33 の MIDI OUT から、外部機器の MIDI IN へ接続しま
す。
GR-33 の電源を入れます。
3.
fig.5-09(Sending)
9.
「BULK DUMP」の設定画面」に戻ったら転送は完了で
す。受信側がシーケンサーの場合は、レコ ーディングを
停止させます。
fig.5-08(BULK DUMP)
10.
[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。
保存したシステムやパッチのデータを 受信する(バルク・ロード)
MIDI データを記録できる外部機器や GR-33 から、システム
やパッチのデータを受信します。
※ エクスクルーシブ・メッセージの受 信は、バルク・ロー
ド画面でのみおこなえます。
5章
4.
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
5.
[PARAMETER]でBULK DUMPを選びます。
fig.5-08(BULK DUMP)
[VALUE]で、送信したいデータを選びます。
6.
All: 全ユーザー・パッチ及びシステム設定
System: システム設定
User Patch: 全ユーザー・パッチ、128 個
Patch Group A: A11 〜 A84 の 32 パッチ
Patch Group B: B11 〜 B84 の 32 パッチ
Patch Group C: C11 〜 C84 の 32 パッチ
Patch Group D: D11 〜 D84 の 32 パッチ
Patch A11: パッチ A11 のみ
Patch A12: パッチ A12 のみ
: :
Patch D84: パッチ D84 のみ
外部機器を データ記 録できる状態にします。(シー ケン
7.
サーならリアルタイム・レコーディングをス タートしま
す。)
■ 外部 MIDI 機器からシステム設定の内容やパッチ・
データを受信する手順
GR-33 の電源を切ります。
1.
2.
外部機器の MIDI OUT から、GR-33の MIDI IN へ接続しま
す。
3.
GR-33 の電源を入れます。
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
4.
5.
[PARAMETER]でBULK LOADを選びます。
fig.5-40
6.
外部機器からデータを送信します。
fig.5-41
元の表示に戻ったら受信は完了です。
ig.5-40
8.
[WRITE]を押します。
選択し たデ ータが外部機 器に 転送されます。送 信中 は
ディスプレイにNow Sending...と表示されます。
37

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
[PLAY]を押して、プレイ・モードに戻ります。
7.
※ シーケンサーなどの外部機器から 1 パッチのみのデータ
を送信する場合、受信側の GR-33 でパッチ・ライト操作
(P.36)をする必要があります。(ライト時に は保存先の
指定(ができますので、同じ番号のパッチに消 したくな
いパッチがあっても、他に待避しなくてすみます。)
※ システム・データやパッチ・データのエクスクルーシブ・
メッセージを受信すると、A11 〜 D84 の「1 個送り」を
除き、受信側のパッチやシステム設定のデ ータは無条件
に書き替えられます。それまでのデータは 失われますの
で、十分にご注意ください。必要な場合は、受信側の GR33 上のデータも、あらかじめ外部機器側に転送し保存し
ておきましょう。
パッチに名前をつける(PATCH NAME)
各パッチ・ナンバーには、最大 12 文字までの名前をつける
ことができます。作成した音をイメージする名前や使用する
曲名など、好みに応じて名前をつけることができます。
■パッチに名前をつける手順
1.
名前を変えたいパッチを選び、[COMMON]を 押して
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]を押して、PATCH NAMEを選びます。
2.
fig.5-10(PATCH NAME)
[VALUE]で文字(文字/数字/記号)を選びます。
4.
fig.5-11(文字)
※ [COMMON]を押して、大文字/小文字を切り替えるこ
とができます。
5.
3. 〜 4. の操作を繰り返して、名前を完成させます。
空白
〜
〜
〜
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
6.
カーソル
3.
[PARAMETER]で修正する文字部分にカーソルを移動さ
せます。
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
パッチごとに音量を記憶させる(PATCH LEVEL)
3.
複数のパッチを曲中で切り替えて使う場合などには、バッキ
ング用のパッチの音量を、ソロ用のパッチよりも小さめにし
ておけば便利です。このような音量設定も、パッチごとにパッ
チ・レベル(PATCH LEVEL)として記憶できます。
■ パッチの音量を決めて記憶させる手順
1.
音量を変えたいパッチを選び、[COMMON]を 押して
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]を押して、PATCH LEVELを選びます。
2.
fig.5-12(PATCH LEVEL)
[VALUE]で値を変更します。
数値は 0 〜 100 の範囲で変化します。0 で消音状態、100
で最大音量になります。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
※ PATCH LEVEL の数値が同じでも、他の項目の設定に
従って音量 レベル は変化します。例えば次の 様な場合、
レベルが高くなりがちです。PATCH LEVEL を低めに設
定すれば、他のパッチとのバランスは取れます。(併せて
下記に関する設定中は、レベル過大によっ てアンプやス
ピーカーを破損しないよう、ボリュームの 設定にもご注
意ください。)
•
1st、2nd の両トーンが重ねられている時。
38

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
リバーブ・センド・レベルが高い時、またはコーラス・
•
センド・レベルが高い時。
•
選んでいるトーン自体に、レベルが高いという特徴があ
る時。
演奏感を変える(PLAY FEEL)
ギターはキー ボードな どと異なり、振動している部分(弦)
に直接触れて、強弱を微妙にコントロールできます。ギター・
シンセにおいて、このメリットを最大限に引き出すには、そ
のパッチで主に用いる奏法や音色自体に適した「演奏に対す
る反応」を設定する必要があります。
この選択をするのがパッチ・エディット・モードの COMMON
の設定項目「PLAY FEEL」(プレイ・フィール)です。例え
ば「指弾き」か「ピック弾き」かによってプレイ・フィール
の選択を変えることで、より自然な強弱表現が得られます。
■ PLAY FEEL を変え、パッチに記憶させる手順
PLAY FEEL を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押
1.
してパッチ・エディット・モードに入ります。
ブライトネス(BRIGHTNESS)の設定値が高い時。
•
ワウ機能が有効になっている時、など。
•
Finger(フィンガー・ピッキング/ finger picking):
指弾きの場合などに適した演奏感が得られる設定です。感度
はノーマルよりやや高めになります。
Hard(ハード・ピッキング/ hard picking):
ピッキングのかなり強い人に適した設定で、感度はノーマル
より低めになります。
※ ギター側の機構上の問題で、GK-2Aのデバイデッド・ピッ
クアップが、弦に近すぎる状態にしか取り 付けられない
時、各パッチをこの設定にすることで、動 作を改善でき
る場合があります。
Soft(ソフト・ピッキング/ soft picking):
やや弱めのピッキングに適しています。感度は、ノーマルよ
りやや高めになります。
5章
2.
[PARAMETER]を押して、PLAY FEELを選びます。
fig.5-13(PLAY FEEL)
[VALUE]で値を変更します。
3.
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ PLAY FEEL で選べる
設定とその効果」をご覧ください。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ PLAY FEEL で選べる設定とその効果
「Normal」「Finger」「Hard」「Soft」「Tapping」「No Dynamics」
「Envelope1」「Envelope2」の 8 タイプの設定と、それぞれ
にアクセル機能が付加されている「Accl Normal」「Accl
Finger」「Accl Hard」「Accl Soft」「Accl Tapping」「Accl No
Dynamics」「Accl Envelope1」「Accl Envelope2」の8 タイ
プの設定があります。
それぞれの意味は次の通りです。
Tapping(タッピング・プレイ/ tapping play):
タッピング・プレイ(いわゆるライトハンド奏法)や、プリ
ング・オフ、ハンマリング・オンを多用する場合に、より安
定した発音が得られます。強弱表現の幅はやや狭くなります。
No Dynamics(ノー・ダイナミクス/ no dynamics):
弦を弾く強さに関わらず、一定の音量/音色で鳴ります。シ
ンセ・リードやオルガンなどのトーンで、無表情な感じを意
識的に出したい場合などに使います。
Envelope1(エンベロープ・フォ ロー 1 / envelope follow
type1):
弦の振幅の変化を、シンセ音の音量変化に反映させる設定で
す。
詳細については、次項の「エンベロープ・フォロー機能につ
いて」をご覧ください。
Envelope2(エンベロープ・フォ ロー 2 / envelope follow
type2):
弦の振幅の変化を、主に音色(明るさ)の変化に反映させる
設定です。
詳細については、次項の「エンベロープ・フォロー機能につ
いて」をご覧ください。
Normal(ノーマル/ normal):
一般的なピック弾きでの演奏に適した、標準的な設定です。
39

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
「Accl Normal」「Accl Finger」「Accl Hard」「Accl Soft」「Accl
Tapping」「Accl No Dynamics」「Accl Envelope1」「Accl
Envelope2」の 8 タイプは、前述の 8 タイプの設定にアクセ
ル機能が付加されたものです。前述の 8 タイプに比べ、発音
速度が速くなります。
詳細については、「発音速度をさらにアップするには(アクセ
ル機能)」(P.40)をご覧ください。
※ ピッキングの強さや強弱の幅などは奏者によ って異なり
ます。各設定の名称(「ノーマル」「ソフト」「ハード」な
ど)は、設定上の目安です。実際に切り替え てみて、自
分が弾 きや すいと感じた り、再現 したい楽器の 特性 に
あっていると感じる場合は、特に名称にこ だわらず、自
由に設定してください。
エンベロープ・フォロー機能について
前項の PLAY FEEL の設定に「Envelope1」か「Envelope2」
を選ぶと、エンベロープ・フォロー(envelope follow)機能
がオンになり、その効果が得られます。
この状態にすると、ギター弦の振動幅の変化(ピッキングに
よる変化や減衰していく様子)が、シンセ音の音量や音色に
反映され、次のような効果が得られます。
Envelope1(エンベロープ・フォロ ー 1 / envelope follow
type1):
弦の振幅の変化が、シンセ音の音量変化に反映されます。減
衰系の音色(ギター類やエレクトリック・ピアノなど)に用
いると、自然な演奏感が得られる場合がありますので、試し
てみてください。(シンセ音の音量変化は、ギター弦の変化よ
りもやや控えめになるよう圧縮されています。)
Envelope2(エンベロープ・フォ ロー 2 / envelope follow
type2):
弦の振幅の変化を、主に音色(明るさ)の変化に反映させる
設定です。ピッキングの強弱や時間の経過による減衰に従い、
音の明るさ(こも り加減)をダ イナミックに変化させます。
特にシンセ・リード系の音色で、音色に独特の効果を与える
ことができます。また次の手順により、ワウのオート・ワウ
機能と組み合わせて、非常に滑らかな反応のタッチ・ワウ風
効果を得ることもできます。
■ PLAY FEEL の設定「Envelope2」で、タッチ・ワ
ウ風効果を得る手順
1.
シンセ・リード系の音色のパッチを選んでみましょう。
2.
[COMMON]を押して、[PARAMETER]でPLAY FEEL
に合わせ、[VALUE]でEnvelope2を選びます。
[PARAMETER]を押して、WAH TYPEを選びます。
3.
4.
[VALUE]でAutoWah1 〜 5を選びます。
WAH TYPE の詳しい内容については、「ワウの効き方を選ぶ
(WAH TYPE)」(P.43)をご覧ください。
5.
弦を弾き、ワウ効果がピッキングの強弱に 反応してかか
るのを確認してください。
※ パッチに記憶させる時は、[WRITE]を押してパッチ・ラ
イト操作(P.36)を行ってください。
※ PLAY FEEL に「Envelope1」か「Envelope2」が選ばれ
ていると、エンベロープ・フォローの情報は、MIDI コン
トロール・チェンジ情報の 18 番(汎用操作子 3)の値と
して、MIDI アウトから送出されます。
発音速度をさらにアップするには(アクセル機能)
P.39 の PLAY FEEL の選択時、後半に表示される「Accl」が
ついたものを選ぶと、GR-33 の「アクセル機能」がオンにな
ります。この状態にすると、ピッキングから発音まで平均時
間が、通常の状態よりもさらに高速化されます。
ただし、この機能を使う場合は、「弾弦ノイズ軽減」の内部処
理の効果が弱まってしまいます。従ってトーンによって、弾
弦時にノイズやピッチのゆらぎを感じる場合がありますので
ご注意ください。アクセル機能を使う際は音作りの段階で使
用するトーンでノイズが気にならないことを確認しておきま
しょう。
40

音の定位を変える(PAN)
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
1st トーンと 2nd トーンは聴感上異なった位置、例えば右端
と左端にステレオ定位させることができます。
また設定を変えれば、弾弦ごとに定位が不規則に変わるなど、
音の定位を変化させるこ とも可能です。これ らは、パッチ・
エディット・モードの COMMON の項目「PAN MODE」(パ
ン・モード)、「PAN」(パン)の設定で決まります。
■ 音の定位を設定し記憶させる手順
1.
定位を決めたいパッチを選び、[COMMON]を 押して
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]でPAN MODEを選びます。
2.
fig.5-14(PAN MODE)
3.
[VALUE]でパン・モードを選択します。
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ PAN で選べる設定とそ
の効果」をご覧ください。
※ Normal、Cross Tones でなければ、手順 6. へ進んでくだ
さい。
[PARAMETER]でPANを選びます。
4.
fig.5-15(PAN)
Cross Tones:
0 では全ての音が中央に定位します。値を -50 〜 50 の範囲
で変化させるとパンニングが連続変化し、1st トーンは 50 で
右端、-50 で左端に定位します。逆に 2nd トーンは、-50 で
右端、50 で左端に定位します。従って両トーンとも使ってい
るパッチで 50 や -50 に近い値に設定すると、左右に広がっ
たステレオ感豊かなパッチにすることができます。
1-6、6-1:
弦別の定位が得られます。「1-6」を選ぶと左から順に、1 弦、
2 弦、...6 弦の順に定位します。「6-1」では逆に、左から 6
弦、5 弦 ...1 弦の順になります。
Odd-Even、Even-Odd (Odd:奇数、Even:偶数):
奇数番弦と偶数番弦で、定位が左右に分かれます。
「Odd-Even」を選ぶと奇数(Odd/1、3、5)弦は左端、偶数
(Even/2、4、6)弦は右端に定位します。
「Even-Odd」は、「Odd-Even」の左右が入れ替わった場合と
同様の効果となります。
Random Both、Random 1st、
Random 2nd (Random:ランダム):
1st、2nd 両トーンの定位が、発音する度に不 規則に変化し
ます。「Random 1st」と「Random 2nd」では、それぞれ 1st
トーンのみ、2nd トーンのみがランダムな定位となり、他方
のトーンは中央に定位します。
5章
5.
[VALUE]で、値または設定を選びます。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
6.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ PAN で選べる設定とその効果
Normal:
0 では全ての音が中央に定位します。値を -50 〜 50 の範囲
で変化させるとパンニングが連続変化し、1st / 2nd 両トー
ンは 50 で右端、-50 で左端に定位します。
Alternate Both、Alternate 1st、
Alternate 2nd (Alternate:オルタネイト):
各弦の 1st、2nd 両トーンの定位が、発音する度に「... →右
→左→右→左 ...」と切り替わります。一方のトーンだけを鳴
らしているパッチでは、音が左右から交互に鳴る効果が得ら
れます。また 1st トーンが右端になっている時、2nd は左端
になるので、両トーンとも使って いるパッチに使うと、
Random(ランダム)とも異なる独特のステレオ 効果となり
ます。
設定値「Alternate 1st」と「Alternate 2nd」では、それぞれ
1st トーンのみ、2nd トーンのみが「Alternate Both」と同
様の定位となり、他方のトーンは中央に定位します。
※ PAN の設定は、内蔵リバーブや内蔵コーラスのエフェク
ト音の定位には、関係しません。
※ PAN の設定による効果は、ステレオ構成の音響機器に 2
本のケーブルでつないでいる時か、ス テレオ・ヘッドホ
ンを使用している時のみに得られます。
※ MULTI-FX でモノラル系のタイプを選んでいると、ここ
での PAN の設定は無効になります。
41

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
連続的な音高変化を半音刻みにする(CHROMATIC)
GR-33 では、弦の押さえ方などによる細かいピッチ変化や中
間ピッチまで、忠実に再現されます。
しかし必 要に 応じて微妙なピ ッチ表 現を抑え、半音刻み の
ピッチ変化に制限することもできます。これをクロマチック
機能と呼び、パッチ・エディット・モードの COMMON の項
目「CHROMATIC」でオン/オフを設定できます。
fig.5-16(CHROMATIC1)
出力される
シンセ音の音高変化
2音
1音半
1音
半音
半音
1音
クロマチックがオン
クロマチックがオフ
1音半
2音
チョーキング
時の実際の
音高変化
■ クロマチック機能をオン/オフし、パッチに記憶さ
せる手順
変更したいパッチを選び、[COMMON]を押してパッチ・
1.
エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]でCHROMATICを選びます。
2.
fig.5-17(CHROMATIC2)
◆ CHROMATIC の設定と、それによって得られる効果
Off(クロマチック・オフ):
ギター側のチョーキングやビブラートによる、半音以下の微
妙な音高変化を、シンセ音で忠実に再現できる状態です。
これを Off 以外の設定に変えると、音 高の変化が半音刻み
の階段状に制限されます。
Type1(タイプ 1):
ギター側 のチ ョーキングなどに より徐 々に音高を変え た場
合、音高の変化を 半音刻み にします。音高が変化する際に、
鳴っている音を止めず、音高変化情報だけを与えて処理しま
す。音高変化時にアタック音が無く、ちょうどリコーダーの
スラー演奏のような変化が得られるのが特徴です。
Type2(タイプ 2):
同様に徐々に音高を変えた場合、音高の変化を半音刻みにし
ます。音高が変化する際に、変化した高さの音をリトリガー
(鳴らし直し)して、半音刻みの音高変化を表現します。従っ
て音高が変わる度にアタック音が鳴ります。
弦振動が弦を弾いた時より減衰していればそれを反映し、リ
トリガー音はだんだん小さくなります。
Type3(タイプ 3):
基本的には「Type2」と同じ効果ですが、音高変化時のリト
リガー(鳴らし直し)音のレベルが、弦振動が弦を弾いた時
より減衰していてもそれを反映せず、弦を弾いた時と同じに
なるのが特徴です。
[VALUE]で設定を変更します。
3.
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ CHROMATIC の設定
と、それによって得られる効果」をご覧ください。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
和音を美しく響かせたい場合
もっぱらコードでの長音プレイを想定したパッチでは、各弦
の押えられ方な どによって 生じる微妙な音高の変化により、
和音の響きが濁って聴こえてしまう場合があります。
このような場合にクロマチックをオンにすると、構成音の音
程が正しく保 たれ、美しい コード・サウンドが得られます。
特に「Type1」を選ぶと、音高変化が気になりにくく、自然
な響きが得られます。
ピアノなどの音高変化を再現する場合
ピアノなどの、半音以下の音程を表現できない楽器を想定し
たパッチでは、ク ロマチッ クを使用した方が「それらしさ」
を演出できます。
これらの場合「Type2」や「Type3」を選ぶと、音高が変わ
る時のアタッ ク音が再現 できます。(音色や 曲調によっては
「Type1」や「Off」の方が良い結果が得られる場合もありま
すので、好みで選んでください。)
42

ワウの効き方を選ぶ(WAH TYPE)
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
ペダル効果モードでペダル 1 を踏んだり離したりして得られ
る「ワウ効果」には、音色変化の幅や速度が異なる 7 グルー
プ・35 種のワウ系の効果と、1 種類のモジュレーション(ビ
ブラート)効果、合わせて 36 種のバリエーションが用意さ
れています。
■ ワウ(モジュレーション)の効きかたを選ぶ手順
効果の種類を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押
1.
してパッチ・エディット・モードに入ります。
2.
[PARAMETER]で、WAH TYPEを選びます。
fig.5-18(WAH TYPE1)
[VALUE]で設定を変更します。
3.
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ WAH TYPE で選べる
ワウ・ペダルのバリエーション」をご覧ください。
※ 設定中は、ギターを弾きながらペダル 1 を踏めば、効果
が試せます。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ WAH TYPEで選べるワウ・ペダルのバリエーション
表示されるタイプ名の末尾の番号(1 〜 5)は、音色の変化
する速度を示します。ペダルの「踏む」「離す」が切り替わる
と、1 で最も高速に音色が変化し、2、3、4、5 と番号が大
きくなるにつれ、順にゆっくりした音色変化になっていきま
す。
fig.5-19(WAH TYPE2)
Wah1 〜 5(ワウ 1 〜 5):
ギター用ワウ・ペダルに似た効果をシンセ音にかけます。音
に独特のクセがつき、ペダルを踏むと「ゥアー」と明るい音
になり、離すと「アーゥ」と暗い音になります。踏む/離す
を繰り返すと、「ワゥワゥワゥ ...」という効果が得られます。
AutoWah1 〜 5(オート・ワウ 1 〜 5):
基本的にワウ(Wah1 〜 5)と同じ効果ですが、ペダルを操
作しなくても、新たなピッキングの度に自動的にワウ効果が
かかります。この 場合もペダ ルでの効果はかかりますので、
両者を組み合わせても使えます。シンセ・ベースなどの音色
に、プレイ・フィールの設定「Envelope2」と組み合わせて
使うと、スムースなタッチ・ワウ風効果も得られます。
タッチ・ワウ風効果の設定方法は、「エンベロープ・フォロー
機能について」(P.40) をご覧ください。
Brightness1 〜 5 (ブライトネス 1 〜 5):
音色にはワウ独特のクセがつかず、単に音色の明るさだけが
コントロールされます。他の挙動は、Wah1 〜 5 と全く同じ
です。
NarrowWah1 〜 5(ナロウ・ワウ 1 〜 5):
踏んだ時と離した時の音色の差が、ワウ(Wah1 〜 5)の半
分程度に抑えられています。他の挙動は、Wah1 〜 5 と全く
同じです。
R.Wah1 〜 5(リバース・ワウ 1 〜 5):
ワウ(Wah1 〜 5)の、ペダルを踏んだ時と離した時の音色
を逆転させ、「踏む→音がこもる」「離す→明るくなる」にし
たものです。
R.Brightness1 〜 5(リバース・ブライトネス 1 〜 5):
ブライトネス(Brightness1 〜 5)の、ペダルを踏んだ時と
離した時の音色を逆転させ、「踏む→音がこもる」「離す→明
るくなる」にしたものです。
R.NarrowWah1 〜 5(リバース・ナロウ・ワウ 1 〜 5):
ナロウ・ワウ(NarrowWah1 〜 5)の、ペダルを踏んだ時と
離した時の音色を逆転させ、「踏む→音がこもる」「離す→明
るくなる」にしたものです。
5章
踏む 離す
音の
明るさ
Wah1〜5、Brightness1〜5
などの例(時間変化のイメージ)
時間
Modulation(モジュレーション):
これを選ぶとワウ系の効果ではなく、ペダルを踏んでいる間、
深いビブラート(ピッチのうねり)がかかります。ギター側
でフィンガー・ビブラート奏法を行なった場合とは雰囲気の
異なる、いかにもシンセサイザーらしい機械的なビブラート
が得られます。
この機能で得られるビブラートの速さと深さは、トーン(音
色)ごとに決まっています。
43
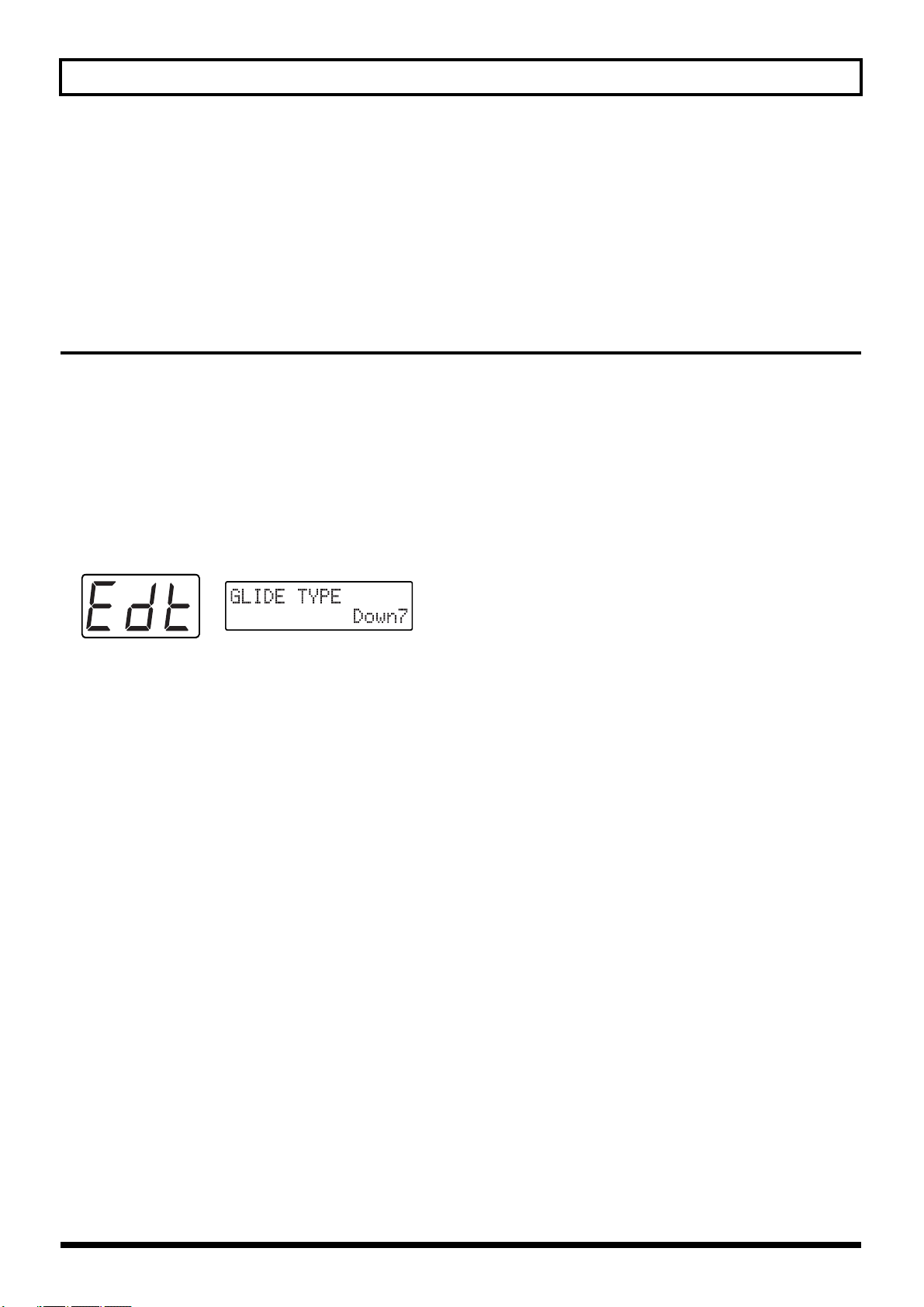
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
※ 1 度ワウを使うと、以後ペダルを離しても、音がこもっ
たりクセがつくなどパッチ呼び出し時の状態 から音が変
わる場合があります。この時は 1 度他のパッチに切り替
えてから再度呼び出し直せば、元の音に戻ります。
※ 「ワウが閉じた状態」の音色が暗すぎる(こもり過ぎてい
る)場合は、「WAH TYPE」を「NarrowWah1 〜 5」か
「R.NarrowWah1 〜 5」にするか、「BRIGHTNESS」(P.
50)の設定を変えて調整してください。
※ ワウ系の効果のかかり方は、選ばれたトー ンによっても
異なります。
ピッチ・グライドの効き方を選ぶ(GLIDE TYPE)
ペダル効果モードのペダル 2 で得られる「ピッチ・グライド
効果」には、音高変化の幅や速度が異なる 7 通りの効きかた
が、アップ、ダウンの双方向に用意されています。
■ ピッチ・グライドの効きかたを選ぶ手順
効果の種類を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押
1.
してパッチ・エディット・モードに入ります。
2.
[PARAMETER]で、GLIDE TYPEを選びます。
fig.5-20(GLIDE TYPE)
[VALUE]で設定を変更します。
3.
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ GLIDE TYPE で選べる
効き方のバリエーション」をご覧ください。
※ 設定中は、ギターを弾きながらペダル 2 を踏めば、効果
が試せます。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ GLIDE TYPE で選べる効き方のバリエーション
選択できる効きかたは、次の 7 タイプです。
これらがピッチ・ダウンとピッチ・アップの双方に準備され
ており、計 14 種類の効果の中から選べます。
例えば「アップ/タイプ 5」なら「Up5」、「ダウン/タイプ
3」なら「Down3」のように表示されます。
Up1(Down1):
ペダルを踏むとピッチが完全 4 度まで連続変化します。離す
と元のピッチに戻ります。
Up2(Down2):
1 と同様の 4 度の変化ですが、ピッチが変化するのに時間が
やや長くかかります。
Up3(Down3):
ペダルを踏むとピッチが完全 5 度まで連続変化します。離す
と元のピッチに戻ります。
Up4(Down4):
ペダルを踏むとピッチが 1 オクターブ連続変化します。離す
と元のピッチに戻ります。
Up5(Down5):
1 オクターブの変化ですが、ピッチが変化するのに時間がや
や長くかかります。(戻る時間は 4 と同じです。)
Up6(Down6):
変化しきる時間、戻る時間ともに長めの、1 オクターブの変
化幅の効果です。
44
Up7(Down7):
ペダルを踏むと「瞬時」に 1 オクターブ上がる(下がる)効
果です。
※ エクスプレッション・ペダルの機能(P.47)に、「Pitch」
または「Tempo&Pitch」を割り当てた時の音高 変化の幅
も、この「GLIDE TYPE」での選択(4 度、5 度、1 オク
ターブ)に従います。
※ ピッチ・グライド機能では、トーンや音域 によりピッチ
上昇の幅が制限される場合があります。

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
ホールドの効き方を選ぶ(HOLD TYPE)
ペダル効果モードのペダル 3 で得られる「ホールド効果」に
は、発音が保持されるトーンが異なるものなど、15 通りのバ
リエーションが用意されており、目的によってひとつを選び、
パッチに記憶させることができます。
■ ホールドの効きかたを選ぶ手順
1.
効果の種類を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押
してパッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]で、HOLD TYPEを選びます。
2.
fig.5-21(HOLD TYPE)
3.
[VALUE]で設定を変更します。
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ HOLD TYPE で選べる
効き方のバリエーション」をご覧ください。
※ 設定中は、ギターを弾きながらペダル 3 を踏めば、効果
が試せます。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ HOLD TYPE で選べる効き方のバリエーション
選択でき る効き かたを大きく分 けると、damper(ダ ン
パー)系、sostenuto(ソステヌート)系、string(スト
リング/弦別)の 3 つの効果に分けられます。
○ ダンパー系ホールド/ Damper:
○ ソステヌート系ホールド/ Sostenuto:
ペダルを踏んだ瞬間に鳴っていたシンセ音だけが、踏み続け
ている間保持されます。
いったんホールドに入るとペダルを離すまで、保持されてい
るシンセ音はギター側の演奏によっても影響を受けることは
ありません。従ってシンセ音でコードを保持し、それにギター
音でメロディを重ねたり、同様の効果 を 1st トーンと 2nd
トーンでつく りたい時な どに便利です。(厳密には違い ます
が)電子ピアノのソステヌート・ペダルによく似たホールド
効果です。
○ 弦別ホールド/ String:
弦別のホールド効果が得られます。上記の「Sostenuto」同
様、ペダルを踏んだ時に発音中であった弦のシンセ音を、弦
振動が停止しても鳴らし続けることができます。
「Sostenuto」との違いは、ペダルを離さなくても、ホールド
されなかった弦のシンセ音は、そのままギター演奏でコント
ロールできる点です。「5、6 弦のシンセ音をホールドしてお
き、1 〜 4 弦のシンセ音をそれに重ねてメロディーを弾く」
といった演奏が可能です。
ペダルから足を離すとホールドされていた音が止まります。
実際に表示され、[VALUE]で選べるのは、次の 15 通りで
す(アルペジエーターがオフの時)。
Damper All:
ダンパー系ホールドが、全内蔵音源、外部 MIDI 音源に効き
ます。
Damper 1st:
ダンパー系ホールドが、内蔵音源の 1st トーンだけに効きま
す。
Damper 2nd:
ダンパー系ホールドが、内蔵音源の 2nd トーンだけに効きま
す。
5章
ペダルを踏んでギターを演奏すると、ピアノのダンパー・ペ
ダルのように発音中の音が消えずに保持されます。
ペダルを踏んだままにすると、全音符のプレイなどで、音を
途切れさせずにコードを変えることができます。
ただし同じ弦のシンセ音同士は、ホールド中でも重なること
はありません。
※ ギター側でのピッチ検出は、弦振動が続いて いる限り行
われ、随時シンセ音の音高に反映されます。
Damper 1&2:
ダンパー系ホールドが、1st、2nd トーンの両 方に効きます
(外部音源には効きません)。
Damper Ext:
ダンパー系ホールドが、外部 MIDI 音源のみに効きます。
Damper Ext&1:
ダンパー系ホールドが、1st トーンと外部 MIDI 音源に効きま
す。
Damper Ext&2:
ダンパー系ホールドが、2nd トーンと外部 MIDI 音源に効き
ます。
45

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
Sostenuto All:
ソステヌート系ホールドが、全内蔵音源、外部 MIDI 音源に
効きます。
Sostenuto 1st:
ソステヌート系ホールドが、内蔵音源の 1st トーンだけに効
きます。
Sostenuto 2nd:
ソステヌート系ホールドが、内蔵音源の 2nd トーンだけに効
きます。
Sostenuto 1&2:
ソステヌート系ホールドが、1st、2nd トーンの両 方に効き
ます(外部音源には効きません)。
Sostenuto Ext:
ソステヌート系ホールドが、外部 MIDI 音源のみに効きます。
CTRL ペダルを使う
Sostenuto Ext&1:
ソステヌート系ホールドが、1st トーンと外部 MIDI 音源に効
きます。
Sostenuto Ext&2:
ソステヌート系ホールドが、2nd トーンと外部 MIDI 音源に
効きます。
String:
弦別ホールドが、全内蔵音源、外部 MIDI 音源に効きます。
※ アルペジエーターがオンになっている時は、上記の 15 通
りの選択肢が「Damper」「Sostenuto」「Latch TypeA」
「Latch TypeB」の 4 通りになります。この時は、ホール
ド機能はアルペジオ音に対してのみ有 効になり、アルペ
ジオのリズムを止めないでコードを更 新するなど、独特
の使い方ができます。
詳細については、「アルペジオ中のホールド機能の有効な使い
方」(P.76)をご覧ください。
ペダル効果モードのペダル 4(CTRL ペダル)は、MULTIFX、アルペジエーター/ハーモニストいずれかのオン/オフ
のきりかえに割当てることができます。この設定はパッチご
とに記憶できます。
■ CTRL ペダルの機能を設定する手順
1.
機能を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押し て
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]で、CTRL PEDALを選びます。
2.
[VALUE]で設定を変更します。
3.
HAR/ARP Control:
ペダルを踏むたびにアルペジエータ/ハ ーモニストのオ
ン/オフが切り替わります。
Multi-FX Bypass:
ペダルを踏むたびに MULTI-FX のバイパスのオン/オフ
が切り替わります。
※ パッチに記憶されている「MULTI-FX SW」(P.53)が
「Off」の状態に設定されていると、CTRL ペダルを踏ん
でもマルチ・エフェクトは「Off」以外の設定にはなり
ません。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
46
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
※ MULTI-FX BYPASS をオン/オフしたときにノイズが聞
こえる場合がありますが、故障ではありません。

エクスプレッション・ペダルを使う
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
本体に装備されたエクスプレッション・ペダル(以降 EXP ペ
ダル)を操作することによって、シンセ音に様々な効果を与
えることができます。EXP ペダルによる効果はピッチ、音量、
アルペジエーターのテンポなど、18 種類の効果から選択でき
ます。
またこの他、EXP ペダルの操作によって外部に MIDI コント
ローラー情報を送信でき、そのコントロール・チェンジ番号
の設定もできます。以上の設定は全てパッチごとに記憶でき
ます。
効果をかけるには
EXP ペダルを操作すると、その時呼び出されているパッチに
設定されている効果がすぐにかかります。
※ 呼び出されているパッチに対して、何らかの効果を EXP
ペダルで与えた後、他のパッチに切り替え ると、ペダル
の踏み込み位置とは関係なく、一旦ペダル効 果は解除さ
れ、呼び出されたパッチ本来の状態で鳴り始めます。パッ
チが切り替わった後、最初にペダルが動かさ れた時点か
ら、再び EXP ペダルの操作が音に反映されます。
ただし、切り替え前後の両方のパッチで、「Volume」
「Volume 1st」「Volume 2nd」のいずれかが割り当てられ
ている場合は、切り替え前の EXP ペダルの位置で音量が
再設定されます。
効果を選ぶには(EXP PEDAL)
■ エクスプレッション・ペダルの、効果の種類を選ぶ
手順
効果の種類を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押
1.
してパッチ・エディット・モードに入ります。
◆ EXP PEDAL で選べる効き方のバリエーション
Volume(音量):
シンセ音量が「0 から GK-2A のボリュームつまみで設定され
ているレベルまで」の範囲で変化します。
Volume 1st(1st トーン音量):
1st トーンのみの音量をコントロールします。両トーンを重
ねたパッチで、鳴っている 2nd トーンに 1st トーンを追加す
る効果が得られます。
Volume 2nd(2nd トーン音量):
2nd トーンのみの音量をコントロールします。両トーンを重
ねたパッチで、鳴っている 1st トーンに 2nd トーンを追加す
る効果が得られます。
Balance(バランス):
1st、2nd 両トーンの音量比が変化します。ペダルを戻しきっ
た時は 1st のみ、踏み込みきった時は 2nd のみとなります。
5章
Tone Param(トーン・パラメーター):
選ばれているトーン特有のパラメーターを変化させます。選
ばれているトーンにより変化は異なります。
Multi-FX Param(マルチ・エフェクト・パラメーター):
選ばれているマルチ・エフェクトのタイプに特有のパラメー
ターを変化させます。選ばれているマルチ・エフェクトのタ
イプにより変化は異なります。
※ 「Multi-FX Param」を選んで EXP ペダルを動かすと軽い
ノイズを感じることがありますが、故障ではありません。
Brightness(ブライトネス):
シンセ音の明るさを連続変化させます。
2.
[PARAMETER]で、EXP PEDALを選びます。
fig.5-22(EXP PEDAL)
[VALUE]で設定を変更します。
3.
※ 詳しい説明は、手順説明後の「◆ EXP PEDAL で選べる
効き方のバリエーション」をご覧ください。
※ 設定中は、ギターを弾きながら EXP ぺダルを踏めば、実
際に効果が試せます。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
Wah(ワウ・ペダル):
ギター用のワウワウ・ペダルに似た、クセの強い音色変化が
得られます。
Pitch(音高):
和音構成を保ったまま、シンセ音のピッチ(音の高さ)を大
きく変化させます。ペダルを引き戻した状態で通常のピッチ
となります。ピッチの変化幅は、ペダル効果の「GLIDE TYPE」
で選ばれている変化幅に従います。
GLIDE TYPE の設定方法は、「ピッチ・グラ イドの効き方を
選ぶ(GLIDE TYPE)」(P.44)をご覧ください。
Modulation(モジュレーション):
シンセ音にかけるピッチの揺らぎの深さを、0 から最大まで
変化させます。(この時の揺らぎの速さは、選ばれているトー
ンによって決まっています。)
47

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
Pan(Normal)(ノーマル・パン):
パッチに設定された「PAN(P.41)」が無視され、EXP ペダ
ルの操作に従って定位が変わります。1st、2nd 両 トーンは
常に一緒に定位します。1st、2nd 両トーンと も、踏み込む
と右、戻しきると左に定位します。
Pan(Cross Tones)(クロストーン・パン)
EXP ペダルを操作することで、1st トーンと 2nd トーンの定
位を -50 〜 +50 の範囲で変化させます。1st トーンと 2nd
トーンは中央である 0 を境として、常に左右対称に分離して
定位しています。1st トーンはペダルを踏み込むと右、戻し
きると左に定位し、また 2nd トーンはその逆に定位します。
Cho Send Level(コーラス・センド・レベル):
コーラスの音量を EXP ペダルで変えられます。踏み込みきっ
た時にパッチに設定されたコーラス音量になり、戻しきると
コーラス音はなくなります。
Rev Send Level(リバーブ・センド・レベル):
リバーブの音量を EXP ペダルで変えられます。踏み込みきっ
た時にパッチに設定されたリバーブ音量になり、戻しきると
リバーブ音は無くなります。
Arp Tempo1(アルペジオ・テンポ 1):
アルペジオのテンポが変わります。踏み込みきるとパッチに
設定されているテンポに、戻しきると非常にゆっくりとした
テンポになります。
CC1 〜 31、CC64 〜 95(MIDI コントロール・チェンジ):
EXP ペダルの踏み込まれ加減を、MIDI OUT からコントロー
ル・チェンジ情報で送出します。番号は 1 〜 31 番、64 〜
95 番のうち任意のものが選べます。外部エフェクターの設定
(パラメーター)などを操作したい場合に使います。内部音源
への効果はありません。
※ 「Pan(Normal)」「Pan(Cross Tones)」を選んで EXP
ペダルを動かすと、軽いノイズを感じるこ とがあります
が故障ではありません。また、リバーブ、コ ーラス音の
定位は変化しません。
※ 設定「Arp Tempo1」「Arp Tempo2」「Arp Tempo3」
「Tempo&Pitch」は、アルペジエーターがオンになって
いる時に使えます。
※ 「Volume 1st」、「Volume 2nd」、「Balance」は、「LAYER」
(P.51)で 1st、2nd の両トーンが選ばれ、かつ「1:2
BALANCE」(P.51)が一方のトーンに振り切られていな
い時に有効です。
※ 「Pitch」か「Tempo&Pitch」を選んだ 際、トーンや音 域
によりピッチ上昇の幅が制限される場合があります。
※ 「Brightness」、「Wah」を選んだ時の効果のかかり方は、
選ばれているトーンや、「BRIGHTNESS」(P.50)の設定
によって異なります。
Arp Tempo2(アルペジオ・テンポ 2):
アルペジオのテンポが変わります。踏み込みきると非常に速
いテンポに、戻しきるとパッチに設定されているテンポにな
ります。
Arp Tempo3(アルペジオ・テンポ 3):
アルペジオのテンポを、パッチの設定値を中心に± 20% の範
囲で微調整できます。
Tempo&Pitch(テンポ&ピッチ):
音高とアルペジオのテンポを、同時にコントロールしてテー
プ・レコーダーのテープ・スピードを変えているような特殊
効果を作り出します。ピッチの変化幅は、ペダル効果の
「GLIDE TYPE」で選ばれている変化幅に従います。
GLIDE TYPE の設定方法は、「ピッチ・グライド の効き方を
選ぶ(GLIDE TYPE)」(P.44)をご覧ください。
48

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
シンセ音を加工する
パッチの基本的な音は 384 個のトーンから選ばれる、1st トーンと 2nd トーンによって決まります。次の手順で実際にトーンを
選び、パッチの音色を組み立ててみましょう。
素材になる音(トーン)を選ぶ
(SELECT)
GR-33 では 384 個のトーンを、音色の種類により「PIANO」、
「E.GUITAR」のようにカテゴリーごとに大きく分類していま
す。
詳しくは「トーン・リスト」(P.124)を参照してください。
■ トーンを選ぶ手順
1.
トーンを変更したいパッチを選び、[TONE]を押し て
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]で、1ST SELECTを選びます。
2.
※ 2ND トーンを選ぶ場合は、2ND SELECTを選びます。
※ [TONE]を押して、1ST SELECTと2ND SELECT
を切り替えることができます。
fig.5-24(1st SELECT)
3.
[VALUE]で、トーンを選びます。
音の立ち上がりを遅く/速くする
(ATTACK)
1ST SELECT(2ND SELECT)(トーン番号の選択)で選ん
だ 1st(2nd)トーンは、「ATTACK(アタック・タイム)」
の設定により、その音量、音色の立ち上がりの時間が変化で
きます。ここで 音色が「フワ ッ」と柔らかく鳴り始めるか、
「カン!」と鋭く鳴り始めるかを調整します。
■ ATTACK を変える操作手順
ATTACKを変えたいパッチを選び、[TONE]を押してパッ
1.
チ・エディット・モードに入ります。
2.
[PARAMETER]で、1ST ATTACKを選びます。
※ 2nd トーンの ATTACK を変更する場合は、
2ND ATTACK を選びます。
※ [TONE]を押して、1ST ATTACKと2ND ATTACK
を切り替えることができます。
fig.5-25(ATTACK TIME)
5章
トーンの種類については「トーン・リスト」(P.124)をご覧
ください。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
※ 「LAYER」で「Mute」もしくは「1st Tone」、「2nd Tone」
が選ばれている場合、1st、2nd 両トーン、もしくは片方
のトーンが鳴りません。必要に応じて「LAYER」の設定
を変更してください。
「LAYER」の詳しい設定方法 については、「各弦で どちらの
トーンを鳴らすかを決める(LAYER)」(P.51)をご覧くださ
い。
[VALUE]を回して、-50 〜 50 の範囲で値を選びます。
3.
設定値を上げていくと、音はゆっくりと立ち上がります。
また、設定値を下げていくと、打楽器的な 速いアタック
に変化します。(値が 0 の時、選んだトーン本来の音とな
ります。)
※ ATTACK の設定はトーン固有の特徴に調節を加える方式
です。従って選ばれたトーンによって変化 の幅は変わり
ます。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
※ 「LAYER」で「Mute」もしくは「1st Tone」、「2nd Tone」
が選ばれている場合、1st、2nd 両トーン、もしくは片方
のトーンが鳴りません。必要に応じて「LAYER」の設定
を変更してください。
「LAYER」の詳しい設定方法については、「各弦でどちらのトー
ンを鳴らすかを決める(LAYER)」(P.51)をご覧ください。
49

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
余韻の長さを変える(RELEASE)
1ST SELECT(2ND SELECT)(トーン番号の選択)で選ん
だ 1st(2nd)トーンは、「RELEASE(リリース)」の設定に
より、その音量、音色の、「余韻の長さ」を変化できます。余
韻を長く する と、弦の振動が止ま っても 徐々に消えてい く
ゆったりした音が得られます。余韻を短くすると、弦をミュー
トすると同時に素早く消える音となり、歯切れの良い演奏が
できます。
■ RELEASE を変える操作手順
1.
RELEASE を変えたいパッチを選び、[TONE]を押して
パッチ・エディット・モードに入ります。
2.
[PARAMETER]で、1ST RELEASEを選びます。
※ 2nd トーンの RELEASE を変更する場合は、
2ND RELEASEを選びます。
※ [TONE]を押して、1ST RELEASEと2ND RELEASE
を切り替えることができます。
fig.5-26(RELEASE)
音の明るさを変える
(BRIGHTNESS)
1ST SELECT(2ND SELECT)(トーン番号の選択)で選ん
だ 1st(2nd)トーンは、「BRIGHTNESS(ブライトネス)」
の設定により、そのパッチの音の明るさ(こもり加減)を変
化できます。数値を変えると、内部のデジタル・フィルター
(*1)の設定が調整され、音色がより明るく(硬く)、あるい
はより暗く(柔らかく)変化します。
(*1)デジタル・フィルター:
エレクトリック・ギター のトーンつまみ に似た効果を、さらに強力
に作り出すデジタル回路。
■ BRIGHTNESS を変える操作手順
BRIGHTNESS を変えたいパッチを選び、[TONE]を押し
1.
てパッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]で、1ST BRIGHTNESSを選びます。
2.
※ 2nd トーンの BRIGHTNESS を変更する場合は、
2ND BRIGHTNESSを選びます。
※ [TONE]を押して、1ST BRIGHTNESSと
2ND BRIGHTNESSを切り替えることができます。
fig.5-27(BRIGHTNESS)
3.
[VALUE]を回して、-50 〜 50 の範囲で値を選びます。
設定値を上げていくと、余韻が長くな ります。また、設
定値を下げていくと、短くなります。(値が 0 の時、選ん
だトーン本来の音となります。)
※ RELEASE の設定はトーン固有の特徴に調節を加える方
式です。従って選ばれたトーンによって変化 の幅は変わ
ります。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
※ 「LAYER」で「Mute」もしくは「1st Tone」、「2nd Tone」
が選ばれている場合、1st、2nd 両トーン、もしくは片方
のトーンが鳴りません。必要に応じて「LAYER」の設定
を変更してください。
「LAYER」の詳しい設定方法 については、「各弦で どちらの
トーンを鳴らすかを決める(LAYER)」(P.51)をご覧くださ
い。
[VALUE]を回して、-50 〜 50 の範囲で値を選びます。
3.
設定値を上げていくと、明るく鋭い音になります。また、
設定値を下げていくと、暗くこもった音になります。(値
が 0 の時、選んだトーン本来の音となります。)
※ BRIGHTNESS の設定はトーン固有の特徴に調節を加え
る方式です。従って選ばれたトーンによっ て変化の幅は
変わります。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
※ 「LAYER」で「Mute」もしくは「1st Tone」、「2nd Tone」
が選ばれている場合、1st、2nd 両トーン、もしくは片方
のトーンが鳴りません。必要に応じて「LAYER」の設定
を変更してください。
50
「LAYER」の詳しい設定方法 については、「各弦で どちらの
トーンを鳴らすかを決める(LAYER)」(P.51)をご覧くださ
い。

2 つの音(トーン)を重ねる
第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
各弦でどちらのトーンを鳴らすかを決 める(LAYER)
1st、2nd の両トーンの組み合わせ方は、パッ チ・エディッ
ト・モードの TONE の設定項目「LAYER」(レイヤー)で決
まります。ここで「1st のみ鳴らす」、「2nd のみ鳴らす」「両
方鳴らす」などが選べます。
LAYER は[STRING SELECT]ボタンの併用により、各弦
別々にも設定できます。
例えば 1 〜 3 弦と 4 〜 6 弦に分け、各々に異なったトーンを
配置するといったことも可能です。
■ 1st、2nd トーンのレイヤーの設定をする操作手順
1.
LAYER を変えたいパッチを選び、[TONE]を押してパッ
チ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]で、LAYERを選びます。
2.
fig.5-28(LAYER)
3.
[STRING SELECT]を押して、設定する弦を選びます。
[STRING SELECT]ボタンについての説明は、「弦ごとに異
なる設定を行う(STRING SELECT)」(P.35)をご覧くださ
い。
※ 全弦を同じ設定にする場合は、ALLを選びます。
[VALUE]で、設定を選びます。
4.
Mute: 1st、2nd 両トーンを消音する。
1st Tone: 1st トーンのみを鳴らす。
2nd Tone: 2nd トーンのみを鳴らす。
Both Tone: 1st、2nd 両トーンを鳴らす。
Weak Detune: 弱いデチューン。
Strong Detune: 強いデチューン。
デチューン(微妙な音高のずれ)を与える
前項(LAYER)の設定手順の 4. で、表示「Weak Detune」
(デチューン弱)か「Strong Detune」(デチューン強)を選
ぶと、1st、2nd の両トーンが鳴り、さらに両者 の音の高さ
を僅かにずらすデチューン(detune)効果がつきます。「弱」
より「強」の方が、両トーンの音高の差が大きくなり、より
深いデチューン効果となります。
デチューンを使うと、音に厚みを加えることができます。ま
た同じトーン同士をデチューンさせ、COMMON の設定項目
「PAN MODE」(P.41)を「Cross Tones」にして 1st、2nd
の両トーンが左 右に振り分 けられて鳴るように設定すると、
音の広がり感が出せます。デチューン機能は「LAYER」設定
の一部ですので、[STRING SELECT]ボタンの併用により、
各弦を異なる設定にもできます(P.35)。
音程を半音単位でずらす
(TRANSPOSE)
GR-33 では通常、シンセ音のピッチはギターと同じになって
います。この関係は必要に応じて、半音単位でずらすことが
できます。この機能を、トランスポーズ(平行移調)と呼び
ます。これにより、ギター音に対して 1 オクターブ、平行 5
度など、音程をずらしたシンセ音を重ねることができます。
また内蔵 音源 用のトランスポ ーズ 設定は、1st ト ーン用の
「1ST TRANSPOSE」と2ndトーン用の「2ND TRANSPOSE」
に分かれています。これにより、シンセ音同士を平行移調し
て重ねたり、ギター音に 1 オクターブ下と 5 度上のシンセ音
を重ねた重厚なサウンドなども実現できます。
「1ST TRANSPOSE」、「2ND TRANSPOSE」は[STRING
SELECT]ボタンの併用により、各弦別々にも設定できます。
■ トーンのトランスポーズを設定する操作手順
TRANSPOSE を変えたいパッチを選び、[TONE]を押し
1.
てパッチ・エディット・モードに入ります。
5章
デチューンの詳細については、次項の「デチューン(微妙な
音高のずれ)を与える」をご覧ください。
他の弦の設定が必要であれば、手順 3. 〜 4. を繰り返しま
5.
す。
6.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
2.
[PARAMETER]で、1ST TRANSPOSEを選びます。
※ 2nd トーンの TRANSPOSE を変更する場合は、2ND
TRANSPOSEを選びます。
※ [TONE]を押して、1ST TRANSPOSEと
2ND TRANSPOSEを切り替えることができます。
fig.5-29(TRANSPOSE)
[STRING SELECT]を押して、設定する弦を選びます。
3.
51

第 5 章 音色(パッチ)を設定/変更する
[STRING SELECT]ボタンについての説明は、「弦ごとに異
なる設定を行う(STRING SELECT)」(P.35)をご覧くださ
い。
※ 全弦を同じ設定にする場合は、ALLを選びます。
[VALUE]を回して、-50 〜 50 の範囲で値を選びます。
3.
50 に近づくほど 1st トーン、-50 に近づくほど 2nd トー
ンの音量が大きくなり、0 付近でほぼ同音量になります。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
4.
[VALUE]で、設定値を選びます。
設定値の変化範囲は、半音単位で -36 〜 0 〜 24 です。
設定が 12 なら 1 オクターブ上へ、-24 なら 2 オクター
ブ下へ音程がずれます。
他の弦の設定が必要であれば、手順 3. 〜 4. を繰り返しま
5.
す。
6.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
※ 「LAYER」で「Mute」もしくは「1st」、「2nd」が選ばれ
ている場合、1st、2nd 両トーン、もしくは片方のトーン
が鳴りません。必要に応じて「LAYER」の設定を変更し
てください。
「LAYER」の詳しい設定方法 については、「各弦で どちらの
トーンを鳴らすかを決める(LAYER)」(P.51)をご覧くださ
い。
2 つのトーンの音量バランスを決める
(1:2 BALANCE)
1st トーンと 2nd トーンを同時に鳴らす場合、両者の音量バ
ランスをとる必要があり ます。これはパッチ・エ ディット・
モードの TONE の設定項目「1:2 BALANCE」でパッチごと
に設定できます。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
鳴るはずのトーンが鳴らない時は?
「1st トーンだけ、または 2nd トーンだけが鳴らない」とい
う場合、次の様なケースが考えられます。各項目をチェック
し、該当する点があれば指定ページを参照して、設定を変え
てみましょう。
○ 全弦、または特定弦の「LAYER」(P.51)が「1st Tone」
(1st トーンのみ)か「2nd Tone」(2nd トーンのみ)に
なっている。
○ 「1:2 BALANCE」(P.52)が「50」か「-50」に設定され
ている。
○ COMMON の設定項目「PAN MODE」(P.41)で「Cross
Tones」が選ばれ、トーンが左右に振り分けられた状態
(50 や - 50)になっている時に、片側のチャンネルだけ
しか鳴らない状態でアンプ類に接続されている。
○ エクスプレッション・ペダルの設定(P.47)に「Volume
1st」「Volume 2nd」「Balance」が選ばれてお り、かつ
ペダルが引き戻されきっている。(または踏み込まれきっ
ている。)
※ 1st、2nd の両トーンが鳴らない時は、P.99 を参照して
チェックしてください。
■ 両トーンの音量バランスをとる手順
設定を変えるパッチを選び、[TONE]を押してパッチ・
1.
エディット・モードに入ります。
※ 設定を変える前に、「LAYER」(P.51)を、1st、2nd の両
方のト ーン が鳴る状態(「Both Tone」「Weak Detune」
「Strong Detune」)に設定しておいてください。
2.
[PARAMETER]で、1:2 BALANCEを選びます。
fig.5-50
52

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
エフェクトの構成と得られる効果
GR-33 の内蔵エフェクトは、次の 3 系統に分類されます。
a. MULTI-FX(マルチ・エフェクト)
b. CHORUS(コーラス)
c. REVERB(リバーブ)
エフェクトの構成は以下のようになっています。
fig.6-00
REV SEND
LEVEL
CHO SEND
LEVEL
MULTI-FX
コーラスとリバーブは並列に接続されています。
MULTI-FX は、40 種類のエフェクト・タイプを持つマルチ・
エフェクトで、ディストーション、ディレイなどのさまざま
なエフェクト・タイプがあります。MULTI-FX のエフェクト・
タイプ中にもコーラス、リバーブがありますが、b. のコーラ
REVERB
CHORUS
MIX
OUT
スとc. のリバーブとは別系統でエフェクトをかけることがで
きます。さらに、2 つのトーンのうちどちらか一方にだけエ
フェクトをかけることもできます。
コーラスは、複数の楽器が重奏しているような感じや、独特
の揺らぎ、空間的な広がりなどをつくるエフェクトです。
リバーブは、響きの良い部屋やホールで演奏した時に得られ
る残響をシミュレーション(模擬的に再現)するエフェクト
です。また GR-33 の内蔵リバーブでは、ディレイ効果(山
びこのような音の繰り返し)も得られます。
これらのエフェクトはそれぞれパッチごとにオン/オフを記
憶することができます。
※ これらのエフェクトは内蔵シンセ音源 専用です。ギター
音など、内蔵シ ンセ音 源以外のものにはかか りません。
なお GUITAR OUT(RETURN)ジャック を使うと、ギ
ター専用エフェクターを外部に追加接続 することができ
ます(P.15)。
※ エフェクトを切り替えたときにノイズが 聞こえる場合が
ありますが、故障ではありません。
マルチ・エフェクトの設定をする
マルチ・エフェクトをオン/オフする
(MULTI-FX SW)
マルチ・エフェクトのオン/オフやマルチ・エフェクトをか
けるトーンの選択は、「MULTI-FX SW」で設定します。
■ マルチ・エフェクトをオン/オフする手順
1.
マルチ・エフェクトを設定するパッチを選び、
[EFFECTS]を押してパッチ・エディット・モードに入
ります。
2.
[PARAMETER]で、MULTI-FX SWを選びます。
fig.6-50
[VALUE]で、設定を変更します。
3.
Off: マルチ・エフェクトをオフにします。
1st: 1st トーンだけにマルチ・エフェクトの効果を
与えます。
Both: 1st / 2nd 両トーンにマルチ・エフェクトの効
果を与えます。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
ペダル効果モードで(または「S1/S2 FUNCTION」で「Patch
Select」を選んだ状態で)、ペダル 4(CTRL)を踏むことに
より、演奏中にマルチ・エフェクトのバイパスをオン/オフ
することもできます。ただし、「CTRL PEDAL」の設定(P.46)
が必要です。
また、パッチ・エディット・モードで、マルチ・エフェクト
関連の設定項目が選ばれている場合も、ペダル 4(CTRL)を
踏むことによりマルチ・エフェクトのバイパスをオン/オフ
することができます。
6章
2nd: 2nd トーンだけにマルチ・エフェクトの効果を
与えます。
53

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
種類を選ぶ(MULTI-FX TYPE)
MULTI-FX には、40 種類のエフェクト・タイプ(MULTI-FX
TYPE)があります。それぞれのエフェクト・タイプには、い
くつかの設定項目(パラメーター)があり、それらを変更す
ることで様々なエフェクト効果を得ることができます。
各エフェクト・タイプの設定項目掲載ページは次の通りです。
1: STEREO-EQ (→ P.55)
2: OVERDRIVE (→ P.55)
3: DISTORTION (→ P.56)
4: PHASER (→ P.56)
5: SPECTRUM (→ P.56)
6: ENHANCER (→ P.57)
7: AUTO-WAH (→ P.57)
8: ROTARY (→ P.57)
9: COMPRESSOR (→ P.58)
10: LIMITER (→ P.58)
11: HEXA-CHORUS (→ P.59)
12: TREMOLO-CHO (→ P.59)
13: SPACE-D (→ P.60)
14: STEREO-CHO (→ P.60)
15: STEREO-FL (→ P.61)
16: STEP-FL (→ P.61)
17: STEREO-DELAY (→ P.62)
18: MOD-DELAY (→ P.63)
19: 3-TAP-DELAY (→ P.63)
20: 4-TAP-DELAY (→ P.64)
21: TIMECTRL-DLY (→ P.65)
22: 2VOICE-P.SFT (→ P.65)
23: FB-P.SFT (→ P.66)
24: REVERB (→ P.67)
25: GATE-REVERB (→ P.67)
26: OD → CHO (→ P.68)
27: OD → FL (→ P.68)
28: OD → DLY (→ P.69)
29: DS → CHO (→ P.69)
30: DS → FL (→ P.69)
31: DS → DLY (→ P.69)
32: EH → CHO (→ P.70)
33: EH → FL (→ P.70)
34: EH → DLY (→ P.71)
35: CHO → DLY (→ P.71)
36: FL → DLY (→ P.72)
37: CHO → FL (→ P.72)
38: CHO / DLY (→ P.73)
39: FL / DLY (→ P.73)
40: CHO / FL (→ P.73)
■ マルチ・エフェクトの設定手順
マルチ・エフェクトを設定するパッチを選び、
1.
[EFFECTS]を押してパッチ・エディット・モードに入
ります。
[PARAMETER]で、MULTI-FX TYPEを選びます。
2.
fig.6-04(MULTI-FX TYPE2)
3.
[VALUE]で、エフェクト・タイプを選びます。
[PARAMETER]を押し、3. で選んだエフェクト・タイプ
4.
の設定項目(パラメーター)を選びます。
各エフェクト・タイプのパラメーター については、次項
「マルチ・エフェクトのパラメーターについて」をご覧く
ださい。
[VALUE]で、値を選びます。
5.
4. 〜 5.の手順を繰り返し、選んだエフェクト・タイプの全
6.
パラメーターを設定します。
7.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
各エフ ェク ト・タイプの設 定 項目(パラメー ター)で
「#」記号のついているものは、EXP ペダルを使って値
を変化させることができます。EXP ペダルの設定につい
ては、「エクスプレッション・ペダルを使う」(P.47) をご
覧ください。
54

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
マルチ・エフェクトのパラメーターに ついて
STEREO-EQ(ステレオ・イコライザー)
1:
低域、中域× 2、高域の音質を調節する、ステレオ・イコラ
イザーです。
fig.6-05(Stereo-EQ)
L in
R in
4-Band EQ
4-Band EQ
LOW FREQ(ロー・フリケンシー)200/400 Hz
低域を調節するときの、基準の周波数を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH FREQ(ハイ・フリケンシー)4000/8000 Hz
高域を調節するときの、基準の周波数を設定します。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
P1 FREQ(ピーキング 1・フリケンシー)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000 (200 〜 8000 Hz)
特定の周波数帯を調節するときの、基準になる周波数を設定
します。
P1 Q(ピーキング 1 ・Q)0.5/1.0/2.0/4.0/8.0
P1 FREQ で設定した周波数を基準として、周波 数帯に幅を
もたせます。値を大きくするほど P1 GAIN で調節する周波
数帯の幅が狭くなります。
P1 GAIN(ピーキング 1・ゲイン)-15 〜 +15 dB
P1 FREQ や P1 Q で設定した周波数帯のゲイン(増幅/減衰
量)を設定します。+ にするほど P1 FREQ、P1 Q で設定し
た周波数帯が強調(増幅)されます。
L out
R out
P2 GAIN(ピーキング 2・ゲイン)-15 〜 +15 dB
P2 FREQ や P2 Q で設定した周波数のゲイン(増幅/減衰
量)を設定します。+ にするほど P2 FREQ、P2 Q で設定し
た周波数帯が強調(増幅)されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127 #
出力音量を設定します。
2:OVERDRIVE(オーバードライブ)
オーバードライブは真空管アンプで歪ませたような、自然な
歪みが得られます。
fig.6-06(OVERDRIVE)
L in
Over
drive
R in
Amp
Simulator
2-Band
EQ
DRIVE(ドライブ)0 〜 127 #
歪み具合を設定します。歪み具合といっしょに音量も変わり
ます。
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
出力音の定位を設定します。
L64 で最も左、0 で中央、R63 で最も右に定位します。
AMP TYPE(アンプ・シミュレーター・タイプ)
Small/Built-In/2-Stack/3-Stack
ギター・アンプの種類を設定します。
Small:
小型アンプをシミュレートしています。
Built-In:
ビルト・イン・タイプのアンプをシミュレートしています。
2-Stack:
大型 2 段積みアンプをシミュレートしています。
3-Stack:
大型 3 段積みアンプをシミュレートしています。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
L out
Pan L
Pan R
R out
6章
P2 FREQ(ピーキング 2・フリケンシー)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000 (200 Hz 〜 8000 Hz)
特定の周波数帯を調節するときの、基準になる周波数を設定
します。
P2 Q(ピーキング 2・Q)0.5/1.0/2.0/4.0/8.0
P2 FREQ で設定した周波数を基準として、周波 数帯に幅を
もたせます。値を大きくするほど P2 GAIN で調節する周波
数帯の幅が狭くなります。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
オーバー ドラ イブをかけたとき とかけ ないときとの音 量差
は、アウトプット・レベルで調節するとよいでしょう。
55

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
Phaser
Resonance
Mix
L in
R in
L out
R out
Pan R
Pan L
3:DISTORTION(ディストーション)
ディストーションはオーバードライブよりも激しい歪みが得
られます。
fig.6-07(DISTORTION)
L in
R in
Distortion
Amp
Simulator
2-Band
EQ
DRIVE(ドライブ)0 〜 127 #
歪み具合を設定します。歪み具合といっしょに音量も変わり
ます。
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
出力音の定位を設定します。
L64 で最も左、0 で中央、R63 で最も右に定位します。
AMP TYPE(アンプ・シミュレーター・タイプ)
Small/Built-In/2-Stack/3-Stack
ギター・アンプの種類を設定します。
Small:
小型アンプをシミュレートしています。
Built-In:
ビルト・イン・タイプのアンプをシミュレートしています。
2-Stack:
大型 2 段積みアンプをシミュレートしています。
3-Stack:
大型 3 段積みアンプをシミュレートしています。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
ディストーションをかけたときとかけないときとのレベル差
はアウトプット・レベルで調節するとよいでしょう。
L out
Pan L
Pan R
R out
4:PHASER(フェイザー)
フェイザーは原音に位相をずらした音を加えて音色を時間的
に変化させ、音をうねらせます。
fig.6-08(PHASER)
MANUAL(マニュアル)100 Hz 〜 8000 Hz
音をうねらせる基準周波数を設定します。
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
うねりの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
うねりの深さを設定します。
RESONANCE(レゾナンス)0 〜 127
フェイザーのフィードバック量を設定します。値を大きくす
るほど、クセの強い音になります。
MIX(ミックス・レベル)0 〜 127
位相をずらせた音を原音に混ぜ合わせる割合を設定します。
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
出力音の定位を設定します。
L64 で最も左、0 で中央、R63 で最も右に定位します。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
5:SPECTRUM(スペクトラム)
スペクトラムはフィルターの一種で、特定の周波数のレベル
を増減させて音色を変えます。
イコライザーと働きが似ていますが、音色のクセをつけるの
に最適な 8 つの周波数が決められているので、より特徴のあ
る音を作ることができます。
fig.6-09(SPECTRUM)
L in
Spectrum
R in
L out
Pan L
Pan R
R out
56
BAND1 〜 8 で各音質を設定します。
BAND1(バンド 1・ゲイン)-15 〜 +15 dB
250 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
BAND2(バンド 2・ゲイン)-15 〜 +15 dB
500 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
BAND3(バンド 3・ゲイン)-15 〜 +15 dB
1000 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
BAND4(バンド 4・ゲイン)-15 〜 +15 dB
1250 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
BAND5(バンド 5・ゲイン)-15 〜 +15 dB
2000 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
BAND6(バンド 6・ゲイン)-15 〜 +15 dB
3150 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
BAND7(バンド 7・ゲイン)-15 〜 +15 dB
4000 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
BAND8(バンド 8・ゲイン)-15 〜 +15 dB
8000 Hz のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
Q 0.5/1.0/2.0/4.0/8.0
各バンド共通で、レベルを変化させる周波数帯の幅を設定し
ます。
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
出力音の定位を設定します。L64 で最も左、0 で中央、R63
で最も右に定位します。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127 #
出力音量を設定します。
7:AUTO-WAH(オート・ワウ)
オート・ワウはフィルターを周期的に動かすことで、ワウ効
果(音色が周期的に変化する効果)を得るエフェクターです。
fig.6-11(AUTO-WAH)
L in
Auto Wah
R in
FILTER TYPE(フィルター・タイプ)LPF/BPF
フィルターの種類を設定します。
LPF(ロー・パス・フィルター):
広い周波数範囲でワウ効果が得られます。
BPF(バンド・パス・フィルター):
狭い周波数範囲でワウ効果が得られます。
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz
ワウ効果の揺れの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
ワウ効果の揺れの深さを設定します。
SENS(センス)0 〜 127
フィルターを変化させる感度を設定します。
L out
R out
6:ENHANCER(エンハンサー)
エンハンサーは 高域の倍音 成分をコントロールすることで、
音にメリハリをつけ、音ヌケをよくします。
fig.6-10(ENHANCER)
L in
R in
Enhancer
Enhancer
Mix
Mix
SENS(センス)0 〜 127
エンハンサーのかかる深さを設定します。
MIX(ミックス・レベル)0 〜 127 #
エンハンサーで生成された倍音を、原音に混ぜ合わせる割合
を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
2-Band
EQ
2-Band
EQ
L out
R out
MANUAL(マニュアル)0 〜 127 #
ワウ効果を与える基準周波数を設定します。
PEAK(ピーク)0 〜 127
基準周波数付近のワウ効果のかかり具合を設定します。
値を小さくすると基準周波数周辺の広い範囲で、値を大きく
すると狭い範囲でワウ効果が得られます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
8:ROTARY(ロータリー)
ロータリーは往年の回転スピーカー・サウンドをシミュレー
トしたエフェクトです。
高域と低域のローターの動作をそれぞれ独立して設定できる
ので、独特のうねり感をリアルに再現できます。オルガンの
パッチに最も効果的です。
fig.6-12(ROTARY)
L in
Rotary
R in
HIGH SLOW
(ハイ・フリケンシー・スロー・レイト)
高域ローターの低速回転時(SLOW)の周期を設定します。
L out
R out
0.05 〜 10.0 Hz
6章
57

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
LOW SLOW
(ロー・フリケンシー・スロー・レイト)
低域ローターの低速回転時(SLOW)の周期を設定します。
0.05 〜 10.0 Hz
HIGH FAST
(ハイ・フリケンシー・ファースト・レイト)
高域ローターの高速回転時(FAST)の周期を設定します。
0.05 〜 10.0 Hz
LOW FAST
(ロー・フリケンシー・ファースト・レイト)
低域ローターの高速回転時(FAST)の周期を設定します。
0.05 〜 10.0 Hz
SPEED(スピード)Slow/Fast #
低域ローターと高域ローターの回転速度(周期)を設定しま
す。
Slow:
Fast 状態から切り換えると、回転スピードが遅くなり、指定
の回転周期(LOW SLOW RATE / HIGH SLOW RATE の
値)になります。
Fast:
Slow 状態から切り換えると、回転スピードが速くなり、指定
の回転周期(LOW FAST RATE / HIGH FAST RATE の値)
になります。
HIGH ACCL
(ハイ・フリケンシー・アクセラレーション)0 〜 15
低速回転から高速回転(または高速回転から低速回転)に切
り替えたときに、高域ローターの回転周期が変化するのに要
する時間を設定します。値を小さくするほど時間がかかりま
す。
9:COMPRESSOR(コンプレッサー)
コンプレッサーは大きなレベルの音を抑え、小さなレベルの
音を持ち 上げ ることで、全体の音 量の ばらつきを抑え るエ
フェクターです。
fig.6-13(COMPRESSOR)
L in
Compressor
R in
2-Band
EQ
SUSTAIN(サスティン)0 〜 127
小さなレベルの音を持ち上げて一定の音量に達するまでの時
間を設定します。
ATTACK(アタック)0 〜 127
入力した音の立ち上がり時間を設定します。
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
出力音の定位を設定します。L64 で最も左、0 で中央、R63
で最も右に定位します。
POST GAIN(ポスト・ゲイン)0/+6/+12/+18 dB
出力するレベルを設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
L out
Pan L
Pan R
R out
LOW ACCL
(ロー・フリケンシー・アクセラレーション)0 〜 15
低速回転から高速回転(または高速回転から低速回転)に切
り替えたときに、低域ローターの回転周期が変化するのに要
する時間を設定します。値を小さくするほど時間がかかりま
す。
HIGH LEVEL
高域ローターの音量を設定します。
(ハイ・フリケンシー・レベル)
0 〜 127
LOW LEVEL(ロー・フリケンシー・レベル)0 〜 127
低域ローターの音量を設定します。
SEPARATION(セパレーション)0 〜 127
音の広がり具合いを設定します。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127 #
出力音量を設定します。
10:LIMITER(リミッター)
リミッターは指定の音量レベルより大きな音を圧縮し、音の
歪みを抑えるエフェクトです。
fig.6-14(LIMITER)
L in
Limiter
R in
2-Band
EQ
THRESHOLD(スレッショルド・レベル)0 〜 127
圧縮を始める音量レベルを設定します。
RELEASE(リリース・タイム)0 〜 127
音量がスレッショルド・レベル以下になってから、効果がな
くなるまでの時間を設定します。
RATIO(コンプレッション・レシオ)
1.5:1 / 2:1 / 4:1 /100:1
圧縮比を設定します。
L out
Pan L
Pan R
R out
58

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
出力音の定位を設定します。L64 で最も左、0 で中央、R63
で最も右に定位します。
POST GAIN(ポスト・ゲイン)0/+6/+12/+18 dB
出力する音のレベルを設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127 #
出力音量を設定します。
11:HEXA-CHORUS
ヘキサ・コーラスは音に厚みと広がりを与える 6 相コーラス
(ディレイ・タイムの異なる 6 つのコーラス音が重なる)です。
fig.6-15(HEXA-CHORUS)
L in
Hexa Chorus
R in
(ヘキサ・コーラス)
Balance D
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
PAN DEV(パン・ディビエーション)0 〜 20
各コーラス音の定位の偏差を設定します。
値を大きくするほどコーラス音の定位が広がります。0 です
べてのコーラス音の定位が中央になります。20 にすると最も
広がります。
BALANCE
原音とコーラス音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でコーラス音
だけが出力されます。
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
TREMOLO-CHO(トレモロ・コーラス)
12:
トレモロ・コーラスはトレモロ効果(音量を周期的に揺らす
効果)のかかったコーラスです。
fig.6-16(TREMOLO-CHORUS)
L in
Tremolo Chorus
R in
PRE DELAY
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
(プリ・ディレイ・タイム)
Balance D
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
0.0 〜 100 ms
6章
PRE DELAY
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
(プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
コーラス音の揺れの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
PRE DLY DEV
プリ・ディレイとは、原音が鳴ってからコーラス音が鳴るま
での時間のことです。このパラメーターは、各コーラス音の
プリ・ディレイの偏差を設定します。値が大きいほど、各コー
ラス音の発音のずれが大きくなります。
(プリ・ディレイ・ディビエーション)
0〜20
DEPTH DEV(デプス・ディビエーション)-20 〜 +20
各コーラス音の揺れの深さの偏差を設定します。
値が大きいほど、各コーラス音の揺れる深さのずれが大きく
なります。
CHORUS RATE(コーラス・レイト)0.05 〜 10.0 Hz
コーラス音の揺れの周期を設定します。
CHORUS DEPTH(コーラス・デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
TREM RATE
トレモロ効果の揺れの周期を設定します。値を大きくするほ
ど周期が速くなります。
TREM SEP
トレモロ効果の広がり具合を設定します。
(トレモロ・レイト)
(トレモロ・セパレーション)
0.05 〜 10.0 Hz #
0 〜 127
TREM PHASE(トレモロ・フェイズ)0 〜 180
トレモロ効果の位相を調節します。
BALANCE
原音とトレモロ・コーラス音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でトレモロ・
コーラス音だけが出力されます。
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
59

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
13:SPACE-D(スペース D)
スペース D は 2相のモジュレーションをステレオでかける多
重コーラスです。変調感はありませんが、透明感のあるコー
ラス効果が得られます。
fig.6-17(SPACE-D)
L in
R in
PRE DELAY
(プリ・ディレイ・タイム)
Balance D
Space D
Space D
Balance D
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
コーラス音の揺れの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
PHASE(フェイズ)0 〜 180
コーラス音の広がり具合を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
2-Band
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
EQ
L out
R out
0.0 〜 100 ms
FILTER TYPE(フィルター・タイプ)Off/LPF/HPF
フィルターの種類を設定します。
Off:
フィルターを使いません。
LPF(ロー・パス・フィルター):
CUTOFF FREQ の値より上の周波数帯域をカットします。
HPF(ハイ・パス・フィルター):
CUTOFF FREQ の値より下の周波数帯域をカットします。
CUTOFF FREQ(カットオフ・フリケンシー)
200/2 50/ 315/400/5 00/6 30/800/10 00/1250 /1600/ 2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 〜 8000 Hz)
フィルターで特定の周波数帯をカットする場合の基準周波数
を設定します。
PRE DELAY
(プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
コーラス音の揺れの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
PHASE(フェイズ)0 〜 180
コーラス音の広がり具合を設定します。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とコーラス音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でコーラス音
だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
14:STEREO-CHO
ステレオ仕様のコーラスです。フィルターを使ってコーラス
音の音質を調節できます。
fig.6-18(STEREO-CHORUS)
L in
Chorus
Chorus
R in
(ステレオ・コーラス)
Balance D
Balance D
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
L out
R out
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とコーラス音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でコーラス音
だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
60

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
15:STEREO-FL(ステレオ・フランジャー)
ステレオ仕様のフランジャーです(LFO は左右同相)。ジェッ
ト機の上昇音/ 下降音のよ うな金属的な響きが得られます。
フィルターを使ってフランジャー音の音質を調節できます。
fig.6-19(STEREO-FLANGER)
L in L out
R in R out
Balance D
Flanger
Feedback
Feedback
Flanger
Balance D
FILTER TYPE(フィルター・タイプ)Off/LPF/HPF
フィルターの種類を設定します。
Off:
フィルターを使いません。
LPF(ロー・パス・フィルター):
CUTOFF FREQ の値より上の周波数帯域をカットします。
HPF(ハイ・パス・フィルター):
CUTOFF FREQ の値より下の周波数帯域をカットします。
CUTOFF FREQ(カットオフ・フリケンシー)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 Hz 〜 8000 Hz)
フィルターで特定の周波数帯をカットする場合の基準周波数
を設定します。
PRE DELAY
原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
(プリ・ディレイ・タイム)
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
0.0 〜 100 ms
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とフランジャー音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でフランジャー
音だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
16:STEP-FL(ステップ・フランジャー)
ステップ・フランジャーはフランジャー音のピッチが段階的
に変化するフランジャーです。ピッチ変化の周期は、特定の
テンポに対する音符の長さで設定することもできます。
fig.6-20(STEP-FLANGER)
L in L out
Step Flanger
Step Flanger
R in R out
PRE DELAY
(プリ・ディレイ・タイム)
Balance D
Feedback
Feedback
Balance D
原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz
フランジャー音の揺れの周期を設定します。
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
0.0 〜 100 ms
6章
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
フランジャー音の揺れの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
PHASE(フェイズ)0 〜 180
フランジャー音の広がり具合を設定します。
FEEDBACK(フィードバック)-98 〜 +98 %
フランジャー 音を再び 入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。値を大きくするほど、クセのある音になり
ます。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
DEPTH(デプス)0 〜 127
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
FEEDBACK(フィードバック)-98 〜 +98 %
フランジャー 音を再び 入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
値を大きくするほど、クセのある音になります。
STEP RATE(ステップ・レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
ピッチ変化の周期を設定します。
PHASE(フェイズ)0 〜 180
フランジャー音の広がり具合を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
61

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とフランジャー音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけ が出力さ れて、D0:100E でフラン
ジャー音だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
STEREO-DELAY(ステレオ・ディレイ)
17:
ステレオ仕様のディレイです。
fig.6-21(STEREO-DELAY)
FeedbackModeがNormalのとき
L in L out
Balance D
Delay
Feedback
Feedback
Delay
R in R out
Balance D
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
DELAY RIGHT
(ディレイ・タイム・ライト)
0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってから右のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
PHASE LEFT(フィードバック・フェイズ・レフト)
Normal/Invert
左のディレイ音の位相を設定します。
Normal:
位相は変わりません。
Invert:
位相が反転します。
PHASE RIGHT(フィードバック・フェイズ・ライト)
Normal/Invert
右のディレイ音の位相を設定します。
Normal:
位相は変わりません。
Invert:
位相が反転します。
FEEDBACK(フィードバック・レベル)-98 〜 +98 %
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
#
FeedbackModeがCrossのとき
L in L out
R in R out
FB MODE
(フィードバック・モード)
Balance D
Delay
Feedback
Feedback
Delay
Balance D
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
Normal/Cross
ディレイ音を戻す入力先を設定します。
Normal:
左のディレイ音は左の入力に、右のディレイ音は右の入力に
戻されます。
Cross:
左のディレイ音は右の入力に、右のディレイ音は左の入力に
戻されます。
DELAY LEFT
(ディレイ・タイム・レフト)
0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってから左のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
HF DAMP(HF ダンプ)
200/250/ 315 /40 0/500/6 30/ 800 /10 00/1250 /16 00/ 200 0/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしないときは Bypass に設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とディレイ音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でディレイ音
だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
62

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
L in
R in
L out
R out
Left Tap
Right Tap
Triple Tap Delay
2-Band
EQ
2-Band
EQ
Balance E
Balance D
Balance E
Balance D
Feedback
Center Tap
18:MOD-DELAY
(モジュレーション・ディレイ)
モジュレーション・ディレイはディレイ音に揺れが加えられ
るエフェクトです。フランジャーのような効果が得られます。
fig.6-22(MODULATION-DELAY)
FeedbackModeがNormalのとき
L in L out
Delay
Feedback
Feedback
Delay
R in R out
FeedbackModeがCrossのとき
L in L out
Delay
Feedback
Feedback
Delay
R in R out
Balance D
Modulation
Modulation
Balance D
Balance D
Modulation
Modulation
Balance D
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
FB MODE(フィードバック・モード)Normal/Cross
モジュレーション・ディレイ音を戻す入力先を設定します。
Normal:
左のモジュレーション・ディレイ音は左の入力に、右のモジュ
レーション・ディレイ音は右の入力に戻されます。
Cross:
左のモジュレーション・ディレイ音は右の入力に、右のモジュ
レーション・ディレイ音は左の入力に戻されます。
RATE(レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
モジュレーション効果の揺れの周期を設定します。
DEPTH(デプス)0 〜 127
モジュレーション効果の揺れの深さを設定します。
PHASE(フェイズ)0 〜 180
モジュレーション・ディレイ音の広がり具合を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とモジュレーション・ディレイ音の音量バランスを設定
します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でモジュレー
ション・ディレイ音だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
19:3-TAP-DELAY
トリプル・タッ プ・ディレ イは、中央、左、右の 3 方 向に
ディレイ音が鳴らせるエフェクターです。ディレイ・タイム
は、特定のテンポに対する音符の長さで設定することもでき
ます
fig.6-23(TRIPLE-TAP-DELAY)
(トリプル・タップ・ディレイ)
6章
DELAY LEFT
(ディレイ・タイム・レフト)
0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってから左のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
DELAY RIGHT
(ディレイ・タイム・ライト)
0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってから右のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
FEEDBACK(フィードバック・レベル)-98 〜 +98 %
モジュレーシ ョン・ディレ イ音を再び入力に戻す割合(%)
を設定します。プラスの値にすると正相で、マイナスの値に
すると逆相で入力に戻されます。
HF DAMP(HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すモジュレーション・ディレイ音について、高域成
分をカッ トす る周波数を設定 します。カ ットしないとき は
Bypass に設定します。
DELAY LEFT(ディレイ・タイム・レフト)
200 〜 1000 ms
原音が鳴ってから左のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
DELAY RIGHT(ディレイ・タイム・ライト)
原音が鳴ってから右のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
※ 設定値はディレイ・タイム・レフトと同様です。
63

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
DELAY CENTER(ディレイ・タイム・センター)
原音が鳴ってから中央のディレイ音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
※ 設定値はディレイ・タイム・レフトと同様です。
FEEDBACK(フィードバック・レベル)-98% 〜 +98%
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
#
HF DAMP(HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしないときは Bypass に設定します。
LEFT LEVEL(レフト・レベル)0 〜 127
左のディレイ音の音量を設定します。
RIGHT LEVEL(ライト・レベル)0 〜 127
右のディレイ音の音量を設定します。
CENTER LEVEL(センター・レベル)0 〜 127
中央のディレイ音の音量を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
原音とディレイ音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でディレイ音
だけが出力されます。
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
4-TAP-DELAY
20:
クアドラプル・タップ・ディレイは 4 つのディレイを持って
います。各ディレイ音のディレイ・タイムは、指定のテンポ
に対する音符の長さで設定することもできます。
fig.6-24(QUADRUPLE-TAP-DELAY)
L in
Feedback
Quadruple Tap Delay
R in
(クアドラプル・タップ・ディレイ)
Balance D
Delay 1
Delay 2
Delay 3
Delay 4
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
DELAY1(ディレイ・タイム 1)200 〜 1000 ms
原音が鳴ってから、ディレイ 1 の音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
※ ディレイ・タイム 2 〜 4 も設定値は同様です。
DELAY2(ディレイ・タイム 2)
原音が鳴ってから、ディレイ 2 の音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
DELAY3(ディレイ・タイム 3)
原音が鳴ってから、ディレイ 3 の音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
DELAY4(ディレイ・タイム 4)
原音が鳴ってから、ディレイ 4 の音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
LEVEL1(レベル 1)0 〜 127
ディレイ 1 の音量を設定します。
LEVEL2(レベル 2)0 〜 127
ディレイ 2 の音量を設定します。
LEVEL3(レベル 3)0 〜 127
ディレイ 3 の音量を設定します。
LEVEL4(レベル 4)0 〜 127
ディレイ 4 の音量を設定します。
64
FEEDBACK(フィードバック・レベル)-98% 〜 +98%
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
#

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
L in
R in
L out
R out
2Voice Pitch Shifter
Level Balance A
Balance E
Balance D
Balance E
Balance D
Level Balance B
PanB R
PanA L
PanA R
PanB L
HF DAMP(HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしないときは Bypass に設定します。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とディレイ音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でディレイ音
だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
21:TIMECTRL-DLAY
(タイム・コントロール・ディレイ)
ディレイ・タイムをリアルタイムにコントロールできます。
ディレイ・タイムを変化させたとき、ディレイ音のディレイ・
タイムとピッチはアクセラレーションで設定した速さで変化
して行きます。設定によっては非常にトリッキーな効果が得
られます。
エクスプレッション・ペダルでディレイ・タイムがコントロー
ルできます。
fig.6-24a(TIME-CONTROL-DELAY)
L in
R in
Balance D
Time Control Delay
Feedback
Balance D
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
L out
R out
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
ディレイ音の定位を設定します。L64 で最も左、0 で中央、
R63 で最も右に定位します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調されます。
BALANCE
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
原音とディレイ音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でディレイ音
だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
22:2VOICE-P.SFT
ピッチ・シフターは原音のピッチをずらすエフェクトです。
2 ボイス・ピッチ・シフターは 2 つのピッチ・シフターを持
ち、ピッチをずらせた 2 つの音を原音に重ねて鳴らすことが
できます。
fig.6-25(2VOICE-PITCH-SHIFTER)
(2ボイス・ピッチ・シフター)
6章
DELAY(ディレイ・タイム)200 〜 1000ms #
原音が鳴ってからディレイ音が発音されるまでの時間を設定
します。
FEEDBACK(フィードバック・レベル)-98 〜 +98 %
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値に設定すると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
ACCELERATION(アクセラレーション)0 〜 15
ディレイ・タイムを変化させた場合、現在のディレイ・タイ
ムから指定のディレイ・タイムに達するまでの時間を調節し
ます。ディレイ・タイムと同時にピッチ変化の速さも変わり
ます。
HF DAMP(HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしないときは Bypass に設定します。
MODE(ピッチ・シフター・モード)1 〜 5
値を大きくするほど反応が遅くなり、音揺れも少なくなりま
す。
COARSE A(コース・ピッチ A)-24 〜 +12 #
ピッチ・シフト A のピッチ・シフト量を半音単位で設定しま
す。(-2 〜 +1 オクターブ)
COARSE B(コース・ピッチ B)-24 〜 +12
ピッチ・シフト B のピッチ・シフト量を半音単位で設定しま
す。(-2 〜 +1 オクターブ)
FINE A(ファイン・ピッチ A)-100 〜 +100
ピッチ・シフト A のピッチ・シフト量を 2 セント単位(1 セ
ント=半音の 1/100)で設定します。
FINE B(ファイン・ピッチ B)-100 〜 +100
ピッチ・シフト B のピッチ・シフト量を 2 セント単位(1 セ
65

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
ント=半音の 1/100)で設定します。
PRE DELAY A
原音が鳴ってからピッチ・シフト A の音が鳴るまでの遅延時
間を設定します。
PRE DELAY B
原音が鳴ってからピッチ・シフト B の音が鳴るまでの遅延時
間を設定します。
(プリ・ディレイ・タイム A)
(プリ・ディレイ・タイム B
)0.0 〜 500 ms
0.0 〜 500 ms
PAN A(アウトプット・パン A)L64 〜 0 〜 R63
ピッチ・シフト A の音の定位を設定します。L64 で最も左、
0 で中央、R63 で最も右に定位します。
PAN B(アウトプット・パン B)L64 〜 0 〜 R63
ピッチ・シフト B の音の定位を設定します。L64 で最も左、
0 で中央、R63 で最も右に定位します。
LVL BALANCE
ピッチ・シフト A とピッチ・シフト B の音量バランスを設定
します。
A100:0B でピッチ・シフト A 音だけが出力され、A0:100B
でピッチ・シフト B 音だけが出力されます。
BALANCE
原音とピッチ・シフト音の音量バラ ンスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でピッチ・シ
フト音だけが出力されます。
(レベル・バランス)
A100:0B 〜 A0:100B
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
23:FB-P.SFT
ピッチ・シフト音を入力に戻すことができるピッチ・シフター
です。
fig.6-26(FBK-PITCH-SHIFTER)
L in
R in
(フィードバック・ピッチ・シフター)
Pitch Shifter
Feedback
Balance D
Balance D
2-Band
EQ
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
L out
R out
MODE(ピッチ・シフター・モード)1 〜 5
値を大きくするほど反応が遅くなり、音揺れも少なくなりま
す。
COARSE(コース・ピッチ)-24 〜 +12 #
ピッチ・シフトする量を半音単位で設定します。(-2 〜 +1 オ
クターブ)
FINE(ファイン・ピッチ)-100 〜 +100
ピッチ・シフトする量を 2 セント単位(1 セント=半音の 1/
100)で設定します。
PRE DELAY
原音が鳴ってからピッチ・シフト音が鳴るまでの遅延時間を
設定します。
(プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 500 ms
FEEDBACK(フィードバック)-98 〜 +98 %
ピッチ・シフト音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
PAN(アウトプット・パン)L64 〜 0 〜 R63
ピッチ・シフト音の定位を設定します。L64 で最も左、0 で
中央、R63 で最も右に定位します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
原音とピッチ・シフト音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でピッチ・シ
フト音だけが出力されます。
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
66

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
24:REVERB(リバーブ)
リバーブは原音に残響を加え、空間の広さなどをシミュレー
トします。
fig.6-27(REVERB)
L in
R in
Balance D
Reverb
Balance D
TYPE(リバーブ・タイプ)
Room1/Room2/Stage1/Stage2/Hall1/Hall2
リバーブの種類を設定します。
Room1: リバーブ音が短く、密度の濃いリバーブ
Room2: リバーブ音が短く、密度の薄いリバーブ
Stage1: 後部リバーブ音の多いリバーブ
Stage2: 初期反射の強いリバーブ
Hall1: 澄んだ響きのリバーブ
Hall2: 豊かな響きのリバーブ
PRE DELAY
原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
(プリ・ディレイ・タイム)
2-Band
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
EQ
L out
R out
0.0 〜 100 ms
25:GATE-REVERB(ゲート・リバーブ)
ゲート・リバーブはリバーブ音を途中でカットするリバーブ
です。
fig.6-28(GATE-REVERB)
L in
R in
Balance D
Gate Reverb
Balance D
TYPE(ゲート・リバーブ・タイプ)
Normal/Reverse/Sweep1/Sweep2
リバーブの種類を設定します。
Normal: 通常のゲート・リバーブ。
Reverse: 逆回転のリバーブ。
Sweep1: リバーブ音が右から左へ移動します。
Sweep2: リバーブ音が左から右へ移動します。
PRE DELAY
原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
(プリ・ディレイ・タイム)
GATE TIME(ゲート・タイム)5 〜 500 ms
リバーブ音の余韻の長さを設定します。
2-Band
Balance E
Balance E
2-Band
EQ
EQ
L out
R out
0.0 〜 100 ms
6章
TIME(リバーブ・タイム)0 〜 127 #
リバーブ音の余韻の長さを設定します。
HF DAMP(HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200〜 8000 Hz), Bypass
リバーブ音の高域成分をカットする周波数を設定します。周
波数を低 くす るほど高域成分 がカッ トされ、やわらかな リ
バーブ音になります。カットしないときは Bypass に設定し
ます。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
原音とリバーブ音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でリバーブ音
だけが出力されます。
(エフェクト・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
LOW GAIN(ロー・ゲイン)-15 〜 +15 dB
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
低域が強調(増幅)されます。
HIGH GAIN(ハイ・ゲイン)-15 〜 +15 dB
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。+ にするほど
高域が強調(増幅)されます。
BALANCE
原音とリバーブ音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でリバーブ音
だけが出力されます。
(エフェクト・バランス)D100:0E〜 D0:100E
#
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
67

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
26:OD → CHO
オーバードライブとコーラスを直列に接続しています。
fig.6-29(OVERDRIVE → CHORUS)
L in
R in
(オーバードライブ→コーラス)
L out
Balance E
Balance E
R out
Overdrive
Balance D
Chorus
Balance D
OD DRIVE(ドライブ)0 〜 127 #
オーバードライブの歪み具合を設定します。歪み具合といっ
しょに音量も変わります。
OD PAN(オーバードライブ・パン)L64 〜 0 〜 R63
オーバードライブ音の定位を設定します。L64 で最も左、0
で中央、R63 で最も右に定位します。
CHO PRE DLY(コーラス・プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
CHO RATE(コーラス・レイト)0.05 〜 10.0 Hz
コーラス音の揺れの周期を設定します。
CHO DEPTH(コーラス・デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
CHO BALANCE
オーバードライブにコーラスを通した音と通さない音の音量
バランスを設定します。
D100:0E でオーバードライブ音だけが出力され、D0:100E
でオーバードライブにコーラスを通した音だけが出力されま
す。
(コーラス・バランス)
D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
27:OD → FL
オーバードライブとフランジャーを直列に接続しています。
fig.6-30(OVERDRIVE → FLANGER)
L in
R in
(オーバードライブ→フランジャー)
Overdrive
Balance D
Feedback
Flanger
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
OD DRIVE(ドライブ)0 〜 127 #
オーバードライブの歪み具合を設定します。歪み具合といっ
しょに音量も変わります。
OD PAN(オーバードライブ・パン)L64 〜 0 〜 R63
オーバードライブ音の定位を設定します。L64 で最も左、0
で中央、R63 で最も右に定位します。
FL PRE DLY
(フランジャー・プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100ms
原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
FL RATE
フランジャー音の揺れの周期を設定します。
(フランジャー・レイト)
0.05 〜 10.0 Hz
FL DEPTH(フランジャー・デプス)0 〜 127
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
FL FEEDBACK
(フランジャー・フィードバック・レベル)
フランジャー 音を再び 入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
-98 % から +98 % まで 2 % きざみで設定できます。0 にす
るとフィードバックはかかりません。
FL BALANCE
オーバードライブにフランジャーを通した音と通さない音の
音量バランスを設定します。
(フランジャー・バランス)
-98 〜 +98 %
D100:0E 〜 D0:100E
68
D100:0E でオーバードライブ音だけが出力され、D0:100E
でオーバードライブにフランジャーを通した音だけが出力さ
れます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
28:OD → DLY
(オーバードライブ→ディレイ)
オーバードライブとディレイを直列に接続しています。
fig.6-31(OVERDRIVE → DELAY)
L in
R in
Overdrive
Balance D
Delay
Feedback
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
OD DRIVE(ドライブ)0 〜 127 #
オーバードライブの歪み具合を設定します。歪み具合といっ
しょに音量も変わります。
OD PAN(オーバードライブ・パン)L64 〜 0 〜 R63
オーバードライブ音の定位を設定します。L64 で最も左、0
で中央、R63 で最も右に定位します。
DLY TIME(ディレイ・タイム)0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
DLY FEEDBACK
(ディレイ・フィードバック・レベル)-98 〜 +98 %
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
-98 % から +98 % まで 2 % きざみで設定できます。0 にす
るとフィードバックはかかりません。
DLY HF DAMP(ディレイ・HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200〜 8000 Hz), Bypass
入力を戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしない時は Bypass に設定します。
29:DS → CHO
(ディストーション→コーラス)
ディストーションとコーラスを直列に接続しています。設定
項目は「26:OD → CHO」とほぼ同じで、以下の 2ヶ所だけ
異なります。
OD DRIVE → DS DRIVE #
(ディストーションの歪み具合を設定します。)
OD PAN → DS PAN
(ディストーション音の定位を設定します。)
fig.6-32(DISTORTION →C HORUS)
L in
R in
30:DS → FL
Balance D
Distortion
Chorus
Balance D
(ディストーション→フランジャー)
L out
Balance E
Balance E
R out
ディストーショ ンとフラン ジャーを直列に接続しています。
設定項目は「27:OD → FL」とほぼ同じで、以下の 2ヶ所だ
け異なります。
OD DRIVE → DS DRIVE #
(ディストーションの歪み具合を設定します。)
OD PAN → DS PAN
(ディストーション音の定位を設定します。)
fig.6-33(DISTORTION →FLANGER)
L in
R in
Distortion
Balance D
Feedback
Flanger
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
6章
DLY BALANCE
(ディレイ・バランス)D100:0E〜 D0:100E
オーバードライブにディレイを通した音と通さない音の音量
バランスを設定します。
D100:0E でオーバードライブ音だけが出力され、D0:100E
でオーバードライブにディレイを通した音だけが出力されま
す。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
31:DS → DLY
(ディストーション→ディレイ)
ディストーションとディレイを直列に接続しています。設定
項目は「28:OD → DLY」とほぼ同じで、以下の 2ヶ所だけ
異なります。
OD DRIVE → DS DRIVE #
(ディストーションの歪み具合を設定します。)
OD PAN → DS PAN
(ディストーション音の定位を設定します。)
fig.6-34(DISTORTION →D ELAY)
L in
Distortion
R in
Balance D
Delay
Feedback
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
69

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
32:EH → CHO
エンハンサーとコーラスを直列に接続しています。
fig.6-35(ENHANCER → CHORUS)
L in
R in
Enhancer
Enhancer
(エンハンサー→コーラス)
Mix
Mix
Balance D
Chorus
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
EH SENS(エンハンサー・センス)0 〜 127
エンハンサーのかかり具合を設定します。
EH MIX(エンハンサー・ミックス・レベル)0 〜 127
原音に対するエンハンサーで生成される倍音の音量を設定し
ます。
CHO PRE DLY(コーラス・プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
CHO RATE(コーラス・レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
コーラス音の揺れの周期を設定します。
CHO DEPTH(コーラス・デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
CHO BALANCE
エンハンサーにコーラスを通した音と通さない音の音量バラ
ンスを設定します D100:0E でエンハンサー音だけが出力さ
れ、D0:100E でエンハンサーにコーラスを通した音だけが
出力されます。
(コーラス・バランス)
D100:0E〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
33:EH → FL
エンハンサーとフランジャーを直列に接続しています。
fig.6-36(ENHANCER → FLANGER)
L in
R in
Enhancer
Enhancer
(エンハンサー→フランジャー)
Balance D
Mix
Mix
Feedback
Flanger
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
EH SENS(エンハンサー・センス)0 〜 127
エンハンサーのかかり具合を設定します。
EH MIX(エンハンサー・ミックス・レベル)0 〜 127
原音に対するエンハンサーで生成される倍音の音量を設定し
ます。
FL PRE DLY(フランジャー・プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
FL RATE
フランジャー音の揺れの周期を設定します。
(フランジャー・レイト)
0.05 〜 10.0 Hz #
FL DEPTH(フランジャー・デプス)0 〜 127
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
FL FEEDBACK
(フランジャー・フィードバック・レベル)
-98 〜 +98 %
フランジャー 音を再び 入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
-98 % から +98 % まで 2 % きざみで設定できます。0 にす
るとフィードバックはかかりません。
70
FL BALANCE
エンハンサーにフランジャーを通した音と通さない音の音量
バランスを設定します。
D100:0E でエンハンサー音だけが出力され、D0:100E で
エンハン サー にフランジャーを 通した 音だけが出力さ れま
す。
(フランジャー・バランス)
D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
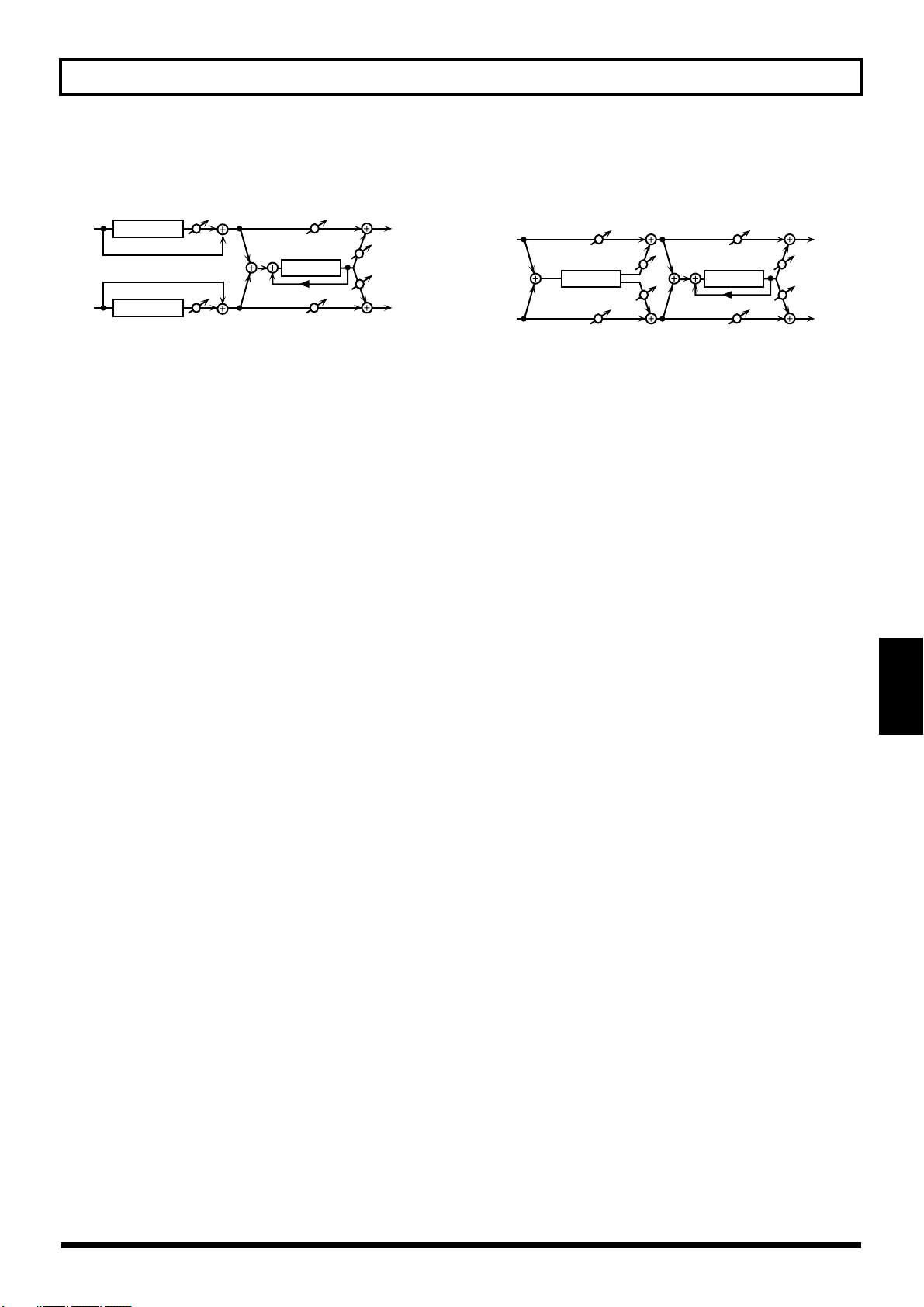
第 6 章 内蔵エフェクトを使う
34:EH → DLY
(エンハンサー→ディレイ)
エンハンサーとディレイを直列に接続しています。
fig.6-37(ENHANCER → DELAY)
L in
R in
Enhancer
Enhancer
Mix
Mix
Balance D
Delay
Feedback
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
EH SENS(エンハンサー・センス)0 〜 127
エンハンサーのかかり具合を設定します。
EH MIX(エンハンサー・ミックス・レベル)0 〜 127
原音に対するエンハンサーで生成される倍音の音量を設定し
ます。
DLY TIME(ディレイ・タイム)0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
DLY FEEDBACK(ディレイ・フィードバック・レベル)
#
-98 〜 +98 %
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
-98 % から +98 % まで 2 % きざみで設定できます。0 にす
るとフィードバックはかかりません。
35:CHO → DLY
(コーラス→ディレイ)
コーラスとディレイを直列に接続しています。
fig.6-38(CHORUS →D ELAY)
L in
R in
CHO PRE DLY
Balance D
Balance E
Chorus
Balance E
Balance D
Balance D
Delay
Feedback
Balance D
(コーラス・プリ・ディレイ)
L out
Balance E
Balance E
R out
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
CHO RATE(コーラス・レイト)0.05 〜 10.0 Hz #
コーラス音の揺れの周期を設定します。
CHO DEPTH(コーラス・デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
CHO BALANCE
(コーラス・バランス)D100:0E〜 D0:100E
原音とコーラス音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でコーラス音
だけが出力されます。
DLY TIME(ディレイ・タイム)0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
6章
DLY HF DAMP(ディレイ HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしない時は Bypass に設定します。
DLY BALANCE
(ディレイ・バランス)D100:0E〜 D0:100E
エンハンサーにディレイを通した音と通さない音の音量バラ
ンスを設定します。
D100:0E でエンハンサー音だけが出力され、D0:100E で
エンハンサーにディレイを通した音だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
DLY FEEDBACK
(ディレイ・フィードバック・レベル)
-98 〜 +98 %
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
-98 % から +98 % まで 2 % きざみで設定できます。0 にす
るとフィードバックはかかりません。
DLY HF DAMP(ディレイ HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/5 00/6 30/800/10 00/1250 /1600/ 2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしない時は Bypass に設定します。
DLY BALANCE
コーラスにディレイを通した音と通さない音の音量バランス
(ディレイ・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
を設定します。
D100:0E でコーラス音だけが出力され、D0:100E でコー
ラスにディレイを通した音だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
71

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
36:FL → DLY
フランジャーとディレイを直列に接続しています。
fig.6-39(FLANGER → DELAY)
Balance D
L in
R in
Feedback
Flanger
Balance D
(フランジャー→ディレイ)
L out
Balance E
Balance E
R out
Balance E
Balance E
Balance D
Delay
Feedback
Balance D
FL PRE DLY(フランジャー・プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
FL RATE
フランジャー音の揺れの周期を設定します。
(フランジャー・レイト)
0.05 〜 10.0 Hz #
FL DEPTH(フランジャー・デプス)0 〜 127
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
FL FEEDBACK
(フランジャー・フィードバック・レベル)
-98 〜 +98 %
フランジャー 音を再び 入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
-98 % から +98 % まで 2% きざみで設定できます。0 にする
とフィードバックはかかりません。
FL BALANCE
原音とフランジャー音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でフランジャー
音だけが出力されます。
(フランジャー・バランス)
D100:0E 〜 D0:100E
DLY TIME(ディレイ・タイム)0.0 〜 500 ms
原音が鳴ってからディレイ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
DLY FEEDBACK
ディレイ音を再び入力に戻す割合(%)を設定します。プラ
スの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入力に
戻されます。
-98 % から +98 % まで 2% きざみで設定できます。0 にする
とフィードバックはかかりません。
(ディレイ・フィードバック)
-98 〜 +98 %
DLY HF DAMP(ディレイ・HF ダンプ)
200/2 50/ 315/400/50 0/6 30/800/100 0/1250 /16 00/2000/
2500/3150/4000/5000/6300/8000(200 〜 8000 Hz), Bypass
入力に戻すディレイ音について、高域成分をカットする周波
数を設定します。カットしない時は Bypass に設定します。
DLY BALANCE
フランジャーにディレイを通した音と通さない音の音量バラ
ンスを設定します。
D100:0E でフランジャー音だけが出力され、D0:100E で
フランジャーにディレイを通した音だけが出力されます。
(ディレイ・バランス)D100:0E 〜 D0:100E
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
37:CHO → FL
コーラスとフランジャーを直列に接続しています。
fig.6-40(CHORUS →FLANGER)
L in
R in
Balance D
Chorus
Balance D
(コーラス→フランジャー)
Balance D
Balance E
Balance E
Feedback
Flanger
Balance D
L out
Balance E
Balance E
R out
CHO PRE DLY(コーラス・プリ・ディレイ・タイム)
0.0 〜 100 ms
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
CHO RATE(コーラス・レイト)0.05 〜 10.0 Hz
コーラス音の揺れの周期を設定します。
CHO DEPTH(コーラス・デプス)0 〜 127
コーラス音の揺れの深さを設定します。
CHO BALANCE
原音とコーラス音の音量バランスを設定します。
D100:0E で原音だけが出力され、D0:100E でコーラス音
だけが出力されます。
(コーラス・バランス)D100:0E〜 D0:100E
FL PRE DLY
(フランジャー・プリ・ディレイ・タイム)
原音が鳴ってからフランジャー音が鳴るまでの遅延時間を設
定します。
FL RATE
フランジャー音の揺れの周期を設定します。
(フランジャー・レイト)
0.0 〜 100 ms
0.05 〜 10.0 Hz #
FL DEPTH(フランジャー・デプス)0 〜 127
フランジャー音の揺れの深さを設定します。
FL FEEDBACK
(フランジャー・フィードバック・レベル)
-98 〜 +98 %
フランジャー 音を再び 入力に戻す割合(%)を設定します。
プラスの値にすると正相で、マイナスの値にすると逆相で入
力に戻されます。
-98 % から +98 % まで 2 % きざみで設定できます。0 にす
るとフィードバックはかかりません。
72

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
FL BALANCE
(フランジャー・バランス)
D100:0E 〜 D0:100E
コーラスにフランジャーを通した音と通さない音の音量バラ
ンスを設定します。
D100:0E でコーラス音だけが出力され、D0:100E でコー
ラスにフランジャーを通した音だけが出力されます。
LEVEL(アウトプット・レベル)0 〜 127
出力音量を設定します。
38:CHO/DLY
コーラス とデ ィレイを並列に 接続し ています。設定項目 は
「35:CHO → DLY」と同じです。
ただし、DLY BALANCE では原音とディレイ音の音量バラン
スを設定します。
fig.6-41(CHORUS/DELAY)
L in L out
R in R out
(コーラス/ディレイ)
Balance D
Chorus
Feedback
Delay
Balance D
Balance E
Balance E
40:CHO/FL
(コーラス/フランジャー)
コーラスとフランジャーを並列に接続しています。設定項目
は「37:CHO → FL」と同じです。
ただし、FL BALANCE では原音とフランジャー音の音量バ
ランスを設定します。
fig.6-43(CHORUS/FLANGER)
Chorus
Feedback
Flanger
Balance D
Balance E
Balance E
Balance D
L in L out
R in R out
39:FL/DLY
(フランジャー/ディレイ)
フランジャーとディレイを並列に接続しています。設定項目
は「36:FL → DLY」と同じです。
ただし、DLY BALANCE では原音とディレイ音の音量バラン
スを設定します。
fig.6-42(FLANGER/DELAY)
Flanger
Feedback
Feedback
Delay
Balance D
Balance E
Balance E
Balance D
L in L out
R in R out
6章
73

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
コーラスの設定をする
揺らぎの深さや速さなど、コーラス音の鳴らし方を設定しま
す。
■ コーラスを設定する手順
1.
コーラスを設定する パッチを選び、[EFFECTS]を押し
てパッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]で、CHORUS 関連のパラメーターを選
2.
びます。
コーラスのパラメーターの種 類については、「◆ コーラ
スのパラメーターとその意味」をご覧ください。
fig.6-02(CHORUS)
3.
[VALUE]で、設定値を選びます。
設定値に ついて は、手順説明後の「◆ コーラスのパ ラ
メーターとその意味」をご覧ください。
2.〜3.の手順を繰り返し、コーラスの全パラメーターを設
4.
定します。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
5.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
◆ コーラスのパラメーターとその意味
CHO SEND LEVEL(コーラス・センド・レベル)
コーラス音の音量を調節します。値が大きいほど音量が大き
くなります。
CHORUS RATE(コーラス・レイト)
コーラス音の揺れの周期を設定します。値が大きいほど揺れ
が速く(周期が短く)なります。
CHORUS DEPTH(コーラス・デプス)
コーラス音の揺れの深さを設定します。値が大きいほど揺れ
が深くなります。
CHORUS PRE-DELAY(コーラス・プリ・ディレイ)
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。値を大きくするほど音が広がります。
CHORUS FEEDBACK(コーラス・フィードバック)
コーラスに通した音を再びコーラスの入力に戻す(フィード
バック)量を設定します。値を大きくするほど複雑なコーラ
ス効果がかかります。
リバーブ(残響)の設定をする
GR-33 では、8 つのタイプ(REVERB TYPE)からひとつを
選び、さらに残響音 の量や長 さなどを自由に設定できます。
タイプの選択により、ディレイ効果(山びこのような音の繰
り返し)などを得ることもできます。
■ リバーブを設定する手順
リバーブを設定する パッチを選び、[EFFECTS]を押し
1.
てパッチ・エディット・モードに入ります。
2.
[PARAMETER]で、REVERB TYPEを選びます。
fig.6-01(REVERB)
[VALUE]で、リバーブ・タイプを選びます。
3.
設定値に ついて は、手順説明後の「◆ リバーブのパ ラ
メーターとその意味」をご覧ください。
[PARAMETER]で、まだ設定していないリバーブのパラ
4.
メーターを選びます。
リバーブのパラメーター の種類については、「◆ リバー
ブのパラメーターとその意味」をご覧ください。
[VALUE]で、値を選びます。
5.
6.
4.〜5.の手順を繰り返し、リバーブの全パラメーターを設
定します。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
7.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
◆ リバーブのパラメーターとその意味
REVERB TYPE(リバーブ/ディレイ・タイプ)
リバーブ(またはディレイ)の種類を設定します。
74

第 6 章 内蔵エフェクトを使う
Room1:リバーブ音が短く、密度の濃いリバーブ
Room2:リバーブ音が短く、密度の薄いリバーブ
Stage1:後部リバーブ音の多いリバーブ
Stage2:初期反射の強いリバーブ
Hall1:澄んだ響きのリバーブ
Hall2:豊かな響きのリバーブ
Delay:一般的なディレイ
Pan Delay:反射音が左右にパンニング(移動)するディレイ
REV SEND LEVEL(リバーブ/ディレイ・センド・レベル)
リバーブ音(またはディレイ音)の音量を調節します。値が
大きいほど音量が大きくなります。
REVERB TIME(リバーブ/ディレイ・タイム)
REVERB TYPE が「Delay」、「Pan Delay」(ディレイ)のと
きはディレイ・タイム(遅延時間)を設定し、それ以外(リ
バーブ)の時はリバーブが続く時間を設定します。値が大き
いほど時間が長くなります。
REVERB HF DAMP(リバーブ/ディレイ・HF ダンプ)
リバーブ音の高域成分をカットする周波数を設定します。周
波数を低 くす るほど高域成分 がカ ットされ、やわらか なリ
バーブ音になります。カットしないときは「Bypass」に設定
します。
DELAY FEEDBACK(ディレイ・フィードバック)
REVERB TYPE が「Delay」、「Pan Delay」(ディレイ)のと
きのみ、設定が有効です。ディレイ音を再びディレイの入力
に戻す(フィード・バック)量を設定します。値が大きくな
るほどディレイ音が持続します。
エフェクトの一時オフについて(EFFECT BYPASS)
「エフェクト有り/無しで、音を比較したい」という場合をは
じめ、エフェクト関連の項目を設定してパッチ作りをしてい
る途中、簡単な操作で、内蔵のリバーブ、コーラス、マルチ・
エフェクトを一時的に切りたい時があります。
このような時に便利なのが、エフェクトのバイパス機能
(EFFECT BYPASS)です。
■ エフェクトを一時的に切る手順
パッチ・エディット・モードの EFFECTS(エフェクト関
1.
連の設定)の状態で、[EFFECTS]を押します。
内蔵のリバーブ、コーラス、マルチ・エフェクトのうち、
エディット中のエフェクトがオフになりバイ パス状態に
なります。3 桁表示器のEdtが点滅し、バイパス状態
であることを示します。
※ バイパス機能によってバイパスになるエ フェクトは、エ
ディット中のエフェクトのみです。
※ パッチ・エディット・モードの EFFECTS(エフェクト
関連の設定)以外の状態では、バイパス機 能は効きませ
ん。
※ バイパス機能を使っても、設定中のエフェ クトの内容が
変更されることはありません。
再度[EFFECTS]を押します。
2.
バイパス機能は解除され、バイパスにする 以前の状態に
戻ります。
3 桁表示器は、Edtの点滅から点灯に戻ります。
※ 「EFFECT BYPASS」状態はあくまで一時的なものですの
で、パッチごとに記憶操作したり、電源を 切ってもバイ
パス状態が保持されることはありません。
パッチ ごと にエフェク トを オフするに は、REV SEND
LEVEL(P.75)と CHO SEND LEVEL(P.74)を「0」に、
MULTI-FX SW(P.53)を「Off」に 設定して、パッ チに
記憶させてください。
6章
内蔵エフェクトが効かない時は
内蔵のリバーブ、コーラス、マルチ・エフェクトが効かない
ときには次の各項目を再確認してください。
3 桁表示器にEdtが点滅表示してバイパス機能が働い
•
ていないか。
•
「MULTI-FX SW」(P.53)を「Off」に設定していないか。
「REV SEND LEVEL」(P.75)が適正な値に上がってい
•
るか。
•
「CHO SEND LEVEL」(P.74)が適正な値に上がってい
るか。
「Rev Send Level」(リバーブ・センド・レベル)機能が
•
選ばれたエクスプレッション・ペダル(P.47)が、引き
戻されきった状態になっていないか。
「Cho Send Level」(コーラス・センド・レベル)機能が
•
選ばれたエクスプレッション・ペダル(P.47)が、引き
戻されきった状態になっていないか。
•
マルチ・エフェクトで選ばれているエ フェクト・タイプ
の「LEVEL」などは、適正な値になっているか。
75

第 7 章 和音演奏を分散和音に展開する〜アルペジエーター
GR-33 にはギターの奏法に特 化した、ユニークなアル ペジ
エーター機能が搭載されています。オンにしてコードをひと
弾きすれば、細かいピッキング作業(弾く弦の選択とそのリ
ズム)を、アルペジエーターが肩代わりして行ってくれます。
アルペジエーターのしくみ
「アルペジオ・パターン」について
実物のアコースティック・ギターで、最も簡単なアルペジオ
奏法をする場合を考えてみましょう。
この時左手は、曲の進行に合わせて押さえるコードを順に変
えていきま す。一方右手 は弦を、例えば「5、4、3、4、1、
3、2、3(数字は弦番号)」のような一定のパターンに従い、
リズムにのせて弾いていきます。
fig.7-01(アルペジオ・パターン)
(コード=C)
1弦
2弦
3弦
4弦
5弦
6弦
0
2
3
0
2
1
0
0
アルペジ エー ターにシンセ音で 簡単な バッキングを担 当さ
せ、その上に手弾きのメロディーを乗せるといった使い方を
はじめ、従来のギター・シンセでは表現できなかった様々な
効果を得ることができます。
この「5、4、3、4、...」のような弾弦順に相当するのが、GR33 でいうアルペジオ・パターン(または単に「パターン」)
です。
GR-33 には 50 種類のアルペジオ・パターンがプリセットさ
れています。それぞれのパッチで、プリセットの中からアル
ペジオ・パターンを選ぶことができます。アルペジエーター
をオンにし、任意のコード(または単音)を押さえてひと弾
きすれば、パターンが各弦の鳴り方と関連する設定項目
(ARP TEMPO など)を参照して、シンセ音でアルペジオを
鳴らします。
※ データ上に仕込まれていない弦(この図の例では 6 弦)
が弾かれた時や、仕込まれたデータと異な る本数の弦が
弾かれた場合、コード中の最低音(ルー ト音)の変化な
どがなるべく自然になるよう設定された 内部ルールに基
づいて、代理の弦を鳴らしアルペジオを構成します。
アルペジオ中のホールド機能の有効な使い方
ペダル効果モード時などでペダル 3 を踏むと得られるホール
ド効果を使うと、アルペジエーターが刻むリズムを止めたり
崩したりせず、演奏するコードを進行させることなどができ
ます。
アルペジエーターがオンになっている時は、ホールド・ペダ
ルの効果が通常と挙動が変わり、アルペジオ効果のみにかか
ります。従ってアルペジエーターによるバッキング・パター
ンをホールドしておき、別のシンセ音(トーン)でメロディ
を手弾きする、といった使い方ができます。
また、ペダルから足を離しても(再度踏むまで)アルペジオ
が継続する、ラッチ式ホールドも用意されています。
ホールドの効き方は、パッチ・エディット・モードの
COMMON の設定項目「HOLD TYPE」で設定します。
詳しい操作方法は、「ホールドの効き方を選ぶ(HOLD
TYPE)」(P.45)をご覧ください。
◆ アルペジエ ーターがオン の時に選べる ホールドの
バリエーション
アルペジエーターがオンの時に選べるのは、次の 4 通りです。
Damper(ダンパー):
ペダルを踏んでギターを演奏するとアルペジオ音が、弦振動
が減衰しても消えずに保持されます。さらに弦を弾き加えて
いくと、その演奏がアルペジオに反映されます。
ペダルを離すと、アルペジオが保持されなくなります。(すで
に弦振動が止まっていれば、アルペジオは止まります。)ア ル
ペジエーターが作るリズムの刻みを乱すことなく、アルペジ
オの鳴りかたを変えていきたい時などに使います。
Sostenuto(ソステヌート):
ギターを弾いてアルペジオ効果が得られている時にペダルを
踏むと、踏んだ瞬間に鳴っていたアルペジオが、ペダルから
足を離すまで保持されます。アルペジオが保持されている間
は、新たに弦を弾いてもその演奏はアルペジオ音に反映され
ません。
1st トーンと 2nd トーン、シンセ音とギター音を使い分けて、
アルペジオをバックにメロディなどを演奏することができま
す。
76

第 7 章 和音演奏を分散和音に展開する〜アルペジエーター
Latch TypeA(ラッチ式ホールド A):
通常のホール ドは、「ペ ダルを踏む→ホー ルド開始、離す→
ホールド解除」という動作です。これに対し、ラッチ式ホー
ルドでは、「ペダルを 1 度踏む→ホールド開始、再度踏む→
ホールド解除」という動作になります。GR-33 では、ラッチ
式ホールドはアルペジエーター使用時のみに用意されていま
す。
アルペジエーターを鳴らし、ペダル 3(HOLD)を踏むと、踏
んだ時点に鳴っていたアルペジオが保持されます。ラッチ式
ですので、ペダルから足を離しても効果は続き、再度ペダル
を踏んだ時 点で解 除されます。ホールド中 は「Sostenuto」
と同様、新たに弦を弾いてもその演奏がアルペジオ音に反映
されることはありません。
またラッチ・ホールド中に限り、ペダル 4(CTRL)(通常は
アルペジオのオン/オフ用)を使って、リズムを崩さずにア
ルペジオ音のコード・チェンジを行うことができます。
アルペジオの鳴りかたを変える
GR-33 のアルペジエーターでは、アルペジオさせるトーンの
選択(HAR/ARP SELECT)、アルペジオ・パターンの選択
(ARP PATTERN)、テンポの設定(ARP TEMPO)ができ
ます。
コード・チェンジをしたい時は、ペダル 4(CTRL)を踏み、
新たなコードを弾いてからペダルから足を離します。鳴って
いるアルペジオ音のリズムを止めることなく、コードが変わ
ります。
Latch TypeB(ラッチ式ホールド B):
基本的な動きは「Latch TypeA」と同じで、ペダルから足を
離してもアルペジオの保持は続き、再度ペダルを踏んだ時点
で解除されます。同様に、ホールド中に新たな弦を弾いても、
その演奏はアルペジオに影響しません。
「Latch TypeA」との違いは、ホールド中にペダル 4(CTRL)
を踏んだ状態でギターを弾いた時の挙動です。
「Latch TypeB」の場合、この操作で得ら れるアルペ ジオの
変化は、「Damper」と同じです。「Latch TypeA」のように、
弾かれた弦の選択や本数を元にしたアルペジオ自体の再構成
はしません。
5.
ペダル効果モードに入ります。
詳しい操作方法は「「ペダル効果モード」とその呼び出しか
た」(P.26)をご覧ください。
アルペジエーターのオン/オフを切り 替える(HAR/ARP CONTROL)
ペダル 4(CTRL)でアルペジエーターをオン/オフ
する
演奏中にアルペジエーターをオン/オフする時などは、以下
のように設定します。
1.
[COMMON]を押して、パッチ・エディット・モードに
入ります。
[PARAMETER]で、CTRL PEDALを選びます。
2.
3.
[VALUE]で、HAR/ARP Controlを選びます。
fig.7-01a
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
※ または、システム・モードの設定項目「S1/S2 FUNCTION」
で「Patch Select」を選び、プレイ・モードに戻ります。
ペダル 4(CTRL)を踏んで、アルペジエーターのオン/
6.
オフを切り替えます。
パッチ・エディット・モードでアルペジエーターをオ
ン/オフする
アルペジエーターのオン/オフをパッチに記憶させる時など
は、以下のように行います。
[EFFECTS]を押して、パッチ・エ ディット・モ ードに
1.
入ります。
[PARAMETER]で、HAR/ARP CONTROLを選びます。
2.
3.
[VALUE]で、OnまたはOffを選び、アルペジエー
ターのオン/オフを設定します。
fig.7-01b
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
7章
77

第 7 章 和音演奏を分散和音に展開する〜アルペジエーター
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
※ また、ア ルペジエー ター関連 の設定項目 である「HAR/
ARP CONTROL」「HAR/ARP SELECT」「ARP PATTERN」
が選ばれている時は、ペダル 4(CTRL)でアルペジエー
ターをオン/オフすることができます。
※ アルペジエーターのオン/オフはパッチごと の設定項目
です。パッチ・ライト操作を実行すると、その 時の状態
(オンかオフか)が記憶され、パッチを呼び出した時に再
現されます。
各パッチで、アルペジエーターとハーモニストのどちらか一
方だけが選べるようになっています。オフのパッチも、内部
ではアルペジエーターかハーモニストのどちらかが選ばれて
います。オンの状態の時、プレイ・モードのディスプレイに
ARPかHARのどちらか選ばれている方が表示されます。
fig.7-03(ARP)
ハーモニストが選ばれたパッチでアルペジエーターを使う時
は、次項の手順に従い、「HAR/ARP SELECT」の設 定で
「Arpeggio All」などのアルペジエーターの設定に切り替えて
ください。
※ アルペジエーターがオフになっているパッチで、アルペジ
オ関連の項目(「HAR/ARP SELECT」「ARP PATTERN」
「ARP TEMPO」)の値や設定を変えると、効果が確認でき
るようアルペジエーターは自動的にオンになります。
[VALUE]で、アルペジエーターの設定を選びます。
3.
「HAR/ARP SELECT」でのアルペジエーターの設定につ
いては、手順説明後の「◆ HAR/ARP SELECT で選べる
アルペジエーターの設定について」をご覧ください。
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
アルペジエーターの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を 選び、項目内容を設定
してください。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
◆ HAR/ARP SELECTで選べるアルペジエーターの設
定について
Arpeggio All:
全ての音(内蔵音源、外部 MIDI 音源)がアルペジオします。
Arpeggio 1st:
内蔵音源の 1st トーンだけがアルペジオします。
Arpeggio 2nd:
内蔵音源の 2nd トーンだけがアルペジオします。
Arpeggio 1&2:
1st、2nd 両トーンがアルペジオします(外部 音源はアルペ
ジオしません)。
Arpeggio Ext:
外部 MIDI 音源のみがアルペジオします。
アルペジオさせるトーンを選択する
(HAR/ARP SELECT)
アルペジエーターが 1st トーン/ 2nd トーン/外部音源の 3
つのうち、どの音色をアルペジオさせるかは、パッチごとに、
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」(ハーモニー/アルペジオ・セレクト)で決
められます。プリセット・パッチのこの設定を実際に変更し、
その働きを耳で確認してみましょう。
■ アルペジオさせるトーンを選択する手順
アルペジエーターの設 定を変更する パッチを選び、
1.
[EFFECTS]を押してパッチ・エ ディット・モード に入
ります。
[PARAMETER]で、HAR/ARP SELECTを選びます。
2.
fig.7-04(ARP SELECT)
Arpeggio Ext&1:
1st トーンと外部 MIDI 音源がアルペジオします。
Arpeggio Ext&2:
2nd トーンと外部 MIDI 音源がアルペジオします。
※ 設定範囲の前半の値(Harmony All、Harmony 1st、
...Harmony Ext&2)も選べますが、これらを選ぶとアルペジ
エーターは停止し、ハーモニスト機能(P.80)が選ばれます。
ハーモニストが選ばれていると、「ARP PATTERN」「ARP
TEMPO」の設定項目も選択できませんのでご注意くださ
い。
アルペジオのパターンを選択する
(ARP PATTERN)
GR-33 には、50 種類のアルペジオ・パターンがプリセット
されています。各パッチで、プリセットから自由にアルペジ
オ・パターンを選択することができます。
アルペジオ・パターンの詳しい内容については、「「アルペジ
オ・パターン」について」(P.76)をご覧ください。
78

第 7 章 和音演奏を分散和音に展開する〜アルペジエーター
■ アルペジオ・パターンを選択する手順
アルペジオ・パターンを変更するパッチを選び、
1.
[EFFECTS]を押してパッチ・エディット・モードに入
ります。
[PARAMETER]で、ARP PATTERNを選びます。
2.
fig.7-05(ARP. PATTERN)
3.
[VALUE]で、アルペジオ・パターンを選びます。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
アルペジエーターの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を選 び、項目内容を設定
してください。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
ペダルを使ってテンポを設定する
(タップ・テンポ・ティーチ機能)
アルペジエーターのテンポの設定中は、ペダルを踏んでリズ
ムをとることでテンポの設定/変更ができます。この機能を
タップ・テンポ・ティーチ機能といいます。
通常ペダル 4(CTRL)は、パッチ・エディット・モ ードに
入りアルペジオ関連の項目の設定をしている場合、アルペジ
オのオン/オフに使われます。
この例外として、アルペ ジオ・テンポの設 定中は、タップ・
テンポ・ティーチ機能にペダル 4(CTRL)を使います。
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「ARP.
TEMPO」で、テンポがディスプレイに表示されている時、ペ
ダル 4(CTRL)を希望するテンポの速さで「ポン、ポン、ポ
ン ...」と数回踏むと、ディスプレイにTAPと表示され、
テンポが変更されます。テンポが確定するとTAPの表示
は消えます。
fig.7-07(タップ・テンポ・ティーチ)
テンポを設定する(ARP TEMPO)
アルペジオのテンポは、自由に変更してパッチに記憶させる
ことができます。
この設定項目が「ARP TEMPO」(アルペジオ・テンポ)です。
■ アルペジオ・テンポを設定する手順
アルペジオ・テンポを変更するパッチを選び、
1.
[EFFECTS]を押してパッチ・エディット・モードに入
ります。
[PARAMETER]で、ARP TEMPOを選びます。
2.
fig.7-06(ARP. TEMPO)
[VALUE]で、設定値を選びます。
3.
ARP TEMPO の設定値は 50 〜 250 です。値が大きいほ
どテンポが速くなります。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
アルペジエーターの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を選 び、項目内容を設定
してください。
元のテンポ
7章
変更完了
※ タップ・テンポ・ティーチ機能は、ペダル効 果モード時
の BANK SHIFT ペダル(アップ側)によっても行えます。
(アルペジエーターがオンの場合のみ)
※ 変更されたテンポはパッチの設定項目 ですので、必要で
あれば[WRITE]ボタンを押してパッチ・ライトを行い、
パッチに記憶させてください。
※ プリセット・パッチのなかには、トレモロ の細かい符割
りを実現するために、「ARP TEMPO」の数値を実際のテ
ンポの倍に設定してあるものがありま す。このように特
殊な設定 により、タ ップ・テンポ・ティーチを 行う時、
テンポの解釈がやや不自然なパターンも ありますがご了
承ください。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
79
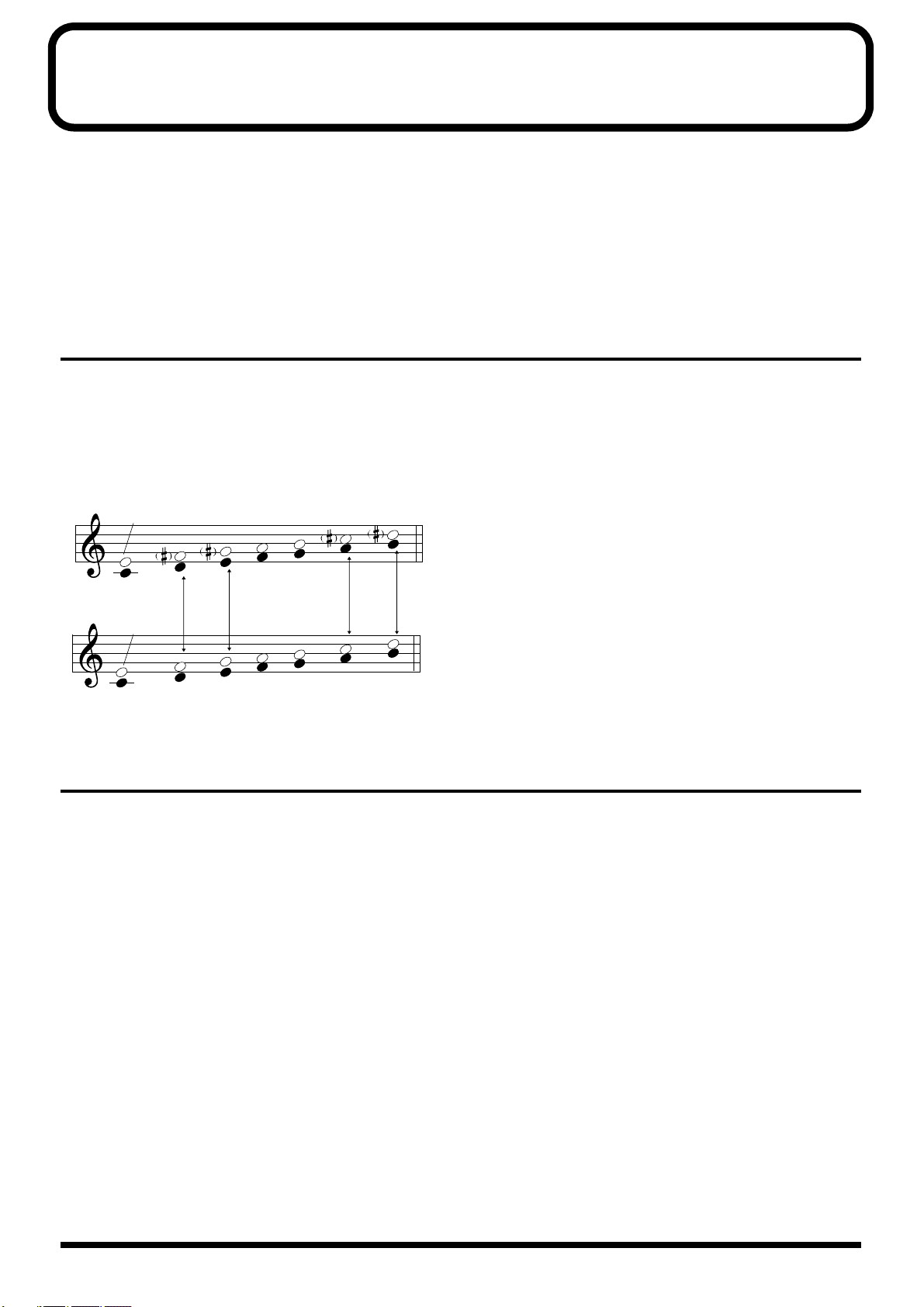
第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト
GR-33 では、TONE の「TRANSPOSE」の設定(P.51)に
より、1st 及び 2nd トーンの音高を、ギター音に対して平行
にずらし、重音効果をつくれます。
しかし、より音楽的なハーモニーを表現するには、2 つのパー
トの音高差を、曲のキー(調)と鳴らしている音階の関係に
従い、随時変化させてやる必要があります。
ハーモニストのしくみ
トランスポーズ機能の効果と比較しながら、ハーモニストの
しくみを確認しましょう。
下の譜面例 は、キー C(ハ長調)で「ドレミ ファソラシド」
を弾いた際の、トランスポーズ機能とハーモニストの効果の
比較です。
fig.8-01(譜面例)
トランスポーズ
トランスポーズ音
ノーマル音
ハーモニスト
ハーモニー音
これを実現するのが、「ハーモニスト機能」です。
演奏するメロディのキーなどをパッチに設定しておけば、ギ
ター音にシンセ音で(またはシンセ音同士で)美しいハーモ
ニーを表現することができます。
両者は図中の↑印の部分が異なっています。
平行音程では調性上、これらの部分が不自然に感じられてし
まいます。この問題が生じる音階上の位置は、キーや長調/
短調、また主旋と副旋律の音程などによって変わります。
GR-33 のハーモニストは、キーなどのパッチにあらかじめ設
定された情報を元に、ギター音対シンセ音(または 1st トー
ン対 2nd トーンなど)の音程を随時調整し、メロディアスな
ハーモニーを作り出します。
また GR-33 のハーモニストは和音演奏に完全対応していま
す。このためミュートを意識しないラフな演奏の際の誤動作
も、非常に少なくなっている上、単純な 3 声コードを弾くだ
けで、複雑なコードの響きをつくるといった効果も得られま
す。
ノーマル音
ハーモニストでできること
ギター音にシンセ音でハーモニーをつ ける
市販のエフェクター「ハーモニスト」は、ピッチ・シフター
の 1 種ですので、ギター音にはギター音でのみハーモニーが
つけられます。
これに対し、GR-33 のシンセ・ハーモニストは、普段使って
いるギターの音に、384 種ものトーンを使って作ったあらゆ
る音色で、ハーモニーをつけることができます。
クリーンなギター音にマリンバなどでさりげないハーモニー
をつけたり、ディストーション・ギターにロック系オルガン
でマイナーのハーモニーをつけるなど、実用的に使用できま
す。
もちろん GR-33 側のトーンにギター系の音色を選べば、「ギ
ター対ギター」風のハーモニーも得られます。
ギター音に GR-33の音でハーモニーをつける場合は、GK-2A
のギター/シンセ切り替えスイ ッチを「MIX」に合わせてお
いてください。
※ パッチで選ばれている全てのシンセ音(1st、2nd の両
トーンから外部 MIDI 音源まで)をギター音に対するハー
モニー・パ ート にするには、P.82 の手 順で HAR/ARP
SELECT の設定を「Harmony All」にします。
シンセ音同士でハーモニーを作る
GK-2A のギター/シンセ切り替えスイッチを「SYNTH」に
合わせ、ギター側の音を鳴らなくしていても、シンセ音だけ
でハーモニーを構成することができます。
よく似た音色同士でハーモニーを構成し、重厚な音づくりを
することができます。全く異なるトーン同士(例えばサック
スとミュート・トラペットなど)でハーモニーを構成し、両
トーンを COMMON の設定項目「PAN MODE」(P.41)で
「Cross Tones」を選んで左右に振り 分ける、なども 非常に
効果的です。GK-2A のスイッチを「MIX」に合わせれば、主
旋律側にさらにギターの音を重ねて鳴らすことも可能です。
80

操作のしかた
第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト
ハーモニストをオン/オフする
(HAR/ARP CONTROL)
ペダル 4(CTRL)でハーモニストをオン/オフする
演奏中にハーモニストをオン/オフする時などは、以下のよ
うに設定します。
1.
[COMMON]を押して、パッチ・エディット・モードに
入ります。
[PARAMETER]で、CTRL PEDALを選びます。
2.
[VALUE]で、HAR/ARP Controlを選びます。
3.
fig.7-01a
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
ペダル効果モードに入ります。
5.
詳しい操作方法は「ペダル効果モード」とその呼び出しか
た」(P.26)をご覧ください。
※ または、システム・モードの設定項目「S1/S2 FUNCTION」
で「Patch Select」を選び、プレイ・モードに戻ります。
パッチ・エディット・モードでハーモニストをオン/
オフする
ハーモニストの オン/オフ をパッチに記憶させる時などは、
以下のように行います。
1.
[EFFECTS]を押して、パッチ・エ ディット・モ ードに
入ります。
[PARAMETER]で、HAR/ARP CONTROLを選びます。
2.
[VALUE]で、OnまたはOffを選び、ハーモ ニス
3.
トのオン/オフを設定します。
fig.7-01b
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
※ また、ハーモ ニス ト関連の設定項 目で ある「HAR/ARP
CONTROL」「HAR/ARP SELECT」「HARMONY STYLE」
「HARMONY KEY」「HARMONY REMOTE」が選ば れて
いる時は、ペダル 4(CTRL)でハーモニストをオン/オ
フすることができます。
※ ハーモ ニス トのオン/オフ はパ ッチごとの設 定項目 で
す。パッチ・ライト操作を実行すると、その時の状態(オ
ンかオフか)が記憶され、パッチを呼び出 した時に再現
されます。
6.
ペダル 4(CTRL)を踏んで、ハーモニストのオン/オフ
を切り替えます。
各パッチで、ハーモニストとアルペジエーターのどちらか一
方だけが選べるようになっています。オフのパッチも、内部
ではハーモニストかアルペジエーターのどちらかが選ばれて
います。オンの状態の時、プレイ・モードのディスプレイに
HARかARPのどちらか選ばれている方が表示されます。
fig.8-02(HRM)
アルペジエーターが選ばれたパッチでハーモニストを使う時
は、次項の手順に従い、「HAR/ARP SELECT」の設 定で
「Harmony All」などのハーモニストの設定に切り替えてくだ
さい。
※ ハーモニストが選ばれ、オフになって いるパッチで、関
連の項目(「HAR/ARP SELECT」「HARMONY STYLE」
「HARMONY KEY」「HARMONY REMOTE」)の値や設定
を変えると、ハーモニストは自動的にオンになります。
81
8章
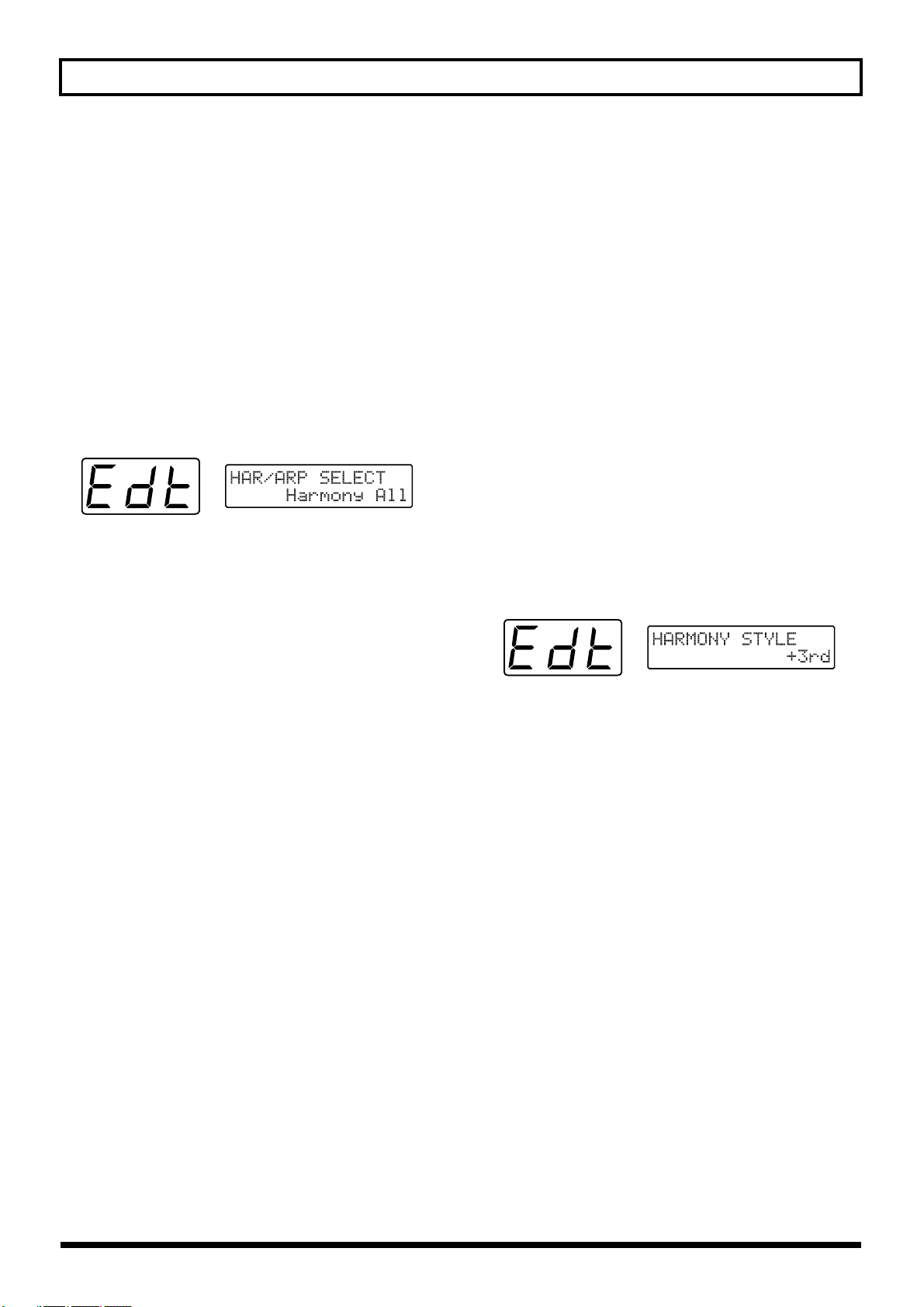
第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト
ハーモニー音を鳴らすトーンを選択す る(HAR/ARP SELECT)
1st トーン、2nd トーン、外部 MIDI 音源の 3 つから、ハー
モニーの副旋律側を担当するものを決めるのが設定項目
「HAR/ARP SELECT」(ハーモニー/アルペジオ・セレクト)
です。
■ ハーモニー・セレクトを設定する手順
ハーモニストの設定を変更するパッチを選び、
1.
[EFFECTS]を押してパッチ・エディット・モードに入
ります。
[PARAMETER]で、HAR/ARP SELECTを選びます。
2.
fig.8-03(HRM SELECT)
[VALUE]で、ハーモニストの設定を選びます。
3.
「HAR/ARP SELECT」でのハーモニストの設定について
は、手順説明後の「◆ HAR/ARP SELECT で選べるハー
モニストの設定について」をご覧ください。
Harmony Ext&2:
2nd トーンと外部 MIDI 音源が副旋律になります。
※ 設定範囲の後半の値(Arpeggio All、Arpeggio 1st、...Arpeggio
Ext&2)も選べますが、これらを選ぶとハーモニストは停止
し、アルペジエーター機能(P.76)が選ばれます。
アルペジエーターが選ばれていると、「HARMONY STYLE」
「HARMONY KEY」「HARMONY REMOTE」の 設定項目も
選択できませんのでご注意ください。
副旋律の音程を設定する
(HARMONY STYLE)
ハーモニストの主旋律と副旋律の間隔(3 度、5 度 ...)は、
「HARMONY STYLE」(ハーモニー・スタイル)で設定します。
■ハーモニー・スタイルを設定する手順
ハーモニー・ス タイル の設定を変更するパッ チを選び、
1.
[EFFECTS]を押してパッチ・エ ディット・モー ドに入
ります。
[PARAMETER]で、HARMONY STYLEを選びます。
2.
fig.8-04(HARMONY STYLE)
4.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
ハーモニストの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を選び、項目内容を設定
してください。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ HAR/ARP SELECT で選べるハーモニストの設定
について
Harmony All:
全ての音(内蔵音源、外部 MIDI 音源)が副旋律になります
(主旋律はギター音)。
Harmony 1st:
内蔵音源の 1st トーンが副旋律になります。
Harmony 2nd:
内蔵音源の 2nd トーンが副旋律になります。
Harmony 1&2:
1st、2nd の両トーンが副旋律になります。
[VALUE]で、ハーモニー・スタイ ルの設定度数を 選び
3.
ます。
設定度数には、-7th、-6th、-5th、-4th、-3rd、-2nd、+2nd、
+3rd、+4th、+5th、+6th、+7th、Diminishがあります。
「Diminish」(ディミニッシュ)は、HARMONY KEY の設
定に関わらず主旋律の短 3 度(3 半音)上に固定された
副旋律となります。ディミニッシュ・スケ ールでフレー
ズを演奏する場合などに有効です。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
ハーモニストの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を選び、項目内容を設定
してください。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
Harmony Ext:
外部 MIDI 音源が副旋律になります。
Harmony Ext&1:
1st トーンと外部 MIDI 音源が副旋律になります。
82
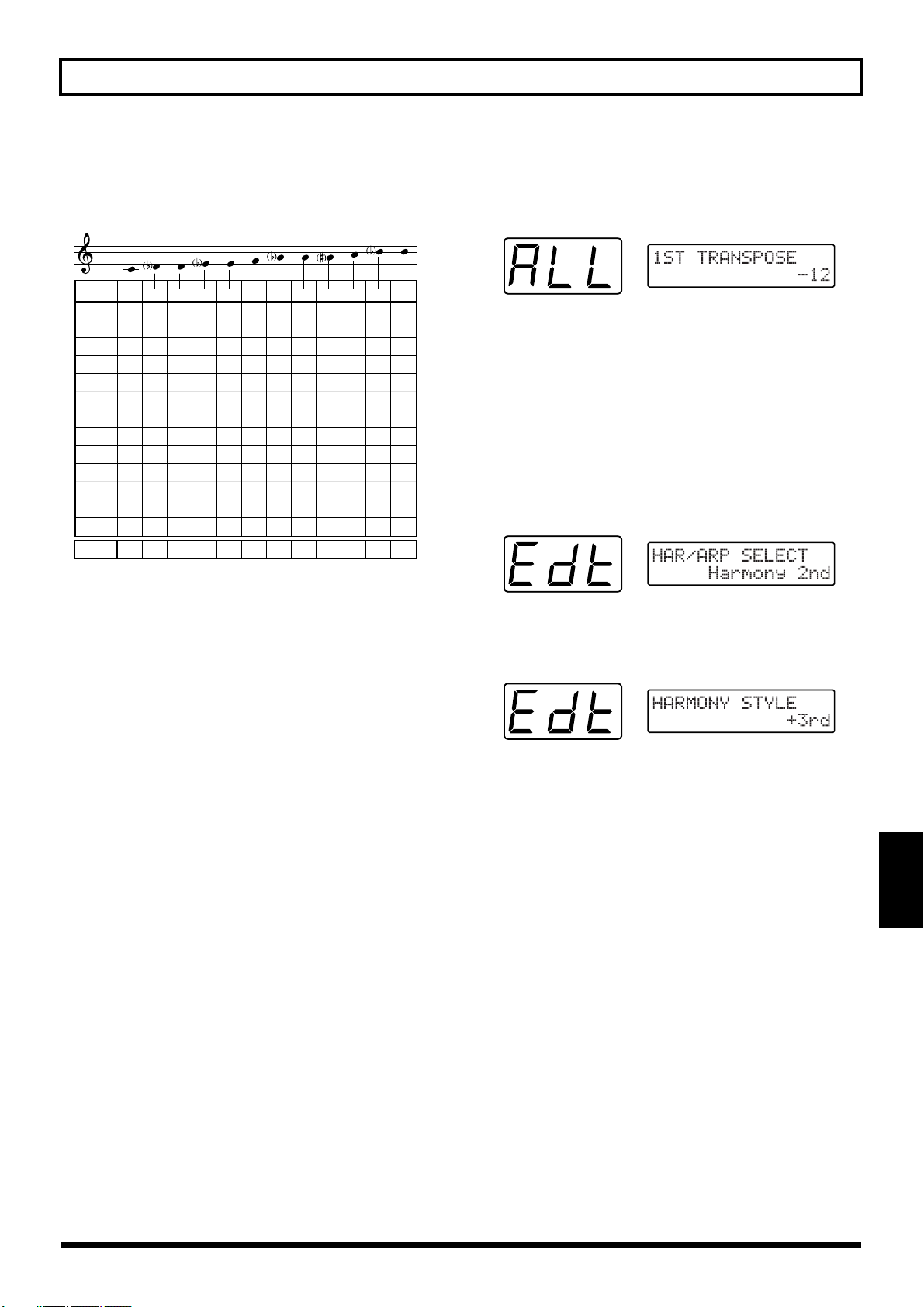
第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト
各設定度 数に おいて、主旋律と副 旋律の 音程は次のよう に
なっています。
fig.8-05(ハーモニー表)
Key=C
HARMONY
tonic b2nd
STYLE
dim
+ 7th
+ 6th
+ 5th
+ 4th
+ 3rd
+ 2nd
- 2nd
- 3rd
- 4th
- 5th
- 6th
- 7th
minor
*
+ 3rd
*HARMONY STYLE が +3 の場合、HARMONY KEY がマイ
ナーに設定されていると、マイナー・スケールを基本にハー
モニーが作られます。
2nd b3rd 3rd 4th b5th 5th #5th 6th b7th 7th
-10 -10-10 -10-10 -10 -10 -10 -11-10 -10 -11
3
33
4
334
333333333333
9911 1110 10 10 10 1010 9 10
889998988988
667766776767
555655555555
334433433333
222222221221
-3 -3-1 -1-2 -2 -2 -2 -2-2 -3 -2
-4 -4-3 -3-3 -4 -3 -4 -4-3 -4 -4
-6 -6-5 -5-6 -6 -5 -5 -6-5 -6 -5
-7 -7-7 -7-7 -7 -7 -7 -7-7 -7 -7
-9 -9-8 -8-9 -9 -8 -9 -9-9 -9 -9
4334
(単位=半音)
3
[TONE]を押し、[PARAMETER]で1ST TRANSPOSE
3.
を選びます。
[VALUE]で、-12(1 オクターブ下)を選びます。
4.
fig.8-06(例:TRANSPOSE)
1st トーンが、ギター音に対してオクターブ・ダウンし
ます。
※ TRANSPOSE の設定は、各弦で異なる設定ができます
(P.35)。この例で、全 弦をオクターブ・ダ ウンさせたい
場合は、[STRING SELECT]で 3 桁表示器にALLを
表示させてから-12を設定してください。
[EFFECTS]を 押 し、[PARAMETER]でHAR/ARP
5.
SELECTを選びます。
[VALUE]で、Harmony 2ndを選びます。
6.
fig.8-07(例:HRM/ARP SELECT)
7.
[PARAMETER]で、HARMONY STYLEを選びます。
トランスポーズの設定と
「HARMONY STYLE」の関係
トランス ポー ズ(音高の平行シ フト)を 設定する項目に は
TONE の「1ST TRANSPOSE」「2ND TRANSPOSE」と、
COMMON の「MIDI [TRANSPOSE]」があり、いずれもハー
モニストの度数を設定する「HARMONY STYLE」とは別に
設定でき、効果も独立してかかります。
従って、ハーモニストを使用する場合は、副旋律として使用
するトーン(または外部音源)のトランスポーズは通常「0」
にしておきます。
ただし、ハーモニーの主(副)旋律を、オクターブ単位でず
らすため にはト ランスポーズを 積極的 に併用すると良い で
しょう。
例:副旋律をオクターブ・ダウンする場合
ここの例では、ギター音の主旋律に対して、1st トーンと 2nd
トーンで副旋律を作ります。1st トーンをオクターブ・ダウ
ンさせ、2nd トーンを 3 度上のハーモニーにします。
GK-2A のギター/シンセ切り替えスイッチを「MIX」に
1.
合わせます。
[VALUE]で、+3rdを選びます。
8.
fig.8-08(例:HARMONY STYLE)
2nd トーンが、ギター音に対して 3 度上のハーモニーに
なります。
以上により、1 オクターブ下の平行音と 3 度上のハーモ
ニーのふたつのシンセ音で、ギター音をサ ンドイッチに
したような分厚い音が得られます。
※ トランスポーズ(TONE の「1ST TRANSPOSE」「2nd
TRANSPOSE」、COMMON の「MIDI [TRANSPOSE]」)
の値(-36 〜 0 〜 24)は、半音単位(1 オクターブ= 12)
で表示されています。これに対して、「HARMONY
STYLE」の値(-7th〜 +7th、Diminish)は度数(3 度、5
度 ...)で表示されていますので、ご注意ください。
8章
設定を行うパッチを選び、1st、2nd 両トーンの音色など
2.
を設定します。
※ トーンの設定については、「シンセ音を加工する」(P.49)
をご覧ください。
83

第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト
キー(調性)を設定する(HARMONY KEY)
ハーモニストのために、C(ハ長調)、Gm(ト短調)など、弾
くメロディーのキーをパッチに設定しておくのが、
「HARMONY KEY」( ハーモニー・キー ) です。
■ ハーモニー・キーを設定する手順
1.
ハーモニー・キーの設定を変更するパッチを選び、
[EFFECTS]を押してパッチ・エディット・モードに入
ります。
2.
[PARAMETER]で、HARMONY KEYを選びます。
fig.8-09(HARMONY KEY 1)
3.
[VALUE]で、設定値を選びます。
HARMONY KEY の設定値については、手順説明後の「◆
HARMONY KEY で選べる設定値について」をご覧くだ
さい。
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
4.
保存します。
ハーモニストの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を選び、項目内容を設定
してください。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
◆ HARMONY KEY で選べる設定値について
ハーモニー・キーで選べる設定値は、以下の通りです。
C、C#、D、D#、E、F、F#、G、G#、A、A#、B、Cm、C#m、
Dm、D#m、Em、Fm、F#m、Gm、G#m、Am、A#m、Bm
◆ キーの表示について
ハーモニ スト が選ばれている パッ チでは、設定されて いる
キーが、エディット・モードの「HARMONY KEY」の設定画
面にしなくても、プレイ・モードで確認できます。
fig.8-10(HARMONY KEY 2)
ただし、HARMONY STYLE が「Diminish」(ディミニッシュ)
に設定されている場合は、キー(HARMONY KEY の設定)の
表示はせず、代わりに「dim」と表示します。
MIDI ノート情報で外部ペダルなどから キーを変える(HARMONY REMOTE)
外部 MIDI 機器(MIDI フット・コントローラーFC-200、MIDI
ペダル鍵盤 PK-5 など/各別売)から GR-33 に、MIDI ノー
ト情報を送ることにより、ハーモニストのキー(HARMONY
KEY)を演奏中に随時切り替えることができます。
この機能のオン/オフをパッチごとに書き込んでおく設定項
目が、「HARMONY REMOTE」(ハーモニー・キー・リモー
ト)です。
■ ハーモニストのキーを外部 MIDI 機器から変更する
手順
1.
MIDI ケーブルで、MIDI 鍵盤やFC-200 などのMIDI アウト
と GR-33 の MIDI インを接続します。
外部機器の送信MIDIチャンネルを、GR-33の MIDIチャン
2.
ネル(P.86)に合わせます。
3.
キーのリモー ト機能を使 いたいパッチを選び、
[EFFECTS]を押してパッチ・エ ディット・モー ドに入
ります。
4.
[PARAMETER]で、HARMONY REMOTEを選びます。
fig.8-11(HARMONY REMOTE)
※ HARMONY STYLE で「Diminish」(ディミニッシュ)が
選ばれていると、HARMONY KEY の設定を変えても得ら
れるハーモニーは同じです。(主旋律の短 3 度上に固定さ
れた副旋律となります。)
84
ディスプレイに現在 の設定が表示 されます。「On」はリ
モート機能オン、「Off」はリモート機能オフです。
5.
[VALUE]で、Onを選びます。
6.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
ハーモニストの他の設定項目に移る場合は、
[PARAMETER]を押して項目を 選び、項目内容を設定
してください。

第 8 章 指定したキーのハーモニーをつける〜ハーモニスト
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
7.
外部機器の取扱説明書に従って、GR-33 に対し MIDI ノー
ト情報を送ります。
FC-200 の場合は、パネル面の「MODE」ボタ ンを押し
てノート・モードに切り替えます。
GR-33 は任意のモードで MIDI ノート・オン情報を受信
し、ノート情報で指定された音名に HARMONY KEY を
切り替えます。
※ 「HARMONY REMOTE」が「On」でも、「HAR/ARP
SELECT」でハーモニストが選ばれていないパッチで
は、ハーモニー・キー・リモート機能の効果は得られま
せん。
※ 「HARMONY REMOTE」が「On」になっていると、GR-
33 の内蔵音源は、外部からの MIDI ノート情報によって
発音しません(発音指示ではなく、キーの変更 指示と解
釈します)。必要な場合以外は、「HARMONY REMOTE」
は「Off」にしておいてください。
※ 「HARMONY REMOTE」は「モノ・モード」(P.88)の場
合のみ有効です。
曲中でメジャー/マイナーを切り替える
ペダル効果モード(P.26)においては、外付け BANK SHIFT
ペダルのアップ側を踏むと、パッチの「HARMONY KEY」(P.
84)で設定されているキーが、メジャーはマイナーへ、マイ
ナーはメジャーへそれぞれ反転します。
(例:C# → C#m → C# → C#m...)
fig.8-12(メジャー/マイナー1)
BANK
SHIFT
(赤)
パッチの「HARMONY STYLE」で「Diminish」(ディミニッ
シュ:「HARMONY KEY」の設定によらず、副旋律を主旋律
の短 3 度上に固定)が選ばれている場合があります。この時
上記の操作を行うと、「HARMONY KEY」のメジャー←→マ
イナーの切り替えではなく、「HARMONY STYLE」の設定が
「Diminish」と「+3rd」で切り替わります。
「+3rd」に切り替わっ た時のキ ーは、「HARMONY KEY」で
設定されているキーになります。結果的に、ディミニッシュ
とメジャー(またはマイナー)を切り替える効果が得られま
す。
白
BANKUP
(例:Diminish → F → Diminish → F...、あるいは Diminish →
Gm → Diminish → Gm... など。)
fig.8-13(メジャー/マイナー2)
BANK
SHIFT
(赤)
※ シーケンサーと GR-33 を組み合わせて使う場合に、演奏
状態の再現性を得るため、メジャー/マイ ナーの切り替
え操作の様子は MIDI アウトから外部に送信されます。
白
BANKUP
8章
85

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
GR-33 に外部音源を接続すると、本体の 384 トーンに含ま
れない音を出したり、本体と外部の音を重ねて分厚い音を作
ることができます。
MIDI について
< MIDI とは>
MIDI とは Musical Instrument Digital Interface(ミュー
ジカル・インストゥルメント・デジタル・インターフェー
ス)の略で、演奏情報や音色の切り替え情報などを電子
楽器と周辺機器の間で、専用ケーブルを介して伝えあう
ための規格のことです。MIDI は、異なったメーカーや種
類の機器にも共通の世界統一規格ですので、これを用い
れば、例えば A 社のギター・シンセを使って、B 社の音
源を鳴らしたり、C 社のシーケンサーにデータを打ち込
んだりすることまで可能になります。
GR-33 も MIDI 端子(IN/OUT)を備えていますので、外
部音源(シンセサイザーやサンプラーなど)をギターで
コントロールしたり、ギターを使って MIDI シーケンサー
への入力をすることができます。
また GR-33 は、MIDI シーケンサー(演奏記録機)の入力ツー
ルとしても便利です。ここでは、このような外部機器と組み
合わせ方(MIDI 機能の応用)について説明します。
GR-33 が扱う MIDI 情報には、
○ 弦がどのピッチ、どの程度の強さで弾かれ たかを伝える
「ノート ON 情報」
○ 弦振動が一定以下に減衰したのを伝える
「ノート OFF 情報」
○ チョーキングやスライド、ハンマリングな どのピッチの
連続変化を伝える
「ベンド情報」
○ パッチの切り替えを伝える
「プログラム・チェンジ情報」
○ 音量や各種効果の変化を伝える
「コントロール・チェンジ情報」
○ パッチの内容について外部とのやりとりなどに用いる、
「システム・エクスクルーシブ情報」
などがあります。
また既に P.37 で説明したとおり、本体上のパッチ情報な
どを外部機器に送り、保存することもできます。
外部 MIDI 音源を鳴らす
外部 MIDI 音源との接続
図に従って GR-33 と外部 MIDI 音源を接続します。
fig.9-01(外部 MIDI 音源)
MIDIOUT
MIDIIN
外部MIDI機器
MIDI チャンネル/ベンド・レンジを設定する
(BASIC CHANNEL、BEND RANGE)
接続ができたら、GR-33 側で必要な設定を行います。
○ MIDI チャンネル(BASIC CHANNEL)
外部機器との間で MIDI 演奏情報のやりとりを行う場合、両
者の「MIDI チャンネル」を合わせる必要があります。
MIDI チャンネルは 1 〜 16 まであり、GR-33 では各弦に 1
つのチャンネル、合計 6 チャンネルを使う方法(モノ・モー
ド)か、弦 6 本分の情報をひとつのチャンネルでやりとりす
る方法(ポリ・モード)が選べます。
モノ・モードの場合は、使用する連続した 6 チャンネルの先
頭のチャンネル(BASIC CHANNEL)を設定します。後述の
手順に従って MIDI チャンネルを設定してください。
※ モノ・モード、ポリ・モードの詳細につ いては、次項の
「モノ・モード送信とポリ・モード送信」をご覧ください。
86
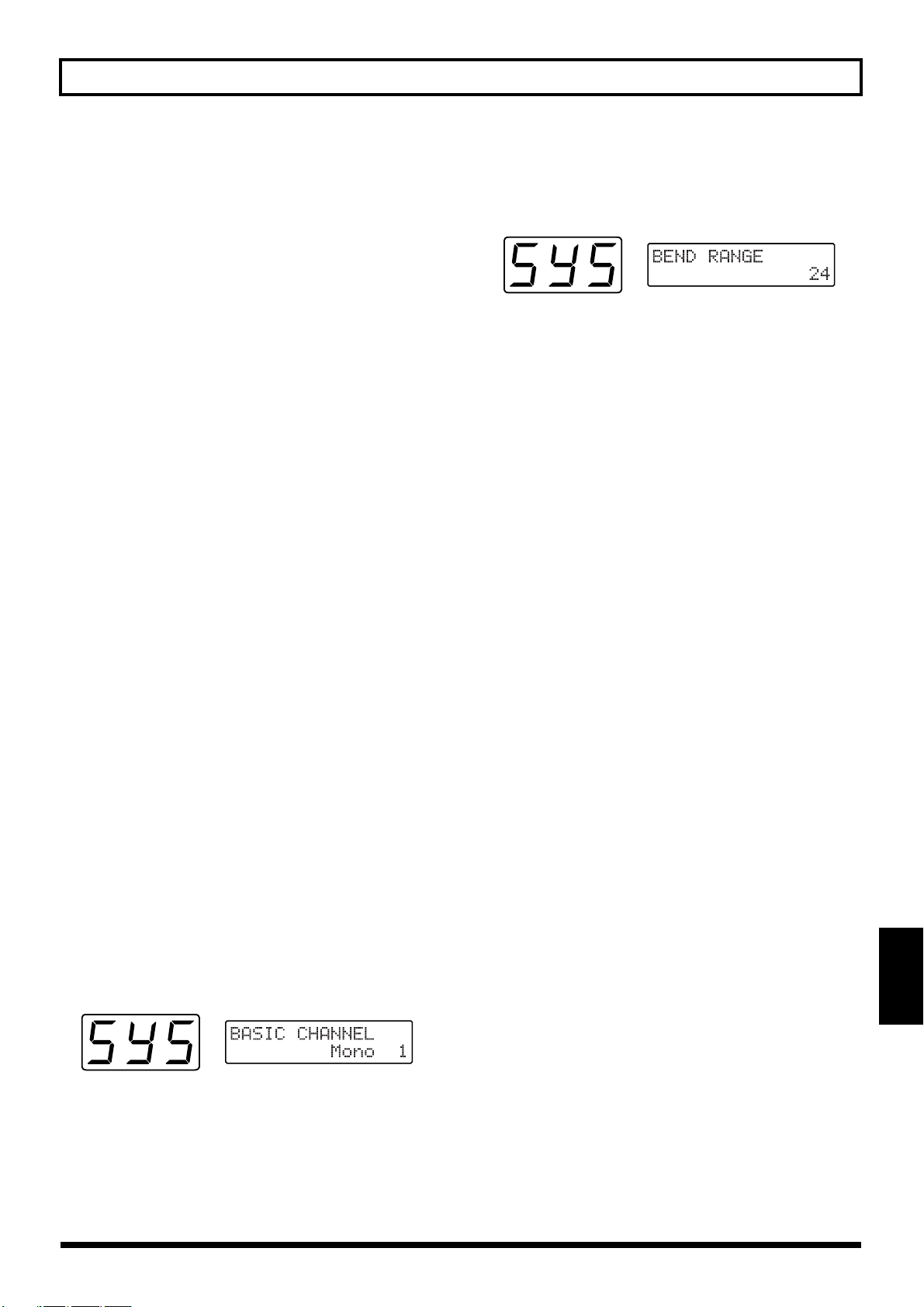
第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
※ マルチ・ティンバー音源(複数の演奏パートを 備えた音
源)や、シーケンサー・システム(自動演奏 装置)と組
み合わせる場合には、他の楽器パートとチャ ンネルが重
ならない様にします。
○ ベンド・レンジ(BEND RANGE)
GR-33 からは、チョーキング 奏法、フィンガー・ビブ ラー
ト、アーミング、スライドなどで得られる連続的なピッチ変
化も外部機器に送信されます。これには、キーボード類のピッ
チ・ベンダーつまみと同様に「MIDI ピッチ・ベンド・チェン
ジ情報」が用いられます。このため、ベンド・レンジと呼ば
れる設定を、送受信双方で合わせる必要があります。
GR-33 は通常、外部 MIDI 機器に対し GR-33 で設定されてい
るベンド・レンジを知らせ、パッチが替わる度に変更を促す
メッセージを送信します。
従って、あらかじめ外部 MIDI 音源側で設定できうる最大の
ベンド・レンジ値に GR-33 側を合わせておくだけで、音源
側のベンド・レンジはパッチ切り替えの度に自動設定されま
す。(ベンド・レンジはなるべく大きな値に設定した方が、よ
り広い範囲のピッチ変化を滑らかに表現できます。設定可能
な範囲は、受信側の音源によって異なります。ベンド・アッ
プ方向とダウン方向で設定可能な幅が異なる機器では、狭い
方の最大値に合わせてください。)
<「外部 MIDI 機器に
ベンド・レンジを知らせ変更を促すメッセージ」について>
ここで使用されるのは MIDI の RPN = レジスタード・パラ
メーター・ナンバーの「ピッチ・ベンド・センシティビティ」
(コントロール・チェンジ 100 番、101 番、6 番、38 番)で
す。(必要な場合は送信を止めることもできます。→ P.98)
この MIDI メッセージを認識できない外部音源を使用する場
合は、音源側のベンド・レンジも GR-33 と同じ値に手動で
変えてください。外部音源側の MIDI 仕様については、音源
機器の取扱説明書でご確認ください。
■ チャンネル(及び送信モード)とベンド・レンジの
設定手順
1.
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
[PARAMETER]で、BASIC CHANNELを選びます。
2.
fig.9-02(MIDI CHANNEL)
を選択することができないようになっています。
BASIC CHANNEL の設定が終わったら、[PARAMETER]
4.
でBEND RANGEを選びます。
fig.9-03(BEND RANGE)
5.
[VALUE]で、設定値を選びます。
BEND RANGE の設定値は、「0、1、2、4、5、7、12、
24」があります。
外部音源側で設定できるベンド・レンジの 最大値に合わ
6.
せたら、[PLAY]を押してプレイ・モードに戻ります。
※ これらはパッチではなくGR-33 本体に関する設定項目な
ので、ライト操作は不要です。電源を切 っても、最後の
設定は自動的に記憶されています。
GR-33 側で送信ベンド・レンジを「0」にすると、パッチ・
エディット・モードの COMMON の設定項目「CHROMATIC」
(P.42)を「Type3」にした時と同じような効果が、外部 MIDI
音源の音で得られます。
マルチ・ティンバー音源を接続し、手順 3. でモノ・モードを
選んだ場合は、音源側の 6 個のパートに使用したい音色を割
り当てます。さらに GR-33 側で選んだ 6 個の連続したチャ
ンネルに、受信側 のチャン ネルを合わせます。この状態で、
GK-2A を搭載したギターを弾けば、外部 MIDI 音源が鳴りま
す。
※ もし外部 MIDI 音源が鳴らない場合は、GK-2A のボリュー
ムつまみを 一杯に 上げ、GK-2A の切 り替え スイッチを
「SYNTH」または「MIX」に合わせてみてください。
それでも鳴らない時は、音源側のボリュー ムなどの音量
に関わる設定や、ケーブル類の接続状態を 再度確認して
ください。また後述(P.88)の設定項目「MIDI[PC]」を
既に変更 して いる場合は、それが「Off」以外の設 定に
なっていることを確認してください。
< GK-2A のボリュームや切り替えスイッチを使うと>
GK-2A のボリュームを操作すると、GR-33 の MIDI アウトか
らは MIDI コントロール・チェンジ情報 7 番によってその変
化が送信されます。(受信側の機器は、コントロール・チェン
ジ 7 番を認識するように設定しておきましょう。)
9章
3.
[VALUE]で、設定値を選びます。
BASIC CHANNEL の設定値は、「Mono 1 〜 11」(モノ・
モード送信)、さらに続けて「Poly 1 〜 16」(ポリ・モー
ド送信)があります。
※ モノ・モード送信では連続した 6 チャンネルを使用する
ため、先頭チャンネル(BASIC CHANNEL)に 12 〜 16
これにより、GK-2A のボリュームつまみの操作で外部機器の
音量をコントロ ールできま す。また、GK-2A の切り替えス
イッチを GUITAR にした場合、外部音源に対し てはコント
ロール・チェンジ 7 番の値「0」を送信して、外部音源から
の音も止めます。MIX または SYNTH に切り替えると、GK2A のボリュームやエクスプレッション・ペダルの状態にそっ
た値が送られ、発音が再開されます。
必要な場合は、コントロール・チェンジ 7 番の送信を止めら
れます(P.97)。
87
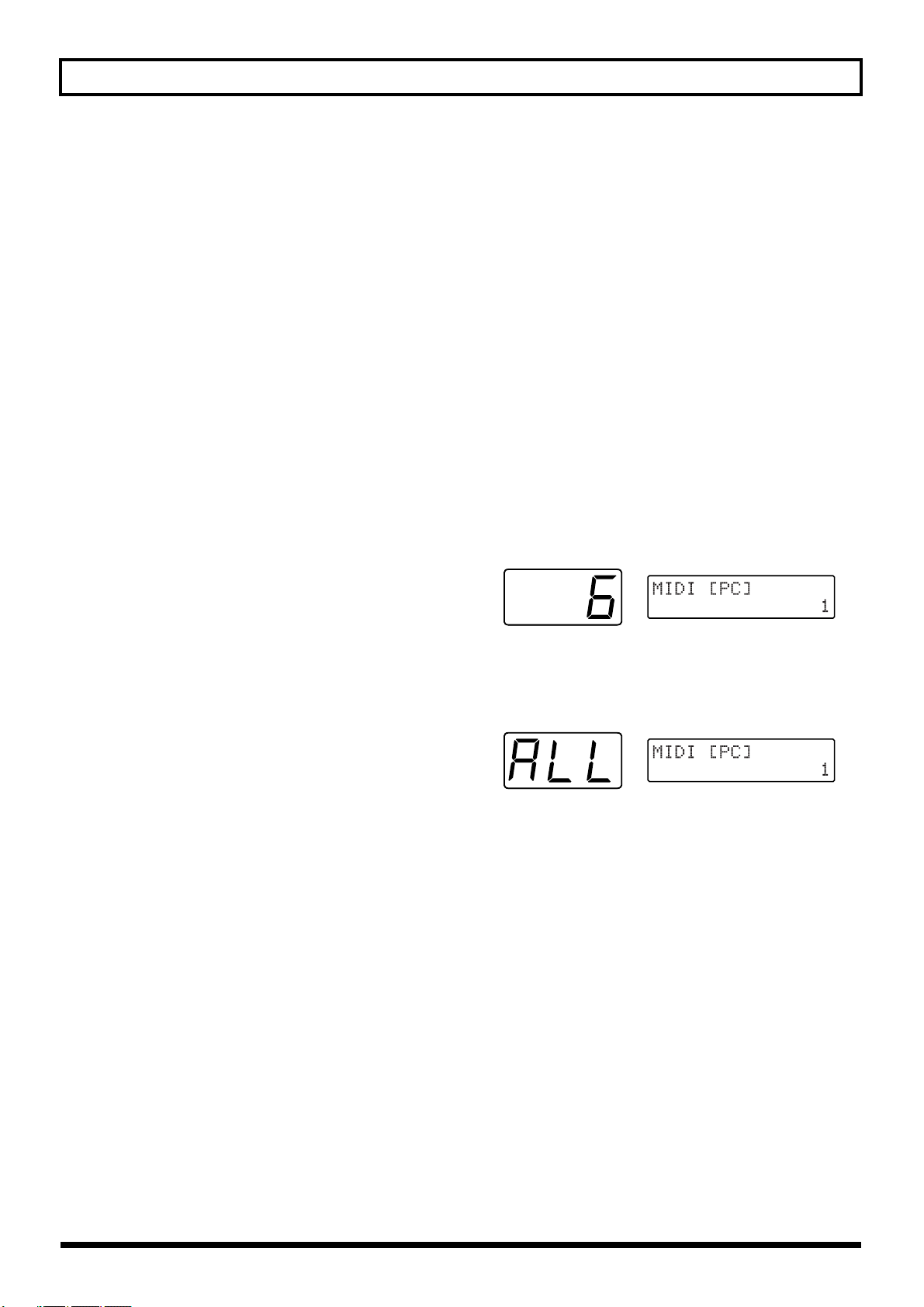
第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
モノ・モード送信とポリ・モード送信
MIDI CHANNEL の設定で、チャンネルと同時に 選んだ「モ
ノ・モード送信」「ポリ・モード送信」には、次のような違い
があります。
○ モノ・モード送信
使用チャンネル数:
各弦ごとに 1 個のチャンネルを使います。システム・モード
でチャンネル指定時に選んだ番号を先頭にして、連続した 6
個のチャンネルが自動的に選ばれます。
(例 ...「Mono 3」を選択した場合→ 3〜 8 の 6 個のチャンネ
ルを、順に 1 〜 6 弦に使用します。このためモノ・モード送
信時には、先頭チャンネルに 12 〜 16 チャンネルを選べませ
ん。)
特徴:
連続したピッチ変化(MIDI ベンド情報)の情報を、各弦ごと
に独立して送ることができます。アーミングやハーモナイズ
ド・チョーキングなどの、ギター独特の奏法が再現できます。
適する使用状況:
主に、6 パート以上を備えたマルチ・ティンバー音源を使う
時。
GR-33 から MIDI 情報を送って音色 などを選ぶ(MIDI[PC])
ペダルや[VALUE]で GR-33 のパッチを切り替えると、MIDI
アウトから外部機器へプログラム・チェンジ(音色切り替え)
情報が送信されます。これにより、外部音源の音色や、ギター
音用エフェクターのパッチを切り替えることができます。
送信されるプログラム・チェンジ情報の番号は、自由に変更
して、GR-33 の各パッチに記憶させておくことができます。
(お買い上げ時には A11 から D84 まで順に、プログラムチェ
ンジ 1 番、2、3、...127、128 が送信されるよう設定されて
います。)
■ パッチ選択時、外部に送信するプログラム・チェン
ジ番号を変更する手順
1.
設定を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押し て
パッチ・エディット・モードに入ります。
2.
[PARAMETER]を押してMIDI [PC]を選びます。
fig.9-04(MIDI[PC] 1)
○ ポリ・モード送信
使用チャンネル数:
全弦共通の 1 個だけのチャンネルを使います。システム・モー
ドでの送信チャンネル設定がそのまま使われます。
特徴:
ギター・パート全体で 1 チャンネルしか使わないため、MIDI
チャンネル数の節約ができます。6 チャンネルを同時に受信
できない音源でもコントロールできます。
ただし、2 本以上の弦が鳴っている時には、ベンド情報は送
信されず、半音刻みのピッチ変化となります。そのため、ギ
ターで実際に鳴っているピッチを、シンセ音に完全に反映さ
せることはできません。
適する使用状況:
パート数が 5 以下の外部音源を使う時、または使用する MIDI
チャンネル数(音源パート数)を節約したい時。
※ ポリ・モードの場合、MIDI に関する弦別設定は無効にな
ります。代わりに 1 弦の設定が使用されます。
3.
[STRING SELECT]を押してALLを選びます。
各弦で設定を変えたい場合は、次項の「弦 別に異なる音
色を選ぶ」をご覧ください。
fig.9-05(MIDI[PC] 2)
[VALUE]で、値を選びます。
4.
プログラム・チェンジ番号の設定値は、Off、1〜 128 が
選べます。
5.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
内蔵音源だけを鳴らしたいパッチは、上記手順の 4. で「Off」
を選びます。「Off」を選んだパッチでは、GR-33 からの演奏
情報の送信を、プログラム・チェンジ以外も含め止めること
ができます。
逆に「特定のパッチでは外部音源だけを鳴らしたい」という
場合は、該当する GR-33 のパッチの「LAYER」の設定(P.
51)を、全弦「Mute」(消音)にしておけば良いでしょう。
88
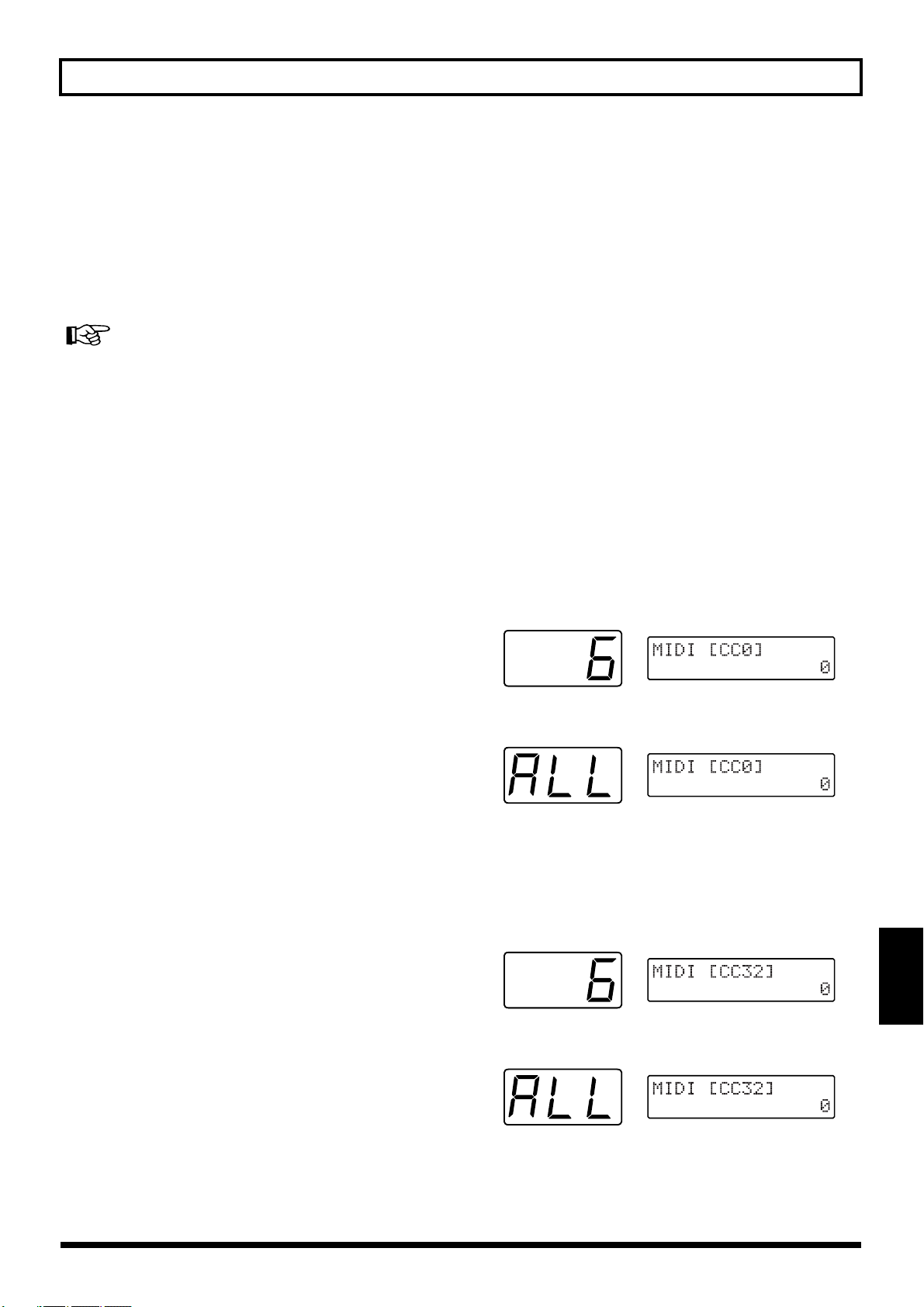
第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
※ GR-33 が「受信」したプログラム・チェンジ番号と、そ
れによって呼び出される GR-33 のパッチの対応 は固定
で、お買い上げ時の状態(A11 から D84 まで順に、プロ
グラムチェンジ 1 番、2、3、...127、128 番)のまま変更
できませんのでご注意ください。
送信番号と受信番号を再度一致させたい時は、システム・モー
ドの FACTORY RESET で、「PC Number」を選んで実行し
てください。
詳しい操作方法については、「プログラム・チェンジ番号を
パッチの順に振り直す」(P.97)をご覧ください。
※ 設定変更は、MIDI ループ接続していない状態で行ってく
ださい。
弦別に異なる音色を選ぶ
外部音源に送信するプログラム・チェンジは、パッチごとに
決められるだけでなく、さらに各弦を異なる設定にすること
もできます。
前項の「パッチ選択時、外部に送信するプログラム・チェン
ジ番号を変更する手順」の 3. で、[STRING SELECT]ボタ
ンを「ALL」以外の各弦番号のポジション(6-5, 6, 5,...1)に
合わせてから[VALUE]で変更するようにすると、選んだ弦
のプログラム・チェンジ番号だけが変更できます。
これにより外部音源では、6 本の弦全てに異なる音色を割り
当てるといった、奇抜な使い方も簡単にできます。また、設
定値「Off(オフ)」を弦別に用いれば、外部音源でも特定の
弦だけを消音することができます。
128 個を越える音色を選ぶ
(MIDI[CC0]、MIDI[CC32])
音色数がプログラム・チェンジ番号の幅(1 〜 128)を上ま
わっている外部音源に対して、GR-33 から外部音源の音色を
呼び出す際には、プログラム・チェンジに MIDI バンク・セ
レクト情報(コントロール・チェンジ 0 番、32 番)を併用
します。
※ ここでいう「バンク」は MIDI 規格にあるプログラム・
チェンジの拡張情報のことで、GR-33 でいうパッチ番号
の 2 桁目の(BANK =「バンク・シフト」、「バンク・アッ
プ・ダウン」のバ ンク)とは 全く異なる意味で すので、
ご注意ください。
GR-33 では、このバンク・セレクト情報の送信機能がサポー
トされています。
■ MIDI バンク・セレクトの送信をさせる手順
設定を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押し て
1.
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]を押してMIDI [CC0](コントロール・
2.
チェンジ 0 番)を選びます。
fig.9-06(MIDI[CC0]1)
[STRING SELECT]を押してALLを選びます。
3.
fig.9-07(MIDI[CC0]2)
※ [STRING SELECT]ボタンを用いた外部 MIDI 音源向け
の弦別設定は、プログラム・チェンジのみでな く次項の
MIDI バンクセレクト送信についても可能です。
4.
[VALUE]で、呼び出したい音色に合った値にします
(OFF, 0 〜 127)。
MIDI [CC0] の設定が終わったら、[PARAMETER]で
5.
MIDI [CC32](コントロール・チェンジ 32 番)を選び
ます。
fig.9-08(MIDI[CC32]1)
6.
[STRING SELECT]ボタンで、ALLを選びます。
fig.9-09(MIDI[CC32]2)
[VALUE]で、呼び出したい音色に合った値にします(Off,
7.
0 〜 127)。
9章
89

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
8.
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モー ドに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押して プレイ・モード
に戻ります。
以上のように設定したパッチを呼び出すと、そのパッチに設
定されているバンク・セレクト情報とプログラム・チェンジ
番号により、外部 MIDI 音源の音色が同時に呼び出されます。
各弦を異なる設定にする時は、前記手順の 3.、6. で、[STRING
SELECT]ボタンを「ALL」以外の各弦番号のポジション(6-
5, 6, 5,...1)に合わ せて から、MIDI[CC0]、MIDI[CC32] を
[VALUE]で変更します。
パッチ・エディット・モードにおいて、[VALUE]でプログ
ラム・チェンジ番号やコントロール・チェンジ 0 番/ 32 番
を切り替えると、外部 MIDI 音源に対し、随時選んだ番号に
対応する MIDI 情報が送信され、設定の結果が外部 MIDI 音源
に表れるようになっています。
なお、[VALUE]を早く回すなどして設定値を早送 りした場
合、外部機器によっては MIDI 情報があふれ、その旨の警告
表示(「MIDI Buffer Full」など)を発する場合があります。
fig.9-10(FC50 →外部機器)
MIDIIN
外部MIDI機器
MIDIOUT
MIDIフット・コントローラー
なお、プログラム・チェンジ番号を先頭から順に振り直す操
作(P.97)を行うと、ユーザー・パッチのバンク・セレクト
はコントロール・チェンジ 0 番、32 番とも「0」に戻ります。
MIDI
IN
MIDI
OUT
< MIDI バンク・セレクトの受信>
バンク・セレクトは送/受信両方にある設定です。GR-33 が
受信側になった場合には、外部からのバンク・セレクト+プ
ログラム・チェンジで、本体上の 256 パッチ全てが自由に呼
び出せるようになります。
プリセット・パッチ(E11 〜 H84)はコントロール・チェン
ジ 0 番の値「1」+プログラム・チェンジ(1 〜 128)で呼
び出せます。また、ユーザー・パッチ(A11 〜 D84)はコン
トロール・チェンジ 0 番の値「0」+プログラム・チェンジ
(1 〜 128)で呼び出せます。
パッチと受信側のバンク・セレクトの対応関係は固定されて
おり、送信するバンク・セレクトやプログラム・チェンジを
書き替えた場合も、変更されません。
FC-200、BOSS FC-50 などの MIDI フット・コントローラー
をつないでいる場合(P.24)、フット・コントローラー側の
操作で GR-33 のパッチを切り替えることがあります。この
時、GR-33 の MIDI アウトから、呼び出されたパッチに設定
されているプログラム・チェンジなどが送信され、下流の機
器も一括コントロールできます。
※ 設定変更は、MIDI ループ接続していない状態で行ってく
ださい。
アルペジエーター、ハーモニストを外 部音源に使う
○ アルペジエーターを使い、外部 MIDI 音源にアルペ
ジオさせる場合
外部 MIDI 音源の音を、内部の 1st トーン/ 2nd トーンと同
様に、GR-33 のアルペジエーターでアルペジオさせることが
できます。
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」(P.78)を「Arpeggio All」「Arpeggio Ext」
「Arpeggio Ext&1」「Arpeggio Ext&2」のいずれかに設定す
ると、外部 MIDI 音源の音がアルペジオします。
○ ハーモニストを使い、外部 MIDI 音源も使ってハー
モニーを構成する場合
内部の 1st トーン/ 2nd トーンと同様に、外部 MIDI 音源の
音でもハーモニーをつくることができます。
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」(P.82)を「Harmony All」「Harmony Ext」
「Harmony Ext&1」「Harmony Ext&2」のいずれかに設定す
ると、外部 MIDI 音源の音でも副旋律を作ることができます。
90

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
エンベロープ・フォロー機能と MIDI データの関係
エンベロープ・フォロ ー機能(P.40)を使って いるパッチ、
すなわちパッチ・エディット・モードの COMMON の設定項
目「PLAY FEEL」で「Envelope1」「Envelope2」が選ば れ
ているパッチでは、発音中に弦の振幅情報(減衰していく様
子)が、MIDI コントロール・チェンジ 18 番(汎用操作子 3)
で MIDI アウトから送出されます。
これは主には、MIDI シーケンサーとのループ接続で GR-33
自体の演奏を記録/再生する時(P.94)、ギター弦のエンベ
ロープ(減衰情報)もいっしょにシーケンサーに記録し、演
奏した時の発音のままに再生するためです。
外部 MIDI 音源に、受信した任意のコントロール・チェンジ
情報を、音色変化などの効果に割り当てることができるタイ
プのものを使う場合は、上記で送出される 18 番を使い、音
の変化を作ることもできます。
外部 MIDI 機器を本体ペダルでコント ロールする
GR-33 本体のペダル効果、及びエクスプレッション・ペダル
の効果の一部は、外部音源にも有効です。
○ ペダル効果 1「WAH」
踏む/離すの情報を、コントロール・チェンジ 19 番で送信
します。なお「WAH TYPE」の設定(P.43)に「Modulation」
(モジュレーション)が選ばれている時はコントロール・チェ
ンジ 19 番でなく 1 番を使います。
○ ペダル効果 4「CTRL」
アルペジエーターまたはハーモニストのオン/オフが、内部
音源と同じようにできます。
<エクスプレッション・ペダルの効果について>
エクスプレッション・ペダルで何らかの効果をかけている時
には、MIDI アウトからペダルの動きを随時出力します。基本
的にコントロール・チェンジ 4 番(フットタイプ)で出力し
ますが、「EXP PEDAL」の設定(P.47)で以下が選ばれてい
る時は、他の番号を使います。
「Volume」(音量):
コントロール・チェンジ 7 番
「Pitch」(音高):
MIDI ピッチ・ベンド情報
「Modulation」(モジュレーション):
コントロール・チェンジ 1 番
「Pan (Normal)」(パン):
コントロール・チェンジ 10 番
「Cho Send Level」(コーラス・センド・レベル):
コントロール・チェンジ 93 番
「Rev Send Level」(リバーブ・センド・レベル):
コントロール・チェンジ 91 番
「Tempo&Pitch」(テンポ & 音高):
MIDIピッチ・ベンド情報とコントロール・チェンジ 4 番の併用
このほか、「EXP PEDAL」の設定(P.47)で「CC1 〜 31」
「CC64 〜 95」が選ばれていると、当該番号のコントロール・
チェンジ情報 がエクスプ レッション・ペダルの操作に従い、
MIDI アウトだけに送信されます。これにより、外部 MIDI 音
源のみにペダルによる制御を与えることができます。
○ ペダル効果 2「P-GLIDE」
MIDI ピッチ・ベンド情報で、内部音源の場合と同じような効
果を作ります。
○ ペダル効果 3「HOLD」
ホールド中は、MIDI ノート・オフの発行を保留して実現させ
ます。(キーボード類で使うコントロール・チェンジ 64 番は
送信しません。ただし内部音源の制御のため、ペダルの動き
はコントロール・チェンジ 82 番(汎用操作子 7)で送出し
ます。)
※ ポリ・モード送信(P.88)では、異弦・同音高時に弦別
の処理ができないため、ホールド効果を完全 に伝えるこ
とはできません。
※ GR-33 がコントロール・チェンジ 4 番を受信すると、GR-
33 の内蔵 音源のシンセ音は、その時エク スプレッショ
ン・ペダルに割り当てられている機能に相 当する変化を
します。ただし上記の、7 番、1 番、91 番など固有のコ
ントロール・チェンジを使う機能が割り当 てられている
時は、4 番は無視されます。
9章
91

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
外部音源への演奏情報を平行移調する(MIDI [TRANSPOSE])
外部音源をお使いの場合、ギターにない低音域(高音域)は、
パッチ・エディット・モードの COMMON の設定項目「MIDI
[TRANSPOSE]」を変え、MIDI OUT からの出力を平行移調
して送信できます。
■ MIDI[TRANSPOSE]を設定する手順
1.
設定を変えたいパッチを選び、[COMMON]を押し て
パッチ・エディット・モードに入ります。
[PARAMETER]を押してMIDI[TRANSPOSE]を選
2.
びます。
fig.9-11(MIDI[TRANSPOSE] 1)
3.
[STRING SELECT]を押してALLを選びます。
各弦で設定 を変え たい場合は、「弦別に異な る音色 を選
ぶ」(P.89)をご覧ください。
fig.9-12(MIDI[TRANSPOSE] 2)
[VALUE]で、値を選びます。
4.
MIDI[TRANSPOSE]で選べる設定値は、-36 〜 0 〜 24
(半音単位)です。
うまく外部音源が鳴らないときは
うまく外部音源が鳴らないときには次の各項目を再確認して
ください。
送受信双方の MIDI チャンネルは合っているか(P.86)。
•
•
エクスプレッション・ペダルのボリューム操作で MIDI ボ
リューム情報(コントロール・チェンジ 7 番)が送ら
れ、外部音源側のレベルが下がっていないか。
•
GK-2A のボリュームやエクスプレッション・ペダルで音
量が絞られていないか。
•
GK-2A の切り替えスイッチが「GUITAR」に設定されて
いないか。
•
6 つの MIDI チャンネルを同時に受信できない音源に対し
て、GR-33 側からモノ・モードで送信していないか
(P.88)。
5.
[WRITE]を押してパ ッチ・ライト操 作(P.36)を行い
保存します。
※ パッチ・ライト操作後、自動的にプレイ・モ ードに戻り
ます。
※ 保存をしない場合は、[PLAY]を押し てプレイ・モード
に戻ります。
※ ピッチがギターとずれて聴こえる場合は、「BEND
RANGE」を確認してください(P.86)。
※ 「BEND RANGE」が「0」に設定されていると、半音刻み
のピッチ変化となります。
※ ポリ・モード送信時は、和音演奏時に限っ てピッチ変化
が半音刻みとなります(P.88)。
92

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
外部シーケンサーの入力ツールとして使う
GR-33 を MIDI シーケンサー(演奏記録/再現装置)につなげば、キーボードが弾けないギタリストにも、シーケンサーへのリ
アルタイム・レコーディングが可能となります。
シーケンサーと接続する
GR-33、シーケンサー(またはコンピューター+シーケンス・
ソフト)、マルチ・ティンバー音源を図の例に従って MIDI ケー
ブルで接続します。
fig.9-13(シーケンサー接続図)
MIDIIN
マルチティンバーMIDI音源
MIDIOUT
MIDI
IN
シーケンサー
MIDI
OUT
入力の手順と各機器の設定
1.
GR-33 側の送信チャンネル、送信モード、ベンド・レン
ジを、使用する音源に合わせます。
詳しい設定内容については、「MIDI チャンネル/ベンド・レ
ンジを設定する」(P.86)をご覧ください。
シーケンサー側で MIDI イン→アウトのデータ・スルー機
2.
能(いわゆる「ソフト・スルー」など)をオンにします。
(レコーディング時に GR-33 から出力された MIDI 情報
が、シーケンサーの MIDI OUT からもスルー出力される
ように設定してください。)
GR-33 の電源を、[PLAY]を押したまま入れ直し、「ロー
3.
カル・コントロール・オフ」の状態に切 り替えます。こ
の時は、ディスプレイにLOCAL CONTROL OFFと表
示されてから起動します。
ローカル・コントロール・オフの詳細については、次項の
「「ローカル・コントロール・オフ」について」をご覧くださ
い。
準備が完了したら、まずギターを弾い て、外部音源が鳴
4.
るのを確認してください。問題がない ようでしたら、外
部シー ケン サーを操作して レコ ーディングを 行ない ま
す。レコーディングができたら、シーケン サーをプレイ
状態にして記録状態を確認します。
5.
GR-33 の音源も曲中で使用する場合は、外部音源の MIDI
THRU から GR-33 の MIDI IN へも接続します。これによ
り、外部音源パートの演奏を聴きながら、GR-33 の音源
をも使っ たレコー ディングができます。(この 時、送信
MIDI チャンネルは、外部音源のチャンネル設定とぶつか
らないように選んでください。)
以上のレコーディングにより、演奏による発音の他、音色の
切り替えや、本体や外部のペダル操作による効果も記録され
ます。(ハーモニスト使用時、ペダル効果モードで外付け
BANK SHIFT ペダルのアップ側を踏むと、キーのメージャー
/マイナーが切り替わり ますが、この情報も コントロール・
チェンジ情報の形で送られ、記録されます。)
※ ギターで出 せない低 音域をレコーディングし たい時は、
「MIDI[TRANSPOSE]」の設定を「-12」(1 オクターブ下)
や「-24」(2 オクターブ下)にしてください。
※ 使用するシーケンサーが、複数チャンネル の同時レコー
ディングに対応してない場合は、ポリ・モ ードで送信/
レコーディングしてください(P.88)。
93
9章

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
「ローカル・コントロール・オフ」に
ついて
GR-33 の内部で、音源部とギタ ー・コントロール部が つな
がっている状態をローカル・オンといいます。これに対して、
ローカル・オフに設定すると、GR-33 の内部で音源がギター・
コントロールから分離され、シーケンサーからの MIDI 情報
のみで発音します。またギターの演奏情報は、MIDI OUT の
みに出力されます。
fig.9-14(ローカル・コントロール・オフ)
シーケンサー
MIDIOUTへの
スルー機能:オン
MIDIOUT
PITCH
TOMIDI
MIDIIN
GKIN
D
O
W
SY
N
N
/S1
TH
V
O
U
L
P/S
2
ITAR
GU
IX
M
SYNTH
MIDIOUT
GR-33
MIDIIN
内蔵音源
ローカル
コントロール
OFF
ローカル・コントロール・オフにすることで、ソフト・スルー
した場合などに起こる、ギターとシーケンサー双方からの演
奏情報の衝突を避けることができます。
ローカル・コントロール・オフにするには、[PLAY]ボタン
を押したまま 電源を入 れ直します。(ローカル・コント ロー
ル・オフの設定は再び電源を入れ直すと解除され、記憶され
ません。)
※ ローカル・コン トロール のオン/オフを切り替 えると、
内部機能の挙動が詳細にわたり変化しま す。通常はロー
カル・コントロール・オンで使用し、外部機器 を介して
ループ接続となる場合は、必ずローカル・コントロール・
オフでお使いください。
オンのまま MIDI ループ接続をすると、スイッチ類を受け付
けないなどの障害が発生し、正常に動作しませんのでご注意
ください。
※ MIDI[PC]、MIDI[CC0]、MIDI[CC32]の設定(P.88、
89)は、MIDI ループ接続していない状態で行ってくださ
い。
撥弦楽器のリアルなデータをつくる
ギター系の弦楽器や、ハープや琴など、撥弦楽器のパートの
入力に GR-33 を使えば、鍵盤での入力では再現しにくかっ
たボイシングや、コード弾き時の弦別の分散感を表現できま
す。この場合は、次の点に注意します。
○ シーケンサー側で、入力データのタイミン グのクォンタ
イズ機能(中途半端な入力タイミング のデータを、正確
な 8 分/ 16 分などの位置に強制修正する機能)が働い
ていないこと。
○ レコーディング後シーケンサー側で、デー タ位置をずら
すような修正を行う際、ノート情報だ けでなく、ベンド
情報もいっしょにずらし、両情報の対応関 係が崩れない
ようにすること。
またギター・シンセなら、ギター独特のピッチ変化(例えば
アーミングやハーモナイズド・チョーキング)も、各弦に 1
つの MIDI チャンネルを使うモノ・モード送信で、シーケン
サーに入力し、再生することが可能です。
アルペジエーター、ハーモニストの演 奏を記録する
■ アルペジエ ーターの効果 をシーケンサ ーに記録さ
せるには
例1.
外部 MIDI 音源の音をアルペジオさせ、それを記録させる
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」を「Arpeggio Ext」にし、P. 93「入 力の 手
順と各機器の設定」の手順 1.2.4. を実行します(手順 3 は必
要ありません)。次に、手順 4. の状態で、ギターを弾くと外
部 MIDI 音源がアルペジオするのを確認します。あとは手順
5. に進んでレコーディングをします。
例2.
本体の 1st、2nd トーンをアルペジオさせ、それを記録させる
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」を「Arpeggio 1st」「Arpeggio 2nd」「Arpeggio
1&2」のいずれかにして、レコーディングをします。(レコー
ディング中アルペジオは鳴りますが、シーケンサーにはアル
ペジオ情報自体は記録されず、元のギター・プレイの演奏情
報が記録されます。)再生時にも同じパッチを使えば、MIDI
インからの演奏情報を受け、GR-33 がアルペジオを再構成し
ます。
※ シーケンサーと GR-33 を MIDI ループ接続(ローカル・
コントロール・オフ)する時の「HAR/ARP SELECT」に
は、「Arpeggio All」は適しません。
94

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
※ 前述の例 1. と同じ様に、「Arpeggio Ext」でアルペジオ自
体をそのままレコーディングし、そのままシ ーケンサー
からの MIDI アウトを(1st、2nd トーンのアルペジオが
オフになっているパッチに)戻して、アルペジ オを再現
させても 構いま せん。ただし、「両トーン 鳴らし、か つ
1st のみアルペジオさせる」といった演奏が、この方法で
は再現できませんのでご了承ください。
※ ポリ・モード送信(P.88)を用いる時は例 1. の方法での
みレコーディング/再生が可能です。
■ ハーモニス トの効果をシ ーケンサーに 記録させる
には
例1.
1st トーンを主旋律、2nd トーンを副旋律(またはその逆)
とし、それを記録させる
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」を「Harmony 2nd」(または「Harmony 1st」)
にし、P.93「入力の手順と各機器の設定」の、手順 4. の状態
で、ギターを弾き、所定のハーモニーが作られるのを確認し
ます。あとは手順 5. に進んでレコーディングをします。その
ままのパッチで再生すると、レコーディング時のハーモニー
が再現されます。
※ ポリ・モードでの再生は、ハーモニー機能が働きません。
モノ・モードでお使いください。
例2.
外部 MIDI 音源の音を主旋律、1st、2nd トーンを副旋律とし、
それを記録させる
パッチ・エディット・モードの EFFECTS の設定項目「HAR/
ARP SELECT」を「Harmony 1&2」にし、例 1. と同様にレ
コーディングし、そのままのパッチで再生します。このとき、
外部音源と GR-33 の MIDI チャンネルは同じに設定してくだ
さい。
ピッチ・ベンド・データの送信量を減らす
<ベンド・データ・シン機能>
ギターではフィンガー・ビブラート奏法により、キーボー
ド類では表現の難しい、振幅や速さを自在に変化させた
人間的なビブラートがかけられます。
GR-33 でシーケンサー・データを作成する際には、この
フィンガー・ビブラートを始め、グリッサンドやアーミ
ングの様子が、MIDI ピッチ・ベンド情 報の形でレコー
ディングされます。結果的に、出力される MIDI 演奏情報
には大量のピッチ・ベンド情報が含まれます。しかし場
合によっては、これらのベンド情報によりデータ量が増
え過ぎ、シーケンサーの許容メモリーを超えてしまうこ
とがあります。
これを最小限にとどめるための機能が、ベンド・データ・
シン(BEND DATA THIN)機能です。
ベンド・データ・シン機能を用いれば、ピッチ・ベンド情報
の送信量が抑えられますので、通常よりピッチ変化の滑らか
さは劣りますが、MIDI データの量を抑えることができます。
■ ベンド・データ・シン機能を呼び出す手順
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
[PARAMETER]で、BEND DATA THINを選びます。
2.
fig.9-15(BEND DATA THIN)
[VALUE]で、Onを選びます。
3.
[PLAY]を押してプレイ・モードに戻ります。
4.
※ これはパッチではなく GR-33 本体に関する設定項目(シ
ステム・モード)なので、ライト操作は 不要です。電源
を切っても、最後の設定は自動的に記憶されています。
再び BEND DATA THIN を「Off」にするまでは、ピッチ・ベ
ンド・データの送信が減量されます。(機能の使用中は、内蔵
音源もピッチ変化の滑らかさに制限を受けます。)
95
9章

第 9 章 外部音源やシーケンサーと接続する
使用するチャンネル数を節約する
fig.9-16(チャンネル節約)
モノ・モード送信
ギター1
モノ・モードch1 モノ・モードch7
MIDIch
1
2345678910111213141516
使用中
ポリ・モード送信
ポリ・モードch1
MIDIch
1
2345678910111213141516
使用中
ギター1
ポリ・モードch2
残り14chを使用可能
ギター2
残り4chのみ
使用可能
ギター2
ひとつの MIDI 系の上には MIDI チャンネルが 16 個あり、通
常は 16 の楽器パートが存在できます。
しかし、ギター・シンセでは 6 本の弦それぞれで 1 チャンネ
ルを消費しますので、例えば 16 パートの外部マルチ・ティ
ンバー音 源の アンサンブルにギ ター・シン セでの入力を 2
パート分行うと、それだけで 12 チャンネル消費してしまう、
といったことが起こります。
このよ うな 場合は、システム・モ ード の設定項目「BASIC
CHANNEL」(P. 86)を「Poly1」〜「Poly16」にし、ポリ・
モード送信でシーケンサーに入力していくと、鍵盤楽器同様、
1 パートに 1 つだけのチャンネル消費でレコーディングを進
めることができます。
ポリ・モード送信では和音発音時に、チョーキングやスライ
ド、ビブラートなどピッチ・ベンド情報を送れないという難
点がありますが、使用する音色や単音演奏の併用を考えなが
ら、モノ・モード入力と使い分ければチャンネルやパートの
節約に貢献します。
うまく記録できないときは
○ MIDI ケーブルの接続(アウト→イン、P.93)やローカ
ル・コントロールのオン/オフの設定(P.94)を再確認
してください。
○ 再生するときには MIDI チャンネルやベンド・レンジの設
定を必ず確認してください(P.86)。
○ 送信のモード(モノ、ポリ)は必ず整合させてください。
再生時、1 弦分の音しか鳴らない時は、非マルチ・ティ
ンバーの音源に対して、モノ・モード送信で作 成した演
奏データを送っている可能性があります。
○ 特定の弦だけMIDIが送出されずレコーディングができな
い時は、パッチ・エディット・モードの COMMON の設
定項目「MIDI[PC]」で、[STRING SELECT]ボタン を
押してその弦の番号に合わせ、「Off」になっていないか
調べてください(P.88)。
○ ポリ・モード送信時には、和音演奏時に限って 音高変化
が半音刻みとなります。音高の連続変化が必 要な時は単
音で弾くか、モノ・モード送信を使ってください。
○ MIDI ベンド・レンジが「1」や「2」に設定されている
と、チョーキングなどにより音高が連続変 化する演奏の
場合、音のリ トリガ ー(鳴らし直し)が頻繁に 起こり、
気になる場合が有ります。ベンド・レンジ を送/受信で
合わせ る 時は、なるべく 大き な値にして くだ さい(P.
86)。
○ GR-33 では、発音の高速化と滑らかな音高変化表現のた
め、音高をノート情報とピッチ・ベンド情 報の組み合わ
せで伝えます。このため、シーケンサーのマイクロスコー
プ(イベント・リスト)画面でノート情報の みを見た場
合、演奏した内容と異なって見える場合が ありますので
ご了承ください。ピッチの連続変化が 不要であれば、送
信ベンド・レンジを「0」にすることで視認性の高いデー
タ作りができます(P.86)。
96

第 10 章 その他の便利な機能
プログラム・チェンジ番号をパッチの順に振り直す
いずれかのパッチを使って設定を変更し、できあがったオリ
ジナルのパッチを他の番号に書き込んでいく ... という作業を
繰り返したり、パッチの並び替え(P.25)を行うと、プログ
ラム・チェンジ番号(MIDI[PC])が、パッチ番号の順番と関
係の無い、不規則な設定になってしまいます。
パッチの先頭から固定されている受信側のプログラム・チェ
ンジ番号と、再び一致させる必要が生じた場合は、次の手順
で送信プログラム・チェンジ番号を先頭のパッチから順に(工
場出荷時の設定に)振り直します。
※ この操作を行うと、各パッチの「MIDI [PC]」の設定内容
がすべて失われますのでご注意ください。
■ プログラム・チェンジ番号をパッチの順に振り直す
手順
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
2.
[PARAMETER]で、FACTORY RESETを選びます。
fig.10-01(PC# RESET 1)
3.
[VALUE]で、PC Numberを選びます。
[WRITE]を押します。
4.
Sure ?とファクトリー・リセットを実行してもよいか
を確認するメッセージが表示されます。
fig.10-02(PC# RESET 2)
5.
実行する時は、もう一度[WRITE]を押します。
Now Writing...と表示 され、プレイ・モードに 戻った
らファクトリー・リセットの完了です。
これにより送信プログラム・チェンジ番号 が先頭のパッ
チから順に 1、2、3、...127、128 となります。(送信バ
ンク・セレクト 情報は、コ ントロール・チェンジ 0 番
(MIDI [CC0])、32 番(MIDI [CC32])とも、ユーザー・
パッチは全て「0」に戻ります。)
中止する時は、[PLAY]を押します。
MIDI コントローラー 7 番(音量)の送信を止める
コントロール・チェンジ 7 番は、GK-2A のボリュームつまみ
の状態送信 だけで なく、「SYNTH、MIX、GUITAR」の切り
替えスイッチにも使われています。
ところが、MIDI 機能付きエフ ェクター には、まれにコント
ロール・チェンジ 7 番の音量制御を無視するように設定でき
ないものがあります。
fig.10-03(MIDI コントローラー7 番)
ギター・アンプヘ
ボリューム情報の受信を→
切れないタイプのエフェクター
シンセ音用アンプヘ
*パッチ切り替え情報をGR-33から
ギター用エフェクターに送信
これを、GR-33 と MIDI 接続してギター音用の外部エフェク
ターとして用いた場合、GK-2A の切り替えスイッチを
「GUITAR」にすると、シンセ音だけでなくギター音も聴こえ
なくなりますので注意が必要です。
この種のエフェクターと組み合わせる場合は、次の操作を行
えば GR-33 はコントロール・チェンジ 7 番を送信しなくな
ります。
MIDIIN*
DOWN/S1
UP/S2
SYNTHVOL
GUITAR
MIX
SYNTH
10 章
97
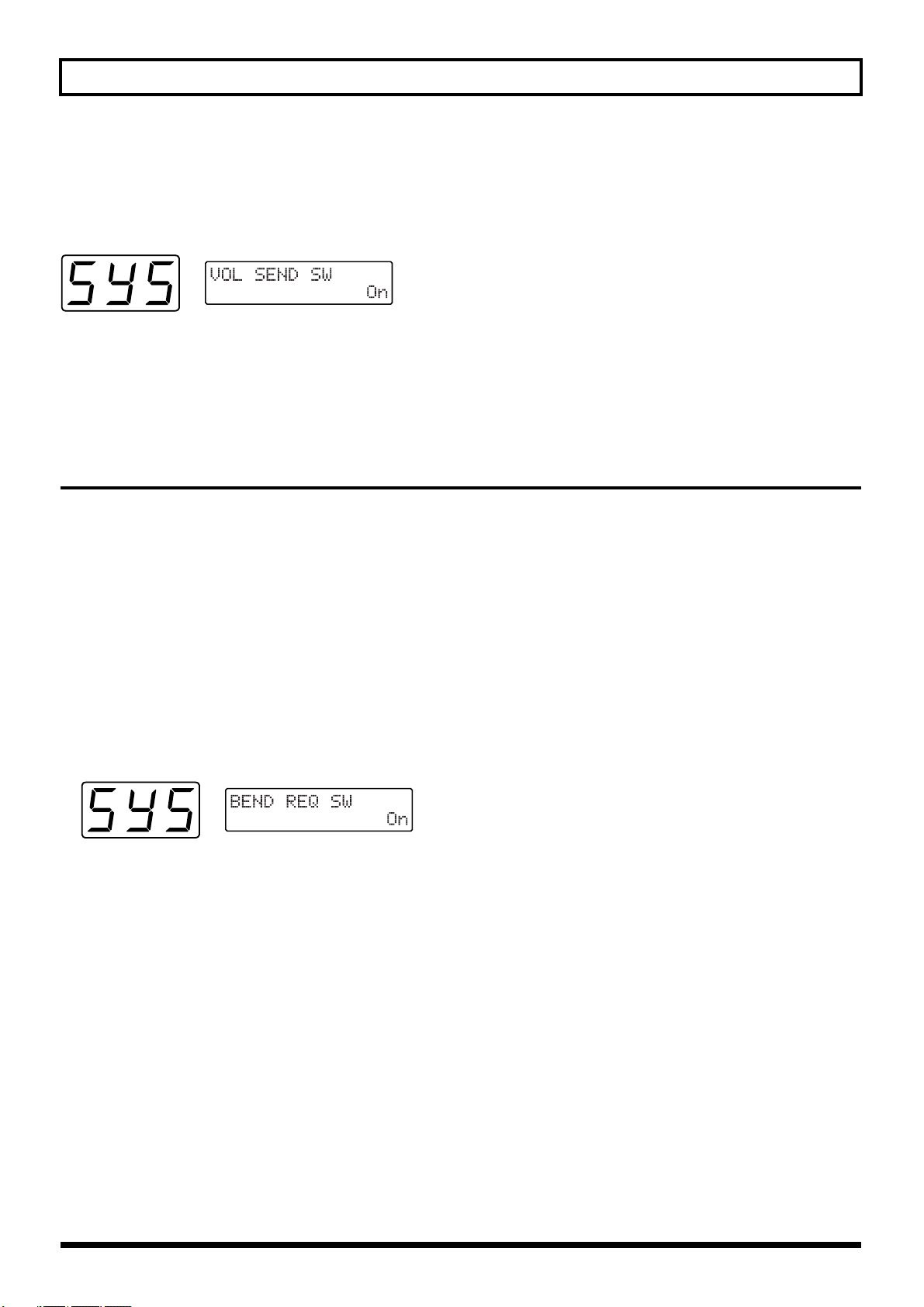
第 10 章 その他の便利な機能
■ MIDI コントローラー 7 番の送信を止める手順
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
[PARAMETER]で、VOL SEND SW を選びます。
2.
fig.10-04(SEND CC7)
3.
[VALUE]で、Offを選びます。
[PLAY]を押してプレイ・モードに戻ります。
4.
※ これはパッチではなく GR-33 本体に関する設定項目(シ
ステム・モード)なので、ライト操作は 不要です。電源
を切っても、最後の設定は自動的に記憶されています。
以上により、コントロール・チェンジ 7 番の MIDI アウトか
らの送信が止まり、前述の障害が解決します。
※ 他のボリューム関連の制御に基づくコ ントロール・チェ
ンジ 7 番の送信も一切止まりますので、必要な場合以外
はこの設定は変更しないでください。一度 送信を止める
と、再度「On」に戻すか、システム関連の設定をお買い
上げ時の状態に戻す操作(P.16)を行わない限り、自動
的に電源オフ後もその状態が記憶されま すのでご注意く
ださい。
ベンド・レンジのリクエスト情報の送信を止める
GR-33 は、パッチが替わる度に、外部 MIDI 機器に対し GR33 で設定さ れているベンド・レ ンジを知らせ、変更を促す
メッセージを送信します。
使用されるのは MIDI の RPN = レジスタード・パラメーター・
ナンバーの「ピッチ・ベンド・センシティビティ」、すなわち
コントロール・チェンジ 100 番、101 番、6 番、38 番です。
もし何らかの必要があれば(シーケンサーの打ち込みに使っ
ており、パッチ切り替え時の送信情報を減らしたい、など)、
次の手順でこの機能を停止させることもできます。
[SYSTEM]を押して、システム・モードに入ります。
1.
2.
[PARAMETER]で、BEND REQ SWを選びます。
fig.10-05(SEND B.REQUEST)
[VALUE]で、Offを選びます。
3.
4.
[PLAY]を押してプレイ・モードに戻ります。
※ これはパッチではなく GR-33 本体に関する設定項目(シ
ステム・モード)なので、ライト操作は不要 です。電源
を切っても、最後の設定は自動的に記憶されています。
以上によりパッチ切り替え時の、ベンド・レンジのリクエス
ト情報(MIDI ピッチ・ベンド・センシティビティ)の送信が
なくなります。
※ 一度送信を止めると、再度「On」に戻すか、システム関
連の設定をお買い上げ時の状態に戻す操作(P.16)を行
わない限り、自動的に電源オフ後もその状態 が記憶され
ますのでご注意ください。
98

第 11 章 資料
故障と思う前に
GR-33 単体での通常演奏において
● ギターを弾いてもシンセ音が出ない
◆ 本体の VOLUME つまみが下がっていませんか?
→ 適正なレベルまで上げてください。
◆ GK-2A のボリュームが下がっていませんか?また切り換
えスイッチが GUITAR に設定されていませんか?
→ スイッチを SYNTH または MIX に合わせ、ボリュームを
適正なレベルまで上げてください。
◆ ボリューム機能を割り当てたエクスプレ ッション・ペダ
ルが、手前に引き戻されていませんか?
→ エクスプレッション・ペダルを踏み込んでください。
◆ レイヤーの設定が、1st、2nd の両トーンとも選択されな
い状態になっていませんか?
→ 1st(2nd)トーンを各弦に割り当ててください。(P.51)
◆ 設定項目「PATCH LEVEL」が下がっていませんか?
→ 適正なレベルまで上げてください。(P.38)
◆ トーン のバ ランスが割り当 てら れたエクスプ レッシ ョ
ン・ペダルが、踏み込まれて(または戻 し切られて)い
ませんか?
→ エクスプレッション・ペダルを動かしてみてください。
● 弦によって音量がばらつく
◆ 各弦の「PICKUP SENS」の設定は正しくできています
か?
→ 必要な場合は調節を行ってください。(P.17)
● ピッチ・グライド(またはエクスプレッ
ション・ペダルのピ ッチ機能)を使 う際、
ピッチが上がりきらない
◆ 連続的にピッチを変化させる機能では、ト ーンや音域に
よってはピッチ上昇時の変化幅が制限さ れる場合があり
ます。
→ 制限が起こった場合は、変化幅を狭くして ご使用くださ
い。(P.44)
● マスター・チューンを変更してもピッチが
変わらない
◆ GR-33 でマスター・チューンの設定を変更しても、ピッ
チが直ちに変わるのは外部MIDI機器からのコントロール
で鳴っているシンセ音のみです。パッ チの項目
「CHROMATIC」が「Type1 〜 3」に設定されている場合
を除き、ギターでコントロールされるシン セ音は、マス
ター・チューンと関係なく、ギターの実際のピ ッチを追
従します。
→ マスター・チューン(P.18)の設定後、内蔵チューナー
でギターのチューニング(P.18)をやり直せば 、ギター
を含める全てのピッチが正しく調律されます。
● レイヤーを正しく設定しても、一方のトー
ンが鳴らない
◆ 「1:2 BALANCE」(P.52)が 1st 側、または 2nd 側に片
寄っていませんか?
→ 適当なバランスに設定し直してください。
● エクスプレッション・ペダルでの音色変化
の効き方が、トーンによって異なる
◆ 384 個のトーンには、ブライトネス及びワウワウの機能
を割り当てた時、通常と効き方のニュアン スが異なるも
のが含まれています。
→ 実際に機能を割り当て、あらかじめ効き方 をご確認くだ
さい。(P.47)
● 本体のペダル効果やエクスプレッション・
ペダル使用時、モジュレーションの効き方
がトーンによって異なる
◆ モジュレーション効果を用いた場合のピ ッチの揺れの速
さは、トーンごとにそれぞれ決まっています。
→ あらかじめ揺れ方を確認し、曲にあった速 さのトーンを
選んでください。
◆ ペダル効果(WAH)の「Modulation」では、効果(揺れ)
の深さもトーンごとに決まっています。
11 章
→ 効果の深さを確認し、曲にあった深さのト ーンを選んで
ください。
99

第 11 章 資料
● エクスプレッション・ペダルでトーンの音
量バランスを変える際、片方のトーンが鳴
らない
◆ TONE の「LAYER」が、1st、2nd のどちらか一方のみし
か発音しない様に設定されていませんか?
→ 1st、2ndの両方が鳴るように設定してください。(P.51)
◆ TONE の「1:2 BALANCE」(P.52)が、「50」または「50」に設定されていませんか?
→ 0 付近にして動作を確認してください。
●内蔵エフェクトが効かない
◆ EFFECTS の設定項目「REV SEND LEVEL」(P.75)、「CHO
SEND LEVEL」(P.74)、に「0」、「MULTI-FX SW」(P.53)
に「Off」が選ばれていませんか?
→ 「0」、「Off」以外の設定を選んでください。
◆ 「REV SENDLEVEL」「CHO SEND LEVEL」、マルチ・エ
フェクトの音量関連のパラメーターなど は、適正な値に
なっていますか?
→ 適正な値に設定してください。
◆ 3 桁表示器のEdtが点滅表示して、EFFECT BYPASS
の状態になっていませんか?
→ [EFFECTS]を押して、バイパス機能から抜けて くださ
い。(P.75)
◆ GR-33 の内蔵エフェクトは、内蔵シンセ音源専用です。
ギター自体の音にはかかりません。
→ ギター・アウト・ジャックを用いれば、ギター 音のみに
ギター用外部エフェクターをかけることができます。(シ
ンセ音とギター音で 1 台のアンプを共用する場合は、ギ
ター・リターン・ジャックも併用します。)(P.15)
● ごく高い音域で細かくうねるノイズが聴
こえることがある
◆ エイリアシング・ノイズと呼ばれるデジタ ル音源独特の
現象です。スライド奏法やピッチ・シフト 機能使用中な
どに聴こえ る場合 がありますが、故障ではあ りません。
GR-33 ではギターによる演奏でも、最小限となるよう工
夫されています。
● ピッチが滑らかに変化しない
◆ COMMON の「CHROMATIC」が「Type1 〜 3」に設定
されていませんか?
→ ピッチの連続変化が必要なパッチでは CHROMATIC は
「Off」に設定してください。(P.42)
◆ ベンド・データ・シン機能(P.95)を使っていませんか?
この機能を用いると通常の演奏でも、ピッ チ変化の滑ら
かさが多少失われます。
→ 必要な場合以外、ベンド・データ・シン機能 は使わない
でください。
● 電源投入時、ディスプレイに
Battery Low!と表示される
◆ ユーザー・パッチやシステム設定のデータ を保持するた
めの内蔵電池が消耗してきていること の警告です。この
表示が現れたら、データを失わない為に早 めの電池交換
が必要です。
→ お買い求めの楽器店、または最寄りの ローランド・サー
ビス・スポットにご相談ください。
パッチの設定項目の変更中に
◆ 「Cho Send Level」(コーラス・センド・レベル)「Rev
Send Level」(リバーブ・センド・レベル)機能が選ばれ
たエクスプレッション・ペダル(P.47)が、引き戻され
きった状態になっていませんか?
→ エクスプレッション・ペダルを踏み込んでみてください。
● シンセ音のピッチが、ギターのピッチ通り
に変わらない
◆ 一部のトーン(打楽器音や効果音など)に は、ギター側
とは異なるピッチ変化を示すものがあり ますが、故障で
はありません。
◆ ハーモニストがオンの場合、「HAR/ARP SELECT」(P. 82)
に「Harmony All」や「Harmony 1&2」が選ばれている場
合、シンセ音の音階変化はギター側とは異なります。
100
● 表示が突然点滅を始めた
◆ [STRING SELECT]ボタンが有効な設定項目で、表示を
「ALL」(全弦)または「5-6」(5、6 弦)に合わせた場合
の文字表示の点滅は、現在その設定が、弦によって異なっ
ていることを知らせています。
◆ EFFECTS のエディット中のEdtの点滅は、バイパス
機能が ON になっていることを知らせています。
● 設定を変更しても音が変わらない
◆ GR-33 のアタック、リリース、ブライトネスの設定は、
トーンがそれぞれ持っているオリジナ ル・データに調節
を加える方式です。従ってトーンによって 変化の範囲は
異なり、あまり大きな変化を示さないものもあります。
 Loading...
Loading...