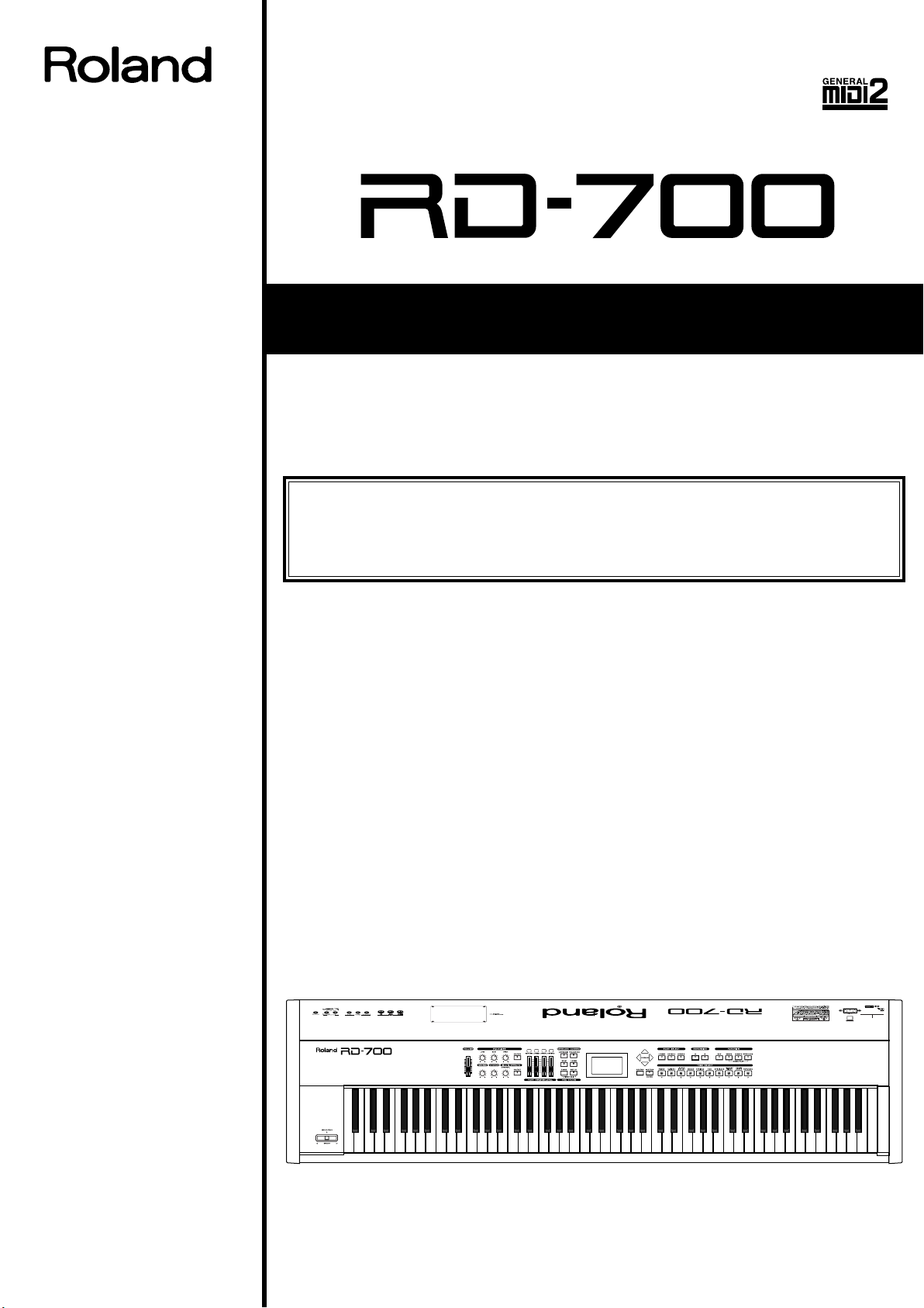
この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前 に
「安全上のご注意」(P.2 〜 4)
また、この機器の優れた機能を
十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよ くお読みください。取扱説明書は 必要
なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。
このたびは、ローランド・デジタル・ピアノ RD-700 をお買い上げいただき、まことにあ
りがとうございます。
と「使用上のご注意」(P.5)をよくお読みください。
取扱説明書
203
215
※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
©
本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。
2001 ローランド
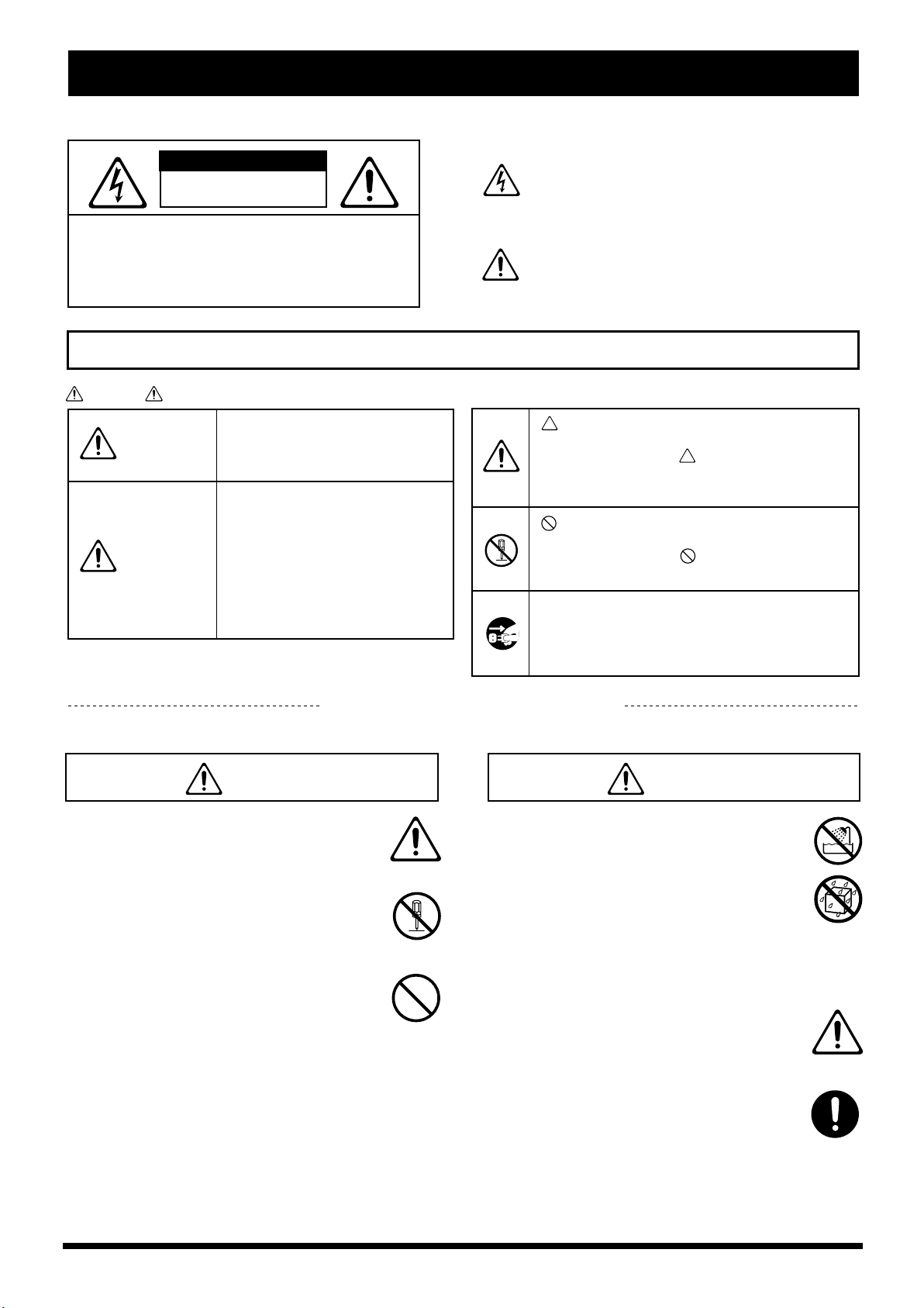
安全上のご注意
安全上のご注意
火災・感電・傷害を防止するには
このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書
などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ
れていることを表わしています。
このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危
険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警
告しています。
マークについて この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。
以下の指示を必ず守ってください
図記号の例
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。
※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
●は、強制(必ずすること)を表わしています。
具体的な強制内容は、
●の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。
警告
注意
注意の意味について警告と
は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。
は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。
注意:
感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。
この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品
はありません。
修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに
依頼してください。
注意
感電の恐れがあります。
キャビネットをあけないでください。
001
● この機器を使用す る前に、以下の 指示と取扱説
明書をよく読んでください。
..............................................................................................................
002b
● この機器を分解し たり(取扱説明 書に記載され
ている指示(P.16)を除く)、改造したりしない
でください。
..............................................................................................................
003
● 修理/部品の交換 などで、取扱説 明書に書かれ
ていないことは、絶 対にしな いでください。必
ずお買い上げ店ま たはローラ ンド・サービスに
相談してください。
..............................................................................................................
警告 警告
004
● 次のような場所で の使用や保 存はしないでくだ
さい。
○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場
所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)
や湿度の高い場所
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
...............................................................................................................
005
● この機器の設置 には、ローラン ドが推奨するス
タンド(型番 :KS-17)を使用してください。
...............................................................................................................
008e
● 電源コードは、必ず 付属のもの を使用してくだ
さい。また、付属の電源 コードを 他の製品に使
用しないでください。
...............................................................................................................
2
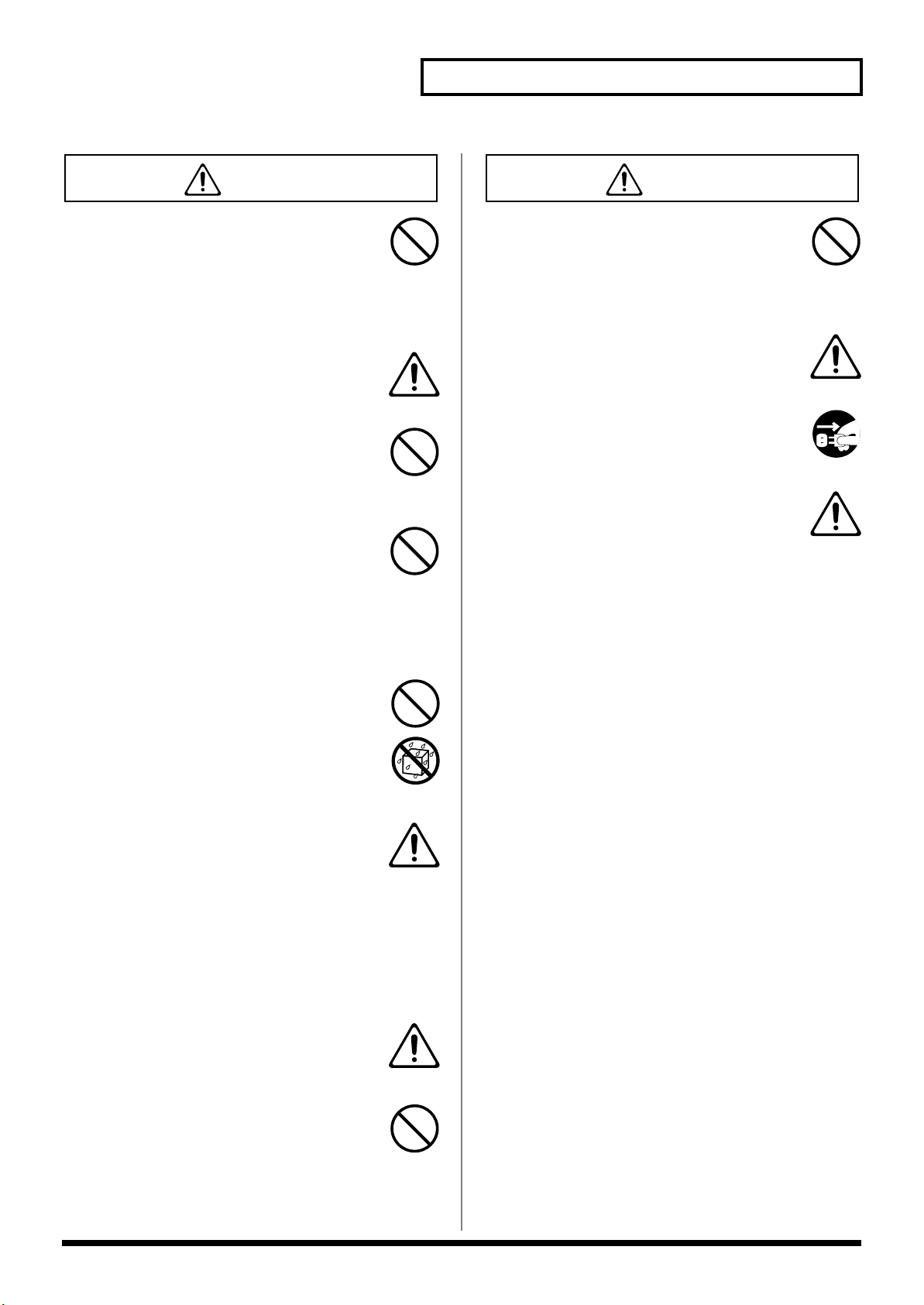
警告
安
全
上
警告
006
● この機器の設置にスタンド(型番 :KS-17)を使
用する場合、ぐらつ いた所や 傾いた所にスタン
ド(型番 :KS-17)を設置しないでください。安
定した水平な所 に設置し てください。機器を単
独で設置する場 合も、同様に 安定した水平な所
に設置してください。
..............................................................................................................
008a
● 電源プラグは、必ず AC100V の電源コンセント
に差し込んでください。
..............................................................................................................
009
●電源コードを無理に曲げ たり、電源コー ドの上
に重いものを載 せたりし ないでください。電源
コードに傷が つき、ショー トや断線の結果、火
災や感電の恐れがあります。
..............................................................................................................
010
●この機器を単独で、あるい はヘッド ホン、アン
プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設
定によっては永 久的な難聴に なる程度の音量に
なります。大音量 で、長時間使 用しないでくだ
さい。万一、聴力低 下や耳鳴 りを感じたら、直
ちに使用をやめ て専門の医師 に相談してくださ
い。
..............................................................................................................
011
●この機器に、異物(燃えや すいも の、硬貨、針
金など)や液体(水、ジ ュース など)を絶対に
入れないでください。
安全上のご注意
015
●電源は、タコ足配線などの無 理な配線を しない
でください。特 に、電源タップ を使用している
場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を
超えると発熱 し、コードの被 覆が溶けることが
あります。
..............................................................................................................
016
● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または
ローランド・サービスに相談してください。
..............................................................................................................
022a
● 基板(型番 :SRX シリーズ)を取り付ける前に、
機器本体の電源 を切って電 源プラグをコンセン
トから外してください(P.21)。
..............................................................................................................
026
● 本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫
剤、香水、アルコール類、マニキュア、スプレー
缶などを置 かないでく ださい。また、表面に付
着した液体は、す みやかに乾 いた柔らかい布で
拭き取ってください。
..............................................................................................................
..............................................................................................................
012a
● 次のような場合は、直ちに電源を切って電源
コードをコンセ ントから 外し、お買い上げ店ま
たはローランド・サ ービスに 修理を依頼してく
ださい。
○ 電源コードやプラグが破損したとき
○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし
たとき
○ 機器が(雨などで)濡れたとき
○ 機器に異常や故障が生じたとき
..............................................................................................................
013
●お子様のいるご家庭で使 用する場合、お 子様の
取り扱いやいた ずらに注 意してください。必ず
大人のかたが、監視/指導してあげてください。
..............................................................................................................
014
●この機器を落としたり、この 機器に強い 衝撃を
与えないでください。
..............................................................................................................
3
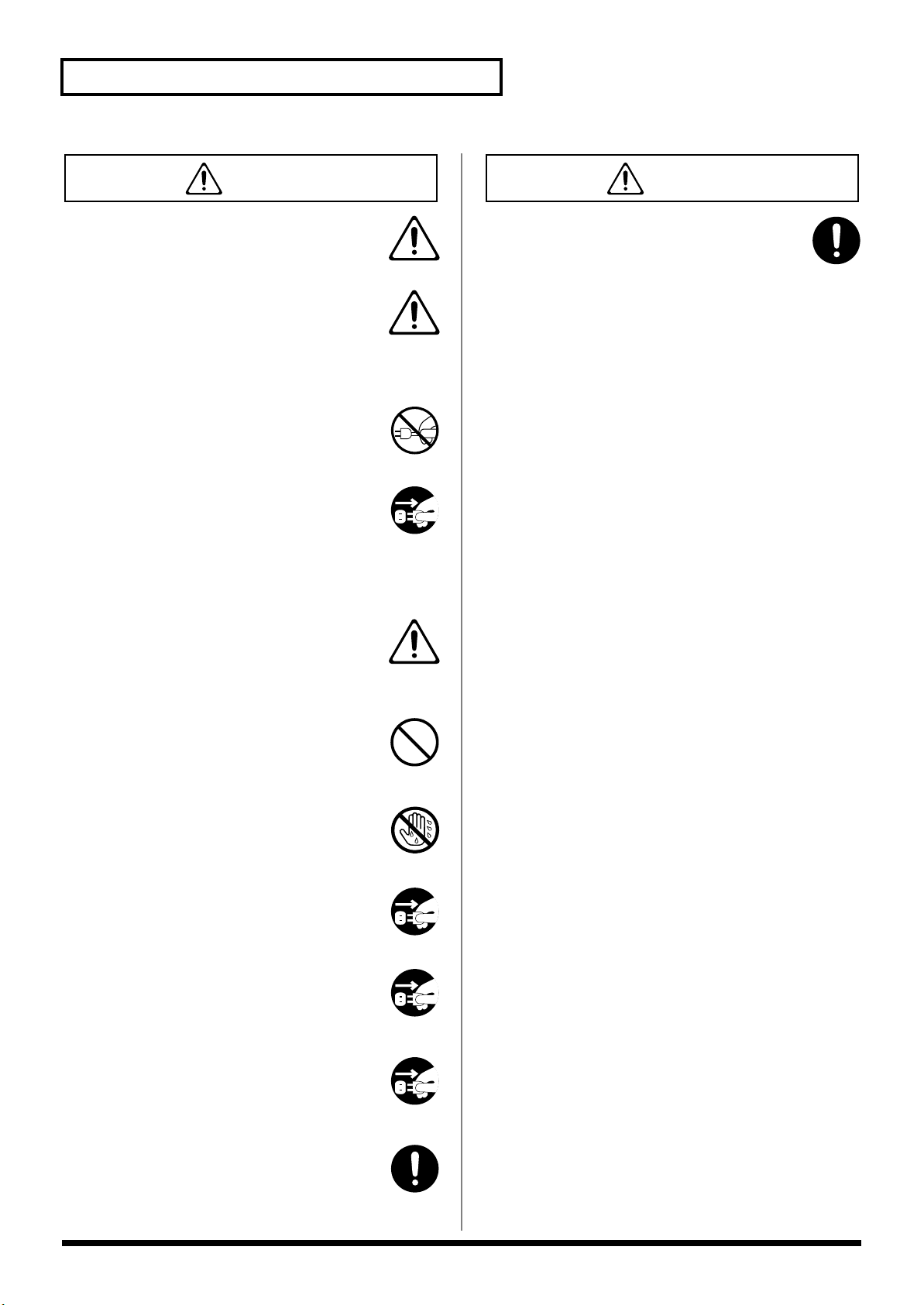
安全上のご注意
注意
注意
101a
●この機器は、風通しのよい、正 常な通気 が保た
れている場所に設置して、使用してください。
..............................................................................................................
101c
● 本製品は当社製のスタンド(KS-17)とのみ、組
み合わせて使用で きる よう設計さ れています。
他のスタンドと 組み合わ せて使うと、不安定な
状態となって落 下や転倒 を引き起こし、けがを
するおそれがあります。
..............................................................................................................
102b
●電源コードを機器本体やコン セントに抜 き差し
するときは、必ずプラグを持ってください。
..............................................................................................................
103a
●定期的に電源プラグを抜 き、乾いた布で ゴミや
ほこりを拭き 取ってく ださい。また、長時間使
用しないときは、電 源プラグ をコンセントから
外してください。電 源プラグ とコンセントの間
にゴミやほこり がたまる と、絶縁不良を起こし
て火災の原因になります。
..............................................................................................................
104
●接続したコードやケーブ ル類は、繁雑に ならな
いように配慮してください。特に、コードやケー
ブル類は、お子様の 手が届か ないように配慮し
てください。
..............................................................................................................
106
●この機器の上に乗ったり、機 器の上に重 いもの
を置かないでください。
118
●基板カバーのネジを外し た場合は、小さ なお子
様が誤って飲み 込んだりす ることのないようお
子様の手の届かないところへ保管してくださ
い。
..............................................................................................................
..............................................................................................................
107b
●濡れた手で電源コードの プラグを持 って、機器
本体やコンセントに抜き差ししないでくださ
い。
..............................................................................................................
108a
●この機器を移動するとき は、電源プラグ をコン
セントから外し、外 部機器と の接続を外してく
ださい。
..............................................................................................................
109a
●お手入れをするときには、電 源を切って 電源プ
ラグをコンセントから外してください(P.21)。
..............................................................................................................
110a
●落雷の恐れがあるときは、早 めに電源プ ラグを
コンセントから外してください。
..............................................................................................................
115a
● 指定の基板(型番 :SRX シリーズ)だけを取り付
け、指 定さ れ たネジ だけを外し てください
(P.15)。
..............................................................................................................
4

使用上のご注意
291a
2〜4ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。
電源について
301
● 本機を冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコンなどのイ
ンバーター制御の製品やモーターを使った電気製品が接
続されているコンセントと同じコンセントに接続しない
でください。電気製品の使用状況によっては、電源ノイ
ズにより本機が誤動作したり、雑音が発生する恐れがあ
ります。電源コンセントを分けることが難しい場合は、
電源ノイズ・フィルターを取り付けてください。
307
● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ
ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。
308
● 電源スイッチを切った後、本機上の LCD や LED などは
消えますが、これは主電源から完全に遮断されているわ
けではありません。完全に電源を切る必要があるときは、
この機器の電源スイッチを切った後、コンセントからプ
ラグを抜いてください。そのため、電源コ−ドのプラグ
を差し込むコンセントは、この機器にできるだけ近い、
すぐ手の届くところのものを使用してください。
設置について
351
● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを
持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあ
ります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えて
ください。
352
● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレ
ビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることが
あります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してく
ださい。
354a
● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め
切った車内などに放置しないでください。変形、変色す
ることがあります。
355
● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用
しないでください。
358
● 鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。発音し
なくなるなどの故障の原因になります。
お手入れについて
401a
● 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く
絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいと
きは、中性洗剤を含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔
らかい布で乾拭きしてください。
402
● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル
コール類は、使用しないでください。
修理について
451b
● お客様がこの機器を分解(取扱説明書に記載されている
指示(P.15)を除く)、改造された場合、以後の性能に
ついて保証できなくなります。また、修理をお断りする
場合もあります。
453
● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維
持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し
ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて
いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇
所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上
げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く
ださい。
その他の注意について
551
● 記憶した内容は、機器の故障や誤った操作などにより、
失われることがあります。失っても困らないように、大
切な記憶内容はバックアップとして他の MIDI 機器
(シーケンサーなど)に保存しておいてください。
552(*** は、複数になる場合もあります)
●他のMIDI 機器(シーケンサーなど)の失われた記憶内
容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。
553
● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端
子などに過度の力を加えないでください。
554
● ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでくださ
い。
556
● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ
ラグを持ってください。
557
● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあ
りません。
558a
● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない
ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。
ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ
ます。
559a
● 輸送や引っ越しをするときは、この機器が入っていたダ
ンボール箱と緩衝材、または同等品で梱包してください。
561
● エクスプレッション・ペダルは、必ず指定のもの(別
売:EV-5)をお使いください。他社製品を接続すると、
本体の故障の原因になる場合があります。
5
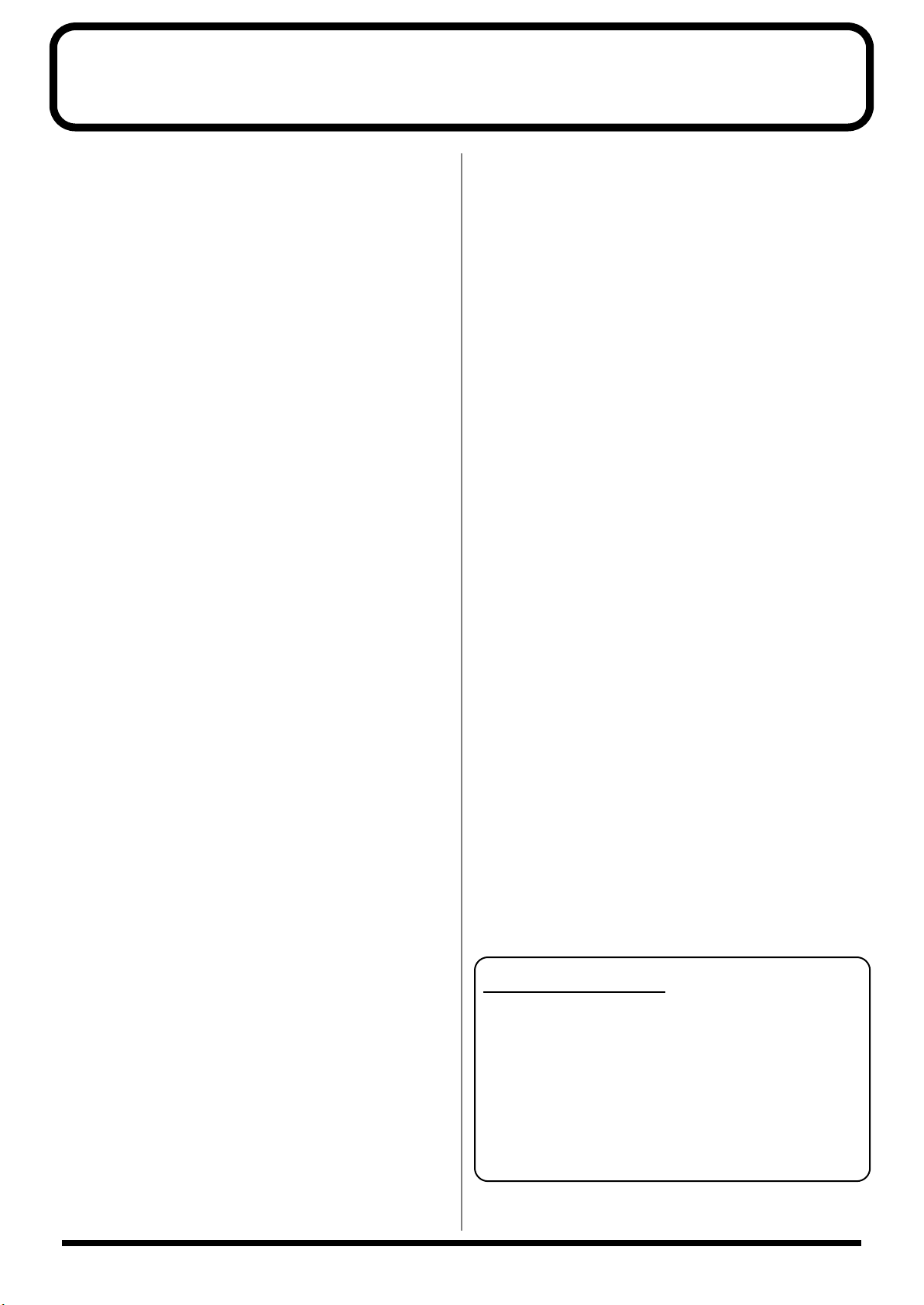
主な特長
■ プログレッシブ・ハンマー・アクション 鍵盤を搭載
グランドピアノの自然で心地よいタッチをリアルに再現し、
ご好評をいただいているローランドのハンマー・アクション
鍵盤をさらに進化させて誕生した「プログレッシブ・ハン
マー・アクション鍵盤」を搭載。連打性や静粛性といった基
本性能をいっそう高め、低音部から高音部への移行に伴う
タッチの微妙な変化まで再現することができます。
また、プログレッシブ・ハンマー・アクション鍵盤は、ハン
マー部に鉛をいっさい使用しない、環境を配慮した設計です。
■ 新開発ピアノ音色
広いダイナミックレンジ、豊かな表現力を持った本格的なピ
アノ音色を搭載。さらにエレクトリック・ピアノ、オルガ
ン、ストリングス、シンセ・パッドなど、ステージ・ピアノ
としての重要な音色を強化。ステージでその存在感を発揮し
ます。
また、ピアノ音色を微妙に変化させることのできる「ピア
ノ・エディット」機能を搭載。あらゆるシチュエーションに
合わせた音作りが可能です(P.62)。
■ 余裕の 128 ボイス
あらゆる演奏方法に対応できる最大同時発音数 128 の音源
を搭載。複数の音を重ねて演奏しても自然な演奏をお楽しみ
いただけます。
■ ボタンを押すだけの簡単操作
スプリット、レイヤーなど、主な操作はボタン一つで設定可
能(P.37)。
また、ONE TOUCH[PIANO]ボタンを押せば、どんな状態
でもすぐにピアノ演奏に最適な設定になります(P.31)。
■ フルグラフィック LCD 画面を搭載
視認性の高いフルグラフィック LCD を搭載。見やすい音色
名表示など、LCD 画面を見ながら操作をスムーズに行えま
す。
■ オルガン用トーン・ホイール音源搭載
オルガン音色には、ローランド・コンボ・オルガン VK-7 ゆず
りのオルガン用トーン・ホイール音源を搭載。各フィートの
レベルを変えるオルガンの音作りを再現しています(P.71)。
■ リズム、アルペジエーター機能を搭載
ボタン一つでリズム・パターンの再生やアルペジオ演奏が可
能。
リアルなドラム演奏をバックにセッション感覚で演奏した
り、和音を押さえるだけでアルペジオやカッティング演奏す
るなど、多彩な演奏が楽しめます(P.45、P.47)。
■ 素早い外部 MIDI コントロール
音量調節、音色選択など、外部 MIDI 機器も簡単にコント
ロール可能。ステージ・キーボードとして、直感的な素早い
コントロールを実現します(P.55)。
■ 優れた拡張性
XV シリーズで好評のウェーブ・エクスパンション SRX シ
リーズを 2 枚搭載可能。「SRX-02 Concert Piano」をはじ
め、今後続々と発表される最新の音色で演奏することができ
ます(P.15)。
■ 洗練されたデザイン
ステージ映えする高級感のあるチタン・カラー・ボディ。操
作性も考慮した洗練されたデザインで、リアのケーブル接続
も簡単に行えます。
■ GM/GM2 に対応
RD-700は GM/GM2 に対応しています。GM/GM2に準拠し
たミュージックデータ(GM スコア)であれば、シーケン
サーと組み合わせて、そのデータを RD-700 で演奏できます。
■ 高品位エフェクト搭載
ローランド・シンセサイザー、XV シリーズで好評のマルチ
エフェクトに加え、アコースティック・ピアノの共鳴音を再
現したシンパセティック・レゾナンスを搭載。ダンパー・ペ
ダルを踏んだときのリアルな音色変化を再現します(P.72)。
さらにデジタル・イコライザーによる幅広い音色調整が可能
です(P.69)。
6
文中の表記について
● []で囲まれた英数字は、パネル上のボタンを表してい
ます。
例:[SPLIT]は SPLIT ボタンを表しています。
● (P.**)は参照ページを表しています。
● 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工
場出荷時の設定(音色名など)と本文中の画面上の設定
は一致していません。あらかじめご了承ください。
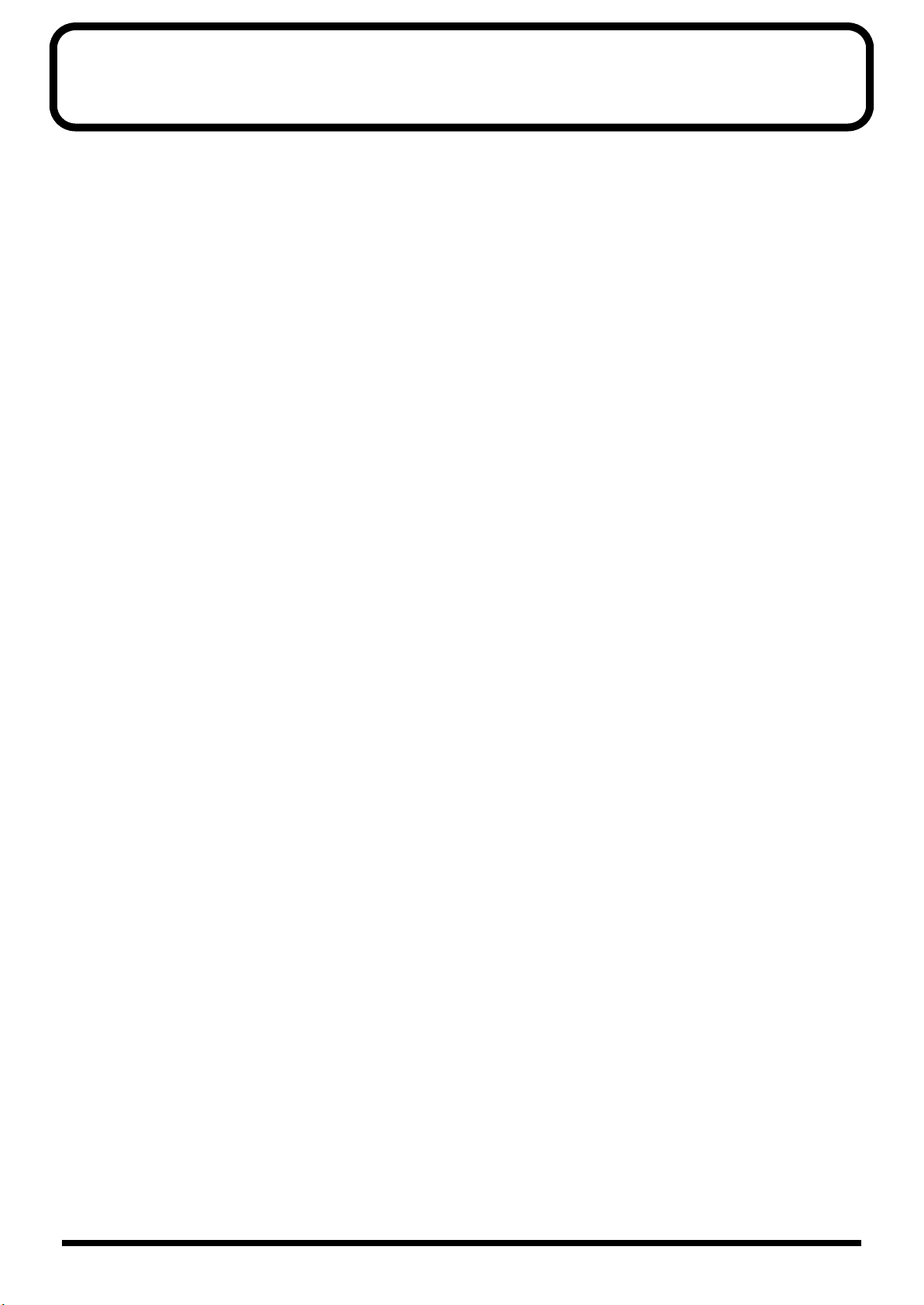
目次
安全上のご注意 ............................................................................................................................................... 3
使用上のご注意 ............................................................................................................................................... 5
主な特長.......................................................................................................................6
各部の名称と働き ...................................................................................................... 12
フロント・パネル .........................................................................................................................................12
リア・パネル..................................................................................................................................................14
演奏する前に .............................................................................................................15
ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける...........................................................................15
ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付けるときの注意...........................................15
ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けかた ...........................................................16
取り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードを確認する...............................................17
外部機器と接続する.....................................................................................................................................18
ペダルの接続......................................................................................................................................19
電源を入れる/切る.....................................................................................................................................20
電源を入れる......................................................................................................................................20
電源を切る..........................................................................................................................................21
音量を調節する .............................................................................................................................................21
工場出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット).........................................................................22
表示の濃さを調節する(LCD コントラスト)........................................................................................24
他の楽器と音の高さを合わせる(マスター・チューニング).............................................................25
RD-700 の概要........................................................................................................... 27
RD-700 の基本構成 .....................................................................................................................................27
鍵盤コントローラー部 .....................................................................................................................27
音源部 ..................................................................................................................................................27
音の単位..........................................................................................................................................................27
トーン ..................................................................................................................................................27
パート ..................................................................................................................................................27
RD-700 の基本操作 .....................................................................................................................................28
主な画面 ..............................................................................................................................................28
特殊な表示..........................................................................................................................................28
ファンクション・ボタンの働き.....................................................................................................28
カーソル・ボタンの働き .................................................................................................................29
設定値の変更......................................................................................................................................29
デモ曲を聴いてみよう(DEMO PLAY)..................................................................... 30
鍵盤で演奏しよう ...................................................................................................... 31
ピアノ演奏をする(ONE TOUCH [PIANO]).........................................................................................31
いろいろな音色(トーン)で演奏する....................................................................................................32
トーン・ナンバーを指定してトーンを選ぶ([NUM LOCK])...............................................33
リズム・セットを鳴らす .................................................................................................................34
ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンを選ぶ ...........................................................35
鍵盤で 2 つのトーンを鳴らす....................................................................................................................37
シングル・モードにするには.........................................................................................................37
2 つのトーンを重ねて演奏する([LAYER]).............................................................................38
鍵盤を 2 つの音域に分けて別々のトーンで演奏する([SPLIT])........................................39
レイヤーやスプリット・モードのトーンの変えかた ...............................................................40
パートごとの音量を調節する(PART SWITCH/PART LEVEL スライダー)...............................41
鍵盤の音の高さを変える([TRANSPOSE])........................................................................................42
7

目次
音に響きをつける(REVERB つまみ).....................................................................................................43
音に広がりをつける(CHORUS つまみ)...............................................................................................43
音の高さをリアルタイムに変化させる(ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー)...........44
音の低域・中域・高域のレベルを調節する(EQUALIZER)..............................................................44
多彩な機能を使って演奏しよう................................................................................. 45
弾いた和音をアルペジオにする([ARPEGGIO])................................................................................45
アルペジオのスタイルを変える.....................................................................................................46
アルペジオのテンポを変える.........................................................................................................46
リズムを鳴らす([RHYTHM]).................................................................................................................47
リズムのパターンを変える.............................................................................................................48
リズムのテンポを変える .................................................................................................................48
音に効果をかける(MULTI EFFECTS)..................................................................................................49
記憶させた設定を選ぶ([SETUP]).........................................................................................................50
設定をセットアップに記憶する([WRITE]).........................................................................................52
RD-700 をマスター・キーボードにする ................................................................... 55
MIDI とは ........................................................................................................................................................55
MIDI 端子について............................................................................................................................55
外部 MIDI 音源との接続例...............................................................................................................55
MIDI 送信チャンネルを設定する...............................................................................................................56
外部 MIDI 音源の音色を切り替える..........................................................................................................57
パートごとに音量を調節する(MIDI TX パート).................................................................................58
MIDI 送信パートの詳細設定をする([MIDI TX]).................................................................................59
設定のしかた......................................................................................................................................59
音量/パンを設定する .....................................................................................................................59
リバーブ/コーラスのレベルを設定する....................................................................................59
鍵域を設定する(キー・レンジ)...................................................................................................59
パートごとに移調の設定をする(トランスポーズ).................................................................60
ベンダーによる音程変化の幅を設定する(ベンド・レンジ).................................................60
トーンの要素を変化させる(ATK / REL / C OF / RES)..................................................60
音を滑らかに変化させる(ポルタメント)..................................................................................61
音の高さを変える(コース・チューン/ファイン・チューン).............................................61
各コントローラーのオン/オフを設定する................................................................................61
鍵盤を弾く強さによる音量変化を設定する(ベロシティー).................................................61
ピアノ音色の詳細設定をする(ピアノ・エディット)............................................... 62
設定のしかた..................................................................................................................................................62
設定項目..........................................................................................................................................................62
ピアノ音色を選ぶ..............................................................................................................................62
音の広がりかたを変える(Stereo Width).................................................................................62
音色のニュアンスを変える(Nuance)........................................................................................62
音の空気感を変える(Ambience)................................................................................................62
リバーブ効果のかかり具合を変える(Reverb Level).............................................................63
中音域のイコライザーを設定する(EQ-SW / EQ Gain / EQ Frequency / EQ Q)....63
8

各機能の詳細設定をする([EDIT])...........................................................................64
設定できる項目........................................................................................................................... 64
パラメーターの選び方 .....................................................................................................................65
システムの設定(System)......................................................................................................... 65
設定のしかた......................................................................................................................................65
全体の音量を設定する(Master Volume)..................................................................................66
イコライザーの設定が切り替わらないようにする(EQ Control)........................................66
トーンを変えても発音中の音を残す(Tone Remain)............................................................66
クロック・ソースを変える(Clock Source)............................................................................66
GM/GM2 システム・オン、GS リセットの受信を切り替える
(Rx GM / GM2 System On、Rx GS Reset).........................................................................66
プログラム・チェンジ情報でセットアップを切り替える(Control Channel).................66
デバイス ID ナンバーを設定する(Device ID)..........................................................................67
ペダルの極性を切り替える(Pedal Polarity)............................................................................67
鍵盤タッチの設定(Key Touch)................................................................................................ 67
設定のしかた......................................................................................................................................67
鍵盤のタッチ感を変える(Key Touch).....................................................................................68
鍵盤のタッチ感を微調整する(Key Touch Offset)...............................................................68
弾く強さによる音量を一定にする(Velocity)...........................................................................68
弾く強さによって発音のタイミングを変える(Velocity Delay Sens)...............................68
鍵域によるタッチ感を変える(Velocity Keyfollow Sens)....................................................68
ペダル/[CONTROL]つまみ/イコライザーの設定(Control/EQ)...................................... 69
設定のしかた......................................................................................................................................69
ペダルに機能を割り当てる(FC1/FC2)....................................................................................69
[CONTROL]つまみの設定を変える(Control/Src).............................................................70
イコライザーの周波数設定を変える(Freq/Q)........................................................................70
オルガンの音作りをシミュレートする(トーン・ホイール・モード)...................................... 71
PART LEVEL スライダーのフィートの割り当てを変える(Harmonic Bar)....................72
マルチエフェクト/リバーブ/コーラスの設定(MFX/Reverb/Chorus)................................. 72
設定のしかた......................................................................................................................................72
マルチエフェクトの設定をする.....................................................................................................73
リバーブの設定をする .....................................................................................................................74
コーラス/ディレイの設定をする ................................................................................................74
トーンの設定(Tone Edit)......................................................................................................... 75
設定のしかた......................................................................................................................................75
設定するパート、トーンを選ぶ(< Part >、Tone)..............................................................76
リバーブ/コーラスの深さを設定をする(Reverb / Chorus Amount)...........................76
トーンにかける効果を変える(MFX).........................................................................................76
単音で発音させる(Mono / Poly).............................................................................................76
音の高さ(ピッチ)を変える(Coarse / Fine Tune)...........................................................76
音をなめらかに変化させる(Portamento Switch / Time)..................................................77
トーンの要素を変化させる
(Attack Time / Release Time / Cutoff / Resonance)....................................................77
ベンド・レンジを変える(Bend Range)..................................................................................77
和音の響きを微妙に変える(Stretch Tune).............................................................................77
リズムの設定(Rhythm Pattern)............................................................................................... 78
設定のしかた......................................................................................................................................78
テンポを変える(Tempo)..............................................................................................................78
パターンを変える(Pattern).........................................................................................................78
リズムのバリエーションを選ぶ(Rhythm Type)....................................................................78
リズム・セットを変える(Rhy Set)...........................................................................................79
パターンを変えてもドラム・セットを変えない(Rhy Set Change).................................79
目次
9
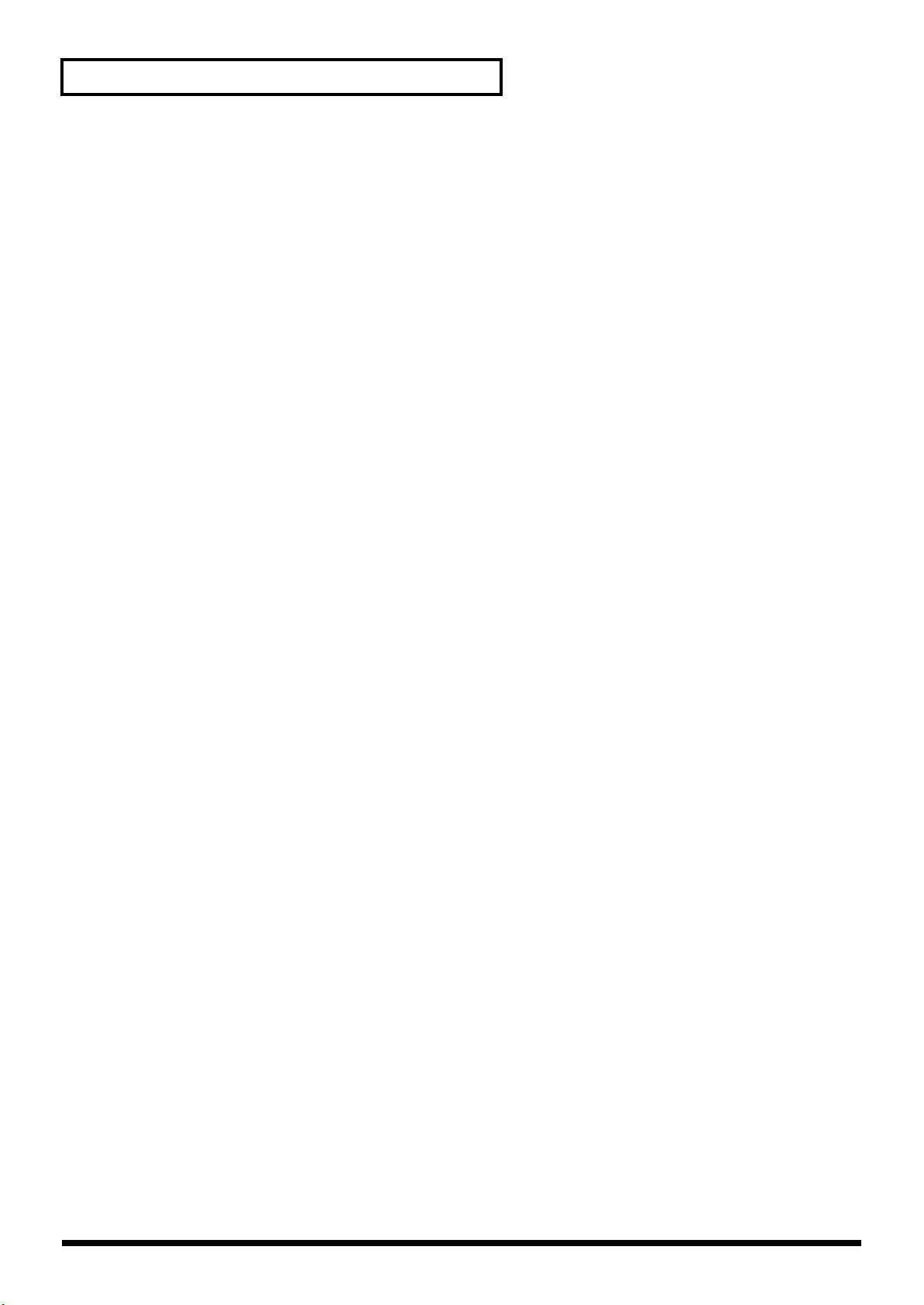
目次
イントロ/エンディングのオン/オフを設定する(Intro/Ending).....................................79
アルペジエーターの設定(Arpeggio)........................................................................................ 79
設定のしかた......................................................................................................................................79
テンポを変える(Tempo)..............................................................................................................80
アルペジオ演奏するパートを選ぶ(Dest.Part)........................................................................80
アルペジオ演奏する鍵域を設定する(Key Range).................................................................80
アルペジオのしかた(スタイル)を設定する(Style)............................................................80
アルペジオの音域を変える(Octave Range)...........................................................................81
音の鳴る順番をかえる(Motif).....................................................................................................81
グルーヴ感を変える(Beat Pattern / Accent Rate / Shuffle Rate).............................82
音の強さを一定にする(Velocity)................................................................................................83
鍵盤から指を離してもアルペジオ演奏を続ける(Arpeggio Hold).....................................83
鍵盤パートやコントローラーの設定(Local Part Param)........................................................ 83
設定のしかた......................................................................................................................................83
設定するパートを選ぶ(< Local Part >).................................................................................84
各パートの鍵域を設定する(Key Range).................................................................................84
鍵盤を弾く強さによる音量変化を設定する(Velocity Sens/Max).....................................84
パートごとに移調の設定をする(Key Transpose)................................................................84
パートごとにコントローラーのオン/オフをする ...................................................................85
内部パートをローカル・パートに割り当てる(Part Assign)...............................................85
内部パートの MIDI 受信の設定(Internal Part Prm)................................................................. 85
設定のしかた......................................................................................................................................85
設定するパートを選ぶ(< Part >、Tone)..............................................................................86
受信チャンネルを設定する(Receive Channel)......................................................................86
音量/パンを設定する(Volume / Pan)...................................................................................86
エフェクトのオン/オフを設定する(MFX Switch)...............................................................86
必要な発音数を設定する(Voice Reserve)...............................................................................86
外部 MIDI コントローラーの MIDI 情報を受ける/受けないを設定する .............................87
調律法を設定する(Temperament / Key)...............................................................................87
その他の機能(Utility)............................................................................................................... 88
本体の設定を外部 MIDI 機器に転送する(バルク・ダンプ)..................................................88
設定を工場出荷時の状態に戻す(ファクトリー・リセット).................................................90
外部 MIDI 機器との接続............................................................................................. 91
RD-700 の演奏を外部 MIDI シーケンサーに録音する.........................................................................91
外部シーケンサーと接続する.........................................................................................................91
録音するときの設定(Rec Setting)............................................................................................91
演奏を録音する..................................................................................................................................92
ローカル・スイッチについて.........................................................................................................92
外部 MIDI 機器から RD-700 の音源部を鳴らす....................................................................................93
接続のしかた......................................................................................................................................93
チャンネルを設定する .....................................................................................................................93
外部 MIDI 機器から RD-700 の音色を切り替える ....................................................................93
GM 音源として使う(GM Mode)............................................................................................................94
GM モードでの注意点......................................................................................................................94
GM スコアを再生する......................................................................................................................94
10
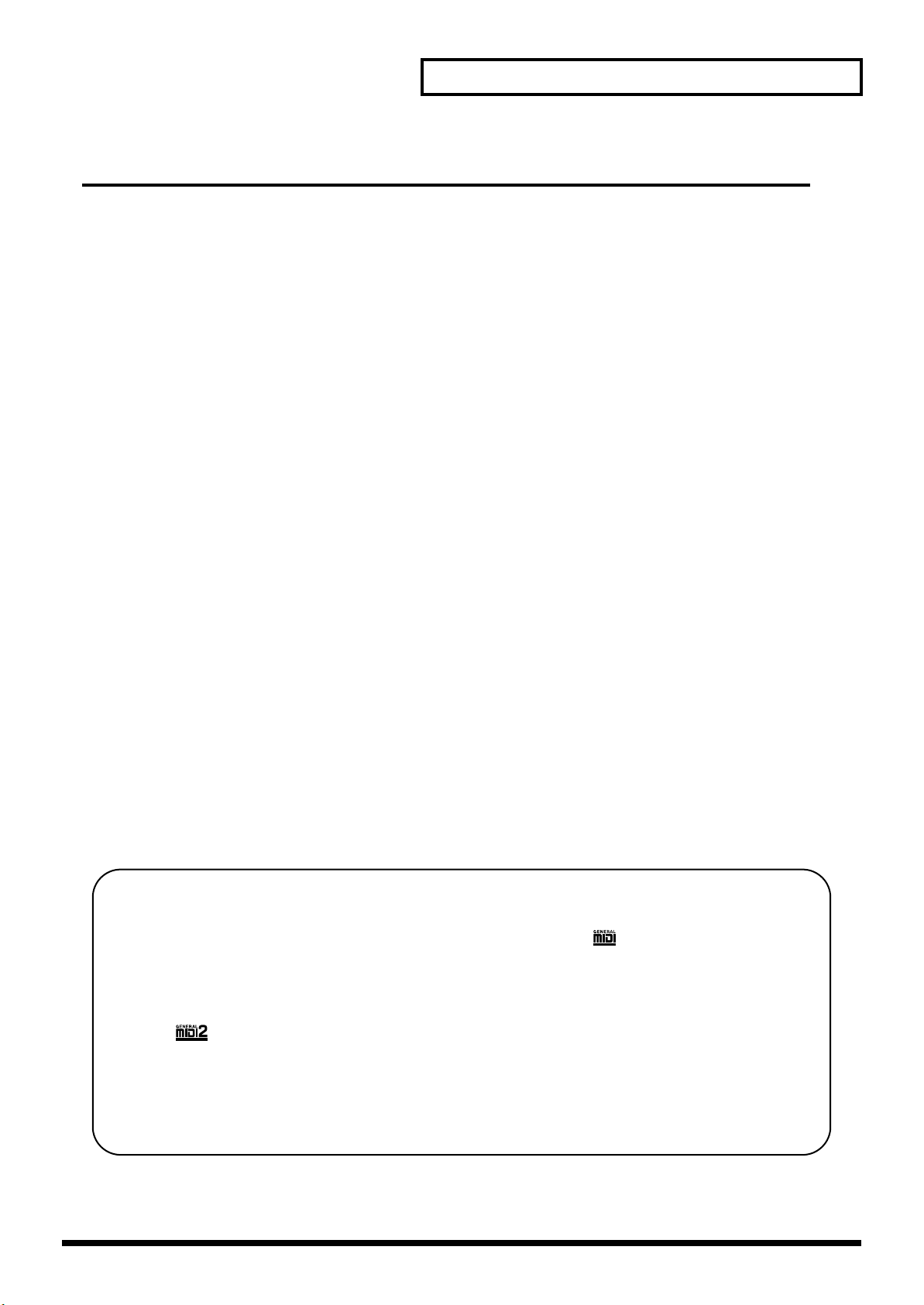
資料...................................................................... 95
GM
GM(General MIDI)とは、音源の MIDI 機能の仕様を、メーカーを越えて標準化することを目的とした推
GM2
GM2( )は、より高度な演奏表現と互換性を実現させるために決められた、GM の上位互換の推奨規
故障かな?と思ったら ............................................................................................... 95
エラー・メッセージ/その他のメッセージ............................................................... 99
エフェクト/パラメーター一覧............................................................................... 100
トーン一覧 ............................................................................................................... 131
リズム・セット一覧.................................................................................................................................. 134
アルペジオ・スタイル一覧 ......................................................................................138
リズム・パターン一覧 ............................................................................................. 139
セットアップ一覧 ....................................................................................................140
ショート・カット一覧 ............................................................................................. 141
MIDI インプリメンテーション................................................................................. 142
目次
主な仕様................................................................................................................... 160
索引 ..........................................................................................................................161
奨規定です。GM に合致した音源やミュージックデータには GM マーク( )が付いており、GM マー
クの付いたミュージックデータは、GM マーク付きの音源であればどれでもほぼ同じ演奏表現ができます。
定です。従来の GM で規定されていなかった音色のエディットやエフェクトなどの動作仕様が細かく規定さ
れ、音色も拡張されています。GM2 に対応する音源は、GM、GM2 のどちらのマークの付いたミュージッ
クデータも、正しく再生できます。
なお、GM2 の追加規定を含まない従来の GM を「GM1」と呼んで、両者を区別することがあります。
11
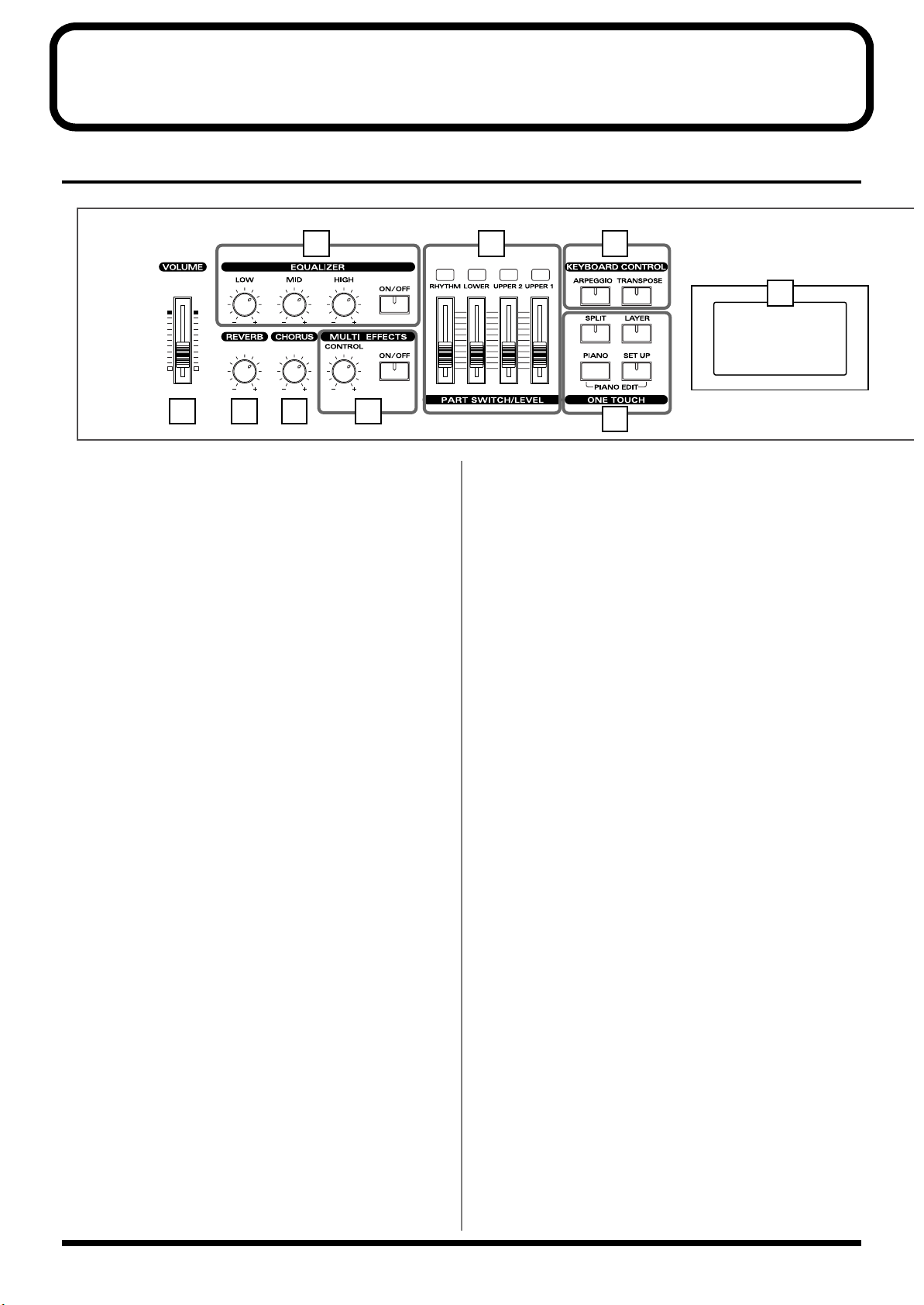
各部の名称と働き
フロント・パネル
2 6 7
9
1 3 4 5
VOLUME スライダー
1.
リア・パネルの OUTPUT ジャックと PHONES ジャックか
ら出力される全体の音量を調節します。(P.21)
2.
EQUALIZER
[ON / OFF]
イコライザーをオン/オフします。(P.44)
[LOW]つまみ
音の低域を調節します。
[MID]つまみ
音の中域を調節します。
[HIGH]つまみ
音の高域を調節します。
REVERB つまみ
3.
リバーブ効果(残響)のかかり具合を調節します。(P.43)
4.
CHORUS つまみ
コーラス効果のかかり具合を調節します。(P.43)
5.
MULTI EFFECTS
8
PART SWITCH/LEVEL
6.
各パートの音のオン/オフ(PART SWITCH)、音量の調節
(PART LEVEL スライダー)をします。(P.41)
[MIDI TX]がオンになっているときは、外部 MIDI 音源の各
パートをコントロールします。(P.58)
7.
KEYBOARD CONTROL
[ARPEGGIO]
アルペジエーターをオン/オフします。(P.45)
[TRANSPOSE]
鍵盤の音域の移調を設定します。(P.42)
ONE TOUCH
8.
[SPLIT]
鍵域を分けて複数の音色で演奏する「スプリット・モード」
にします。(P.39)
[LAYER]
2 つの音色を重ねて演奏する「レイヤー・モード」にしま
す。(P.38)
[PIANO]
ピアノ演奏に最適な設定にします。(P.31)
[CONTROL]つまみ
エフェクトのかかり具合を調節します。(P.49)
[ON / OFF]
マルチエフェクトをオン/オフします。(P.49)
12
[SETUP]
記憶した設定(セットアップ)を呼び出します。(P.50)
また、[PIANO]と[SETUP]を同時に押すと、ピアノ演奏
の詳細設定をおこなうことができます。(PIANO EDIT)
(P.62)
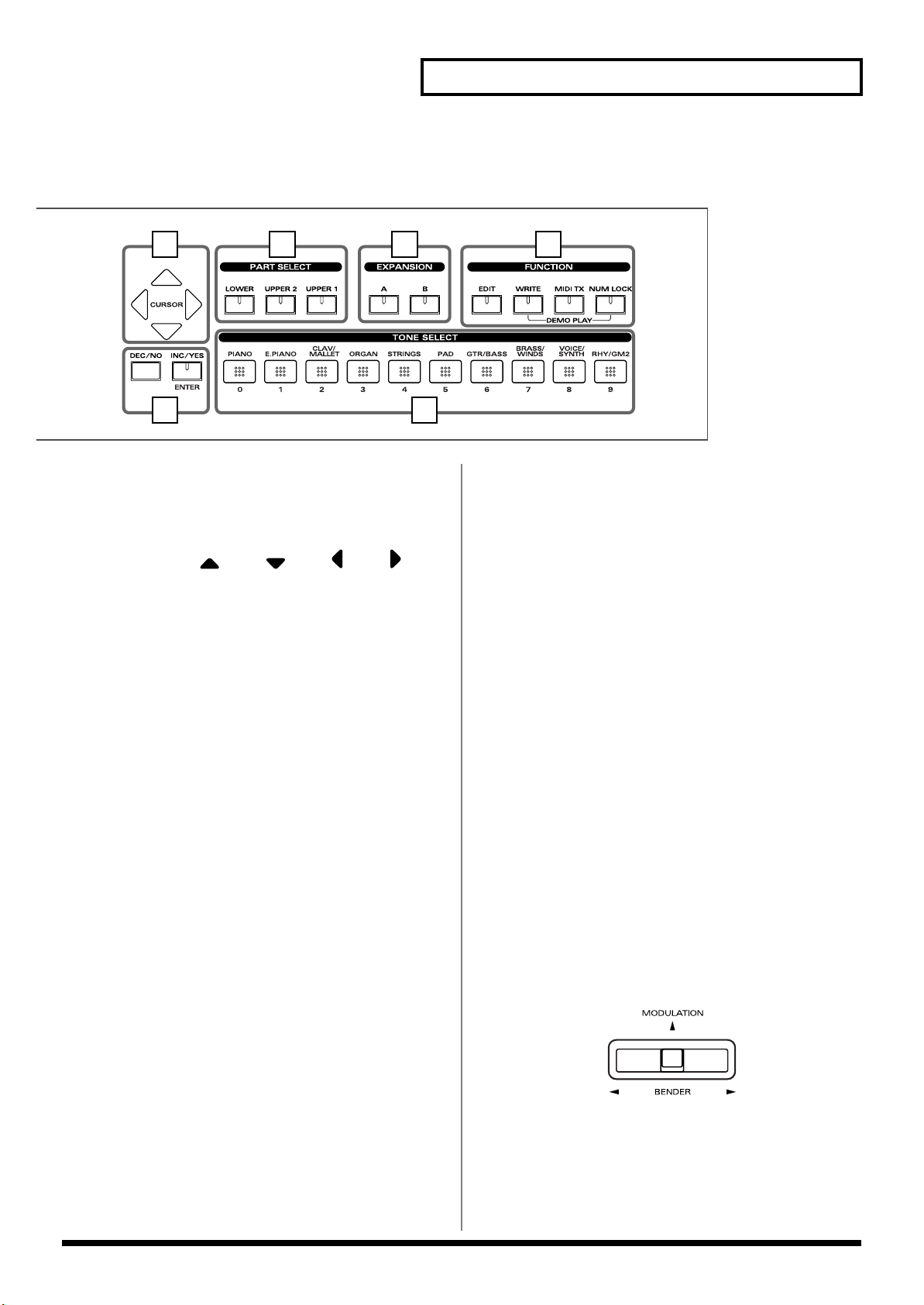
各部の名称と働き
10
12 13 14
11 15
9.
ディスプレイ
トーン名や、さまざまな設定を表示します。(P.28)
CURSOR[ ]、[]、[]、[]
10.
画面の切り替えや、カーソルを移動するときに押します。
(P.29)
11.
値を変更します。
片方のボタンを押しながら、もう一方のボタンを押すと、値
が速く変わります。
[ENTER]は値の確定や操作の実行に使います。
12.
[DEC/NO]、[INC/YES]/[ENTER]
PART SELECT ボタン
14.
FUNCTION
[EDIT]
いろいろな設定を変更するときに押します。(P.64)
[WRITE]
現在の設定を「セットアップ」に記憶します。(P.52)
[MIDI TX]
RD-700 で外部 MIDI 音源をコントロールします。(P.55)
[NUM LOCK]
このボタンをオンにすると、TONE SELECT ボタンで数値
を入力することができます。(P.33)
また、このボタンと[WRITE]を同時に押すと、デモ曲を
聴くことができます。(DEMO PLAY)(P.30)
音色(トーン)を選択するパートを選びます。(P.40)
EXPANSION[A]、[B]
13.
ウェーブ・エクスパンション・ボードの音色を選ぶときに押
します。(P.35)
15.
TONE SELECT ボタン
音色(トーン)のカテゴリーを選びます。(P.32)
[NUM LOCK]がオンになっているときは、このボタンで数
値を入力することができます。エディット画面などでは、
[NUM LOCK]が自動でオンになり、数値を入力するボタン
になります。
ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー
ピッチ(音の高さ)を変化させたり、ビブラートをかけたり
します。(P.44)
13
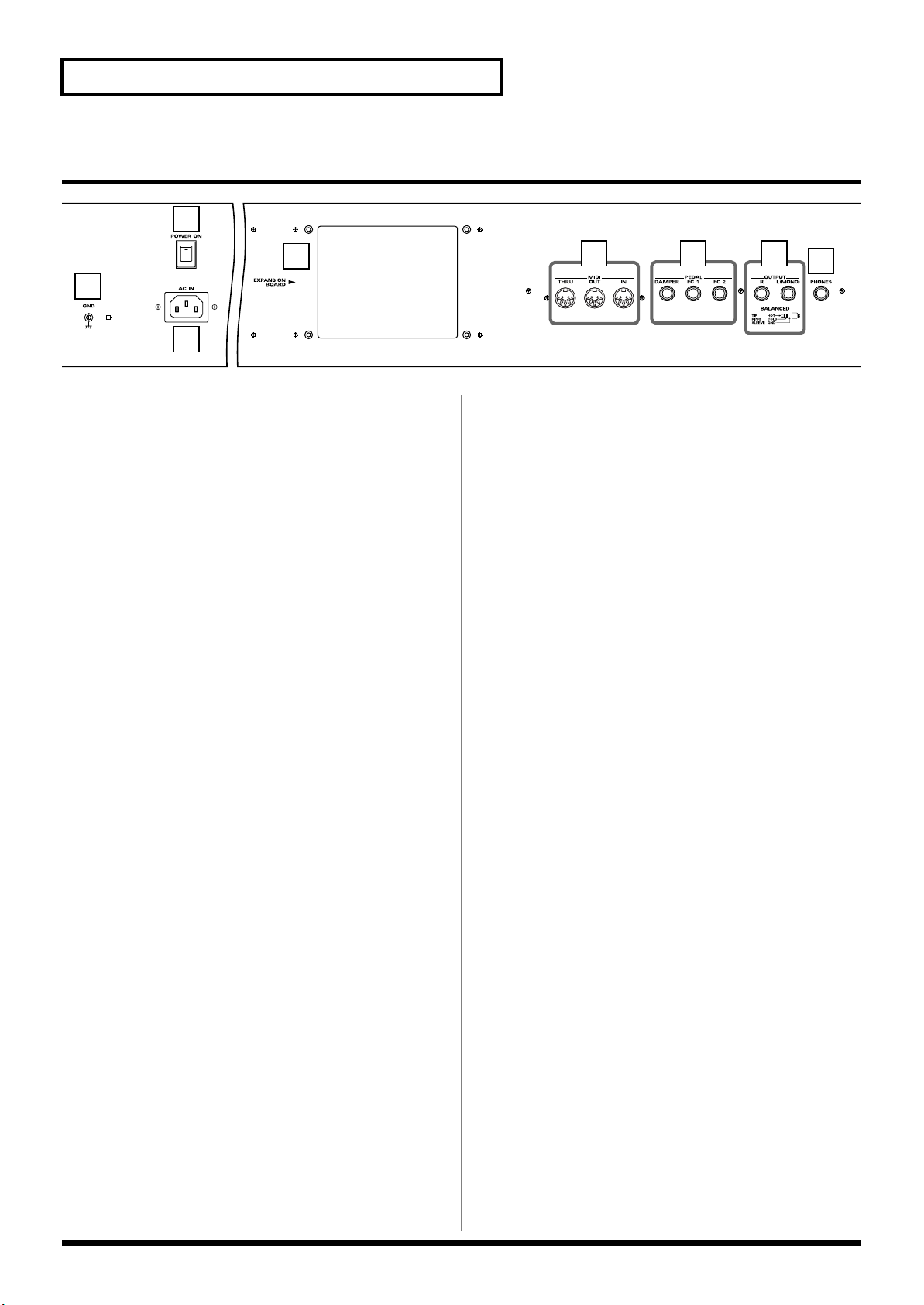
各部の名称と働き
リア・パネル
2
4
1
3
1.
GND(グランド)端子
接地条件や必要に応じて、グランド・ケーブルを接続します。
本機は、設置条件によってパネル面がざらつくような感じに
なるときがあります。これは人体に全く害のない極微量の帯
電によるものですが、気になる方は、必要に応じ、グランド
端子を使って外部のアースか大地に接地してご使用ください。
接地した場合、設置条件によってはわずかにハム(うなり)
が混じる場合があります。
なお接続方法がわからないときはローランド・サービスにご
相談ください。
接続してはいけないところ
・水道管(感電の原因になります)
・ガス管(爆発や引火の原因になります)
・電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)
5 6 7
6.
PEDAL 端子(DAMPER、FC1、FC2)
DAMPER 端子に付属のペダルを接続すると、ダンパー・ペ
ダルとして使用することができます。
FC-1、FC-2 端子にエクスプレッション・ペダル(別売:
EV-5 など)を接続すると、ペダルにいろいろな機能を割り
当てることができます。(P.19、P.69)
7.
OUTPUT R/L(MONO)端子
オーディオ信号の出力端子です。アンプなどと接続します。
モノラルで出力するときは、L(MONO)端子に接続してく
ださい。(P.18)
バランス出力にも対応しています。
PHONES 端子
8.
8
2.
[POWER]スイッチ
電源をオン/オフします。(P.20)
3.
AC インレット
付属の電源コードを接続します。(P.18)
4.
ウェーブ・エクスパンション・ボード
取り付け口
カバーを外して、別売のウェーブ・エクスパンション・ボー
ド(SRX シリーズ)を取り付けます。(P.15)
5.
MIDI 端子(IN、OUT、THRU)
外部 MIDI 機器と接続して、MIDI メッセージを送受信しま
す。(P.18、P.55、P.91)
ヘッドホンを接続します。(P.18)
ヘッドホンを接続しても、OUTPUT からはオーディオ信号
が出力されます。
14
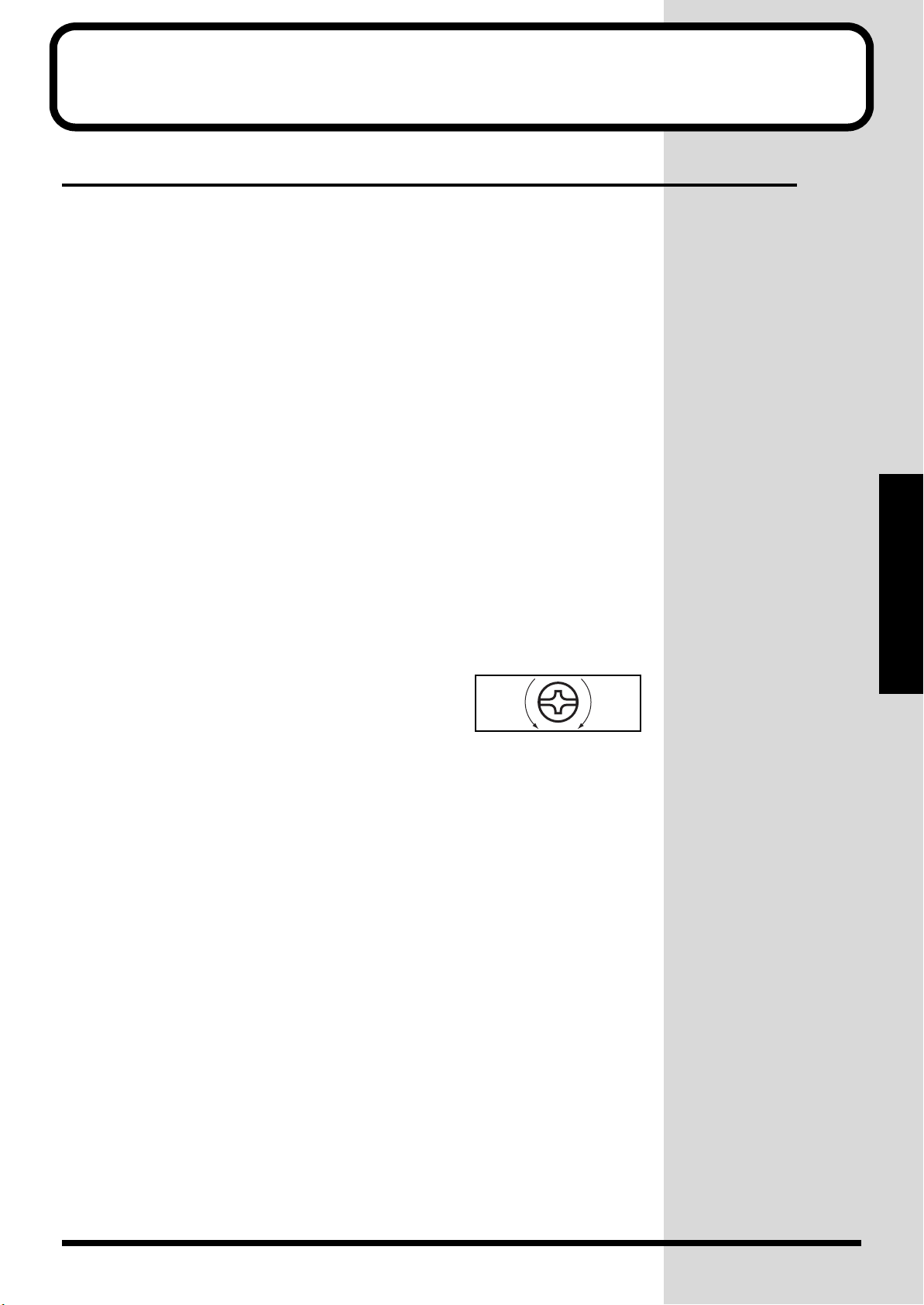
演奏する前に
ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける
RD-700 は、別売のウェーブ・エクスパンション・ボードを 2 枚(SRX
シリーズ)まで取り付けることができます。
ウェーブ・エクスパンション・ボードには、パッチ(RD-700 ではトーン
といいます。)、リズム・セットが記録されており、RD-700 に取り付ける
ことによって音色を増やすことができます。
ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付けるときの注 意
● この基板は、静電気により部品が破壊される恐れがあります。基板を
取り扱うときは、次の点に注意してください。
○ 基板を持つときは、あらかじめ何らかの金属に触れて、体や衣類に
たまっている静電気を放電してください。
○ 基板を持つときは、基板の縁を持ち、部品やコネクターの部分に直
接手を触れないでください。
○ 基板を保管するとき、または輸送するときなどは、購入時に基板が
入っていた袋(導電袋)に入れてください。
● 使用するプラス・ドライバーは、ネジの頭に合ったものを使ってくだ
さい(No.2 のドライバー)。ネジの頭に合っていないと、ネジの頭を
つぶしてしまうことがあります。
● ネジを外すときは、反時計方向にドライバー
を回してください。ネジを締めるときは、時
計方向にドライバーを回してください。
● ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付けるときは、指定され
たネジだけを外してください。
● 外したネジは、RD-700 内部に落とさないように注意してください。
● 外した背面のカバーをそのまま放置しておくことはおやめください。
ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けが終わったら、必ず
元通りに取り付けてください。
● 回路部やコネクター部には手を触れないでください。
● 取り付け開口部で手を切らないように注意してください。
● 基板を無理に押し込まないでください。装着しにくい場合、いったん
基板を外してやり直してください。
締まるゆるむ
演 奏する前に
● 取り付けを終えたら、正しく取り付けられていることを再度確認して
ください。
ウェーブ・エクスパンション・ボードは背面のカバーを外して取り付けま
す。ボードの取り付け場所には、A スロットと B スロットがあります。
ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーン(パッチ)/リズム・セッ
トを使うときは、フロント・パネルの EXPANSION[A]、[B]でこれら
のスロットを指定します。
15
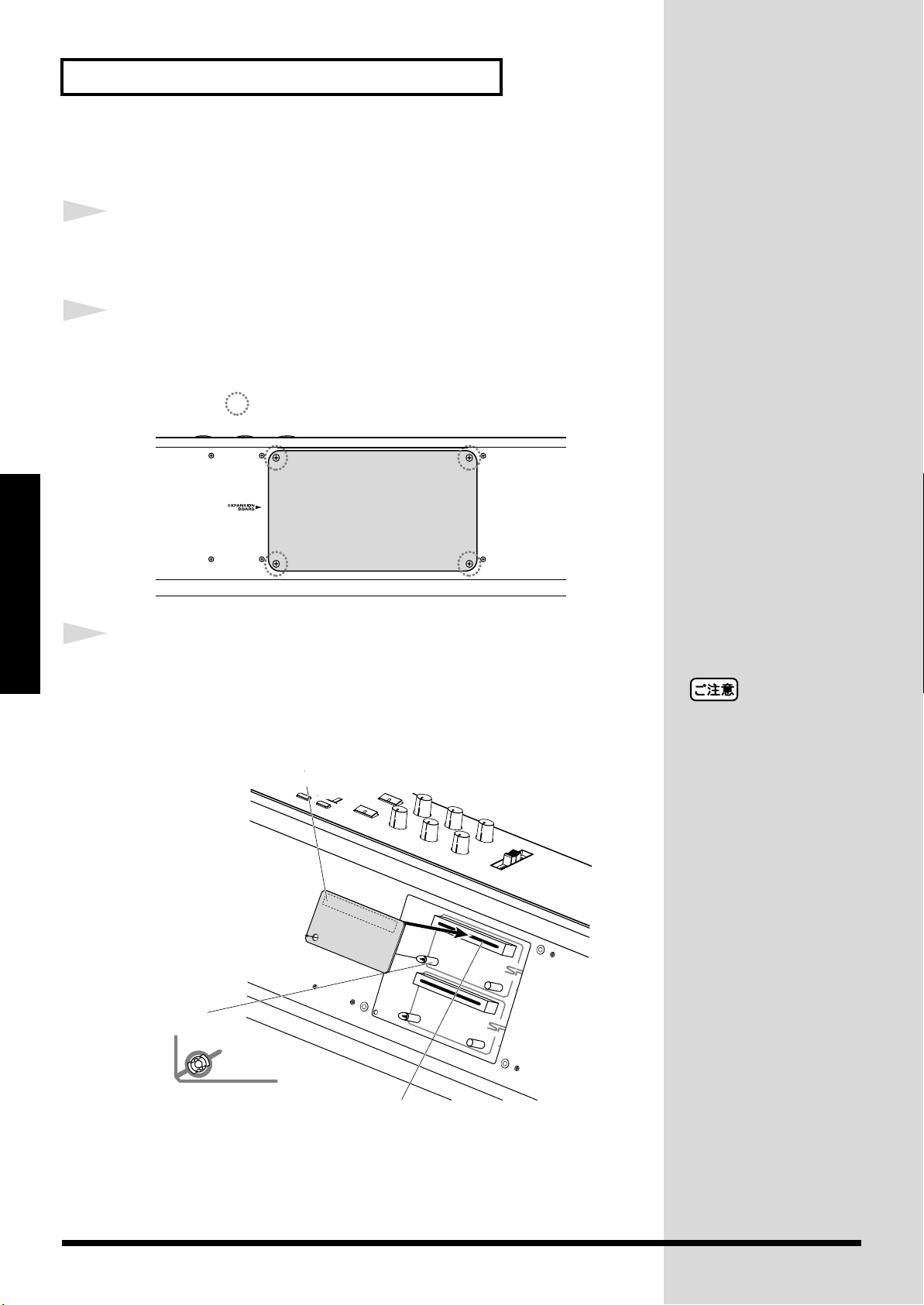
ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けかた
SRX A スロットと SRX B
演 奏する前に
演奏する前に
1
ウェーブ・エクスパンション・ボードを取り付ける前に、
RD-700 と接続機器の電源を切ります。
2
RD-700 背面の、次図で指定された銀色のネジだけを外して、
カバーを取り外します。
fig.00-02.j
取り外すネジ
3
いずれかのスロット(SRX A、SRX B)にウェーブ・エクス
パンション・ボードのコネクターを差し込み、同時に基板ホ
ルダーをウェーブ・エクスパンション・ボードの穴にはめ込
みます。
fig.00-03.j
ウェーブ・エクスパンション・ボード(SRXシリーズ)
基板ホルダー
スロットに、同じ種類の
ウェーブ・エクスパンショ
ン・ボードを取り付けた場
合は、SRX A スロットに
取り付けたウェーブ・エク
スパンション・ボードの
データのみ選ぶことができ
ます。
取り付ける前に図のような
向きに合わせます
16
コネクター
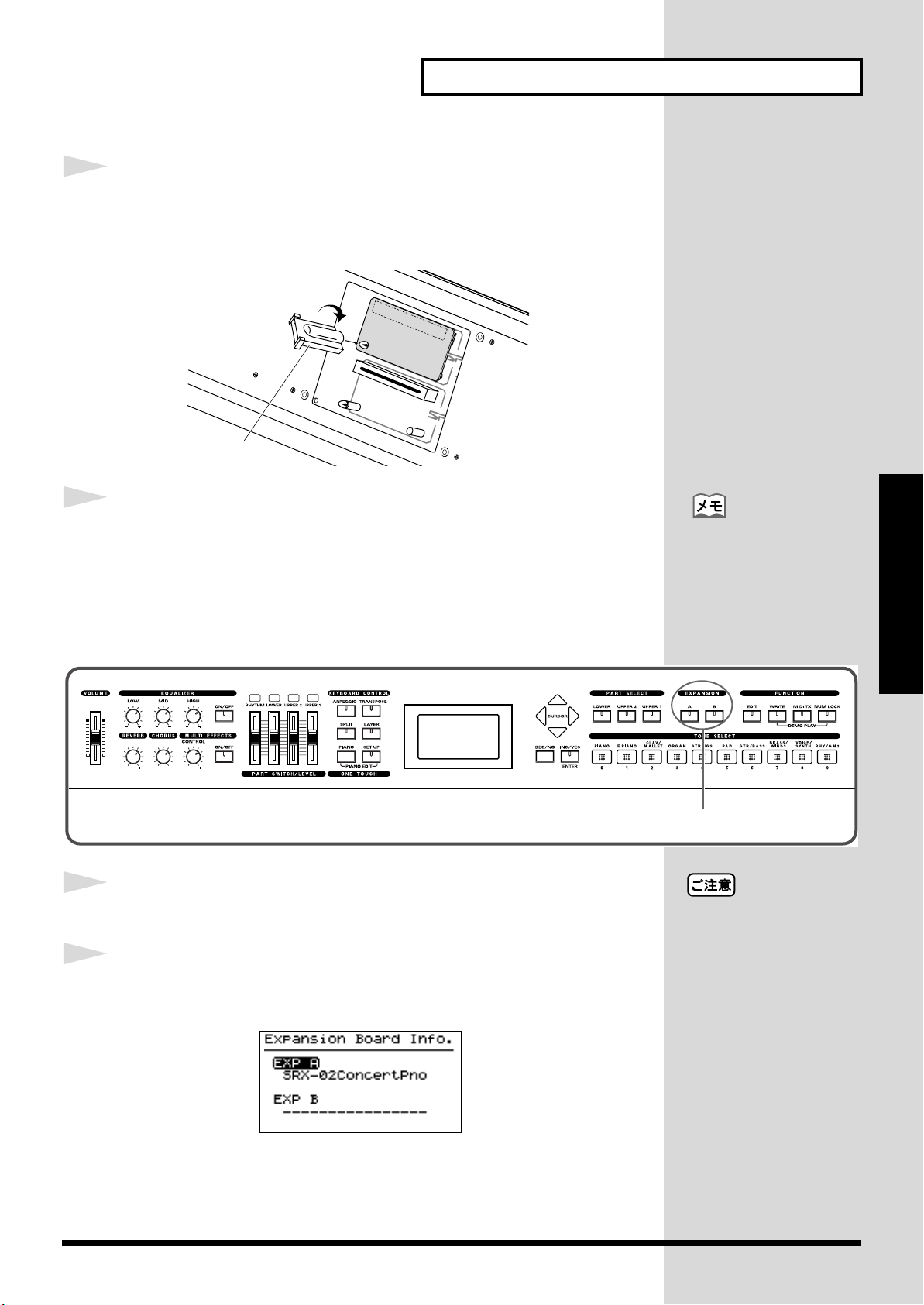
4
取り付けたスロット名の横
電源を切
る
(P.21)にしたがって電
源を切り、ウェーブ・エク
スパンション・ボードを正
しく取り付けなおしてくだ
さい。
ウェーブ・エクスパンショ
ン・ボードの音色の選びか
たは、
ウェーブ・エクスパ
ンション・ボードのトーン
を選ぶ
(P.35)をご覧くだ
さい。
5
演奏する前に
ウェーブ・エクスパンション・ボードに付属の固定用具で基
板ホルダーを LOCK 方向に回し、ウェーブ・エクスパンショ
ン・ボードを固定します。
fig.00-04.j
LOCK
固定用具
手順 2 で外したネジで、カバーを元通りに取り付けます。
取り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードを確認する
ウェーブ・エクスパンション・ボードの取り付けが終わったら、次に、取
り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードが正しく認識されるかを確
認しましょう。
fig.panel
1
「電源を入れる」(P.20)にしたがって電源を入れます。
2
EXPANSION[A]または[B]を押し続けます。
取り付けたウェーブ・エクスパンション・ボードの名称が表示されます。
fig.LCD
演 奏する前に
2
に「---------------」と表示さ
れた場合は、ウェーブ・エ
クスパンション・ボードが
正しく認識されていない可
能性があります。
SRX A スロットにウェーブ・エクスパンション・ボード SRX-02
Concert Pianoを取り付けた場合の表示例です。
ボタンを離すと元の画面に戻ります。
17
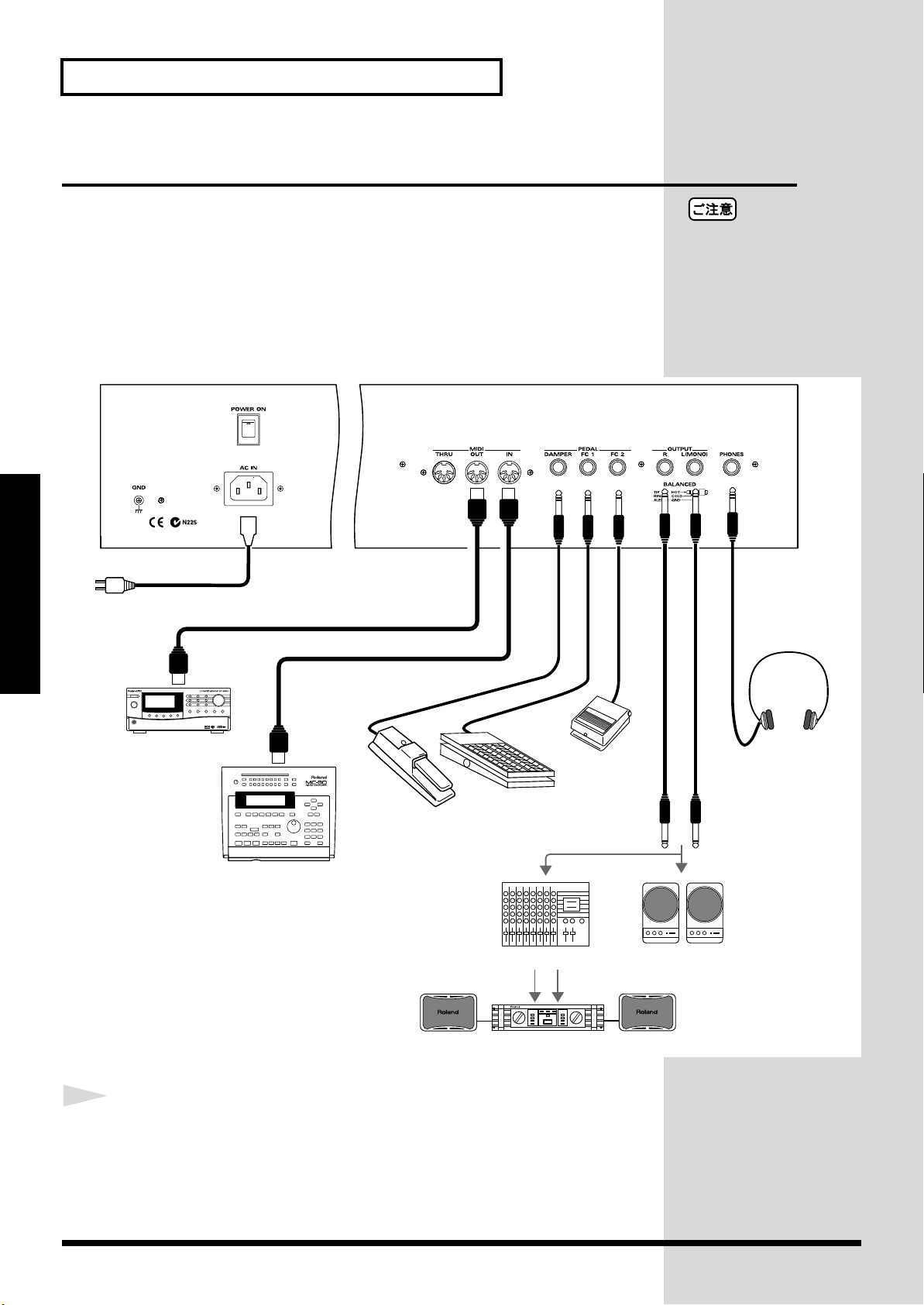
外部機器と接続する
他の機器と接続するときは、
ステレオ・
ヘッドホン
モニター・スピーカー
(アンプ内蔵)
パワー・アンプ
ミキサーなど
MIDIIN
MIDI音源など
MIDIOUT
MIDIシーケンサーなど
電源コンセントへ
エクスプレッション・ペダル
(EV-5)または
ペダル・スイッチ
ペダル・
スイッチ
(DP-2、DP-6
など)
Roland
演 奏する前に
演奏する前に
RD-700 は、アンプやスピーカーを内蔵していません。音を出すにはモニ
ター・スピーカーやステレオ・セットなどのオーディオ機器、または、
ヘッドホンなどをご用意ください。
※ オーディオ・ケーブル、MIDI ケーブル、ヘッドホン、エクスプレッショ
ン・ペダルは付属していません。ご購入の際は、本機をお求めになった販
売店にお問い合わせください。
fig.00-05.j
誤動作やスピーカなどの破
損を防ぐため、必ずすべて
の機器の音量を絞った状態
で電源を切ってください。
1
接続をはじめる前に、次のことを確認します。
本体および接続するアンプなどの音量が最小になっていますか?
18
本体および接続するアンプなどの電源がオフになっていますか?
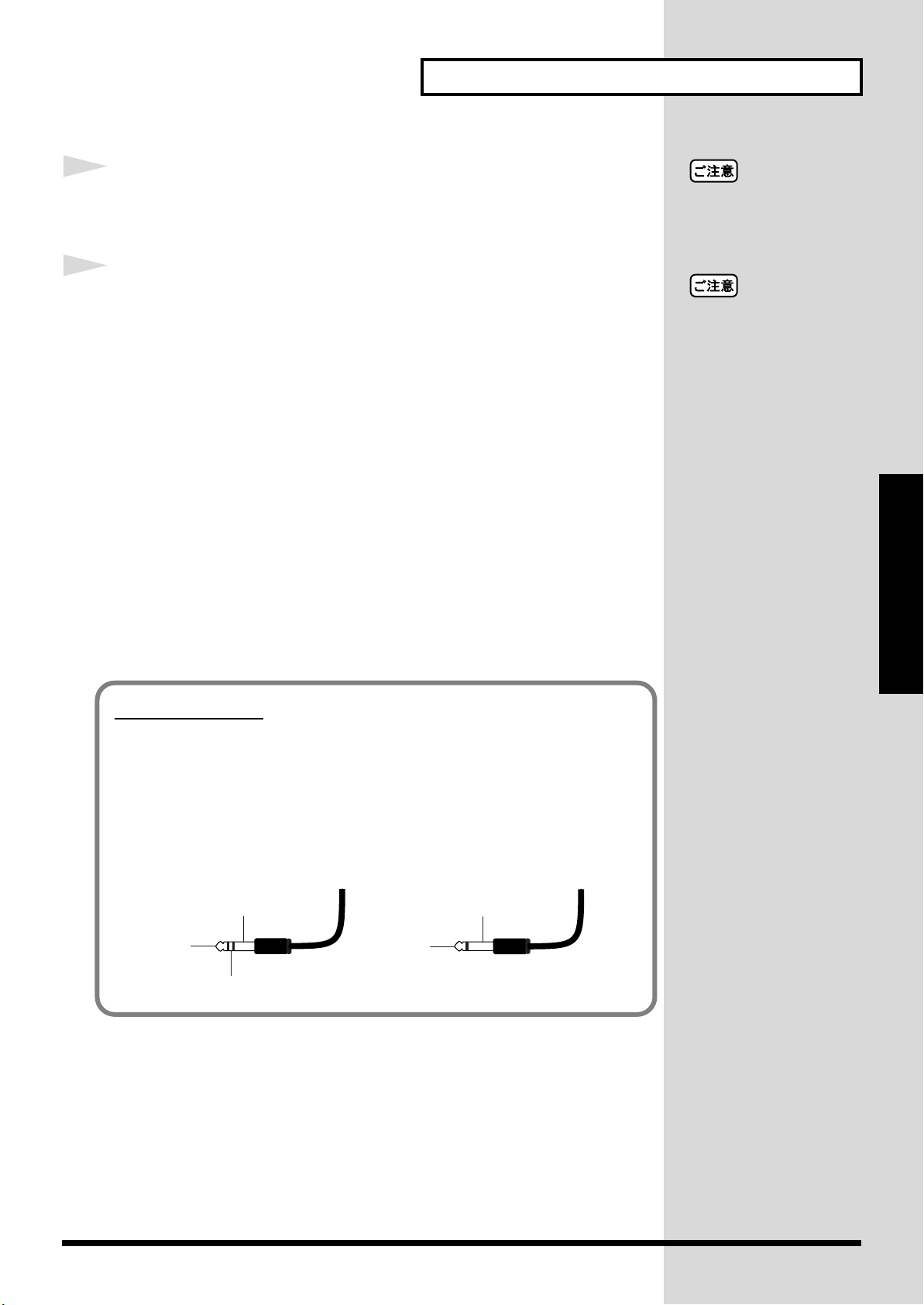
2
ヘッドホンはステレオ・タイ
エクスプレッション・ペダ
売
出力端子について
RD-700 の出力端子は、バランス出力とアンバランス出力のどちらでも使
fig.TRS
演奏する前に
付属の AC コードを本体につなぎ、電源コンセントに差し込み
ます。
3
RD-700 と外部機器を接続します。
アンプやスピーカーなどのオーディオ機器を接続するには、オーディオ・
ケーブルを使います。MIDI 機器は MIDI ケーブルを使って接続します。
ヘッドホンを使う場合は、PHONES ジャックにプラグを差し込みます。
また必要に応じて、ペダル・スイッチ、エクスプレッション・ペダルも接
続します。
ペダルの接続
付属のペダルを、PEDAL 端子のいずれかに接続します。
DAMPER 端子に接続すると、ダンパー・ペダルとして使用することがで
きます。
FC1 または FC2 端子に接続すると、さまざまな機能を割り当てることが
できます(P.69)。
プのものをお使いください。
ルは、必ず指定のもの(別
:EV-5)をお使いくだ
さい。他社製品を接続する
と、本体の故障の原因にな
る場合があります。
演 奏する前に
用することができます。
バランス出力時には、バランス・タイプ(TRS タイプ)の標準プラグを
持つケーブルを、アンバランス出力時には、アンバランス・タイプ(TS
タイプ)の標準プラグを持つケーブルを使用してください。
TRS TS
TIP (Hot)
SLEEVE (Ground)
RING (Cold)
SLEEVE (Ground)
TIP (Hot)
19
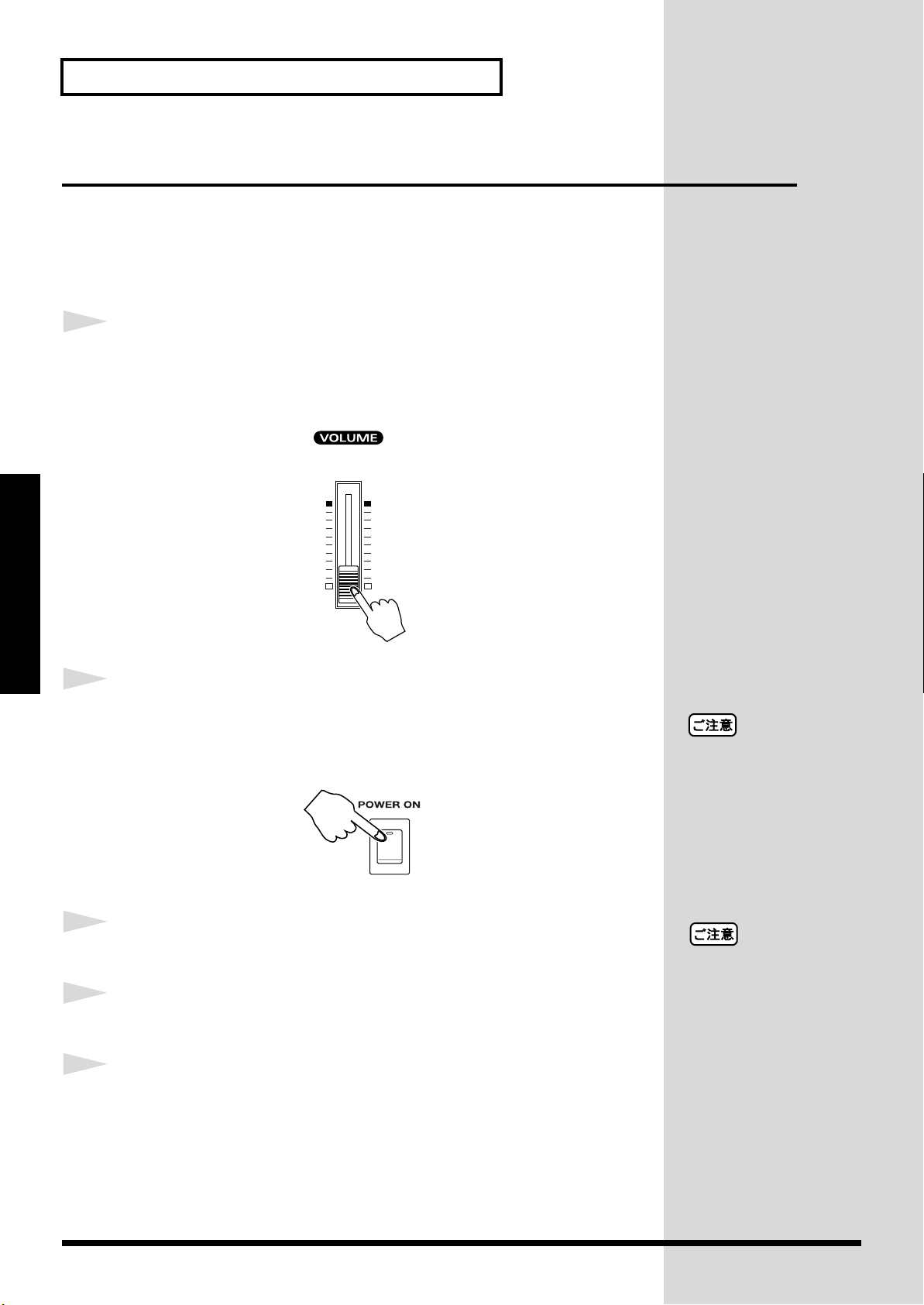
電源を入れる/切る
ピッチ・ベンド・レバー
この機器は回路保護のた
電源を入れる
演 奏する前に
演奏する前に
正しく接続したら、必ず次の手順で電源を投入してください。手順を間違
えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損する恐れがあります。
1
電源を入れる前に、VOLUME スライダーで、音量を最小にし
ます。
接続している外部オーディオ機器などの音量も最小にしてください。
fig.00-06
2
3
4
5
RD-700 の背面にある[POWER]スイッチの ON 側(上部)
を押します。
電源が入り、ディスプレイが点灯します。
fig.00-07
接続している外部機器の電源を入れます。
接続している外部機器の音量を調節します。
RD-700 の音量を適当な音量に調節します。
(P.44)操作時の誤動作を
防ぐため、電源投入時には
ピッチ・ベンド・レバーに
触れないようにしてくださ
い。
め、電源をオンしてからし
ばらくは動作しません。
20
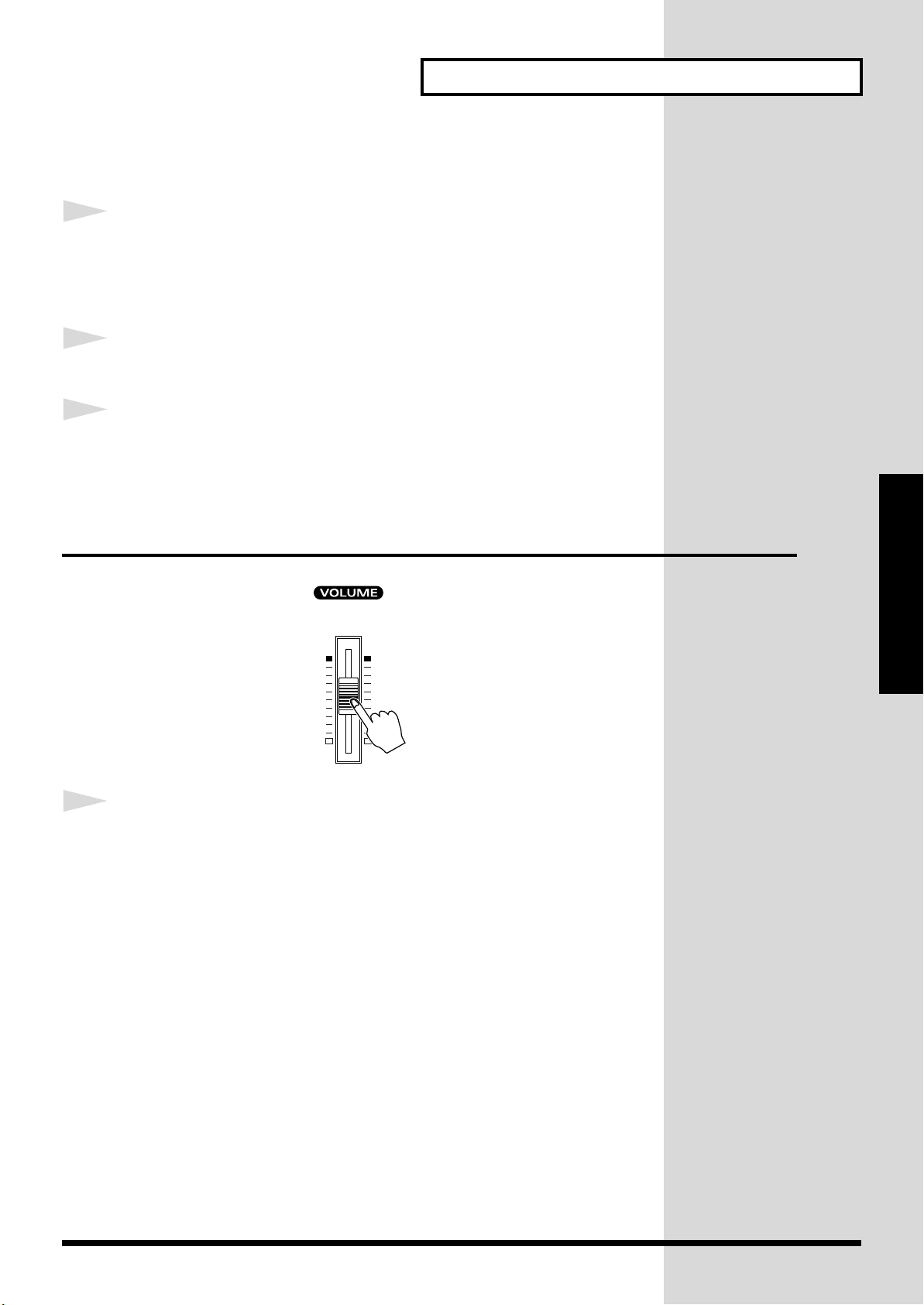
電源を切る
1
電源を切る前に、VOLUME スライダーで、音量を最小にしま
す。
接続している外部オーディオ機器などの音量も最小にしてください。
2
接続している外部機器の電源を切ります。
3
RD-700 の背面にある[POWER]スイッチを押します。
電源が切れます。
演奏する前に
音量を調節する
fig.00-08
1
VOLUME スライダーで音量を調節します。
上に動かすと音が大きくなり、下に動かすと音が小さくなります。
接続している機器も適当な音量に調節してください。
演 奏する前に
21
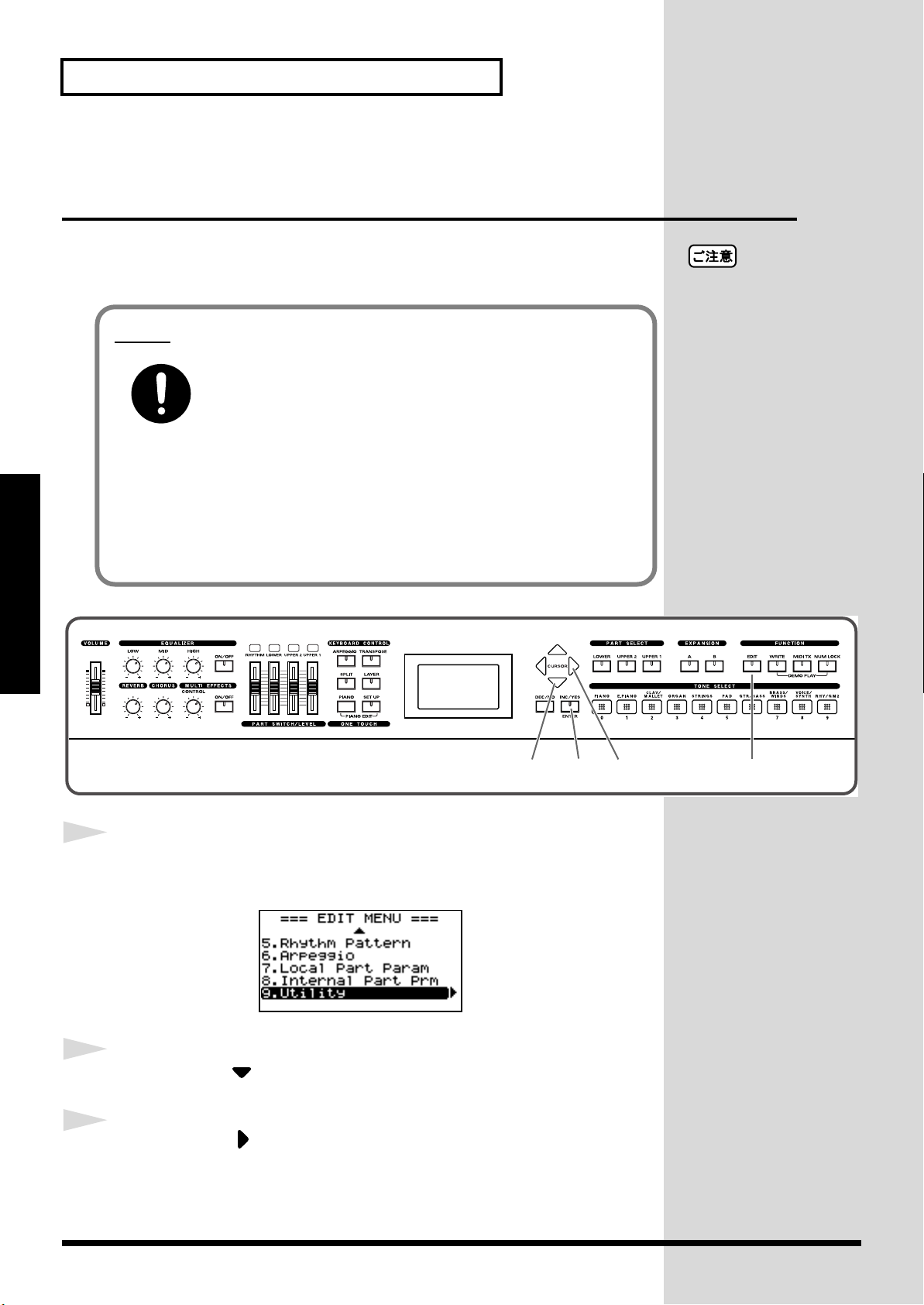
演奏する前に
この操作を行うと、セット
ご注意
fig.(!)(!マーク)
ファクトリー・リセット中(「Now, Executing」表示中)は、
12,4 6,7 3,5
工場出荷時の設定に戻す
(ファクトリー・リセット)
RD-700 をはじめてお使いになるときは、取扱説明書の手順にそって正し
く動作させるために、最初に工場出荷時の設定に戻してください。
絶対に電源を切らないでください。
ファクトリー・リセット中に電源を切ると、本体内のデータが破壊された
り電源が入らなくなる場合があります。本体内のデータが失われているな
どの症状が確認された場合には、お買い上げ店またはローランド・サービ
演 奏する前に
スにご相談ください。ただし、失われた記録内容の修復に関しましては、
補償も含めご容赦願います。
アップ(P.50)の設定が失
われます。記憶させた内容
を残しておきたい場合は、
「バルク・ダンプ(Bulk
Dump SETUP)」で外部
シーケンサーに保存してく
ださい(P.88)。
fig.panel
1
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
2
CURSOR[ ]を押して「9.Utility」を選びます。
3
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。
22
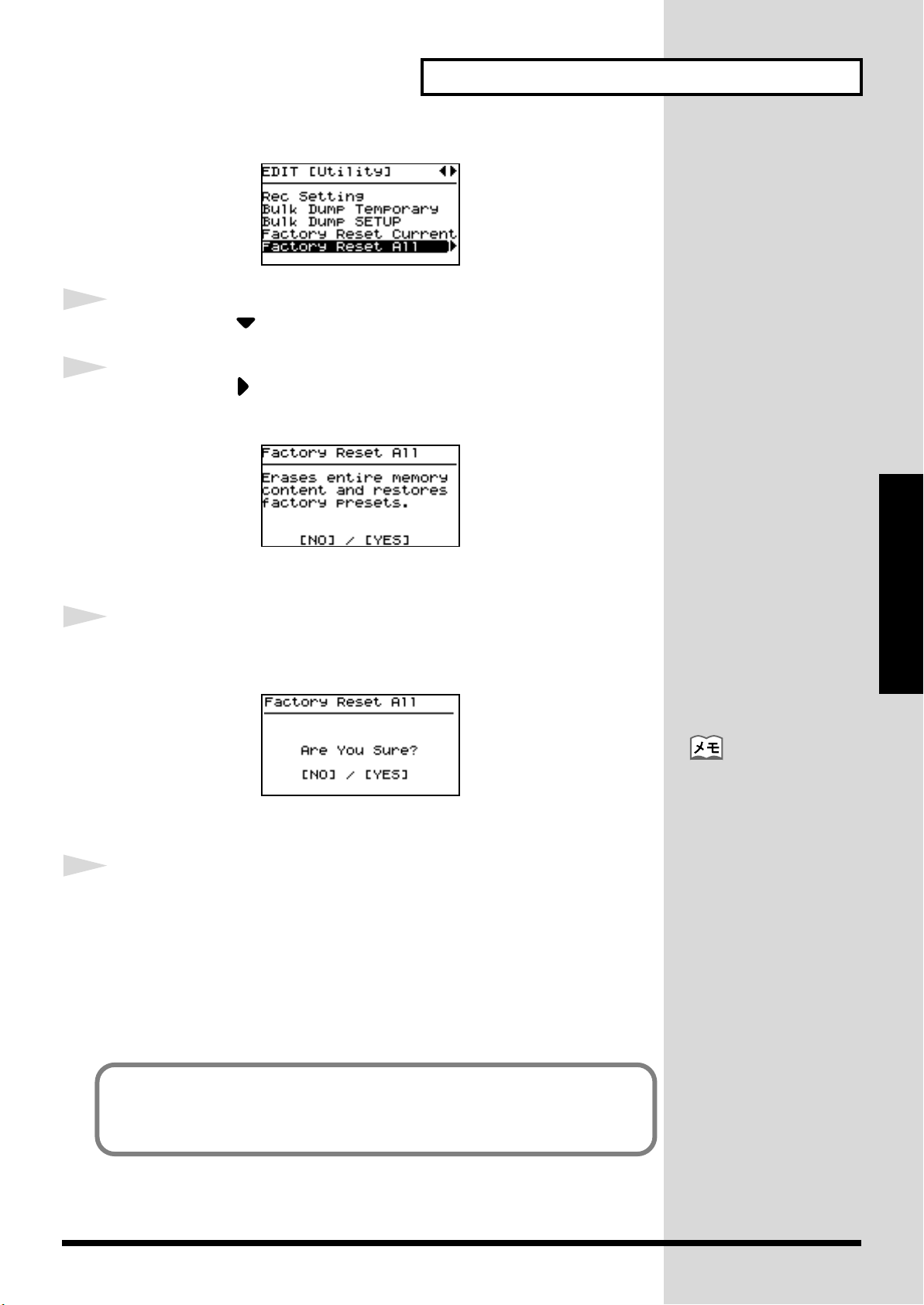
4
設定を工場出荷時の状態に戻す (ファクトリー・リセット)
(P.90)
をご覧ください。
ファクトリー・リセットを
5
fig.utility1.eps150
CURSOR [ ]を押して、「Factory Reset All」を選びます。
CURSOR [ ]を押します。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD150
演奏する前に
6
7
ファクトリー・リセットを中止するときは、[DEC/NO]を押します。
[INC/YES]を押します。
確認のメッセージが表示されます。
fig.LCD150
ファクトリー・リセットを中止するときは、[DEC/NO]を押します。
もう一度[INC/YES]を押すと、ファクトリー・リセットが
実行されます。
実行中は「Now, Executing...」と表示されます。
ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに「COMPLETED」
と表示され、トーン画面に戻ります。
演 奏する前に
行うと、見る角度によって
は画面が見にくくなる場合
があります。その場合は、
表示の濃さを調節してくだ
さい(P.24)。
選んだセットアップ(P.50)だけを工場出荷時の設定に戻すこともできま
す。
23
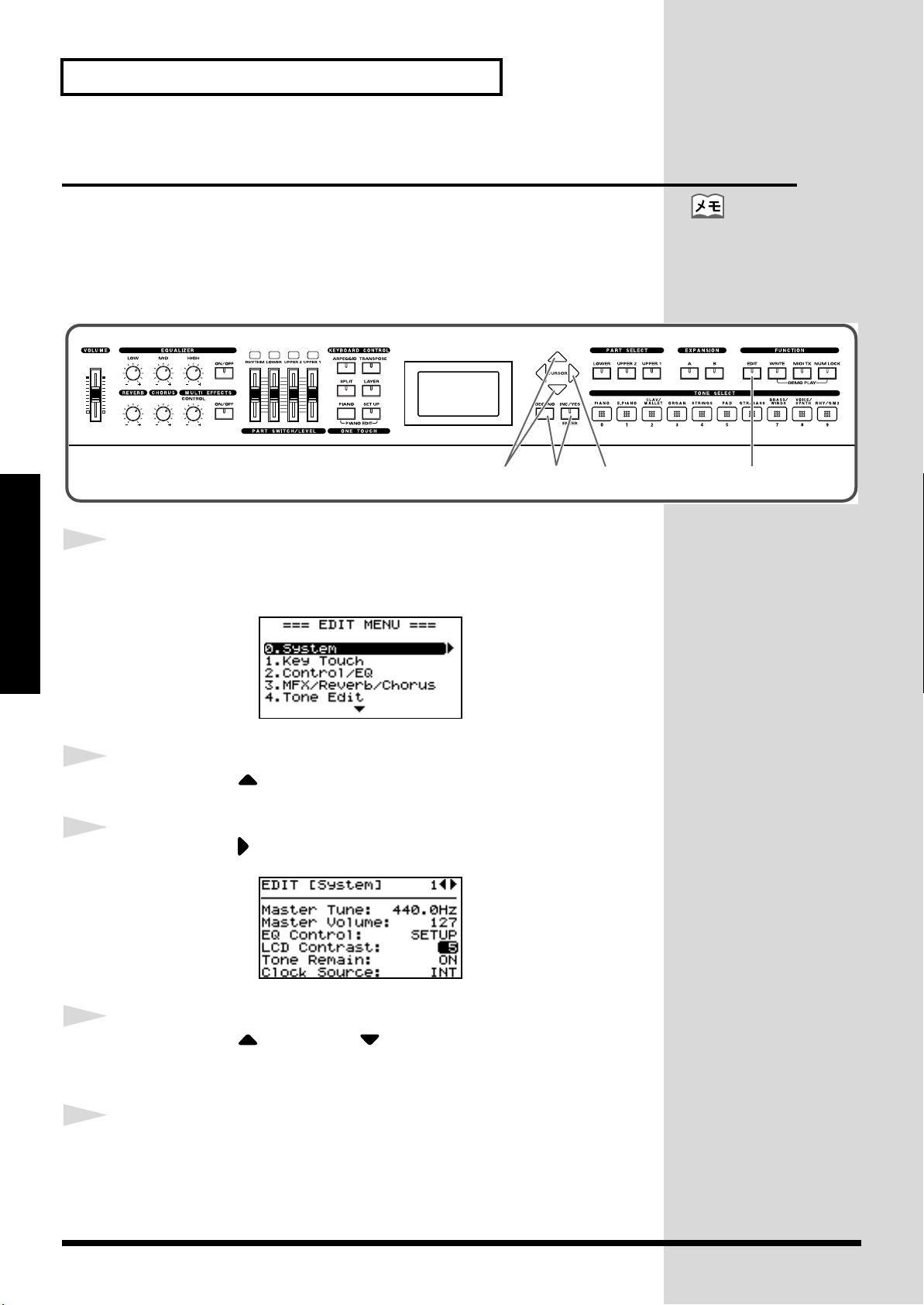
表示の濃さを調節する(LCD コントラスト)
LCD コントラストは、RD-
演 奏する前に
演奏する前に
電源を入れた直後や長時間使用した後、または設置条件などによって、
ディスプレイの文字が見づらくなることがあります。このようなときは、
以下の手順で表示の濃さを調節してください。
fig.panel
1
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
700 全体(システム)の設
定です。電源を切っても、
設定は記憶されています。
1,62,4 5 3
2
3
4
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
CURSOR [ ]を押して「0.System」を選びます。
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。
fig.system1.eps150
CURSOR [ ]または[ ]を押して、「LCD Contrast」
のパラメーターにカーソルを移動します。
5
[INC/YES]または[DEC/NO]を押して値(1 〜 10)を設定
します。
値が変わると、ディスプレイの濃さが変わります。見やすい濃さに調節し
24
てください。
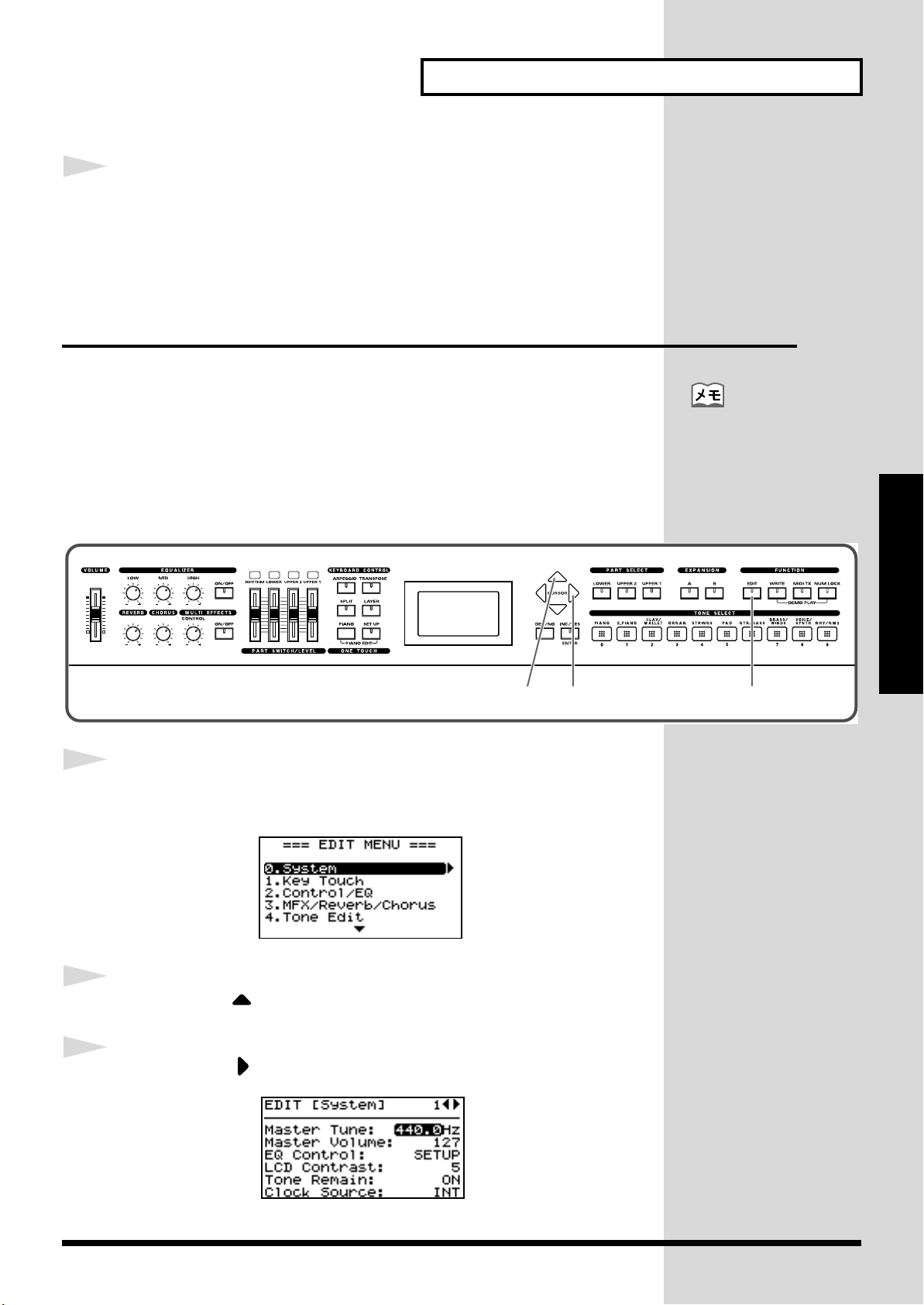
6
マスター・チューニング
12 3
[EDIT]を押して、インジケーターを消灯させます。
トーン画面に戻ります。
他の楽器と音の高さを合わせる
(マスター・チューニング)
他の楽器と一緒に演奏するときには、きれいな演奏にするために基準とな
る音の高さを合わせておきます。一般には、中央の A(中央のラ)の音の
高さが何ヘルツ(Hz)かを基準にして、他の楽器と音の高さを合わせま
す。
他の楽器と基準となる音の高さを合わせることを、「チューニング」とい
います。
演奏する前に
は、RD-700 全体(システ
ム)の設定です。電源を
切っても、設定は記憶され
ています。
1
fig.panel
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
演 奏する前に
2
CURSOR[ ]を押して「0.System」を選びます。
3
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。
fig.system1.eps150
25
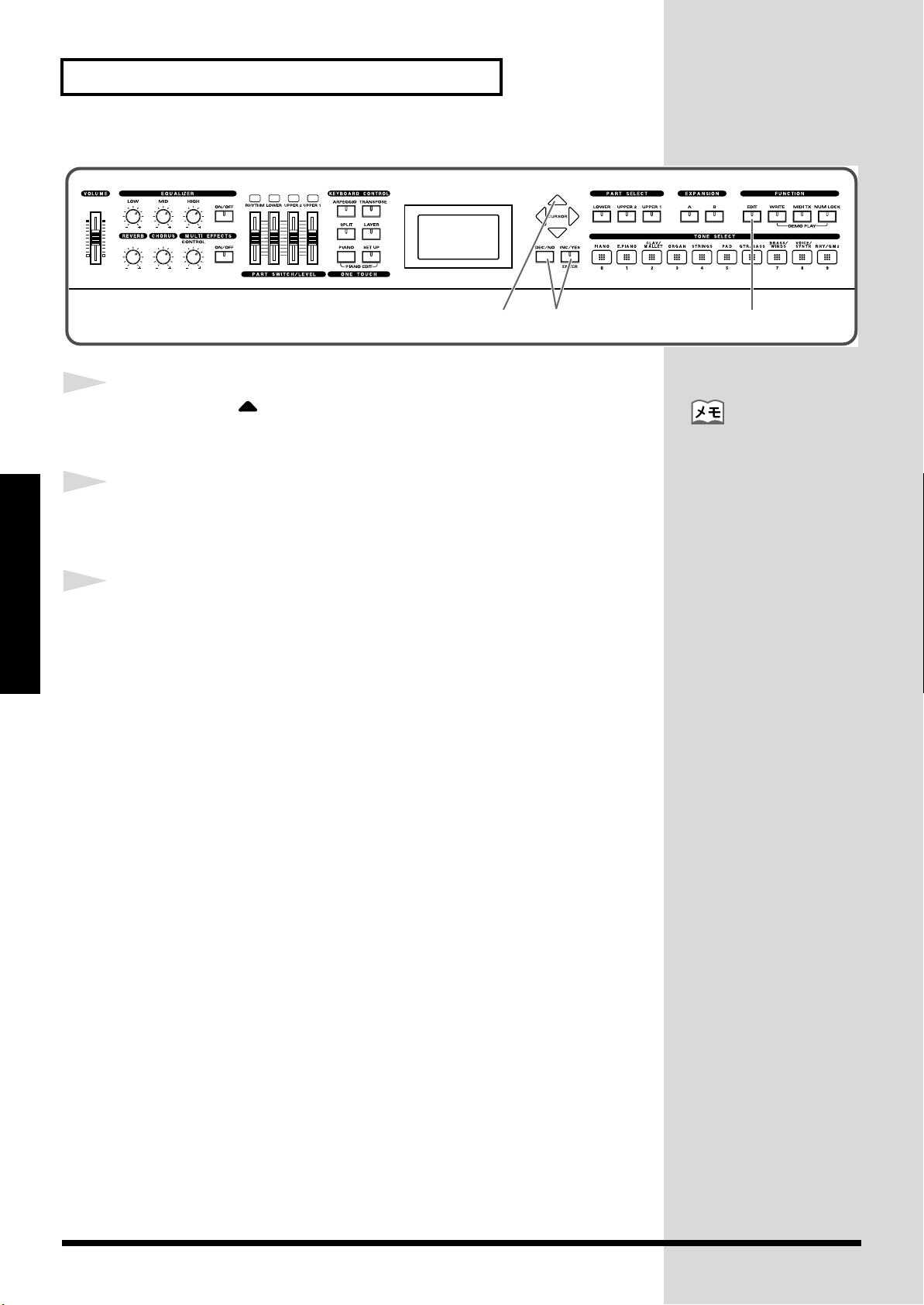
演奏する前に
値を速く大きくしたいとき
fig.panel
4
CURSOR [ ]を押して、「Master Tune」のパラメー
645
演 奏する前に
5
6
ターにカーソルを移動します。
[INC/YES]または[DEC/NO]を押して値(415.3〜 440.0
〜 466.2)を設定します。
[EDIT]を押して、インジケーターを消灯させます。
トーン画面に戻ります。
は、[INC/YES]を押しな
がら[DEC/NO]を押しま
す。逆に、[DEC/NO]を
押しながら[INC/YES]を
押すと、値が速く小さくな
ります。
26
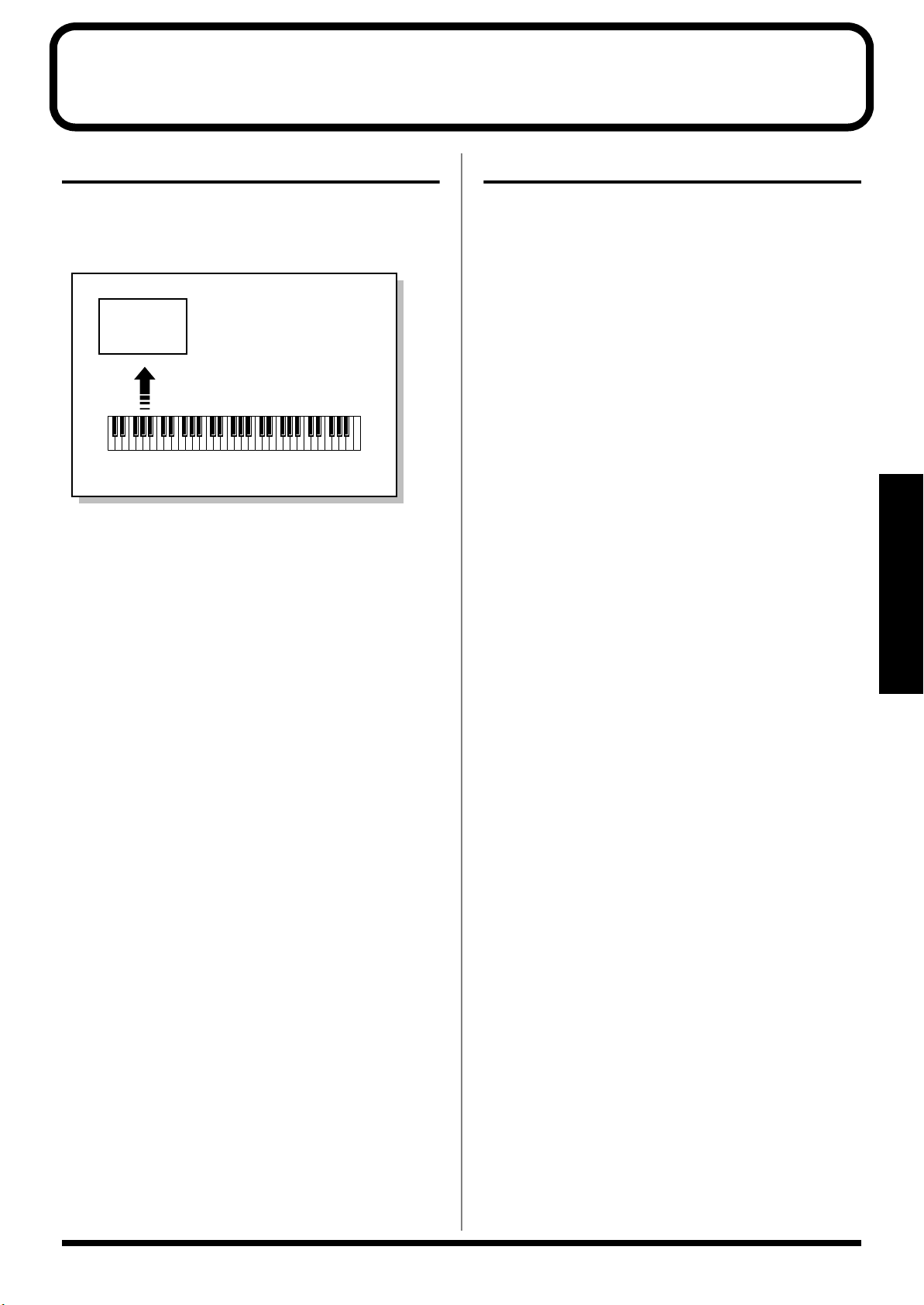
RD-700 の概要
RD-700 の基本構成
RD-700 は大きく分けて、鍵盤コントローラー部と音源部で
構成されており、これらの間は MIDI で内部接続されていま
す。
fig.R01-01(XV-88 P.19 の図)
音源部
演奏
鍵盤コントローラー部
(鍵盤、ピッチ・ベンド・レバーなどのコントローラー)
鍵盤コントローラー部
鍵盤、ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー、パネル
上のつまみ、およびリア・パネルに接続したペダルなどが含
まれます。キーを押す/離す、ホールド・ペダルを踏むなど
の演奏情報を MIDI メッセージに変換して、音源部や外部
MIDI 機器に送信します。
音の単位
RD-700 を使う場合、いくつかの音の単位があります。ここ
では、それぞれの音の単位について簡単に説明します。
トーン
RD-700 では、演奏に使う 1 つの音色を「トーン」と呼びま
す。RD-700 には 468 個のトーンが記憶されています。
トーンは、パートに割り当てて鳴らします。
また、トーンの中には、複数の打楽器音を集めた「リズム・
セット」も含まれます。リズム・セットでは、押さえる鍵盤
(ノート・ナンバー)によって異なった打楽器音が鳴るよう
になっています。
パート
1 台で複数の音色を鳴らすことのできる音源のことを「マル
チティンバー音源」といいます。RD-700 は 16 種類の音色
を同時に鳴らすことができるマルチティンバー音源です。
「パート」とは、RD-700 をマルチティンバー音源として使
うときのトーンを割り当てるところです。16 個のパートに
は、それぞれ異なるトーンを割り当ててコントロールするこ
とができるので、複数のトーンを重ねて鳴らしたり(レイ
ヤー)、鍵域を分割し別々のトーンで鳴らしたり(スプリッ
ト)、アンサンブル演奏を楽しむことができます。
R D-700の概要
音源部
音を発生させる部分です。鍵盤コントローラー部や外部
MIDI 機器からの MIDI メッセージを楽音信号に変換して、
OUTPUT ジャックや PHONES ジャックからアナログ信号
として出力します。
RD-700 では、内部音源を鳴らす 16 個のパートのことを、
「内部パート(Internal Part)」といいます。
ローカル(Local)・パートと MIDI TX
パート
RD-700 は、内部パートを本体のボタンと鍵盤で自由にコン
トロールするための 3 つのパート(UPPER1、UPPER2、
LOWER)を持っています。内部パートをコントロールする
この 3 つのパートをまとめて「ローカル(Local)パート」
といいます。16 個の内部パートのうち 3 つを各ローカル・
パートに割り当ててコントロールします(RHYTHM パート
はパート 10 に固定です)。
また、RD-700 では、外部 MIDI 音源をローカル・パートと
同じ感覚で自由にコントロールすることができます。外部
MIDI 音源も 3 つのパート(UPPER1、UPPER2、LOWER)
でコントロールでき、この 3 つのパートをまとめて「MIDI
TX パート」といいます。外部 MIDI 音源をこの 3 つの MIDI
TX パートに割り当ててコントロールします(RHYTHM
パートについても一部設定できます)。
27
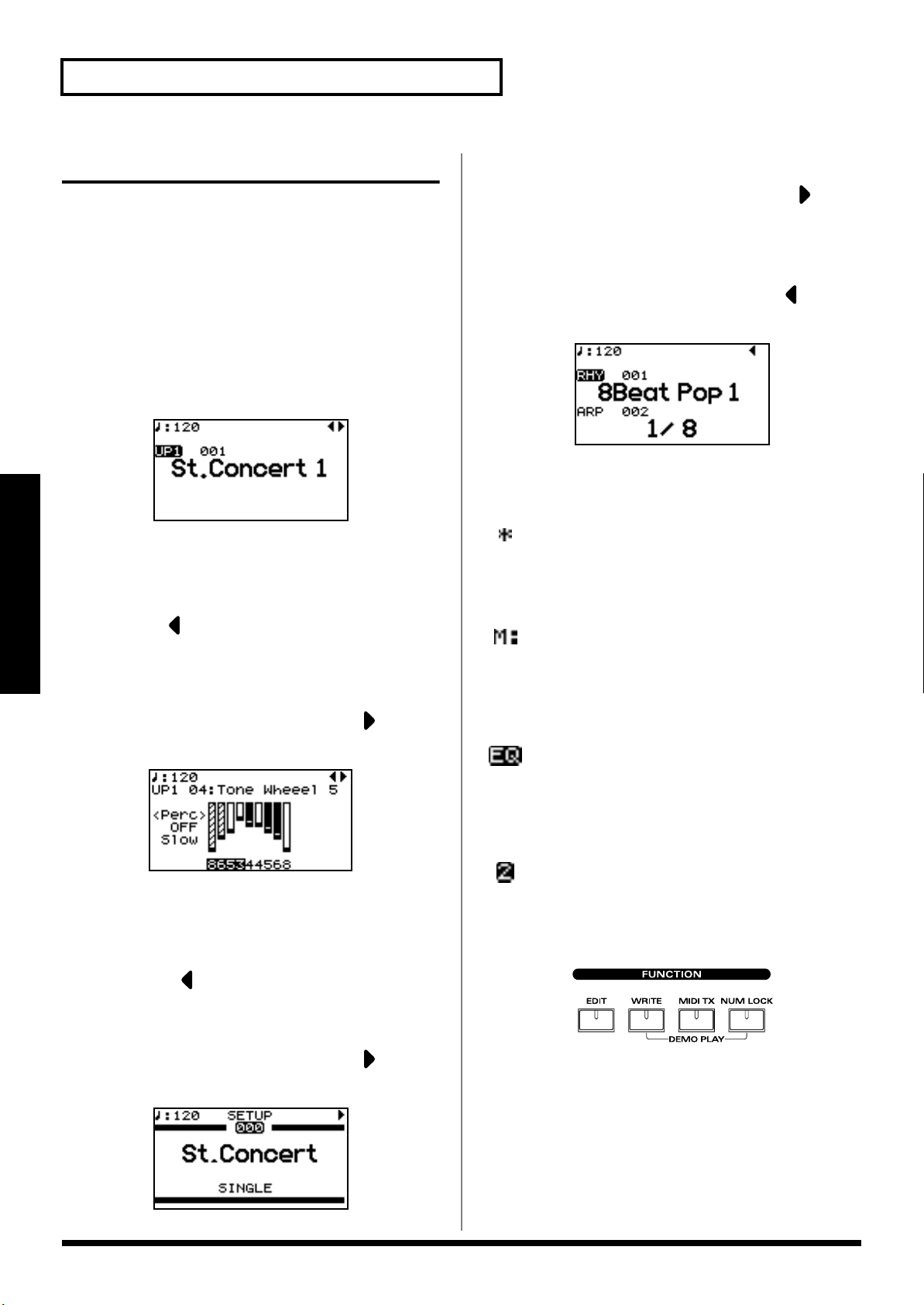
RD-700 の概要
RD-700 の基本操作
主な画面
トーン画面(基本画面)
現在ローカル・パートに選んでいるトーン名が表示されま
す。通常は、トーン画面が表示されます。
ONE TOUCH [PIANO]ボタンを押すと、RD-700 はピアノ
演奏に最適な状態になり、トーン画面を表示します(P.31)。
ローカル・パートの UPPER1、UPPER2、LOWER のトー
ンやテンポを変えることができます。
fig.LCD
R D-700の概要
トーン・ホイール画面
トーン画面で、ローカル・パートのいずれかのパートに、
ORGAN 音色の「Tone Wheel 1 〜 10」のいずれかを選択
リズム/アルペジオ画面
トーン画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押
すとこの画面になります。
リズム・パターン、アルペジオ・パターン、テンポを変える
ことができます。
この画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押す
と、トーン画面に戻ります。
fig.LCD
特殊な表示
セットアップ(P.50)の内容を変更すると、テンポ
表示の右側にこのマークが表示されます。
変更した内容を消したくないときは、新しいセット
アップとして記憶してください(P.52)。
し、CURSOR[ ]を押すとこの画面が表示されます。こ
の画面が表示されている状態を「トーン・ホイール・モー
ド」といい、オルガンのハーモニック・バーを使った音作り
をシミュレートすることができます(P.71)。
この画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押す
と、トーン画面に戻ります。
fig.LCD
セットアップ画面
現在選んでいるセットアップ(P.50)が表示されます。
トーン画面またはトーン・ホイール画面が表示されていると
きに、CURSOR[ ]を押すとこの画面になります。また、
[SETUP]ボタンを押しても、この画面が表示されます。
セットアップを変えることができます。
この画面が表示されているときに、CURSOR[ ]を押す
と、トーン画面またはトーン・ホイール画面に戻ります。
fig.LCD
クロック・ソースの設定(P.66)を「MIDI」にして
いるときは、画面左上のテンポ表示の音符が「M:」
マークに変わります。このマークが表示されている
ときは、外部 MIDI 機器で RD-700 のテンポを設定
することができます。
EQ Control の設定(P.66)を、「SYSTEM」にして
いるときは、画面右上に「EQ」マークが表示されま
す。このマークが表示されているときは、セット
アップを切り替えてもイコライザーの設定は変わり
ません。
Rhythm Type の設定(P.78)を「2」にしていると
きは、画面右上に「2」マークが表示されます。
ファンクション・ボタンの働き
fig. ボタン
[EDIT]
[EDIT]を押してボタンのインジケーターを点灯させると、
エディット・モードになります。エディット・モードでは、
さまざまな機能の詳細設定をすることができます。
28
[EDIT]を押して、ボタンのインジケーターを消灯させる
と、エディット・モードを抜けます。エディット・モードを
抜けると、[EDIT]ボタンのインジケーターは消灯します。
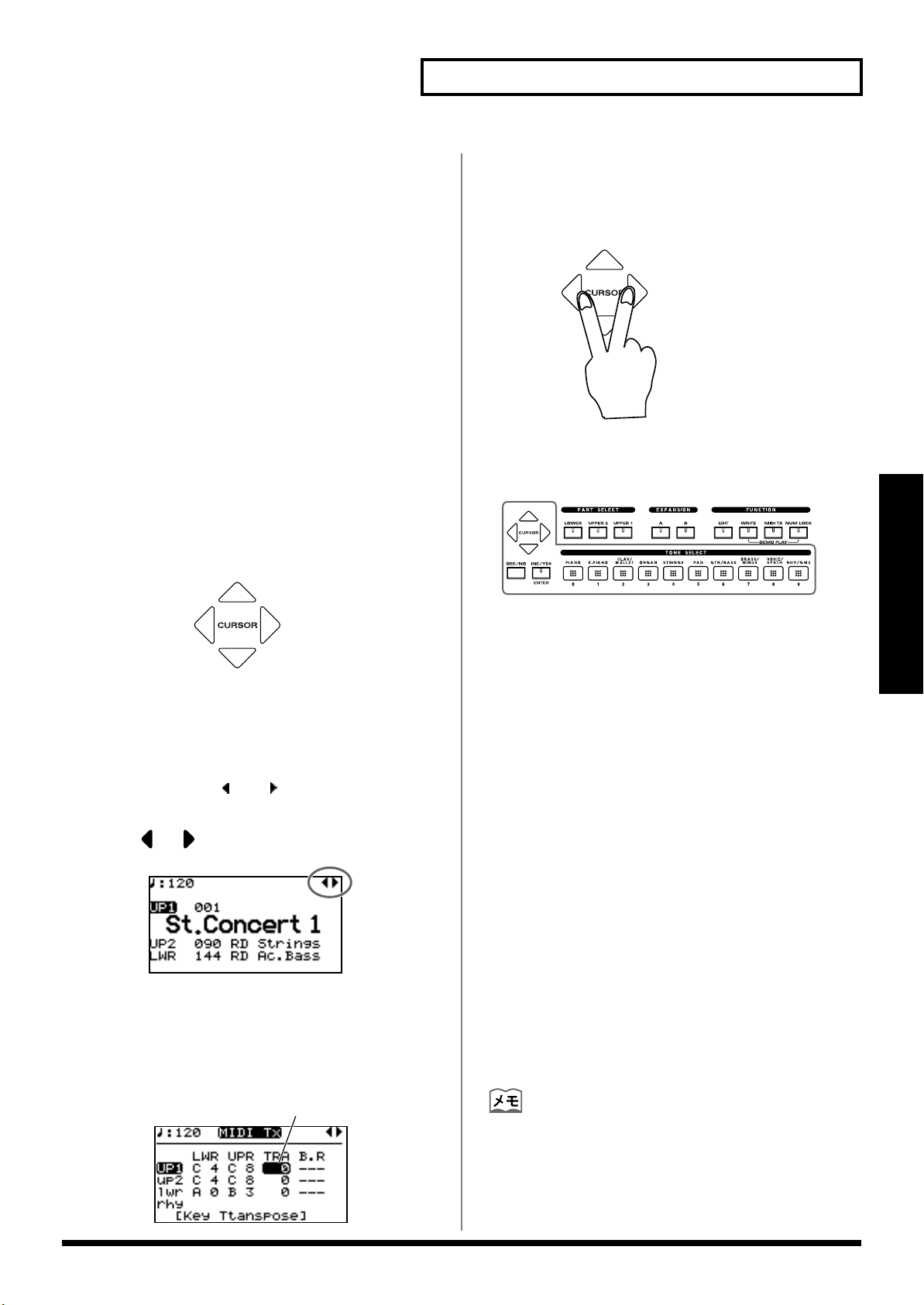
RD-700 の概要
[WRITE]
現在の設定をセットアップに記憶させます。
[MIDI TX]
[MIDI TX]を押してボタンのインジケーターを点灯させる
と、RD-700 で外部 MIDI 音源をコントロールする状態にな
ります。RD-700 のボタンでローカル・パートをコントロー
ルするか([MIDI TX]がオフ)、MIDI TX パートをコント
ロールするか([MIDI TX]がオン)を切り替えることにな
ります。
また、外部音源に送信する MIDI 情報の詳細設定をすること
ができます。
[NUM LOCK]
[NUM LOCK]を押してボタンのインジケーターを点灯させ
ると、TONE SELECT ボタンで数値を入力することができ
ます。設定する項目によっては自動的にボタンのインジケー
ターが点灯します。
カーソル・ボタンの働き
fig. ボタン
また、MIDI TX 画面のように、複数の設定項目が横に並んで
いるとき、動かしたい方向の CURSOR ボタンを押しなが
ら、逆方向の CURSOR ボタンを押すと、カーソルを速く移
動することができます。
fig. 画面 + カーソル
動かしたい方向を押し
ながら、逆方向を押す
と、カーソルが速く移動
設定値の変更
fig. ボタン
カーソル・ボタンは画面の切り替えや、設定を変更したい項
目の移動(カーソルの移動)に使います。
画面の切り替え
画面の右上に矢印記号(「 」や「 」)が表示されているとき
は、矢印方向に画面があること示しています。
CORSOR[ ][ ]で画面を切り替えます。
fig.LCD
設定項目(カーソル)の移動
1 つの画面に複数の項目が表示されている場合、設定を変更
したい項目名や値が黒枠で囲まれます。この黒枠を「カーソ
ル」といい、CURSOR ボタンで移動します。
fig.LCD(トーン画面とエディット画面でのカーソル)
カーソル
設定値を変更するときは、[DEC/NO]、[INC/YES]や、
TONE SELECT ボタン(テン・キー)を使います。
[DEC/NO]、[INC/YES]
値を大きくするときは[INC/YES]を押し、小さくすると
きは[DEC/NO]を押します。連続して大きく(または小さ
く)するときはボタンを押し続けます。値を速く大きくした
いときは、[INC/YES]を押しながら[DEC/NO]を押しま
す。逆に、[DEC/NO]を押しながら[INC/YES]を押す
と、値が速く小さくなります。
TONE SELECT ボタン(テン・キー)
[NUM LOCK]をオン(点灯)にすると、TONE SELECT ボ
タンを[0]〜[9]のテン・キーにして、数値を直接指定
します。数値を指定すると値が点滅します。点滅している状
態では値が確定されていないので、[ENTER]を押して確定
させます。
設定する項目によっては、自動的に[NUM LOCK]がオン
になり、TONE SELECT ボタンで数値を入力することがで
きます。
テン・キーで入力できるのは、数値のみです。
数値の正(+)/負(ー)の切り替えは、[INC/YES]また
は[DEC/NO]を押して、連続的に数値を変化させておこな
います。
R D-700の概要
29
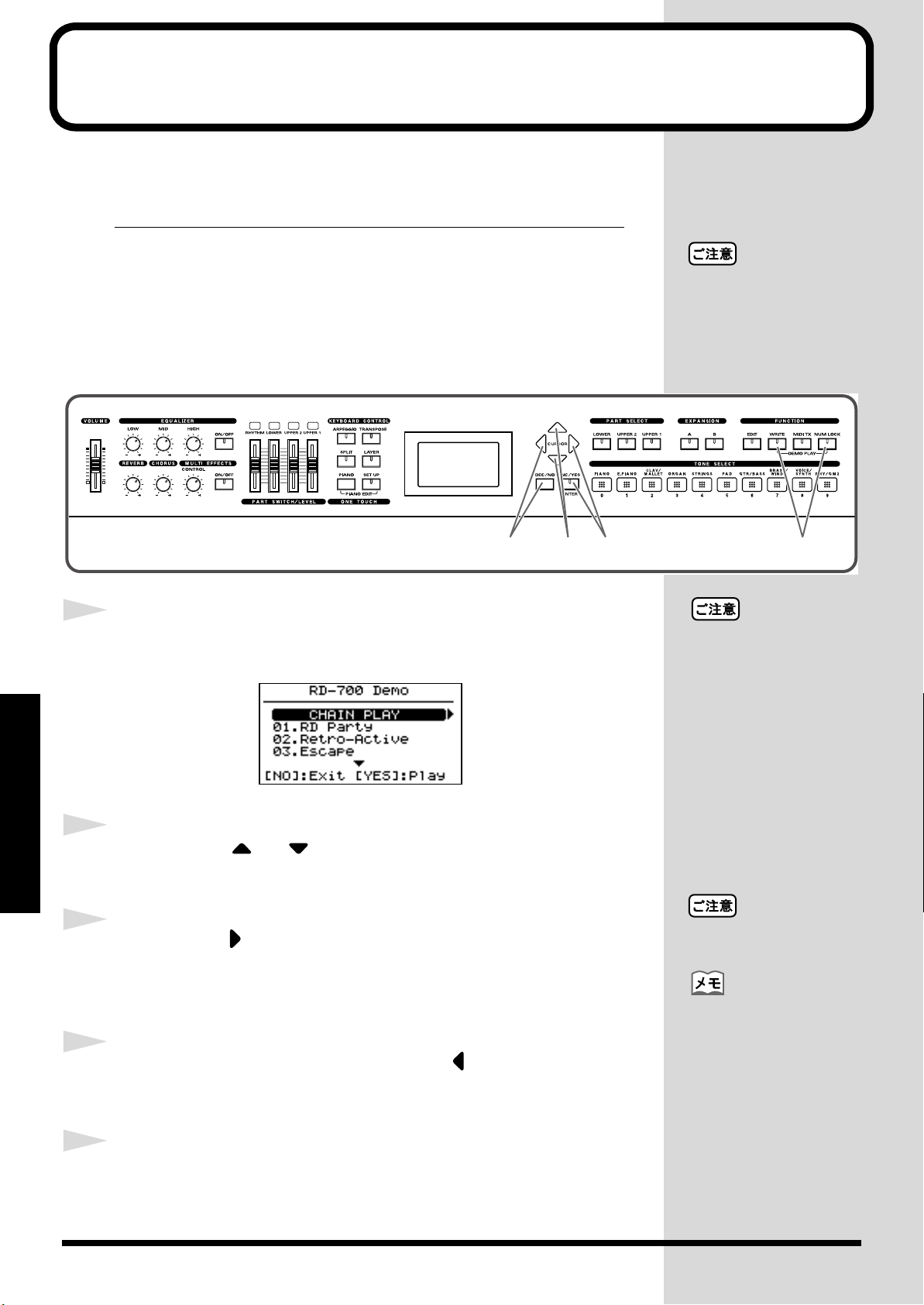
デモ曲を聴いてみよう(DEMO PLAY)
これらのデモ曲を個人で楽
デモ曲の再生中は、鍵盤を
デモ曲の演奏データは、
MIDI OUT 端子からは出力
されません。
ONE TOUCH [PIANO]
デモ曲を聴いてみましょう。
RD-700 には、特長を活かしたデモ曲が内蔵されています。
No. ソング・ネーム 作曲者/コピーライト
01. RD Party Scott Wilkie © 2001 Roland Corporation
02. Retro-Active Igor Len © 2001 Roland Corporation
03. Escape Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation
04. High-End Speak Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation
05. No me digas Scott Tibbs © 2001 Roland Corporation
06. Pastorale Igor Len © 2001 Roland Corporation
fig.panel
しむ以外に権利者の許諾な
く使用することは、法律で
禁じられています。
1
[NUM LOCK]を押しながら[WRITE]を押します。
デモ画面が表示されます。
fig.LCD
デモ曲を聴いてみよう
2
CURSOR[ ][ ]を押して聴きたい曲を選びます。
CHAIN PLAY を選ぶと、すべての曲を繰り返し再生します。
3
CURSOR[ ]または[INC/YES]を押してデモ曲の再生を
始めます。
曲が最後まで再生されると、曲の先頭に戻って繰り返し再生します。
12 34,5
弾いても音は鳴りません。
4
曲を途中で止めるときは、CURSOR[ ]または、[DEC/
NO]を押します。
5
30
曲が止まっているときに、[DEC/NO]を押すとデモを終わり
ます。
元の画面に戻ります。
または[SETUP]を押す
と、曲が止まり、トーン画
面、またはセットアップ画
面が表示されます。

鍵盤で演奏しよう
ONE TOUCH [PIANO]
を押すと、ピアノ・エ
ディットの設定(P.62)を
除く各種設定は、電源投入
時の状態になります。
残しておきたい設定は、
セットアップに記憶してく
ださい(P.52)。
ピアノ音色の微調整(ピアノ・エディット)→ P.62
鍵盤のタッチ感の微調整→ P.67
ピアノ演奏をする(ONE TOUCH [PIANO])
ピアノ演奏をしてみましょう。
RD-700 では、ボタンひとつでいつでもピアノ演奏に最適な設定を呼び出
すことができます。
fig.panel
1
1
ONE TOUCH [PIANO]を押します。
fig.LCD
RD-700 は、鍵盤全体でピアノの音色を演奏する設定(シングル・モード
→ P.37)になります。
RD-700 では、お好みのピアノ演奏に合うようにより細かい設定すること
ができます。詳しくは各項目をご覧下さい。
•
•
鍵 盤で演奏しよう
31

鍵盤で演奏しよう
RD-700 に内蔵されている
「トーン
一覧」
(P.131)をご覧く
ださい。
レイヤー・モード(P.38)
やスプリット・モード
変えるときは、ONE
TOUCH[PIANO]ボタン
を押さずに、PART
SELECT ボタンでトーンを
変えるパートを選びます。
詳しくは
「レイヤーやスプ
リット・モードのトーンの
変えかた」
(P.40)をご覧
ください。
詳
「トーン一覧」
いろいろな音色(トーン)で演奏する
RD-700 には、468 種類の音が内蔵されています。
このひとつひとつの音のことを「トーン」といいます。
トーンは音の種類(カテゴリー)によって TONE SELECT ボタンに割り
当てられています。
いろいろなトーンを選んで演奏してみましょう。
fig.panel
132,4
トーンについては
1
ONE TOUCH [PIANO]を押します。
鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。
2
TONE SELECT ボタンのいずれかを押して、トーンの種類
鍵 盤で演奏しよう
(カテゴリー)を選びます。
3
[INC/YES]または[DEC/NO]でトーンを選びます。
選んでいるカテゴリーの TONE SELECT ボタンが点滅します。
4
点滅している TONE SELECT ボタンを押すか、鍵盤を弾きま
す。
TONE SELECT ボタンが点灯し、選んだトーンが確定します。
鍵盤を弾くと、選んだトーンが鳴ります。
次に同じ TONE SELECT ボタンを押すと、ここで選ばれたトーンが鳴り
ます。
ケーターが点灯していると
きは、TONE SELECT ボタ
ンでトーンのカテゴリーを
選ぶことはできません。詳
しくは、P.33 をご覧くだ
さい。
32
トーンは、「リズム・セッ
ト」、「GM2 のリズムセッ
ト」、「GM2 トーン」の順
に登録されています。
しくは、

トーン・ナンバーを指定してトーンを選ぶ([NUM LOCK])
RD-700 に内蔵されている
「トー
ン一覧」
(P.131)をご覧
ください。
レイヤー・モード(P.38)
やスプリット・モード
変えるときは、ONE
TOUCH[PIANO]ボタン
を押さずに、PART
SELECT ボタンでトーンを
変えるパートを選びます。
詳しくは、
「レイヤーやス
プリット・モードのトーン
の変えかた」
(P.40)をご
覧ください。
トーンの一つ一つは、トーン・ナンバーという番号を持っています。
TONE SELECT ボタンで数字を入力し、トーン・ナンバーを指定して
トーンを選ぶこともできます。
TONE SELECT ボタンで数字を入力するときは、[NUM LOCK]をオンに
します。
fig.panel
143 2
鍵盤で演奏しよう
トーンについては、
1
2
3
4
ONE TOUCH [PIANO]を押します。
鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。
[NUM LOCK]を押して、インジケーターを点灯させます。
TONE SELECT ボタンで数字を入力できるようになります。
各ボタンで入力できる数値は、TONE SELECT ボタンの下に表記されて
います。
TONE SELECT ボタンでトーン・ナンバーを入力します。
画面のトーン名が点滅します。
鍵 盤で演奏しよう
[ENTER]を押します。
トーンが確定します。
鍵盤を弾くと、選んだトーンが鳴ります。
[NUM LOCK]をオフにすると、選んだトーンが含まれるカテゴリーの
TONE SELECT ボタンが点灯します。
33

鍵盤で演奏しよう
リズム・セットによって、
鍵
音
「リズム・セット一覧」
トーンは、「リズム・セッ
ト」、「GM2 のリズムセッ
ト」、「GM2 トーン」の順
に登録されています。
詳しくは、
「トーン一覧」
リズム・セットを鳴らす
TONE SELECT で選べる音色のなかに、さまざまな打楽器を集めたリズ
ム・セットがあります。リズム・セットを使って打楽器の演奏をしてみま
しょう。
fig.panel
1
ONE TOUCH [PIANO]を押します。
214
2
鍵 盤で演奏しよう
3
4
鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。
TONE SELECT [RHY/GM2]を押します。
このとき、[NUM LOCK]がオンになっていると、リズム・セットのカテ
ゴリーを選ぶことができません。[NUM LOCK]はオフにしてください。
押さえる鍵によっていろいろな打楽器音が鳴ります。
他のリズム・セットを選ぶときは、[INC/YES]または
[DEC/NO]を押します。
盤に割り当てられている
の組み合わせが異なりま
す。
34

ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンを選ぶ
ウェーブ・エクスパンショ
「ウェーブ・エクスパ
ンション・ボードの取り付
けかた」
(P.16)をご覧く
ださい。
ウェーブ・エクスパンショ
レイヤー・モード(P.38)
やスプリット・モード
変えるときは、ONE
TOUCH[PIANO]ボタン
を押さずに、PART
SELECT ボタンでトーンを
変えるパートを選びます。
詳しくは、
「レイヤーやス
プリット・モードのトーン
の変えかた」
(P.40)をご
覧ください。
RD-700 には、別売のウェーブ・エクスパンション・ボード(SRX シ
リーズ)を 2 枚まで取り付けることができます。
ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンを選ぶときは、次のように
操作します。
fig.panel
142 3
鍵盤で演奏しよう
ン・ボードの取り付けかた
は、
1
ONE TOUCH [PIANO]を押します。
鍵盤全体で 1 つのトーンで演奏する設定になります。
2
EXPANSION[A]または[B]を押して、インジケーターを
点灯させます。
fig.LCD
EXPANSION[A]または[B]をしばらく押し続けたときは、取り付け
たウェーブ・エクスパンション・ボードの名称が表示されます(P.17)。
3
[NUM LOCK]ボタンを押して、インジケーターを点灯させ
ます。
4
[INC/YES]/[DEC/NO]または TONE SELECT ボタンで
5
トーン・ナンバーを選びます。
TONE SELECT ボタンでトーン・ナンバーを入力したときは、[ENTER]
を押して、トーンを確定してください。
鍵盤を弾くと、選んだトーンが鳴ります。
鍵 盤で演奏しよう
ン・ボードの音色リストに
ついては、SRX シリーズ
取扱説明書の「Patch List」
と「Rhythm Set List」を
ご覧ください。
35

鍵盤で演奏しよう
[NUM LOCK]せずにトーンを選ぶ
エクスパンション・ボードのトーンを選ぶとき、[NUM LOCK]をオフに
したままトーンを選ぶこともできます。
1.
EXPANSION[A]または[B]を押して、インジケーターを点灯させ
ます。
2.
TONE SELECT ボタンでトーン・ナンバーを指定します。
ウェーブ・エクスパンション・ボードのトーンは次のように TONE
SELECT ボタンに割り当てられます。
fig.
3.
[DEC/NO]または[INC/YES]でトーンを選びます。
選んでいるトーン・ナンバーを含む TONE SELECT ボタンが点滅しま
す。
4.
点滅している TONE SELECT ボタンを押すか、鍵盤を弾きます。
TONE SELECT ボタンが点灯し、選んだトーンが確定します。
ウェーブ・
RD-700 でウェーブ・エクスパンション・ボードのリズム・セットを
トーン・
ナンバー
001
010
011
021
031
041
051
061
071
081
リズム・
:
:
:
:
:
:
:
020
030
040
050
060
070
:
080
:
090
091
100
101
セット
:
:
鍵 盤で演奏しよう
エクスパンション・ボードのリズム・セットのトーン・
ナンバー
選ぶとき、ウェーブ・エクスパンション・ボードのリズム・セット
は、パッチ(RD-700 ではトーンといいます)の後に配置されます。
そのため、RD-700 でウェーブ・エクスパンション・ボードのリズ
ム・セットをトーン・ナンバーで指定するときは、パッチ・リスト末
尾のパッチ・ナンバーに、リズム・セット・リストの鳴らしたいリズ
ム・セット・ナンバーを足した数がトーン・ナンバーになります。
36

鍵盤で 2 つのトーンを鳴らす
UPPER1
UPPER2
レイヤー・モード
スプリット・ポイント
UPPERLOWER
スプリット・モード
鍵盤で 1 つのトーンを鳴らすか、2 つのトーンを鳴らすか、などの鍵盤の
状態を「キー・モード」と呼びます。キー・モードには、次の 3 種類があ
ります。
● シングル: 全鍵で 1 つのトーンを鳴らします。
● スプリット: あるキー(スプリット・ポイント)を境に鍵盤の音域を
2 つに分け、右手と左手で違うトーンを鳴らします。
● レイヤー:2つのトーンを重ねて鳴らします。
また、レイヤ・モードで重なる 2 つのパートを UPPER1、UPPER2 とい
い、スプリット・モードで鍵盤右側で鳴るパートを UPPER、鍵盤左側で
鳴るパートを LOWER といいます。
シングル・モードのときは、UPPER1 が鍵盤全体で鳴ります。
各パートには、トーンが一つずつ割り当てられます。
fig.Q1-
鍵盤で演奏しよう
シングル・モードにするには
スプリットやレイヤーなど、2 つ以上のトーンで演奏している状態から、
全鍵で 1 つのトーンを演奏する状態(シングル・モード)にするには、次
の2つの方法があります。
・ONE TOUCH [PIANO]を押す
全鍵でピアノ音色を演奏する、ピアノ演奏に最適な状態になります。
ただし、ONE TOUCH [PIANO]を押すと、それまでの設定は無効に
なります。気に入った設定は ONE TOUCH [PIANO]を押す前にセッ
トアップ(P.52)に記憶してください。
・[LAYER]、[SPLIT]をオフ(インジケーターが消灯)にする
全鍵で UPPER1 のトーンで演奏する状態になります。
鍵 盤で演奏しよう
37

鍵盤で演奏しよう
2つ
※ この操作をするときは、[NUM LOCK]はオフにしてください。
2 つのトーンを重ねて演奏する([LAYER])
fig.panel
1,2
1
[LAYER]を押して、インジケーターを点灯させます。
PART SWITCH の[UPPER1]と[UPPER2]が点灯します。
鍵盤を弾いてみましょう。
fig.LCD(画面図説明入り)
UPPER1 と UPPER2 のトーンが重なって鳴ります。
2
鍵 盤で演奏しよう
もう一度[LAYER]を押すと、インジケーターが消灯し、レ
イヤーが解除されます。
のTONE SELECT ボタンを同時に押す(レイヤー・モード )
[LAYER]ボタンを押さなくても、2 つの TONE SELECT ボタンを同時
に押すことで、レイヤー・モードにすることができます。
例えば、ピアノの音とストリングスの音を重ねたいときは、[PIANO]と
[STRINGS]を同時に押します。
[LAYER]のインジケーターが、自動的に点灯し、鍵盤を弾くとピアノの
音とストリングスの音が重なって鳴ります。
このとき、先に押されたボタン(インジケーターが赤色に点灯)のトーン
が UPPER1、もう一方(インジケーターがオレンジ色に点灯)が
UPPER2 に割り当てられます。画面のパート名は UP1 と UP2 の両方が
反転し、両方のパートが選ばれている状態になります。
2つのTONE SELECT ボタンが選ばれているとき、TONE SELECT ボタ
ンのいずれかひとつを押すと、押したボタンのトーンが選ばれ、シング
ル・モードになります。
※ PART SELECT ボタンで[LOWER]が選ばれているときは、上記の操作をして
もレイヤー・モードにはなりません。
38

鍵盤を 2 つの音域に分けて別々のトーンで演奏する
「音
域の分かれる位置を変える
鍵盤で演奏しよう
([SPLIT])
鍵盤が右側と左側に分かれることを「スプリット」といい、鍵盤が分かれ
る位置を「スプリット・ポイント」と言います。スプリット・ポイントの
鍵は UPPER に含まれます。
スプリット・ポイントは、工場出荷時は「C4」に設定されています。
fig.panel
1
[SPLIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
PART SWITCH の[LOWER]が点灯します。
鍵盤を弾いてみましょう。
fig.LCD(画面図説明入り)
スプリット・ポイントは変
えることができます。
1,2
鍵盤右側で UPPER のトーン、鍵盤左側で LOWER のトーンが鳴ります。
2
もう一度[SPLIT]を押すと、インジケーターが消灯し、ス
プリットが解除されます。
レイヤー・モードとスプリット・モードを両方選ぶ
[LAYER]と[SPLIT]の両方をオンにすると、スプリット・ポイントか
ら左側で LOWER のトーンが鳴り、右側で UPPER1 と UPPER2 のトー
ンが重なってなります。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(画面図説明入り)
Split Point (C4)
UPPERLOWER
鍵 盤で演奏しよう
39

鍵盤で演奏しよう
UPPER1、UPPER2、
「各パートの鍵域を
設定する (Key Range)」
音域の分かれる位置を変える(スプリット・ポイント)
スプリット・モードの鍵盤の分かれる位置(スプリット・ポイント)を変
えることができます。
1
[SPLIT]を数秒間押し続けます。
次のような画面が表示され、現在の設定値が表示されます。
fig.LCD
2
レイヤーやスプリット・モードのトーンの変えかた
鍵 盤で演奏しよう
1
[SPLIT]を押したまま、鍵を押します。
[SPLIT]から指を離すと画面が元に戻ります。
スプリット・ポイントの鍵は、UPPER に含まれます。
レイヤー・モードやスプリット・モードでトーンを変えたいときは、
PART SELECT ボタンを使って、変更するトーンのパートを指定します。
fig.panel
PART SELECT ボタンを押して、トーンを変えたいパートの
LOWER の鍵域を自由に設
定することができます。詳
しくは
12
インジケーターを点灯させます。
現在選ばれている TONE SELECT ボタンのインジケーターが、選んだ
パートのインジケーターと同じ色で点灯します。
ただし、[NUM LOCK]がオンになっているときは、TONE SELECT ボタ
ンは点灯しません。
2
TONE SELECT ボタンでトーンのカテゴリーを選び、[INC/
YES]/[DEC/NO]でトーンを選びます。
40
[NUM LOCK]をオンにすると、TONE SELECT ボタンでトーン・ナン
バーを指定することができます(P.33)。

パートごとの音量を調節する
外部音源のトーンを割り当
てるパートは、MIDI TX
パートといいます。RD-
700 では、MIDI TX パート
もローカル・パートと同じ
ようにコントロールするこ
とができます。
詳しくは、
「パートごとに
音量を調節する(MIDI TX
パート)」
(P.58)をご覧く
ださい。
全体の音量を調節するとき
Tone Wheel1 〜 10 のい
(PART SWITCH/PART LEVEL スライダー)
fig.panel
PARTLEVELスライダー
PARTSWITCH
RD-700 では、内蔵音源のトーンで演奏するパートのことをローカル・
パートといいます。
RHYTHM パートと、ローカル・パート(LOWER、UPPER1、UPPER2)
は、PART SWITCH、PART LEVEL スライダーで音のオン/オフや音量
をパートごとに設定することができます。
鍵盤で演奏しよう
PART SWITCH
各パートの音を出す/出さないを設定します。
PART SWITCH のインジケーターが点灯(オン)しているパートは、鍵
盤を弾くと音が出ます。画面のパート名が大文字で表示されます。
PART SWITCH のインジケーターが消灯(オフ)しているパートは、鍵
盤を弾いても音は出ません。画面のパート名が小文字で表示されます。
PART SWITCH のオン/オフは、ボタンを押すごとに切り替わります。
PART
LEVEL スライダー
各パートの音量を調節します。
PART SWITCH のインジケーターが消灯しているときは、スライダーを
動かしても音はでません。
ずれかのトーンが選ばれて
いるパートは、PART
LEVEL スライダーで音量
を調節することができませ
ん。
は、VOLUME スライダー
を使います(P.21)。
鍵 盤で演奏しよう
41

鍵盤で演奏しよう
MIDI IN 端子からのノート
トランスポーズをオンにし
ローカル・パート(P.27)
「パートご
とに移調の設定をする
(P.84)
をご覧ください。
鍵盤の音の高さを変える([TRANSPOSE])
自分が弾く鍵盤の位置を変えずに移調したり、音の高さのオクターブを変
えて演奏することができます。このような機能を「トランスポーズ」とい
います。
歌う人の声の高さに合わせて演奏したいときや、トランペットなどの移調
楽器の譜面どおりに演奏したいときなどに使うと便利です。
トランスポーズの設定は C4 を基準に半音単位で -41 〜 0 〜 +42 の範囲
で設定できます。
fig.panel
情報は、移調されません。
1
鍵 盤で演奏しよう
2
1,2,3
[TRANSPOSE]を数秒間押し続けます。
次のような画面が表示され、現在の設定値が表示されます。
fig.LCD
[TRANSPOSE]を押したまま、鍵を押します。
例えば、「ド」の鍵を弾いたときに「ミ」の音がでるようにするには、
[TRANSPOSE]を押しながら、E4(ミ)の鍵を押します。このときの、
トランスポーズ量は「+4」になります。
[TRANSPOSE]から指を離すと、画面は元に戻ります。
トランスポーズ量が設定されると、トランスポーズがオンになり、
[TRANSPOSE]が点灯します。
ても、スプリット・ポイン
ト(P.40)は変わりませ
ん。
トランスポーズ量が「0」のときは、[TRANSPOSE]をオンにするとイ
ンジケーターが点滅します。
3
トランスポーズをオフにするときは、[TRANSPOSE]を押
42
してインジケーターを消灯させます。
次に[TRANSPOSE]を押すと、ここで設定した値でトランスポーズさ
れます。
はパートごとに異なるトラ
ンスポーズ量を設定するこ
とができます。

音に響きをつける(REVERB つまみ)
エディット・モードで
リバーブ効果の設定につい
「リバーブ
の設定をする」
(P.74)を
ご覧ください。
エディット・モードで
コーラス効果の設定につい
て、詳しくは、
「コーラス
/ディレイの設定をする」
鍵盤で弾く音に「リバーブ効果」(残響)をかけることができます。リ
バーブ効果をかけると、コンサート・ホールなどで演奏しているような心
地よい響きが得られます。
fig.panel
鍵盤で演奏しよう
て、詳しくは、
1
REVERB つまみで、リバーブ効果のかかり具合を調節します。
つまみを右側に回すとリバーブ効果が深くなり、左側に回すとリバーブ効
果が浅くなります。
音に広がりをつける(CHORUS つまみ)
鍵盤で弾く音に「コーラス効果」をかけることができます。コーラス効果
をかけると、音に立体的な広がりと厚みを持たせることができます。
fig.panel
[CHORUS]つまみで、コーラス効果のかかり具合を調節します。
1
CHORUS つまみで、コーラス効果のかかり具合を調節しま
す。
つまみを右側に回すとコーラス効果が深くなり、左側に回すとコーラス効
果が浅くなります。
Tone Edit の「Reverb
Amount」の設定が「0」
になっているときは、
REVERB つまみを回して
も、効果はかかりません
(P.76)。
Tone Edit の「Chorus
Amount」の設定が「0」
になっているときは、
CHORUS つまみを回して
も、効果はかかりません
(P.76)。
鍵 盤で演奏しよう
43

鍵盤で演奏しよう
トーンによって、レバーを
トーン・ホイール画面を表
示しているときは、ピッ
チ・ベンド・レバーを左右
に倒すとロータリー効果の
遅い/速いが切り替わりま
す。詳しくは、
「オルガン
の音作りをシミュレートす
る (トーン・ホイール・
モード)」
(P.71)をご覧く
ださい。
イコライザーのより細かい
設
「イコラ
イザーの周波数設定を変え
る(Freq/Q)」
(P.70)を
ご覧ください。
イコライザーは OUTPUT
つまみの設定によっては、
音の高さをリアルタイムに変化させる
(ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー)
鍵盤を弾きながらレバーを左に倒すとピッチが下がり、右に倒すとピッチ
が上がります。これをピッチ・ベンド効果といいます。
また、レバーを向こう側に倒すとビブラートがかかります。これをモジュ
レーション効果といいます。
レバーを左または右に倒しながら向こう側に倒したときは、両方の効果が
同時に得られます。
fig.Q1-
動かしたときの効果が異な
るものがあります。また、
このレバーによる効果は、
トーンごとに決まってお
り、変更することはできま
せん。
音の低域・中域・高域のレベルを調節する
(EQUALIZER)
RD-700 には、3 バンドのイコライザーが装備されています。
鍵 盤で演奏しよう
EQUALIZER[LOW]、[MID]、[HIGH]の各つまみで、それぞれ音の低
域、中域、高域のレベルを自由に調節できます。
fig.Q1-
1
EQUALIZER[ON/OFF]を押して、インジケーターを点灯
させます。
イコライザーがオンになります。
2
つまみで各音域のレベルを調節します。
3
44
つまみを−側に回すと各音域が弱くなり、+側に回すと各音域が強くなり
ます。
イコライザーをオフにするときは、EQUALIZER[ON/OFF]
を押して、インジケーターを消灯させます。
ピッチ・ベンド効果
モジュレーション効果
端子から出力される音全体
に効果がかかります。
音がひずむことがありま
す。その場合、PART
LEVEL スライダーなどで
パートごとの音量を下げる
か、エディット・モード、
System の Master Volume
の設定(P.66)で全体の音
量を下げてください。
定ができます。

多彩な機能を使って演奏しよう
パートや鍵域を指定してア
「アル
ペジオ演奏する鍵域を設定
する(Key Range)」
アルペジオを使った演奏
は、MIDI OUT 端子から外
部 MIDI 機器に送信するこ
ともできます。送信すると
きは、エディット・モー
ド、Arpeggio の Dest.Part
の設定を ALL にしてくだ
さい(P.80)。
エディット・モード、
工場出荷時の設定では、鍵
弾いた和音をアルペジオにする
([ARPEGGIO])
和音(コード)を弾くだけで、その構成音に従ってアルペジオ(分散和
音)演奏をすることができます。
fig.panel(手順図)
ルペジオ演奏することがで
きます。詳しくは、
1
2
1,3
[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを点灯させます。
図のようにキーを押さえます。
fig.Q2-(RS Q-45)
CEG
C
C、E、G、E、C、E、G、E・・・の順番でアルペジオ演奏をします。
他のコードも弾いてみましょう。
CE EE
E
GG
盤を離すとアルペジオ演奏
が止まりますが、鍵盤を離
してもアルペジオを鳴らし
続けることができます
(P.83)。
多彩な機能を使って演奏しよう
3
もう一度[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを消灯さ
せると、通常の演奏状態に戻ります。
Arpeggio の Arpeggio
Hold の設定(P.83)が
ON になっているとき
・[ARPEGGIO]のインジ
ケーターが点滅します。
・リズムを鳴らしながらア
ルペジオ演奏していると
き、リズムが止まると同
時にアルペジオ演奏が止
まります。
45

多彩な機能を使って演奏しよう
アルペジオのスタイルにつ
「アルペジオのし
かた(スタイル)を設定す
る(Style)」
(P.80)をご
覧ください。
トーン画面が表示されてい
るときに、CURSOR[ ]
を押すと、アルペジオ/リ
ズム画面が表示されます。
アルペジオ/リズム画面が
表示されているときに、
CURSOR[ ]を押すと、
トーン画面が表示されます。
「アルペジエーターの設定(Arpeggio)」
(P.79)をご覧ください。
アルペジオのスタイルを変える
アルペジオは、いろいろなジャンルに合わせて演奏のしかた(スタイル)
を選ぶことができます。
1
[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを点灯させます。
2
トーン画面で、CURSOR[ ]を押して、アルペジオ/リズ
ム画面を表示させます。
fig.LCD(画面)
いては、
3
CURSOR[ ]でカーソルを「ARP」に移動します。
4
[INC/YES]/[DEC/NO]でスタイルを選びます。
アルペジオのスタイルが変わります。
多彩な機能を使って演奏しよう
5
鍵盤を弾いてみましょう。
6
もう一度[ARPEGGIO]を押して、インジケーターを消灯さ
せると、通常の演奏状態に戻ります。
アルペジオのテンポを変える
1
アルペジオ/リズム画面で、CURSOR[ ]を押して、
カーソルを画面上段のテンポ表示に移動させます。
2
[INC/YES]/[DEC/NO]でテンポを変えます。
鍵盤を弾くと、設定したテンポでアルペジオが演奏されます。
アルペジオのスタイルやテンポのほかにも、さまざまな設定を変えること
ができます。
46
詳しくは

リズムを鳴らす([RHYTHM])
ローカル・パートのリズム
リズムの始まりと終わり
に、イントロとエンディン
グのリズム・パターンを鳴
らすことができます。
詳しくは
「イントロ/エン
ディングのオン/オフを設
定する(Intro/Ending)」
PART SWITCH
「パターンを変える
(P.78)をご覧
ください。
エディット・モード、
RD-700 には、ジャズやロックなどさまざまな音楽ジャンルのドラム・パ
ターンを内蔵しています。このドラム・パターンのことを「リズム」とい
います。
リズムは、キー・モードがいずれの場合でも、独立してオン/オフするこ
とができます。リズムを鳴らしながらアルペジオ演奏など、いろいろな機
能と組み合わせて演奏することができます。
fig.panel
1,2,3
多彩な機能を使って演奏しよう
と MIDI TX パートのリズ
ムを同時に鳴らすと、両方
の演奏は同期します。
1
PART SWITCH[RHYTHM]を押して、インジケーターを点
灯させます。
リズムが鳴り始めます。
2
[RHYTHM]スライダーでリズムの音量を調節します。
3
もう一度[RHYTHM]を押して、インジケーターを消灯させ
ると、リズムが止まります。
リズムのエンディングが演奏される設定になっているとき(P.79)は、
エンディングが鳴ってからリズムが止まります。
また、この設定のとき、リズムが鳴っているときに、[RHYTHM]を素早
く2回押すと、エンディングを鳴らさずにリズムを止めることができま
す。
[RHYTHM]を押してもリ
ズムが鳴らないようにする
ことができます。詳しく
は、
多彩な機能を使って演奏しよう
Arpeggio の Arpeggio
Hold の設定(P.83)を
ON にすると、リズムを鳴
らしながらアルペジオ演奏
しているとき、リズムを止
めると、同時にアルペジオ
演奏も止まります。
47

多彩な機能を使って演奏しよう
リズムのパターンについて
「リズム・パターン一
覧」
(P.139)をご覧くだ
さい。
トーン画面が表示されてい
るときに、CURSOR[ ]
を押すと、アルペジオ/リ
ズム画面が表示されます。
アルペジオ/リズム画面が
表示されているときに、
CURSOR[ ]を押すと、
トーン画面が表示されます。
「リズムの設定 (Rhythm Pattern)」
(P.78)をご覧ください。
リズムのパターンを変える
リズムは、いろいろなジャンルに合わせて演奏のしかた(パターン)を選
ぶことができます。
1
PART SWITCH[RHYTHM]を押して、インジケーターを点
灯させます。
リズムが鳴り始めます。
2
トーン画面で、CURSOR[ ]を押して、アルペジオ/リズ
ム画面を表示させます。
fig.LCD(画面)
3
CURSOR[ ][ ]でカーソルを「RHY」に移動します。
多彩な機能を使って演奏しよう
4
[INC/YES]/[DEC/NO]でパターンを選びます。
リズムのパターンが変わります。
5
リズムを止めるときは、PART SWITCH[RHYTHM]を押し
て、インジケーターを消灯させます。
は
リズムのテンポを変える
1
アルペジオ/リズム画面で、CURSOR[ ]を押して、
カーソルを画面上段のテンポ表示に移動させます。
2
[INC/YES]/[DEC/NO]でテンポを変えます。
リズムが設定したテンポで鳴ります。
リズムのテンポやパターンのほかにも、さまざまな設定を変えることがで
きます。
詳しくは、
48

音に効果をかける(MULTI EFFECTS)
エフェクト・タイプについ
「エフェクト
/パラメーター一覧」
エディット・モード、
節できる設定は、選ばれて
いるエフェクトによって異
なります。詳しくは
「MFX
Control」
(P.73)をご覧く
ださい。
スプリットとレイヤーでマルチエフェクトを使うときは
RD-700 では、2 種類以上のマルチエフェクトを同時に使うことができま
「MFX Source、MFX Dest」
(P.73)をご覧ください。
「マルチエフェクトの設定をする」
(P.73)をご覧ください。
RD-700 では、コーラス(P.43)やリバーブ(P.43)のほかに「マルチ
エフェクト」をかけることができます。マルチエフェクトは、ディストー
ションやロータリーを始めとする 65 種類のエフェクト・タイプから選ぶ
ことができます。
工場出荷時の設定では、各トーンにあったエフェクトが設定されています。
fig.panel(手順図)
1,2,3
多彩な機能を使って演奏しよう
て、詳しくは
1
MULTI EFFECTS [ON/OFF]を押して、インジケーターを
点灯させます。
2
[CONTROL]つまみで、マルチエフェクトのかかり具合を調
節します。
3
マルチエフェクトをかけないときは、MULTI EFFECTS
[ON/OFF]を押して、インジケーターを消灯させます。
せん。そのために、どのマルチエフェクトの設定を使うかを選ぶ「MFX
Source」と、そのマルチエフェクトをどのパートにかけるかを選ぶ
「MFX Dest」という設定項目があります。したがって、スプリットとレイ
ヤーのときは、MFX Source や MFX Dest の設定によって、マルチエ
フェクトが効かないパートがありますのでご注意ください。
Tone Edit の MFX の設定
が「00 THROUGH」に
なっているトーンには効果
はかかりません(P.76)。
その場合、MULTI
EFFECTS[ON/OFF]の
インジケーターは点滅しま
す。
多彩な機能を使って演奏しよう
詳しくは
マルチエフェクトのタイプなどさまざまな設定を変えることができます。
詳しくは、
49

多彩な機能を使って演奏しよう
セットアップを呼び出す
トーン画面が表示されてい
るときに、CURSOR[ ]
を押すと、[SETUP]のイ
ンジケーターが点灯し、
セットアップ画面が表示さ
れます。
セットアップ画面が表示さ
れているときに、CURSOR
面に戻ります。
ただし、トーン画面で、い
ずれかのパートに「Tone
Wheel」を選んでいるとき
は、「トーン・ホイール画
面」が表示されます。
詳しくは
「オルガンの音作
りをシミュレートする
ド)」
(P.71)
をご覧くださ
い。
記憶させた設定を選ぶ([SETUP])
RD-700 のローカル・パート(P.27)や MIDI TX パート(P.27)のトー
ンやエフェクトなどの設定をまとめて「セットアップ」と呼びます。
気に入った設定や演奏する曲にあった設定をセットアップとして記憶して
おけば、演奏時にセットアップを切り替えるだけで、まとめて設定を切り
替えることができます。
セットアップは 100 個まで記憶することができます。
工場出荷時は、おすすめのセットアップが用意されています。
ここでは、実際にセットアップを呼び出してみましょう。
fig.panel
1
[SETUP]を押して、インジケーターを点灯させます。
多彩な機能を使って演奏しよう
次のようなセットアップ画面が表示されます。
fig.LCD(画面)
と、現在の設定は消えてし
まいます。気に入った設定
はあらかじめセットアップ
に記憶してください。セッ
トアップへの記憶のしかた
は、P.52 をご覧ください。
123
2
3
50
[NUM LOCK]ボタンを押して、インジケーターを点灯させ
ます。
[INC/YES]/[DEC/NO]または TONE SELECT ボタンで
呼び出すセットアップを選びます。
[INC/YES]/[DEC/NO]を押すと、次のような画面が表示され、しばら
くすると、セットアップ画面に戻ります。
TONE SELECT ボタンでセットアップ・ナンバーを入力したときは、画面は
変わりません。[ENTER]を押して、セットアップを確定してください。
fig.LCD
アップは、リズム(P.47)
を鳴らしてお楽しみくださ
い。

4
Intro/Ending の設定
[NUM
LOCK]せずにセットアップを選ぶ
TONE SELECT ボタンを使うと、セットアップを 10 単位で指定すること
ができます。
1.
[SETUP]を押して、インジケーターを点灯させます。
このとき、[NUM LOCK]はオフにしてください。
2.
TONE SELECT ボタンでセットアップ・ナンバーを指定します。
セットアップは次のように TONE SELECT ボタンに割り当てられます。
fig.
3.
[INC/YES]/[DEC/NO]でセットアップを選びます。
[INC/YES]/[DEC/NO]を押すと、選んでいるセットアップ・ナン
バーを含む TONE SELECT ボタンが点滅し、次のような画面が表示さ
れます。
fig.LCD
4.
点滅している TONE SELECT ボタンを押すか、鍵盤を弾きます。
TONE SELECT ボタンが点灯し、選んだセットアップが確定します。
鍵盤を弾いてみましょう。
呼び出したセットアップの設定になります。
多彩な機能を使って演奏しよう
(P.79)が ON のセット
アップを選ぶと、
[RHYTHM]のインジケー
ターが点滅します。
[RHYTHM]を押すと、リ
ズムがイントロから始まり
ます。
001
011
021
031
041
051
061
071
080
081
:
:
090
セットアップ・
ナンバー
010
:
:
:
:
020
030
040
:
050
060
:
:
070
091
:
100
多彩な機能を使って演奏しよう
51

多彩な機能を使って演奏しよう
設定をセットアップに記憶する([WRITE])
セットアップの内容を変更すると、トーン画面やセットアップ画面のテン
ポ表示の右側に「*」マークがつきます。
変更した内容を新しいセットアップとして使うには、以下の操作でセット
アップに記憶してください。
また、セットアップの名前を変更することもできます。
RD-700 は、100 個のセットアップを記憶することができます。
fig.panel
12,4,8 3,6 359,10
1
[WRITE]を押して、インジケーターを点灯させます。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD
多彩な機能を使って演奏しよう
2
CURSOR[ ]を押して、記憶先のセットアップ名にカー
ソルを移動します。
3
[INC/YES]/[DEC/NO]で記憶先のセットアップを選び
ます。
TONE SELECT ボタンでセットアップ・ナンバーを指定し、[ENTER]で
セットアップを選ぶこともできます。
新しいセットアップ名
記憶先
4
52
CURSOR [ ]を押して、新しいセットアップ名にカーソ
ルを移動します。
fig.LCD

5
画面に「Please keep on
6
多彩な機能を使って演奏しよう
CURSOR [ ]/[ ]を押して、文字を入力したい位置
にカーソルを動かします。
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して、文字を入力します。
選べる文字は次の通りです。
7
8
スペース、A 〜 Z、a 〜 z、0 〜 9、!
> ? @ [ \ ] ^ _ ‘ { i
また、EXPANSION[A]を押すと一文字の空白が入り、[B]を押すと一
文字削除します。
操作 5 〜 6 を繰り返して、名前を入力します。
名前を入力している途中でも、CURSOR [ ]を押すと、カーソルは
記憶先のセットアップ・ナンバーに移動します。
記憶先と新しいセットアップ名が決定したら、CURSOR
[ ]を押して、確認のメッセージにカーソルを移動させま
す。
[INC/YES]のインジケーターが点滅します。
fig.LCD
}
" # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < =
セットアップを記憶しないときは、[DEC/NO]を押してください。
操作を中断し、トーン画面に戻ります。
9
[INC/YES]を押します。
次のような確認のメッセージが表示されます。
fig.LCD
10
[INC/YES]を押すと、セットアップの記憶が始まります。
セットアップの記憶が終わると、画面に「COMPLETED」と表示され、
[WRITE]のインジケーターが消灯します。トーン画面に戻ります。
多彩な機能を使って演奏しよう
power」と表示されている
間は、決して電源を切らな
いでください。本機の内部
メモリーが破壊され、使用
できなくなります。
53

多彩な機能を使って演奏しよう
以下の項目は、セットアップに記憶することができません。
SETUP
<0
00 >(ピアノ・セットアップ)
ONE TOUCH[PIANO]ボタンを押してトーン画面を表示させてから
CURSOR[ ]を押して、セットアップ画面を表示させると、SETUP
< 000 >になります。
SETUP < 000 >を、「ピアノ・セットアップ」といいます。
fig.LCD
この SETUP < 000 >は、ONE TOUCH[PIANO]の設定を記憶してい
るセットアップで、他のセットアップのように、[WRITE]で内容を書き
替えることはできません。
ONE TOUCH[PIANO]の設定から変更した内容を保存するときは、
SETUP < 001 >以降に書き込みます。
セットアップに記憶しない設定
・Rec Setting(P.91)の設定
・[CONTROL]つまみの位置(値)
・System(P.65)の設定
システム設定は、項目を変更するごとに設定を記憶しています。
多彩な機能を使って演奏しよう
54

RD-700 をマスター・キーボードにする
外部機器との接続のしかた
「外部機器と接続する」
RD-700 のリア・パネルにある MIDI OUT 端子に外部の MIDI 機器を接続
して、RD-700 でコントロールすることができます。
通常、RD-700 は、ノート情報を MIDI OUT 端子から送信していますが、
[MIDI TX]をオンにすると、ノート情報だけでなく、外部 MIDI 機器のさ
まざまな設定をコントロールすることができます。
内部音源と外部音源は独立してコントロールすることができます。
MIDI とは
MIDI(ミディ:Musical Instruments Digital Interface)とは、電子楽器や
コンピューターの間で演奏などの情報をやりとりできる統一規格です。
MIDI 端子を持つ機器同士を MIDI ケーブルで接続すると、1 台の MIDI
キーボードで複数の楽器を鳴らす、複数の MIDI 楽器をアンサンブルで演
奏する、曲の演奏の進行に合わせて自動的に設定を変える、などができる
ようになります。
MIDI 端子について
RD-700 の MIDI 端子には次の 3 種類があり、それぞれ働きが異なります。
fig.Q3-(MIDI 端子図)
MIDI IN 端子
外部の MIDI 機器から送られてくる MIDI 情報を受信します。MIDI 情報を
受信した RD-700 は、音を出す、音色を切り替えるなどの動作をします。
MIDI OUT 端子
外部の MIDI 機器に対して MIDI 情報を送信します。RD-700 では、MIDI
OUT 端子から鍵盤コントローラー部の演奏情報を送信する、いろいろな
設定の内容を保存するための情報を送信する(バルク・ダンプ→ P.88)
ときなどに使います。
MIDI THRU 端子
MIDI IN 端子で受信したメッセージを、そのまま外部 MIDI 機器へ送信し
ます。複数の MIDI 機器を同時に使用するときなどに使います。
は
マスター・キーボードにする
外部 MIDI 音源との接続例
fig.Q3-(fig.R10-05)
MIDI OUT
MIDI IN
音源A
RD-700
55

RD-700 をマスター・キーボードにする
外部 MIDI 機器の各パート
の受信チャンネルの設定の
しかたは、それぞれの取扱
説明書を参照してください。
鍵盤の送信チャンネルの設
エディット・モード、
PART SWITCH がオフに
MIDI 送信チャンネルを設定する
外部 MIDI 音源との接続が終わったら、鍵盤の送信チャンネルと外部 MIDI
音源の各パートの受信チャンネルを合わせます。送信側(RD-700)と受
信側(外部 MIDI 音源)の MIDI チャンネルを同じチャンネルに合わせる
と音が鳴ります。
fig.panel(MIDI ボタン)
定は、セットアップに記憶
することができます
(P.52)。
12
1
[MIDI TX]を押して、インジケーターを点灯させます。
MIDI TX 画面が表示されます。
画面に「Ch」が表示されていないときは、CURSOR [ ]を数回押し
て、次のような画面を表示させます。
fig.LCD(画面)
マスター・キーボードにする
2
CURSOR [ ]/[ ]/[ ]/[ ]でカーソルを
動かし、[INC/YES]/[DEC/NO]で各パートの送信チャ
ンネル(Ch)を設定します。
パート 設定値 解説
UP1(UPPER1)
UP2(UPPER2)
LWR(LOWER)
RHY(RHYTHM)
1〜16
選んだチャンネルで
RD-700 の演奏情報
が送信されます。
なっているパートは、画面
のパート名が、「up1」
「up2」「lwr」「rhy」と小文
字で表示されます。
PART SWITCH がオフに
なっているパートの MIDI
情報は送信されません。
Utility の Rec Setting の設
定で、Rec Mode が「ON」
になっていると、左図のよ
うな MIDI TX 画面は表示
されません。MIDI 送信
チャンネルを設定するとき
は、Rec Mode を「OFF」
にしてください(P.91)。
56

外部 MIDI 音源の音色を切り替える
外部 MIDI 音源に、音色が
配置されていないプログラ
ム・ナンバーやバンク・ナ
ンバーを送信すると、代わ
りの音色が選ばれたり、場
合によっては音が鳴らない
こともあります。プログラ
ム・チェンジやバンク・セ
レクトを送信したくないと
きは、左記の操作 2 で
MSB / LSB の設定を「---
きは、セットアップを切り
替えても、音色切り替えの
情報は送信されません。
外部 MIDI 機器のトーンの切り替えは、RD-700 でプログラム・ナンバー
やバンク・セレクト MSB / LSB を数値で入力します。
fig.panel
1
[MIDI TX]を押して、インジケーターを点灯させます。
MIDI TX 画面が表示されます。
RD-700 をマスター・キーボードにする
12
画面に「MSB」が表示されていないときは、CURSOR [ ]を数回押
して、次のような画面を表示させます。
fig.LCD(画面)
パラメーター Tx 設定値
MSB(Bank Select MSB) CC 32 0〜127、---(オフ)
LSB(Bank Select LSB) CC 00 0〜127、---(オフ)
PC(Program Change) Program Change 0〜127、---(オフ)
2
CURSOR [ ]/[ ]/[ ]/[ ]でカーソルを
動かし、[INC/YES]/[DEC/NO]で各パートの MSB/
LSB/PC を設定してください。
[INC/YES]/[DEC/NO]を同時に押すと、設定値は「---(オフ)」に
なります。
「---(オフ)」にすると、プログラム・チェンジやバンク・セレクトは送信
されません。
マスター・キーボードにする
57

RD-700 をマスター・キーボードにする
ローカル・パートのコント
「パー
トごとの音量を調節する
LEVEL スライダー)」
パートごとに音量を調節する(MIDI TX パート)
fig.panel
PARTSWITCH
[MIDI TX]のインジケーターが点灯しているときは、ローカル・パート
(P.27)と同じように PART SWITCH/LEVEL で MIDI TX パートをコント
ロールすることができます。
PART
マスター・キーボードにする
SWITCH
[MIDI TX]のインジケーターが点灯しているときは、MIDI TX パートの
のノート情報を MIDI OUT から送信する、送信しないを設定します。
PART SWITCH のインジケーターが点灯(オン)しているパートは、鍵
盤を弾くと、そのノート情報が MIDI OUT から送信されます。
PART SWITCH のインジケーターが消灯(オフ)しているパートは、鍵
盤を弾いてもノート情報は送信されません。
PART SWITCH のオン/オフは、ボタンを押すごとに切り替わります。
PART LEVEL スライダー
[MIDI TX]のインジケーターが点灯しているときは、MIDI TX パートの
各パートの音量を調節します。
PARTLEVELスライダー
[MIDITX]点灯
ロールについては、
58

RD-700 をマスター・キーボードにする
MIDI 送信パートの詳細設定をす る([MIDI TX])
MIDI TX パートについて、[MIDI TX]を押して、以下の項
目を設定することができます。
fig.LCD(画面図× 7)
音量/パンを設定する
各パートの音量と定位(パン)を設定します。
音量の設定は、主にキー・モードがスプリットやレイヤーの
ときに、パート間の音量バランスをとるために使います。
パンの設定は、ステレオ出力するときの、各パートの音像の
定位です。L の数字が大きくなるほど左から音が聞こえま
す。R の数字が大きくなるほど、右から音が聞こえます。0
にすると、中央から音が聞こえます。
パラメーター TX CC# 設定値
VOL(Volume) CC07 0〜127
PAN(Pan) CC10 L63 〜 0 〜 63R
リバーブ/コーラスのレベルを設定する
リバーブ効果、コーラス効果の深さを設定します。
パラメーター TX CC# 設定値
REV(Reverb)
CHO(Chorus) CC91 0〜127
CC93 0〜127
設定のしかた
[MIDI TX]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
RD-700 で外部 MIDI 機器をコントロールする設定にな
ります。
CURSOR [ ]/[ ]/[ ]/[ ]を押
2.
して、設定する項目にカーソルを移動させます。
動かしたい方向の CURSOR ボタンを押しながら、逆方
向の CURSOR ボタンを押すと、カーソルを速く移動す
ることができます。
鍵域を設定する(キー・レンジ)
各パートの鍵域(キー・レンジ)を設定します。
鍵域によってトーンを弾きわけるときなどに設定します。
設定する鍵域の下限(LWR)と、上限(UPR)を指定しま
す。指定する鍵を押し、[ENTER]を押して設定することも
できます。
パラメーター
LWR(Lower) A0 〜 C8
UPR(Upper) A0 〜 C8
キー・レンジの設定は、[SPLIT]がオン(P.39)のときだ
け有効です。
鍵域の下限(LWR)を上限(UPR)より上げたり、上限を
下限より下げることはできません。
MIDI のノート情報を送信する/しないは、PART SWITCH
でパートごとに設定することができます。(P.58)
設定値
マスター・キーボードにする
3.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
[INC/YES]と[DEC/NO]を同時に押すと、設定値は
「---(オフ)」になります。
59

RD-700 をマスター・キーボードにする
パートごとに移調の設定をする
(トランスポーズ)
各パートを、それぞれ異なる音の高さに移調させて演奏する
ことができます。
キー・モードがレイヤーのときに、一方のトーンをオクター
ブ違いに設定すると、厚みのあるトーンを作ることができま
す。また、キー・モードをスプリットにして、ロワーでベー
スのトーンを鳴らすような場合に、より低い音で鳴らすこと
ができます。
パラメーター 設定値
TRA(Transpose) -48 〜 0 〜 +48
ベンダーによる音程変化の幅を設定す る(ベンド・レンジ)
ピッチ・ベンド・レバーを動かしたときのピッチの変化量を
半音単位で設定します。(+/-4 オクターブ)。
パラメーター
B.R
(Bend Range)
マスター・キーボードにする
00H/00H 0〜48
RPN 設定値
トーンの要素を変化させる(ATK / REL / COF / RES)
トーンの次の 4 つの要素を設定することで、音色に変化を
与えることができます。
ATK(Attack Time):
アタック・タイム:キーを押さえてから、音が立ち上がるま
での時間です。
REL(Release Time):
リリース・タイム:キーを離してから、音が消えるまでの時
間です。
COF(Cutoff):
カットオフ:フィルターの開き具合を調節します。
RES(Resonance):
レゾナンス:カットオフ周波数付近の音の成分を強調し、音
にクセをつけます。設定値を上げすぎると発振して音が歪む
ことがあります。
パラメーター TX CC# 設定値 解説
値を大きくすると立
ち上がりがゆるやか
ATK
REL CC72 -63 〜 +63
COF CC74 -63 〜 +63
RES CC71 -63 〜 +63
CC73 -63 〜 +63
に、小さくすると立
ち上がりが鋭くなり
ます。
値を大きくすると余
韻の長い音になり、
小さくすると歯切れ
の良い音になりま
す。
値を大きくすると音
が明るくなり、小さ
くすると暗くなりま
す。
値が大きくなるとク
セが強くなり、小さ
くすると弱くなりま
す。
60

RD-700 をマスター・キーボードにする
音を滑らかに変化させる(ポルタメント)
はじめに弾いた鍵と次に弾いた鍵との間の音程をなめらかに
変化させる効果のことを「ポルタメント」といいます。
ポルタメント・タイムは、ポルタメント効果をかけた音の高
さが変化する時間を設定します。値が大きくなるほど、次の
音の高さに移動する時間が長くなります。
パラメーター TX CC# 設定値
POR
(Portamento Switch)
P.T
(Portamento Time)
CC65 OFF、ON
CC5 0〜127
音の高さを変える(コース・チューン /ファイン・チューン)
トーンの音の高さ(ピッチ)を設定します。
パラメーター RPN 解説 設定値
C.T
(Coarse
Tune)
F.T
(Fine
Tune)
00H/02H
00H/01H
音の高さを半
音単位で設定
します。
音の高さを 1
セント単位で
設定します。
-48 〜 +48
(+/-4オクターブ)
-50 〜 +50
(+/- 50 セント)
鍵盤を弾く強さによる音量変化を設定 する(ベロシティー)
鍵盤を弾く強さ(ベロシティー)に対する音量の変化のしか
たと、変化の最大値を設定します。
トーンによって、この設定が無効なものがあります。
パラメーター 設定値 解説
ベロシティーに対する
音量の変化のしかた。
設定値が+のときは、
鍵盤を強く弾くほど音
SNS(Velocity
Sensitivity)
MAX(Velocity
Max)
-63 〜 63
1〜127
量が大きくなり、−の
ときは、鍵盤を強く弾
くほど音量が小さくな
ります。設定値が 0 の
ときは、弾く強さに関
わらず、音量は一定に
なります。
ベロシティーに対する
音量の変化の最大値。
値を小さくすると、鍵
盤を強く弾いても音量
があまり大きくなりま
せん。
1 セント = 半音の 100 分の 1
各コントローラーのオン/オフを設定 する
各 PEDAL 端子に接続したペダル、CONTROL つまみ、モ
ジュレーション・レバー、ベンダーで外部 MIDI 機器をコン
トロールするか(ON)、しないか(OFF)を設定します。
パラメーター 解説 設定値
DMP ダンパー・ペダル
FC1 FC1 端子に接続したペダル
FC2 FC2 端子に接続したペダル
CTR [CONTROL]つまみ
MOD モジュレーション・レバー
BND ベンダー
ON、OFF
マスター・キーボードにする
61

ピアノ音色の詳細設定をする(ピアノ・エディット)
ONE TOUCH [PIANO](P.31)を押したときのピアノ音色
を、お好みの音色になるように詳細設定することができま
す。
この機能を「ピアノ・エディット」といいます。
ピアノ・エディットの設定は、ONE TOUCH [PIANO]に
記憶されます。
ONE TOUCH [PIANO]を押すと、ピアノ・エディットの
設定を除く各種設定は、電源投入時の状態になります。
残しておきたい設定は、セットアップに記憶してください
(P.52)。
設定のしかた
ONE TOUCH [PIANO]を押しながら[SETUP]を押
1.
します。
[EDIT]と[NUM LOCK]が点灯し、次のようなピア
ノ・エディット画面が表示されます。
fig.
設定項目
ピアノ音色を選ぶ
ONE TOUCH [PIANO]を押したときに選ばれるピアノ音
色を選びます。
選べるトーンは 16 個あります。
音の広がりかたを変える
(Stereo Width)
音の広がりかたを設定します。
パラメーター 設定値 解説
音の広がりかたを変えま
Stereo Width 0〜63
音色のニュアンスを変える
(Nuance)
す。値が大きいほど音の
広がりが増します。
2.
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
3.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
設定が終わったら、ONE TOUCH [PIANO]を押しま
ピアノ・エディット
4.
す。
左右の音の位相を変化させることで、音色の微妙なニュアン
スを変えます。
パラメータ
Nuance OFF、TYPE1、2、3
選んでいるピアノ音色によっては、設定することができませ
ん。
ヘッドホンをご使用の場合は、効果がわかりにくくなりま
す。
設定値
音の空気感を変える(Ambience)
音の空気感を変えて、広い空間で演奏しているような音を得
ることができます。
パラメーター 設定値 解説
62
Ambience 0〜5
選んでいるピアノ音色によっては、設定することができませ
ん。
値が大きいほど、効果のか
かり具合が深くなります。

リバーブ効果のかかり具合を変える
(Reverb Level)
リバーブ効果のかかり具合を変えます。REVERB つまみと
同じ働きをしますが、ここで行った設定は、ONE TOUCH
[PIANO]を押して簡単に呼び出すことができます。
パラメーター 設定値 解説
値が大きいほどリバーブ
Reverb Level 0〜127
効果のかかり具合が深く
なります。
中音域のイコライザーを設定する
(EQ-SW / EQ Gain /
EQ Frequency / EQ Q)
中音域のイコライザーを設定します。
ピアノ音色の詳細設定をする(ピアノ・エディット)
パラメーター 設定値 解説
以下の EQ-Freq、
EQ Gain、EQ Q の
EQ-SW
EQ Gain
EQ
Frequency
EQ Q
ON、OFF
-15.0 〜 +15.0
dB
200、250、
315、400、
500、630、
800、1000、
1250、1600、
2000、2500、
3150、4000、
5000、6300、
8000 Hz
0.5、1.0、2.0、
4.0、8.0
設定を有効にする
(ON)かしないか
(OFF)を切り替え
ます。
イコライザーのか
かりかた(ゲイン)
を変えます。
設定する周波数ポ
イント。この周波
数を中心とする所
定帯域のレベルが
変わります。
帯域幅を変えます。
数値が大きくなる
と、コントロール
できる帯域が狭く
なります。
選んでいるピアノ音色によっては、設定することができませ
ん。
ピアノ・エディット
63

各機能の詳細設定をする([EDIT])
0.System (P. 65) Master Tune (→P. 25)
Master Volume
EQ Control
LCD Contrast (→P. 24)
Tone Remain
Clock Source
Rx GM System ON
Rx GM2 System ON
Rx GS Reset
Control Channel
Device ID
Pedal Polarity
1. Key Touch (P.67) Key Touch
Key Touch Offset
Velocity
Velocity Delay Sensitivity
Velocity Keyfollow Sensitivity
2. Control/EQ (P. 69) FC1
FC2
Control
Source
EQ Low Frequency
EQ Mid Frequency
EQ Mid Q
EQ High Frequency
<Band> Gain
Harmonic Bar (P. 72)
3. MFX/Reverb/Chorus (P.72) MFX Source
MFX Destination
Type
MFX Control
<Other Parameter> Value
Reverb Type
Reverb Pre-Delay
Reverb Time
Reverb High Cut
<Other Parameter> Value
Chorus/Delay
Chorus Pre-Delay
Chorus Rate
Chorus Feedback
<Other Parameter> Value
Delay-Center
Delay-Left
Delay-Right
<Other Parameter> Value
EDIT
4. Tone (P. 75) <Part> Tone
Reverb Amount
Chorus Amount
MFX
Mono/Poly
Coarse Tune
Fine Tune
Por tamento Switch
Por tamento Time
Attack Time
Release Time
Cutoff
Resonance
Bend Range
Stretch Tune
5. Rhythm Pattern (P. 78) Tempo
Pattern
Rhythm Type
Rhythm Set
Rhythm Set Change
Intro/Ending
6. Arpeggio (P. 79) Tempo
Destination Part
Key Range
Style
Octave Range
Motif
Beat Pattern
Accent Rate
Shuffle Rate
Velocity
Arpeggio Hold
7. Local Part Parameter (P. 83) <Local Part>
Key Range
Velocity Sensitivity
Velocity Max
Key Transpose
Damper Pedal Switch
FC1 Pedal Switch
FC2 Pedal Switch
Modulation Switch
Bender Switch
Control Switch
Part Assign
8. Internal Part Parameter (P. 85) <Part>
Receive Channel
Volume
Pan
MFX Switch
Voice Reserve
Rx Bank Select
Rx Program Change
Rx Modulation
Rx Bender
Rx Volume
Rx Hold -1
Rx Pan
Temperament
Temperament Key
9. Utility (P. 88) Rec Setting
Bulk Dump Temporary
Bulk Dump SETUP
Factory Reset Current
Factory Reset All
トーンのパラメーターを変更して好みの音色にしたり、さま
ざまな機能の設定を変えることをエディット(EDIT)とい
います。
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させると「エ
ディット・モード」になります。
エディットした設定は、セットアップに記憶することができ
ます。エディットした設定は、電源を切ると消えてしまいま
すので、気に入った設定はセットアップに記憶してください
(P.52)。
ただし、
システム機能(0.System)の設定は、各パラメー
ターが変更されると本体に保存されます。電源を切っても変更
した設定は失われません。
設定できる項目
エディット・モードでは、次のようなパラメーターを設定す
ることができます。
fig.EditTable.j
詳 細 設 定
64
fig.EditTable.j

各機能の詳細設定をする([EDIT])
エディット・メニュー画面
エディット画面
メニュー選択
設定項目の選択
画面切り替え
設定値の変更
(選んだメニューによって
エディット画面の枚数が
異なります)
:
[EDIT]ボタンの
ランプを点灯
[EDIT]ボタンの
ランプを消灯
エディット・モードを抜ける
エディット・モードへ
数値はTONESELECTボタンで入力
し、[ENTER]で確定することも
できます。
パラメーターの選び方
fig.
システムの設定(System)
RD-700 全体の動作環境に関する機能をシステム機能といい
ます。
設定のしかた
1.
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps
2.
CURSOR [ ]を押して、「0.System」を選びます。
3.
CURSOR []を押して、エディット画面を表示します。
fig.system1.eps150
fig.system2.eps150
fig.system1.eps150
4.
fCURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
5.
6.
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
消灯させます。
エディット・モードを抜けると、システム設定が記憶さ
れます。トーン画面に戻ります。
システム機能の設定は、各パラメーターが変更されると本体に
保存されます。電源を切っても変更した設定は失われません。
システム機能の次のパラメータについては該当ページをご覧
ください。
Master Tune → P.25
LCD Contrast → P.24
詳 細 設 定
65

各機能の詳細設定をする([EDIT])
全体の音量を設定する
(Master Volume)
RD-700 全体の音量を設定します。
パラメーター 設定値
Master Volume 0〜127
イコライザーの設定が切り替わらない ようにする(EQ Control)
イコライザーの設定(P.70)は、セットアップ(P.50)ご
とに記憶することができます。
セットアップを切り替えたときに、イコライザーの設定を
セットアップに記憶されている値に変えるか、変えないかを
設定します。
パラメーター
EQ
Control
設定値 解説
SETUP
SYSTEM
セットアップを切り替えると、イ
コライザーの設定も変わります。
セットアップを切り替えても、
イコライザーの設定は変わりま
せん。
クロック・ソースを変える
(Clock Source)
テンポを外部 MIDI 機器からコントロールすることができま
す。外部 MIDI 機器のクロック(テンポ)に合わせるとき
は、MIDI に設定してください。
パラメーター 設定値 解説
INT 内部クロックに合わせます。
外部 MIDI 機器のクロックに
合わせます。
Clock Source
内部テンポの設定は、トーン画面(P.28)、リズムのエ
ディット画面(P.78)、アルペジエーターのエディット画面
(P.80)で設定します。
外部 MIDI 機器に接続せずに ClockSource の設定を MIDI に
すると、テンポが設定されません。そのため、アルペジオ演
奏(P.45)やリズム(P.47)が鳴らなかったり、エフェクト
によっては、かかりかたが変わってしまうことがあります。
MIDI
RD-700 でテンポを設定す
ることはできません。
画面のテンポ表示「 」が
「 」に変わります。
この設定を、SYSTEM にすると、各画面の右上に「 」
マークが表示されます。
この設定を SYSTEM にすると、Control/EQ(P.70)の設
定は変更できません。
トーンを変えても発音中の音を残す
(Tone Remain)
他のトーンを選んだときに、発音中の音を残すか(ON)、残
詳 細 設 定
さないか(OFF)を設定します。
パラメーター 設定値
Tone Remain
エフェクトの設定は、Tone Remain の設定にかかわらず、
トーンの切り替えと同時に切り替わります。したがって、
Tone Remain を ON に設定していても、エフェクトの設定
によっては発音中の音が残らない場合があります。
OFF、ON
GM/GM2 システム・オン、GS リ
セットの受信を切り替える
(Rx GM / GM2 System On、Rx
GS Reset)
外部 MIDI 機器から GM システム・オン、GM2 システム・
オン、GS リセットの MIDI 情報を受信するか(ON)、受信
しないか(OFF)を設定します。
パラメーター 設定値
Rx GM System On
ON、OFFRx GM2 System On
Rx GS Reset
プログラム・チェンジ情報でセット
アップを切り替える
(Control Channel)
外部 MIDI 機器の MIDI メッセージで RD-700 のセットアッ
プを切り替えることができます。
外部 MIDI 機器から MIDI メッセージ(プログラム・チェン
ジ)を受信して、セットアップを切り替えるときの MIDI 受
信チャンネルを設定します。
外部 MIDI 機器からセットアップを切り替えないときは OFF
に設定します。
66

パラメーター 設定値
Control Channel 1〜16、OFF
各機能の詳細設定をする([EDIT])
鍵盤タッチの設定(Key Touch)
鍵盤のタッチ感を細かく設定することができます。
Control Channel の設定が、パートの MIDI 受信チャンネル
と重なったときは、音色切り替えよりもセットアップの切り
替えが優先されます。セットアップを切り替えるプログラ
ム・チェンジについては、
(P.93)をご覧ください。
「セットアップの切り替え」
デバイス ID ナンバーを設定する
(Device ID)
デバイス ID ナンバーとは、MIDI のエクスクルーシブ情報を
送受信するための認識番号です。エクスクルーシブ情報を
使ってデータをやりとりするときは、相互の機器のデバイス
ID ナンバーを合わせます。
パラメーター
Device ID
17 〜 32
設定値
ペダルの極性を切り替える
(Pedal Polarity)
RD-700 に接続しているペダルの極性を切り替えます。
リア・パネルの Pedal ジャック(FC1、FC2、DAMPER)
ごとに設定します。
ペダルによっては、ペダルを踏んだときと離しているときの
動作が逆になるものがあります。動作が逆になるペダルを使
うときは REVERSE にしてください。
設定のしかた
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して「1.Key
2.
Touch」を選びます。
3.
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
す。
fig.keytouch1.eps150
4.
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
5.
6.
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
ローランドのペダル(ポラリティー・スイッチが付いていな
い)を使うときは STANDARD にします。
パラメーター 設定値
Damper
STANDARD、REVERSEFC1
FC2
詳 細 設 定
67

各機能の詳細設定をする([EDIT])
鍵盤のタッチ感を変える
(Key Touch)
鍵盤を弾くタッチ感を調節します。
パラメーター 設定値 解説
SUPER LIGHT
LIGHT よりもさらに軽
い設定です。
この設定値を + または - 方向に変え続けると、その値にあわ
せて、Key Touch の 5 段階の値も自動的に切り替わります。
弾く強さによる音量を一定にする
(Velocity)
Key Touch
LIGHT
MEDIUM
HEAVY
鍵盤のタッチ感を軽め
の設定にします。標準
より弱いタッチでフォ
ルティッシモ(ff)が
出せるので、鍵盤が軽
くなったように感じら
れます。力の弱い方で
も、演奏しやすい設定
です。
鍵盤のタッチ感を標準
設定にします。もっと
も自然なタッチで弾け
ます。アコースティッ
ク・ピアノに一番近い
タッチです。
鍵盤のタッチ感を重め
の設定にします。標準
より強いタッチで弾か
ないとフォルティッシ
モ(ff)が出せなくな
るので、鍵盤が重く
なったように感じられ
ます。ダイナミックに
弾くとき、さらに感情
がこめられます。
鍵盤を弾く強さ(ベロシティー)に関わらず、一定の音量で
鳴るように設定します。
パラメーター 設定値 解説
鍵盤を弾く強さによって音
REAL
Velocity
1〜127
量や音の鳴りかたが変化し
ます。
音量や音の鳴りかたが設定
した値で一定になります。
弾く強さによって発音のタイミングを 変える(Velocity Delay Sens)
鍵盤を押した瞬間から発音するまでのタイミングを設定しま
す。
値が大きいほど、弱く弾いたときの発音のタイミングが遅く
なります。
パラメーター 設定値
Velo Delay Sens -63 〜 +63
SUPER HEAVY
この設定は、次項目の Key Touch Offset の値によっては、
自動的に切り替わります。
詳 細 設 定
鍵盤のタッチ感を微調整する
(Key Touch Offset)
鍵盤のタッチ感を Key Touch の設定よりさらに細かく調節
します。
Key Touch の設定値間をさらに 10 段階で設定することが
できます。
パラメーター 設定値 解説
Key Touch
Offset
68
-10 〜 +9
HEAVY よりさらに重
い設定です。
値が大きいほどタッ
チ感が重くなります。
鍵域によるタッチ感を変える
(Velocity Keyfollow Sens)
鍵域による鍵盤のタッチ感を設定します。
値が大きいほど、鍵域の高い鍵はより重く、鍵域の低い鍵は
より軽い設定になります。
パラメーター
Velo Keyfolw Sens -63 〜 +63
設定値

各機能の詳細設定をする([EDIT])
ペダル/[CONTROL]つまみ
/イコライザーの設定
(Control/EQ)
ペダルや[CONTROL]つまみに割り当てられている機能を
変更したり、イコライザーの設定を変えることができます。
設定のしかた
1.
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
2.
CURSOR [ ]/[ ]を押して「2.Control/
EQ」を選びます。
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
3.
す。
fig.conteq1.eps150
ペダルに機能を割り当てる
(FC1/FC2)
リア・パネルの FC1 / FC2 端子に接続したペダル・スイッ
チやエクスプレッション・ペダル(別売 EV-5 など)の働き
を設定します。
パラメーター 設定値 機能/変化する設定項目
OFF コントロールしません。
CC01 - CC31,
CC33 - CC95
96:
PITCH BEND
97: AFTER
TOUCH
98: OCT UP
99:
OCT DOWN
コントローラー・ナン
バー 1 〜 31、33 〜 95
ベンダーを左右に倒した
ときと同じ効果(ピッチ・
ベンド)がかかります。
アフタータッチ
ペダルを踏むごとに、鍵
域がオクターブ単位(最
大3オクターブ)で上が
ります。
ペダルを踏むごとに、鍵
域がオクターブ単位(最
大3オクターブ)で下が
ります。
fig.conteq2.eps150
4.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
5.
6.
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
FC1
FC2
100:
START/STOP
101:
TAP TEMPO
102: RHY
PLY/STP
103:
RHYTHM
TYPE
104:
ARPEGGIO
SW
105:
MFX ON/OFF
106:
CONTROL
SRC
外部シーケンサーをス
タート/ストップします。
ペダルを踏む間隔でテン
ポを設定します。
リズム(P.47)をスター
ト/ストップします。
リズムのタイプ(P.78)
を切り替えます。
[ARPEGGIO]と同じ働き
です。アルペジエーター
(P.45)をオン/オフしま
す。
MULTI EFFECTS[ON/
OFF]と同じ働きです。
マルチエフェクト(P.49)
をオン/オフします。
後述の Src の設定(P.70)
と同じ MIDI メッセージを
送信します。
詳 細 設 定
69

各機能の詳細設定をする([EDIT])
[CONTROL]つまみの設定を変える (Control/Src)
通常、[CONTROL]つまみは、マルチエフェクトの効果を
調節する設定(MFX CONTROL)になっていますが、この
つまみでトーンの鳴らしかたやテンポを変える設定にするこ
とができます。
パラメーター 設定値 解説
OFF
[CONTROL]つまみ
MFX CONTROL
Control
TONE CONTROL
TEMPO
CONTROL
OFF、
CC1 〜 31、
CC33 〜 95、
Src
Control に TONE CONTROL を設定したとき、
[CONTROL]つまみで変化するパラメーターを変更するこ
とはできません。変化するパラメータはトーンごとに決まっ
ています。
また、音色によって(GM 音色など)は、効果がかからない
ことがあります。
詳 細 設 定
Control に TONE CONTROL を設定しているときは、
MULTI EFFECT[ON/OFF]のオン/オフにかかわらず、
[CONTROL]つまみを回すとトーンの鳴りかたが変化しま
す。
96:
PITCH BEND、
97:
AFTER TOUCH
でマルチエフェクトの
かかり具合を調節しま
す。
[CONTROL]つまみ
でトーンの鳴らしかた
を変えます。
[CONTROL]つまみ
でテンポを変えます。
[CONTROL]つまみ
の設定をどの MIDI
メッセージを使って送
信するか設定します。
ただし、Control に
TEMPO CONTROL
を選んでいるときは、
MIDI メッセージは送
信されません。
イコライザーの周波数設定を変える
(Freq/Q)
EQUALIZER つまみの周波数設定を変えます。
パラメーター 設定値 解説
低音域の周波数ポイ
EQ Low Freq 200、400 Hz
200、250、
315、400、
500、630、
800、1000、
EQ Mid Freq
EQ Mid Q
EQ High Freq
<Band>
Gain
System の EQ Control の設定(P.66)を SYSTEM にする
と、上記パラメーターを設定することはできません。画面に
は「---」が表示されます。
1250、1600、
2000、2500、
3150、4000、
5000、6300、
8000 Hz
0.5、1.0、
2.0、4.0、8.0
2000、4000、
8000 Hz
LOW、MID、
HIGH
-12.0 〜+ 12.0
dB
(0.2 dB 単位)
ント。おおむねこの
周波数以下の帯域の
レベルが変わります。
中音域の周波数ポイ
ント。この周波数を
中心とする所定帯域
のレベルが変わりま
す。
中音域の帯域幅を変
えます。数値が大き
くなると、コント
ロールできる帯域が
狭くなります。
高音域の周波数ポイ
ント。おおむねこの
周波数以上の帯域の
レベルが変わります。
Gain を設定する音
域を選びます。
EQUALIZER つまみ
の LOW、MID、
HIGH と対応してい
ます。
< Band >で設定し
た音域のゲインを変
えます。
EQUALIZER つまみ
を回してもこの値が
変わります。
70

各機能の詳細設定をする([EDIT])
「フィート」とは
フィートは、もともとパイプ・オルガンのパイプの長さ
に由来します。各鍵盤に与えられた本来の音の高さ(基
音)を生み出すパイプの長さは 8 フィートとされていま
す。パイプの長さを半分に縮めると 1 オクターブ高い
ピッチを生み出し、逆にパイプの長さを倍にすると 1 オ
クターブ低いピッチを生み出します。したがって基音で
ある 8' の 1 オクターブ下が 16'、1 オクターブ上が 4'、
さらにその 1 オクターブ上が 2' になります。
オルガンの音作りをシミュレートする
(トーン・ホイール・モード)
ローカル・
かのパートに「Tone Wheel 1 〜 10」のいずれかのトーンを
選んでいるときに、オルガンの音作りをシミュレートする
「トーン・ホイール・モード」で演奏することができます。
オルガンでは、ハーモニック・バーという 9 本のバーを前
後にスライドさせて、その組み合わせでさまざまな音色を作
ります。各バーには異なるフィートが割り当てられており、
フィートによって音の高さが決まっています。
このハーモニック・バーを使った音作りを、PART LEVEL
スライダーにフィートを割り当ててシミュレートすることが
できます。
PART LEVEL スライダーは 4 本ですが、PART SWITCH ボ
タンをオン/オフすることで、フィートを切り替え、計 8
つのフィートをスライダーに割り当てることができます。
1.
[MIDI TX]を押して、一度インジケーターを点灯させ
2.
「Tone Wheel1 〜 10」のいずれかのトーンを選びます。
パート(UPPER1、UPPER2、LOWER)のいずれ
トーン画面を表示させます(P.28)。
トーン画面が表示されていないときは、[EDIT]または
てから、消灯させてください。
トーン画面で、いずれかのパートに[ORGAN]の
トーン・ホイール画面が表示されているときは、TONE
SELECT ボタンで Tone Wheel1 〜 10 を選ぶことがで
きます。
5.
PART LEVEL スライダーを動かすと、画面のハーモ
ニック・バーがスライドし、音色が変わります。
各PART SWITCH ボタンをオン/オフすると、異なる
フィートの音を調節することができます。
カーソルを画面下段の値に移動させると、[DEC/NO]
または[INC/YES]でフィートの音を調節することがで
きます。
6.
CURSOR[ ]/[ ]を押して、カーソルを
< Perc:>に移動すると、[DEC/NO]または[INC/
YES]で値を変えることができます。
Perc(パーカッション)は、音の立ち上がり部分にア
タック感のある音を加えて、音にメリハリをつけます。
値によって立ち上がりの音色が変わります。
パーカッションは、UPPER1 のトーンにしかかかりません。
設定値 解説
OFF
2nd
3rd
Slow
Fast
ここで変更した設定は各トーンに記憶されます。
トーン・ホイール・モードを抜けても、[ORGAN]を押し
て、設定を変更したトーンを選ぶことができます。
パーカッションがつきません。
押した鍵盤の高さより1オクターブ高い音の
パーカッションが鳴ります。
押した鍵盤の高さより1オクターブと 5 度
高い音のパーカッションが鳴ります。
パーカッションの減衰時間が長くなります。
アタック感がやわらくなります。
パーカッションの減衰時間が短くなります。
アタック感のある、鋭い音になります。
3.
CURSOR[ ]を押します。
次のようなトーン・ホイール画面が表示されます。
このトーン・ホイール画面はトーン画面でいずれかの
パートに Tone Wheel 音色を選んでいるときだけ表示さ
れます。
fig.LCD
4.
TONE SELECT ボタンを押して、Tone Wheel1 〜 10 の
いずれかを選びます。
オルガン音色のうねりを変える
(ロータリー効果)
トーン・ホイール画面を表示しているときは、ピッチ・ベン
ド・レバーでロータリー効果のうねりの速さを切り替えるこ
とができます。
ロータリー効果とは、オルガンの音に回転スピーカーを使っ
たときのようなうねりをつける効果のことです。
ピッチ・ベンド・レバーを左右に動かすと、動かす方向に関
係なく、ロータリー効果の速い/遅いが交互に設定されま
す。
このピッチ・ベンド・レバーの設定はトーン・ホイール画面
でのみ有効です。
詳 細 設 定
71

各機能の詳細設定をする([EDIT])
8'16' 5 1/3' 2'4' 2 2/3' 1'1 3/5'
1 1/3'
トーン・ホイール画面のフィートの割り当て(画面左から)
PART LEVEL スライダーのフィー
トの割り当てを変える
(Harmonic Bar)
トーン・ホイール・モードの各 PART LEVELスライダーに
割り当てられているフィートを変更することができます。
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して「2.Control/
2.
EQ」を選びます。
CURSOR[ ]を押して、エディット画面を表示しま
3.
す。
fig.conteq3.eps150
マルチエフェクト/リバーブ/
コーラスの設定
(MFX/Reverb/Chorus)
RD-700 には、マルチエフェクト、コーラス、リバーブの 3
系統のエフェクターが内蔵されています。各エフェクター
は、独立して設定することができます。
設定のしかた
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して「3.MFX/
2.
Reverb/Chorus」を選びます。
3.
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
す。
fig.mfx1.eps150
fig.conteq3.eps150
CURSOR[ ][][][]を押して、
4.
フィートを変更するパラメーターにカーソルを移動しま
す。
画面の「LED ON」「LED OFF」は、PART SWITCH の
オン/オフ切り替えを表しています。
詳 細 設 定
PART SWITCH 設定値
RHY
LWR
UP2
UP1
5.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押してフィートを設定し
ます。
fig.mfx2.eps150
「CHORUS」の設定画面
16'、5-1/3'、8'、4'、2-2/3'、
2'、1-3/5'、1-1/3'、1'
fig.mfx3-1.eps150
「DELAY」の設定画面
fig.mfx3-2.eps150
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
6.
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
72

4.
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
5.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
6.
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
マルチエフェクトの設定をする
各機能の詳細設定をする([EDIT])
MFX Source を FIXED にすると、MFX Dest は ALL PART
に固定され、すべてのパートにマルチエフェクトがかかる設
定になります。
Type
マルチエフェクトのタイプを選びます。
65 種類のエフェクトがあります。設定できる値は、
クト/パラメーター一覧
」(P.100)をご覧ください。
「エフェ
マルチエフェクトは、音そのものを変化させて、まったく違
う種類の音に変える汎用マルチエフェクトです。65 種類の
タイプを持ち、その中から目的に合ったものを選んで使いま
す。ディストーション、フランジャーなどの単一のエフェク
トで構成されたもの以外にそれらを直列や並列につないだも
のまでさまざまなタイプが用意されています。また、マルチ
エフェクトのタイプの中にもリバーブ、コーラスがあります
が、後述のリバーブ(P.74)やコーラス(P.74)とは別系
統で扱います。
MFX Source、MFX Dest
RD-700 では、各パートに割り当てられている各トーンに
MFX Type を記憶させておくことができます。ここでは、
どのマルチエフェクトの設定を使うか、そのマルチエフェク
トをどのパートにかけるか、を設定します。
パラメーター 設定値 解説
トーンを変えてもマルチ
エフェクトが切り替わら
FIXED
MFX
Source
UPPER1,
UPPER2,
LOWER,
RHYTHM
ないようにします。
トーンを変えても同じマ
ルチエフェクトをかけて
おきたいときに便利です。
選んだパートに割り当て
られているトーンの MFX
Type が有効になります。
MFX Source の設定が UPPER1、UPPER2、LOWER、
RHYTHM のときは、各パートの Tone Edit の MFX Type
の設定(P.76)も変わります。
MFX Control
[CONTROL]つまみでマルチエフェクトのパラメーターを
リアルタイムに変化させることができます。ここでは、どの
パラメーターを変化させるかを設定します。
変化させることのできるパラメーターは Type に設定されて
いるマルチエフェクトによって異なります。
「エフェクト/パラメーター一覧」(P.100)をご覧ください。
< Other Prm >、Value
マルチエフェクトのパラメーターを設定をすることができま
す。Other Prm を設定すると、それに合わせて Value の表示
が変わり、値を設定します。設定できる値は、「エフェクト
/パラメーター一覧
Internal Part Prm の MFX Switch の設定(P.86)が「OFF」
になっているパートには、マルチエフェクトはかかりません。
マルチエフェクトのタイプによっては、マルチエフェクトを
かけたパートの音量を下げると、エフェクトのかかり具合が
変わってしまうことがあります。そのような場合は、MFX
の< Other Parm >でレベル(Level)を調節してください。
」(P.100)をご覧ください。
MFX Dest
SOURCE
PART
SAME MFX
ALL PART
MFX Source で選んだ
パートにだけマルチエ
フェクトがかかります。
MFX Source で選んだ
パートのマルチエフェク
トと同じマルチエフェク
トが設定しされている
パートに、マルチエフェ
クトがかかります。
すべてのパートにマルチ
エフェクトがかかります。
マルチエフェクトの中には、値を音符記号で設定できるパラ
メーターがあります。(例:16:STEP FLANGER の STEP
RATE など。)このようなパラメーターを MFX Control と<
Other Prm >に割り当てたとき、Value に音符記号が設定さ
れていると、[Control]つまみで変化させることができませ
ん。
つまみで値を変えたいときは、数値で設定してください。
Feedback パラメーターの値が最小または最大になっている
と、音が鳴り続けることがありますので、ご注意ください。
73
詳 細 設 定

各機能の詳細設定をする([EDIT])
リバーブの設定をする
リバーブはホールで音を鳴らしているような響きを与えるエ
フェクトです。4 種類のタイプを持ち、その中から目的のも
のを選んで使います。
トーンごとにリバーブのかかり具合を設定することができま
す(P.76)。
Reverb Type
リバーブ・タイプを変更すると、リバーブの設定項目が、自
動的に最適な値に変更されます。リバーブの設定項目をひと
つひとつ設定するより、リバーブ・タイプを先に設定し、そ
の後必要な設定項目だけを変更するほうが、設定が楽にでき
ます。
パラメーター
Reverb Type
設定値 解説
OFF
REVERB
SRV ROOM
SRV HALL
SRV PLATE
リバーブを使いませ
ん。
基本的なリバーブで
す。
室内での残響を再現し
たリバーブです。きれ
の良い、広がりのある
残響が得られます
ホールでの残響を再現
したリバーブです。
Room より奥行き感の
ある響きが得られま
す。
プレート・エコー(金
属板の振動を利用した
リバーブ)を再現して
います。
Reverb Time
リバーブ音の余韻の長さを設定します。
値が大きいほど余韻が長くなります。
設定値:0 〜 127
Reverb High Cut
最終出力音の高域成分をカットする基準周波数を設定しま
す。カットしないときは、Bypass に設定します。
設定値:160、200、250、320、400、500、640、800、
1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000、
5000、6400、8000、10000、12500、BYPASS
< Other Prm >、Value
リバーブに関するさらに細かい設定をすることができます。
Other Prm を設定すると、それに合わせて Value の表示が変
わり、値を設定します。設定できる値は、
(P.130)をご覧ください。
「REVERB」
コーラス/ディレイの設定をする
コーラスは音に厚みや広がりを与えるエフェクトです。コーラ
スとして使うか、ディレイとして使うか選ぶことができます。
トーンごとにコーラスのかかり具合を設定することができま
す(P.76)。
Chorus/Deley
コーラスとして使うかディレイとして使うかを選びます。
設定値:Chorus、Delay
Chorus/Delay が Chorus の場合
詳 細 設 定
Reverb Type の設定によっては、設定できないパラメー
ターがあります。設定ができないパラメーターには「-------
-」と表示されます。
Reverb Pre-Delay
原音が鳴ってからリバーブ音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
値が大きいほど遅延時間が長くなります。
設定値:0.0 〜 100.0
74
Chorus Pre-Dly
原音が鳴ってからコーラス音が鳴るまでの遅延時間を設定し
ます。
値が大きいほど遅延時間が長くなります。
設定値:0.0 〜 100.0
Chorus Rate
コーラス音の揺れの周期を設定します。
値が大きいほど短い間隔で音が揺れます。
設定値:0.05 〜 10.00

各機能の詳細設定をする([EDIT])
Chorus Feedback
コーラス音を再びコーラスへ入力する(フィードバック)レ
ベルを設定します。フィードバックすることで、より密度の
高いコーラス効果を得ることができます。
値を大きくするほどフィードバック・レベルが上がります。
設定値:0 〜 127
< Other Prm >、Value
コーラスに関するさらに細かい設定をすることができます。
Other Prm を設定すると、それに合わせて Value の表示が変
わり、値を設定します。設定できる値は、
(P.130)をご覧ください。
「CHORUS」
Chorus/Delay が Delay の場合
Delay-Center
中央に定位したディレイ音のディレイ・タイム(音を遅らせ
る時間)を調節します。
設定値
:0 〜 1000(ms)、音符
トーンの設定(Tone Edit)
内部パート(Internal Part)の各パートに割り当てられている
トーンを細かく設定することができます。
選んでいるトーンによっては、変更することができないパラ
メーターがあります。
設定のしかた
1.
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu1.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して「4.Tone Edit」
2.
を選びます。
3.
CURSOR []を押して、エディット画面を表示します。
fig.tone1.eps150
Delay-Left
左に定位したディレイ音のディレイ・タイム(音を遅らせる
時間)を調節します。
設定値:0 〜 1000(ms)、音符
Delay-Right
右に定位したディレイ音のディレイ・タイム(音を遅らせる
時間)を調節します。
設定値:0 〜 1000(ms)、音符
Delay Center、Delay Left、Delay Right の設定値は特定の
テンポに対する音符の長さで設定することもできます。その
場合は、音符記号の値を設定してください。
< Other Prm >、Value
ディレイに関するさらに細かい設定をすることができます。
Other Prm を設定すると、それに合わせて Value の表示が変
わり、値を設定します。設定できる値は、
(P.130)をご覧ください。
「DELAY」
fig.tone2.eps150
fig.tone3-1.eps150
4.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
5.
6.
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
詳 細 設 定
75

各機能の詳細設定をする([EDIT])
設定するパート、トーンを選ぶ
(< Part >、Tone)
設定するパートとトーンを選びます。
パラメーター 設定値
1〜16
<Part>
Tone
ローカル・パートが割り当てられてい
るパートは、パート名の後に
(UPPER1)のように表示されます。
< Part >で選んだパートに割り当てら
れているトーンが表示されます。
TONE SELECT ボタンを使ってトーン
を選ぶこともできます。
リバーブ/コーラスの深さを設定をす る(Reverb / Chorus Amount)
リバーブ効果、コーラス効果の深さを設定します。
この設定値が「0」になっていると、REVERB つまみまたは
CHORUS つまみを回しても、効果がかかりません。
トーンにかける効果を変える(MFX)
トーンにかけるマルチエフェクトを設定します。
MFX Source や MFX Dest の設定によっては、ここで選ん
だマルチエフェクトがかからないことがあります。詳しく
は、
「MFX Source、MFX Dest」(P.73)をご覧ください。
パラメーター 設定値
MFX
「エフェクト/パラメーター一覧
(P.100)をご覧ください。
」
単音で発音させる(Mono / Poly)
トーンの鳴らしかたをポリフォニック(POLY)にするか、
モノフォニック(MONO)にするかを設定します。
単音楽器(サックスやフルートなど)のトーンを使うとき
は、MONO にすると効果的です。
また、MONO/LEGATO に設定すると、モノフォニックで演
奏するときにレガートをかけることができます。レガートと
は、音と音の間をなめらかに切れ目を感じさせないで演奏す
る方法です。ギターのハンマリング・オンやプリング・オフ
のような効果が得られます。
Reverb Amount 0〜127
Chorus Amount 0〜127
Reverb/Chorus Amount のかかりかた
この設定は、MFX Source / MFX Dest の設定(P.73)に
よって、効果のかかりかたが異なります。
- MFX Dest の設定が、ALL PART なっている場合
MFX Source で選ばれているパートの Reverb/
詳 細 設 定
Chorus Amount が、全体にかかります。
ただし、MFX Source が FIXED の場合には、
UPPER1 のパートが、全体にかかります。
- MFX Dest の設定が SAME MFX になっている場合
MFX Source のパートと同じ MFX Type が割り当て
られているパートに、MFX Source のパートの
Reverb/Chorus Amount がかかります。
パラメーター
設定値
パラメーター 設定値 解説
1 音ずつ最後に押した鍵の
音だけを鳴ります。
モノフォニックでレガート
をかけます。
Mono/Poly
MONO
POLY 複数の音が同時に鳴ります。
MONO/
LEGATO
音の高さ(ピッチ)を変える
(Coarse / Fine Tune)
トーンの音の高さ(ピッチ)を設定します。
パラメーター
Coarse Tune
Fine Tune
1 セント = 半音の 100 分の 1
設定値 解説
-48 〜 +48
(+/- 4 オクターブ)
-50 〜 +50
(+/- 50 セント)
音の高さを半音単
位で設定します。
音の高さを 1 セ
ント単位で設定し
ます。
76
トーンによっては、ピッチが思ったように変化しない音域が
あります。

各機能の詳細設定をする([EDIT])
音をなめらかに変化させる
(Portamento Switch / Time)
はじめに弾いた鍵と次に弾いた鍵との間の音程をなめらかに
変化させる効果のことを「ポルタメント」といいます。
Mono/Poly の値を MONO に設定したときにポルタメント
をかけると、バイオリンなどのスライド奏法のような効果が
得られます。
ポルタメント・タイムは、ポルタメント効果をかけた音の高
さが変化する時間を設定します。値が大きくなるほど、次の
音の高さに移動する時間が長くなります。
パラメーター 設定値
Portamento Switch ON、OFF
Portamento Time 0〜127
トーンの要素を変化させる
(Attack Time / Release Time
/ Cutoff / Resonance)
トーンの次の 4 つの要素を設定することで、音色に変化を
与えることができます。
Attack Time:アタック・タイム:
キーを押さえてから、音が立ち上がるまでの時間です。
Release Time:リリース・タイム:
キーを離してから、音が消えるまでの時間です。
Cutoff :カットオフ:
フィルタの開き具合を調節します。
Resonance:レゾナンス:
カットオフ周波数付近の音の成分を強調し、音にクセをつけ
ます。設定値を上げすぎると発振して音が歪むことがありま
す。
パラメーター 設定値 解説
値を大きくすると音が
Cutoff -63 〜 +63
Resonance -63 〜 +63
この設定を変えても、音色によっては、思ったような効果が
得られないことがあります。
明るくなり、小さくす
ると暗くなります。
値が大きくなるとクセ
が強くなり、小さくす
ると弱くなります。
ベンド・レンジを変える
(Bend Range)
ピッチ・ベンド・レバーを動かしたときのピッチの変化量を
半音単位で設定します(2 オクターブ)。
パラメーター
Bend Range 0〜24
設定値
和音の響きを微妙に変える
(Stretch Tune)
高音域はより高く、低音域はより低いピアノ独特の調律手法
(ストレッチ・チューニング)でピッチを設定します。
OFF にすると平均律になり、3 にすると高音域と低音域の
ピッチ変化がもっとも大きくなります。
パラメーター
設定値 解説
OFF 標準的な調律曲線です。
設定値を急激に変化させると、音が歪んだり、音が大きくな
りすぎることがあります。音量に注意しながら設定してくだ
さい。
パラメーター
Attack Time -63 〜 +63
Release Time -63 〜 +63
設定値 解説
値を大きくすると立ち
上がりがゆるやかに、
小さくすると立ち上が
りが鋭くなります。
値を大きくすると余韻
の長い音になり、小さ
くすると歯切れの良い
音になります。
Stretch Tune
1
2
3
やや低音域と高音域を拡大し
た調律曲線です(ストレッ
チ・チューニング)。ピアノ
の独奏などに適しています。
詳 細 設 定
77

各機能の詳細設定をする([EDIT])
リズムの設定
(Rhythm Pattern)
RD-700 には、ジャズやロックなどさまざまな音楽ジャンル
のドラム・パターンを内蔵しています。このドラム・パター
ンのことを「リズム」といいます。
リズムのオン/オフについては、「リズムを鳴らす
([RHYTHM])
設定のしかた
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して「5.Rhythm
2.
Pattern」を選びます。
」(P.47)をご覧ください。
パラメーター 設定値
Tempo 20 〜 250
Clock Source(P.66)が MIDI のときは「M:」と表示さ
れ、外部 MIDI 機器のテンポに同期します。「M:」と表示さ
れているときは、RD-700 でテンポを変えることはできませ
ん。
パターンを変える(Pattern)
リズムのパターンを設定します。85 種類の中から選びます。
OFF に設定すると、PART SWITCH[RHYTHM]を押して
も、リズムが鳴らなくなります。
パラメーター 設定値
Pattern
リズムのパターンは、「リズム/アルペジオ画面」(P.48)
でも変更することができます。
「リズム・パターン一覧」(P.139)をご覧く
ださい。
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
3.
す。
fig.rhythm1.eps150
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
4.
メーターにカーソルを移動します。
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
5.
6.
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
詳 細 設 定
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
テンポを変える(Tempo)
リズムのテンポを設定します。
RD-700 のテンポ設定はひとつです。この設定を変えると、
トーン画面のテンポ表示や、アルペジエーターのテンポ設定
(P.80)も変わります。
リズムの再生中にパターンを変えると、小節の区切りで次の
パターンに変わります。
リズムのバリエーションを選ぶ
(Rhythm Type)
各リズム・パターンは、構成される打楽器音が異なるバリ
エーションを持っています。
「タイプ 1」はシンプルなリズム、「タイプ 2」はより構成音
の多い、派手なリズムになります。
パラメーター
Rhythm Type 1、2
この設定を、2 にすると、各画面の右上に「 」マークが
表示されます。
この機能をペダルに割り当てて操作することができます。詳
しくは、
をご覧ください。
リズムの再生中にタイプを変えると、1小節のフィルイン
(短いフレーズ)が挿入され、次のタイプが演奏されます。
「ペダルに機能を割り当てる (FC1/FC2)」(P.69)
設定値
78

各機能の詳細設定をする([EDIT])
リズム・セットを変える
(Rhy Set)
リズムのリズム・セット(ドラムやパーカッションの音色
セット)を変えることができます。
パラメーター 設定値
Rhy Set
リズム・セット以外のトーンを選ぶこともできます。
この設定を変えると、パート 10 のトーンも変わります。
選ぶリズム・セットによっては、リズムが正しく鳴らないこ
とがあります。
「リズム・セット一覧」(P.134)をご覧
ください。
パターンを変えてもドラム・セットを 変えない(Rhy Set Change)
アルペジエーターの設定
(Arpeggio)
和音(コード)を弾くだけで、その構成音に従ってアルペジ
オ(分散和音)演奏をすることができる機能を「アルペジ
エーター」といいます。
アルペジオのテンポや音域など、より細かい設定を行うこと
ができます。
アルペジエーターのオン/オフについては、「弾いた和音を
アルペジオにする([ARPEGGIO])
い。
設定のしかた
1.
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
」(P.45)をご覧くださ
各リズム・パターンは、それぞれのリズムに最適なリズム・
セットが割り当てられています。リズム・パターンを変える
と、リズム・セットも切り替わり、音色が変わりますが、こ
の設定を OFF にすると、リズム・セットを変えずに固定に
します。
パラメーター 設定値 解説
リズム・パターンを変える
ON
Rhy Set
Change
OFF
と、リズム・セットも変わ
ります。
リズム・パターンを変えて
も、リズム・セットは変わ
りません。
イントロ/エンディングのオン/オフ を設定する(Intro/Ending)
リズムのイントロ、エンディングの鳴らす、鳴らさないを選
びます。
パラメーター 設定値 解説
2.
CURSOR [ ]/[ ]を押して「6.Arpeggio」
を選びます。
3.
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
す。
fig.arpeggio1.eps150
fig.arpeggio2.eps150
4.
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
詳 細 設 定
Intro/Ending
ON
OFF
リズムにイントロ/エン
ディングをつけます。
リズムにイントロ/エン
ディングをつけません。
5.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
6.
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
79

各機能の詳細設定をする([EDIT])
テンポを変える(Tempo)
アルペジオ演奏の速さを設定します。
RD-700 のテンポ設定はひとつです。この設定を変えると、
トーン画面のテンポ表示や、リズムのテンポ設定(P.78)
も変わります。
パラメーター 設定値
Tempo 20 〜 250
Clock Source(P.66)が MIDI のときは「M:」と表示さ
れ、外部 MIDI 機器のテンポに同期します。「M:」と表示さ
れているときは、RD-700 でテンポを変えることはできませ
ん。
アルペジオ演奏するパートを選ぶ
(Dest.Part)
スプリット・モードやレイヤー・モードで演奏しているとき
(P.37)、どのパートでアルペジオ演奏するかを設定します。
パラメーター 設定値
Dest.Part
アルペジオの演奏を MIDI OUT 端子から送信するときは、
「ALL」に設定してください。
UPPER1、UPPER2、LOWER、ALL
アルペジオ演奏する鍵域を設定する
(Key Range)
アルペジオ演奏をする鍵域では、通常の演奏はできなくなり
ますが、アルペジオ演奏する鍵域を指定しておけば、例えば
詳 細 設 定
シングル・モード(P.37)でも鍵域をわけて、鍵盤左側で
アルペジオ演奏の伴奏をつけ、右側でメロディーを弾くこと
ができます。
アルペジオする鍵域の一番左の鍵と、右の鍵を指定します。
パラメーター 設定値
アルペジオのしかた(スタイル)を設 定する(Style)
アルペジオのスタイルを設定します。以下の 45 種類の中か
ら選びます。
パラメーター 設定値 解説
1/4
1/6
1/8
1/12
1/16
1/32
PORTAMENTO
A、B
GLISSANDO
SEQUENCE A 〜Dシーケンス・パターンの
Style
ECHO
SYNTH BASS、
HEAVY SLAP、
LIGHT SLAP、
WALK BASS
RHYTHM GTR 1
〜5
3 FINGER
STRUM GTR
UP、STRUM
GTR DW、
STRUM GTR UD
4 分音符の間隔でリズム
を刻みます。
3連 4分音符の間隔でリ
ズムを刻みます。
8 分音符の間隔でリズム
を刻みます。
3連 8分音符の間隔でリ
ズムを刻みます。
16 分音符の間隔でリズ
ムを刻みます。
32 分音符の間隔でリズ
ムを刻みます。
ポルタメント効果を伴っ
たスタイルです。
グリッサンドのスタイル
です。
ようなスタイルです。
やまびこのようなスタイ
ルです。
ベースの演奏に適したス
タイルです。
ギターのカッティングの
スタイルです。2 〜 5 の
スタイルは 3 〜 4 音押さ
えると効果的です。
ギターのスリー・フィン
ガーのスタイルです。
ギターで、コードを弾き
上げ(下ろし)たような
スタイルです。5 〜 6 音
押さえると効果的です。
Key Range A0 〜 C8
80
PIANO BACK.、
CLAVI CHORD
WALTZ、
SWING WALTZ
鍵盤楽器のバッキングの
スタイルです。
3 拍子のスタイルです。

各機能の詳細設定をする([EDIT])
パラメーター 設定値 解説
レゲエ風のスタイルで
REGGAE
PERCUSSION
HARP
SHAMISEN
BOUND BALL
RANDOM
BOSSA NOVA
SALSA
Style
MAMBO
LATIN PERC
す。3 音押さえると効果
的です。
打楽器音に適したスタイ
ルです。
ハープ演奏のようなスタ
イルです。
三味線の演奏のようなス
タイルです。
ボールが弾んだようなス
タイルです。
音の鳴る順番がランダム
(無作為)なスタイルで
す。
ボサ・ノヴァのギターの
カッティングのスタイル
で、3 〜 4 音押さえると
効果的です。テンポを速
くするとサンバとしても
使えます。
サルサの典型的なスタイ
ル。3 〜 4 音押さえると
効果的です。
マンボの典型的なスタイ
ル。3 〜 4 音押さえると
効果的です。
Clave、Cowbell、Clap、
Bongo、Conga、
Agogo などのラテン系
打楽器用のリズム・スタ
イルです。
アルペジオの音域を変える
(Octave Range)
アルペジオ演奏をする音域をオクターブ単位で設定します。
弾いた和音の音だけで演奏したいときは 0 にします。
弾いた和音とその 1 オクターブ上の音で演奏するときは +1
に、弾いた和音とその 1 オクターブ下の音で演奏するとき
は-1に設定します。
パラメーター 設定値
Octave Range -3 〜 +3
音の鳴る順番をかえる(Motif)
押さえた鍵の鳴る順番を以下の中から設定します。
Style(P.80)の設定によっては選べないものもあります。
設定できる値については
(P.138)をご覧ください。
パラメーター
SINGLE UP
SINGLE DOWN
SINGLE
UP&DOWN
「アルペジオ・スタイル一覧」
設定値 解説
押さえたキーの低い方か
ら順番に、1 音ずつ鳴り
ます。
押さえたキーの高い方か
ら順番に、1 音ずつ鳴り
ます。
押さえたキーの低い方か
ら高い方へ、さらに折り
返して低い方へ順番に、
1 音ずつ鳴ります。
SAMBA
TANGO
HOUSE
LIMITLESS
サンバの典型的なスタイ
ル。リズム・パターンや
ベース・ラインに使えま
す。
タンゴの典型的なリズ
ム・スタイル。3 和音の
ルート、3rd、5th などの
押さえかたが効果的です。
ハウス系ピアノ・バッキ
ングのスタイルです。3
〜4音で押さえると効果
的です。
各設定項目の設定を、制
限なく自由に組み合わせ
られます。
Motif
SINGLE
RANDOM
DUAL UP
DUAL DOWN
DUAL
UP&DOWN
DUAL RANDOM
押さえたキーの音がラン
ダム(無作為)に、1 音
ずつ鳴ります。
押さえたキーの低い方か
ら順番に、2 音ずつなり
ます。
押さえたキーの高い方か
ら順番に、2 音ずつなり
ます。
詳 細 設 定
押さえたキーの低い方か
ら高い方へ、さらに折り
返して低い方へ順番に、
2 音ずつ鳴ります。
押さえたキーの音がラン
ダム(無作為)に、2 音
ずつ鳴ります。
81

各機能の詳細設定をする([EDIT])
パラメーター 設定値 解説
押さえたキーの低い方か
ら順番に、3 音ずつ鳴り
ます。
押さえたキーの高い方か
ら順番に、3 音ずつ鳴り
ます。
押さえたキーの低い方か
ら高い方へ、さらに折り
返して低い方へ順番に、
3 音ずつ鳴ります。
押さえたキーの音が、ラ
ンダム(無作為)に 3 音
ずつ鳴ります。
キーを押さえた順番にな
ります。32 音まで記憶
することができるので、
キーを押さえる順番を工
夫すれば、メロディー・
ラインを作ることができ
ます。
押さえた和音の最低音と
最高音の間を、半音ずつ
上昇、下降を繰り返しな
がら鳴ります。和音を弾
くときは、最低音と最高
音の 2 つを押さえるよう
にします。
押さえたキーの音がすべ
て同時になります。
Motif
TRIPLE UP
TRIPLE DOWN
TRIPLE
UP&DOWN
TRIPLE
RANDOM
NOTE ORDER
GLISSANDO
CHORD
グルーヴ感を変える(Beat Pattern / Accent Rate / Shuffle Rate)
Beat Pattern
リズムの種類を以下の中から設定します。それぞれアクセン
トの位置や音の長さが異なりますので、いろいろなリズムで
演奏することができます。
Style(P.80)の設定によっては選べないものもあります。
設定できる値については
(P.138)をご覧ください。
パラメーター 設定値
1/4、1/6、1/8、1/12、1/16 1 〜 3、
1/321〜3、PORTA-A 01 〜 11、
PORTA-B 01 〜 15、SEQ-A 1 〜 7、SEQ-B
1〜5、SEQ-C 1 〜 2、SEQ-D 1 〜 8、
Beat
Pattern
PORTA-A 01 〜 11、PORTA-B 01 〜 15 を選んだ場合は、
Tone Edit の Portamento Time(P.77)でポルタメントの
立ち上がりをコントロールできます。このとき、
Portamento Switch を ON にする必要はありません。
ECHO 1 〜 3、MUTE 01 〜 16、STRUM
1〜8、REGGAE1 〜 2、REFRAIN1 〜 2、
PERC1 〜 4、WALKBS、HARP、BOUND、
RANDOM、BOSSA NOVA、SALSA 1 〜 4、
MAMBO 1 〜 2、CLAVE、REV CLA、
GUIRO、AGOGO、SAMBA、TANGO
1〜4、HOUSE 1 〜 2、3/4、SWING 3/4
「アルペジオ・スタイル一覧」
詳 細 設 定
BASS+CHORD
1〜5
BASS+UP 1 〜 8
BASS+RND
1〜3
TOP+UP 1 〜 6
BASS+UP+TOP
押さえたキーの最低音
と、それ以外の音を和音
で鳴らします。
押さえたキーの最低音
と、それ以外の音を分散
させて鳴らします。
押さえたキーの最低音
と、それ以外の音をラン
ダム(無作為)に鳴らし
ます。
押さえたキーの最高音
と、それ以外の音を分散
させて鳴らします。
フォーク・ギターのス
リー・フィンガー奏法の
運指をシミュレーション
して鳴らします。
Accent Rate
アクセントの強さや音の長さを変えて、演奏のグルーブ感を
変化させます。100% のときに最もグルーブ感が出ます。
パラメーター 設定値
Accent Rate
0〜100%
Shuffle Rate
発音のタイミングを変化させて、シャッフルのリズムを作る
ことができます。50% のときは等間隔で鳴り、値が大きく
なるにつれて付点音符のような弾んだ感じになります。
パラメーター 設定値
Shuffle Rate 50 〜 90%
fig. 図(Shuffle Rate 図f igR05-01)
Shuffle Rate = 50%
50 50 50 50
Shuffle Rate = 90%
90 10 90 10
82

各機能の詳細設定をする([EDIT])
ボタンでホールドのオン/オフを切り替える
エディット画面でなくても、ボタン操作でホールドのオ
[ARPEGGIO]を押しながら[TRANSPOSE]を押
鍵盤パートやコントローラーの設
Beat Pattern(P.82)が 1/4 のときは、シャッフル・レイ
トの値を大きくしてもシャッフルはかかりません。
音の強さを一定にする(Velocity)
鍵盤を弾いたときの発音の強さを設定します。
パラメーター 設定値 解説
REAL
Velocity
1〜127
実際の鍵盤タッチの強さ
を再現します。
鍵盤タッチに関わらず設
定した値で一定の強さに
なります。
鍵盤から指を離してもアルペジオ演奏 を続ける(Arpeggio Hold)
ホールドの設定をオンにしておくと、鍵盤から指を離しても
アルペジオを演奏し続けることができます。
パラメーター
設定値 解説
定(Local Part Param)
RD-700 の内部で内蔵音源をコントロールする 16 個のパー
トのことを「内部パート(Internal Part)」と呼びます。
16 個の内部パートのうち 3 パートを、本体のボタンと鍵盤
で自由にコントロールするための 3 つのパート(UPPER1、
UPPER2、LOWER)に割り当てることができます。この 3
つのパートをまとめて「ローカル(Local)パート」といい
ます。
ローカル・パートは、RD-700 の鍵盤でスプリットやレイ
ヤーなどの操作も簡単にでき、パートごとにより細かい設定
が可能です。
設定のしかた
1.
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
ON
Arpeggio Hold
OFF
ホールド(Arpeggio Hold)の設定が ON になっているとき
は、[ARPEGGIO]のインジケーターは点滅しています。
ン/オフを切り替えることができます。
1.
します。
ボタンを押すごとにホールドのオン/オフが切り替
わります。
鍵盤から指を離してもアル
ペジオ演奏を続けます。
鍵盤から指を離すと、アル
ペジオ演奏が止まります。
2.
CURSOR [ ]/[ ]を押して「7.Local Part
Param」を選びます。
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
3.
す。
fig.intext1.eps150
fig.intext2.eps150
fig.IntExt3-1.eps150
詳 細 設 定
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
4.
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
83

各機能の詳細設定をする([EDIT])
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
5.
「Key Range」は、指定する鍵を押して設定することが
できます。
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
6.
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
鍵盤を弾く強さによる音量変化を設定 する(Velocity Sens/Max)
鍵盤を弾く強さ(ベロシティー)に対する音量の変化のしか
たと、変化の最大値を設定します。
トーンによって、この設定が無効なものがあります。
設定するパートを選ぶ
(< Local Part >)
設定するパートを選びます。
PART SELECT ボタンでも選ぶことができます。
パラメーター 設定値
<Local Part> UPPER1、UPPER2、LOWER
各パートの鍵域を設定する
(Key Range)
通常の演奏状態で[SPLIT]を押すと、スプリット・ポイン
トで鍵域が分かれ、一つの鍵盤で 2 つのトーンを鳴らすこ
とができます。
Key Range を使うと、さらに鍵域を細かく設定できます。
各パートの鍵域の下限と上限を設定します。
設定するパラメーターにカーソルを移動したら、指定する鍵
を押し、[ENTER]を押して設定することもできます。
パラメーター 設定値
Key Range A0 〜 C8
キー・レンジの設定は、[SPLIT]がオン(P.39)のときだ
け有効です。
詳 細 設 定
パラメーター 設定値 解説
ベロシティーに対する
音量の変化のしかた。
設定値が + のときは、
鍵盤を強く弾くほど音
Velocity Sens
Velocity Max 1〜127
-63 〜 +63
量が大きくなり、- のと
きは、強く弾くほど小
さくなります。設定値
が0のときは、弾く強
さに関わらず、音量は
一定になります。
ベロシティーに対する
音量の変化の最大値。
値を小さくすると、鍵
盤を強く弾いても音量
があまり大きくなりま
せん。
パートごとに移調の設定をする
(Key Transpose)
各パートを、それぞれ異なる音の高さに移調させて演奏する
ことができます。
キー・モードがレイヤーのときに、一方のトーンをオクター
ブ違いに設定すると、厚みのあるトーンを作ることができま
す。また、キー・モードをスプリットにして、ロワーでベー
スのトーンを鳴らすような場合に、より低い音で鳴らすこと
ができます。
パラメーター
設定値
鍵域の下限を上限より上げたり、上限を下限より下げること
はできません。
84
Key Transpose -48 〜 0 〜 +48
[TRANSPOSE]で、全パートに同じトランスポーズ量を設
定することもできます。詳しくは、
る([TRANSPOSE])
」(P.42)をご覧ください。
「鍵盤の音の高さを変え

各機能の詳細設定をする([EDIT])
パートごとにコントローラーのオン/ オフをする
各 PEDAL 端子に接続したペダル(Damper、FC1、FC2)、
モジュレーション・レバー(Modulation)、ベンダー
(Bender)、[CONTROL]つまみ(Control)で各パートを
コントロールするか(ON)、しないか(OFF)を設定しま
す。
パラメーター 設定値
Damper Pedal SW
FC1 Pedal SW
FC2 Pedal SW
Modulation SW
Bender SW
Control SW
ON、OFF
内部パートをローカル・パートに割り 当てる(Part Assign)
ローカル・パートにどの内部パートを割り当てるかを設定し
ます。
パラメーター
設定値
内部パートの MIDI 受信の設定
(Internal Part Prm)
RD-700 の内部で内蔵音源をコントロールする 16 個のパー
トのことを「内部パート(Internal Part)」と呼びます。
外部 MIDI 機器にシーケンサーなどを接続しているときは、
内部パートに受信チャンネルを割り当てることで、外部
MIDI 機器から MIDI 情報を受信して、内部パートをコント
ロールすることができます。
パートごとに MIDI 情報の受信のしかたを設定します。
設定のしかた
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して「8.Internal
2.
Part Prm」を選びます。
3.
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
す。
fig.midipart1.eps150
Part Assign 1〜16
fig.midipart2.eps150
fig.midipart3.eps150
4.
CURSOR[ ]/ [ ]で、画面を切り替え、
CURSOR[ ]/[ ]を押して、設定するパラ
メーターにカーソルを移動します。
5.
[INC/YES]/[DEC/NO]を押して値を設定します。
6.
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
詳 細 設 定
85

各機能の詳細設定をする([EDIT])
設定するパートを選ぶ
(< Part >、Tone)
設定するパートを選びます。
パラメーター 設定値
1〜16
<Part>
Tone
ローカル・パートが割り当てられてい
るパートは、パート名の後に
(UPPER1)のように表示されます。
< Part >で選んだパートに割り当てら
れているトーンが表示されます。
TONE SELECT ボタンを使ってトーン
を選ぶこともできます。
受信チャンネルを設定する
(Receive Channel)
外部 MIDI 機器の MIDI 情報で RD-700 を鳴らすときは、
RD-700 の各パートの受信チャンネルと外部 MIDI 機器の送
信チャンネルを合わせます。
パラメーター
Receive Channel 1〜16
設定値
エフェクトのオン/オフを設定する
(MFX Switch)
マルチエフェクトをかけるか(ON)、かけないか(OFF)を
設定します。
例えば、MFX Dest 設定(P.73)を「ALL」にしているとき
(全てのパートにマルチエフェクトがかかる)、この設定を
「OFF」にしたパートにはマルチエフェクトがかかりません。
パラメーター 設定値
ON
MFX Switch
OFF
必要な発音数を設定する
(Voice Reserve)
RD-700 の最大同時発音数(音源が同時に発音できる音数)
は128 音(ボイス)です。
128 ボイスを越える発音数で演奏された場合に、各パート
が確保するボイス数を設定します。例えば、パート 1 のボ
イス・リザーブを 6 に設定した場合、128 音を越えたとき
でもパート 1 の音数は必ず 6 音まで確保されます。
ボイス・リザーブの設定は、パートごとに設定することがで
きます。
音量/パンを設定する
(Volume / Pan)
各パートの音量と定位(パン)を設定します。
音量の設定は、主にキー・モードがスプリットやレイヤーの
ときに、パート間の音量バランスをとるために使います。
パンの設定は、ステレオ出力するときの、各パートの音像の
定位です。L の数字が大きくなるほど左から音が聞こえま
す。R の数字が大きくなるほど、右から音が聞こえます。0
にすると、中央から音が聞こえます。
詳 細 設 定
パラメーター 設定値
Volume
Pan L64 〜 0 〜 R63
0-127
パラメーター 設定値
0〜64
()の値は設定できる残りのボイス数
Voice Reserve
です。
各パートの設定値の合計が 64 を越え
ることはできません。
86

各機能の詳細設定をする([EDIT])
外部 MIDI コントローラーの MIDI 情 報を受ける/受けないを設定する
外部 MIDI 機器のモジュレーション・レバー、ペダル、つま
みなどを動かしたときの MIDI メッセージを受信して RD-
700 の音色を変化させることができます。
以下の MIDI メッセージを受信するか(ON)、受信しないか
(OFF)をパートごとに設定できます。
パラメーター 設定値
Rx.Bank Select
Rx.Program Change
Rx.Modulation
Rx.Bender
Rx.Volume
Rx.Hold-1
Rx.Pan
ON、OFF
調律法を設定する
(Temperament / Key)
各パートの調律法と主音を設定します。
現在では、一般に平均率を前提に作曲され、演奏されるのが
あたりまえとなっていますが、古典音楽の時代にはいろいろ
な調律法が存在していました。当時の調律法で演奏してみる
と、その曲が本来持っている和音の響きをあじわうことがで
きます。
また、平均律以外の調律法で演奏するときは、演奏する曲の
調に合わせて主音(長調ならド、短調ならラに当たる音)を
指定する必要があります。
平均律を選んでいる場合は、主音を選ぶ必要はありません。
パラメーター 設定値 解説
純正調[短]。純正調は
長調と短調で調律が異な
ります。長調のときと同
じ効果を短調で得ること
ができます。
ピタゴラス音律。哲学者
ピタゴラスによって考え
られた 4 度と 5 度の濁り
をなくした調律です。3
度の和音に濁りが生じま
すが、メロディーはきれ
いに聴こえます。
キルンベルガー。中全音
律と純正調を改良し、転
調の自由度を高めた調律
法です。全ての調での演
奏ができます(第三法)。
中全音律。純正調を一部
妥協させて、転調を可能
にした音律です。
ベルクマイスター。中全
音律とピタゴラス音律を
組み合わせた調律です。
全ての調での演奏ができ
ます(第一技法 第三番)。
アラビア音階。アラビア
音楽に適した調律です。
主音を設定します。
Temperament
Temperament
Key
JUST MIN
PYTHAGORE
(Pythagorean)
KIRNBERGE
(Kirnberger)
MEANTONE
WERCKMEIS
(Werckmeister)
ARABIC
C、C#、D、
D#、E、F、
F#、G、G#、
A、Bb、B
パラメーター 設定値 解説
平均律。オクターブを均
等に 12 分割してできた
EQUAL
Temperament
JUST MAJ
調律です。どの音程も同
じくらいわずかな濁りが
生じます。電源を入れた
時は、この設定です。
純正調[長]。5 度と 3
度の濁りをなくした調律
です。メロディーの演奏
には不向きで転調はでき
ませんが、美しい和音の
響きをもちます。
詳 細 設 定
87

各機能の詳細設定をする([EDIT])
その他の機能(Utility)
ユーティリティーには、外部 MIDI シーケンサーなどへデー
タを転送する機能や、各設定を工場出荷時の状態に戻す機能
があります。
CURSOR [ ]/[ ]を押して、「Bulk Dump
5.
Temporary」または「Bulk Dump SETUP」を選びま
す。
パラメーター 解説
ユーティリティー「Rec Setting」については「録音すると
きの設定(Rec Setting)
」(P.91)をご覧ください。
本体の設定を外部 MIDI 機器に転送す る(バルク・ダンプ)
セットアップの内容やシステム設定を外部 MIDI 機器に転送
することができます。このような操作をバルク・ダンプとい
います。
もう 1 台同じ設定の RD-700 を接続して演奏したいときや、
セットアップやシステムの設定が壊れたときに備えて、あら
かじめデータを外部 MIDI 機器に保存しておくときに使いま
す。
1.
本体のMIDI OUT コネクターと外部シーケンサーのMIDI
IN コネクターを、MIDI ケーブル(別売)で接続します。
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
2.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
Bulk Dump
Temporary
Bulk Dump
SETUP
Bulk Dump の操作中は鍵盤を弾いても音が鳴らなくなりま
す。また、演奏中のリズムやアルペジオも止まります。
現在選んでいるセットアップの内
容を送信します。
指定した範囲内のセットアップの
内容を送信します。
Bulk Dump Temporary のとき
6.
CURSOR [ ]を押します。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(x2)
7.
外部シーケンサーを録音状態にします。
CURSOR [ ]を押して「9.Utility」を選びます。
3.
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示しま
4.
す。
fig.utility1.eps150
詳 細 設 定
[INC/YES]を押すと、設定の送信をはじめます。
8.
バルク・ダンプを中止するときは、[DEC/NO]を押し
ます。
送信中は「Now, Executing...」と表示されます。
送信が終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と
9.
表示されます。
エディット画面に戻ります。
外部シーケンサーを停止させます。
10.
88

各機能の詳細設定をする([EDIT])
Bulk Dump SETUP のとき
6.
CURSOR [ ]を押します。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(x2)
パラメーター 解説
From 送信する先頭のセットアップ・ナンバー
To 送信する末尾のセットアップ・ナンバー
Send System
7.
CURSOR [ ]/[ ]と[DEC/NO]、[INC/
YES]で送信するセットアップを設定してください。
設定したら、CURSOR [ ]を押します。
8.
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(x2)
システム設定を送信する(YES)しない
(NO)
保存した設定を RD-700 に戻す
外部シーケンサーで保存した設定を RD-700 に戻すときは、
外部シーケンサーからエクスクルーシブ情報を送信し、RD-
700 で受信します。
本体に「Bulk Dump SETUP」のデータを戻すと、本体に記
憶されていたデータは上書きされ、失われてしまいますので
ご注意ください。
1.
外部シーケンサーのMIDI OUTコネクターと本体のMIDI
IN コネクターを、MIDI ケーブルで接続します。
2.
デバイス ID ナンバーをバルク・ダンプのときと同じ設定
にします。
デバイス ID ナンバーの設定→「デバイス ID ナンバーを設定
する(Device ID)
[EDIT]のインジケーターが消灯していることを確認し
3.
ます。
[EDIT]のインジケーターが点灯しているときは、
[EDIT]を押してインジケーターを消灯させ、通常の演
奏状態にしてください。
」(P.67)
外部シーケンサーを録音状態にします。
9.
[INC/YES]を押すと、設定の送信をはじめます。
10.
バルク・ダンプを中止するときは、[DEC/NO]を押し
ます。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(x2)
送信が終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と
11.
表示されます。
エディット画面に戻ります。
12.
外部シーケンサーを停止させます。
4.
外部シーケンサーから設定を送信(再生)します。
5.
送信が終わると、ディスプレイに「COMPLETED」と
表示されます。
Bulk Dump Setup のデータは、再生後、RD-700 が受信し
たデータを内部メモリーに書き込みます。データの書き込み
中(「Now, writing Bulk Dump Data. Keep on POWER!」表
示中)は、決して電源を切らないでください。
エクスクルーシブ情報の送信のしかたは、お使いの外部シー
ケンサーの取扱説明書をご覧ください。
外部シーケンサーは、バルク・ダンプのときと同じテンポで
再生してください。それよりも速いテンポで再生すると、設
定を正しく戻せないことがあります。
バルク・ダンプしたときのデバイス ID と、受け側のデバイ
スIDが異なる場合は受信できません。
詳 細 設 定
GM モード(P.94)に設定されていると、エクスクルーシ
ブ情報を受信できません。GM モードを解除してから操作し
てください。
89

各機能の詳細設定をする([EDIT])
設定を工場出荷時の状態に戻す
(ファクトリー・リセット)
RD-700 に記憶した設定を工場出荷時の設定に戻すことがで
きます。
「Factory Reset All」を実行すると、セットアップ(P.50)
の設定が失われます。記憶させた内容を残しておきたい場合
は、「バルク・ダンプ(Bulk Dump SETUP)」で外部シーケ
ンサーに保存してください(P.88)。
1.
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
2.
CURSOR [ ]を押して「9.Utility」を選びます。
[INC/YES]を押します。
6.
確認のメッセージが表示されます。
fig.LCD
ファクトリー・リセットを中止するときは、[DEC/NO]
を押します。
7.
もう一度[INC/YES]を押すと、ファクトリー・リセッ
トが実行されます。
実行中は「Now, Executing...」と表示されます。決して電源
を切らないでください。
8.
ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに
「COMPLETED」と表示されます。
トーン画面に戻ります。
3.
CURSOR [ ]を押して、エディット画面を表示します。
fig.utility1.eps150
CURSOR [ ]/[ ]を押して、「Factory
4.
Reset Current」または「Factory Reset All」を選びます。
パラメーター
Factory Reset
Current
Factory Reset All
詳 細 設 定
Factory Reset の操作中は鍵盤を弾いても音が鳴らなくなり
ます。また、演奏中のリズムやアルペジオも止まります。
Factory Reset Current のとき
5.
CURSOR [ ]を押します。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(x2)
解説
現在選んでいるセットアップを
工場出荷時の設定に戻します。
RD-700 のすべての設定を工場
出荷時の設定に戻します。
Factory Reset All のとき
5.
CURSOR [ ]を押します。
次のような画面が表示されます。
fig.LCD(x2)
6.
[INC/YES]を押します。
確認のメッセージが表示されます。
fig.LCD
ファクトリー・リセットを中止するときは、[DEC/NO]
を押します。
7.
もう一度[INC/YES]を押すと、ファクトリー・リセッ
トが実行されます。
実行中は「Now, Executing...」と表示されます。決して電源
を切らないでください。
90
ファクトリー・リセットが終わると、ディスプレイに
8.
「COMPLETED」と表示されます。
トーン画面に戻ります。

外部 MIDI 機器との接続
RD-700 の演奏を外部 MIDI
CURSOR [ ]を押して「9.Utility」を選びます。
2.
シーケンサーに録音する
外部シーケンサーを使って、複数のトラックに演奏を重ねて
録音したり、録音した演奏を再生してみましょう。
外部シーケンサーと接続する
fig.
MIDIIN MIDIOUT
MIDIシーケンサー
MIDIIN MIDIOUT
RD-700
接続を始める前に、すべての機器の電源がオフになって
1.
いることを確認します。
外部機器と接続する(P.18)に従って、オーディオ機器
2.
またはヘッドホンなどを接続します。
図のように、RD-700、外部 MIDI 機器を MIDI ケーブルで
3.
接続します。
4.
「電源を入れる」(P.20)に従って、各機器の電源を入れ
ます。
3.
CURSOR[ ]を押して、エディット画面を表示します
fig.utility1.eps150
CURSOR [ ]を押して、「Rec Setting」を選びま
4.
す。
5.
CURSOR [ ]を押すと、次のような画面が表示され
ます。
fig.LCD
パラメーター 設定値 解説
通常は OFF にしておきま
Rec Mode
ON、OFF
Local Switch
す。ON にすると、Rec
Mode になり、録音に適
した設定になります。
ローカル・スイッチのオ
ン/オフを切り替えます。
通常は ON にしておきま
すが、録音するときは、
OFF にするとよいでしょ
う。
詳しくは、後述の「ロー
カル・スイッチについて」
をご覧ください。
録音するときの設定(Rec Setting)
外部シーケンサーに録音するときは、Rec Mode 機能を使う
と便利です。
Rec Mode 機能を使うと、パートやチャンネルの各設定を行
わなくても、RD-700 を外部シーケンサーに録音するのに最
適な設定にすることができます。
[EDIT]を押して、インジケーターを点灯させます。
1.
エディット・メニュー画面が表示されます。
fig.Editmenu2.eps150
6.
CURSOR [ ]/[ ]と[DEC/NO]、[INC/
YES]で設定してください。
7.
設定が終わったら、[EDIT]を押してインジケーターを
消灯させます。
トーン画面に戻ります。
外部シーケンサーに録音する設定になりました。
Rec Mode が ON になっているときは、MIDI TX パートの
設定(P.56)を変えることはできません。[MIDI TX]を押
しても、MIDI TX 画面は表示されません。
91
外部 MIDI 機器との接続

外部 MIDI 機器との接続
音源部
鍵盤コントローラー部
MIDIOUT MIDIIN
MIDIIN MIDIOUT
RD-700
シーケンサー
録音
MIDIスルー:オン
ローカル・スイッチ:オフ
演奏を録音する
外部シーケンサーに録音するときは、次の手順でおこなって
ください。
1.
2.
3.
4.
5.
外部シーケンサーのスルー機能をオンにします。
詳しくは、次項の「ローカル・スイッチについて」をご
覧ください。
操作については、お使いになるシーケンサーの取扱説明
書をご覧ください。
録音する演奏のセットアップを選びます。
セットアップの選びかたは、P.50 をご覧ください。
Rec Setting の設定をします。
前項の「録音するときの設定」の操作にしたがって、以
下のように設定してください。
Rec Mode: ON
Local Switch: OFF
外部シーケンサーの録音を開始します。
セットアップをバルク・ダンプします。
エディット・モード、Utility の Bulk Dump Temporary
で、選んでいるセットアップの内容を外部シーケンサー
に送信します。
操作については、
る(バルク・ダンプ)
本体の設定を外部 MIDI 機器に転送す
(P.88)をご覧ください。
ローカル・スイッチについて
鍵盤コントローラー部と音源部(P.27)の間の MIDI 接続を
切り離したり、つないだりするスイッチをローカル・スイッ
チといいます。ローカル・スイッチをオフにすると、鍵盤コ
ントローラー部から音源部に演奏情報が伝わらなくなります
ので、通常、ローカル・スイッチはオンの状態で使用しま
す。
ただし、演奏しながらその演奏情報を MIDI メッセージとし
て外部シーケンサーに録音したいような場合は、外部に接続
したシーケンサーを MIDI スルー(MIDI IN で受信した情報
をそのまま MIDI OUT から送信する)の状態にし、RD-700
のローカル・スイッチをオフにして演奏します。
fig.
6.
RD-700 で演奏します。
7.
演奏が終わったら外部シーケンサーの録音を止めます。
録音が終わりました。
外部シーケンサーを再生すると、録音した演奏を聴くこ
とができます。
Rec Mode を解除する
Rec Mode が ON に設定されていると、MIDI TX の設定を変
外部 MIDI 機器との接続
えることができません。演奏の録音が終わったら、前項の
「録音するときの設定」の操作にしたがって Rec Mode を
OFF にしてください。
Rec Setting の設定を記憶することはできません。
Rec Setting は、電源投入後、
Rec Mode: OFF、Local Switch ON
の設定になります。
このとき、ローカル・スイッチをオンにして演奏すると、鍵
盤コントローラー部から音源部へ直接伝達される情報と、鍵
盤コントローラー部から外部シーケンサーを経由して音源部
へ伝達される情報の 2 つの情報が同時に音源部に送られて
しまいます。このため、例えば「ド」の鍵を 1 回押したと
きでも、音源部では 2 回「ド」の音を鳴らそうとして正し
く発音できなくなります。
92

外部 MIDI 機器との接続
外部 MIDI 機器から RD-700 の 音源部を鳴らす
外部 MIDI 機器から RD-700 を鳴らしてみましょう
接続のしかた
fig.
MIDIOUT
MIDIシーケンサー
MIDIIN
RD-700
1.
接続を始める前に、すべての機器の電源がオフになって
いることを確認します。
外部機器と接続する(P.18)に従って、オーディオ機器
2.
またはヘッドホンなどを接続します。
図のように、RD-700、外部 MIDI 機器を MIDI ケーブルで
3.
接続します。
外部 MIDI 機器から RD-700 の音色 を切り替える
外部 MIDI 機器から RD-700 にバンク・セレクト(コント
ローラー・ナンバー 0、32)とプログラム・チェンジを送
信することで、セットアップやトーンを切り替えることがで
きます。
セットアップの切り替え
外部 MIDI 機器から送信する MIDI メッセージとセットアッ
プ・ナンバーは、以下のように対応しています。
ナンバー バンク・セレクト プログラム・チェンジ・ナンバー
MSB LSB
1〜100
セットアップを切り替えるときは、送信側の MIDI チャンネ
ルと RD-700 のコントロール・チャンネルを合わせる必要
があります。(P.66)
各パートのトーンを切り替えるときは、送信側の MIDI チャ
ンネルと RD-700 の受信チャンネルを合わせます。ただし、
コントロール・チャンネルと受信チャンネルが一致している
ときは、コントロール・チャンネルが優先され、セットアッ
プが切り替わることになります。
トーンの切り替え
外部 MIDI 機器から送信する MIDI メッセージとトーン・ナ
ンバーは、以下のように対応しています。
85 0 1〜100
4.
電源を入れる/切る(P.20)に従って、各機器の電源を
入れます。
チャンネルを設定する
RD-700 の受信チャンネルと外部 MIDI 機器の送信チャンネ
ルを合わせます。
RD-700 の受信チャンネルの設定のしかたは、
ルを設定する(Receive Channel)
両方のチャンネルを合わせて外部 MIDI 機器を演奏すると、
RD-700 の音源が鳴ります。
外部 MIDI 機器の送信チャンネルの設定方法は、お使いの
MIDI 機器の取扱説明書をご覧ください。
(P.86)をご覧ください。
受信チャンネ
グループ
PIANO 001 - 019 087 064 001 - 019
E.PIANO 020 - 039 087 065 001 - 020
CLAV/
MALLET
ORGAN 060 - 089 087 067 001 - 030
STRINGS 090 - 109 087 068 001 - 020
PAD 110 - 129 087 069 001 - 020
GTR/
BASS
BRASS/
WINDS
VOICE/
SYNTH
リズム・
セット
エクスパンション・ボード SRX シリーズの音色を選ぶとき
は、SRX シリーズに付属の取扱説明書をご覧ください。
ナンバー バンク・セレクト プログラム
MSB
040 - 059 087 066 001 - 020
130 - 159 087 070 001 - 030
160 - 179 087 071 001 - 020
180 - 199 087 072 001 - 020
200 - 203 086 064 001 - 004
LSB
・チェンジ・ナンバー
外部 MIDI 機器との接続
93

外部 MIDI 機器との接続
GM 音源として使う(GM Mode)
RD-700 には、GM スコア(GM 音源用のミュージックデー
タ)を再生するのに便利な「GM モード」があります。
GM モードに切り替えると、GM スコアを正しく再生できる
だけでなく、特定のパートをミュート(消音)してそのパー
トを RD-700 の鍵盤で演奏したり、指定したパートのトー
ンを変更することもできます。
GM モードでの注意点
•
GM モードでは、CURSOR ボタン、[INC/YES][DEC/
NO]、ONE TOUCH [PIANO]、[SETUP]以外のボタ
ンやつまみはきかなくなります。
必ず曲の先頭部分から再生してください。途中から再生
•
すると、音源の設定が GM や GM2 の初期設定値に戻ら
ないので、正しく演奏されません。
本機は GS リセット・メッセージを受信すると、GS
•
フォーマット(ローランドが提唱するマルチティンバー
音源の標準化を目的とした共通仕様)に対応できるよう
になります。これにより、GS マークが付いたミュー
ジックデータ(GS ミュージックデータ)を再生するこ
とができます。ただし、当社のサウンド・キャンバス・
シリーズ(SC-8850/SC-8820 など)とは音源方式や
音色の拡張マップが異なるため、サウンド・キャンバ
ス・シリーズ専用に作成されたミュージックデータは、
正しく再生できないことがあります。
RD-700 本体で GM モードにすることはできません。再
•
生する曲の先頭部分に GM System On、GM2 System
On、GS Reset のいずれかのメッセージをいれておく
と、RD-700 はそのメッセージを受信して、GM モード
になります。
•
エディット画面の System 設定、Rx GM System On、
Rx GM2 System On、GS Reset の設定が「OFF」に
なっていると、GM モードになりません。詳しくは、
外部 MIDI 機器との接続
GM/GM2 システム・オン、GS リセットの受信を切り替
える (Rx GM / GM2 System On、Rx GS Reset)
(P.66)をご覧ください。
GM スコアの再生を始めると、RD-700 には次のような
GM モード画面が表示されます。
fig.
Part 1~8
Part 9~16
RD-700 の鍵盤を弾くと、現在選ばれているパートの
トーンで演奏することができます。
特定のパートのトーンを変える
GM モード画面で、CURSOR ボタンでパート番号にカー
1.
ソルを移動します。
[DEC/NO]または[INC/YES]でトーンを変えるパー
2.
トを選びます。
CURSOR[ ]でトーン・ナンバーにカーソルを移動
3.
します。
[DEC/NO]または[INC/YES]でトーンを選びます。
4.
指定したパートの演奏が、選んだトーンで鳴ります。
特定のパートをミュートする
GM モード画面で、CURSOR ボタンでミュートするパー
1.
トのマークにカーソルを移動します。
2.
[DEC/NO]または[INC/YES]でミュートのオン・オ
フを選びます。
表示 意味
○
--
ミュートしても RD-700 の鍵盤で演奏することができま
す。
MIDI メッセージを受信します。MIDI
メッセージによる演奏を再生します。
MIDI メッセージを受信しません。この
パートはミュートされています。
GM スコアを再生する
外部シーケンサーを接続します。
1.
P.93 をご覧ください。
外部シーケンサーで GM スコアを再生します。
2.
94
GM モードを解除する
1.
GM モード画面で、ONE TOUCH [PIANO]または
[SETUP]を押します。
GM モードが解除され、トーン画面が表示されます。
GM スコアを再生中に GM モードを解除したときは、
GM スコアを再生したまま、トーン画面が表示されます。

故障かな?と思ったら
思ったように動作しないときは、まず以下の点をチェックし
てください。チェックしても原因がわからないときは、お買
い上げ店または最寄りのローランド・サービス・ステーショ
ンにお問い合わせください。
※ 操作中、何らかのメッセージが画面に表示されたとき
エラー・メッセージ/その他のメッセージ(P.99)
は、
をご覧ください。
現象 確認事項/対処
RD-700 の AC コードがコンセント
電源が入らない
音が鳴らない
や本体に正しく接続されています
か?
接続しているアンプやスピーカー
の電源が入っていますか?音量が
下がっていませんか?
VOLUME スライダーで音量を絞っ
ていませんか?
正しく接続されていますか?
・ RD-700 単体で使用する場合は、
オーディオ・ケーブルまたはヘッ
ドホンを接続してください
(P.18)。
ヘッドホンを接続して音が聞こえ
ますか?
・ ヘッドホンから音が出るようで
あれば、接続しているケーブルが
断線していたり、アンプやミキ
サーが故障している場合が考えら
れます。もう一度、接続ケーブル
や機器を確認してください。
PART SWITCH がオフになってい
ませんか?(P.41、P.58)
PART LEVEL スライダーでパート
の音量を絞っていませんか?
(P.41、P.58)
鍵盤を押さえて音が鳴らない場合、
ローカル・スイッチがオフに設定
されていませんか?
・ エディット・モード、Utility の
Rec Setting で、Local Switch を
ON に設定してください(P.91)。
現象 確認事項/対処
ウェーブ・エクスパンション・
ボードが正しく取り付けられてい
ますか?
・ EXPANSION[A]または[B]
のトーンまたはリズム・セットを
使用した設定を選んでいるとき、
指定のスロットに指定のウェー
音が鳴らない
特定のパートの
音が鳴らない
接続している
MIDI 機器の音
が鳴らない
ブ・エクスパンション・ボードが
正しく取り付けられていることを
確認してください(P.16)。
ペダルの操作や外部 MIDI 機器から
受信した MIDI メッセージ(ボ
リューム・メッセージとエクスプ
レッション・メッセージ)によっ
て、音量が下がっていませんか?
パートの音量レベルが下がってい
ませんか?
・ PART LEVEL スライダー
(P.41、P.58)と、エディット・
モード、Internal Part Prm の
Volume の設定(P.86)を確認し
てください。
パートの MIDI 受信チャンネルと、
接続している MIDI 機器の MIDI 送
信チャンネルが合っていますか?
・ エディット・モード、Internal
Part Prm の Receive Cannel で
MIDI 受信チャンネルを設定して
ください(P.86)。
MIDI メッセージが送信できる状態
になっていますか?
・ [MIDI TX]をオンにして、
PART SWITCH をオンにしてく
ださい(P.58)。
PART SWITCH がオフになって
いると、MIDI 情報が送信されま
せん。
RD-700 の鍵盤コントローラー部の
MIDI 送信チャンネルと、接続して
いる MIDI 機器の MIDI 受信チャン
ネルが合っていますか?
・ MIDI TX 画面で、Ch を設定して
ください(P.56)。
エフェクトの設定は正しいです
か?
・ MULTI EFFECTS[ON/OFF]の
オン/オフ(P.49)、エディッ
ト・モード、MFX/Reverb/
Chorus の MFX < OtherPrm >
のエフェクト・バランスやレベル
などの設定を確認してください
(P.73、P.100)。
特定の音域の音
が出ない
発音域(キー・レンジ)が設定さ
れていませんか?
・ MIDI TX 画面で各パートの
LWR、UPR の設定(P.59)、エ
ディット・モード、Local Part
Param の Key Range の設定を確
認してください(P.84)。
リズム・セット、ベース音色や
Timpani(ティンパニ)など、発音
域が限られたトーンがあります。
資 料
95

故障かな?と思ったら
資 料
現象 確認事項/対処
セットアップを呼び出していませ
んか?
・ セットアップを呼び出すと、トー
ンやエフェクトなどの現在の設定
は無効になり、選んだセットアッ
プの設定になります(P.50)。必
要な設定は、セットアップに新た
に記憶してください(P.52)。
ONE TOUCH [PIANO]を押して
いませんか?
・ ONE TOUCH [PIANO]を押す
音が変わる
UPPER のトーン
を選ぶと LOWER
のトーンも同じ
トーンに変わって
しまう。
トーンが変わら
ない/スプリッ
トやレイヤーに
ならない
リズムのイント
ロがならない/
リズムが途中か
ら始まる。
と、トーンやエフェクトなどの現
在の設定は無効になり、ピアノ演
奏のための設定になります
(P.31)。必要な設定は、セット
アップに新たに記憶してください
(P.52)。
[CONTROL]つまみにトーン・コ
ントロールの機能を割り当ててい
ませんか?
・ エディット・モード、Control
EQ の Control の設定を確認して
ください(P.70)。
エディット・モード、Local Part
Param の Part Assign の設定で、
UPPER パートと LOWER パートに
同じ値を設定していませんか?
(P.85)
[MIDI TX]がオンになっていませ
んか?
・ [MIDI TX]がオンになっている
ときは、外部音源をコントロール
します。RD-700 のトーンを変え
たり、キーボード・モードを設定
するときは、[MIDI TX]をオフ
にしてください(P.55)。
トーンを変えたいパートの PART
SELECT ボタンをオンにしてあり
ますか(P.40)?
[NUM LOCK]がオンになっていま
せんか?
・ [NUM LOCK]をオンにする
と、TONE SELECT ボタンで
トーンのカテゴリーを選ぶことが
できません。
MIDI TX パートの PART SWITCH
[RHYTHM]がオンになっていませ
んか?
・ ローカル・パートのリズムと
MIDI TX パートのリズムは同期し
ます(P.47)。
現象 確認事項/対処
エディット・モード、System の
Clock Source の設定が MIDI に
なっていませんか(P.66)?外部
MIDI 機器が接続されていますか?
・ Clock Source を MIDI すると、
RD-700 でテンポを設定すること
はできません。そのため、外部
MIDI 機器が接続されていないと、
リズムのテンポが設定されず、リ
ズムは鳴りません。
リズムが鳴らな
い
エフェクトがか
からない/かか
りかたがおかし
い
エディット・モード、Internal Part
Prm で、Part 10 の Receive
Channel の設定を 10 にしてくださ
い(P.86)。
MIDI TX 画面(P.59)になってい
ませんか?
・ MIDI TX 画面が表示されている
と、リズムは鳴りません。[MIDI
TX]を押して、ボタンのインジ
ケーターを消灯させてください。
エディット・モード、Rhythm
Pattern の Pattern の設定を OFF
にしていませんか?(P.78)
Tone Wheel 1 〜 10 のトーンを選
んでいませんか? Tone Wheel は
他のトーンとエフェクトのかかり
かたが異なります。
・ Internal Part Prm の各パートの
MFX Switch のオン/オフ
(P.86)や、Tone Edit の各トー
ンの MFX の設定(P.76)に関わ
らず、MFX/Reverb/Chorus の
MFX Source で設定されている
エフェクトがかかります
(P.73)。
・ Tone Wheel を複数のパートに選
んでいる場合、Internal Part Prm
の設定で Rx Bender Switch や
Rx Hold-1 Switch のオン/オフ
設定(P.87)に関わらず、すべ
てのパートに効果がかかります。
MULTI EFFECTS[ON/OFF]がオ
フになっていませんか(P.49)?
[CONTROL]つまみに MFX
CONTROL が設定されています
か?
・ エディット・モード、MFX/
Reverb/Chorus の Control の設
定を MFX CONTROL にしてくだ
さい(P.73)。
96

故障かな?と思ったら
現象 確認事項/対処
MFX/Reverb/Chorus の DELAY
エフェクトがか
からない/かか
りかたがおかし
い
Lower パートに
かけたマルチエ
フェクトがかか
らない
ピッチ・ベン
ド・レバーを動
かしてもピッ
チ・ベンドがか
からない
押鍵するたびに
音が右や左から
聴こえる(パン
ニングされる)。
音がひずむ
ドローバーの画
面(トーン・ホ
イール画面)を
選べない
TONE SELECT
ボタンでトーン
が変わらない
キー・レンジ
(Key Range)
の設定が効かな
い
の設定で、ディレイのタイミング
を音符の値に設定していると、
ディレイ音が鳴らないことがあり
ます。テンポを調節するか、ディ
レイのタイミングを数値で設定し
てください(P.75)。
MFX Source、MFX Dest の設定を
確認してください(P.73)。
・ 設定によっては Lower パートの
MFX の設定は無視されます。
トーン・ホイール画面が表示され
ていませんか?
・ トーン・ホイール画面では、
ピッチ・ベンド・レバーでピッ
チ・ベンドの効果をかけることは
できません。ピッチ・ベンド・レ
バーは、ロータリー効果のスロー
/ファーストの切り替えスイッチ
になります。(P.71)
音色によっては、押鍵するたびに
ランダムに音が左右に振られる
(パンニングされる)ように設定さ
れているものがあります。この設
定を変更することはできません。
イコライザー、マルチエフェクト、
パート・ボリュームの設定によっ
ては、音がひずむ場合があります。
以下の設定を調節してください
・PART LEVEL スライダー(P.41)
・エディット・モード、MFX/
Reverb/Chorus の MFX <
Other Prm >のエフェクト・レベ
ル(P.73)
・System の Master Volume の設定
(P.66)
音が歪むようなエフェクトをかけ
ていませんか?(P.73、P.76)
トーン画面で Upper1、Upper2、
Lowerのいずれかのパートに Tone
Wheel の音色を選んで、CURSOR
[ ]を押すと表示されます。
(P.71)
トーン・ホイール画面が表示され
ていませんか(P.71)?
・ トーン・ホイール画面では、
TONE SELECT ボタンを押すと、
Tone Wheel1 〜 10 が切り替わ
ります。
[SPLIT]がオフになっていません
か?
・ キー・レンジは、[SPLIT]がオ
ンのときに有効になります
(P.59、P.84)。
現象 確認事項/対処
エディット・モード、System の
Clock Source の設定が MIDI に
テンポが変わら
ない
音程(ピッチ)
がおかしい
音が途切れる
鍵盤を押さえる
と音が鳴りっぱ
なしになる
エクスクルーシ
ブ・メッセージ
を受信しない
なっていませんか?
・ RD-700 のテンポで演奏すると
きは、「INT」に設定してくださ
い(P.66)。
選んでいるトーンによっては、あ
る音域で音程が他の音色と変わっ
て聞こえる場合があります。
特定のパートにコース・チューン、
ファイン・チューン、ストレッチ・
チューンを設定していませんか?
・ エディット・モード、Tone Edit
の Course Tune、Fine Tune、
Stretch Tune の設定(P.76、
P.77)または MIDI TX 画面の
C.T、F.T の設定を確認してくだ
さい(P.61)。
RD-700 のチューニングがずれてい
ませんか?
・ エディット・モード、System の
Master Tune の設定を確認して
ください(P.25)。
ペダルの操作や外部 MIDI 機器から
受信したピッチ・ベンド・メッ
セージによって、ピッチがずれて
いませんか?
128 ボイスを超える発音をしよう
とした場合、現在鳴っている音が
途切れる場合があります。
・ 音抜けさせたくないパートのボ
イス・リザーブを多めに設定して
ください(P.86)
ホールド・ペダルの極性(ペダル・
ポラリティー)が逆になっていま
せんか?
・ エディット・モード、System の
Pedal Polarity の設定を確認して
ください(P.67)。
送信側のデバイス ID ナンバーと、
RD-700 のデバイス ID ナンバーが
合っていますか?
・ エディット・モード、System の
Device ID の設定を確認してくだ
さい(P.67)。
GM モードになっていませんか?
・ ONE TOUCH [PIANO]または
[SETUP]を押して、GM モード
を解除してください。(P.94)
資 料
97

故障かな?と思ったら
現象 確認事項/対処
セットアップ名を登録する際
セットアップ名
が正しく表示さ
れない
曲データが正し
く再生できない
(P.52)、M、N、W の文字を 8 文
字以上使うと正しく表示されませ
ん。M、N、W の文字数を減らして
ください。
レシーブ・GM / GM2 システム・
オン・スイッチはオンになってい
ますか?
・ エディット・モード、System の
Rx GM System On / Rx GM2
System On を ON に設定してく
ださい(P.66)。
曲の途中から再生していません
か?
・GMスコアの曲の頭には、GM
/GM2 システム・オン・メッ
セージが書き込まれています。こ
のメッセージを受信しないと、
GM スコアが正しく再生できない
場合があります。
曲データが正し
く再生できない
GS フォーマットの曲データを再生
していませんか?
・ RD-700 は GS リセット・メッ
セージを受信すると、GS フォー
マットに対応できるようになりま
す。これにより、GS マークが付
いたミュージックデータ(GS
ミュージックデータ)を再生する
ことができますが、当社のサウン
ド・キャンバス・シリーズ専用に
作成されたミュージックデータ
は、正しく再生できないことがあ
ります。
資 料
98

エラー・メッセージ/その他のメッセージ
エラー・メッセージ
表示: MIDI Buffer Full
原因: 受信した MIDI メッセージの量が多いため、正しく
受信できませんでした。
対応: 送信する MIDI メッセージの量を減らしてください。
表示: MIDI Communication Error
原因: MIDI ケーブルの接続に問題があります。
対応: MIDI ケーブルの抜けや断線がないことを確認して
ください。
表示: BULK DUMP: Receive Data Error
原因: MIDI メッセージが正しく受信できませんでした。
対応: 何度も同じメッセージが表示されるときは、MIDI
メッセージの内容に問題があります。
表示: BULK DUMP: Check Sum Error
原因: System Exclusive メッセージのチェックサムに問題
があります。
対応: チェックサムを確認してください。
その他のメッセージ
表示: Now, Transmitting System Exclusive.
原因: データ要求メッセージ (RQ1) を受信した場合に表
示されます。
対応: このメッセージが表示されている間、本機は、要求
のあったデータを MIDI 出力しています。
表示: Now, writing Bulk Dump Data. Keep on POWER!!
原因: バルク・ダンプ・データを受信した場合に表示され
ます。
対応: 受信が終了すると本機の内部メモリーへの書き込み
が行われますので、「COMPLETED」と表示される
までは、決して電源を切らないでください。
表示: Unavailable while in Rec Mode
原因: Rec Mode が「ON」の時に、[MIDI TX] ボタンを押
すと表示されます。
対応: Rec Mode が「ON」の時には、MIDI Tx の設定を変
更することができません。MIDI Tx の設定を変更す
るには、Rec Mode を「OFF」にしてください
(P.91)。
99
資 料

エフェクト/パラメーター一覧
資 料
※ 「#」マークのついているパラメーターは、MULTI
EFFECTS[CONTROL]つまみに割り当てることがで
きます。「設定のしかた」(P.72)の操作にしたがって、
「MFX CONTROL」を設定してください。
01: STEREO EQ(ステレオ・イコライザー)
低域、中域× 2、高域の音質を調節するステレオ・イコライ
ザーです。
Low Freq(ロー・フリケンシー)
低域を調節するときの、基準周波数(200Hz/400Hz)を設定
します。
Low Gain(ロー・ゲイン)
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
+にするほど低域が強調(増幅)されます。
High Freq(ハイ・フリケンシー)
高域を調節するときの、基準周波数(2000Hz/4000Hz/
8000Hz)を設定します。
High Gain(ハイ・ゲイン)
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
+にするほど高域が強調(増幅)されます。
Mid1 Freq(ミドル 1・フリケンシー)
特定の周波数帯を調節するときの、基準周波数を設定します。
Mid1 Q(ミドル 1・Q)
Mid1 Freq で設定した周波数を基準として、 周波数帯に幅を持
たせます。
値を大きくするほど Mid1 Gain で調節する周波数帯の幅が狭く
なります。
Mid1 Gain(ミドル 1・ゲイン)
Mid1 Freq や Mid1 Q で設定した周波数帯のゲイン(増幅/減
衰量)を設定します。
+にするほど Mid1 Freq、 Mid1Q で設定した周波数帯が強調
(増幅)されます。
Mid2 Freq(ミドル 2・フリケンシー)
特定の周波数帯を調節するときの、基準周波数を設定します。
Mid2 Q(ミドル 2・Q)
Mid2 Freq で設定した周波数を基準として、 周波数帯に幅を持
たせます。
値を大きくするほど Mid2 Gain で調節する周波数帯の幅が狭く
なります。
Mid2 Gain(ミドル 2・ゲイン)
Mid2 Freq や Mid2 Q で設定した周波数帯のゲイン(増幅/減
衰量)を設定します。
+にするほど Mid2 Freq、 Mid2Q で設定した周波数帯が強調
(増幅)されます。
Level(アウトプット・レベル)#
出力音量を設定します。
02: OVERDRIVE(オーバードライブ)
オーバードライブは真空管アンプで歪ませたような、自然な歪
みが得られます。
Drive(ドライブ)#
歪み具合を設定します。歪み具合といっしょに音量も変わりま
す。
Level(アウトプット・レベル)
出力音量を設定します。
オーバードライブをかけたときとかけないときとの音量差は、
アウトプット・レベルで調節するとよいでしょう。
Low Gain(ロー・ゲイン)
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
+にするほど低域が強調(増幅)されます。
High Gain(ハイ・ゲイン)
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
+にするほど高域が強調(増幅)されます。
Amp Type(アンプ・シミュレーター・タイプ)
ギター・アンプの種類を設定します。
SMALL:小型アンプ
BUILT-IN:ビルト・イン・タイプのアンプ
2-STACK:大型 2 段積みアンプ
3-STACK:大型 3 段積みアンプ
Pan(アウトプット・パン)#
出力音の定位を設定します。
L64 で最も左、0 で中央、63R で最も右に定位します。
03: DISTORTION(ディストーション)
ディストーションはオーバードライブよりも激しい歪みが得ら
れます。
Drive(ドライブ)#
歪み具合を設定します。歪み具合といっしょに音量も変わりま
す。
Level(アウトプット・レベル)
出力音量を設定します。
ディストーションをかけたときとかけないときとの音量差は、
アウトプット・レベルで調節するとよいでしょう。
Low Gain(ロー・ゲイン)
低域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
+にするほど低域が強調(増幅)されます。
High Gain(ハイ・ゲイン)
高域のゲイン(増幅/減衰量)を設定します。
+にするほど高域が強調(増幅)されます。
Amp Type(アンプ・シミュレーター・タイプ)
ギター・アンプの種類を設定します。
SMALL:小型アンプ
BUILT-IN:ビルト・イン・タイプのアンプ
2-STACK:大型 2 段積みアンプ
3-STACK:大型 3 段積みアンプ
Pan(アウトプット・パン)#
出力音の定位を設定します。
L64 で最も左、0 で中央、63R で最も右に定位します。
100
 Loading...
Loading...