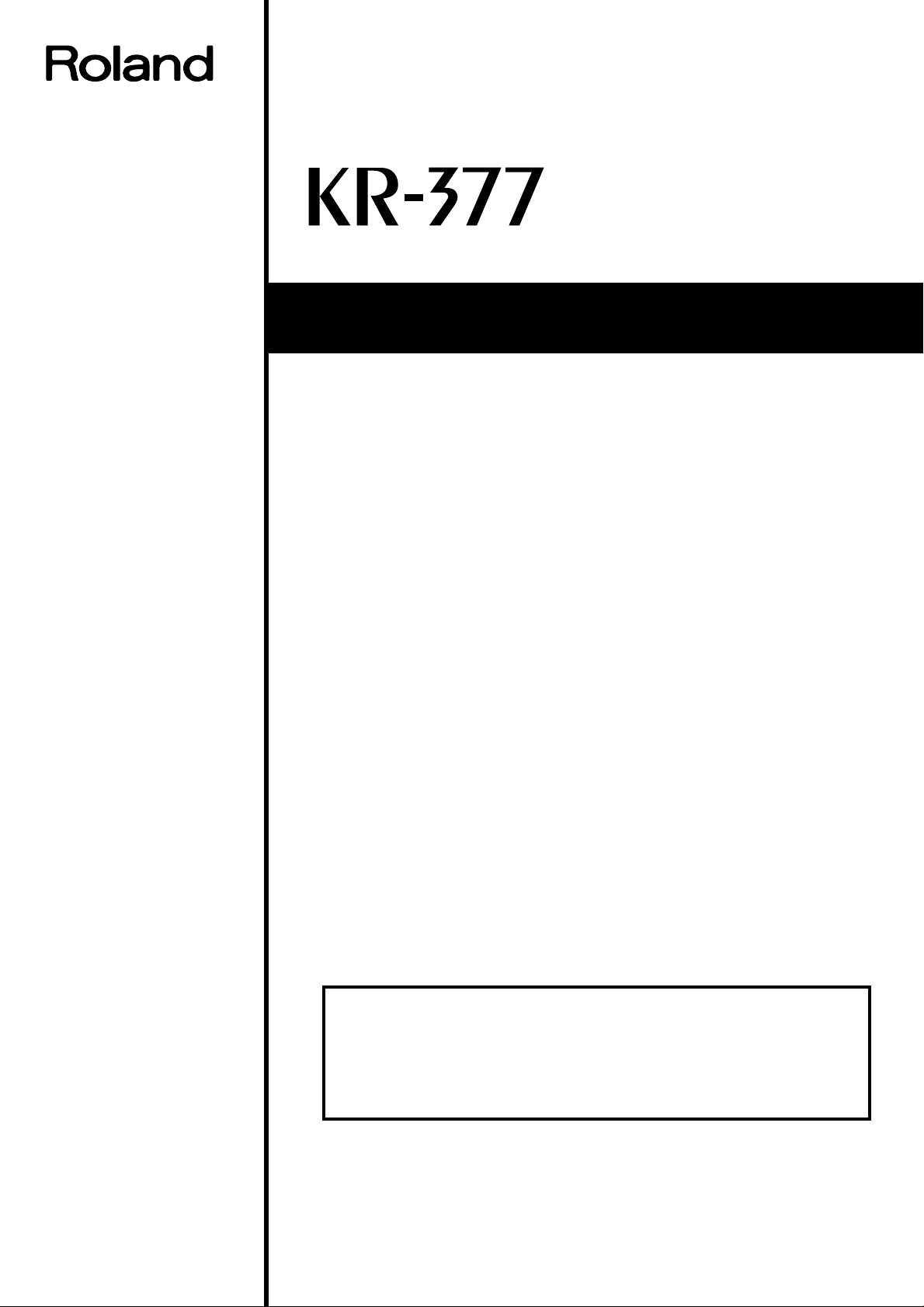
DIGITAL INTELLIGENT PIANO
取扱説明書
この機器を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」
(P.2、3)と「使用上のご注意」(P4、5)をよくお読みください。また、こ
の機器の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお
読みください。取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手
元に置いてください。
2000 ローランド
©
本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。
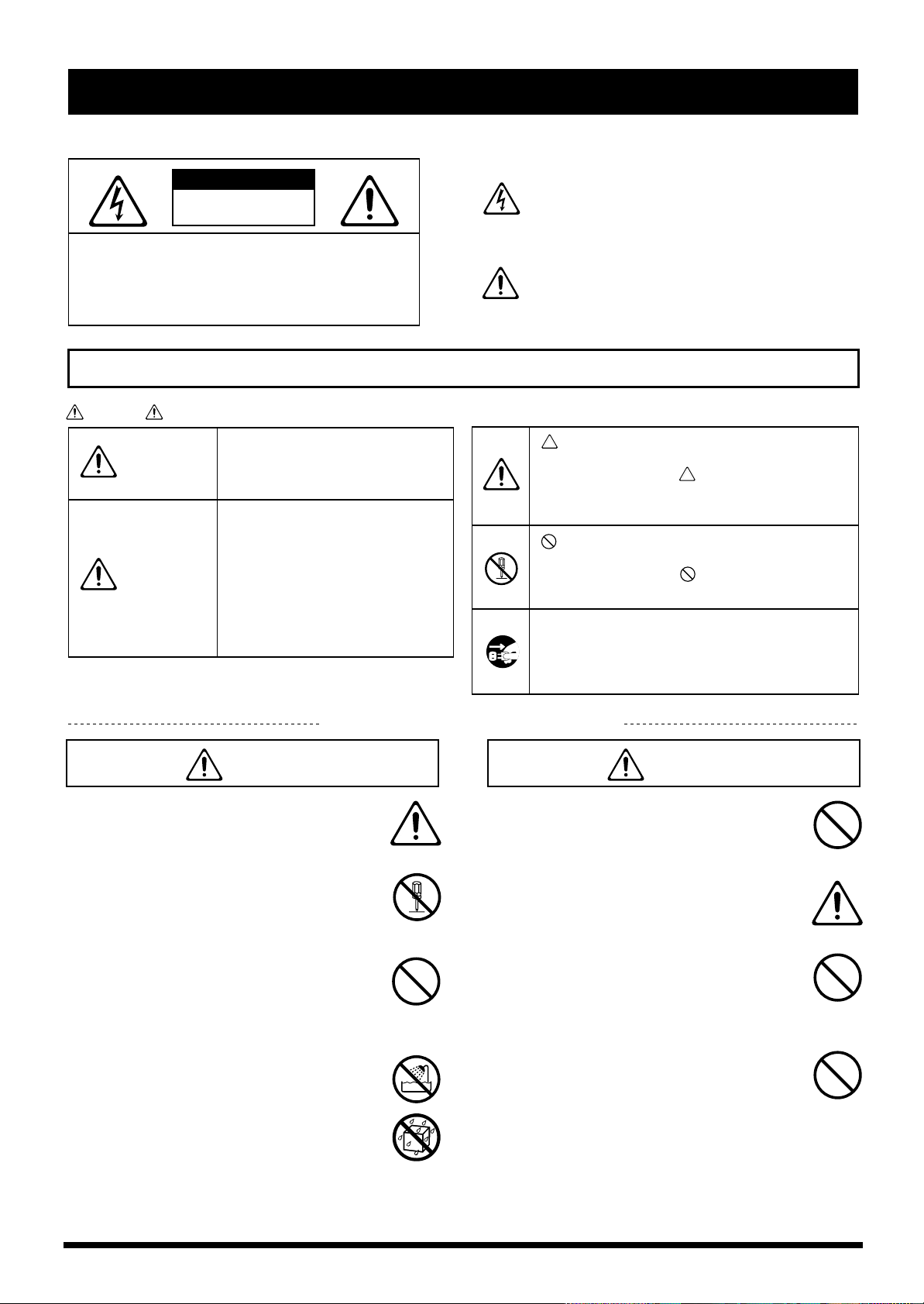
安全上のご注意
安全上のご注意
マークについて この機器に表示されているマークには、次のような意味があります。
注意:
注意
感電の恐れあり
キャビネットをあけるな
感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。
この機器の内部には、お客様が修理/交換できる部品
はありません。
修理は、お買い上げ店またはローランド・サービスに
依頼してください。
火災・感電・傷害を防止するには
注意の意味について警告と
取扱いを誤った場合に、使用者が
警告
注意
死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を表わしています。
取扱いを誤った場合に、使用者が
傷害を負う危険が想定される場合
および物的損害のみの発生が想定
される内容を表わしています。
※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表わしています。
このマークは、機器の内部に絶縁されていない「危
険な電圧」が存在し、感電の危険があることを警
告しています。
このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書
などに、一般的な注意、警告、危険の説明が記載さ
れていることを表わしています。
図記号の例
は、注意(危険、警告を含む)を表わしていま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表わしています。
は、禁止(してはいけないこと)を表わしてい
ます。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表わしています。
●は、強制(必ずすること)を表わしています。
具体的な強制内容は、●の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表わしています。
以下の指示を必ず守ってください
警告 警告
001
● この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説
明書をよく読んでください。
..............................................................................................................
002a
● この機器を分解したり、改造したりしないでく
ださい。
..............................................................................................................
003
● 修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれ
ていないことは、絶対にしないでください。必
ずお買い上げ店またはローランド・サービスに
相談してください。
..............................................................................................................
004
● 次のような場所での使用や保存はしないでくだ
さい。
○ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場
所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など)
○ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)
や湿度の高い場所
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
..............................................................................................................
007
● この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に
設置しないでください。必ず安定した水平な場
所に設置してください。
..............................................................................................................
008a
● 電源プラグは、必ず AC100Vの電源コンセント
に差し込んでください。
..............................................................................................................
009
● 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上
に重いものを載せたりしないでください。電源
コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火
災や感電の恐れがあります。
..............................................................................................................
010
● この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アン
プ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設
定によっては永久的な難聴になる程度の音量に
なります。大音量で、長時間使用しないでくだ
さい。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直
ちに使用をやめて専門の医師に相談してくださ
い。
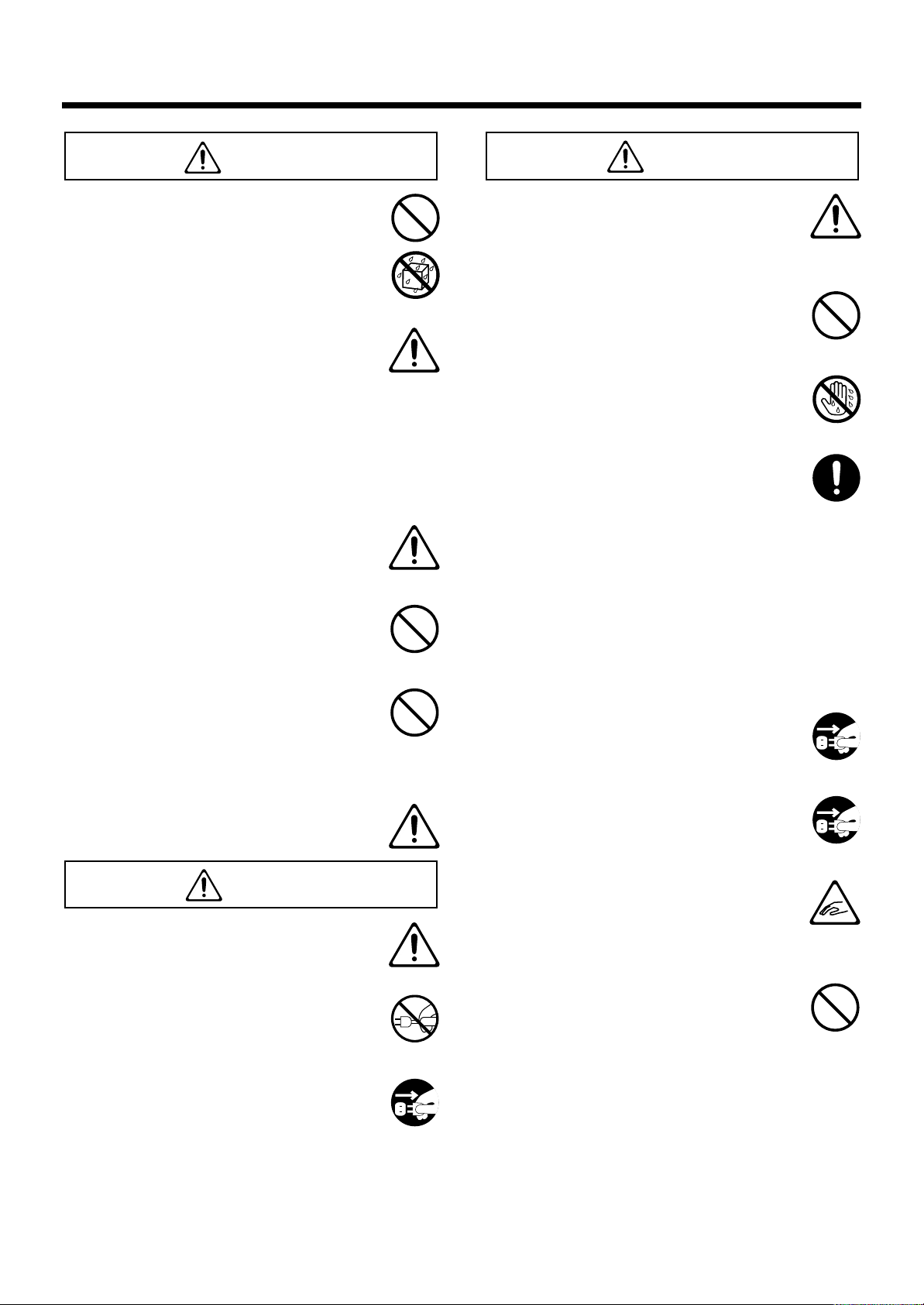
警告
注意
011
● この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針
金など)や液体(水、ジュースなど)を絶対に
入れないでください。
..............................................................................................................
012a
● 次のような場合は、直ちに電源を切って電源
コードをコンセントから外し、お買い上げ店ま
たはローランド・サービスに修理を依頼してく
ださい。
○ 電源コードやプラグが破損したとき
○ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりし
たとき
○ 機器が(雨などで)濡れたとき
○ 機器に異常や故障が生じたとき
..............................................................................................................
013
● お子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の
取り扱いやいたずらに注意してください。必ず
大人のかたが、監視/指導してあげてください。
..............................................................................................................
014
● この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を
与えないでください。
..............................................................................................................
015
● 電源は、タコ足配線などの無理な配線をしない
でください。特に、電源タップを使用している
場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を
超えると発熱し、コードの被覆が溶けることが
あります。
..............................................................................................................
016
● 外国で使用する場合は、お買い上げ店または
ローランド・サービスに相談してください。
104
● 接続したコードやケーブル類は、繁雑にならな
いように配慮してください。特に、コードやケー
ブル類は、お子様の手が届かないように配慮し
てください。
..............................................................................................................
106
● この機器の上に乗ったり、機器の上に重いもの
を置かないでください。
..............................................................................................................
107b
● 濡れた手で電源コードのプラグを持って、機器
本体やコンセントに抜き差ししないでくださ
い。
..............................................................................................................
108d(選択)
● この機器を移動するときは以下のことを確認し
た後、必ず 2 人以上で水平に持ち上げて運んで
ください。このとき、手をはさんだり、足の上
に落とさないように注意してください。
○ 機器本体とスタンドを固定しているネジが
ゆるんでいないか、確認する。ゆるんでいる
場合は、しっかり固定する。
○ 電源コードを外す。
○ 外部機器との接続を外す。
○ スタンドのアジャスティング・ボルトを上げ
る(P.14)。
○ フタを閉じる。
○ 譜面立てを倒す。
..............................................................................................................
109a
● お手入れをするときには、電源を切って電源プ
ラグをコンセントから外してください(P.13)。
..............................................................................................................
110a
● 落雷の恐れがあるときは、早めに電源プラグを
コンセントから外してください。
注意
101a
● この機器は、風通しのよい、正常な通気が保た
れている場所に設置して、使用してください。
..............................................................................................................
102b
● 電源コードを機器本体やコンセントに抜き差し
するときは、必ずプラグを持ってください。
..............................................................................................................
103a
● 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセ
ントから外してください。
..............................................................................................................
..............................................................................................................
116
● フタの開け閉めは、指などをはさまないように、
注意して行なってください(P.13)。小さいお子
様が使用されるときは、大人のかたが介添えし
てください。
..............................................................................................................
117(選択)
● ピアノ椅子を使用するときは、必ず次の事項を
守ってください。
○ 椅子で遊んだり、踏み台にしない。
○ 2人以上で腰掛けない。
○ 腰掛けたままで、高さ調節しない。
○ ピアノ椅子の脚を止めているボルトが緩ん
でいたら、腰掛けない。(緩みがあるときは
随時付属のスパナで締め直してください)
..............................................................................................................
3

使用上のご注意
291a
2、3 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。
電源について
301
● 雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電
力の大きな機器とは、別のコンセントを使用してくださ
い。
307
● 接続するときは、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐ
ため、必ずすべての機器の電源を切ってください。
308
● 完全に電源を切る必要があるときは、この機器の電源ス
イッチを切った後、コンセントからプラグを抜いてくだ
さい。そのため、電源コードのプラグを差し込むコンセ
ントは、この機器にできるだけ近い、すぐ手の届くとこ
ろのものを使用してください。
設置について
351
● この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを
持つ機器があると、ハム(うなり)を誘導することがあ
ります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えて
ください。
352
● テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレ
ビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることが
あります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してく
ださい。
353
● この機器はフロッピー・ディスク・ドライブが搭載され
ていますので、次の点に注意してください。詳細は、「フ
ロッピー・ディスクをお使いになる前に」をご覧くださ
い(P.5)。
○ スピーカーなどの強い磁界の発生する場所には近づ
けない
○ この機器を極端に傾けない
○ フロッピー・ディスク・ドライブ動作中は、振動を
与えたり移動したりしない
354b
● 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く、閉め
切った車内などに放置しないでください。また、至近距
離から照らす照明器具(ピアノ・ライトなど)や強力な
スポット・ライトで長時間同じ位置を照射しないでくだ
さい。変形、変色することがあります。
355
● 故障の原因になりますので、雨や水に濡れる場所で使用
しないでください。
356
● 本機の上にゴム製品やビニール製品などを長時間放置し
ないでください。変形、変色することがあります。
357
● 本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫剤、香
水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置か
ないでください。また、表面に付着した液体は、すみや
かに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
お手入れについて
401b
● お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布
で汚れを拭き取ってください。木目にそって全体を均一
の力で拭きます。同じ所ばかり強くこすると、仕上げを
損なう恐れがあります。
402
● 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアル
コール類は、使用しないでください。
修理について
451a
● お客様がこの機器を分解、改造された場合、以後の性能
について保証できなくなります。また、修理をお断りす
る場合もあります。
453
● 当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維
持するために必要な部品)を、製造打切後 6 年間保有し
ています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて
いただきます。なお、保有期間が経過した後も、故障箇
所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上
げ店、または最寄りのローランド・サービスにご相談く
ださい。
その他の注意について
552(*** は、複数になる場合もあります)
● 本体メモリーやフロッピー・ディスクの失われた記憶内
容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。
553
● 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端
子などに過度の力を加えないでください。
554
● ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでくださ
い。
556
● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、プ
ラグを持ってください。
557
● この機器は多少発熱することがありますが、故障ではあ
りません。
558a
● 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからない
ように、特に夜間は、音量に十分注意してください。
ヘッドホンを使用すれば、気がねなくお楽しみいただけ
ます。
559b
● 輸送や引っ越しをするときは、機器を緩衝材などで十分
に梱包してください。そのまま移動すると、傷、破損、
故障などの原因となります。
560
● 譜面立てを、手前に引き倒さないでください。
● 本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外
装の仕上げを損なうことがあります。
● 鍵盤の上に物を置いたままにしないでください。
発音しなくなるなどの故障の原因になります。
562
● 接続には、当社ケーブル(PCS シリーズなど)をご使用
ください。他社製の接続ケーブルをご使用になる場合は、
次の点にご注意ください。
○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。本
機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用しない
でください。音が極端に小さくなったり、全く聞こ
えなくなる場合があります。ケーブルの仕様につき
ましては、ケーブルのメーカーにお問い合わせくだ
さい。
4
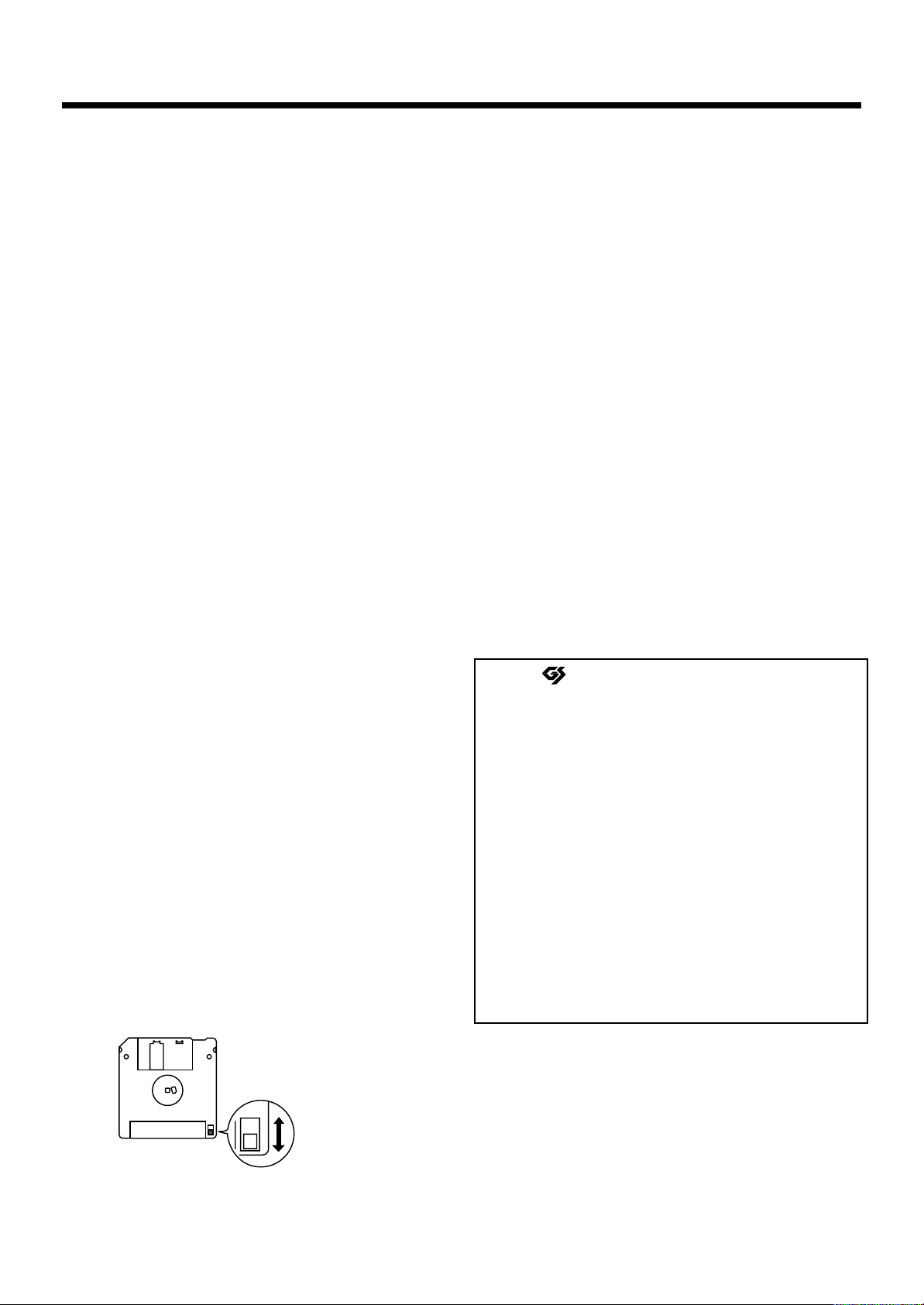
使用上のご注意
フロッピー・ディスクをお使いになる前に
フロッピー・ディスク・ドライブの取り扱い
602
● 外部からの振動を受けない、しっかりした水平な場所に
設置してください。極端に傾けると、ディスク・ドライ
ブの動作に悪影響を与えることがあります。
603
● 極端に湿度の違う場所に移動すると、ディスク・ドライ
ブに水滴がつくことがあります。このまま使用すると故
障の原因になりますので、数時間放置してから使用して
ください。
604
● ディスクを挿入するときは、確実に奥まで入れてくださ
い。ディスクを取り出すときは、イジェクト・ボタンを
奥まで押してください。万一ディスクが引っ掛かった場
合は、無理に取り出さないでください。
605b
● 読み込み/書き込み中は、ディスクを取り出さないでく
ださい。ディスクの磁性面に傷がつき、使用できなくな
ります。(データの読み込み/書き込み時は、ディスク・
ドライブのランプが明るく点灯します。通常はやや暗く
点灯、または消灯しています。)
606
● 電源を入れたり切ったりするときは、ディスクをディス
ク・ドライブから抜いてください。
607
● ディスクはディスク・ドライブに対して水平になるよう
にして、無理な力を加えずに挿入してください。無理に
挿入すると、ディスク・ドライブのヘッドが破損するこ
とがあります。
608
● ディスク・ドライブにフロッピー・ディスク以外のもの
(針金、硬貨、別の種類のディスクなど)を入れないでく
ださい。ディスク・ドライブの故障の原因になります。
フロッピー・ディスクの取り扱い
651
● ディスクはフィルムに磁性体を塗布した円盤状の記憶媒
体です。磁性面には非常に高密度でデータが記憶されま
すので、取り扱いについては次の点に注意してください。
○ 磁性面に触れない
○ ホコリの多い場所で使用しない
○ 直射日光の当たる場所や、閉め切った自動車の中な
どに放置しない(保存温度 : 10〜 50℃)
○ スピーカーなどの強い磁界を発生する場所やものに
近づけない
652
● ディスクには、書き込んだデータを誤って消さないよう
に保護するプロテクト・タブがあります。書き込み操作
を行なうとき以外は、プロテクト・タブをプロテクトの
位置にしておいてください。
フロッピー・ディスクの図
裏面
653
● ディスクのラベルは、しっかりと貼り付けてください。
ディスク・ドライブの中ではがれると、ディスクが取り
出せなくなります。
654
● ディスクは、傷めたり、チリ、ホコリなどが付かないよ
う保管には十分注意してください。チリ、ホコリなどが
付いたディスクを使用すると、ディスクが破損したり、
ディスク・ドライブの故障の原因になります。
655
● 本機の演奏データが入ったディスクを、プロテクト・タ
ブがライトの状態で、他の機種(HP-G シリーズ、MT
シリーズ、KR シリーズ、ATELIER シリーズ、PR-300
を除く)やコンピューターなどでディスク操作(内容確
認、セーブ、削除など)をすると、以降、本機のディス
ク・ドライブで使用できなくなる場合があります。他の
機種やコンピューターで、演奏データの内容確認やロー
ドをする場合は、ディスクのプロテクト・タブをプロテ
クトの状態で行なってください。
203
※ GS( )は、ローランド株式会社の登録商標です。
※ COMPOSER は、ローランド株式会社の登録商標です。
207
※ Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国及びその他
の国における登録商標です。
208
※ Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の米国及びそ
の他の国における登録商標です。
211
※ IBM PC は、米国 International Business Machines
Corporation の米国及びその他の国における登録商標で
す。
212
※ PC-9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。
215
※ MIDI は社団法人 音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標
です。
220
※ 文中記載の会社名及び製品名は、各社の商標または登録
商標です。
プロテクト・タブ
ライト
(書き込み可能)
プロテクト
(書き込み禁止)
5
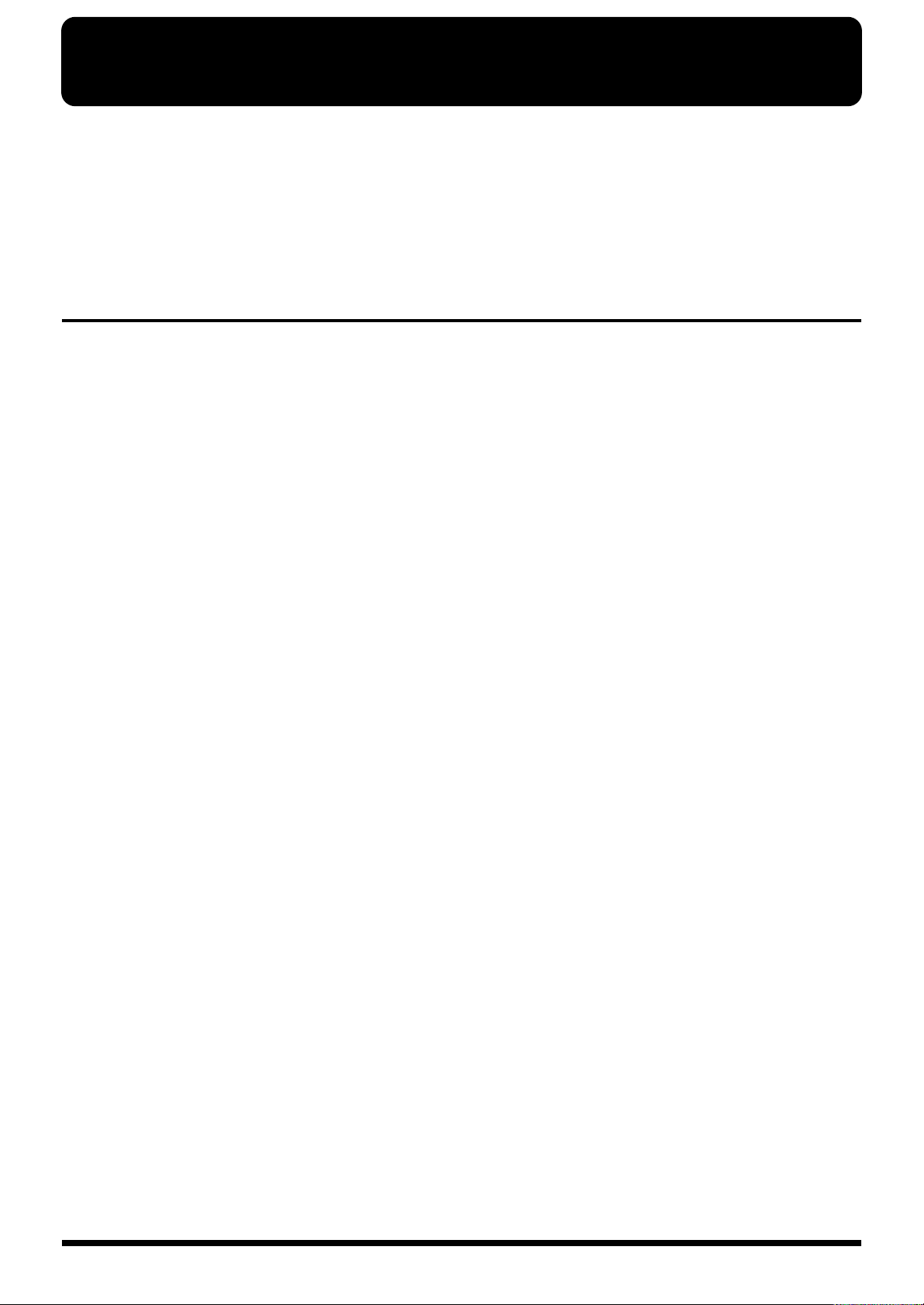
はじめに
主な特長
○本格的なピアノ演奏
このたびは、ローランド・デジタル・インテリジェント・ピアノ KR-377 をお買い上
げいただき、誠にありがとうございます。
KR-377 は、本格的なピアノ演奏はもちろん、簡単な操作で自動伴奏などの多彩な機能
を楽しめるインテリジェント・ピアノです。
本機を存分にお楽しみいただき、いつまでも良い状態でご愛用いただくためにも、この
取扱説明書をよくお読みいただけるようお願い申しあげます。
ハンマーが弦を叩く音までもリアルに再現するステレオ・サンプリング・ピアノ音源を
採用し、高品位なコンサート・グランド・ピアノの音色を再現しています。ピアノ音色
の最大同時発音数ステレオ64 音を実現したことで、ペダルを多用した演奏にも余裕で
対応できます。また、鍵盤には、低音域は重く高音域は軽く、よりピアノらしいタッチ
が得られるプログレッシブ・ハンマー・アクション鍵盤を採用。より自然で本格的なピ
アノ演奏を楽しむことができます。
○再生する曲を譜表形式で表示
ミュージックデータや録音した演奏を画面に譜表形式で表示することができます
(P.79)。
歌詞付きで表示したり、演奏パートを変えて表示させることもできます。
○簡単にやりたいことがすぐできるかんたん機能
かんたん機能は、初めてお使いになる方でも、複雑な操作をしなくても、対話形式で簡
単に演奏を録音/再生したり(P.35、P.39)、自動伴奏を使うことができます(P.29)。
また、[ヘルプ]ボタンは、いつでも画面に用語や機能の説明を表示することができま
す(P.23)。
○多彩な伴奏スタイルと自動伴奏機能
約160種類の豊富なミュージック・スタイルと自動伴奏機能を使えば、自分の演奏に、
思いどおりの伴奏をつけることができます(P.60)。
○演奏に立体的な広がりが得られる効果(アドバンスト 3D)
演奏パートを選んで音に立体的な広がりをつけるができます。
伴奏パートにこの効果をかければ、伴奏に包み込まれるような効果が得られるなど、こ
れまでになかった立体的な奥行きを感じることができます(P.33)。
6

○演奏練習をサポートする便利な機能
テープ・レコーダー感覚の録音機能 (P.91)、片手パートずつの再生 (P.85)、メトロノー
ム機能 (P.56) など練習に役立つ機能を多く備えており、電子ピアノならではの効果的
な練習を行うことができます。
○ MIDI で広がるアンサンブル(MIDI アンサンブル)
本機のMIDI 端子に電子パーカッションなど、ピアノ以外の楽器を接続して、アンサン
ブルをすることができます。「MIDI アンサンブル」を使えば、MIDI 端子に楽器を接続
し、めんどうなMIDI 設定を行わなくても、すぐに演奏することが可能です。(P.152)
○市販のミュージックデータを鑑賞したり、レッスンにも利用
ディスク・ドライブを内蔵していますので、市販のミュージックデータを再生したり、
録音した曲をフロッピー・ディスクに保存することができます(P.77、P.104)。
○カラオケを楽しむ
はじめに
マイクを接続して、曲にあわせてカラオケを楽しむこともできます(P.41)。
7
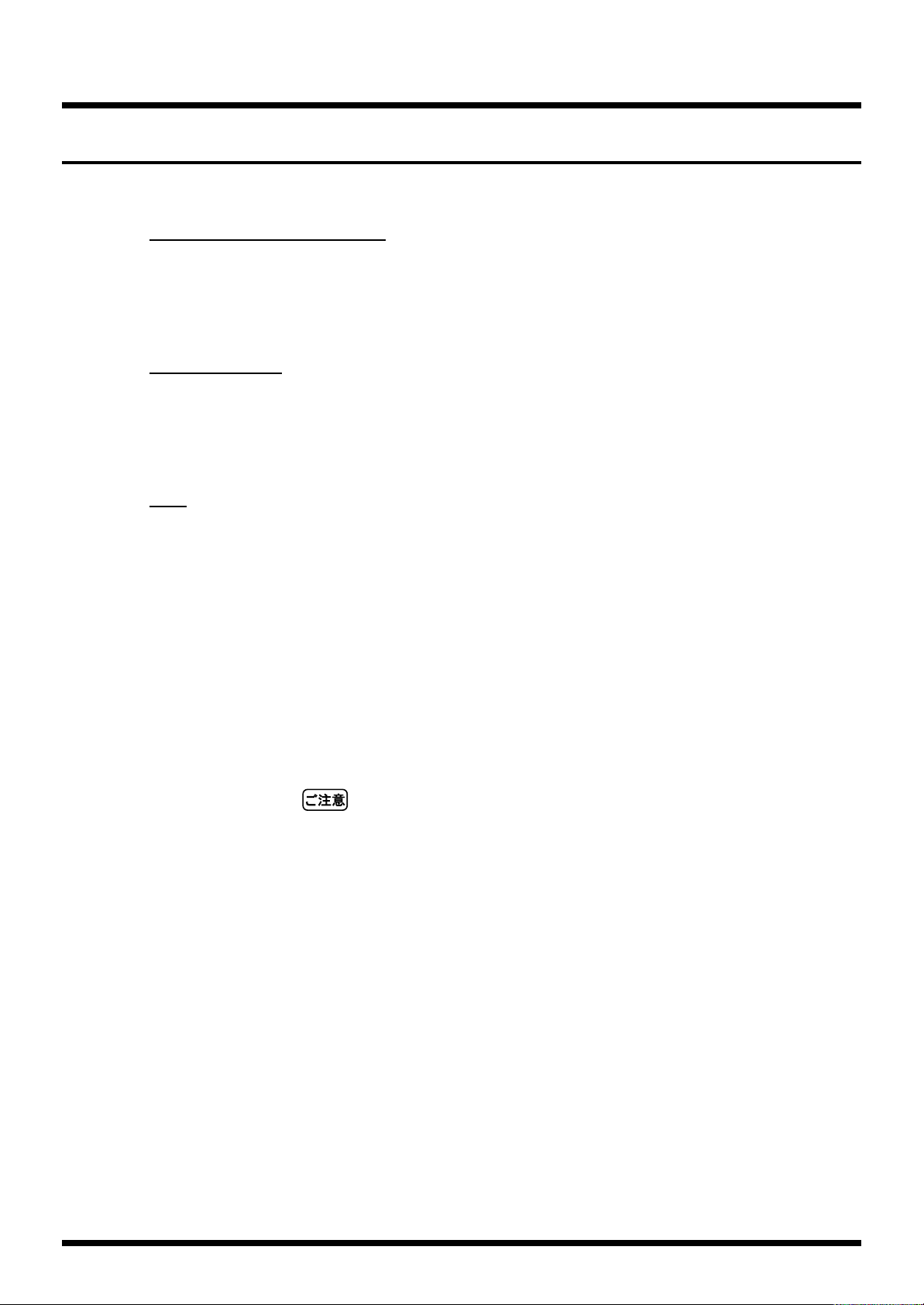
はじめに
この取扱説明書の読み方
KR-377 の取扱説明書は、次のような構成になっています。
KR-377 に触れてみましょう
KR-377 をはじめてお使いになる方のために、楽しく多彩な演奏機能を簡単にお使いい
ただけるように解説してあります。簡単操作編を読みながら演奏していただくと、KR377 でどのようなことができるのか理解いただけるようになっていますので、ぜひお
読みください。
第1章〜第 9章
KR-377 で使用できる機能について、画面図を使ってわかりやすく説明しています。
目的に合わせて必要なページをご覧ください。
やりたいことが決まっているときは「目次」を、KR-377 のボタン名から機能を知りた
いときには「各部の名称と働き」をご覧ください。また、巻末の「索引」もご利用ください。
資料
思ったように動作しないときは「故障かな?と思ったら」を読んで、設定に誤りがない
かを確認してください。また、操作中に何らかのエラー・メッセージが表示されたとき
は「こんな表示がでたら」で対応を確認してください。その他、音色一覧やスタイル一
覧、MIDI インプリメンテーションなどの資料があります。
本文中の表記について
■
この取扱説明書では、操作方法を簡潔に説明するために、次のように表記しています。
[ ]で囲まれた文字は、ボタンやつまみの名前を表し、[拡張機能]ボタン、のように
•
表記します。
< >で囲まれた文字は、画面上の文字を表し、<設定>、のように表記します。
•
この項目を選ぶときは、項目に対応する(項目の下や横に位置する)ボタンを押します。
•
文章の先頭に、 や※マークが付いているものは注意文です。
必ずお読みください。
文中の(P.**)は参照ページを表しています。
•
8
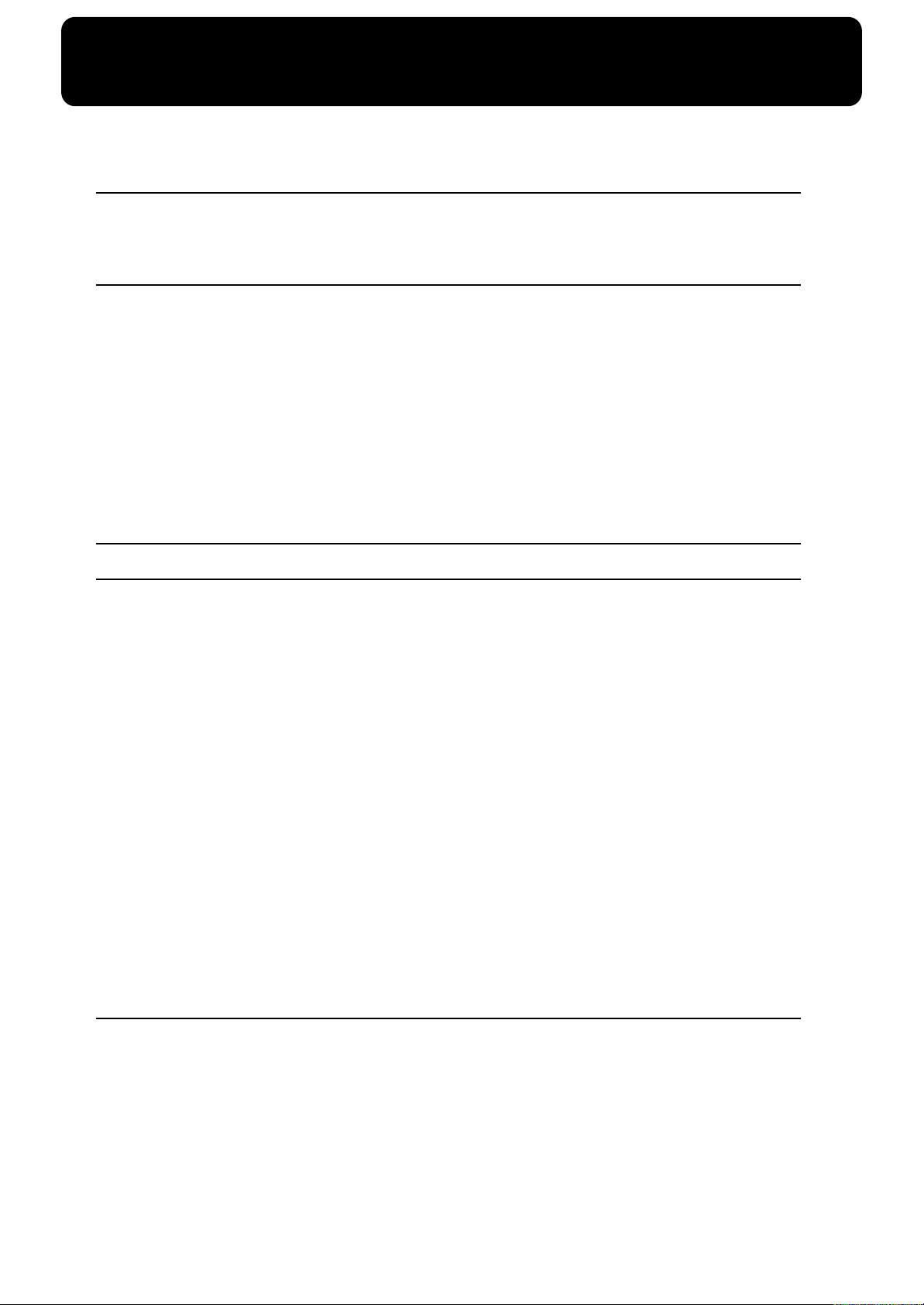
目次
安全上のご注意.............................................................................................................................2
使用上のご注意.............................................................................................................................4
はじめに...................................................................................................................6
主な特長......................................................................................................................................................6
この取扱説明書の読み方.........................................................................................................................8
本文中の表記について ...................................................................................................................................8
演奏する前に .........................................................................................................13
電源コードを接続する...........................................................................................................................13
譜面立ての立てかた...............................................................................................................................13
フタの開け閉め.......................................................................................................................................13
電源を入れる/切る...............................................................................................................................13
音の大きさを調節する...........................................................................................................................13
ペダルについて.......................................................................................................................................14
ヘッドホンをつなぐ...............................................................................................................................15
マイクをつなぐ.......................................................................................................................................15
ディスプレイの見方と基本操作..........................................................................................................16
取扱説明書の表記のきまり ........................................................................................................................16
基本画面 .........................................................................................................................................................16
ディスプレイを使った基本操作................................................................................................................17
各部の名称と働き ..................................................................................................18
KR-377 に触れてみましょう .................................................................................21
KR-377 の紹介デモを見る...................................................................................................................21
ゲームをする............................................................................................................................................22
[ヘルプ]ボタンの使いかた.................................................................................................................23
〜演奏してみましょう .....................................................................................................................24
ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)........................................................................................24
オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)...............................................................................25
いろいろな楽器の音を鳴らす...............................................................................................................26
音色を選ぶ便利な機能(音色検索)....................................................................................................27
メトロノームを鳴らす...........................................................................................................................28
〜自動伴奏を使って演奏しましょう ............................................................................................... 29
簡単に自動伴奏を楽しむ(かんたんアレンジャー).......................................................................29
自動伴奏で演奏する(ワンタッチ・アレンジャー).......................................................................30
伴奏の音に立体的な広がりをつける(アドバンスト3D)............................................................33
〜演奏を録音してみましょう .......................................................................................................... 34
簡単に演奏を録音する(かんたんレコーダー)...............................................................................34
演奏を録音する.......................................................................................................................................35
録音した演奏を聴く...............................................................................................................................37
〜ミュージックデータを使ってみましょう.....................................................................................38
ディスク・ドライブを使う...................................................................................................................38
ミュージックデータを聴く...................................................................................................................39
カラオケや弾き語りをする...................................................................................................................41
第 1 章 演奏しましょう .......................................................................................42
ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)........................................................................................42
オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)...............................................................................43
ドラムの音を鳴らす...............................................................................................................................44
効果音を鳴らす.............................................................................................................................................45
いろいろな楽器の音を鳴らす...............................................................................................................46
二つの楽器の音を重ねる(レイヤー演奏)........................................................................................47
鍵盤の右手側と左手側で別の音を鳴らす(スプリット演奏).......................................................49
鍵盤の音の高さをオクターブ単位で変える(オクターブ・シフト)..........................................51
音の明るさを調節する...........................................................................................................................52
音に響きをつける(リバーブ効果)....................................................................................................52
伴奏の音に立体的な広がりをつける(アドバンスト3D)............................................................53
9
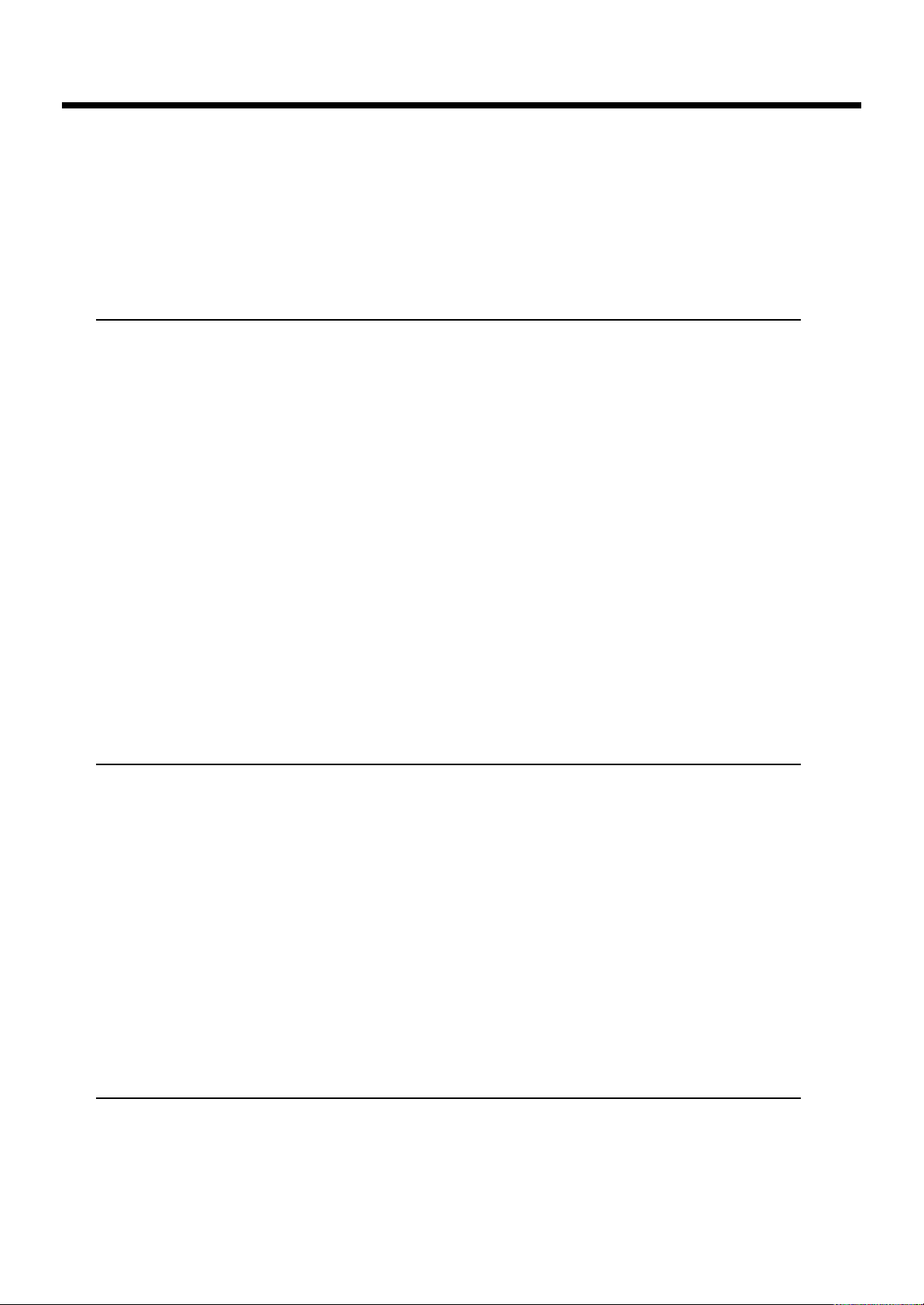
目次
鍵盤のレイヤー音色だけに効果をかける ...............................................................................................54
音にさまざまな効果をかける(エフェクト)....................................................................................55
メトロノームを鳴らす...........................................................................................................................56
テンポを調節する.........................................................................................................................................56
拍子を変える.................................................................................................................................................56
アニメーションを切り替える....................................................................................................................57
拍の刻み方(パターン)を変える............................................................................................................57
音の種類を変える.........................................................................................................................................58
音量を変える.................................................................................................................................................59
第 2 章 自動伴奏 ..................................................................................................60
ミュージック・スタイルと自動伴奏..................................................................................................60
コードについて.......................................................................................................................................61
簡単な指使いでコードを押さえる(コード・インテリジェンス機能)...........................................61
コードの押さえ方を画面に表示させる(コード検索)........................................................................62
ミュージック・スタイルを選ぶ..........................................................................................................63
データ・ディスクのスタイルを使う........................................................................................................64
自動伴奏を鳴らしながら左手で弾いた音を鳴らす.........................................................................65
リズム・パターンだけを鳴らす..........................................................................................................66
自動伴奏のテンポを調節する...............................................................................................................66
ミュージック・スタイルを鳴らす(スタート/ストップ)...........................................................67
鍵盤左側を弾くと同時に自動伴奏をスタートする(シンクロ・スタート)...................................67
ボタンを押してスタートする....................................................................................................................67
自動伴奏をストップする ............................................................................................................................68
伴奏の途中でタイミングを合わせて再スタートする(リセット)....................................................68
イントロの終わりにカウント音を鳴らす..........................................................................................69
伴奏に変化をつける...............................................................................................................................70
曲中で伴奏パターンを変える(フィルイン).........................................................................................70
伴奏のアレンジを変える ............................................................................................................................71
右手で弾いた音にハーモニーをつける(メロディー・インテリジェンス)..............................73
通常のピアノ演奏に自動伴奏をつける(ピアノ・スタイル・アレンジャー).........................74
伴奏と鍵盤の音量バランスを変える..................................................................................................75
演奏パートごとに音量を調節する......................................................................................................75
第 3 章 曲の練習に便利な機能.............................................................................77
練習する曲を再生する...........................................................................................................................77
すべての曲を連続して再生する................................................................................................................78
譜表表示をする.......................................................................................................................................79
グラフ/鍵盤画面で自分の演奏を確認する...........................................................................................80
テンポを調節する...................................................................................................................................82
ボタンを押す間隔でテンポを決める........................................................................................................82
一定のテンポで再生する.......................................................................................................................83
演奏が始まる前にカウント音を鳴らす..............................................................................................84
練習するパートを鳴らさないようにする..........................................................................................85
曲中にマークをつけて練習する..........................................................................................................86
曲中にマークをつける/取り消す............................................................................................................86
マークの位置から再生する ........................................................................................................................87
マークを移動する.........................................................................................................................................87
同じところを繰り返し再生する..........................................................................................................88
鍵盤の音の高さを変える(キー・トランスポーズ).......................................................................89
曲を移調して再生する...........................................................................................................................90
第 4 章 演奏の録音と保存....................................................................................91
簡単に演奏を録音する...........................................................................................................................91
自動伴奏を使って録音する...................................................................................................................94
録音をやり直す.......................................................................................................................................96
録音した曲を消す...................................................................................................................................97
特定のトラック・ボタンの演奏だけを消す...........................................................................................97
録音の止め方を変える...........................................................................................................................98
10
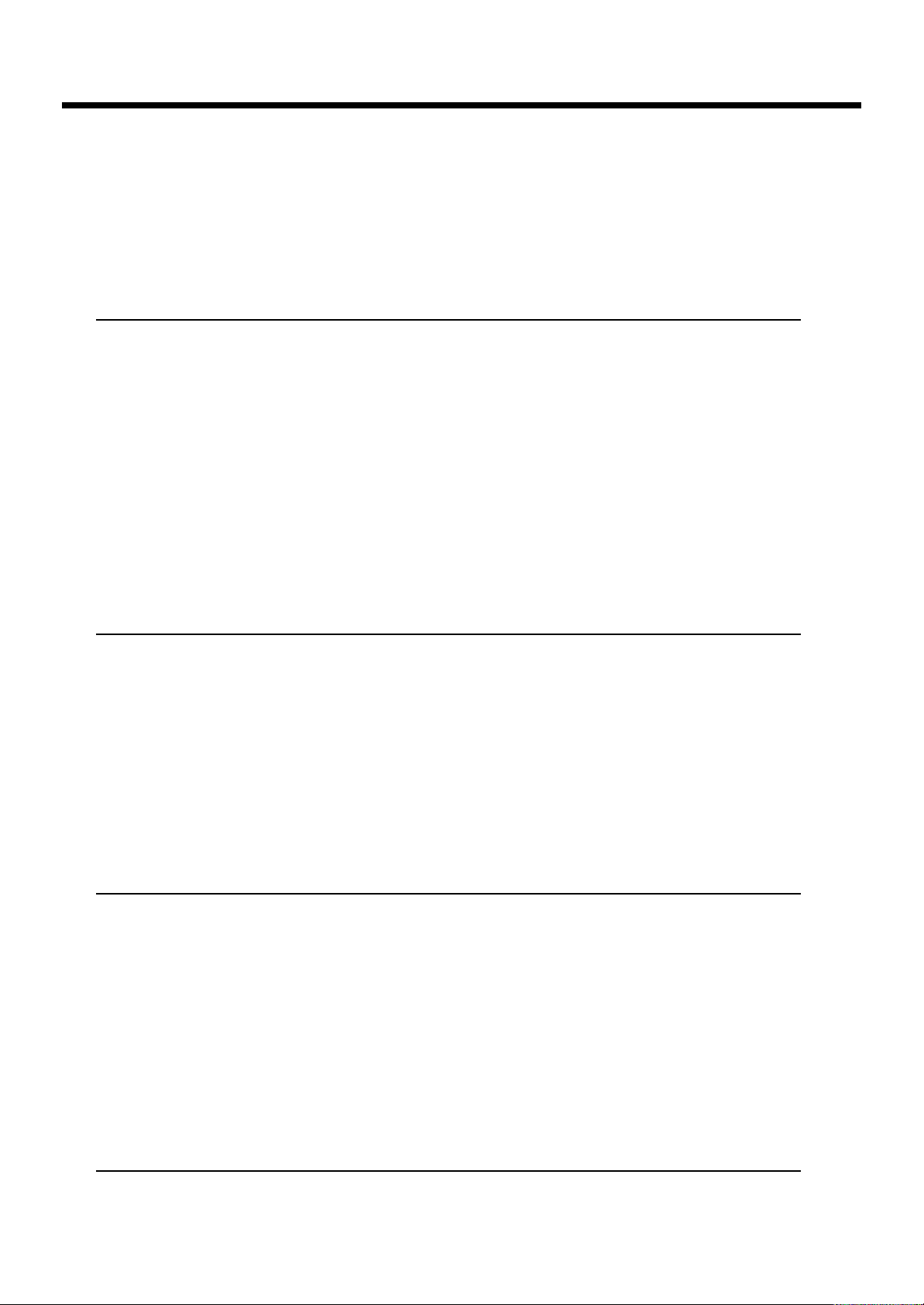
弱起の曲を録音する...............................................................................................................................99
コードを入力して曲の伴奏を作る(コード・シーケンサー)....................................................100
簡単にリズム・パートを作る............................................................................................................103
曲をフロッピー・ディスクに保存する...........................................................................................104
フロッピー・ディスクの初期化(フォーマット)...............................................................................104
フロッピー・ディスクに保存する..........................................................................................................105
曲の音色セットを変えて保存する(保存モード機能)......................................................................107
フロッピー・ディスクに保存したデータを消す..........................................................................108
フロッピー・ディスクの曲順を変える...........................................................................................109
第 5 章 より進んだ録音機能 ..............................................................................110
録音方法を選ぶ....................................................................................................................................110
録音方法の選び方.......................................................................................................................................110
録音済みの音を消して録音する(リプレース・レコーティング)..................................................110
録音済みの音を消さずに重ねて録音する(ミックス・レコーディング).....................................110
同じ区間を繰り返し録音する(ループ・レコーディング)..............................................................111
ある区間の録音をやり直す(パンチ・イン・レコーティング)......................................................112
16 パートを使って多重録音する(16 トラック・シーケンサー)........................................... 113
16 トラック・シーケンサー画面............................................................................................................113
16 トラック・シーケンサーの録音方法...............................................................................................114
パートごとの設定を変える................................................................................................................115
曲の途中で拍子の変わる曲を作る...................................................................................................116
曲の基本テンポを変える....................................................................................................................117
曲の途中でテンポを変える................................................................................................................117
曲を聴きながらテンポを変える..............................................................................................................117
ある小節からテンポを変える..................................................................................................................118
目次
第 6 章 編集する ................................................................................................119
編集機能の選びかた............................................................................................................................ 119
編集を取り消す....................................................................................................................................119
小節をコピーする................................................................................................................................120
リズム・パターンをコピーする.......................................................................................................121
音のばらつきを揃える........................................................................................................................121
ある小節を削除する............................................................................................................................ 122
空白の小節を挿入する........................................................................................................................122
小節を空白にする................................................................................................................................123
パートごとに移調する........................................................................................................................123
パートを入れ替える............................................................................................................................ 124
1 つ1 つの音符を修正する................................................................................................................ 124
曲の途中の音色変更を修正する.......................................................................................................125
第 7 章 その他の機能を使う ..............................................................................126
オリジナルのスタイルを作る(ユーザー・スタイル)................................................................126
スタイルを組み合わせて新しいスタイルを作る(スタイル・コンポーザー).............................126
ディビジョンごとにパートを鳴らさないようにする.........................................................................127
録音した曲からスタイルを作る(スタイル・コンバーター)..........................................................128
ユーザー・スタイルをボタンに登録する....................................................................................... 131
パネルの設定を登録する(ユーザー・プログラム)....................................................................131
ユーザー・プログラムを呼び出す...................................................................................................132
ユーザー・プログラムの呼び出しかたを変える.................................................................................132
ユーザー・スタイルやユーザー・プログラムをディスクに保存する.....................................132
ユーザー・スタイルやユーザー・プログラムをディスクに保存する ...........................................132
ディスクに保存したユーザー・スタイルやユーザー・プログラムを消す ...................................133
ディスクに保存したユーザー・プログラムを呼び出す ....................................................................133
ピアノ演奏以外できないようにする(パネル・ロック)............................................................133
第 8 章 いろいろな設定を変える.......................................................................134
ワンタッチ・ピアノの設定を変える...............................................................................................134
いろいろな演奏場所の雰囲気を味わう(アンビエンス)..................................................................134
鍵盤のタッチ感を変える(キー・タッチ)...........................................................................................135
11
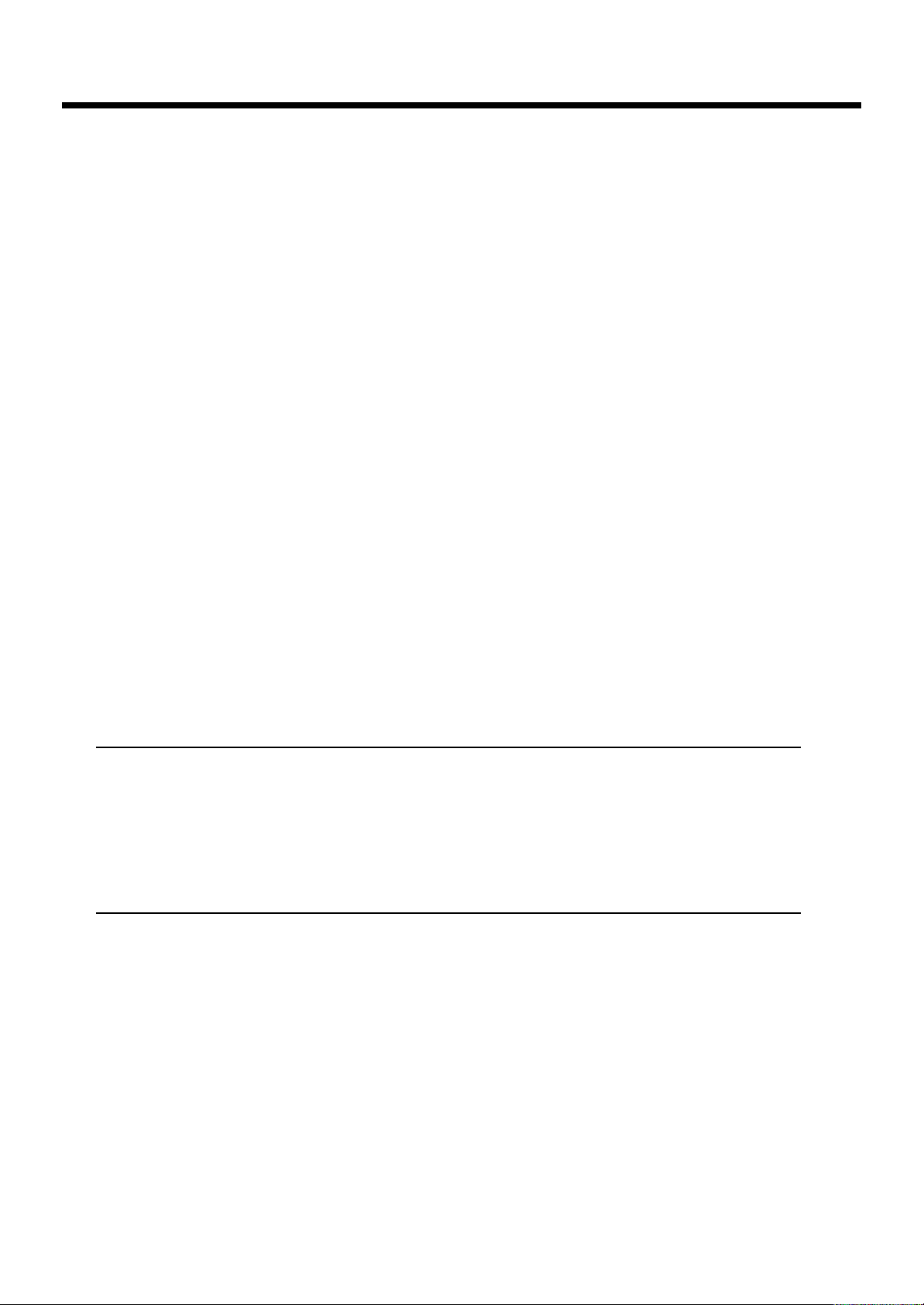
目次
ペダルの感度を調節する(ペダル・モード).......................................................................................135
共鳴音を調節する(レゾナンス)............................................................................................................135
調律方法を変える(調律)........................................................................................................................136
ピアノ音色を微調整する(サウンド)....................................................................................................137
自動伴奏の設定を変える....................................................................................................................137
鍵盤が分かれる位置を変える..................................................................................................................137
自動伴奏の鳴り方を変える ......................................................................................................................138
コード・トーンやベース・トーンの音色を変える.............................................................................138
コード・インテリジェンス機能を解除する.........................................................................................139
パッド・ボタンやペダルに機能を割り当てる.....................................................................................139
ミュージック・スタイルを変えても音色やテンポが変わらないようにする...............................141
ワンタッチ・オルガンの設定を変える...........................................................................................141
オルガン演奏時の自動伴奏の鳴りかたを変える.................................................................................142
鍵盤左側の鳴りかたを変える..................................................................................................................142
フッテージを調節する ..............................................................................................................................143
譜表の設定を変える............................................................................................................................ 144
曲再生時の音色セットを変える.......................................................................................................144
マークやカウント音の設定を変える...............................................................................................145
カウント音の小節数や音を変える..........................................................................................................145
繰り返しのたびにカウント音を鳴らす .................................................................................................145
小節の途中にマークをつける..................................................................................................................145
基準ピッチを変える(マスター・チューニング)........................................................................146
リバーブ効果の種類を変える............................................................................................................146
コーラス効果の種類を変える............................................................................................................147
ベンド・レンジを変える....................................................................................................................147
画面の設定を変える............................................................................................................................ 148
歌詞を表示させないようにする..............................................................................................................148
画面に表示される言語を変える..............................................................................................................148
画面の明るさを調節する ..........................................................................................................................148
電源投入時の画面表示を変える(オープニング・メッセージ)...............................................148
電源を切っても設定を記憶させておく(メモリー・バックアップ).......................................149
製品出荷時の設定に戻す(ファクトリー・リセット)................................................................149
第 9 章 外部機器との接続..................................................................................150
接続端子の名称と働き........................................................................................................................150
MIDI機器と接続する...........................................................................................................................151
接続の手順............................................................................................................................................. 151
MIDI楽器とアンサンブルをする(MIDI アンサンブル)............................................................. 152
MIDIの設定...........................................................................................................................................152
オーディオ機器と接続する................................................................................................................154
コンピューターと接続する................................................................................................................155
資料......................................................................................................................158
故障かな?と思ったら..............................................................................................................158
こんな表示がでたら..................................................................................................................160
音色一覧....................................................................................................................................162
ドラム/効果音一覧..................................................................................................................166
ミュージック・スタイル一覧...................................................................................................171
リズム・パターン一覧..............................................................................................................173
コードの押さえかた一覧 ..........................................................................................................174
エフェクト一覧.........................................................................................................................176
KR-377 で使用できるミュージックデータ...............................................................................178
KR-377 で使用できるミュージックデータ..........................................................................................178
KR-377 の音源について...........................................................................................................................178
用語集.......................................................................................................................................179
MIDI インプリメンテーションチャート ...................................................................................180
主な仕様....................................................................................................................................181
12
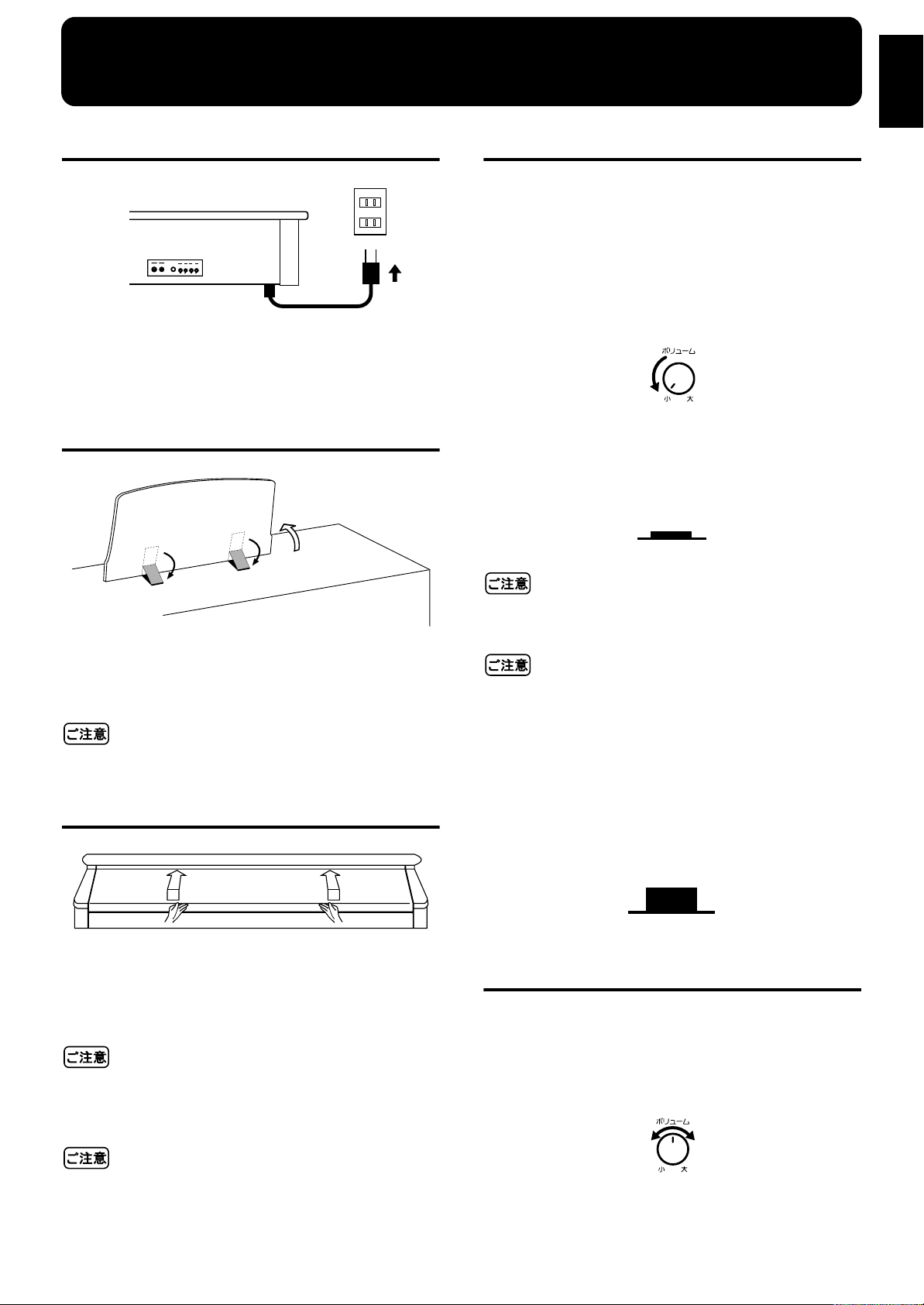
演奏する前に
演奏する 前に
電源コードを接続する
fig.00-01
MIDI
PedalInOut
Output
Input
)
)
RL(Mono
RL(Mono
Stereo
Stereo
1. 付属の電源コードを、ピアノ本体の底面にある AC
インレットに接続します。
2.
付属の電源コードを、コンセントに差し込みます。
譜面立ての立てかた
fig.00-02
(1)
(2)
譜面立てを静かに起こし、図のように固定します。
1.
(2)
電源を入れる/切る
必ず次の手順で電源を入れたり、切ったりしてください。手
順を間違えると、誤動作をしたりスピーカーなどが破損
する恐れがあります。
■ 電源を入れる
1.
電源を入れる前に、[ボリューム]つまみを「小」
側へいっぱいまで回します。
fig.00-04
[Power(電源)]スイッチを押します。
2.
電源が入り、数秒後には、鍵盤を弾いて音を出せるよう
になります。
fig.00-05
押し下げられた状態が
オン
本機は、回路保護のため電源を入れてからしばらくは動作し
ません。
2.
後ろに倒すときは、譜面立てを手で支え、金具を
折り曲げてからゆっくりと倒します。
譜面立てを、手前に引き倒さないでください。
フタの開け閉め
fig.00-03
1.
フタを開けるときは、フタを両手で持って軽く立
ち上げ、奥にスライドさせます。
2.
フタを閉めるときは、ゆっくりと手前に引き、止
まったところで静かに下におろします。
指をはさまないように注意して、フタを開け閉めしてくださ
い。小さなお子さまが使用される場合は、大人の方が介添し
てください。
電源コードは必ず付属のものをお使いください。
■ 電源を切る
電源を切る前に、[ボリューム]つまみを「小」側
1.
いっぱいまで回します。
2.
[Power(電源)]スイッチを押します。
電源が切れます。
fig.00-06
上がった状態が
オフ
音の大きさを調節する
全体の音量を調節します。
1.
[ボリューム]つまみを左右に回します。
「大」側に回すと音が大きくなり、「小」側に回すと音が
小さくなります。
fig.00-07
ピアノの移動は、危険防止のため必ずフタを閉じた状態で行
なってください。
13
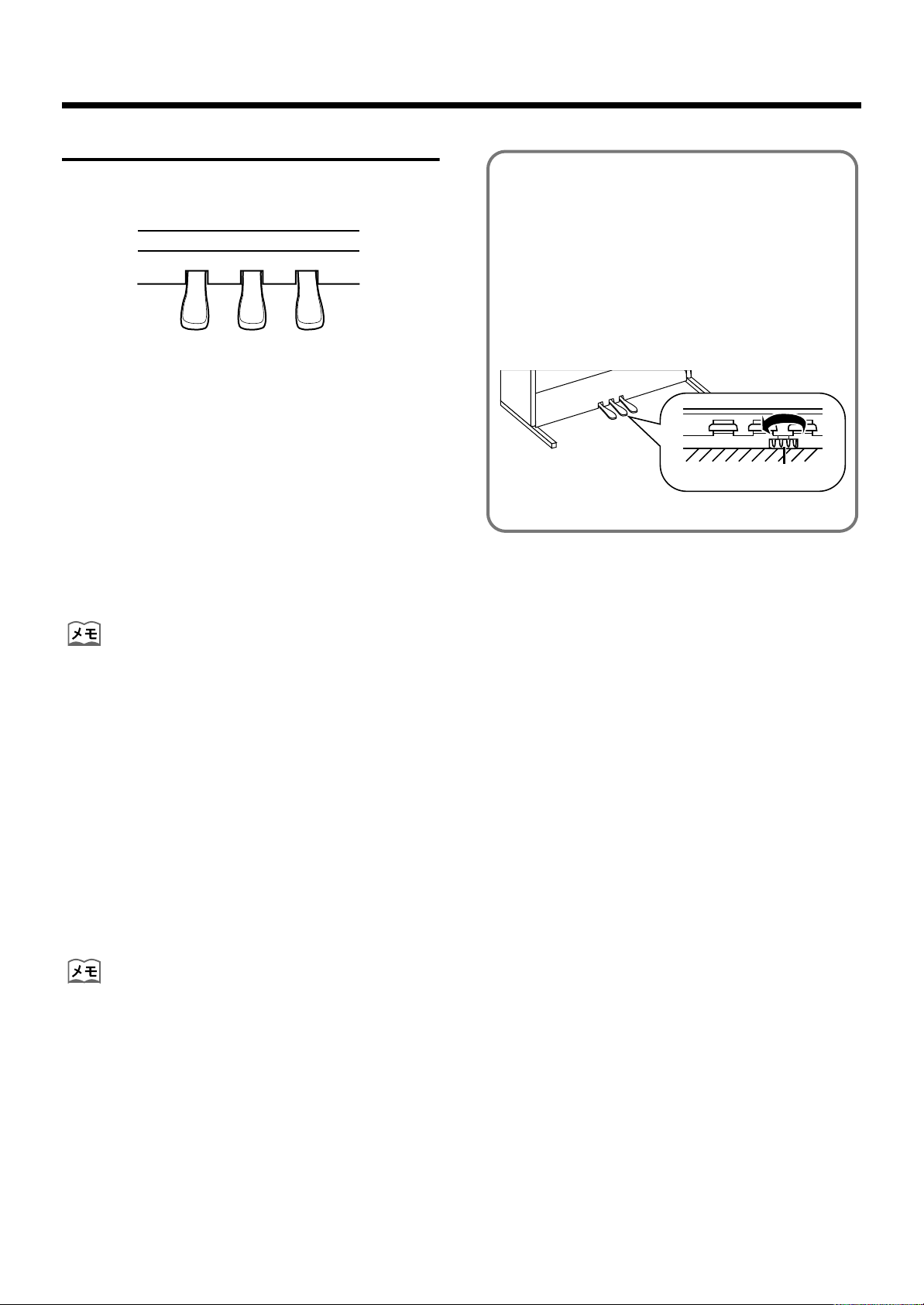
演奏する前に
ペダルについて
[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押してピアノ演奏をしてい
るとき(P.42)、ペダルは次のように働きます。
fig.00-08
ソフト・ペダル
ソステヌート・ペダル
ソフト・ペダル(左ペダル)
音に柔らかさを与えたいときに使います。
ソフト・ペダルを踏んだまま鍵盤を弾くと、通常同じ強さで
弾いたときの音よりも柔らかい音が鳴ります。ペダルを踏む
深さによって、音の柔らかさを微妙に変えることができま
す。
ダンパー・ペダル
本機を移動したときや、ペダルが不安定に感じるとき
は、ペダルの下部にあるアジャスト・ボルトを次のよう
に調節し直してください。
○ アジャスターを下げ、確実に床にあたるように調節
してください。床との間に隙間があると、ペダルを
踏んだときに破損する原因になります。特にカー
ペットの上などに接地する場合は床面を強く押しつ
けるように調節してください。
アジャスター
ソステヌート・ペダル(中央ペダル)
このペダルを踏んだ時点で、押さえていた鍵盤の音だけに余
韻を与えます。
ソステヌート・ペダルとソフト・ペダルには、このほかの機
能を持たせることができます。詳しくは「ペダルに機能を割
り当てる」(P.139)をご覧ください。
ダンパー・ペダル(右ペダル)
音に余韻を与えたいときに使います。
ダンパー・ペダルを踏んでいる間、鍵盤から指を離しても音
が切れずに長い余韻が続きます。ペダルを踏む深さによって
余韻の長さを微妙に変えることができます。
アコースティック・ピアノでは、ダンパー・ペダルを踏んだ
ときに、弾いた鍵盤の音が他の弦に共鳴して豊かな響きと広
がりが加わります。KR-377 ではこの共鳴音(シンパセ
ティック・レゾナンス)を再現しています。
ダンパー・ペダルを踏んだときの共鳴量を変えることができ
ます。「共鳴音を調節する(レゾナンス)」(P.135)をご覧
ください。
14
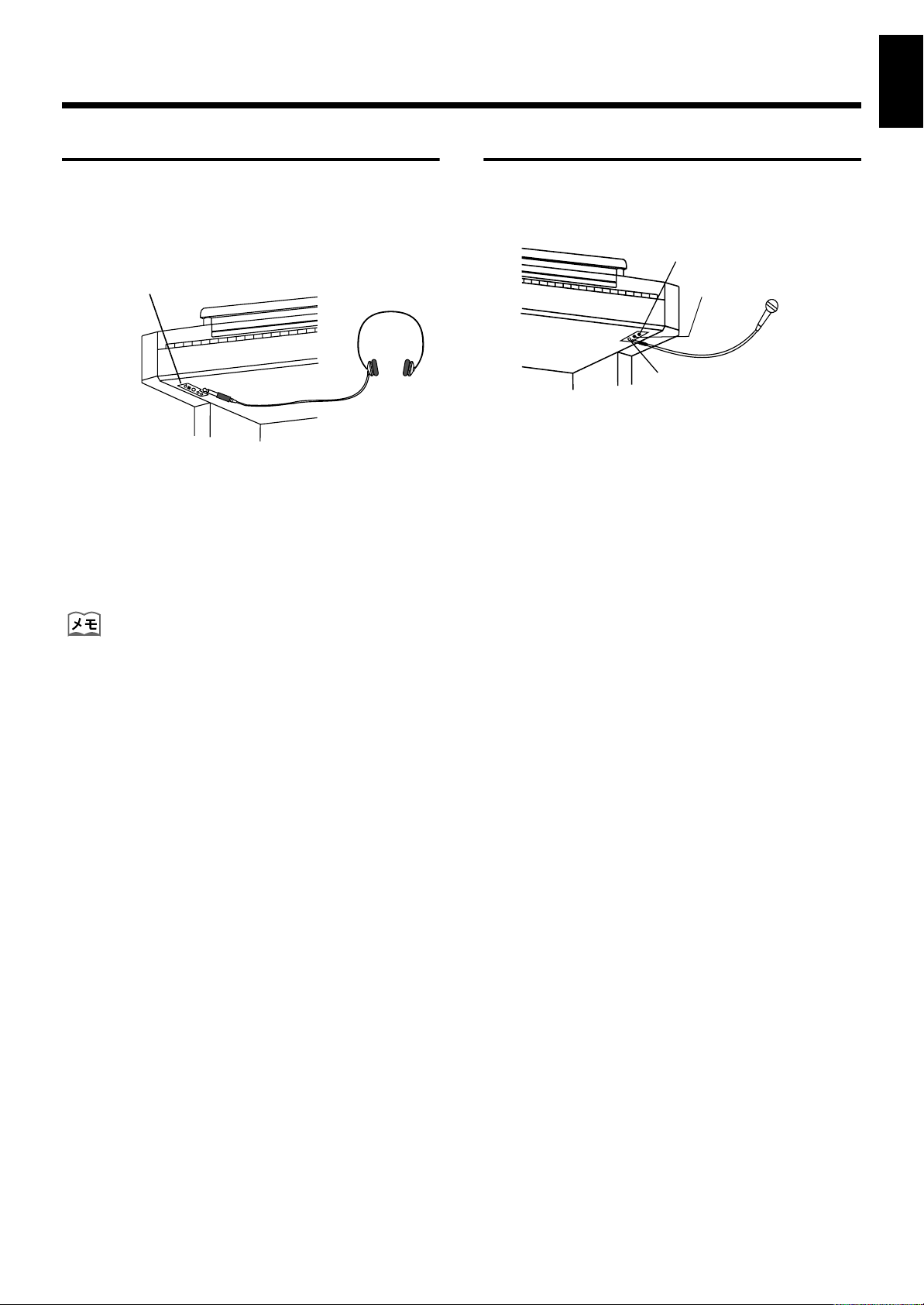
演奏する前に
演奏する 前に
ヘッドホンをつなぐ
KR-377 にはヘッドホン端子が 2 つあります。2 人で同時に
ヘッドホンを使うことができますので、レッスン時や連弾曲
を演奏するときなどに便利です。また、夜間でも周囲を気に
せずに演奏を楽しむことができます。
fig.00-09
ヘッドホン端子×2
2
1
-
C
c
C
I
P
r
a
P
D
e
I
t
M
u
M
p
m
n
I
o
I
C
D
I
M
s
e
n
o
h
P
1.
本体左下面の Phones(ヘッドホン端子)のどちら
かに、ヘッドホンを接続します。
本体スピーカーからは音が出なくなります。ヘッドホン
からのみ音が出ます。
2.
ヘッドホンの音量は、KR-377本体の[ボリュー
ム]つまみで調節します。
ヘッドホンはステレオ・タイプのものをお使いください。
マイクをつなぐ
マイク端子にマイクを接続して、カラオケや弾き語りをする
ことができます。
fig.00-10
Volume
(マイク音量つまみ)
MicEcho
(マイク・エコーつまみ)
MicIn(マイク端子)
1.
本体右下面の Mic In(マイク端子)に、マイクを接
続します。
2.
マイク端子の手前にある[Mic Echo(マイク・エ
コー)]つまみで、エコーを調節します。
[Mic Echo(マイク・エコー)]つまみの手前にあ
3.
る[Mic Volume(マイク音量)]つまみを回して、
音量を調節します。
マイクは、ローランド・マイク DR-10 / 20(別売)な
→
どを使用することができます。ご購入の際には、本機を
お買い上げになった販売店にご相談ください。
●ヘッドホンご使用上の注意
コードの断線の原因になりますので、ヘッドホンは、本
•
体またはプラグ部分を持って取り扱ってください。
•
接続の際、使用機器の音量が上がっているとヘッドホン
を壊す恐れがあります。音量を最小にしてから接続して
ください。
•
過大入力で使用すると、耳を痛めるだけでなく、ヘッド
ホンにも無理がかかります。適当な音量でお楽しみくだ
さい。
●マイクご使用上の注意
•
夜間や早朝にご使用の際には、音量にご注意ください。
本体とマイクを接続するときは音量を下げてください。
•
音量が大きいとスピーカーから雑音が出ることがありま
す。
マイクとスピーカーの位置によっては、ハウリング音
•
(キーンという音)が出ることがあります。その場合は、
以下のように対処してください。
- マイクの向きを変える
- マイクをスピーカーから遠ざける
- 音量を下げる
15
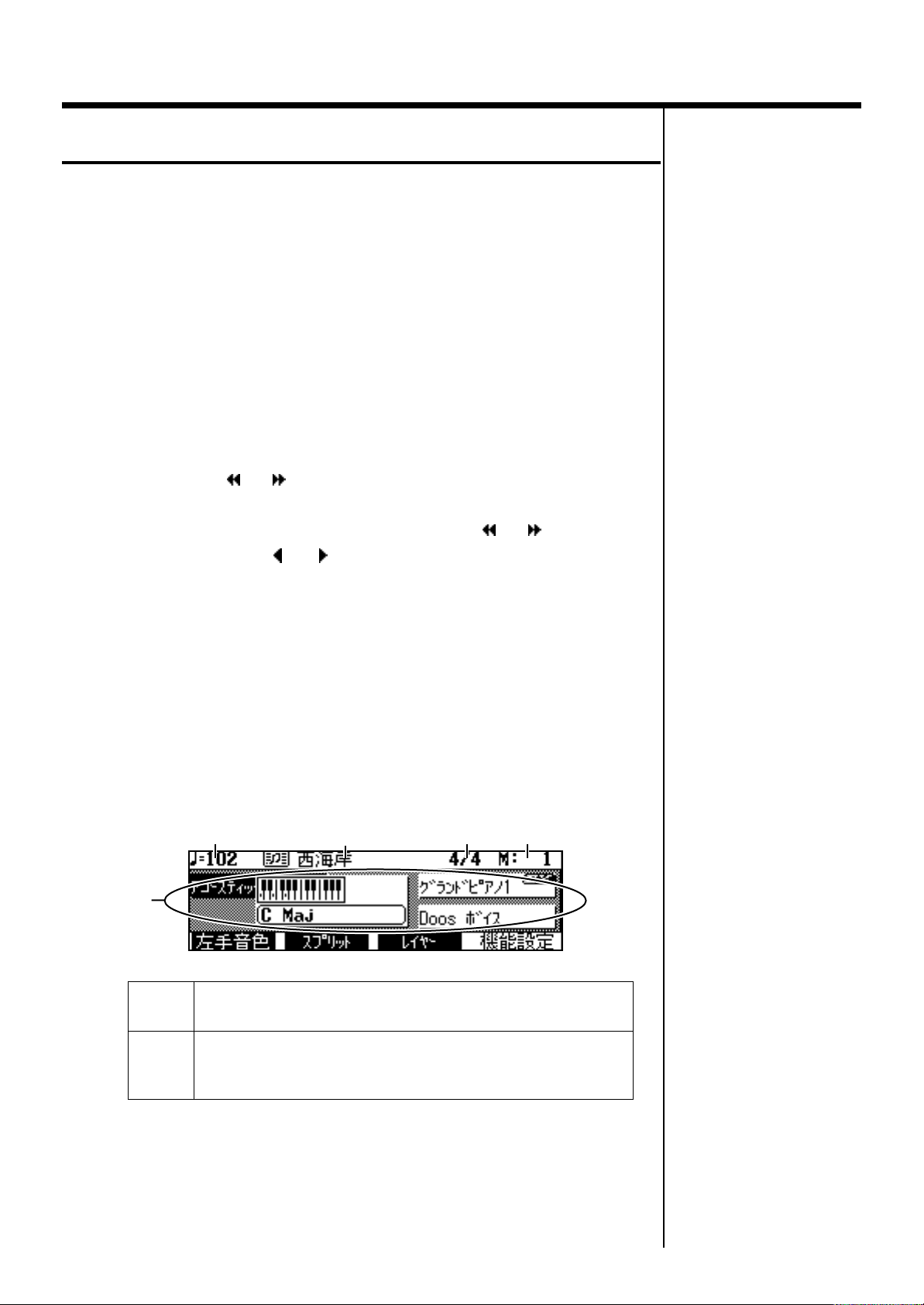
演奏する前に
ディスプレイの見方と基本操作
ディスプレイにはさまざまな情報が表示されます。また操作の多くはディ
スプレイを使っておこないます。
■ 取扱説明書の表記のきまり
本書では、パネル上にあるボタンと、ディスプレイに表示される項目を次
のように区別して表記しています。
[ ]: パネル上にあるボタンやつまみを示します。
例:[ユーティリティー]ボタンを押します。
< >:ディスプレイに表示される項目を示します。
ディスプレイに表示される項目を選ぶときは、項目に対応する
(項目の下や横に位置する)ボタンを押します。
例:ディスプレイ下の<レイヤー>を押します。
[ー][+]、< > < > などの表記は、どちらかのボタンを押すことを
示しています。
例:テンポ[ー][+]ボタン、ページ < > < >、
選択 < > < >
■ 基本画面
次のような画面を「基本画面」といいます。
通常、[戻る]ボタンを数回押すと、この画面が表示されます。
[戻る]ボタンを押しても基本画面が表示されないときは、次のどちらか
の操作をします。
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押す。
•
基本画面が表示され、自動伴奏の設定になります。
•
[ワンタッチ・ピアノ]ボタンまたは、[ワンタッチ・オルガン]ボタン
を押してから、いずれかの音色ボタンを押し、[戻る]ボタンを押す。
2
1
2
テンポ 拍子 小節
現在選んでいる曲またはミュージック・スタイルの名前など
が表示されます。
現在選んでいる音色名が表示されます。
自動伴奏を使っているときは、コードの押さえかたが表示さ
れます。
1
16
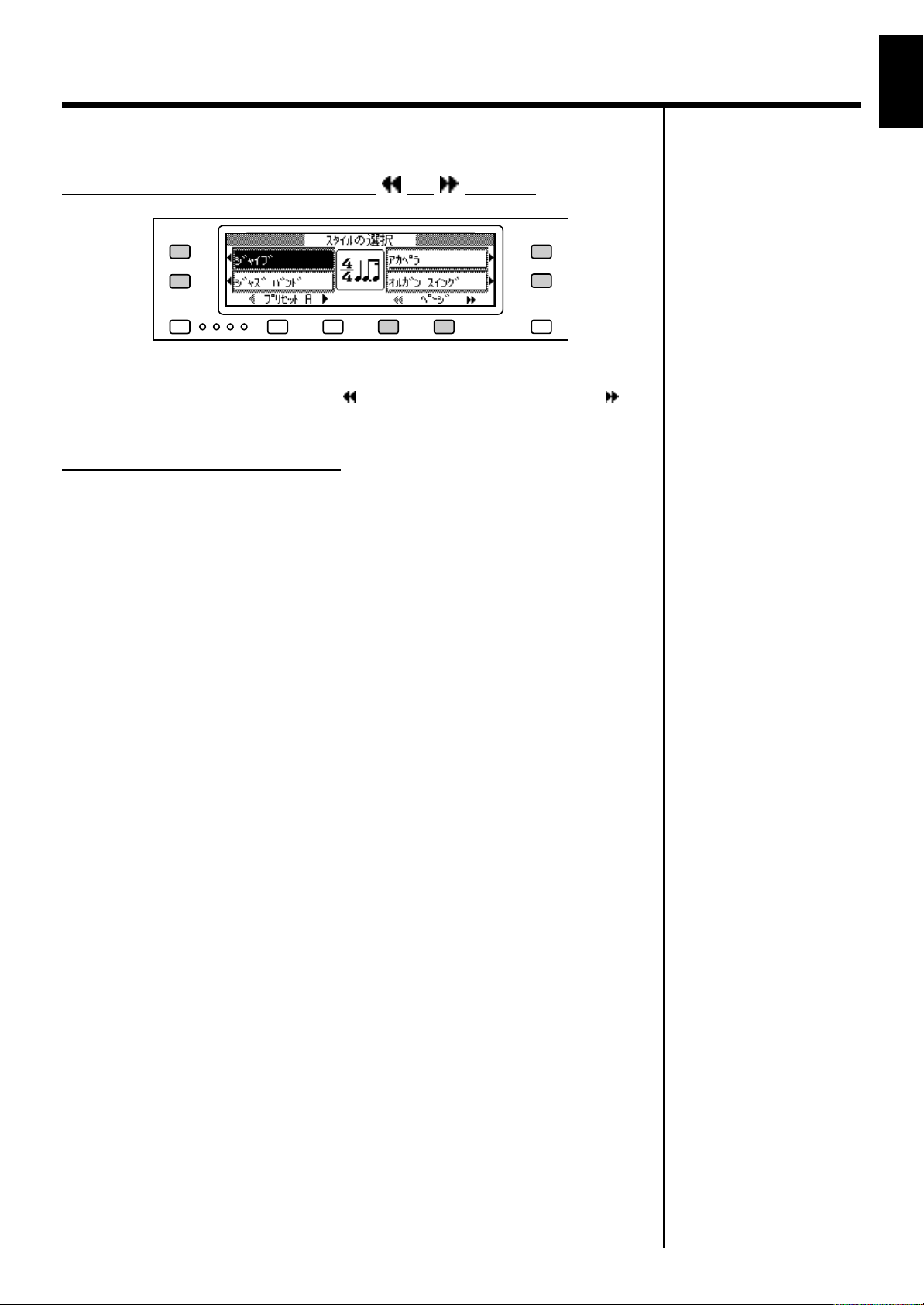
■ ディスプレイを使った基本操作
画面のページを切り替える−ページ < > < >ボタン
画面によっては複数のページで構成されるものがあります。
ディスプレイ下のボタンで、< > を押すと、前のページに戻り、< >
を押すと、次のページに進みます。
元の画面に戻る−[戻る]ボタン
現在おこなっている設定をキャンセルしたり、表示されている画面を終了
したいときは、[戻る]ボタンを押します。
通常、[戻る]ボタンを数回押すと、基本画面や元の画面に戻ります。
演奏する 前に
演奏する前に
※ 画面の明るさを調節することができます。「画面の明るさを調節する」
(P.148)をご覧ください。
※ 本書では、画面を使用して機能説明をしていますが、工場出荷時の設
定(音色名など)と本文中の画面が異なる場合もあります。あらかじ
めご了承ください。
17
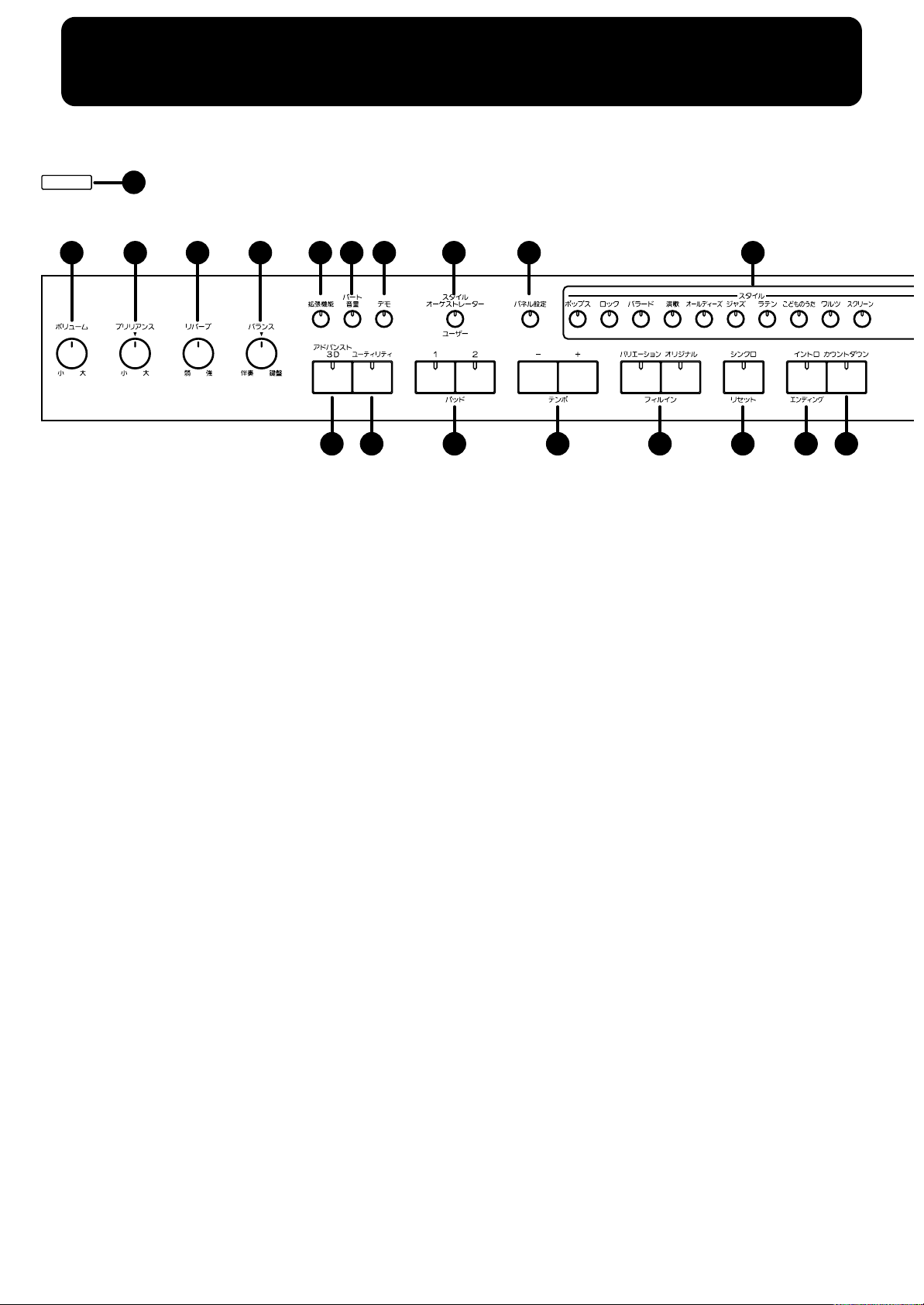
各部の名称と働き
Power
1
2 3 4 5 6 7 8 11 13 14
9 10 12 15 16 17 18 19
1. [Power(電源)]スイッチ
電源を入れたり、切ったりします (P.13)。
2. [ボリューム]つまみ
全体の音量を調節します (P.13)。
3. [ブリリアンス]つまみ
音の明るさを調節します (P.52)。
4. [リバーブ]つまみ
リバーブ効果(残響)のかかり具合を調節します (P.52)。
5. [バランス]つまみ
鍵盤を弾く音と、曲や伴奏の音量のバランスを変えます
(P.75)。
6. [拡張機能]ボタン
演奏に関するさまざまな機能を選びます(P.146 〜 P.149)。
7. [パート音量]ボタン
自動伴奏の演奏パートごとの音量や鍵盤で弾く打楽器/効果
音、鍵盤で弾く音色ごとの音量を調節します (P.75)。
8. [デモ]ボタン
内蔵のデモ曲を聴いたり、主な機能の説明など、KR-377 の
特長を画面で見ることができます (P.21)。
9. [アドバンスト 3D]ボタン
演奏空間に奥行きが加わる効果をかけます(P.33、P.53)。
10.[ユーティリティ]ボタン
音当てゲームや、自動伴奏、録音、再生、音色検索に便利な
機能を選びます。
11.[スタイル・オーケストレーター/ユーザー]ボタン
パッド・ボタンで自動伴奏のアレンジを変えられるようにし
たり (P.71)、パッド・ボタンにさまざまな機能を割り当て
て使うことができます (P.139)。
12. パッド・ボタン
パッド[1]ボタン、パッド[2]ボタンの 2 つがあります。
それぞれのボタンは、11 番のボタンによって働きが変わり
ます。
13.[パネル設定]ボタン
選んでいる機能やボタンの状態を登録します。また、登録さ
れている設定を呼び出します (P.131)。
14. スタイル・ボタン
内蔵のミュージック・スタイルを選びます(P.30、P.63)。
15. テンポ[−][+]ボタン
テンポを調節します(P.28、P.56、P.66、P.82)。
[−]ボタンと[+]ボタンを同時に押すと、基本のテンポ
に戻ります。
16. フィルイン
[バリエーション]ボタン
自動伴奏にフィルインを入れて、バリエーションの伴奏パ
ターンに変えます (P.70)。
[オリジナル]ボタン
自動伴奏にフィルインを入れて、オリジナルの伴奏パターン
に変えます (P.70)。
18
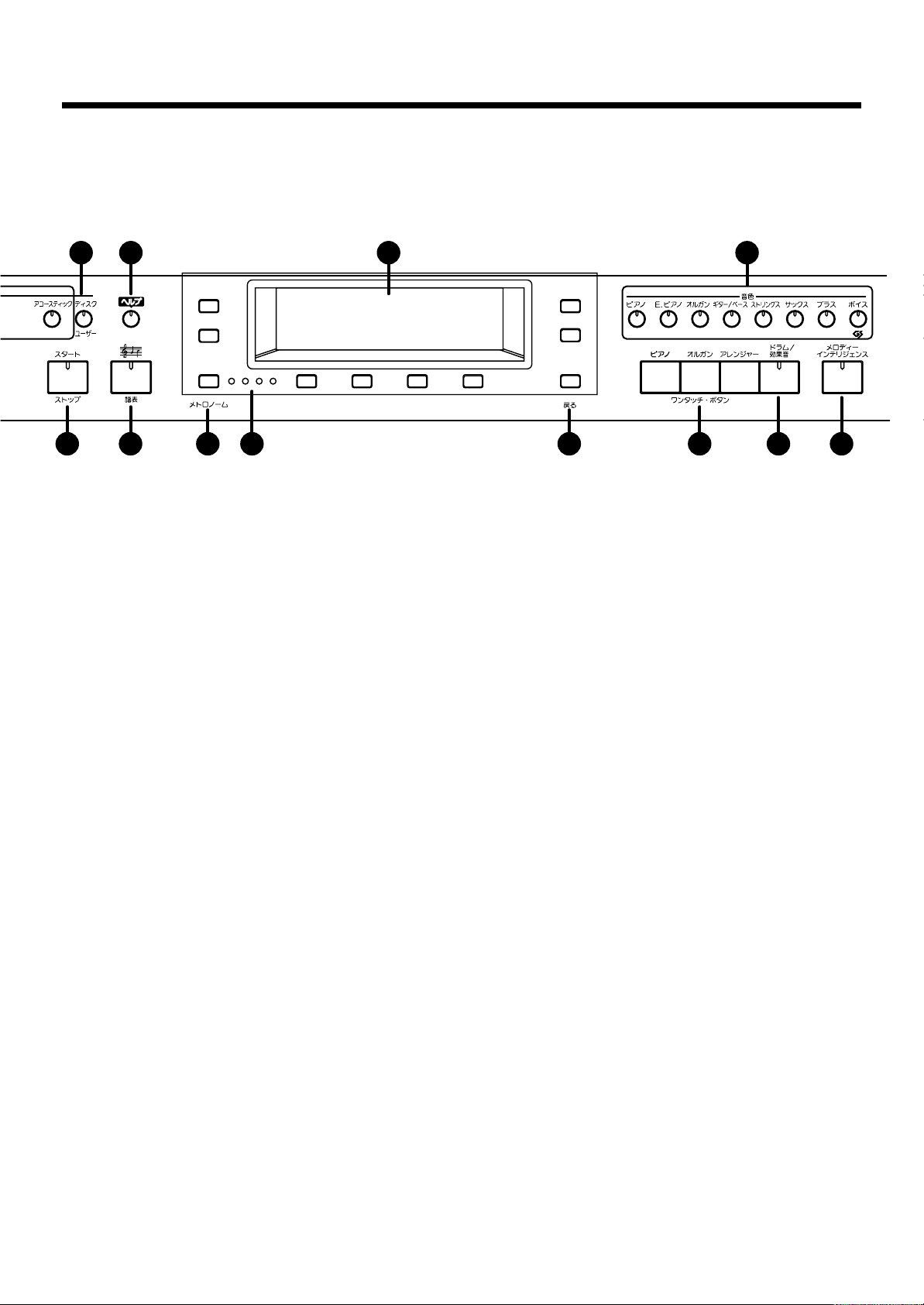
各部の名称と働き
21 22 26 31
20 2524 27 28 29 3023
17.[シンクロ/リセット]ボタン
左側の鍵盤を弾くと同時に、自動伴奏をスタートさせる(シ
ンクロ)設定にします (P.67)。
また、自動伴奏の演奏中にこのボタンを押すと、伴奏を合わ
せて再スタートする(リセット)ことができます (P.68)。
18.[イントロ/エンディング]ボタン
自動伴奏時にイントロやエンディングを鳴らします (P.67)。
19.[カウントダウン]ボタン
イントロの終わりにカウント音を入れることができます
(P.69)。
20.[スタート/ストップ]ボタン
自動伴奏をスタート/ストップします (P.67)。
21.[ディスク/ユーザー]ボタン
フロッピー・ディスクのミュージック・スタイル (P.64) や、
自分で作ったユーザー・スタイル (P.126) を選びます。
22.[ヘルプ]ボタン
画面で機能の説明を見ることができます (P.23)。
26. ディスプレイ
操作に応じていろいろな情報を表示します (P.16)。
27.[戻る]ボタン
一つ前の画面に戻ります。または、操作を終了します。
28. ワンタッチ・ボタン
[ワンタッチ・ピアノ]ボタン
鍵盤を弾いたときの音がピアノの音に変わり、ピアノ演奏に
最適な設定になります(P.24、P.42)。
[ワンタッチ・オルガン]ボタン
鍵盤を弾いたときの音がオルガンの音に変わり、オルガン演
奏に最適な設定になります(P.25、P.43)。
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタン
自動伴奏で演奏するために最適な設定になります(P.30、
P.63)。
29.[ドラム/効果音]ボタン
鍵盤を弾いたときの音が打楽器音や効果音に変わります
(P.44)。
23.[譜表]ボタン
再生する曲や、録音した曲の譜表を表示します (P.79)。
24.[メトロノーム]ボタン
内蔵のメトロノームを鳴らします(P.28、P.56)。
25. 拍ランプ
選ばれた曲や伴奏の拍に合わせて点灯します。
30.[メロディー・インテリジェンス]ボタン
鍵盤で弾いている音にハーモニーをつけます (P.73)。
31. 音色ボタン
鍵盤で鳴らす音の種類(音色グループ)を選びます(P.26、
P.46)。
19
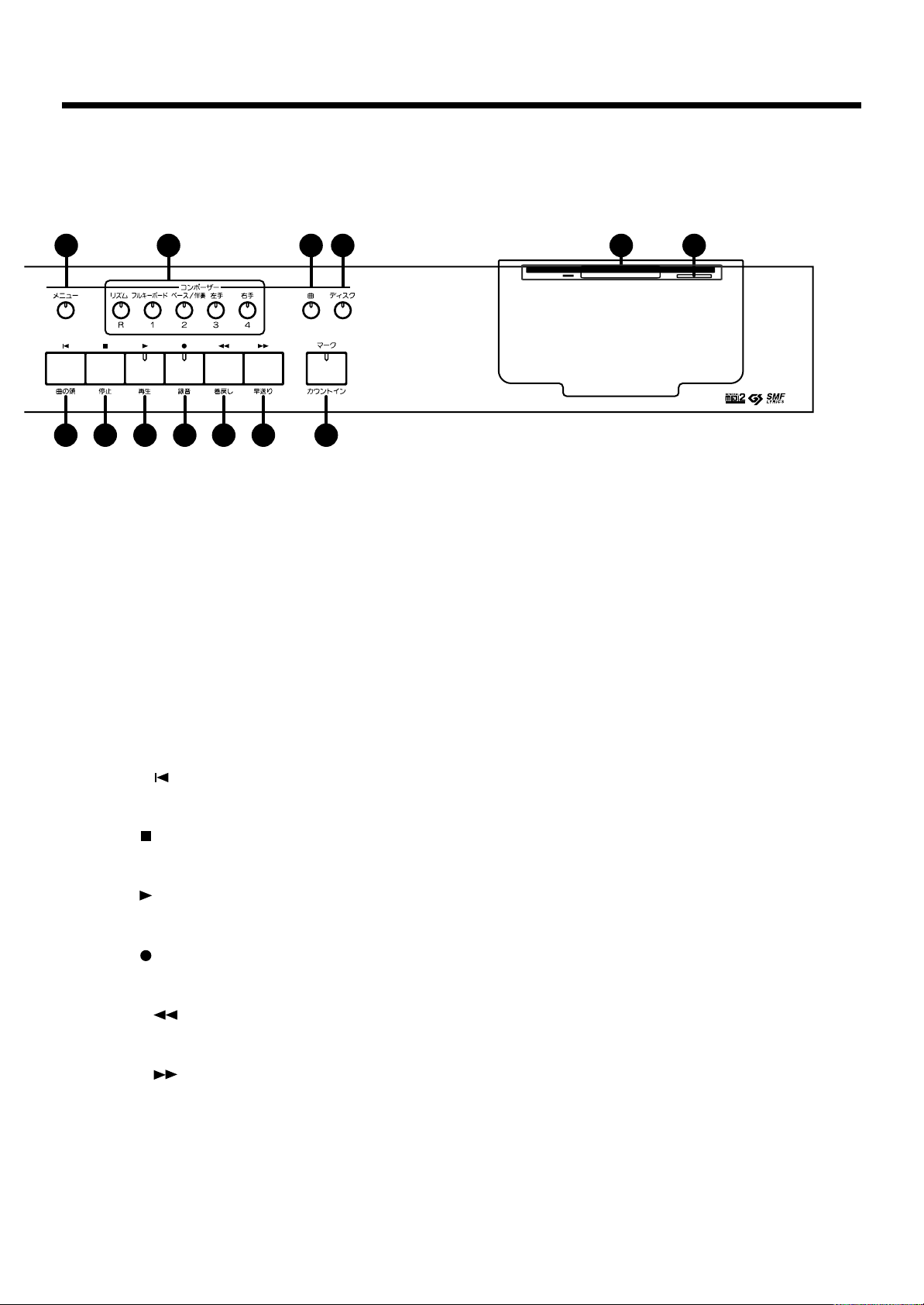
各部の名称と働き
36 37 38 39 40 41 42
444332 3533 34
32.[メニュー]ボタン
録音機能や編集機能を選ぶことができます。
33. トラック・ボタン
曲を演奏パートごとに再生したり、自分の演奏を録音したり
します(P.85、P.91)。
34.[曲]ボタン
曲を選びます (P.77)。
35.[ディスク]ボタン
録音した曲をフロッピー・ディスクに保存するなど、フロッ
ピー・ディスクに関する機能を選びます。
36. 曲の頭[ ]ボタン
曲の再生を始める位置を、曲の先頭に戻します。
37. 停止[ ]ボタン
曲の再生や録音を止めます。
38. 再生[ ]ボタン
曲の再生や録音を始めます。
43. ディスク・ドライブ
フロッピー・ディスクを挿入して、曲を再生したり保存した
りします(P.38、P.104)。
44. イジェクト・ボタン
ディスク・ドライブから、フロッピー・ディスクを取り出し
ます (P.38)。
39. 録音[ ]ボタン
録音待機状態にします。
40. 巻戻し[ ]ボタン
曲を巻戻します。
41. 早送り[ ]ボタン
曲を早送りします。
42.[マーク/カウントイン]ボタン
曲中にマークをつけて小節を移動したり (P.86)、演奏が始
まる前にカウント音を鳴らすことができます (P.84)。
20
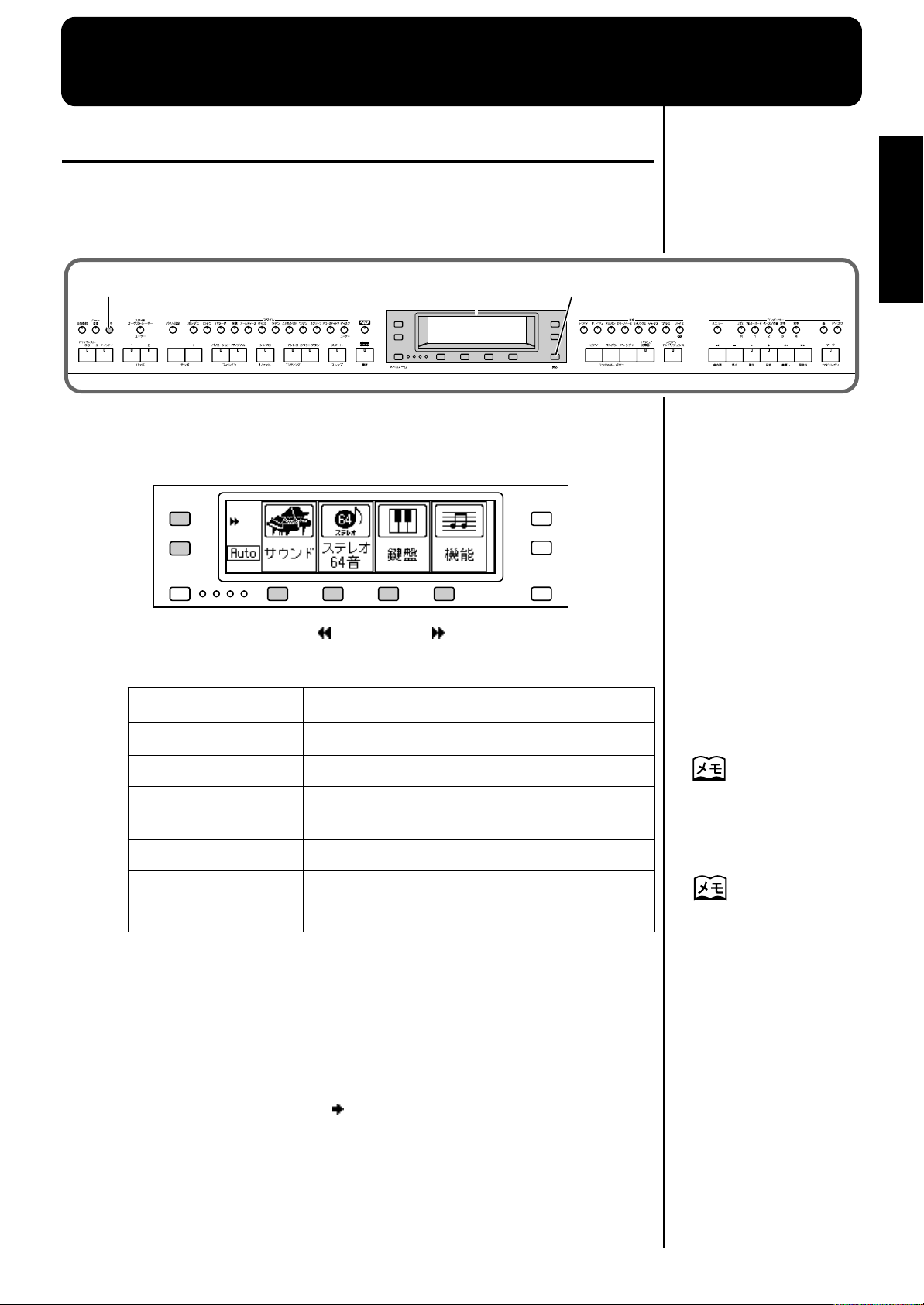
KR-377 に触れてみましょう
・
覧
KR-377の紹介デモを見る
KR-377 に内蔵されている楽器の音や、ミュージック・スタイル(さまざ
まな音楽ジャンルの伴奏スタイル)を使ったデモ曲を聴いたり、KR-377
の音や鍵盤の特徴などを画面で見ることができます。
fig.00-01z
1 2, 3, 4 5
1.
[デモ]ボタンを押します。
次のような「デモ画面」が表示されます。
fig.00-02.j
KR-377 に触れてみましょう
2.
3.
ディスプレイ左上の< >または< >を押して画面を切り
替え、デモの種類を選びます。
表示 解説
サウンド KR-377 のピアノ音色についての説明
ステレオ 64 音 同時発音数についての説明
鍵盤
機能 主な機能の紹介
音色紹介 内蔵音色の紹介演奏
スタイル紹介 内蔵ミュージック・スタイルの紹介演奏
KR-377 の鍵盤(プログレッシブ・ハンマー・
アクション)についての説明
見たいデモの下のボタンを押します。
デモが始まります。
ディスプレイ左の<Auto >を押すと、「サウンド」、「ステレオ 64 音」、
「鍵盤」、「機能」のデモを自動で繰り返し表示します。
音色については、「音色一
」(P.162)をご覧くだ
さい。
ミュージック・スタイルに
ついては、「ミュージック
スタイル一覧」(P.171)
をご覧ください。
4.
5.
画面に従って操作します。
ディスプレイ右のボタンで< >を選ぶと、次の画面へ進みます。
デモを終了するときは、[戻る]ボタンを押します。
[戻る]ボタンを数回押すと、元の画面に戻ります。
21
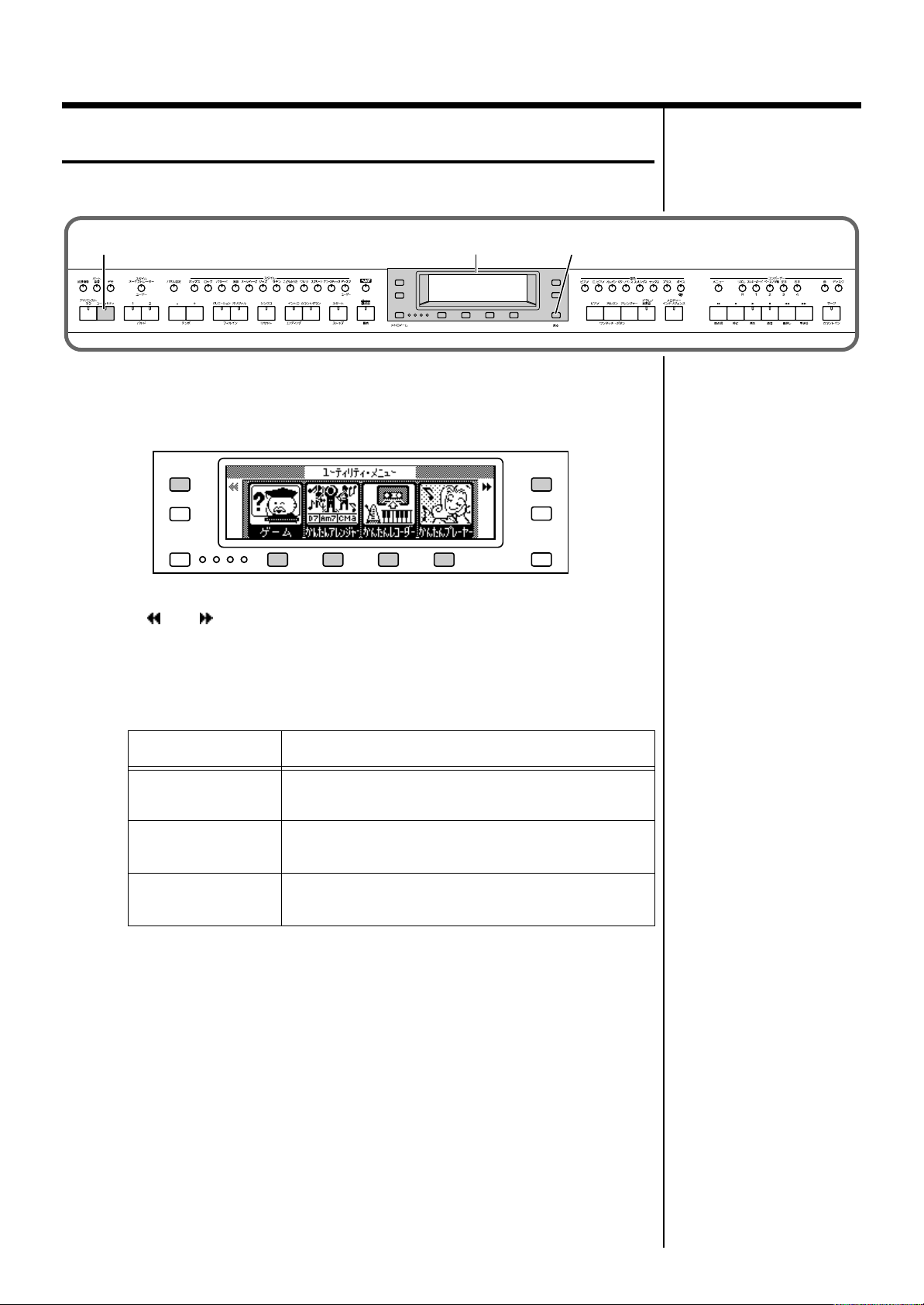
KR-377 に触れてみましょう
ゲームをする
KR-377 には、音やコード(和音)のゲームなどがあります。
fig.00-03
1 2, 3, 4 5
1.
2.
3.
[ユーティリティ]ボタンを押します。
「ユーティリティ画面」が表示されます。
fig.00-04.j
画面に<ゲーム>が表示されていないときは、ディスプレイ左上と右上の
< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ下の<ゲーム>を押します。
ゲームの種類を選び、ディスプレイ下のボタンを押します。
ゲームの種類 説明
音当て
コード当て
ピアノ音が一つ鳴ります。聞こえた音を鍵盤で弾
いてください。
コード音が鳴ります。聞こえたコードを鍵盤で弾
いてください。
4.
5.
22
コード練習
コード名が表示されます。表示されたコードを鍵
盤で弾いてください。
画面の説明に従って操作します。
ゲームが終わったら、[戻る]ボタンを押します。
[戻る]ボタンを数回押すと、元の画面に戻ります。

KR-377 に触れてみましょう
[ヘルプ]ボタンの使いかた
KR-377 にはヘルプ機能があります。KR-377 の機能の説明をディスプレ
イに表示させることができます。
操作がわからないときには、ヘルプ機能を使ってみましょう。
1.
[ヘルプ]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
次のような画面が表示されます。
fig.00-06.j
KR-377 に触れてみましょう
2, 3, 41, 5
2.
3.
4.
下線のついている単語や文について、より詳しい説明を見ることができま
す。
ディスプレイ下の<メニューへ>を押すと、説明内容の一覧
が表示されます。
fig.00-06.j
ディスプレイ下の選択< > < >で知りたい項目を選びま
す。
ディスプレイ右の< >を押すと説明が下方向に進み、< >を押すと
上方向に戻ります。
ディスプレイ下の<ジャンプ>を押します。
選んだ項目の説明が表示されます。
5.
ヘルプ機能を終了するときは、[ヘルプ]ボタンを押してラン
プを消灯させます。
[戻る]ボタンを数回押しても、ヘルプ機能を終了して元の画面に戻るこ
とができます。
23
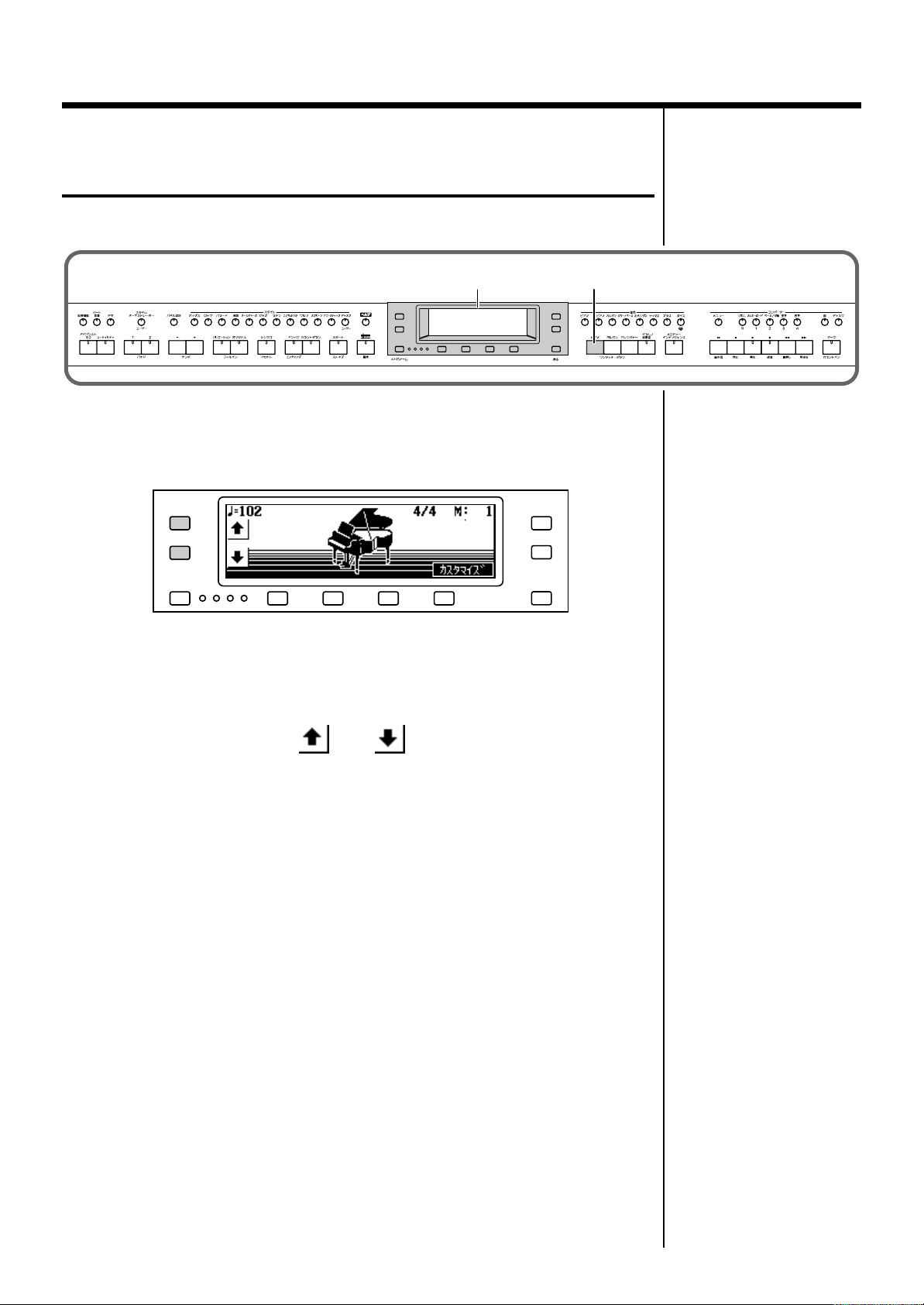
KR-377 に触れてみましょう
〜演奏してみましょう ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)
ボタン1 つで、ピアノ演奏に最適な設定にすることができます。
fig.00-07(ボタン)
1.
2.
3
[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押します。
次のような「ピアノ画面」が表示されます。
fig.00-08.j
鍵盤を弾くと、グランドピアノの音色が鳴ります。
このように、[ワンタッチ・ピアノ]ボタンで、いつでもピアノ演奏の設
定にすることができます。
1
3.
ディスプレイ左の< >< >を押します。
ピアノの大屋根の開き具合が変わり、音色も変わります。
グランド・ピアノの大屋根の開き具合による音のひびきを再現していま
す。
24
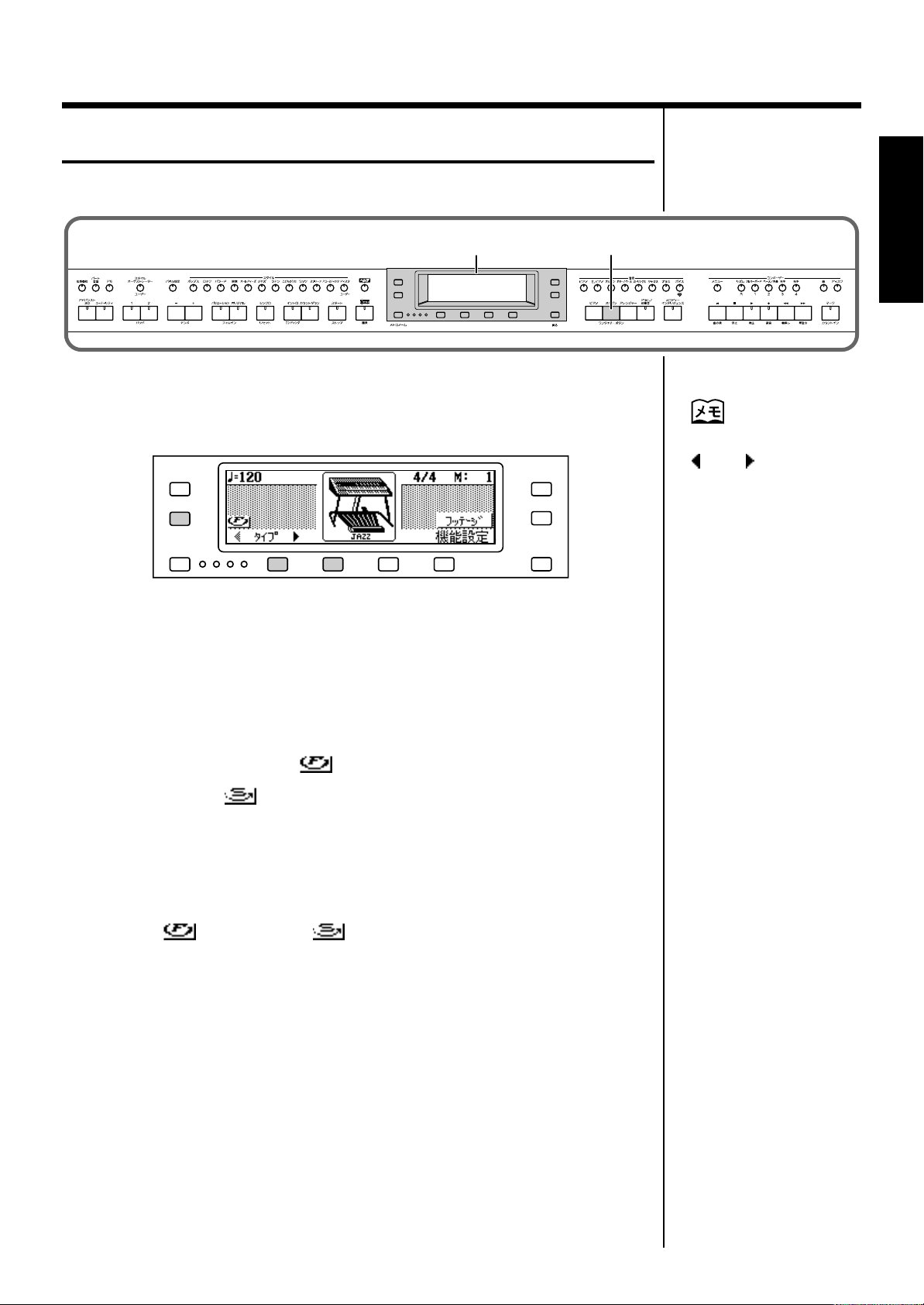
KR-377 に触れてみましょう
オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)
ボタン1 つで、オルガン演奏に最適な設定にすることができます。
fig.00-09(パネル図)
1
1.
3
[ワンタッチ・オルガン]ボタンを押します。
次のような「オルガン画面」が表示されます。
fig.00-10.j
KR-377 に触れてみましょう
ディスプレイ下のタイプ<
> < >を押すと、4
種類のオルガンから音色を
選ぶことができます。
詳しくは、「オルガン演奏
をする(ワンタッチ・オル
ガン)」(P.43)をご覧くだ
さい。
2.
3.
鍵盤を弾くと、ジャズ・オルガンの音色が鳴ります。
「ジャズ・オルガン」を選んでいるときは、鍵盤の右側と左側で別々の音
色を鳴らすことができます。
[ワンタッチ・オルガン]ボタンを押すと、いつでもオルガン演奏の設定
にすることができます。
ディスプレイ左の< >を押します。
画面の表示が に変わり、音のうねりが遅くなります。
「ジャズ・オルガン」の音には、ロータリー効果がかかっています。
ロータリー効果とは、オルガンの音に回転スピーカーを使ったときのよう
なうねりをつける効果です。
回転スピーカーの回転速度を変えるように、ボタンを押すたびに、速い回
転( )と遅い回転( )を切り替えることができます。
25
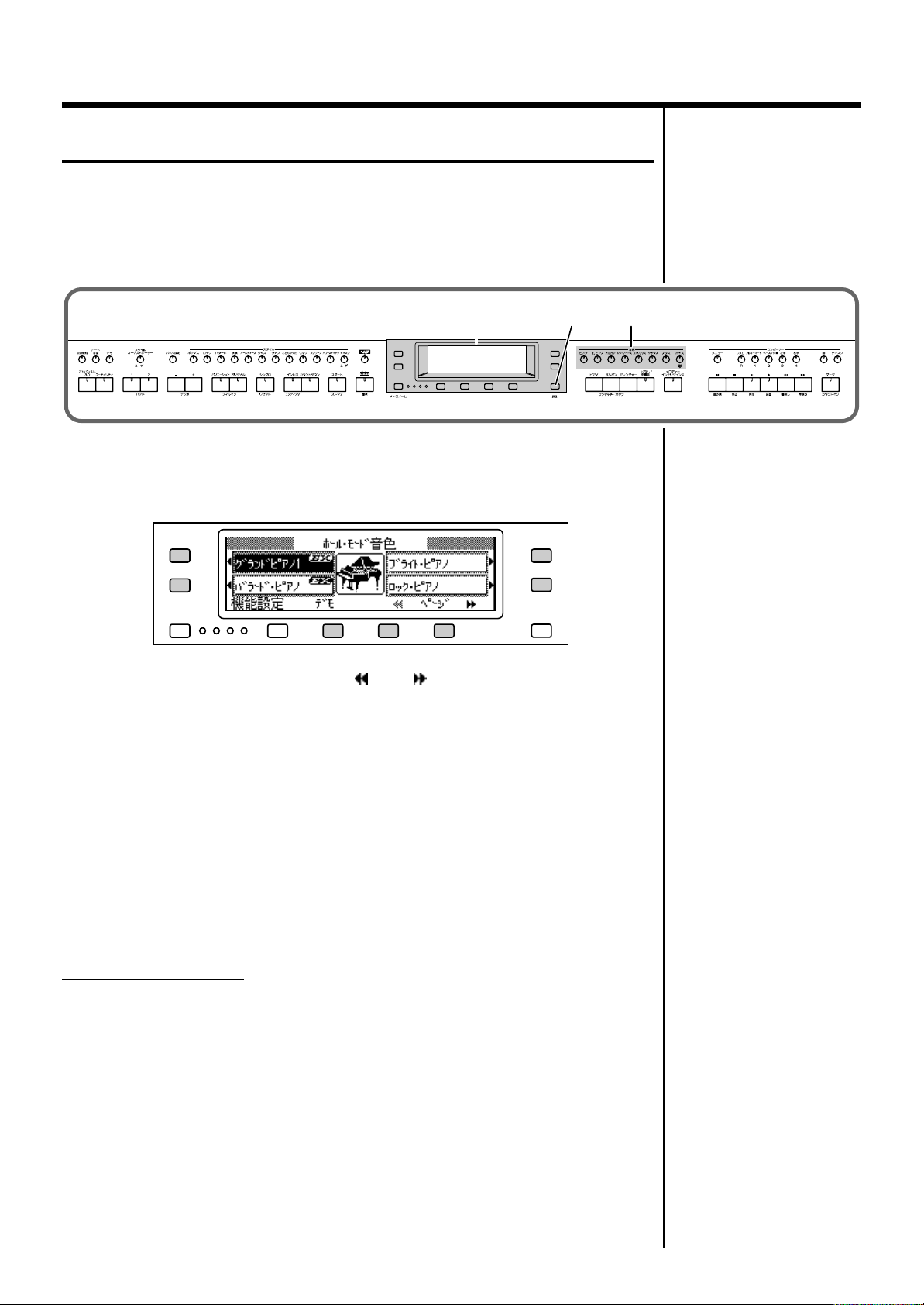
KR-377 に触れてみましょう
いろいろな楽器の音を鳴らす
KR-377 は多くの楽器の音や効果音を内蔵しています。さまざまな音楽
ジャンルの曲に合った音で演奏をお楽しみください。内蔵されているさま
ざまな種類の音を「音色」といいます。
音色は8 つのグループに分けられ、音色ボタンに割り当てられています。
fig.00-11
2, 3 14
1.
2.
3.
4.
いずれかの音色ボタンを押して、音色グループを選びます。
画面には、そのグループに含まれる音色のうち、4つが表示されます。
fig.00-12.j
ディスプレイ下のページ< >< >を押して、画面を切り
替えます。
選んだ音色グループの他の音色が表示されます。
演奏したい音色の横のボタンを押して、音色を選びます。
ディスプレイ下の<デモ>を押すと、その音色を代表するフレーズを聴く
ことができます。
鍵盤を弾くと、選んだ音色が鳴ります。
[戻る]ボタンを押すと、基本画面に戻ります。
いろいろな音色を選んで、演奏してみましょう。
<EX>音色について
ローランドが自信を持ってお勧めする、表現力に優れた音色です。
EX音色の中には、鍵盤を弾く強さ(ベロシティ)によって音色が変化す
るものもあります。
26
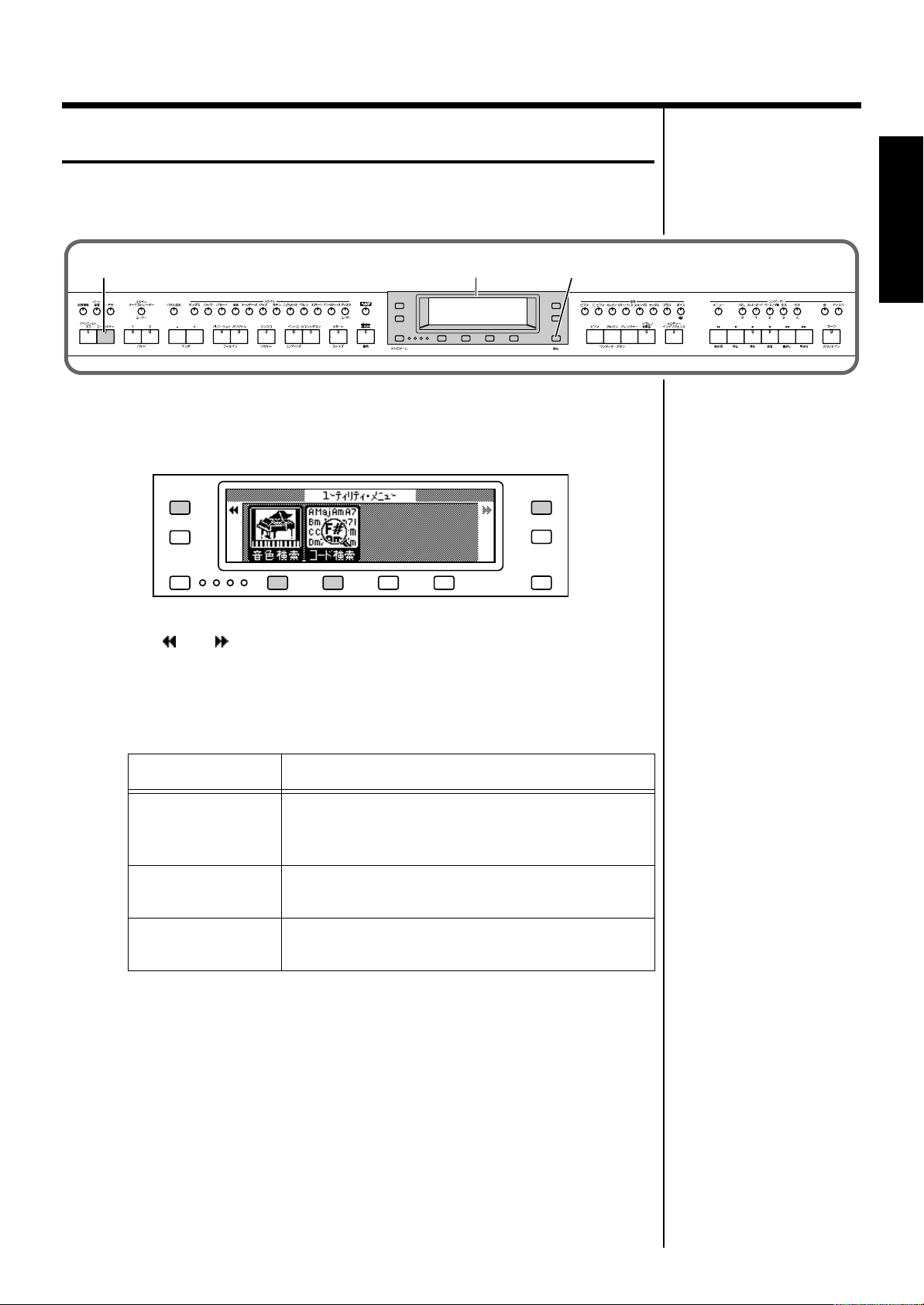
KR-377 に触れてみましょう
音色を選ぶ便利な機能(音色検索)
「音色検索」を使って、おすすめ音色や文字検索など、音色を選ぶときに
便利な機能を使うことができます。
fig.00-03
1 2, 3, 4 5
1.
[ユーティリティ]ボタンを押します。
「ユーティリティ画面」が表示されます。
fig.00-04.j
KR-377 に触れてみましょう
2.
3.
4.
画面に<音色検索>が表示されていないときは、ディスプレイ左上と右上
の< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ下の<音色検索>を押します。
機能を選び、ディスプレイ下のボタンを押します。
表示 説明
おすすめ音色を選ぶことができます。1 つの楽器だ
おすすめ音色
ジャンル検索
文字検索
けでなく、2 つの楽器を組み合わせた音色などを選
ぶことができます。
音色を楽器の種類や、音楽のジャンルから選ぶこ
とができます。
探したい音色名の1 文字から音色を探すことがで
きます。
画面の説明に従って操作します。
鍵盤を弾くと、選んだ音色で演奏することができます。
5.
検索が終わったら、[戻る]ボタンを押します。
[戻る]ボタンを数回押すと、元の画面に戻ります。
27
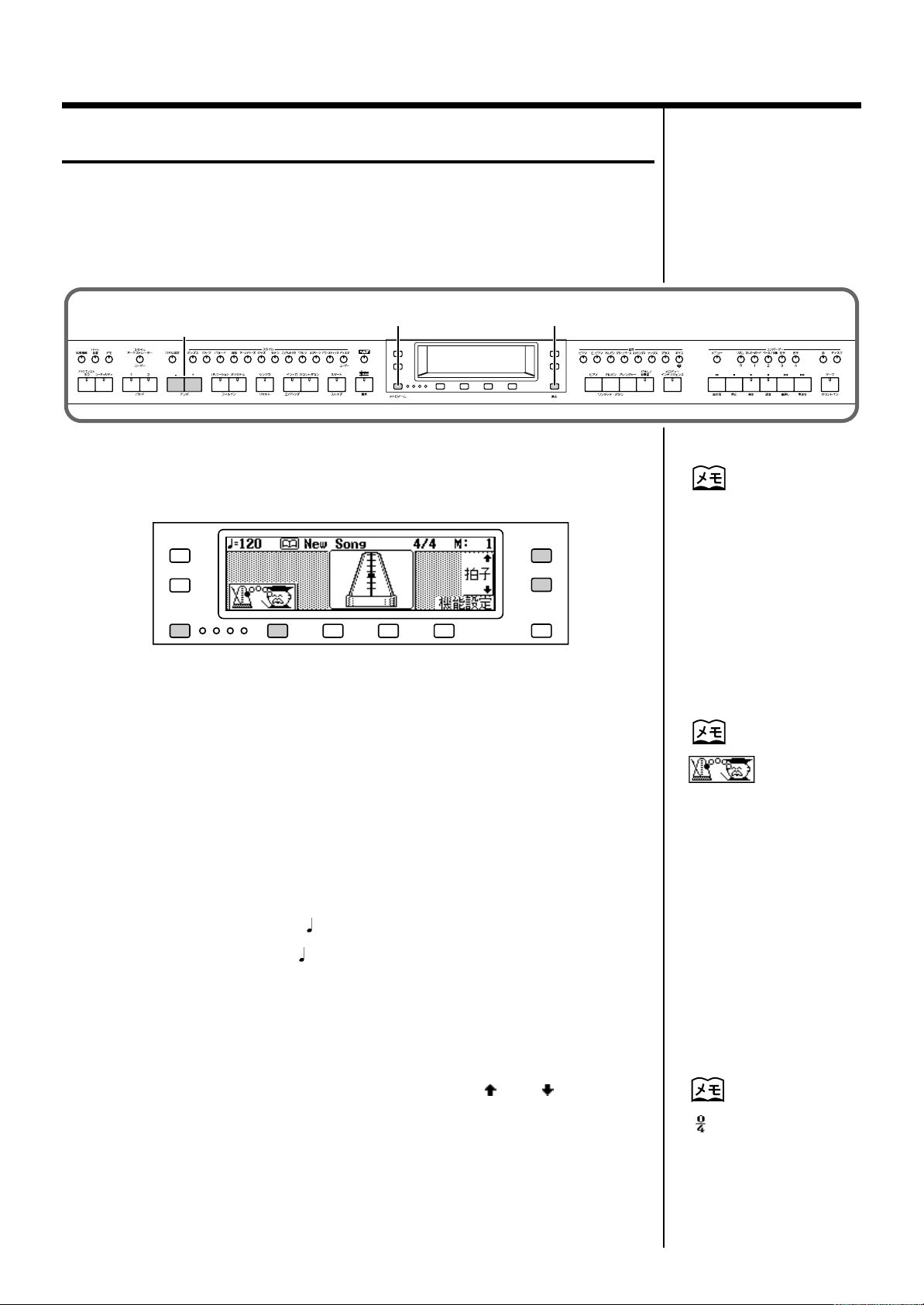
KR-377 に触れてみましょう
押
電
メトロノームを鳴らす
KR-377 はメトロノーム機能を内蔵しています。メトロノームはボタン 1
つで鳴らしたり、止めたりすることができます。
メトロノームは、曲の再生中や自動伴奏の演奏中には、曲のテンポや拍子
で鳴ります。
fig.00-13
テンポの調節
1.
2.
3.
[メトロノーム]ボタンを押すと、メトロノームが鳴ります。
メトロノーム画面が表示されます。
fig.00-14.j
もう一度[メトロノーム]ボタンを押すと、メトロノームが
止まります。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
■ テンポを調節する
メトロノームの速さを変えることができます。また、メトロノームのテン
ポは自動伴奏を使ったり、曲を再生したりすると、自動的に変わります。
1.
テンポ[−][+]ボタンで、テンポを変えます。
1, 2 3
メトロノーム画面が表示さ
れているときに、メトロ
ノームの音量や拍子などを
変えることができます。詳
しくは「メトロノームを鳴
らす」(P.56)をご覧くだ
さい。
の下のボタンを
して、画面中央の表示を
かえることができます。
源投入時は、「メトロ
ノーム」が選ばれていま
す。
メトロノームのテンポは =20 〜 250 の範囲で調節することができます。
電源を入れたときは、「 =120」に設定されます。
[−][+]ボタンを同時に押すと、スタイルや曲の基本テンポに戻すこと
ができます。
■ 拍子を変える
1.
28
メトロノーム画面で、ディスプレイ右の< >< >を押し
て拍子を設定します。
画面上段に表示されている拍子が変わります。
選べる拍子:
2/2、0/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、9/8、12/8
を選んでいるときは、
弱拍の音だけがなります。
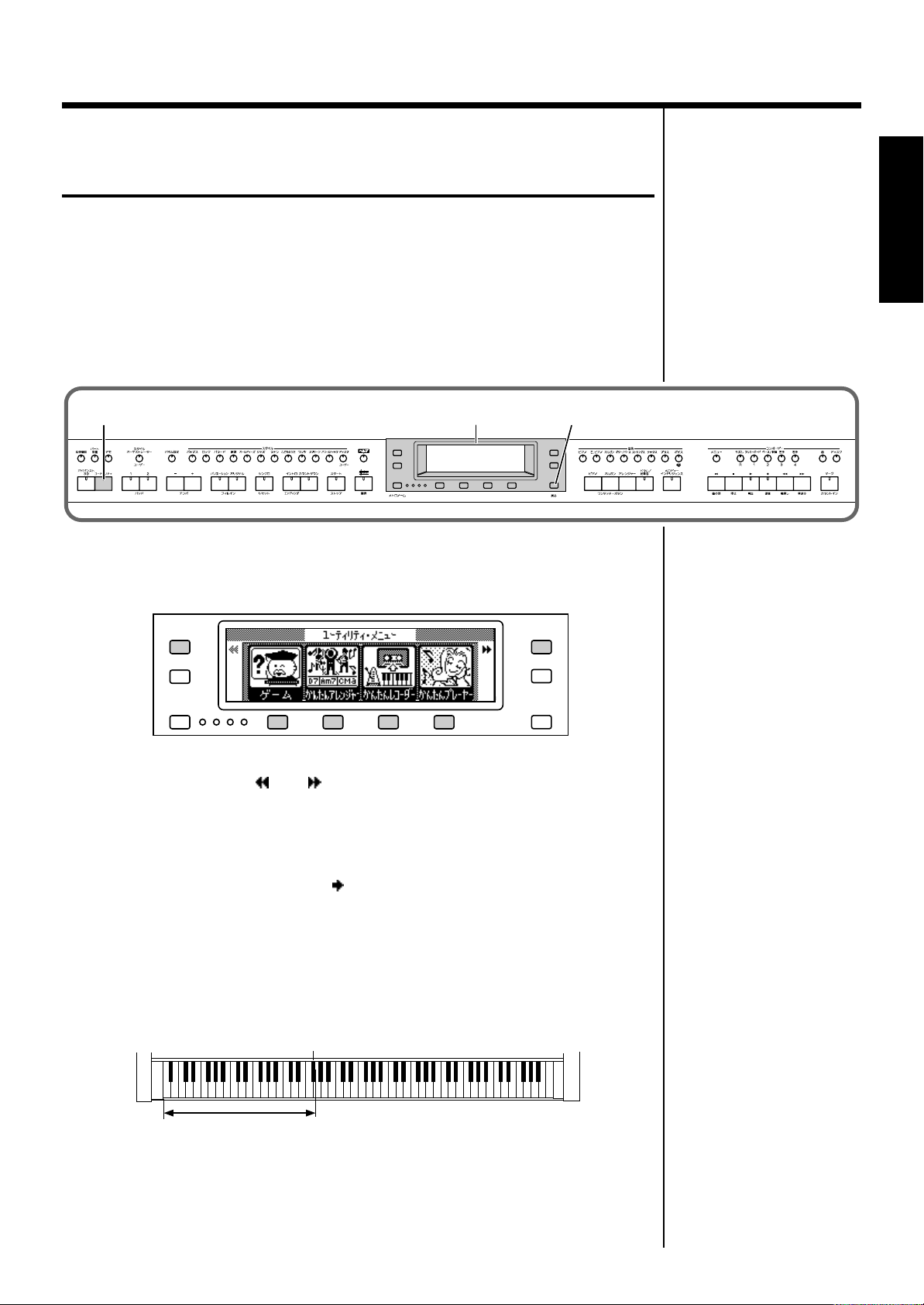
KR-377 に触れてみましょう
〜自動伴奏を使って演奏しましょう
簡単に自動伴奏を楽しむ(かんたんアレンジャー)
自動伴奏を使って演奏してみましょう。
自動伴奏を左手でコードを指定すると、それに合わせて伴奏がつくので、
演奏がぐっと豪華に、楽しくなる機能です。
自動伴奏を使うためには、いくつかのボタンを押して自動伴奏の設定をし
ますが、「かんたんアレンジャー」を使うと、画面の質問に答えるだけで、
自動伴奏を使うことができます。また、コードを自動的に演奏することも
できます。
fig.00-20-2
1 2, 3 4
1.
[ユーティリティ]ボタンを押します。
ユーティリティ画面が表示されます。
fig.00-04.j
KR-377 に触れてみましょう
2.
3.
4.
画面に<かんたんアレンジャー>が表示されていないときは、ディスプレ
イ左上と右上の< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ下の<かんたんアレンジャー>を押します。
画面の指示に従って、質問に答えてください。
ディスプレイ右のボタンで< >を選ぶと、次の画面へ進みます。
すべての質問に答えると、すぐに自動伴奏で演奏できる状態になります。
鍵盤で、いろいろな演奏をしてみましょう。
コードを自動で指定して演奏することもできます。
自分でコードを指定して演奏するときは、下図の鍵盤左側でコードを指定
してください。
fig.00-20.j
F3
自動伴奏のコードを指定する鍵域
かんたんアレンジャーを終了するときは、[戻る]ボタンを押
します。
ユーティリティ画面に戻ります。
29
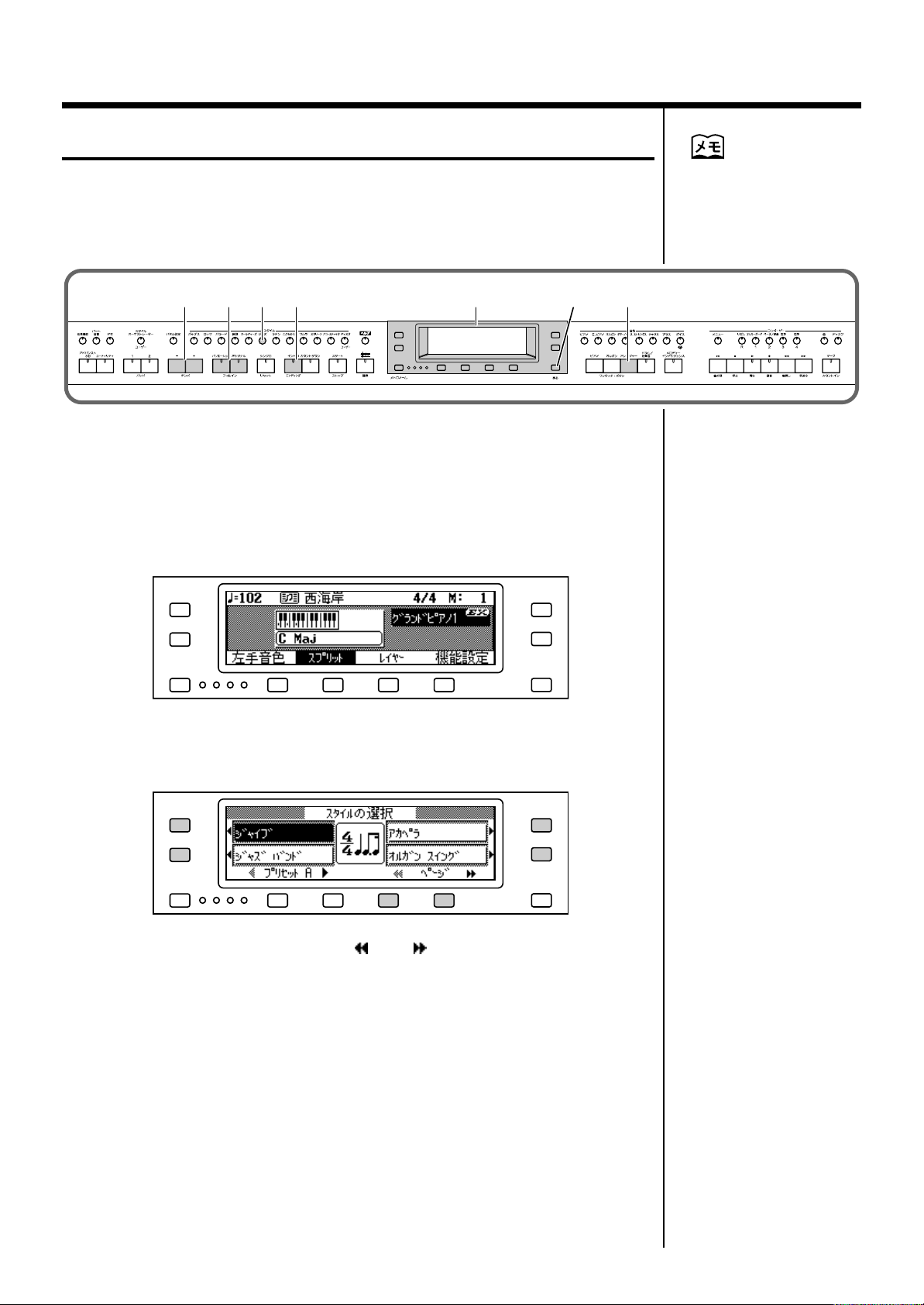
KR-377 に触れてみましょう
自動伴奏で演奏する(ワンタッチ・アレンジャー)
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタン1 つで自動伴奏を使って演奏するた
めに最適な設定にすることができます。「ミュージック・スタイル」を変
えれば、全く違った雰囲気の演奏を楽しむことができます。
fig.00-15
25 7 8 13
■「茶色のこびん」を弾く
自動伴奏を使って、32 ページの「茶色のこびん」を弾いてみましょう。
ここでは、「スインギン」のミュージック・スタイルで演奏します。
1.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
fig.00-16.j
自動伴奏の詳しい使い方
は、「第 2 章 自動伴奏」
(P.60)をご覧ください。
4
2.
3.
4.
5.
スタイル・ボタンの[ジャズ]ボタンを押します。
次の画面が表示されます。
fig.00-17.j
ディスプレイ下のページ< >< >を押してページを切り
替えて、<スインギン>の横のボタンを押します。
[戻る]ボタンを押します。
元の画面に戻ります。
テンポ[−][+]ボタンで、伴奏のテンポを調節します。
[−]ボタンと[+]ボタンを同時に押すと、選んでいるスタイルの基本
テンポに戻ります。
30

KR-377 に触れてみましょう
6.
7.
次の図の「C」の鍵盤を弾いて演奏を始めます。
鍵盤を弾くと、はじめに8 小節のイントロが演奏されます。
譜面の「右手」「左手」の通り、鍵盤を弾いてみましょう。
左手は、鍵を押さえ続ける必要はありませんので、次に押さえる鍵の準備
をしておきましょう。
fig.00-18
CF
G
左手
F 3
右手
譜面のタイミングで、フィルイン[バリエーション]ボタン
を押します。
伴奏パターンが変わります。
[オリジナル]ボタンを押すと、元の伴奏パターンに戻ります。
演奏に慣れてきたら、好きなタイミングで伴奏パターンを変えてみましょう。
KR-377 に触れてみましょう
8.
譜面のタイミングで、[イントロ/エンディング]ボタンを押
します。
エンディングが演奏されてから、伴奏が止まります。
31
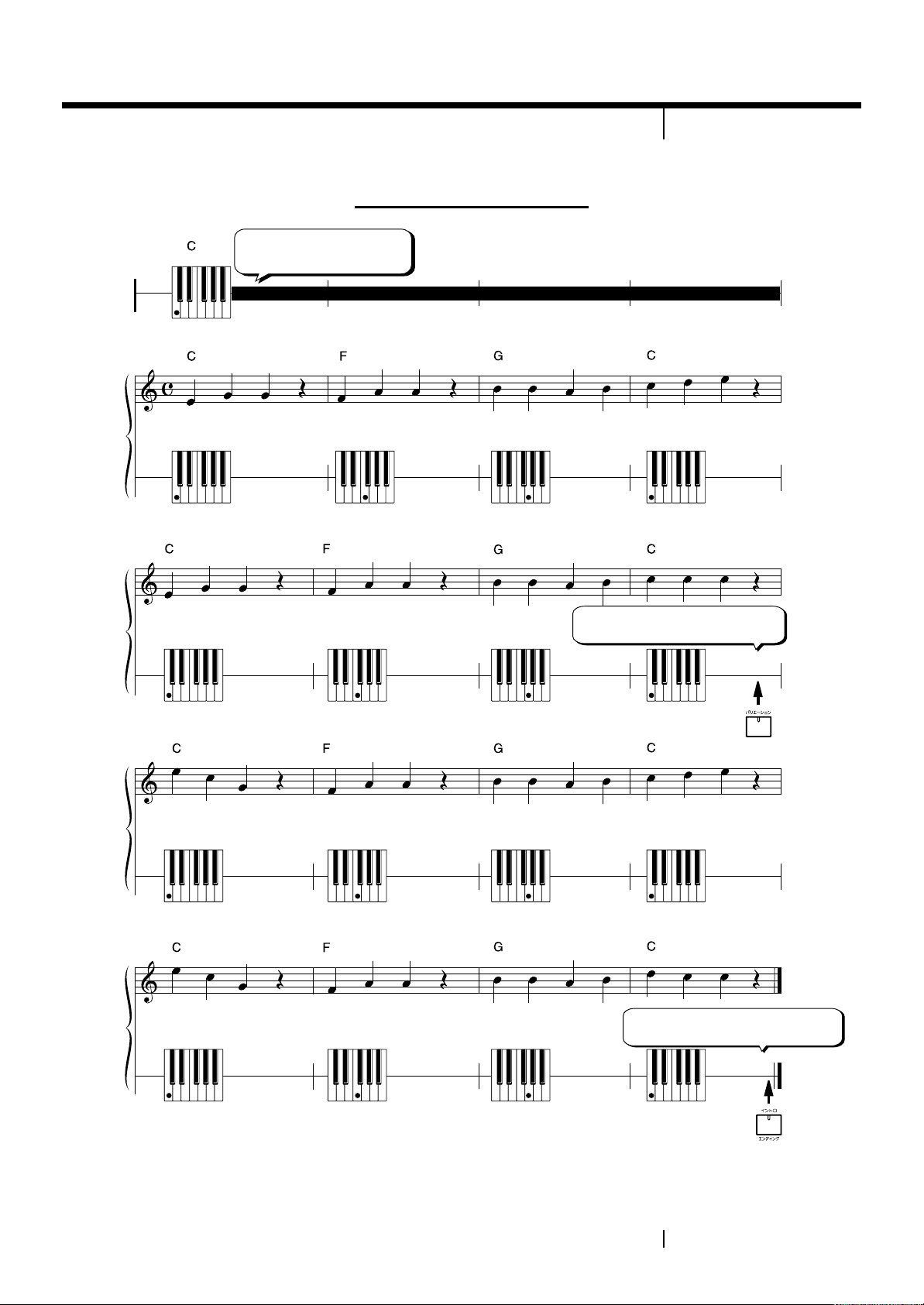
KR-377 に触れてみましょう
fig.00-19.j
左手
右手
左手
鍵盤を押して、イントロ
を始めます。
イントロが8小節演奏されます
茶色のこびん
フィルイン[バリエーション]を
押して、フィルインを入れます。
32
[イントロ/エンディング]を
押して、エンディングを入れます。

KR-377 に触れてみましょう
伴奏の音に立体的な広がりをつける
(アドバンスト 3D)
自動伴奏や内蔵曲に合わせて演奏しているとき、伴奏の音に立体的な広が
りをつけることができます。
伴奏の音につつみ込まれるような心地よさを得ることができます。
fig.00-21
2, 5 3 1
1.
2.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
[アドバンスト 3D]ボタンを押します。
「アドバンスト3D 画面」が表示されます。
鍵盤左側を弾くと、自動伴奏が始まります。
fig.00-22.j
オン
4
KR-377 に触れてみましょう
3.
4.
5.
アイコンの下のボタンを押すと、それぞれオン/オフが切り
替わります。
fig.00-23.j
オフ
オンにしているパートの音に立体的な広がりがつきます。
[戻る]ボタンを押すと、効果はかかったままで、元の画面に
戻ります。
もう一度[アドバンスト 3D]ボタンを押してランプを消灯さ
せると、効果が解除されます。
すべてのパートにアドバンスト3D 効果がかからなくなります。
33
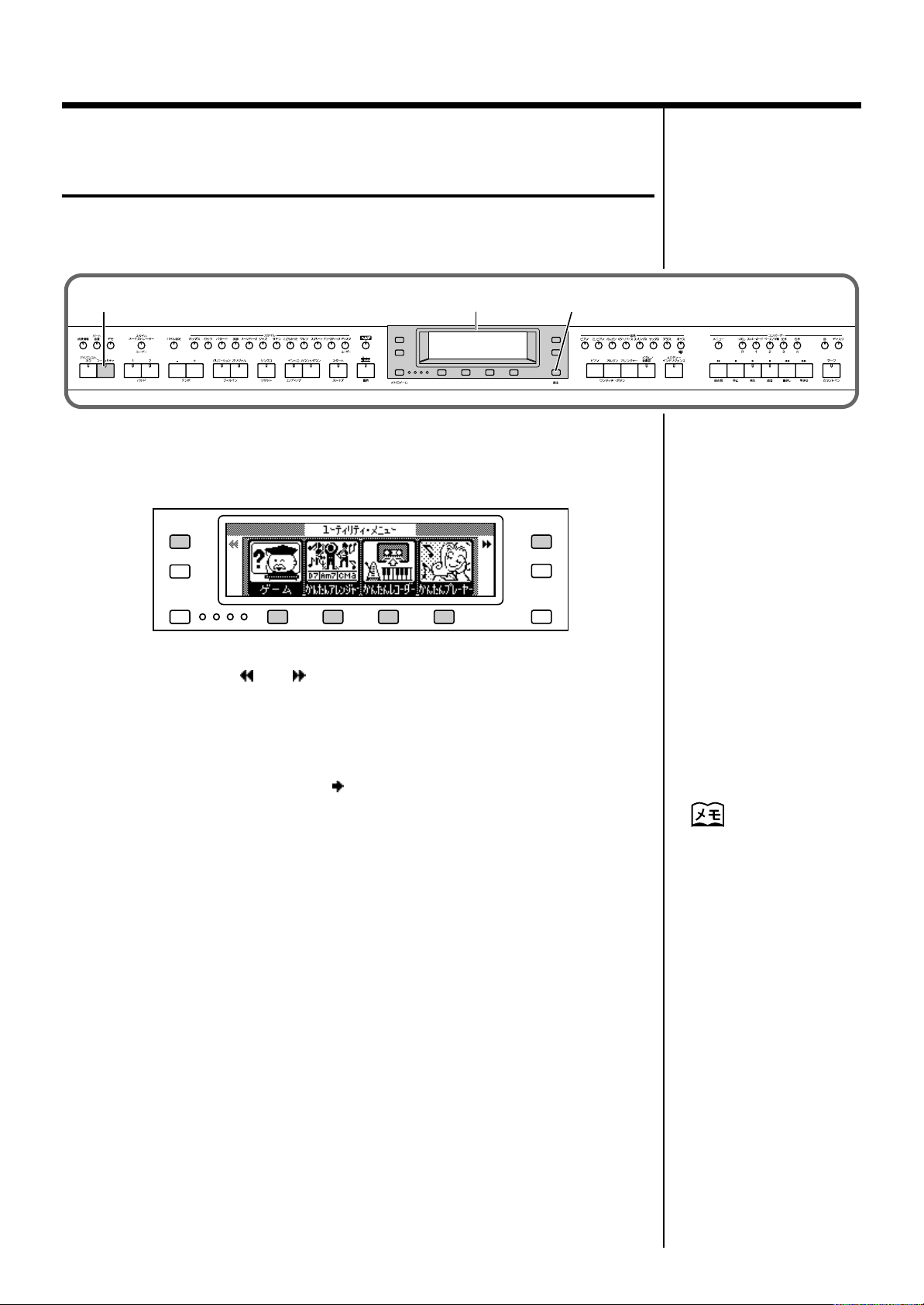
KR-377 に触れてみましょう
〜演奏を録音してみましょう 簡単に演奏を録音する(かんたんレコーダー)
KR-377 には、画面の指示に従うだけで簡単に録音することができる「か
んたんレコーダー」機能があります。
fig.00-03
1 2, 3, 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
[ユーティリティ]ボタンを押します。
ユーティリティ画面が表示されます。
fig.00-04.j
画面に<かんたんレコーダー>が表示されていないときは、ディスプレイ
左上と右上の< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ下の<かんたんレコーダー>を押します。
画面の説明に従って、音色、拍子、テンポを設定します。
ディスプレイ右のボタンで< >を選ぶと、次の画面へ進みます。
画面に従って、演奏を録音します。
かんたんレコーダーが終わったら、[戻る]ボタンを押します。
録音した演奏をフロッ
ピー・ディスクに保存する
ことができます。
フォーマット済みのフロッ
ピー・ディスクを用意して
ください。
フォーマットについて詳し
くは、「フロッピー・ディ
スクの初期化(フォーマッ
ト)」(P.104)をご覧くだ
さい。
34
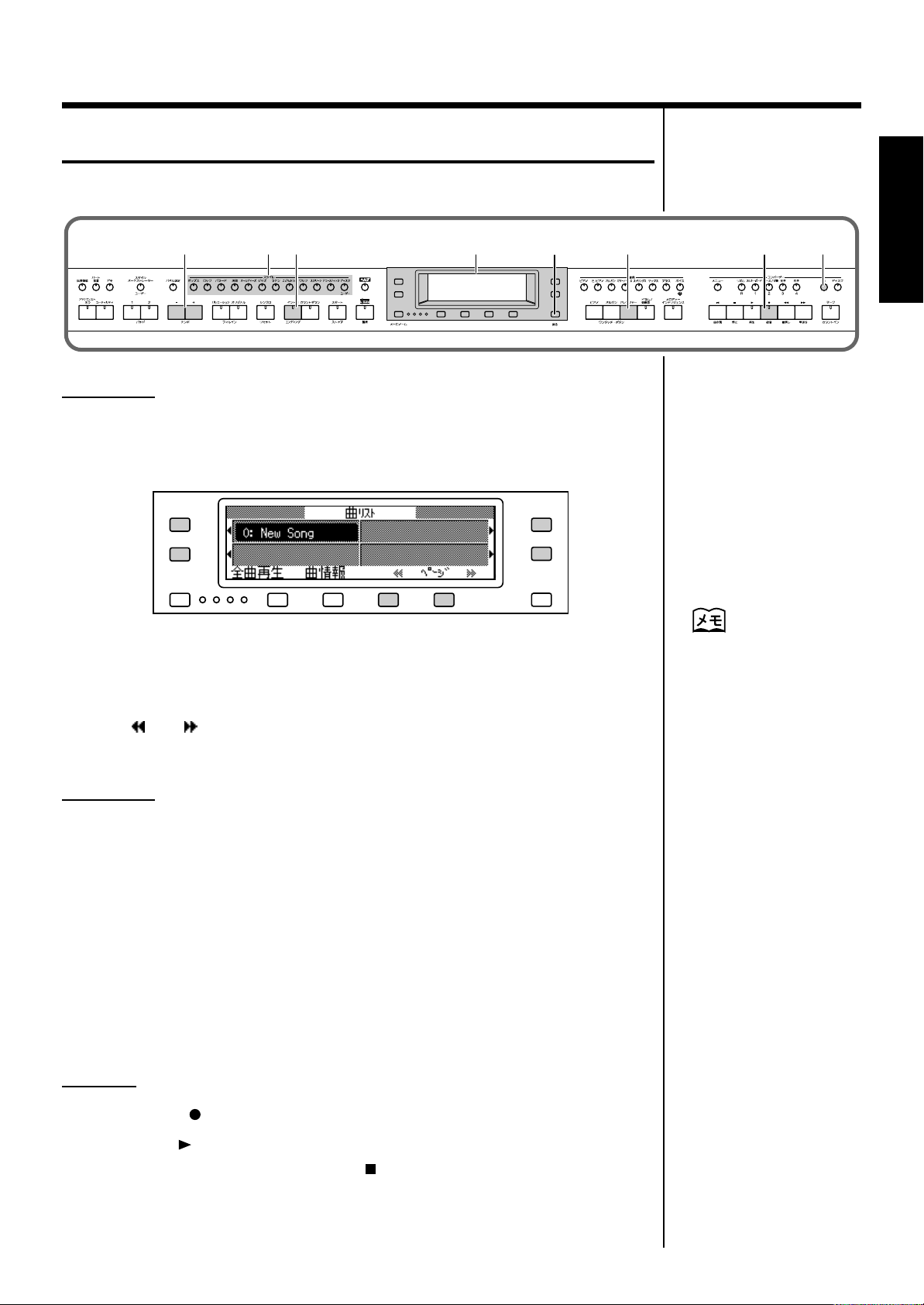
KR-377 に触れてみましょう
演奏を録音する
ここでは、32 ページの「茶色のこびん」の演奏を録音してみましょう。
fig.00-24
録音の準備
1.
[曲]ボタンを押します。
次のような「曲リスト画面」が表示されます。
fig.00-25.j(画面)
46 59 32
KR-377 に触れてみましょう
17
2.
演奏の準備
3.
4.
5.
6.
録音する
ディスプレイ左の<0:>を押して<0:New Song>を表示させ
ます。
画面に<0: >が表示されていないときは、ディスプレイ下のページ<
>< >を押して画面を切り替えます。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
スタイル・ボタンとディスプレイ横のボタンで演奏する
ミュージック・スタイルを選びます。
32 ページの「茶色のこびん」を演奏するときは、[ジャズ]ボタンを押し
て、<スインギン>を選んでください。
[戻る]ボタンを押して、元の画面に戻ります。
テンポ[−][+]ボタンで、伴奏のテンポを調節します。
内部メモリーに曲が記憶さ
れているときに他の曲を選
ぼうとすると、メッセージ
が表示されます。
「●次の画面が表示された
ら」(P.36)をご覧くださ
い。
7.
録音[ ]ボタンを押します。
再生[ ]ボタンのランプが点滅し、録音待機状態になります。
録音を中止したいときは、停止[ ]ボタンを押します。
35

KR-377 に触れてみましょう
8.
鍵盤左側の鍵を押さえます。
自動伴奏のイントロがスタートして、同時に録音も始まります。
曲を演奏してください。
fig.00-26
録音を止める
9.
[イントロ/エンディング]ボタンを押します。
エンディングが演奏されてから自動伴奏がストップし、同時に録音も止ま
ります。
●次の画面が表示されたら
内部メモリーに曲が記憶されているときに他の曲を選ぼうとすると、次の
画面が表示されます。
fig.00-27.j(メッセージ画面)
曲を消したくない場合
ディスプレイ下の<いいえ>を押します。
曲をフロッピー・ディスクに保存してください。
保存の方法については、「曲をフロッピー・ディスクに保存する」
(P.104)をご覧ください。
曲を消す場合
ディスプレイ下の<はい>を押します。
録音した演奏や設定を変更した曲が消えます。
36

KR-377 に触れてみましょう
録音した演奏を聴く
それでは、録音した演奏を、再生して聴いてみましょう。
fig.00-28(パネル)
1.
2.
3.
曲の頭[ ]ボタンを押します。
曲の先頭から再生するようになります。
再生[ ]ボタンを押します。
先程録音した演奏が再生されます。
停止[ ]ボタンを押します。
演奏の再生が止まります。
KR-377 に触れてみましょう
1, 2, 3
電源を切ると、録音した演
奏は消えてしまいます。録
音した演奏を消したくない
ときは、フロッピー・ディ
スクに保存してください。
保存の方法については、
「曲をフロッピー・ディス
クに保存する」(P.104)
をご覧ください。
録音した演奏が KR-377 の
内部メモリーに残っている
と、他の曲を再生すること
はできません。「録音した
曲を消す」(P.97)をご覧
ください。
37

KR-377 に触れてみましょう
〜ミュージックデータを使ってみましょう ディスク・ドライブを使う
ディスク・ドライブを使用して、市販のミュージックデータの曲を聴いて
みましょう。
また、KR-377 の演奏データを保存したフロッピー・ディスクも同じよう
に聴くことができます。
■ フロッピー・ディスクの入れかた/取り出しかた
fig.00-28(パネル)
ディスク・ドライブを初め
てお使いになる前には、5
ページの注意事項を必ずお
読みください。
ディスク・ドライブ
1.
フロッピー・ディスクの表面を上側にして、ディスク・ドラ
イブの挿入口にカチッというまで差し込みます。
ディスク・ドライブは本体の鍵盤上部の右端にあります。
fig.00-29.j(ディスク・ドライブ)
2.
ディスクを取り出すときは、イジェクト・ボタンを押します。
フロッピー・ディスクの端が挿入口から出てきます。フロッピー・ディス
クの端を指でつまんで、静かに引き出してください。
ランプ
挿入口
イジェクト・ボタン
フロッピー・ディスク
読み込み/書き込み中は、
ディスクを取り出さないで
ください。ディスクの磁性
面に傷がつき、使用できな
くなります。(データの読
み込み/書き込み時は、
ディスク・ドライブのラン
プが明るく点灯します。通
常はやや暗く点灯、または
消灯しています。)
38
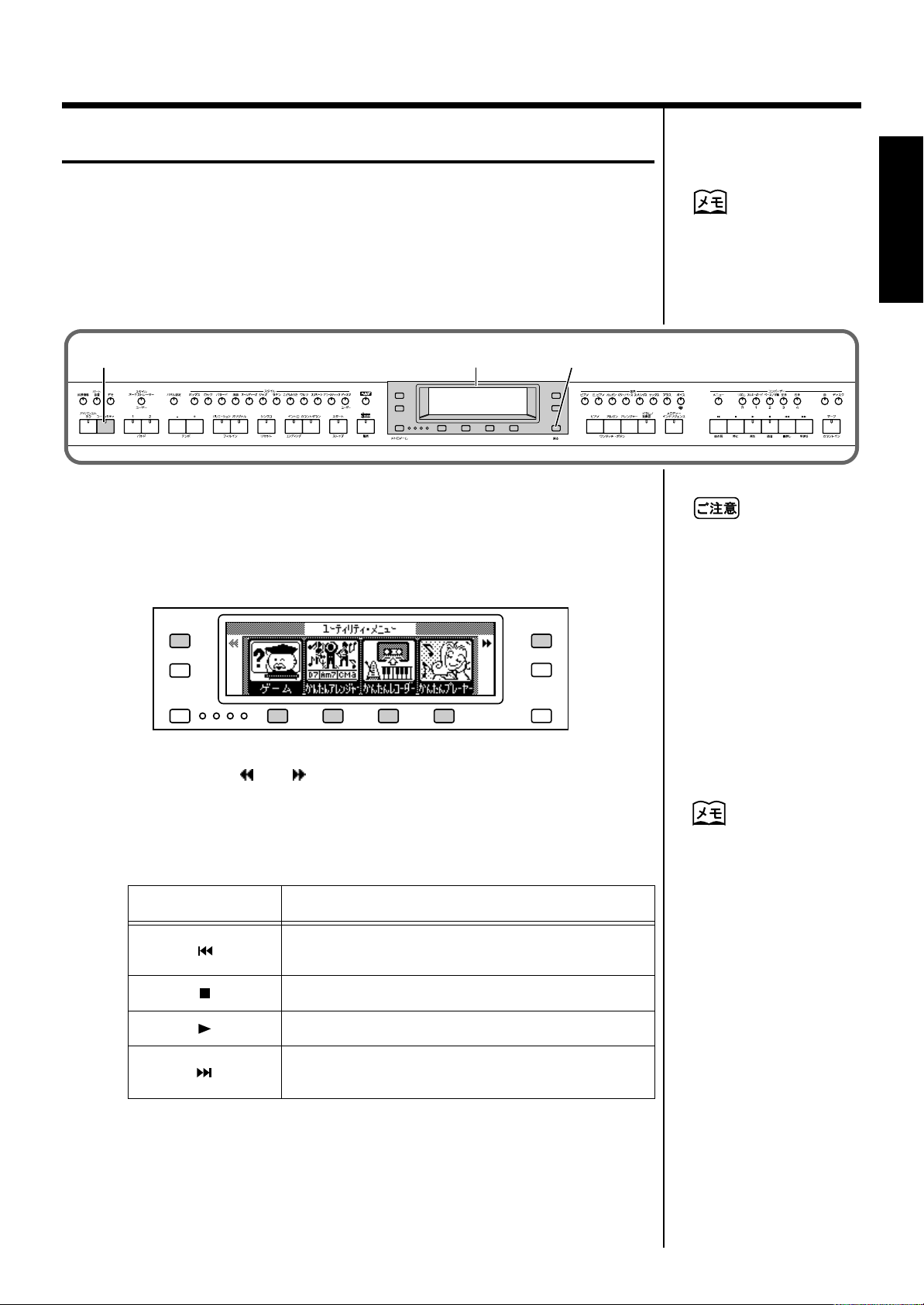
KR-377 に触れてみましょう
読
ミュージックデータを聴く
ディスク・ドライブを使用して、市販のミュージックデータの曲を聴いて
みましょう。
■ 簡単に曲を再生する(かんたんプレイヤー)
「かんたんプレーヤー」を使えば、CD プレーヤーを操作するような感覚
でミュージックデータなどの曲データを再生できます。
fig.00-03
2 3, 4 5
1.
2.
フロッピー・ディスクをディスク・ドライブに入れます。
[ユーティリティ]ボタンを押します。
ユーティリティ画面が表示されます。
fig.00-04.j
KR-377 に触れてみましょう
ミュージックデータについ
ては、「KR-377 で使用で
きるミュージックデータ」
(P.178)をご覧ください。
ディスク・ドライブを初め
てお使いになる前には、5
ページの注意事項を必ずお
みください。
3.
4.
5.
画面に<かんたんプレーヤー>が表示されていないときは、ディスプレイ
左上と右上の< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ下の<かんたんプレーヤ−>を押します。
画面下のボタンを押して、曲を聴きます。
ボタン 説明
前の曲を選択します。曲の再生中にこのボタンを
押すと、前の曲を再生します。
曲が止まります。
曲を再生します。
次の曲を選択します。曲の再生中にこのボタンを
押すと、次の曲を再生します。
かんたんプレーヤーを終わるときは、[戻る]ボタンを押しま
す。
[戻る]ボタンを押すと、ユーティリティ画面に戻ります。
内部メモリーに曲が記憶さ
れているときに他の曲を選
ぼうとすると、メッセージ
が表示されます。
「●次の画面が表示された
ら」(P.40)をご覧くださ
い。
39
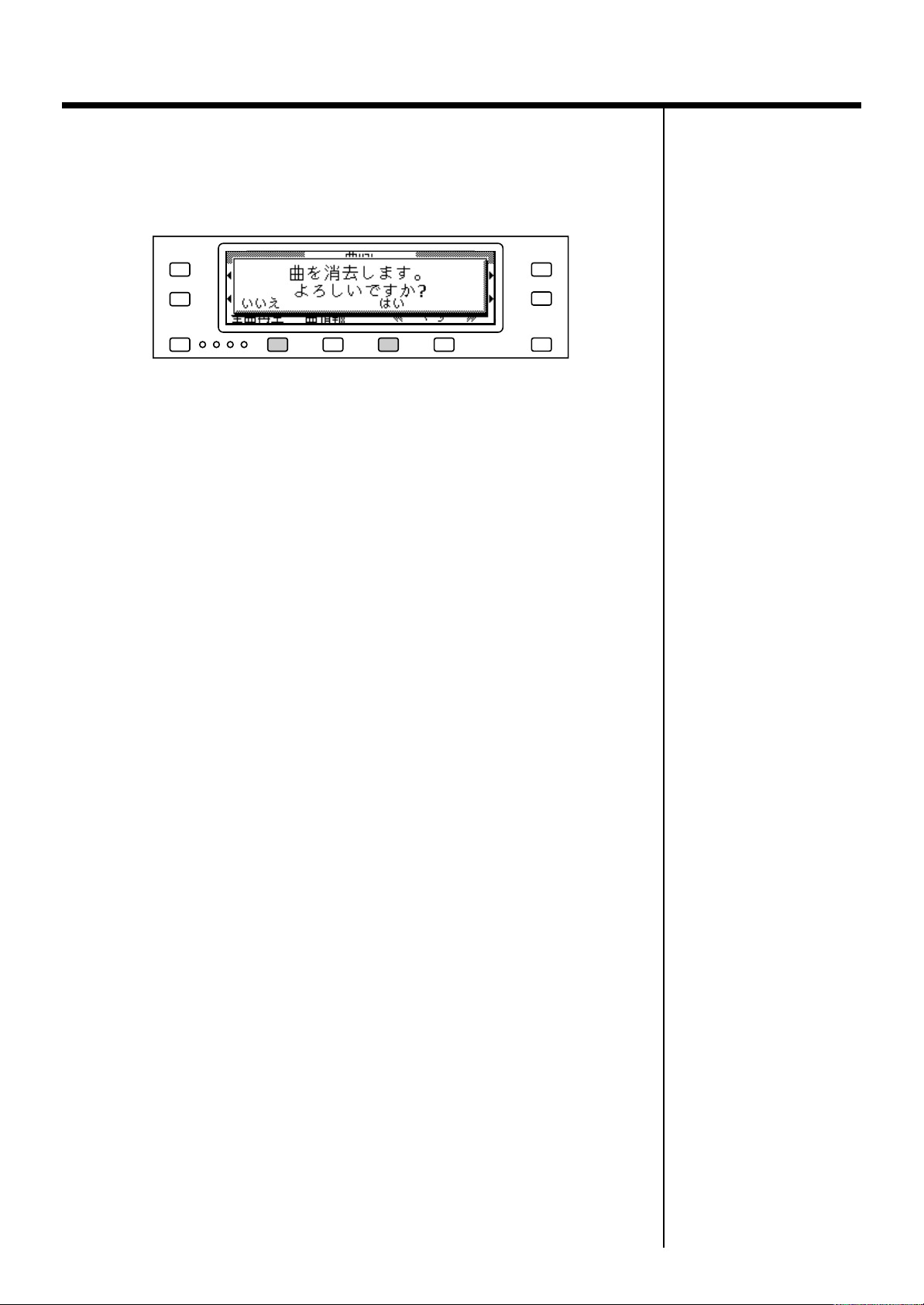
KR-377 に触れてみましょう
●次の画面が表示されたら
内部メモリーに曲が記憶されているときに他の曲を選ぼうとすると、次の
画面が表示されます。
fig.00-27.j(メッセージ画面)
曲を消したくない場合
ディスプレイ下の<いいえ>を押します。
曲をフロッピー・ディスクに保存してください。
保存の方法については、「曲をフロッピー・ディスクに保存する」
(P.104)をご覧ください。
曲を消す場合
ディスプレイ下の<はい>を押します。
録音した演奏や設定を変更した曲が消えます。
40
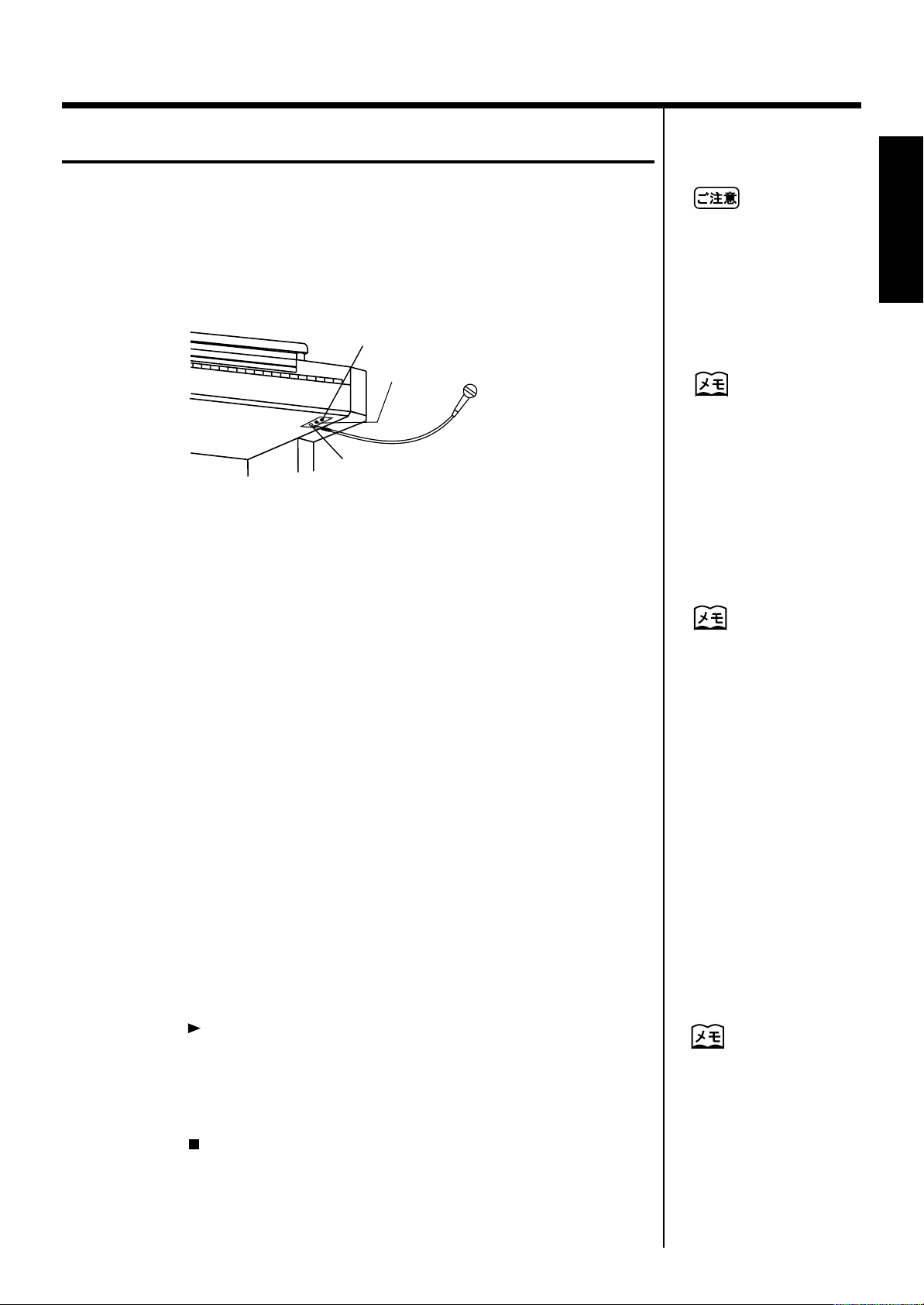
KR-377 に触れてみましょう
機
カラオケや弾き語りをする
マイク端子にマイクを接続して、カラオケや弾き語りをしてみましょう。
■ マイクをつなぐ
KR-377 にはマイクを接続することができます。
マイク端子は、本体の右下面にあります。
fig.01-32.j(マイクをつなぐ図)
Volume
(マイク音量つまみ)
MicEcho
(マイク・エコーつまみ)
MicIn(マイク端子)
マイクの音量は、マイク端子の横にあるMic(マイク)[Volume(音量)]
つまみで調節します。
エコーのかかり具合は、Mic(マイク)[Echo(エコー)]つまみで調節し
ます。
KR-377 に触れてみましょう
マイクを初めてお使いにな
る前には、15 ページの
「マイクご使用上の注意」
を必ずお読みください。
カラオケ用のミュージック
データは、別途ご購入くだ
さい。
「KR-377 で使用できる
ミュージックデータ」
(P.178)をご覧ください。
■ カラオケをする
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
マイクをつないで、音量とエコーのかかり具合を調節します。
ミュージックデータの入ったフロッピー・ディスクをディス
ク・ドライブに入れます。
「フロッピー・ディスクの入れかた/取り出しかた」(P.38)をご覧くだ
さい。
[曲]ボタンを押します。
ディスプレイ横のボタンで曲を選びます。
必要に応じて、テンポ[−][+]ボタンで、テンポを調節し
ます。
必要に応じて、曲のキーを変えます(P.90)。
再生[ ]ボタンを押すと、曲の伴奏が鳴り出します。
歌ってみましょう。
歌詞付きのミュージックデータを再生すると、画面には歌詞が表示されま
す。
停止[ ]ボタンを押すと、曲の伴奏が止まります。
マイクは、ローランド・マ
イク DR-10 / 20(別売)
などを使用することができ
ます。ご購入の際には、本
をお買い上げになった販
売店にご相談ください。
歌詞を表示させないように
することもできます。「歌
詞を表示させないようにす
る」(P.148)をご覧くだ
さい。
41

第 1 章 演奏しましょう
ピアノ演奏をする(ワンタッチ・ピアノ)
ボタン1 つで、ピアノ演奏に最適な設定にすることができます。
fig.01-01
1.
[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押します。
次のような「ピアノ画面」が表示されます。
fig.01-02.j
次の状態に設定されます。
鍵盤が右側と左側に分かれていたとき(P.49)は、1 つの鍵盤に戻りま
•
す。
•
ペダルの働きは、通常のペダルの働きに戻ります(P.14)。
•
グランド・ピアノの音色が選ばれます。
エフェクトは「シンパセティック・レゾナンス」になります。
•
ピアノの音色を調節する
1.
ディスプレイ左の< >< >を押します。
ピアノの大屋根の開き具合が変わり、音色も変わります。
グランド・ピアノの大屋根の開き具合による音のひびきを再現していま
す。
ピアノ画面に のマー
クが表示されているとき
は、トランスポーズが設定
されています。詳しくは、
「鍵盤の音の高さを変える
(キー・トランスポーズ)」
(P.89)をご覧ください。
ディスプレイ下部の<カス
タマイズ>を押すと、ピア
ノ演奏に関する設定を変え
ることができます。詳しく
は「ワンタッチ・ピアノの
設定を変える」(P.134)
をご覧ください。
42
本機はアコースティック・
ピアノの動作を忠実に再現
しているため、高音部の
1.5 オクターブ程度の範囲
はダンパー・ペダルに関係
なく音が最後まで延び、ま
た、音色も違って聞こえま
す。ダンパー・ペダルの影
響を受けない範囲は、
キー・トランスポーズ
(P.89)の設定によっても
変化します。
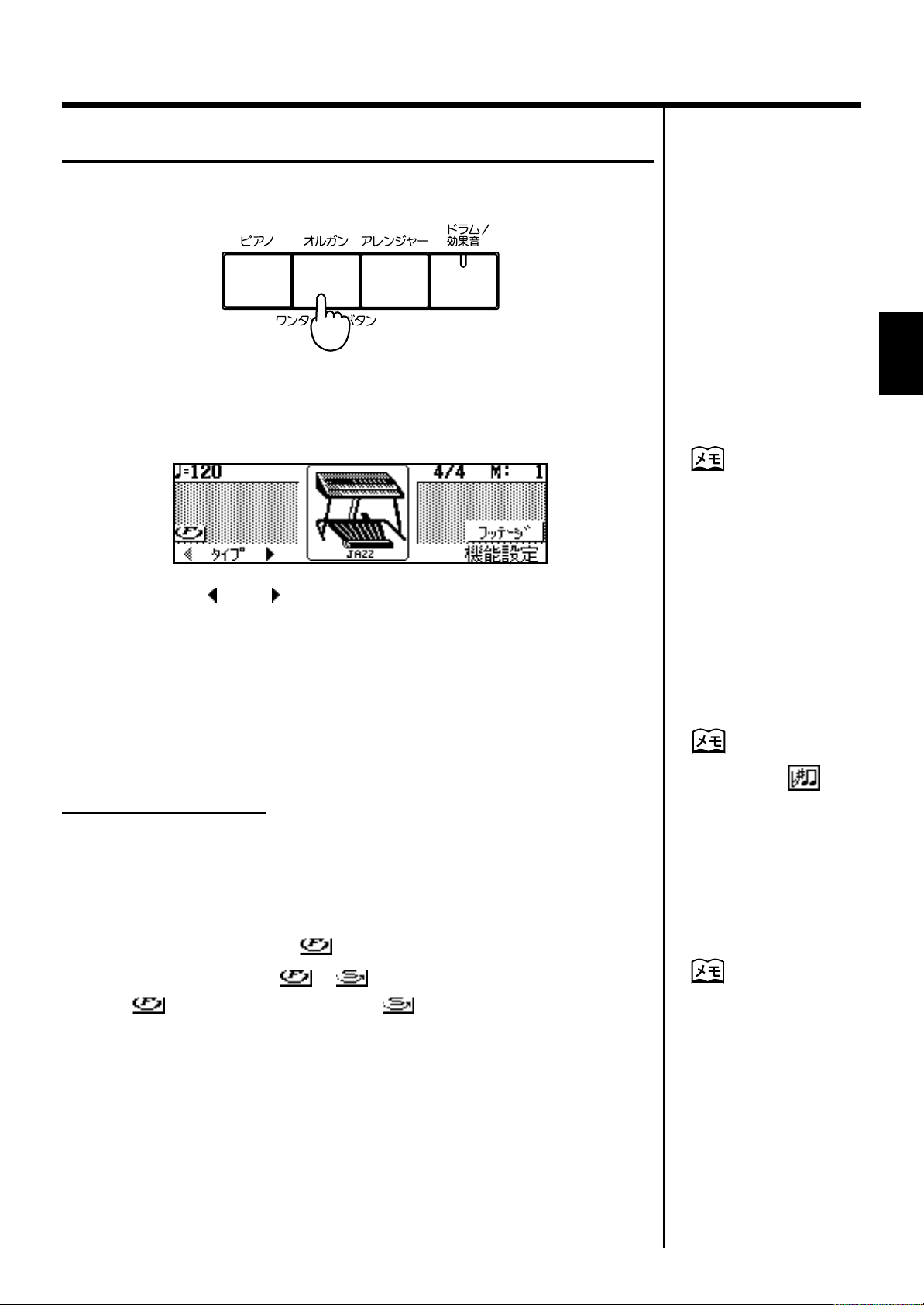
オルガン演奏をする(ワンタッチ・オルガン)
)
ボタン1 つで、オルガン演奏に最適な設定にすることができます。
fig.01-03(パネル図)
第 1 章 演奏しましょう
第1章
1.
2.
[ワンタッチ・オルガン]ボタンを押します。
次のような「オルガン画面」が表示されます。
fig.01-04.j
タイプ< > < >を押して、オルガンの種類を選びます。
ここで選ぶことができるオルガンのタイプは次の4 種類です。
ジャズ・オルガン
•
•
パイプ・オルガン
•
シアター・オルガン
クラシック・オルガン
•
ロータリー効果を変える
「ジャズ・オルガン」の音には、ロータリー効果がかかっています。
オルガンの音にロータリー効果をかけると、回転スピーカーを使ったとき
のようなうねりのついた音になります。このスピーカーの回転速度は変え
ることができます。
1.
ディスプレイ左の< >を押します。
「ジャズ・オルガン」を選
ぶと、鍵盤の右側と左側で
別々の音色が鳴ります。こ
のように、鍵盤が右側と左
側に分かれることを、「ス
プリット」といいます。詳
しくは、「鍵盤の右手側と
左手側で別の音を鳴らす
(スプリット演奏)」(P.49
をご覧ください。
オルガン画面に の
マークが表示されていると
きは、トランスポーズが設
定されています。詳しく
は、「鍵盤の音の高さを変
える(キー・トランスポー
ズ)」(P.89)をご覧くださ
い。
ボタンを押すたびに、 と が切り替わります。
にすると回転速度が速くなり、 にすると回転速度が遅くなりま
す。
ディスプレイ下部の<機能
設定>を押すと、オルガン
演奏のための設定を変える
ことができます。また、
ジャズ・オルガンを選んで
いるときは、<フッテージ
>を押して、好みの音色を
作ることができます。詳し
くは「フッテージを調節す
る」(P.143)をご覧くだ
さい。
43

第 1 章 演奏しましょう
ドラムの音を鳴らす
打楽器の音や、パトカーの音や動物の声などの効果音を、鍵盤から鳴らす
ことができます。
fig.01-05(パネル図)
1.
2.
3.
[ドラム/効果音]ボタンを押します。
ボタンのランプが点灯し、ドラム画面が表示されます。
鍵盤を弾くと、1つ 1 つの鍵から違う打楽器の音が鳴ります。
fig.01-06.j(ドラム画面)
ディスプレイ下のタイプ< > < >を押して、ドラム・
セットの種類を変えます。
画面中央に、ドラム・セットの種類が表示されます。
「スタンダード・セット」などの打楽器音の音色セットを「ドラム・セッ
ト」といいます。
ドラム・セットは、いろいろな種類の打楽器音や効果音がセットになって
おり、1つ 1 つの鍵盤から違う音が鳴ります。
もう一度[ドラム/効果音]ボタンを押すと、元の音に戻り
ドラム・セットによって、
鍵盤に割り当てられている
音の組み合わせは違いま
す。「ドラム/効果音一覧」
(P.166)をご覧ください。
44
ます。
ボタンのランプが消灯し、元の画面に戻ります。
鍵盤の音は[ドラム/効果音]ボタンを押す前に鳴っていた楽器の音に戻
ります。

■ 効果音を鳴らす
第 1 章 演奏しましょう
1.
2.
3.
[ドラム/効果音]ボタンを押します。
ボタンのランプが点灯し、ドラム画面が表示されます。
ディスプレイ下の<効果音>を押します。
鍵盤を弾くと1 つ1 つの鍵から違う効果音が鳴ります。
画面が次のように変わります。
fig.01-07.j(SFX 画面)
効果音の音色セットを「効果音セット」といいます。
ディスプレイ下の<ドラム>を押すと、ドラム画面が表示され、打楽器の
音が鳴るようになります。
もう一度[ドラム/効果音]ボタンを押すと、元の音に戻り
ます。
ボタンのランプが消灯し、元の画面に戻ります。
鍵盤の音は[ドラム/効果音]ボタンを押す前に鳴っていた楽器の音に戻
ります。
第1章
効果音セットの音色につい
ては「ドラム/効果音一
覧」(P.166)をご覧くだ
さい。
45

第 1 章 演奏しましょう
いろいろな楽器の音を鳴らす
KR-377 は多くの楽器の音や効果音を内蔵しています。様々な音楽ジャン
ルの曲に合った音で演奏をお楽しみください。内蔵しているさまざまな種
類の音を「音色」といいます。音色は8 つの音色グループに分けられてい
ます。
次のボタンを音色ボタンといいます。
fig.01-08(パネル図)
1.
2.
いずれかの音色ボタンを押して、音色グループを選びます。
押した音色ボタンのランプが点灯します。
画面には、そのグループに含まれる音色のうち、4つが表示されます。
fig.01-09.j(音色画面)
このような画面を「音色選択画面」といいます。
ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えると、他の音色
が表示されます。
ディスプレイ横のボタンを押して、音色を選びます。
鍵盤を弾くと選んだ音色が鳴ります。また、次に操作1 で選んだ音色ボタ
ンを押したときには、ここで選ばれた音色が鳴ります。
ディスプレイ下の<デモ>を押すと、その音色をフレーズで確認すること
ができます。
KR-377 に内蔵されている
音色については、「音色一
覧」(P.162)をご覧くだ
さい。
音色選択画面でディスプレ
イ下の<機能設定>を押す
と、音色に効果をかけるな
どの設定をすることができ
ます。詳しくは「音にさま
ざまな効果をかける(エ
フェクト)」(P.55)をご覧
ください。
3.
[戻る]ボタンを押します。
元の画面に戻ります。
<EX>音色について
ローランドが自信を持ってお勧めする、表現力に優れた音色です。
EX音色の中には、鍵盤を弾く強さ(ベロシティ)によって音色が変化す
るものもあります。
46

二つの楽器の音を重ねる(レイヤー演奏)
1つの鍵盤で、2 つの音色を同時に鳴らして演奏することができます。こ
のような演奏を「レイヤー演奏」といいます。例えば、ピアノとストリン
グスの音色を重ねて鳴らすことができます。
fig.01-10.j(レイヤーの説明)
レイヤー演奏:選んだ2つの音色を重ねて鳴らす
グランドピアノ1
ストリングス
第 1 章 演奏しましょう
第1章
1.
2.
基本画面で、ディスプレイ下の<レイヤー>を押します。
fig.01-11.j(基本画面)
画面が次のように変わります。
fig.01-12.j(レイヤー画面)
画面右下に音色名が表示されます。この音色を「レイヤー音色」といいま
す。
鍵盤を弾くと、操作1 で選んでいた音色とレイヤー音色が、重なって鳴り
ます。
レイヤー演奏を解除するには、もう一度<レイヤー>を押し
ます。
「基本画面」(P.16)
それぞれの音色の音量を調
節することができます。
「演奏パートごとに音量を
調節する」(P.75)をご覧
ください。
鍵盤を弾くと、画面右上に表示されていた音色だけが鳴ります。
47
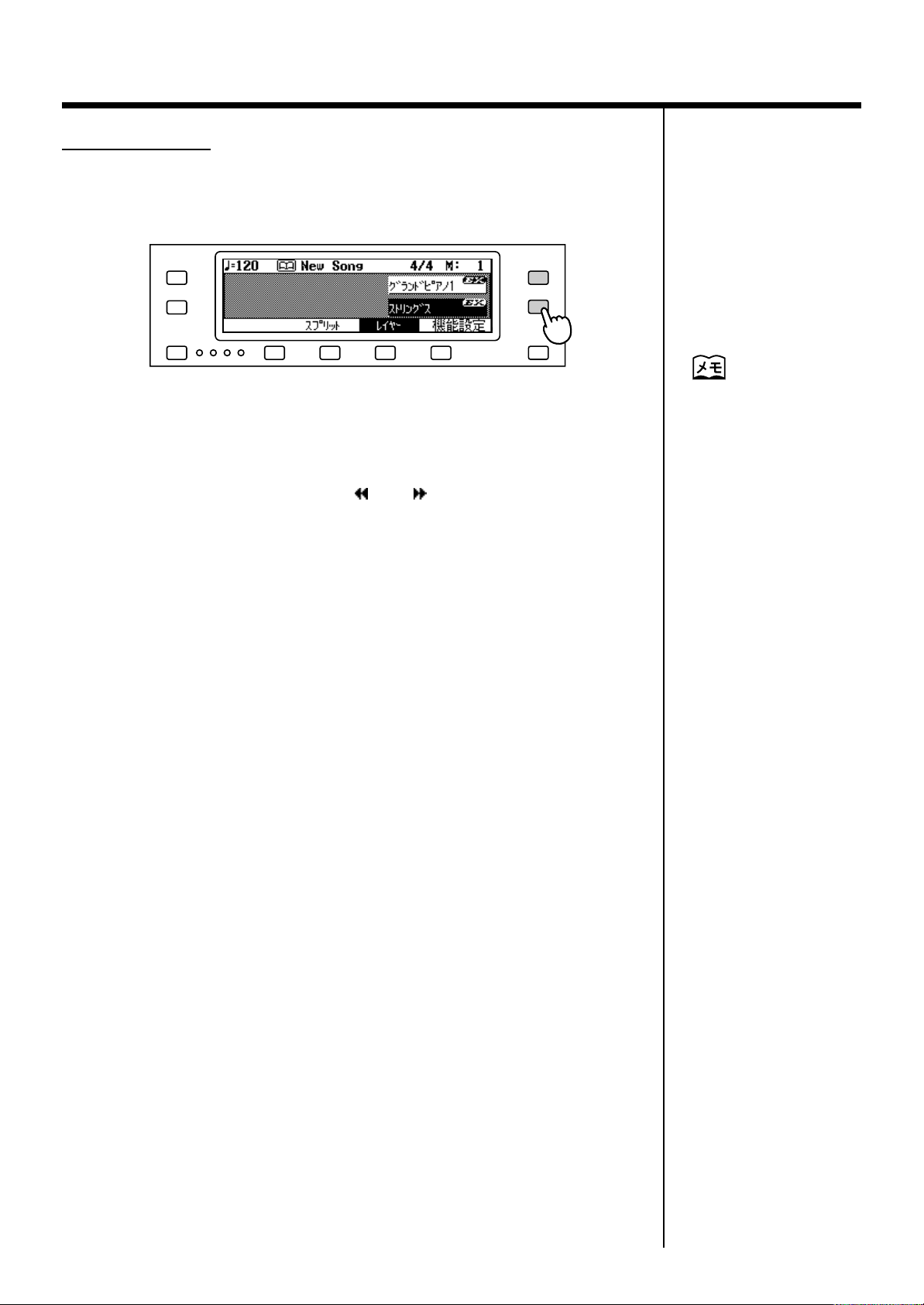
第 1 章 演奏しましょう
高
音色を変えるには
1.
2.
3.
4.
変更したい音色名の横のボタンを押します。
選んだ音色の表示が反転します。
fig.01-12.e
音色ボタンを押します。
音色選択画面が表示されます。
ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えて、
ディスプレイ横のボタンを押して、音色を選びます。
[戻る]ボタンを押します。
元の画面に戻ります。
鍵盤を弾くと、選んだ音色ともう一方の音色が鳴ります。
レイヤー演奏の設定になっ
ている時、音色選択画面で
ディスプレイ下の<機能設
定>を押すと、鍵盤の音の
さをオクターブ単位で変
えることができます。詳し
くは「鍵盤の音の高さをオ
クターブ単位で変える(オ
クターブ・シフト)」
(P.51)をご覧ください。
48

鍵盤の右手側と左手側で別の音を鳴らす
盤
節
)
側
合
(スプリット演奏)
ある鍵を境に、鍵盤を右側と左側に分けて、それぞれで違う音色を鳴らす
ことができます。
鍵盤が右側と左側に分かれることを「スプリット」といい、鍵盤が分かれ
る位置を「スプリット・ポイント」といいます。スプリット・ポイントの
鍵は、左側に含まれます。スプリット・ポイントは、電源を入れた時には
「F#3」に設定されます。
fig.01-13.j(スプリット・ポイントの説明)
スプリット演奏:鍵盤の右側と左側で違う音色を鳴らす
スプリット・ポイント
アコースティック・ベース
グランドピアノ1
第 1 章 演奏しましょう
スプリット・ポイントは変
えることができます。「鍵
が分かれる位置を変え
る」(P.137)をご覧くだ
さい。
レイヤー演奏からスプリッ
トにすると、重ねている 2
つの音色が鍵盤右側の音色
として鳴ります。
第1章
1.
基本画面でディスプレイ下の<スプリット>を押します。
鍵盤右側は画面右上に表示されている音色、鍵盤左側は画面左上に表示さ
れた音色が鳴ります。
鍵盤右側で鳴る音色を「右手音色」、鍵盤左側で鳴る音色を「左手音色」
といいます。
fig.01-14.j(ディスプレイ図)
2.
スプリット演奏を解除するときは、もう一度<スプリット>
●レイヤー演奏からスプリット演奏にした場合
スプリット・ポイント
アコースティック・ベース
グランドピアノ1
ストリングス
「基本画面」(P.16)
鍵盤が右側と左側に分かれ
ている時にダンパーペダル
を踏むと、鍵盤右側の音だ
けに余韻がかかります。左
の音に余韻をかけたい場
は「パッド・ボタンやペ
ダルに機能を割り当てる」
(P.139)をご覧ください。
を押します。
鍵盤右側で鳴っていた音色が、鍵盤全体で鳴ります。
それぞれの音色の音量を調
することができます。詳
しくは、「演奏パートごと
に音量を調節する」(P.75
をご覧ください。
49
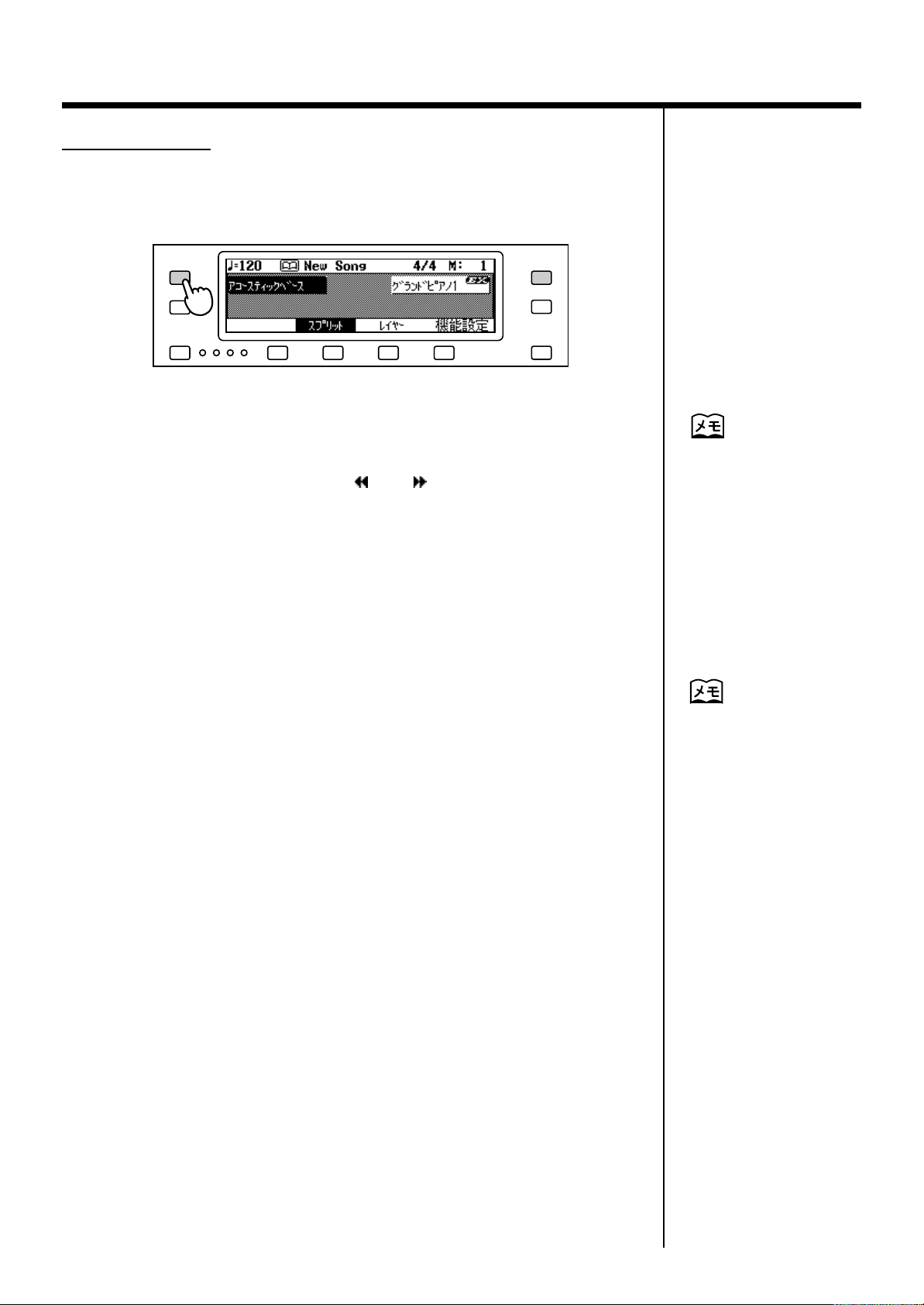
第 1 章 演奏しましょう
音色を変えるには
1.
2.
3.
4.
変更したい音色名の横のボタンを押します。
選んだ音色の表示が反転します。
fig.01-12.e
音色ボタンを押します。
音色選択画面が表示されます。
ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えて、
ディスプレイ横のボタンを押して、音色を選びます。
[戻る]ボタンを押します。
元の画面に戻ります。
鍵盤を弾いて、選んだ音色を確認しましょう。
自動伴奏の状態で<スプ
リット>を押してスプリッ
トをオフにすると、「ピア
ノ・スタイル・アレン
ジャー」の状態になりま
す。「通常のピアノ演奏に
自動伴奏をつける (ピア
ノ・スタイル・アレン
ジャー)」(P.74)をご覧く
スプリット演奏の設定に
なっている時、音色選択画
面でディスプレイ下の<機
能設定>を押すと、鍵盤の
音の高さをオクターブ単位
で変えることができます。
詳しくは「鍵盤の音の高さ
をオクターブ単位で変える
(オクターブ・シフト)」
(P.51)をご覧ください。
50

鍵盤の音の高さをオクターブ単位で変える
(オクターブ・シフト)
鍵盤の右手側と左手側で別の音を鳴らす設定(スプリット演奏→P.49)
になっているときや、二つの楽器の音を重ねる設定(レイヤー演奏→
P.47)になっているときに、音の高さをオクターブ単位で変えることが
できます。この機能を「オクターブ・シフト」といいます。
例えば、スプリット演奏時に、鍵盤左手側の音の高さを鍵盤右手側の音の
高さにあわせることができます。またレイヤー演奏時に、それぞれの音の
高さを変えて、重ねて鳴らすこともできます。
第 1 章 演奏しましょう
鍵盤全体で一つの楽器の音
が鳴っているときは、この
機能は使えません。
第1章
1.
2.
3.
4.
5.
基本画面を表示します。
fig.01-16.j
ディスプレイ下の<レイヤー>または<スプリット>を押し
て、レイヤー演奏かスプリット演奏の設定にします。
オクターブ・シフトする音色の横のボタンを押します。
選んだ音色の表示が反転します。
鳴らしたい音色の音色ボタンを押します。
音色選択画面が表示されます。
ディスプレイ下の<機能設定>を押します。
次のような画面が表示されます。
fig.01-17.j
「基本画面」(P.16)
6.
ディスプレイ下のオクターブ< > < >で音の高さを調節し
ます。
「オクターブ **」には現在の音の高さが表示されます。
オクターブ< >を押すたびに、1 オクターブずつ高くなります。
オクターブ< >を押すたびに、1 オクターブずつ低くなります。
音の高さは、2オクターブ低い音から 2 オクターブ高い音まで(-2 〜
+2)変えられます。
51
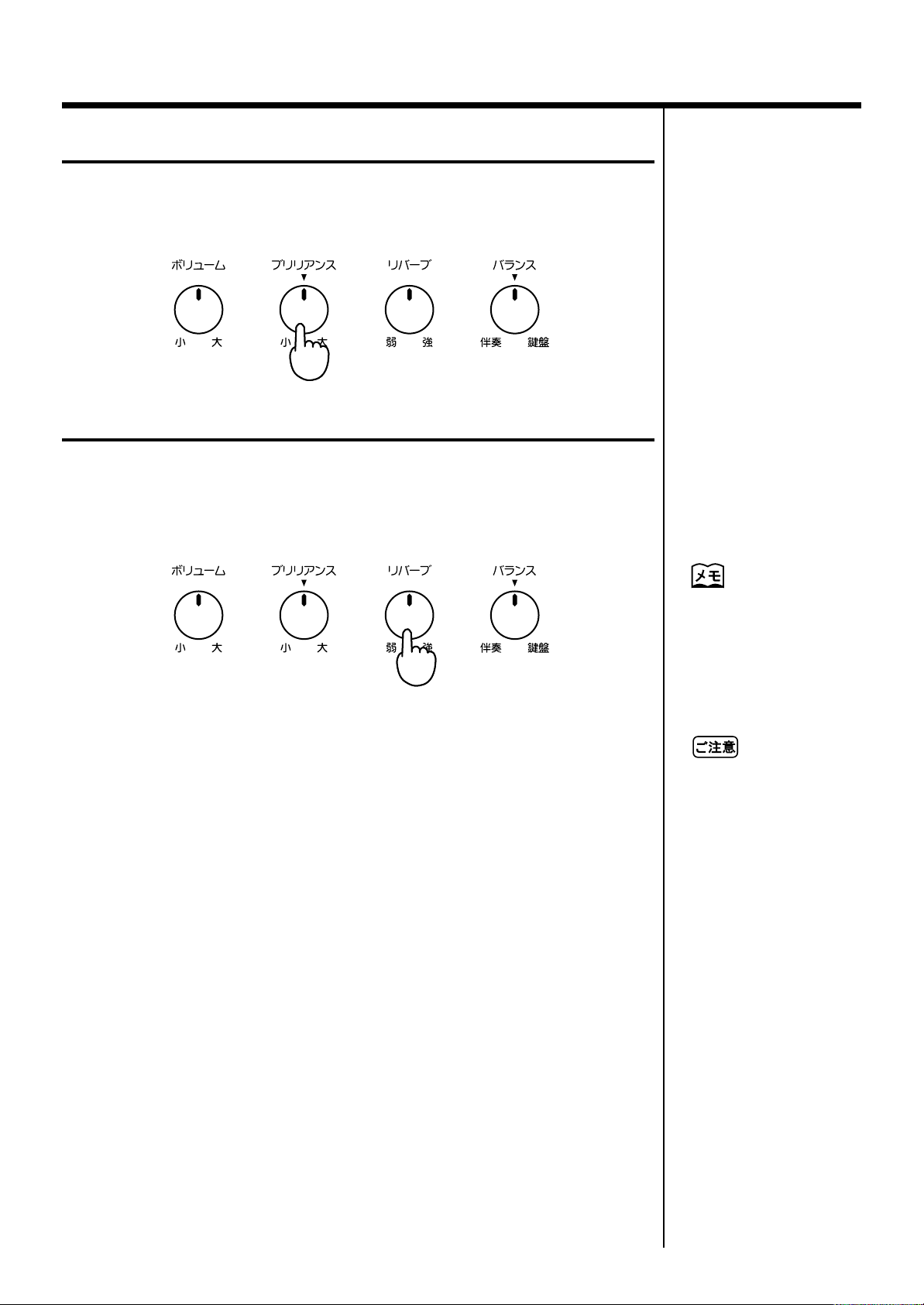
第 1 章 演奏しましょう
音の明るさを調節する
1.
[ブリリアンス]つまみで、全体の音量を調節します。
右側に回すと音が明るくなり、左側に回すと音がやわらかくなります。
fig.01-18(ブリリアンス・つまみ)
音に響きをつける(リバーブ効果)
KR-377 は、鍵盤で弾く音に「リバーブ効果」(残響)をかけることがで
きます。
リバーブ効果をかけると、コンサート・ホールなどで演奏しているような
心地よい響きが得られます。
fig.01-19(リバーブ・つまみ)
リバーブ効果の種類は変え
ることができます。「リ
バーブ効果の種類を変え
る」(P.146)をご覧くだ
さい。
1.
[リバーブ]つまみで、リバーブ効果(残響)のかかり具合を
調節します。
右側に回すとリバーブ効果が深くなり、左側に回すとリバーブ効果が浅く
なります。
[ワンタッチ・ピアノ]ボ
タンを押して、ピアノ演奏
の設定にすると、[リバー
ブ]つまみで設定した効果
のかかり具合が変わること
があります。
52

伴奏の音に立体的な広がりをつける
(アドバンスト 3D)
自動伴奏や内蔵曲に合わせて演奏しているとき、伴奏の音に立体的な広が
りをつけることができます。伴奏の音につつみ込まれるような心地よさを
得ることができます。
fig.01-20
第 1 章 演奏しましょう
第1章
1.
2.
[アドバンスト 3D]ボタンを押します。
ボタンのランプが点灯し、アドバンスト3D 画面が表示されます。
各演奏パートの下のボタンを押して、オン/オフを切り替え
ます。
オンにした演奏パートの音に立体的な広がりがつきます。
fig.01-22.j
アドバンスト3Dオン
3.
アドバンスト3Dオフ
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻りますが、[アドバンスト 3D]ボ
タンのランプが点灯しているときは、選んだパートに効果がかかります。
効果を解除するときは、[アドバンスト 3D]ボタンを押して
ランプを消灯させます。
すべてのパートにアドバンスト3D 効果がかからなくなります。
53

第 1 章 演奏しましょう
■ 鍵盤のレイヤー音色だけに効果をかける
アドバンスト3D 効果を「鍵盤」にかけているとき、レイヤー音色
(P.47)だけに効果をかけることができます。
電源投入時は、「全パート」が選ばれています。
1.
2.
アドバンスト3D 画面でディスプレイ右の< Option >を押しま
す。
次の画面が表示されます。
fig.01-23.j
表示 説明
全パート 鍵盤で弾く全ての音色に効果がかかります。
レイヤー音色のみに効果がかかります。レイヤー
レイヤー・パート
演奏以外の時は「鍵盤」をオンしても鍵盤の演奏
には効果がかかりません。
ディスプレイ横の< >< >で設定を選びます。
[戻る]ボタンを押すと、アドバンスト3D 画面に戻ります。
54
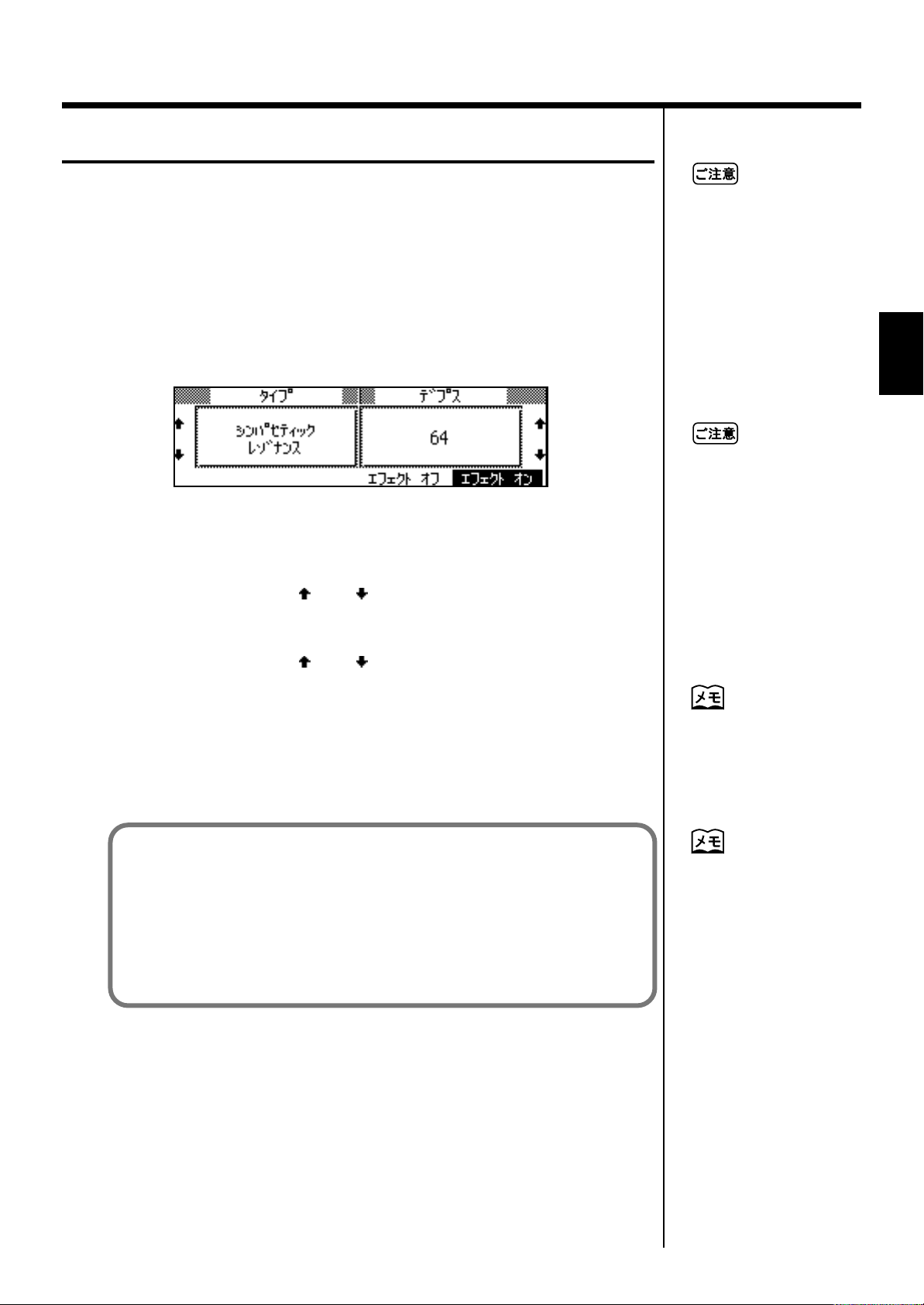
音にさまざまな効果をかける(エフェクト)
鍵盤で弾いた音に、さまざまな効果をかけることができます。
1.
2.
3.
4.
音色ボタンを押して、効果をかける音色を選びます。
音色選択画面が表示されます。
音色選択画面でディスプレイ下の<機能設定>を押します。
次のような画面が表示されます。
この画面を「エフェクト画面」と言います。
fig.01-24.j(エフェクト画面)
ディスプレイ下の<エフェクト オン>を押します。
選んでいる音色に最適の効果がかかります。
ディスプレイ左の< >< >で、タイプ(効果の種類)を
選びます。
第 1 章 演奏しましょう
[ワンタッチ・ピアノ]ボ
タンや[ワンタッチ・オル
ガン]ボタンを押した時に
は、効果の種類を変えるこ
とはできません。
第1章
右手音色(基本画面右上に
表示される音色)と異なる
エフェクトをレイヤー音色
(P.47)や左手音色
(P.49)にかけると、効果
がかからないことがありま
す。右手音色と同じエフェ
クトを選んでください。
5.
6.
ディスプレイ右の< >< >で、デプス(効果のかかり具
合)を調節します。
効果を解除するには、エフェクト画面で、ディスプレイ下の
<エフェクト オフ>を押します。
[戻る]ボタンを押すと、音色選択画面に戻ります。
エフェクトについて
エフェクトをオンにすると、現在選ばれている音色に最適な効果がかかり
ます。また、各音色ごとに、それぞれ効果をかけることができます。エ
フェクトの設定は、電源を切ると初期設定に戻りますが、メモリー・バッ
クアップ(P.149)をしておくと、電源を切ってもエフェクトの設定を記
憶しておくことができます。
効果の種類については、
「エフェクト一覧」
(P.176)をご覧ください。
[ボイス/ GS]ボタンの音
色で、音色名のあとに
「GS」マークがついている
音色は、すべて同じ効果が
かかります。また、その音
色の効果を変えると、他の
「GS」マークがついている
音色の効果も自動的に変わ
ります。
55
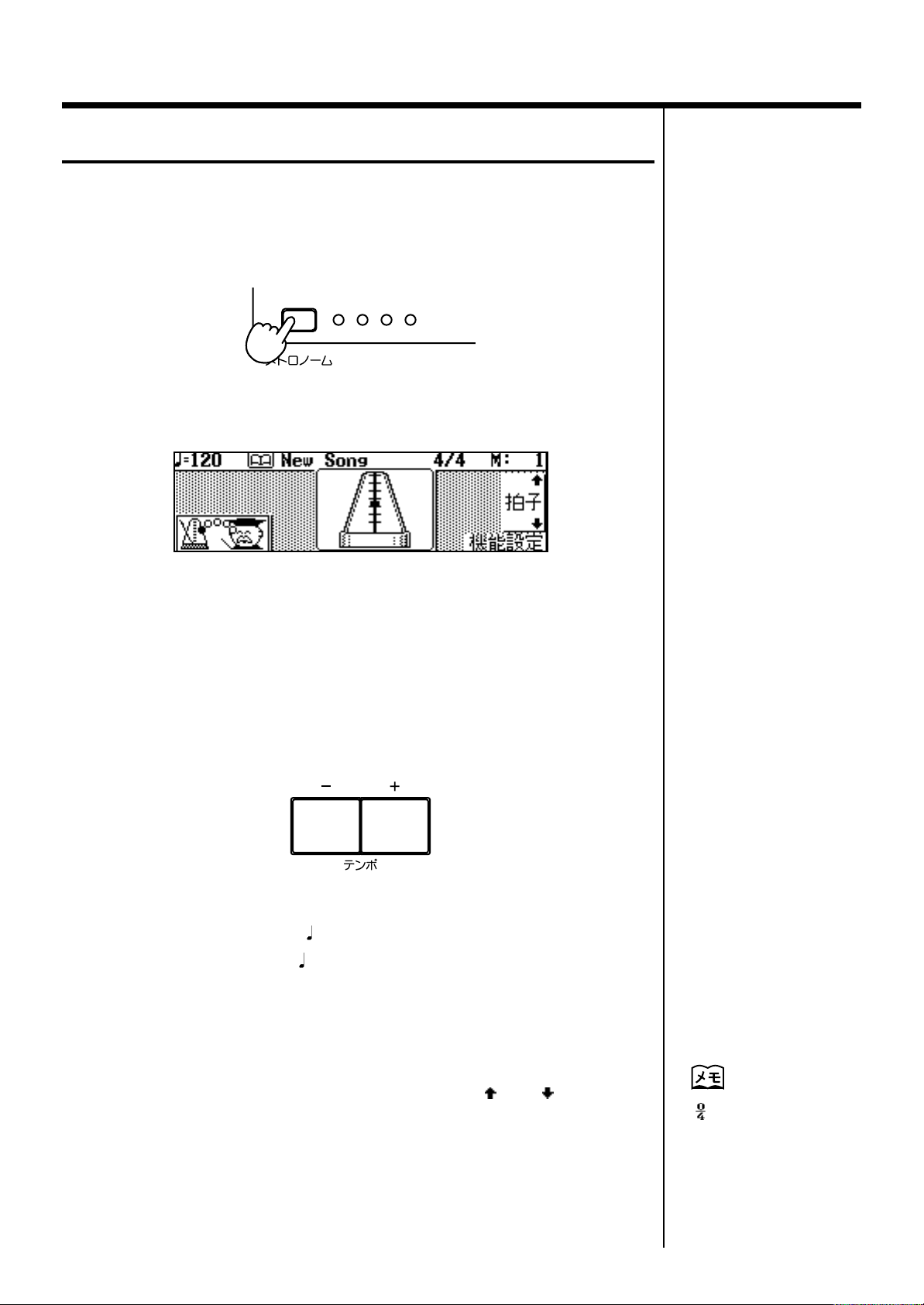
第 1 章 演奏しましょう
メトロノームを鳴らす
KR-377 は、メトロノーム機能を内蔵しています。
メトロノームは、[メトロノーム]ボタン 1 つで鳴らしたり止めたりする
ことができます。曲の再生中や自動伴奏の演奏中には、メトロノームは曲
や伴奏のテンポや拍子に合わせて鳴ります。
fig.01-25(メトロノーム・ボタン)
1.
2.
[メトロノーム]ボタンを押すと、メトロノームが鳴ります。
次のような「メトロノーム画面」が表示されます。
fig.01-26.j(メトロノーム画面)
メトロノームを止めるときは、もう一度[メトロノーム]ボ
タンを押します。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
■ テンポを調節する
メトロノームが鳴る速さを変えることができます。また、メトロノームの
テンポや拍子は自動伴奏を使ったり、曲を再生したりすると、自動的に変
わります。
fig.01-27(テンポ・ボタン)
1.
テンポ[−][+]ボタンで、テンポを選びます。
メトロノームのテンポは =20 〜 250 の範囲で調節することができます。
電源を入れたときは、「 =120」に設定されます。
[−][+]ボタンを同時に押すと、スタイルや曲の基本テンポに戻すこと
ができます。
■ 拍子を変える
1.
56
メトロノーム画面で、ディスプレイ右の< >< >を押し
て拍子を設定します。
画面上段に表示されている拍子が変わります。
選べる拍子
2/2、0/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、9/8、12/8
を選んでいるときは、
弱拍の音だけが鳴ります。

■ アニメーションを切り替える
通常、メトロノーム画面の中央の表示を変えることができます。
電源を入れた時には、「メトロノーム」が表示されます。
第 1 章 演奏しましょう
1.
メトロノーム画面で の下のボタンを押します。
アニメーションが切り替わります。
■ 拍の刻み方(パターン)を変える
通常、メトロノームは、四分音符を一拍として鳴りますが、例えば付点四
分音符ごとに鳴らすなど、拍の刻み方を変えることができます。
1.
2.
3.
メトロノーム画面で、ディスプレイ下の<機能設定>を押し
ます。
ディスプレイ下の選択< > < >で<パターン>を選びま
す。
選んだ項目名が反転します。
ディスプレイ横の< >< >でパターンを設定します。
表示 解説
通常の鳴り方です。
第1章
弱拍が付点 2 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
弱拍が 2 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
弱拍が付点 4 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
弱拍が 4 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
弱拍が付点 8 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
弱拍が 8 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
弱拍が 16 分音符の間隔で小節頭から刻みます。
追加音が 1 拍の裏拍で鳴ります。
追加音が 1 拍を3 連符で刻みます。
追加音がシャッフルで鳴ります。
3連系の拍子(6/8、9/8、
12/8)では、「+Double」
を選んだとき、追加音が 3
連符で鳴ります。
[戻る]ボタンを押すと、メトロノーム画面に戻ります。
57
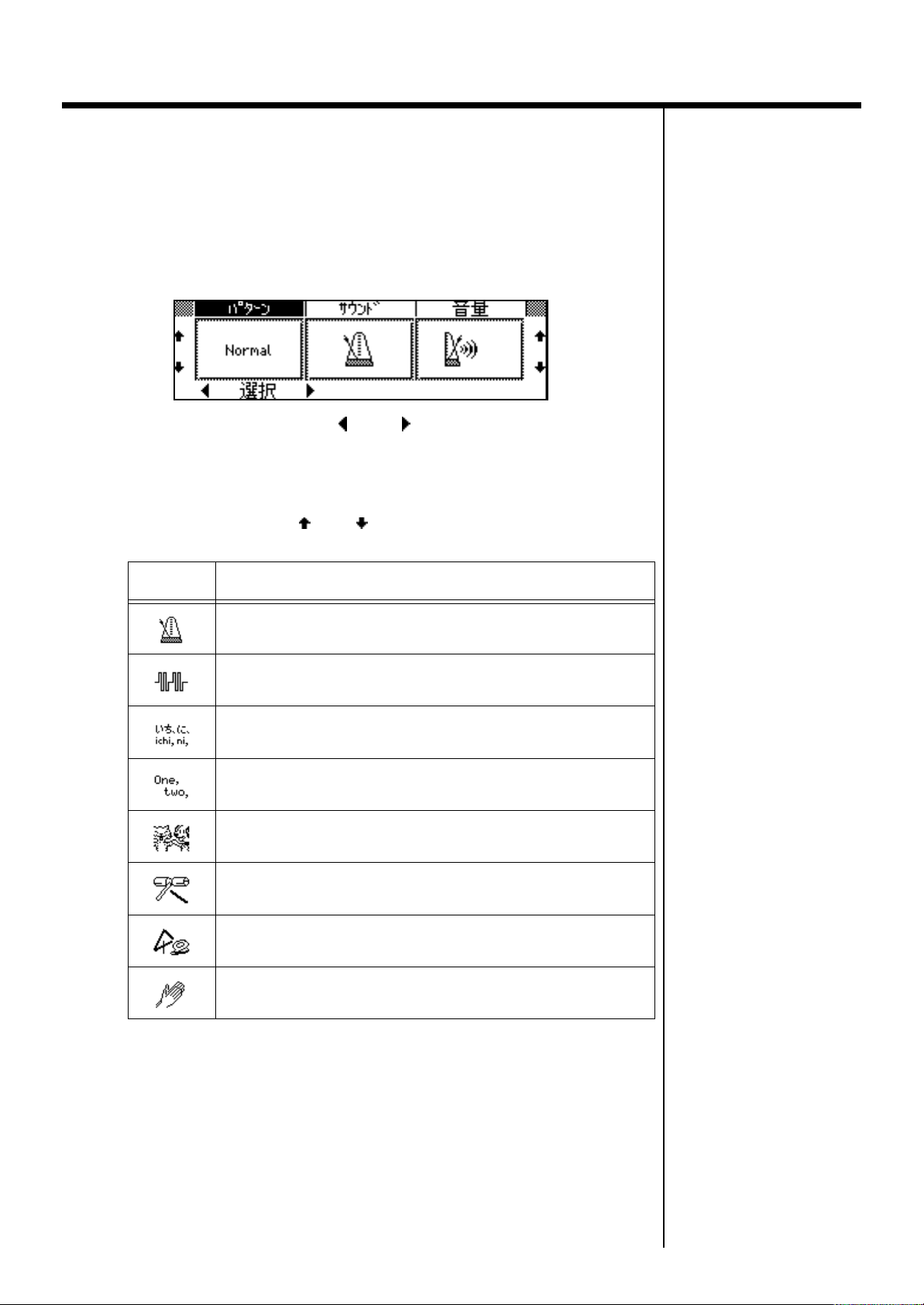
第 1 章 演奏しましょう
■ 音の種類を変える
メトロノームの音の種類を変えることができます。
電源を入れた時には「通常のメトロノームの音」に設定されます。
1.
2.
3.
メトロノーム画面で、ディスプレイ下の<機能設定>を押し
ます。
fig.01-28.j
ディスプレイ下の選択< > < >で<サウンド>を選びま
す。
選んだ項目名が反転します。
ディスプレイ横の< >< >で音の種類を設定します。
表示 解説
通常のメトロノームの音
電子メトロノームの音
日本語で「1」「2」「3」
英語で「1」「2」「3」
犬とねこの声
ウッド・ブロックの音
トライアングルとカスタネットの音
手拍子
[戻る]ボタンを押すと、メトロノーム画面に戻ります。
58
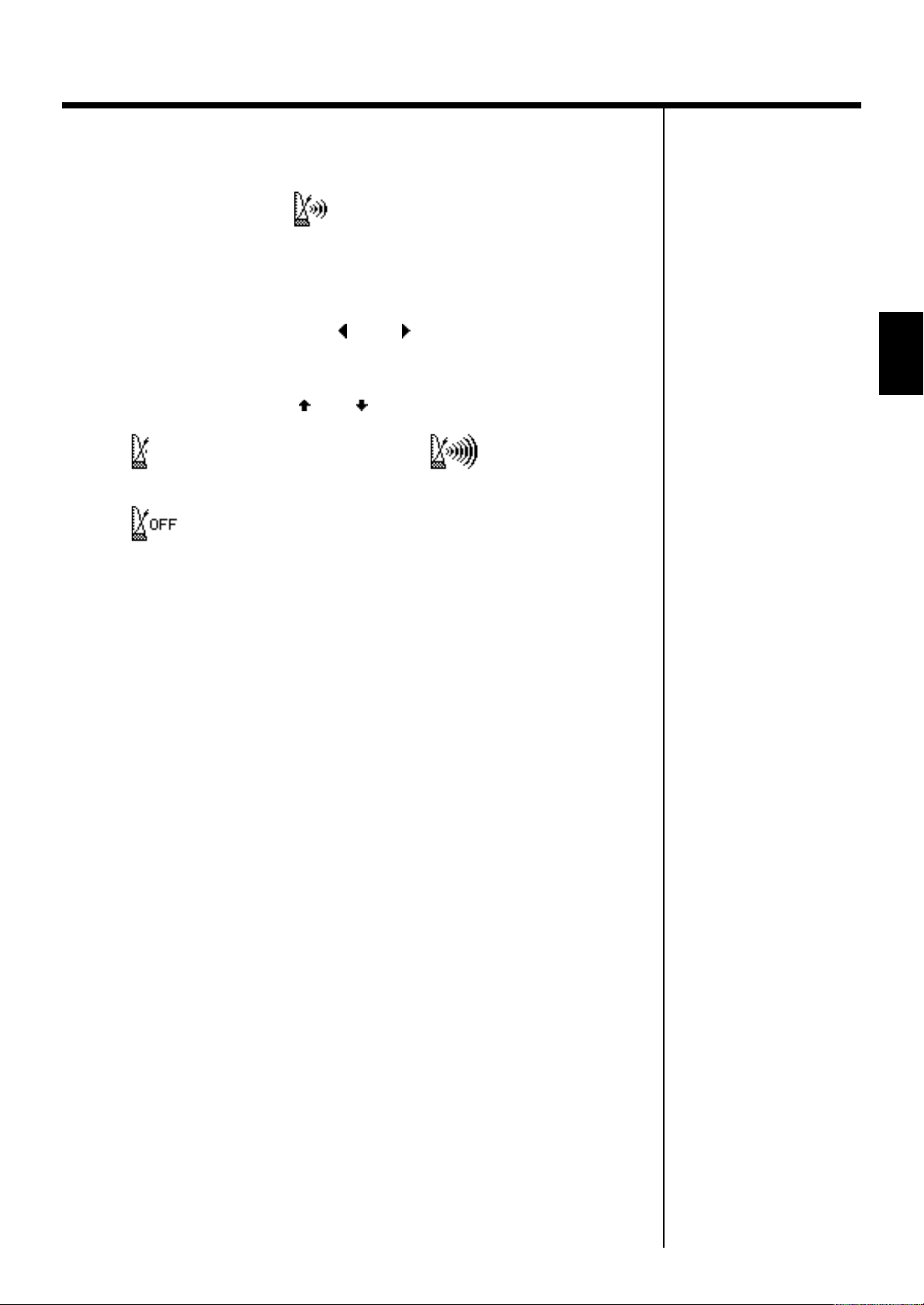
■ 音量を変える
メトロノームの音量を10 段階で調節することができます。
電源を入れた時には、「(5)」に設定されます。
第 1 章 演奏しましょう
1.
2.
3.
メトロノーム画面で、ディスプレイ下の<機能設定>を押し
ます。
ディスプレイ下の選択< > < >で<音量>を選びます。
選んだ項目名が反転します。
ディスプレイ横の< >< >で音量を設定します。
も大きい音量になります。
[戻る]ボタンを押すと、メトロノーム画面に戻ります。
を選ぶと、最も小さい音量になり、 を選ぶと、最
を選ぶと、音が鳴らなくなります。
第1章
59

第 2 章 自動伴奏
ミュージック・スタイルと自動伴奏
ミュージック・スタイルとは
さまざまな音楽ジャンルの伴奏パターンをミュージック・スタイルといい
ます。
世界中にはいろいろな音楽があり、それぞれ特徴を持っています。ジャズ
なら「ジャズらしさ」、クラシックなら「クラシックらしさ」を感じること
ができるのは、使う楽器やメロディー、フレーズなどの要素の組み合わせ
で、「その音楽らしい雰囲気」が作られているからだといえます。ミュー
ジック・スタイルはこれらの要素を取り入れて、「それぞれの音楽ジャンル
らしい雰囲気」を作り出しています。
ミュージック・スタイルの構成
ミュージック・スタイルは、「ディビジョン」とよばれる 6 つの演奏状態が
1セットになって構成されています。
また、ミュージック・スタイルは、「リズム」「ベース」「伴奏 1」「伴奏 2」
「伴奏3」の 5 つの演奏パートで構成されています。
イントロ(Intro) 曲の最初に演奏します。前奏です。
オリジナル(Original) 基本型の伴奏パターンです。
バリエーション(Variation)
フィルインからバリエー
ションへ
(Fill In To Variation)
フィルインからオリジナル
へ
(Fill In To Original)
エンディング(Ending) 曲の最後に演奏します。後奏です。
自動伴奏とは
KR377では、[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押すだけで、自動伴
奏の設定にすることができます。自動伴奏とは、左手でコードを指定する
だけで、さまざまな音楽ジャンルの伴奏を自動的に鳴すことができる機能
です。自動伴奏を使えば、1人でもオーケストラをバックにアンサンブル
演奏を楽しむことができます。
ディビジョン 解説
発展型の伴奏パターンです。オリジナル
とは変化をつけます。
曲調の変わり目で入れる 1 小節のフレー
ズです。曲を盛り上げるとき(バリエー
ションに移るとき)に使います
曲調の変わり目で入れる 1 小節のフレー
ズです。曲を落ち着かせるとき(オリジ
ナルに移るとき)に使います。
自動伴奏の演奏方法につい
ては、「ミュージック・ス
タイルを選ぶ」(P.63)を
ご覧ください。
60

コードについて
コードとは、複数の音を同時に鳴らす和音のことで、基準となる音の高さ
(ルート音)と、構成音の種類をコード・タイプで表します。
例えば、C Maj というコードの場合、C(ド)というルート音(根音)と、
Maj(メジャー)というコード・タイプで表されています。また、C Maj は
「C(ド)」「E(ミ)」「G(ソ)」の 3 音で構成されています。
基本画面の左側のコード名には「C Maj」と表示されます。
fig.02-C1.j
C
ルート音
コードのルート音はすべてアルファベットと または で表示され、次のよ
うに対応しています。
fig.02-C2.j
Maj
コード・タイプ
ルート音
CEG
ド ミ ソ
第 2 章 自動伴奏
コードの押さえ方について
は、「コードの押さえかた
一覧」(P.174)をご覧く
ださい。
第2章
(D )
(D )
CCDEEFFGAAB
ド レ ミ ファ ソ ラ シ
(G )
(G )(A )
■ 簡単な指使いでコードを押さえる (コード・インテリジェンス機能)
自動伴奏時にコードを指定するいくつかの鍵を押さえるだけで、伴奏のコー
ドを認識させる機能を「コード・インテリジェンス機能」といいます。
例えば「C Maj」というコードならば、普通は「ド」「ミ」「ソ」の 3 つの鍵
を押さえなければなりませんが、コード・インテリジェンス機能を使えば、
「ド」の鍵を1 つを押さえるだけで、「C Maj」のコードで伴奏を鳴らすこと
ができます。
fig.02-C3.j
●コード・インテリジェンス機能を使ったコードの押さえ方
メジャー
例)
C Maj
コードのルート音を押さえます。
マイナー
例)
B
C min
通常は、コード・インテリ
ジェンス機能を使う設定に
なりますが、使わない設定
にすることもできます。詳
しくは、「コード・インテ
リジェンス機能を解除す
る」(P.139)をご覧くだ
さい。
コードのルート音とその3つ上の音
(ルート音より短3度上の音)を押
さえます。
セブンス
C 7
例)
コードのルート音とその2つ下の音
(ルート音より長2度下の音)を押
さえます。
メジャー・セブンス
C Maj 7
例) 例)
コードのルート音とその1つ下の音
(ルート音より短2度下の音)を押
さえます。
マイナー・セブンス
ディミニッシュ
例)
C dim
C min 7
コードのルート音とその3つ上の音
(ルート音より短3度上の音)およ
び2つ下の音(長2度下の音)をいっ
しょに押さえます。
コードのルート音とその6つ上の音
(ルート音より減5度上の音)を押
さえます。
61
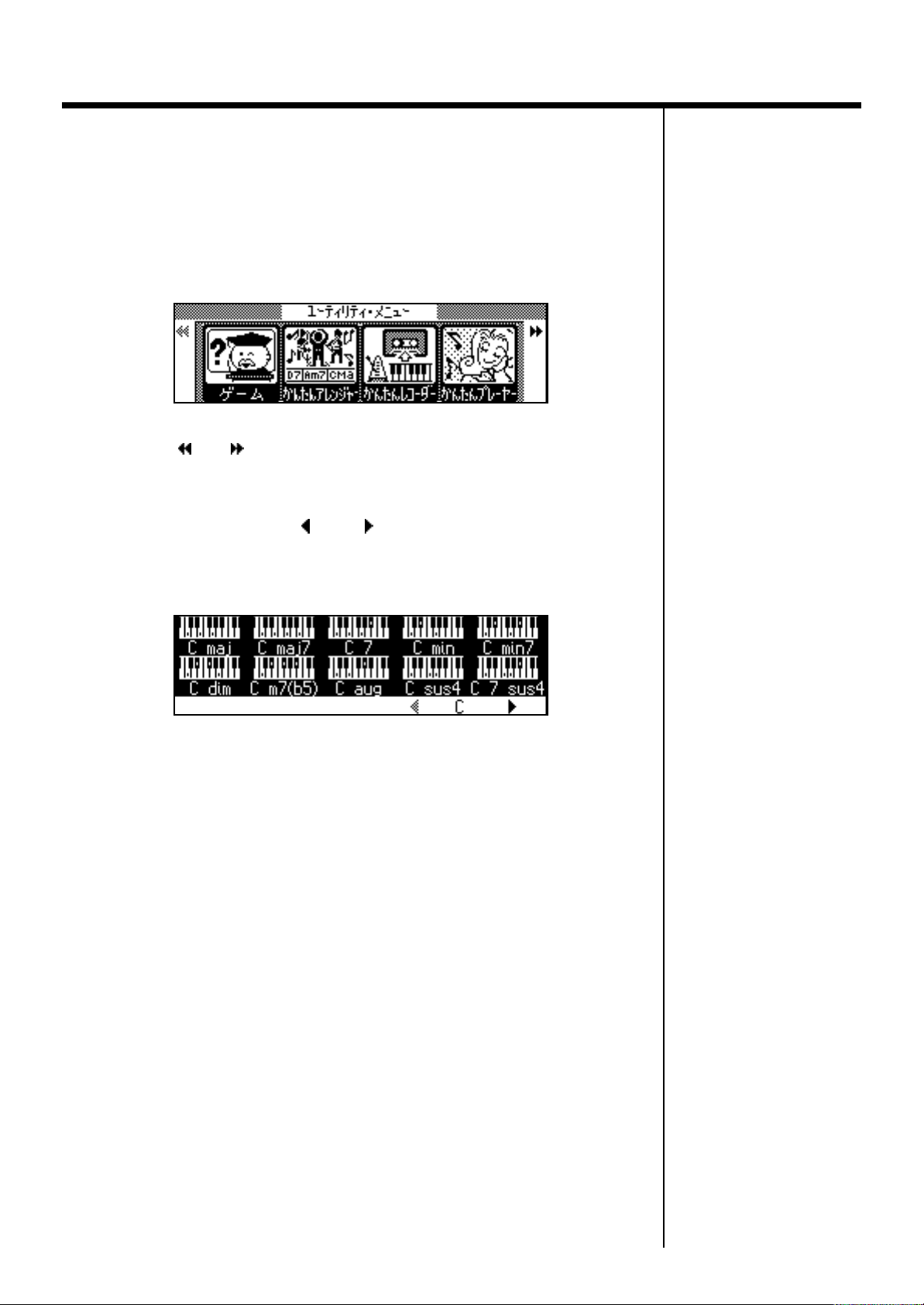
第 2 章 自動伴奏
■ コードの押さえ方を画面に表示させる(コード検索)
コードの押さえ方が分からないとき、画面にコードを構成している音を表
示させることができます。
1.
2.
3.
[ユーティリティ]ボタンを押します。
ユーティリティ画面が表示されます。
fig.02-01.j
画面に<コード検索>が表示されていないときは、ディスプレイ左上と右
上の< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ下の<コード検索>を押します。
ディスプレイ下の< > < >で、調べたいコードのルート
音を指定します。
画面には、コードの押さえ方が表示されます。
fig.02-02.j
[戻る]ボタンを押すと、ユーティリティ画面に戻ります。
62
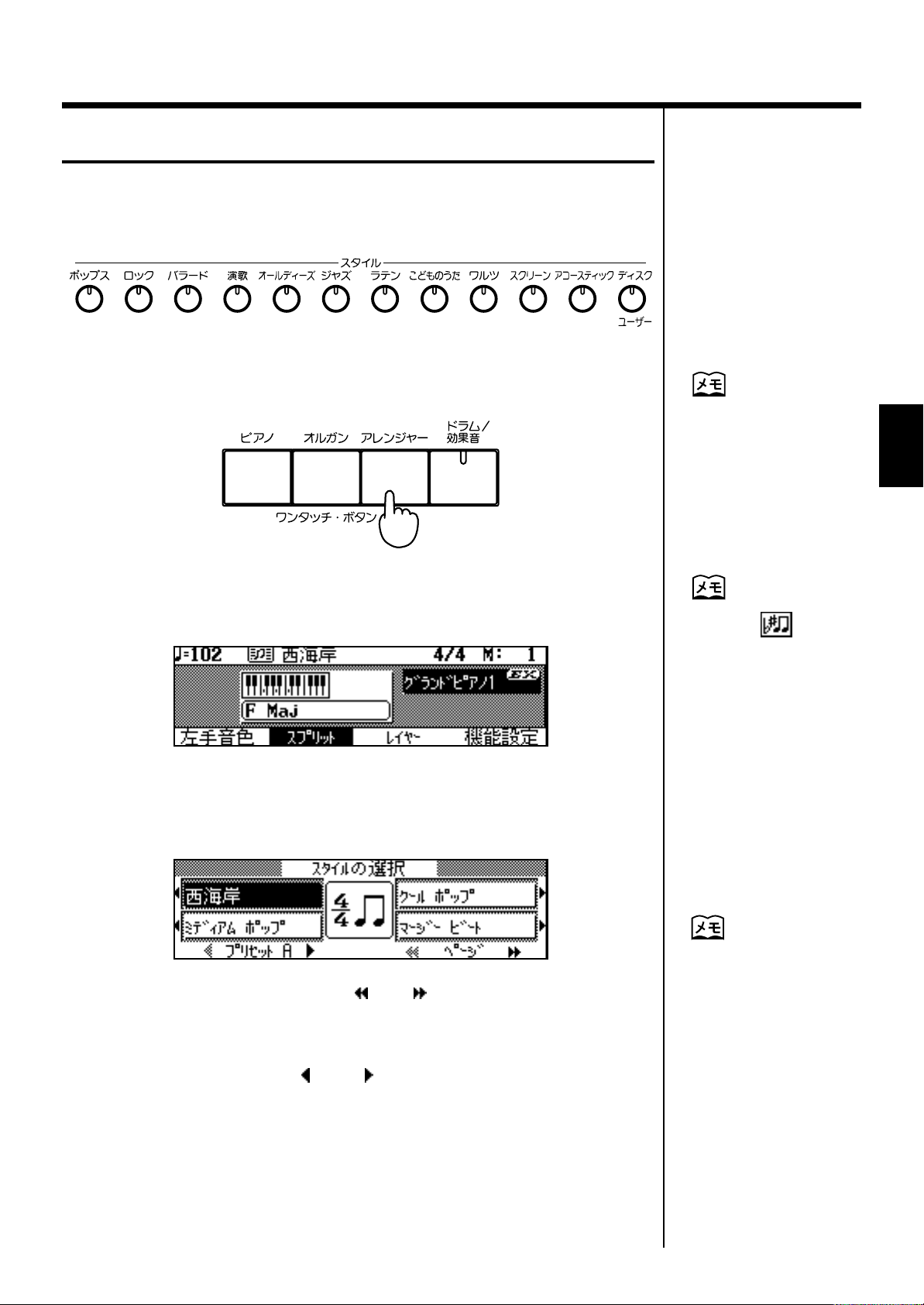
ミュージック・スタイルを選ぶ
種
スタイル・ボタンを押して、さまざまなミュージック・スタイルを選ぶこ
とができます。以下のボタンをスタイル・ボタンといいます。
ミュージック・スタイルは、11 のグループに分かれています。
fig.02-03
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押して、ミュージック・スタイルを
変えると、鍵盤右手側で鳴る音色やテンポが選んだミュージック・スタイ
ルに最適なものに変わり、すぐに自動伴奏で演奏できる設定になります。
fig.02-04
第 2 章 自動伴奏
ミュージック・スタイルの
類については、「ミュー
ジック・スタイル一覧」
(P.171)をご覧ください。
第2章
1.
2.
3.
4.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
次のような基本画面が表示されます。
fig.02-05.j
スタイル・ボタンを押して、ミュージック・スタイルのグ
ループを選びます。
次のような画面を「スタイル選択画面」といいます。
fig.02-06.j
ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替え、ス
タイル名の横のボタンを押して、ミュージック・スタイルを
選びます。
ディスプレイ下の< > < >でプリセット A 〜 D のいずれ
かを選びます。
プリセットを変えると、ミュージック・スタイルのテンポや右手側の音色、
スタイル・オーケストレーター(P.71)の設定などが変わります。
テンポや音色を変えると、同じミュージック・スタイルでも、雰囲気の違
う演奏を楽しむことができます。
基本画面に のマーク
が表示されているときは、
トランスポーズが設定され
ています。詳しくは、「鍵
盤の音の高さを変える
(キー・トランスポーズ)」
(P.89)をご覧ください。
通常、ミュージック・スタ
イルを変えると、テンポや
音色が、選んだミュージッ
ク・スタイルにふさわしい
ものに変わります。テンポ
や音色を変えたくないとき
には、「ミュージック・ス
タイルを変えても音色やテ
ンポが変わらないようにす
る」(P.141)をご覧くだ
さい。
63
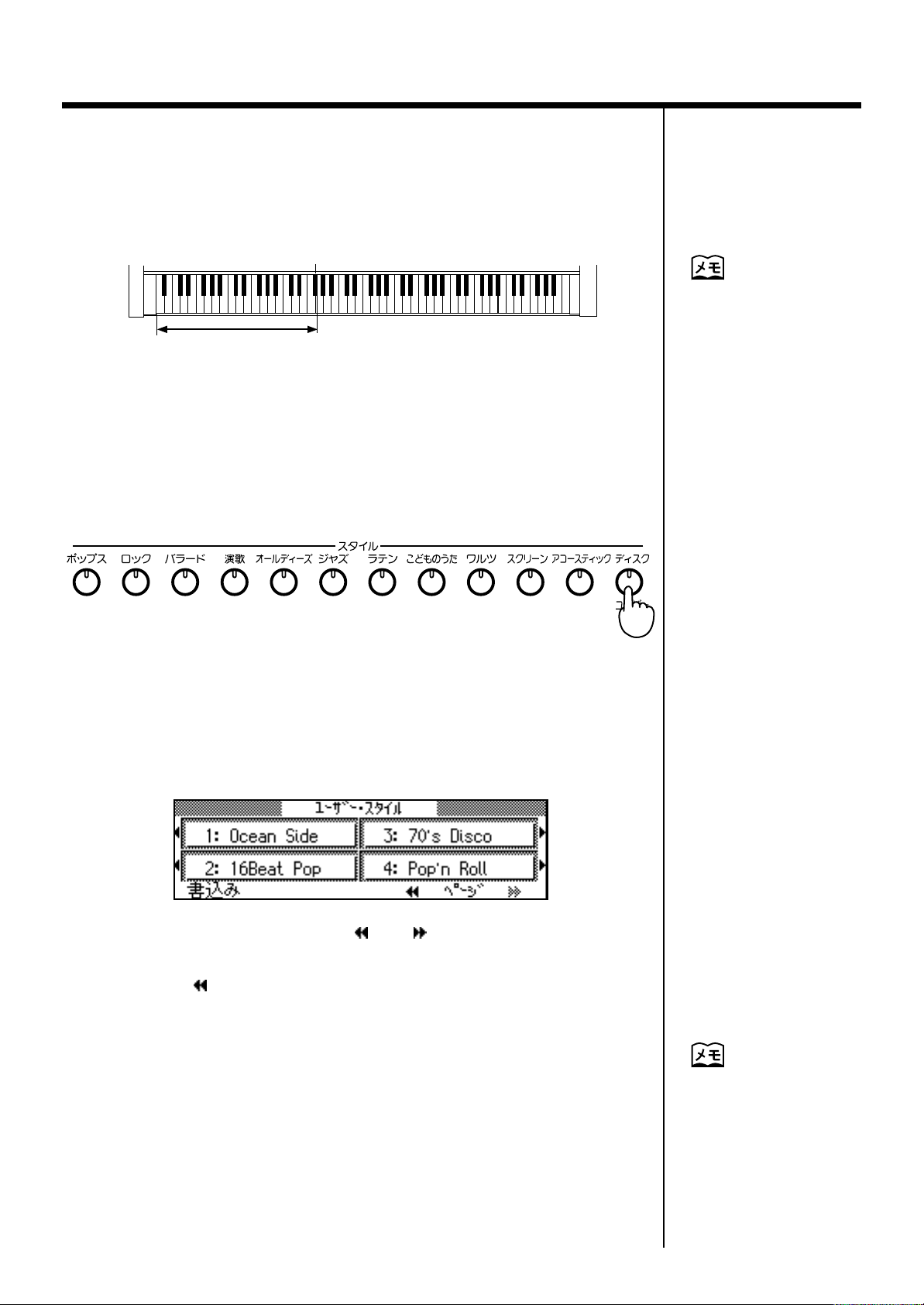
第 2 章 自動伴奏
5.
6.
7.
[戻る]ボタンを押して、基本画面を表示させます。
鍵盤左側でコードを指定します。
指定したコードで、選んだミュージック・スタイルが自動的に演奏されます。
fig.02-07.j
スプリット・ポイント( )
自動伴奏のコードを指定する鍵域
F3
[イントロ/エンディング]ボタンを押すと、エンディングが
演奏されて伴奏が止まります。
■ データ・ディスクのスタイルを使う
付属のデータ・ディスクのミュージック・スタイルや、フロッピー・ディ
スクに保存したユーザー・スタイル(P.132)を使って演奏することがで
きます。
fig.02-08
[スタート/ストップ]ボ
タンを押すと、エンディン
グが演奏されずに自動伴奏
が止まります。
1.
2.
3.
4.
ディスク・ドライブにフロッピー・ディスクを入れます。
ディスク・ドライブの使い方は38 ページを参照してください。
[ディスク/ユーザー]ボタンを押します。
次のような画面が表示されます。
fig.02-09.j
ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えて、
スタイルを選びます。
ページ< >を数回押すと、[ディスク/ユーザー]ボタンに登録されて
いるスタイルが表示されます。
「L」ではじまる番号のついたスタイルは、内部メモリーに記憶されている
スタイルです。ディスクのスタイルは、その後に表示されます。
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押して、鍵盤左側で
コードを指定します。
選ばれたスタイルが鳴ります。
フロッピー・ディスクから選んだミュージック・スタイルは、電源を切る
まで本体内に記憶されています。フロッピー・ディスクを取り出しても、
[ディスク/ユーザー]ボタンを押せば、最後に選んだミュージック・スタ
イルを同じように鳴らすことができます。
複数のユーザー・スタイル
を本体の[ディスク・ユー
ザー]ボタンに登録するこ
とができます「ユーザー・
スタイルをボタンに登録す
る」(P.131)をご覧くだ
さい。
64

自動伴奏を鳴らしながら左手で弾いた音を鳴らす
通常、自動伴奏を使って演奏するときは、鍵盤左手側で押さえた鍵の音は
鳴りません。<左手音色>を選ぶと、自動伴奏と同時に左手側の音色を鳴
らすことができます。
第 2 章 自動伴奏
1.
2.
3.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
基本画面が表示されます。
fig.02-05.j(画面)
第2章
ディスプレイ下の<左手音色>のボタンを押します。
画面が次のように変わります。
fig.02-11.j(画面)
左手音色オン
鍵盤左側でコードを指定します。
4.
自動伴奏のイントロが演奏されます。
鍵盤左側でコードを押さえると、押さえた音が鳴り、伴奏のコードが変わ
ります。
鍵盤左側の音を鳴らさないときは、もう一度<左手音色>を
押します。
左手音色を変えるときは、
「音色を変えるには」
(P.50)をご覧ください。
65
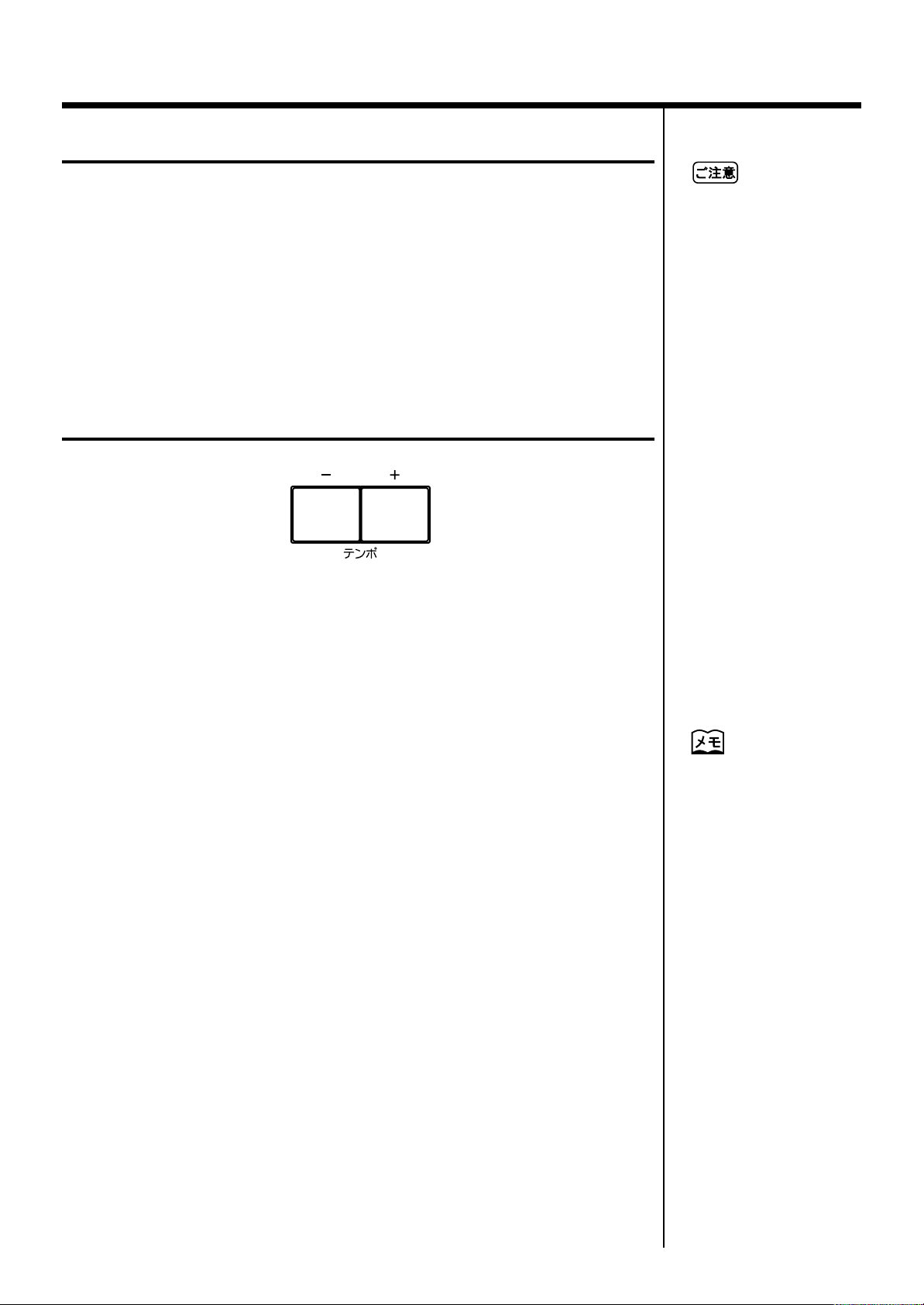
第 2 章 自動伴奏
リズム・パターンだけを鳴らす
ミュージック・スタイルは、リズム・パターンだけで鳴らすこともできま
す。
1.
2.
スタイル・ボタンでミュージック・スタイルを選びます。
[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押してから、[スタート/ス
トップ]ボタンを押します。
選んだミュージック・スタイルのリズム・パターンだけが鳴ります。
自動伴奏のテンポを調節する
fig.02-12
1.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
ミュージック・スタイルの
中にはリズム・パターンを
含んでいないものもありま
す。そのようなミュージッ
ク・スタイルを選んでいた
場合など、左記の操作をし
てもリズム・パターンが鳴
らないことがあります。
2.
自動伴奏の設定になります。
テンポ[−][+]ボタンで、テンポを調節します。
画面の左上にテンポが表示されています。
[+]ボタンを押すとテンポが早くなり、[−]ボタンを押すとテンポが遅
くなります。
[−][+]ボタンを同時に押すと、スタイルの基本テンポに戻すことがで
きます。
自動伴奏のテンポは、演奏
中にも変えることができま
す。
66
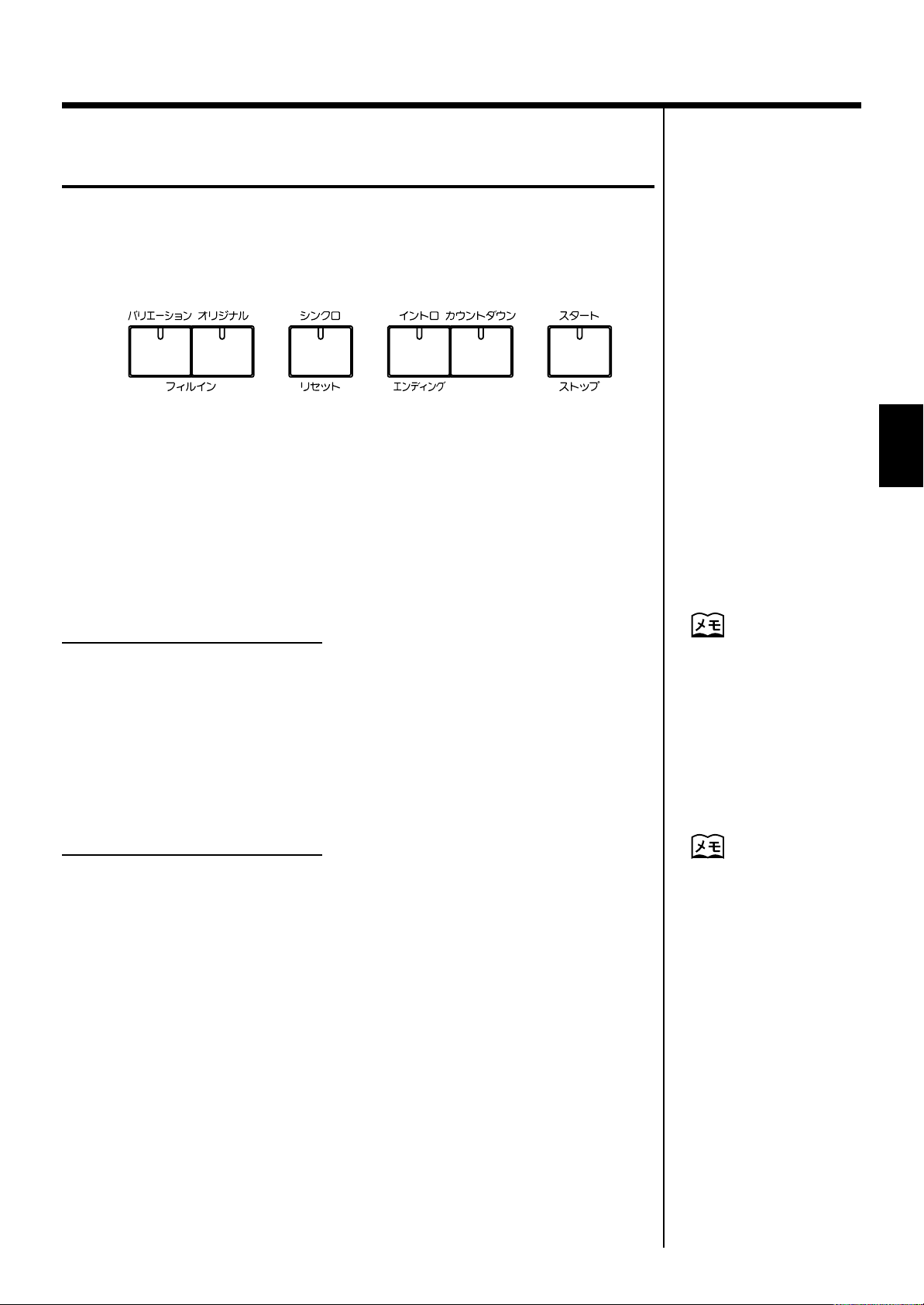
ミュージック・スタイルを鳴らす
(スタート/ストップ)
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押して、鍵盤を弾くと、伴奏がシン
クロ・スタート(鍵盤左側を弾くと同時に伴奏がスタート)して、伴奏に
ふさわしいイントロが自動的に演奏される設定になります。このようなス
タートの方法や、ストップの方法をいろいろと変えることができます。
fig.02-13
第 2 章 自動伴奏
■ 鍵盤左側を弾くと同時に自動伴奏をスタートする (シンクロ・スタート)
1.
2.
イントロを短くシンプルにする
1.
2.
3.
イントロなしでスタートさせる
1.
2.
[シンクロ/リセット]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
[イントロ/エンディング]ボタンのランプが点滅します。
鍵盤左側でコードを指定します。
イントロが演奏されて自動伴奏がスタートします。
[シンクロ/リセット]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
フィルイン[オリジナル]ボタンを押して、ボタンのランプ
を点滅させます。
鍵盤左側で、コードを弾きます。
短いイントロがついて、伴奏がスタートします。
コードを指定する前に、次の操作をすることで、イントロを鳴らさないよ
うにすることができます。
[イントロ/エンディング]ボタンを押して、ランプを消灯させ
ます。
鍵盤左側でコードを指定します。
第2章
フィルイン[オリジナル]
ボタンや[バリエーショ
ン]ボタンを押すと、伴奏
パターンも変わります。詳
しくは「伴奏に変化をつけ
る」(P.70)をご覧くださ
い。
自動伴奏を止めた後で、も
う一度シンクロ・スタート
させるときは、[シンクロ
/リセット]ボタンを押し
てランプを点灯させてから
コードを指定します。
イントロは演奏されずに自動伴奏がスタートします。
■ ボタンを押してスタートする
1.
2.
[シンクロ/リセット]ボタンを押して、ランプを消灯させます。
[イントロ/エンディング]ボタンのランプも消灯します。
鍵盤左側で最初のコードを指定します。
67

第 2 章 自動伴奏
・
3.
[イントロ/エンディング]ボタンまたは[スタート/ストッ
プ]ボタンを押します。
自動伴奏がスタートします。
[スタート/ストップ]ボタンを押した場合は、イントロは演奏されません。
コード・トーンとベース・トーン
[シンクロ/リセット]ボタンのランプが消灯しているときに鍵盤左側の鍵
を押さえると、コードが鳴ります。この音を「コード・トーン」といい、
同時に鳴るコードのルート音を「ベース・トーン」といいます。
■ 自動伴奏をストップする
エンディングをつけてストップする
1.
エンディングを短くシンプルにする
[イントロ/エンディング]ボタンを押します。
エンディングが演奏されてから、自動伴奏がストップします。
「コード・トーン」や
「ベース・トーン」の音色
を変えることができます。
「コード・トーンやベース
トーンの音色を変える」
(P.138)をご覧ください。
1.
2.
フィルイン[オリジナル]ボタンまたは[バリエーション]
ボタンを押して、ランプを点滅させます。
[オリジナル]ボタンまたは[バリエーション]ボタンのラン
プが点滅している間に、[スタート/ストップ]ボタンを押し
ます。
短いエンディングが演奏されてから、伴奏がストップします。
ボタンを押すと同時にストップさせる
1.
[スタート/ストップ]ボタンを押します。
ボタンを押すとすぐに、自動伴奏がストップします。
■ 伴奏の途中でタイミングを合わせて再スタートする(リセット)
演奏の途中で、伴奏とずれてしまったときに、このボタンを押すと、あら
ためてディビジョン(P.60)の先頭から演奏することができます。
fig.02-14
フィルイン[オリジナル]
ボタンや[バリエーショ
ン]ボタンを押すと、伴奏
パターンも変わります。詳
しくは「伴奏に変化をつけ
る」(P.70)をご覧くださ
い。
1.
68
[シンクロ/リセット]ボタンを押します。
すぐにカウント音が鳴り、続けて伴奏がスタートします。

イントロの終わりにカウント音を鳴らす
イントロをつけて演奏するとき、イントロの終わりにカウント音を鳴らし
て、演奏を始める場所を分かりやすくすることができます。
fig.02-15
第 2 章 自動伴奏
1.
2.
3.
[カウントダウン]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
[イントロ/エンディング]ボタンを押します。
イントロが始まり、イントロの終わりに1 小節のカウント音が鳴ります。
[シンクロ/リセット]ボタンのランプが点灯しているときは、鍵盤左側で
コードを指定すると、イントロが始まり、同じように、カウント音が鳴り
ます。
fig.02-16.j(模式図?1、2、3、はい)
例)4分の4拍子
カウントダウンを止めるときは、[カウントダウン]ボタンを
押して、ランプを消灯させます。
イントロ
第2章
イントロが終わり、
伴奏が演奏されます
〜
1 2 3 はい
カウント音
69
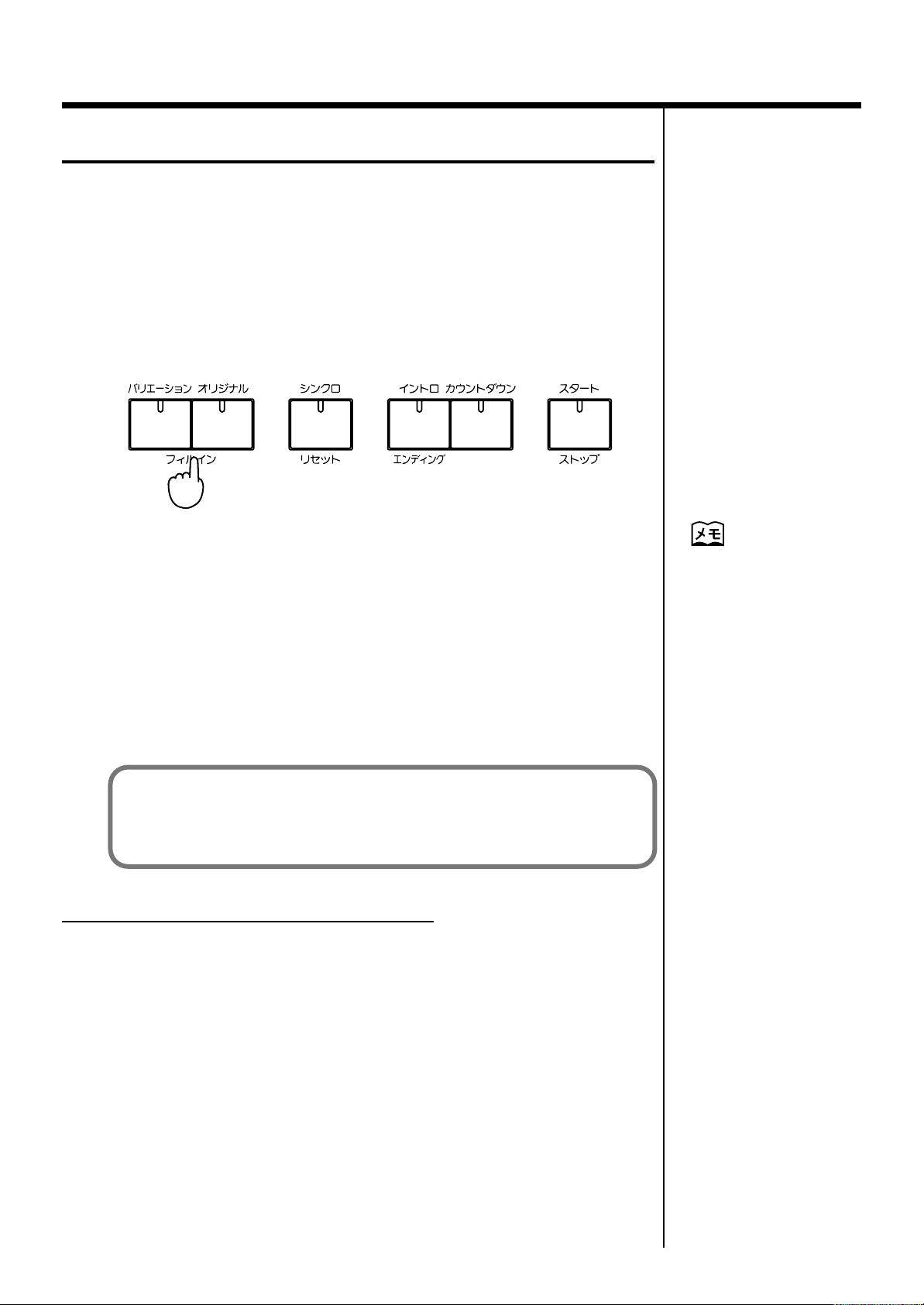
第 2 章 自動伴奏
伴奏に変化をつける
自動伴奏のアレンジ(編曲内容)や伴奏パターンを変えることができます。
■ 曲中で伴奏パターンを変える(フィルイン)
伴奏パターンには、オリジナルの伴奏パターンと、バリエーションの伴奏
パターンの2 つがあります。また、伴奏パターンの変わり目には、フィル
イン(短いフレーズ)が入り、曲にメリハリがつきます。
曲の前半部分は静かなオリジナル、後半の盛り上がる部分でバリエーショ
ンの伴奏パターンに変える、という使い方をすると効果的です。
fig.02-17
1.
フィルイン[バリエーション]ボタンを押してランプを点灯
させると、バリエーションの伴奏パターンが演奏される設定
2.
になります。
フィルイン[オリジナル]ボタンを押してランプを点灯させる
と、オリジナルの伴奏パターンが演奏される設定になります。
演奏中にこれらのボタンを押すと、ボタンを押したタイミングでフィルイ
ンが1 小節入り、伴奏パターンが変わります。
フィルインとは
曲の節目に即興的に入る短いフレーズのことを、「フィル イン」といいます。
選ばれているミュージック・スタイルに最適なフレーズが演奏されます。
伴奏パターンを変えずにフィルインを入れる
演奏中に、フィルイン[オリジナル]ボタンとフィルイン[バリエーショ
ン]ボタンのうちランプが点灯している方のボタンを押すと、伴奏パター
ンを変えずにフィルインだけを鳴らすことができます。
ペダルを使ってアレンジや
伴奏パターンを変えたり、
フィルインを入れたりする
ことができます。また、演
奏中にフィルインを入れず
に伴奏パターンを変えるこ
ともできます。「ペダルに
機能を割り当てる」
(P.139)をご覧ください。
70
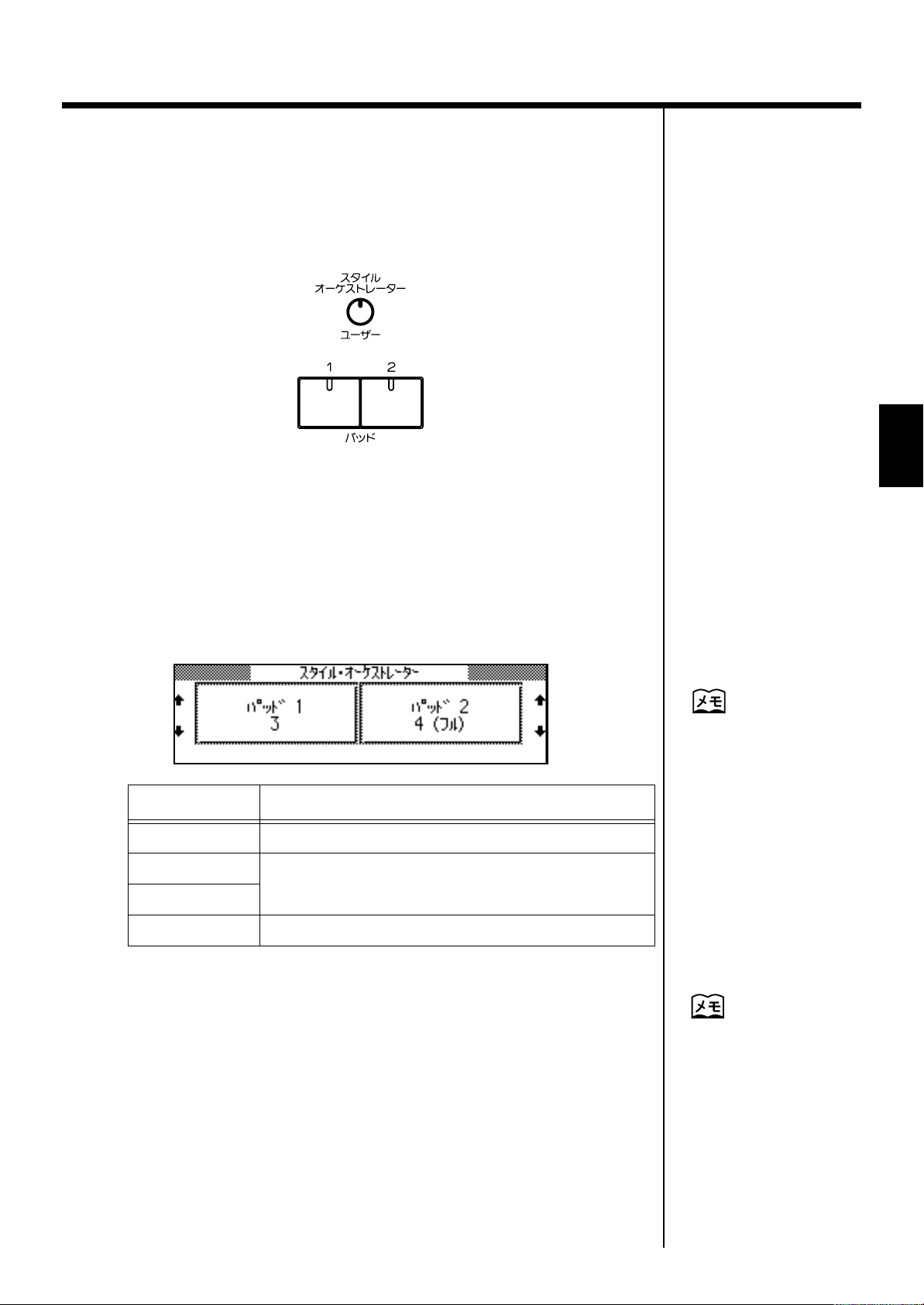
■ 伴奏のアレンジを変える
機
自動伴奏の演奏中や停止中に、伴奏のアレンジ(編曲内容)を変えること
ができます。この機能を、「スタイル・オーケストレーター」といいます。
スタイル・オーケストレーターは各ミュージック・スタイルにつき4 段階
あります。
fig.02-18
第 2 章 自動伴奏
第2章
1.
[スタイル・オーケストレーター/ユーザー]ボタンを押し
て、ランプを点灯させます。
パッド[1]または[2]ボタンで、アレンジを変えることができるように
なります。
次のような画面が表示されます。
現在パッド・ボタンに割り当てているスタイル・オーケストレーターの値
が表示されます。
fig.02-19-2.j
表示 解説
1(シンプル) 最もシンプルなアレンジです。
2
より華やかなアレンジです。
3
4(フル) 最も華やかなアレンジです。
[スタイル・オーケスト
レーター/ユーザー]ボタ
ンのランプが消灯している
ときは、パッド・ボタンで
スタイル・オーケストレー
ターを変えることができま
せん。「パッド・ボタンに
能を割り当てる」
(P.139)を参照してくだ
さい。
2.
3.
[戻る]ボタンを押します。
元の画面に戻ります。
パッド[1]または[2]ボタンを押して、伴奏のアレンジを
変えます。
ミュージック・スタイルの
中には、左記の操作をして
もアレンジが変わらないも
のがあります。
71
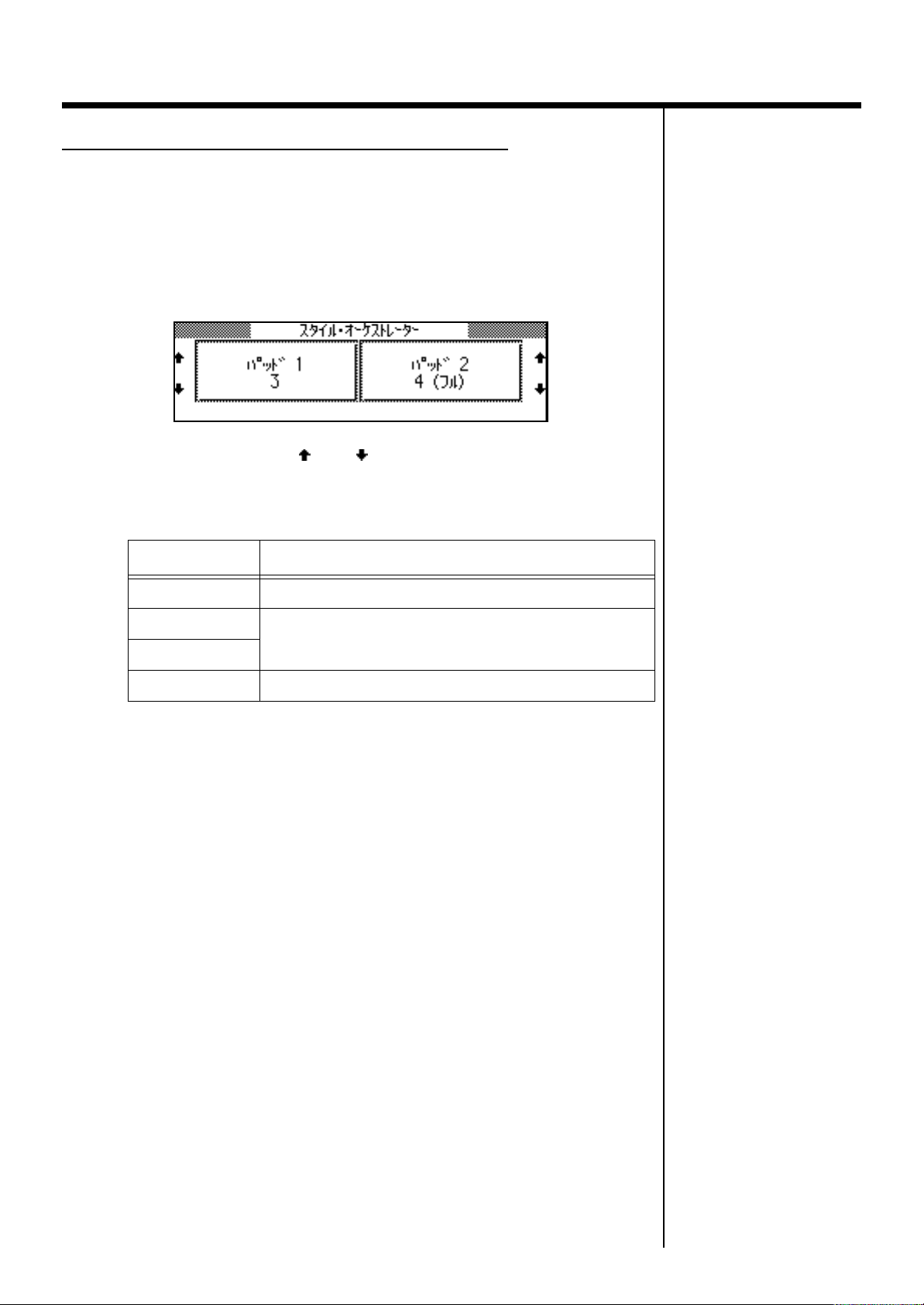
第 2 章 自動伴奏
スタイル・オーケストレーターの割り当てを変更する
パッド[1]または[2]ボタンに割り当てるスタイル・オーケストレー
ターの値を変更することができます。
1.
2.
[スタイル・オーケストレーター/ユーザー]ボタンを押し
て、ランプを点灯させます。
次のような画面が表示されます。
fig.02-19-2.j
ディスプレイ横の< >< >で、割り当てる値を選びます。
ディスプレイ左横のボタンでパッド[1]に割り当てる値が変わります。
ディスプレイ右横のボタンでパッド[2]に割り当てる値が変わります。
表示 解説
1(シンプル) 最もシンプルなアレンジです。
2
より華やかなアレンジです。
3
3.
4(フル) 最も華やかなアレンジです。
[戻る]ボタンを押します。
パッド[1]または[2]ボタンを押すと、伴奏のアレンジが変わります。
72

右手で弾いた音にハーモニーをつける
(メロディー・インテリジェンス)
鍵盤で弾いた音に、ハーモニーをつけることができます。
自動伴奏で演奏しているときは、右手で弾いた音に、鍵盤左側で指定した
コードに合ったハーモニーが自動的につきます。この機能を「メロ
ディー・インテリジェンス機能」といいます。
fig.02-20
第 2 章 自動伴奏
第2章
1.
2.
3.
[メロディー・インテリジェンス]ボタンを押して、ランプを
点灯させます。
鍵盤右側を弾くと、鍵盤で弾いた音にハーモニーがつきます。
次のような「メロディー・インテリジェンス画面」が表示されます。
fig.02-21.j
ディスプレイ下のページ< >< >で画面を切り替えて、
ハーモニーの種類を選びます。
鍵盤を弾くと、鍵盤で弾いた音に、選んだ種類のハーモニーがつきます。
[戻る]ボタンを押すと、メロディー・インテリジェンス機能が設定された
状態で、画面だけ元の画面に戻ります。
メロディー・インテリジェンス機能を解除するときは、[メロ
ディー・インテリジェンス]ボタンを押して、ランプを消灯
させます。
ハーモニーの種類の中に
は、音色を自動的に変える
ものがあります。また、い
くつかの鍵を同時に弾いた
場合には、一つの音にハー
モニーがつくことがありま
す。
73

第 2 章 自動伴奏
通常のピアノ演奏に自動伴奏をつける
(ピアノ・スタイル・アレンジャー)
通常の自動伴奏の演奏では、鍵盤左側でコードを指定して伴奏を鳴らし、
鍵盤右側でメロディーを弾きますが、鍵盤を分けずに鍵盤全体でコードを
認識するようにして、自動伴奏で演奏することができます。この機能を
「ピアノ・スタイル・アレンジャー」といいます。
鍵盤が分かれる場所を意識せずに自動伴奏をつけて演奏することができます。
1.
2.
3.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
fig.02-22.j(画面)
ディスプレイ下の<スプリット>を押して、スプリット演奏
を解除します。
画面が次のように変わります。
fig.02-22.j(画面)
スプリットオフ
スタイル・ボタンを押して、ミュージック・スタイルを選び
4.
74
ます。
[戻る]ボタンを押すと、基本画面に戻ります。
鍵盤を弾きます。
コードを弾くと、伴奏がスタートします。
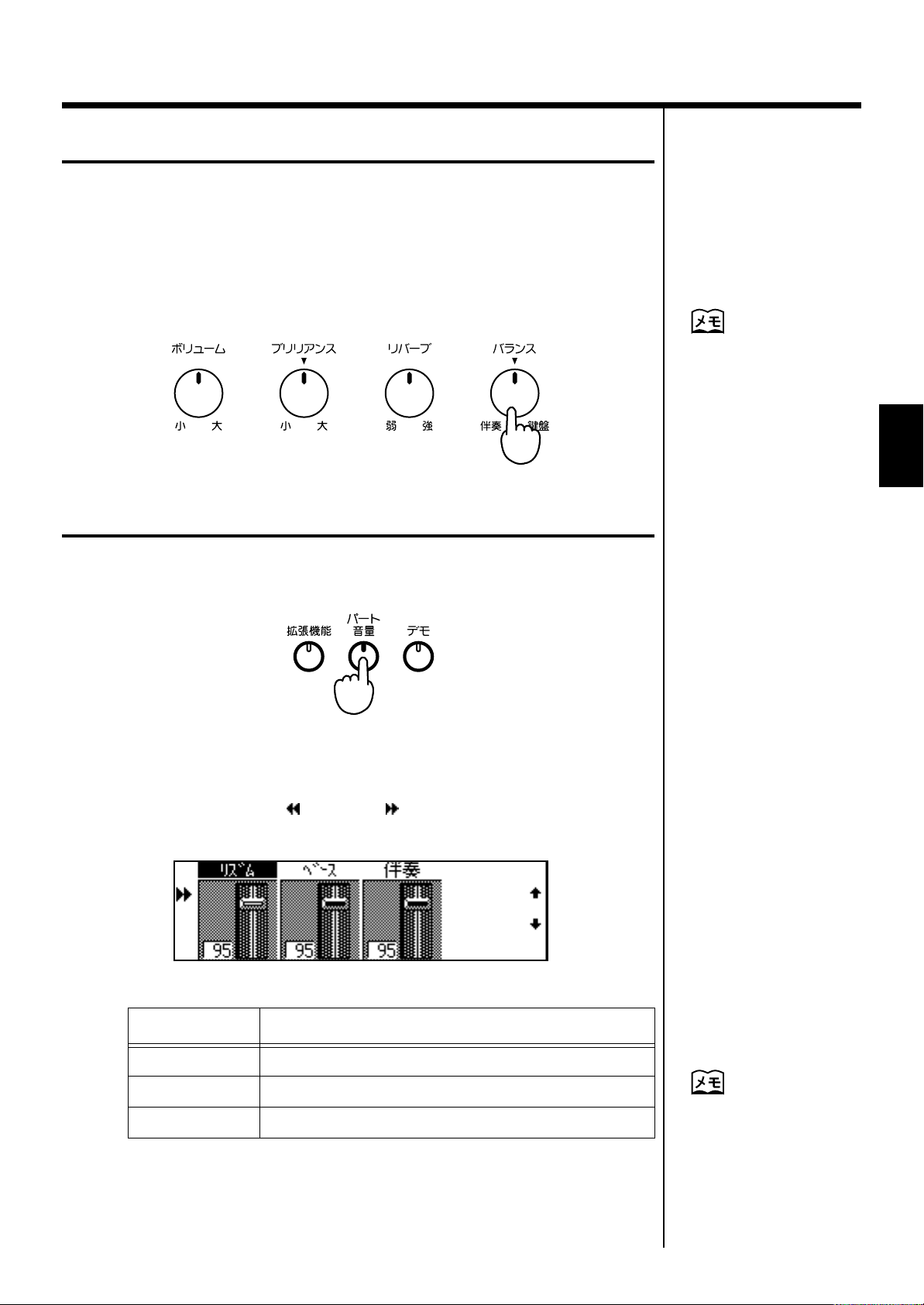
伴奏と鍵盤の音量バランスを変える
曲や伴奏の音と、鍵盤で弾いている音の音量のバランスを変えることがで
きます。
第 2 章 自動伴奏
1.
[バランス]つまみで、音量バランスを変えます。
つまみを「伴奏」側に回すと、鍵盤の音が小さくなります。
つまみを「鍵盤」側に回すと、曲や伴奏の音が小さくなります。
fig.02-23
演奏パートごとに音量を調節する
ミュージック・スタイルの各パートや、鍵盤で複数の音色を鳴らしている
ときの各音色の音量バランスを調節することができます。
fig.02-24
このつまみが一番「伴奏」
側になっていると、鍵盤を
弾いても音が聴こえませ
ん。通常は、中央の位置に
しておくようにしてくださ
い。
第2章
1.
[パート音量]ボタンを押します。
次のような画面が表示されます。
ディスプレイ左上の< >または< >を押すと、2 つの画面が切り替わ
ります。
fig.02-26.j(画面)
ミュージック・スタイルの各パートの音量バランスを表しています。
表示 パート
リズム リズム
ベース ベース、ベース・トーン(P.68)
伴奏 伴奏1、伴奏 2、伴奏 3
演奏パートについては
「ミュージック・スタイル
の構成」(P.60)をご覧く
ださい。
75

第 2 章 自動伴奏
fig.02-25.j(画面)
レイヤー演奏(P.47)やスプリット演奏(P.49)しているときの鍵盤の各
音色、または鍵盤で打楽器や効果音を鳴らしているとき(P.44)の音量バ
ランスを表しています。
表示 パート
ドラム 鍵盤で鳴る打楽器/効果音
左手 左手音色(基本画面左上に表示された音色)
レイヤー レイヤー音色(基本画面右下に表示された音色)
右手 右手音色(基本画面右上に表示された音色)
2.
3.
画面上の各ボリュームの下のボタンを押して、音量を調節す
るパートを選びます。
ディスプレイ右の< >< >で音量を調節します。
選んだパートの音量が変わります。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
76

第 3 章 曲の練習に便利な機能
。
練習する曲を再生する
市販のミュージックデータや、フロッピー・ディスクに保存した曲を再生
しながら練習してみましょう。
巻き戻しや早送りなど、簡単に小節を移動して、その位置から再生をする
ことができます。
fig.03-01
1.
2.
3.
4.
5.
6.
フロッピー・ディスクをディスク・ドライブに入れます。
[曲]ボタンを押します。
曲リスト画面が表示されます。
ディスプレイ横のボタンで曲を選びます。
ディスク内に4 曲以上の曲が入っている場合は、ディスプレイ下のページ
< >< >を押して、表示する曲を切り替えます。
[戻る]ボタンを数回押します。
基本画面のように、右上に小節番号が表示される画面を表示します。
再生[ ]ボタンを押します。
曲の再生が始まります。
巻戻し[ ]ボタンや早送り[ ]ボタンを押して、聴き
たい小節に移動します。
ボタンを1 回押すと、1 小節移動します。ボタンを押し続けると、連続的
に早送り、巻き戻しをすることができます。
7.
曲の再生を止めるときは、停止[ ]ボタンを押します。
曲の先頭に戻すには
1.
曲の頭[ ]ボタンを押します。
曲リスト画面下の<情報>
を押すと、選んでいる曲の
情報を見ることができます
第3章
内部メモリーに曲が記憶さ
れているときに他の曲を選
ぼうとすると、メッセージ
が表示されます。「● 次の
画面が表示されたら」
(P.78)をご覧ください。
弱起の曲(1 拍目以外で始
まる曲)を再生すると、基
本画面に表示される小節番
号は「PU」「1」「2」・・・
と表示されます。
ミュージックデータの再生
を始めると、基本画面の小
節番号の表示が反転しま
す。反転している間は、
KR-377 がフロッピー・
ディスクから演奏データを
読み出し中ですので、少し
の間お待ちください。
曲の最後に移動するには
1.
停止[ ]ボタンを押しながら、早送り[ ]ボタンを押
します。
マークで指定した区間を繰
り返す設定(P.88)にして
いるときは、マーク A と
マーク B の範囲内でしか巻
戻しや早送りをすることが
できません。
77

第 3 章 曲の練習に便利な機能
■ すべての曲を連続して再生する
すべての曲を連続して繰り返し再生することができます。この機能を
「オール・ソング・プレイ」といいます。
1.
2.
曲リスト画面で、ディスプレイ下の<全曲再生>を押します。
fig.03-05.j
すべての曲を順に再生します。最後の曲まで再生が終わると、また最初の
曲に戻って再生が始まります。
もう一度、ディスプレイ下の<全曲再生>を押します。
再生が止まります。
停止[ ]ボタンを押しても、再生が止まります。
● 次の画面が表示されたら
KR-377 の内部メモリーに曲が記録されている場合、曲を選ぼうとすると
次の画面が表示されます。
fig.03-02.j
曲を消したくない場合
ディスプレイ下の<いいえ>を押します。
曲をフロッピー・ディスクに保存してください。
保存の方法については、「曲をフロッピー・ディスクに保存する」
(P.104)をご覧ください。
曲を消す場合
ディスプレイ下の<はい>を押します。
録音した演奏や設定を変更した曲が消えます。
78

譜表表示をする
録音した演奏やフロッピー・ディスクの曲の譜表表示をすることができます。
歌詞データを含むミュージックデータを再生すると、歌詞も表示されます。
fig.03-03
1.
2.
3.
[曲]ボタンを押します。
「曲リスト画面」が表示されます。
ディスプレイ横のボタンで曲を選びます。
[譜表]ボタンを押します。
「譜表画面」が表示されます。
fig.03-04.j
第 3 章 曲の練習に便利な機能
歌詞データを含むデータの
再生中、<歌詞>を押して
も歌詞が表示されないとき
は、歌詞表示の設定が
「OFF」になっています。
「歌詞を表示させないよう
にする」(P.148)の設定
を「ON」にしてください。
第3章
表示 解説
ミュート
左手 左手パートの譜表を表示します。
右手 右手パートの譜表を表示します。
ユーザー 録音した自分の演奏の譜表を表示します。
設定
歌詞 譜表に歌詞を表示させます。
4.
再生[ ]ボタンを押します。
曲の再生が始まり、演奏に合わせて譜表も進行します。
譜表画面のご注意
曲の再生を始めると、譜表画面に が表示されます。このマークが表示されてい
•
る間は、フロッピー・ディスクから演奏データを読み出し中です。データの読み
出しには、数十秒かかるものもあります。しばらくお待ちください
表示される譜表はミュージックデータを元にして作成され、また、複雑・高度な
•
演奏の正確な表現よりもディスプレイ上での見やすさを優先しています。そのた
め、市販の楽譜とは異なる場合があり、特に詳細な譜表を必要とする高度な曲や
複雑な曲の表示には向いていません。また、16分音符より細かい音符や装飾音符
の表現はできません。
•
譜表表示画面では、歌詞や音符が画面の表示範囲から外れて、表示されないこと
があります。
曲の再生中に、譜表を表示したり、表示するパートを変えると、曲がもう一度頭
•
から再生されることがあります。
譜表表示しているパートの音を鳴らさないようにします。
ミュート中は、画面の の表示が に変わります。
表示させるパートを変更したり、譜表表示のしかたを変
えることができます(P.144)。
演奏データのないパートを
選んでいると、譜表に音符
が表示されません。<設定
>で表示させるパートを変
更してください。詳しくは
「譜表の設定を変える」
(P.144)をご覧ください。
パートについて詳しくは、
「16パートを使って多重録
音する(16 トラック・
シーケンサー)」(P.113)
をご覧ください。
79

第 3 章 曲の練習に便利な機能
)
■ グラフ/鍵盤画面で自分の演奏を確認する
1.
譜表画面で、ディスプレイ横の< >(鍵盤)または
< >(グラフ)を押します。
次のような「鍵盤画面」または「グラフ画面」が表示されます。
鍵盤画面
fig.03-05.j
この画面が表示されているときには、音階を確認することができます。
音が鳴っている鍵に印がつきます。
グラフ画面
fig.03-06.j
2.
この画面が表示されているときには、音の強さと長さを確認することがで
きます。
棒グラフの高さが音の強さ、横幅が音の長さを表わします。
2つの画面はディスプレイ右上の< >または< >を押すと切り
替わります。
どちらの画面でも、上段が再生している曲の演奏、下段が自分の演奏を表
わします。
再生[ ]ボタンを押して曲を再生し、曲に合わせて演奏し
ます。
画面で、自分の演奏を確認してみましょう。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
曲を再生しても、上段が変
わらない場合は、上段に表
示させるパート設定が合っ
ていません。「表示させる
パートを指定する」(P.81
で表示させるパートを設定
してください。
80
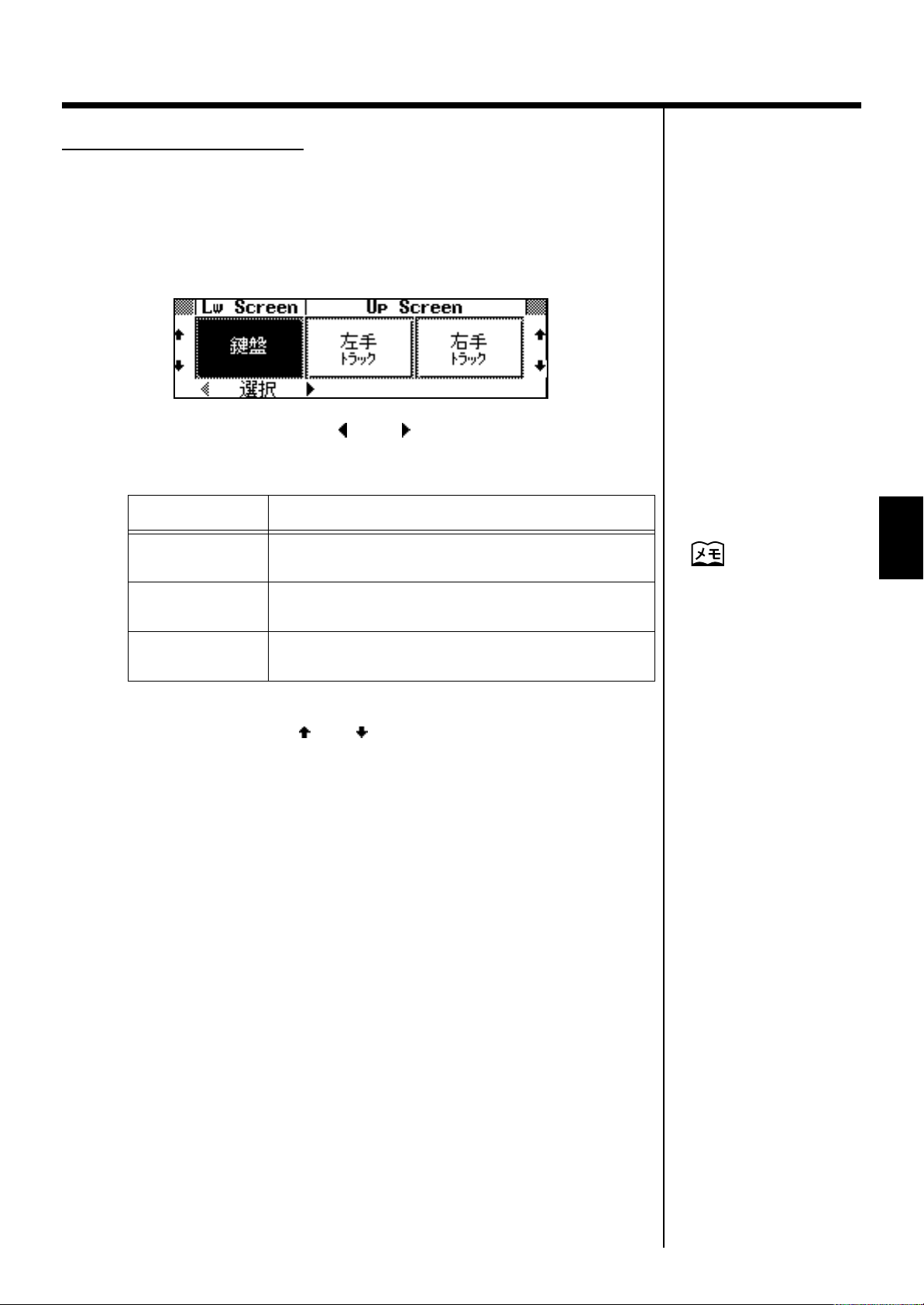
表示させるパートを指定する
表示させるパートを変えることができます。
第 3 章 曲の練習に便利な機能
1.
2.
鍵盤画面またはグラフ画面でディスプレイ右下の<設定>を
押します。
次の画面が表示されます。
fig.03-07.j
ディスプレイ下の選択< > < >で設定する項目を選びま
す。
設定 値
Lw Screen
(下段表示)
Up Screen(左)
(上段表示)
Up Screen(右)
(上段表示)
鍵盤、フル・キーボード・トラック、パート 1 〜16
左手トラック、パート 1 〜16、OFF
右手トラック、パート 1 〜16、OFF
第3章
パートについては、「16
パートを使って多重録音す
る(16トラック・シーケ
ンサー)」(P.113)をご覧
ください。
3.
4.
ディスプレイ横の< >< >を押して、表示させるパート
を切り替えます。
上段表示には、2つのパートを同時に表示させることができます。
電源投入時は、「左手トラック」と「右手トラック」が同時に表示される
設定になっていますが、必要に応じて、パート1 〜16 を選ぶこともでき
ます。
どちらかに「OFF」を選ぶと、片手だけ表示することができます。
下段表示に<鍵盤>が選ばれているときには、鍵盤の演奏が表示されま
す。演奏を録音してから、あらためてお手本の演奏と比べて確認したいと
きは、自分の演奏を録音したパートを選ぶと良いでしょう。
設定が終わったら[戻る]ボタンを押します。
鍵盤画面またはグラフ画面に戻ります
81

第 3 章 曲の練習に便利な機能
テンポを調節する
ミュージック・スタイルや曲のテンポを変えることができます。
テンポを変えても音の高さは変わりません。また、テンポは曲の再生中で
も変えることができます。
fig.03-08
1.
テンポ[−][+]ボタンで、テンポを調節します。
•
[+]ボタンを押すと、1 つずつテンポが早くなります。押し続けると、
連続的に早くなります。
•
[−]ボタンを押すと、1 つずつテンポが遅くなります。押し続けると、
連続的に遅くなります。
[+]ボタンと[−]ボタンを同時に押すと、基本のテンポに戻ります。
•
■ ボタンを押す間隔でテンポを決める
パッド・ボタンを押す間隔でテンポを決めることができます。この機能を
「タップ・テンポ」といいます。タップ・テンポ機能を使うと、数字でテ
ンポを指定しなくても、すばやく思い通りのテンポに設定することができ
ます。
タップ・テンポ機能を使うためには、パッド・ボタンに機能を割り当てて
使います。
fig.03-09
1.
2.
82
[スタイル・オーケストレーター/ユーザー]ボタンを押し
て、ランプを消灯させます。
次のような画面が表示されます。
fig.03-10.j
パッド[1]に割り当てるときは、ディスプレイ左、パッド
[2]に割り当てるときは、ディスプレイ右の< >< >を
押して「タップ・テンポ」を割り当てます。
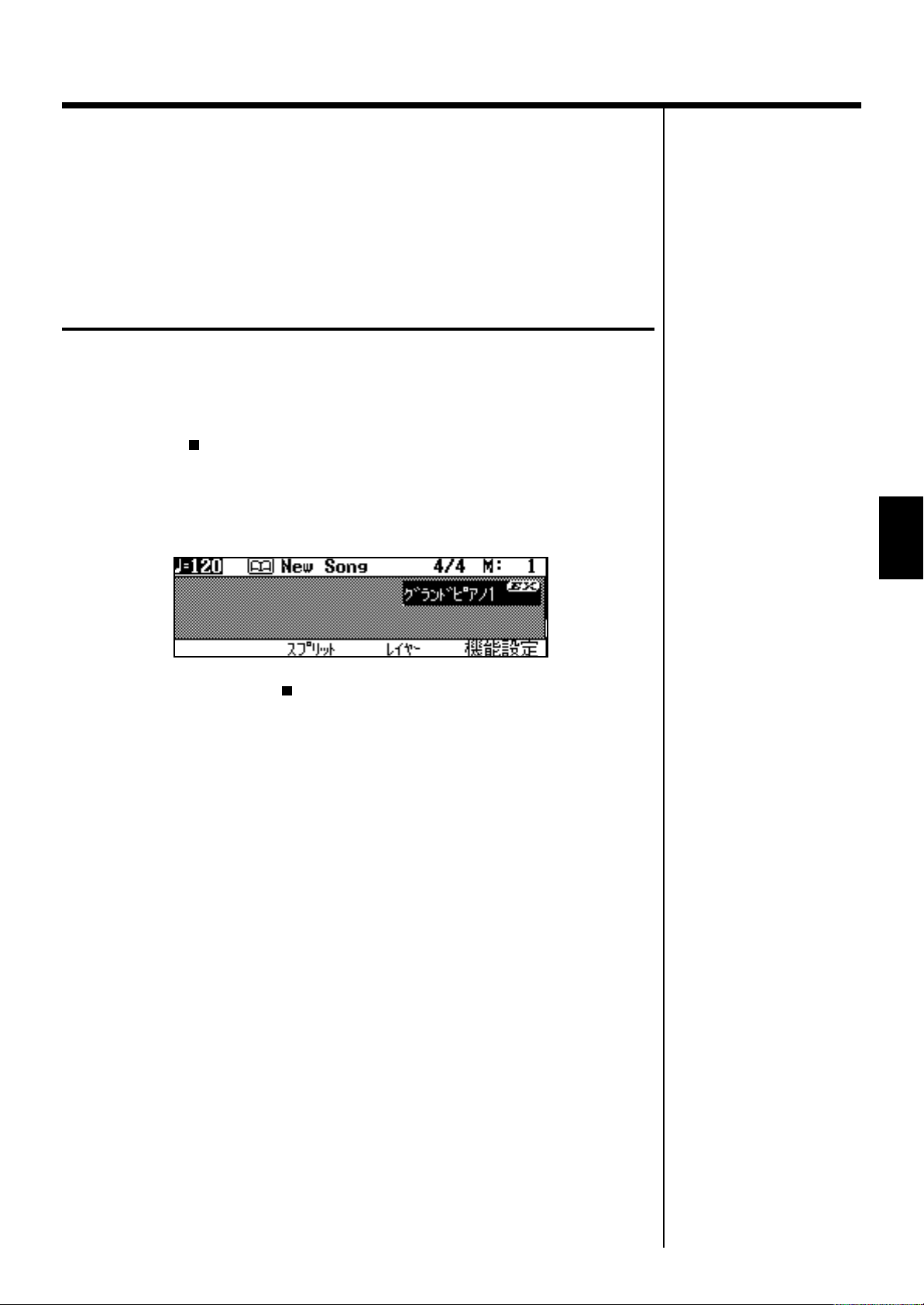
第 3 章 曲の練習に便利な機能
3.
4.
[戻る]ボタンを押します。
元の画面に戻ります。
「タップ・テンポ」を割り当てたパッド・ボタンを数回押します。
ボタンを押した間隔でテンポが調節されます。
一定のテンポで再生する
テンポの変化が難しい曲は、まず最初にテンポを一定にして練習すると効
果的です。テンポ変化をなくして一定のテンポで再生することを「テン
ポ・ミュート」といいます。
1.
停止[ ]ボタンを押しながら、テンポ[−][+]ボタンの
どちらかを押します。
曲が一定のテンポで再生されるようになります。
「テンポ・ミュート」の状態のときは、テンポの表示が反転します。
fig.03-11.j
第3章
2.
もう一度、停止[ ]ボタンを押しながら、テンポ[−]
[+]ボタンのどちらかを押します。
テンポ・ミュートが解除されます。
また、違う曲を選んでも、テンポ・ミュートは解除されます。
83

第 3 章 曲の練習に便利な機能
演奏が始まる前にカウント音を鳴らす
曲に合わせて演奏するときなど、曲を再生する前にカウント音を鳴らすこ
とで、曲と自分の演奏のタイミングを合わせることができます。
カウント音を鳴らしてから曲を再生することを「カウントイン」といいます。
1.
2.
3.
[マーク/カウントイン]ボタンを押します。
次のような「マーク画面」が表示されます。
fig.03-13.j
ディスプレイ右の<カウントイン>を押します。
<カウントイン>の表示が反転し、曲が再生される前に、2小節のカウン
ト音が鳴るようになります。
fig.03-13.j
カウント音を止めるときは、もう一度ディスプレイ右の<カ
ウントイン>を押します。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
カウントする小節数と音の
種類は変えることができま
す。「カウント音の小節数
や音を変える」(P.145)
をご覧ください。
84

練習するパートを鳴らさないようにする
複
場
市販されているピアノ・レッスン用のミュージックデータは、片手パート
ずつの再生ができますので、「曲の右手パートに合わせて右手のなぞり弾
きをする」「曲の右手パートに合わせて左手を弾く」というような、片手
ごとの練習をすることができます。
例えば、ピアノレッスン用のミュージックデータは、次のように5 つのト
ラック・ボタンに割り当てられます。
fig.03-14.j
打楽器/
効果音
このトラック・ボタンを使って、特定のパートの音を一時的に鳴らさない
ようにすることができます。
特定のパートの音を鳴らないようにすることを「ミュート」といいます。
自分で作った曲もこのようにトラック・ボタンに録音してあれば、同じよ
うにミュートすることができます。
伴奏
パート
左手
パート
右手
パート
第 3 章 曲の練習に便利な機能
ミュージックデータについ
ては、「KR-377 で使用で
きるミュージックデータ」
(P.178)をご覧ください。
1 つのトラック・ボタンに
数の楽器が含まれている
合に、1 つの楽器の音を
消して演奏したいときは、
「パートごとの設定を変え
る」(P.115)をご覧くだ
さい。
第3章
1.
2.
3.
ランプの点灯しているトラック・ボタンを押して、ボタンの
ランプを消灯させます。
選んだトラック・ボタンの音はミュートされます。
再生[ ]ボタンを押します。
曲が再生されます。
ランプが点灯しているトラック・ボタンの音は鳴りますが、ランプの消灯
しているトラック・ボタンの音は鳴りません。
ランプの消灯しているトラック・ボタンを押して、ランプを
点灯させます。
ランプを点灯させたトラック・ボタンの音が鳴るようになります。
鍵盤の音量と、曲の音量の
バランスを変えることがで
きます。「伴奏と鍵盤の音
量バランスを変える」
(P.75)をご覧ください。
85

第 3 章 曲の練習に便利な機能
曲中にマークをつけて練習する
曲中の繰り返し練習したい箇所にマークをつけておけば、簡単に小節を移
動して繰り返し再生することができます。
■ 曲中にマークをつける/取り消す
曲中に2 箇所(A / B)マークをつけておくことができます。マークは小
節の頭につきます。マークをつけておくと、何度も同じところから再生を
始めるときなど便利です。
1.
2.
3.
[マーク/カウントイン]ボタンを押します。
「マーク画面」が表示されます。
fig.03-15.j
巻戻し[ ]ボタンや早送り[ ]ボタンで、マークをつ
けたい位置に移動します。
小節番号は画面右上に表示されます。
ディスプレイ下のマーク< A >を押します。
移動した小節の頭にマークA がつきます。
画面の「---」がマークをつけた小節番号に変わります。
曲の再生中にも、同じ操作
でマークをつけたり、マー
クの場所へ移動することが
できます。
通常、マークは小節の頭に
つきますが、小節の途中に
マークがつくようにするこ
とができます。「小節の途
中にマークをつける」
(P.145)
4.
同じようにして位置を決めて、ディスプレイ下のマーク< B
>を押すとマーク B がつきます。
マークがつくと、画面にはマークのついている小節の番号が表示されます。
fig.03-16.j
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
マークを取り消す
1.
ディスプレイ下の<クリア>を押しながら、消したいマーク
の下のボタンを押します。
マークが消えて、画面の表示は<--- >になります。
マーク A とマーク B を同
じ場所につけることはでき
ません。また、マーク A よ
り前の位置にマーク B をつ
けることはできません。
86

■ マークの位置から再生する
第 3 章 曲の練習に便利な機能
1.
マーク画面で、移動したいマーク(A または B)の下のボタン
を押します。
再生開始位置がマークA やマークB をつけた位置に移動します。
fig.03-16.j
2.
再生[ ]を押すと、マークの位置から曲が再生されます。
■ マークを移動する
つけたマークを移動することができます。
マークA とB の繰り返す区間は、そのままの間隔で前後に移動すること
ができます。
1.
マーク画面で、移動したいマーク(A または B)の下のボタン
を押して、ディスプレイ左の< >や< >を押します。
第3章
マークのついた小節番号が変わります。
マーク AとBを同時に移動する
1.
マーク画面で、マーク<A>と< B>の下のボタンを両方押し
て、ディスプレイ左の< >や< >を押します。
マークA とB の間隔はそのままで移動します。
例えば5 小節目の頭にマークA、9 小節目の頭にマーク B をつけた場合
•
< >にタッチすると、マークAは 9小節目の頭に、マーク Bは13小節
目の頭に移動します。
fig.03-17.j
小節番号
•
< >にタッチすると、マークAは1小節目の頭に、マーク Bは5小節目
の頭に移動します。
fig.03-18.j
小節番号
1 591323
1 591323
4
4
678 101112 141516
マークA
678 101112 141516
マークB
マークA
マークB
87

第 3 章 曲の練習に便利な機能
同じところを繰り返し再生する
ある区間だけを繰り返し再生することができます。同じ場所を繰り返し何
度も練習するのに便利です。
1.
2.
3.
[マーク/カウントイン]ボタンを押します。
「マーク画面」が表示されます。
繰り返したい区間をはさむように、マークAとマーク Bをつけ
ます。
マークのつけかたは、86 ページをご覧ください。
例えば、5小節目から 8 小節目までを繰り返し再生したいときは、5 小節
目の頭にマークA をつけて、9 小節目の頭にマーク B をつけます。
fig.03-19.j(図)
1 5913
小節番号
2 3 4 6 7 8 101112 141516
マークA
マークB
ディスプレイ右の<リピート>を押します。
<リピート>の表示が反転し、マークA からマークB の区間が、繰り返
し再生される設定になります。
fig.03-20.j(画面)
4.
5.
再生[ ]ボタンを押します。
マークA からマークB の区間が、繰り返し再生されます。
•
マークをつけない場合は、曲の頭から最後までを繰り返し再生します。
•
マークA だけをつけた場合は、マーク A から曲の最後までの区間を繰り
返し再生します。
マークB だけをつけた場合は、曲の頭からマーク Bまでの区間を繰り返
•
し再生します。
曲を止めるときは、停止[ ]ボタンを押します。
繰り返し再生する設定を解除するときは、マーク画面で<リピート>を押
してください。
[戻る]ボタンを押すと、元の画面に戻ります。
88
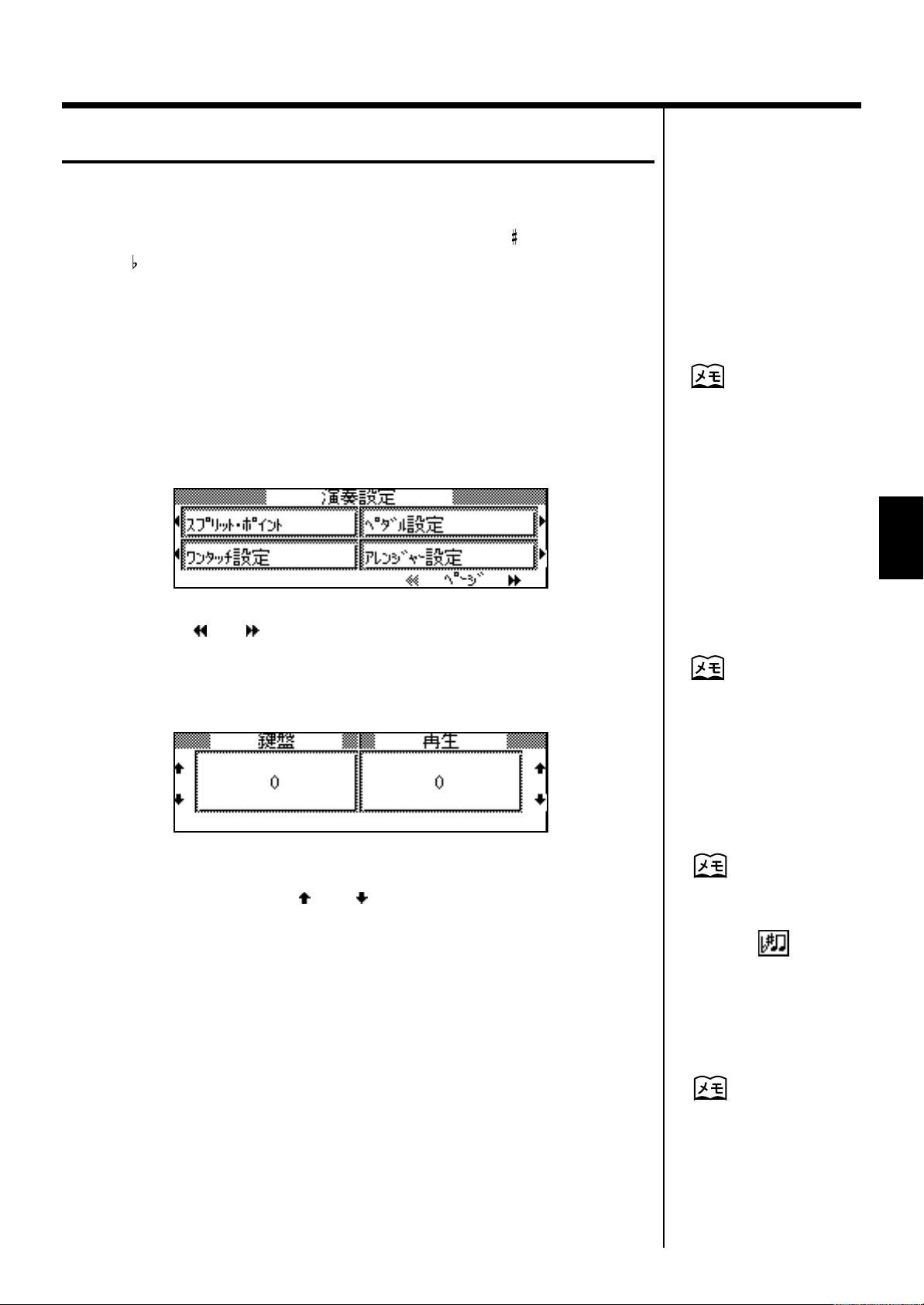
第 3 章 曲の練習に便利な機能
鍵盤の音の高さを変える(キー・トランスポーズ)
自分が弾く鍵盤の位置を変えずに、移調して演奏することができます。こ
のような機能「キー・トランスポーズ機能」といいます。
例えば、ホ長調の曲をハ長調の鍵盤の位置で弾くなど、(シャープ)や
(フラット)がたくさんついた難しい調の曲でも、自分の弾きやすい調
に変えて演奏することができます。
また、歌の伴奏をするときなど、歌う人の声の高さに合わせてキー・トラ
ンスポーズを行えば、楽譜(弾く位置)はそのままで簡単に移調すること
ができます。
1.
2.
基本画面を表示して、ディスプレイ下の<機能設定>を押し
ます。
「演奏設定画面」が表示されます。
fig.03-21.j
画面に<トランスポーズ>が表示されていないときは、ディスプレイ下の
ページ< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ横の<トランスポーズ>を押します。
次のような「トランスポーズ画面」が表示されます。
fig.03-22.j(画面)
「基本画面」(P.16)
第3章
ピアノ画面の<カスタマイ
ズ>やオルガン画面の<機
能設定>を押しても、「ト
ランスポーズ」を設定する
ことができます。
3.
4.
鍵盤の音を移調するので、<鍵盤>の値を設定をします。
ディスプレイ左の< >< >を押して、移調する値を選び
ます。
設定できる値は-6 〜 0 〜5 です。
値が「1」変わると、鍵盤の音が半音変わります。
値を 0にすると、鍵盤の移調が元に戻ります。
[戻る]ボタンを押すと、演奏設定画面に戻ります。
トランスポーズを設定して
いるときは、基本画面
(P.16)に のマーク
が表示されます。トランス
ポーズが0になっていると
きは、マークは、表示され
ません。
電源を切ったり、他の曲を
選んだりすると、移調の設
定は元に戻ります。
89

第 3 章 曲の練習に便利な機能
設
<例>ホ長調の曲をハ長調の鍵盤の位置で弾く
ここでは、ハ長調のド(C)の音を基準に考えます。ホ長調のドにあたる
ハ長調ミ(E)まで
は、黒鍵を含み上に4 鍵あるので、「4」と設定します。
fig.03-23.j
ドミソ
と弾くと
曲を移調して再生する
曲を移調して再生することができます。
♯
ミソシ
と聞こえるようになります
1.
2.
3.
4.
基本画面を表示して、ディスプレイ下の<機能設定>を押し
ます。
画面に<トランスポーズ>が表示されていないときは、ディスプレイ下の
ページ< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ横の<トランスポーズ>を押します。
次のような「トランスポーズ画面」が表示されます。
fig.03-22.j
再生する音を移調するので、<再生>の値を設定をします。
ディスプレイ右の< >< >を押して、移調する値を選び
ます。
設定できる値は-24 〜0 〜+24 です。
値が「1」変わると、再生される音が半音変わります。
値を 0にすると、曲の移調が元に戻ります。
[戻る]ボタンを押すと、演奏設定画面に戻ります。
「基本画面」(P.16)
ピアノ画面<カスタマイズ
>やオルガン画面の<機能
定>を押しても、「トラ
ンスポーズ」を設定するこ
とができます。
電源を切ったり、他の曲を
選んだりすると、移調の設
定は元に戻ります。
90

第 4 章 演奏の録音と保存
・
KR-377 では、5 つのトラック・ボタンを使って手軽に演奏を録音した
り、「16 トラック・シーケンサー」などの録音機能を使って本格的なアン
サンブルの曲を作ることができます。
簡単に演奏を録音する
自動伴奏を使わずに、鍵盤の演奏だけを録音します。
次の5 つのボタンを、トラック・ボタンといいます。
録音した演奏は、演奏パートによって5 つのトラック・ボタンに自動的に
割り当てられます。
トラック・ボタンを指定して録音をやり直すなど、トラック・ボタンごと
に録音や再生することができます。
fig.04-01
アンサンブル曲の作り方
は、「16 パートを使って多
重録音する(16トラック
シーケンサー)」(P.113)
をご覧ください。
打楽器/
効果音
伴奏
パート
左手
パート
右手
パート
自動伴奏を使わないときの演奏は、次のようにトラック・ボタンに割り当
てられます。
トラック・ボタン 録音される演奏
[R/リズム] 打楽器の音や効果音が録音されます。
自動伴奏を使わない場合、通常、このトラックに
[1 /フル・キー
ボード]
録音されます。レイヤー演奏(P.47)のときも、
このトラックに録音されます。
自動伴奏を使わない場合は録音されません。ト
[2 /ベース / 伴奏]
ラック・ボタンを指定して録音すれば(P.96)、録
音することができます。
[3 /左手]
スプリット演奏(P.49)のとき、鍵盤左側での演
奏が録音されます。
スプリット演奏(P.49)のとき、鍵盤右側での演
奏が録音されます。
[4 /右手]
レイヤー演奏(P.47)からスプリット演奏にした
ときのレイヤー音色もこのトラックに録音されま
す。
第4章
通常、自動伴奏を使わないときの演奏は、トラック・ボタンの[1/フ
ル・キーボード]に録音されますが、録音するトラック・ボタンを指定す
ることもできます。
91

第 4 章 演奏の録音と保存
fig.04-02
その 1 録音の準備をする
1.
2.
3.
4.
[曲]ボタンを押します。
曲リスト画面が表示されます。
fig.04-03.j
ディスプレイ横の<0:>を押して、<0: New Song>を表示さ
せます。
画面に<0: >が表示されていないときは、ディスプレイ下のページ<
>< >を押して画面を切り替えます。
[ワンタッチ・ピアノ]ボタンを押します。
演奏する音色、テンポ、拍子を決めます。
音色ボタンやディスプレイ横のボタンを使って音色を選んでください。
必要であれば[メトロノーム]ボタンでメトロノームを鳴らしてください。
テンポと拍子の選び方につ
いては、P.56をご覧くだ
さい。
5.
録音[ ]ボタンを押します。
再生[ ]ボタンのランプが点滅して、録音待機状態になります。
録音を中止したいときは、停止[ ]ボタンを押します。
その 2 演奏を録音する
6.
7.
再生[ ]ボタンを押して、録音を始めます。
2小節のカウント音が鳴ってから、録音が始まります。
再生[ ]ボタンを押さなくても、鍵盤を弾いて録音を始めることもで
きます。このときは、カウント音は鳴りません。
録音が始まると、再生[ ]ボタンのランプが点灯に変わります。
停止[ ]ボタンを押して、録音を止めます。
92

録音した演奏を聴く
第 4 章 演奏の録音と保存
1.
2.
3.
曲の頭[ ]ボタンを押します。
曲の先頭から再生するようになります。
再生[ ]ボタンを押します。
録音した演奏が再生されます。
演奏を止めるときは、停止[ ]ボタンを押します。
●次の画面が表示されたら
内部メモリーに曲が記憶されているときに、他の曲を選ぼうとすると、次
の画面が表示されます。
fig.04-04.j
曲を消したくない場合
ディスプレイ下の<いいえ>を押します。
曲をフロッピー・ディスクに保存してください。
保存の方法については、「曲をフロッピー・ディスクに保存する」
(P.104)をご覧ください。
電源を切ると、録音した演
奏は消えてしまいます。録
音した演奏を消したくない
ときは、フロッピー・ディ
スクに保存してください。
保存の方法については、
「曲をフロッピー・ディス
クに保存する」(P.104)
をご覧ください。
録音した演奏を消すまで
は、他の曲を聴くことはで
きません。「録音した曲を
消す」(P.97)をご覧くだ
さい。
第4章
曲を消す場合
ディスプレイ下の<はい>を押します。
録音した演奏や設定を変更した曲が消えます。
93

第 4 章 演奏の録音と保存
自動伴奏を使って録音する
自動伴奏を使った演奏を録音します。
録音した演奏は、次のようにトラック・ボタンに割り当てられます。
トラック・ボタン 録音される演奏
自動伴奏のリズム・パートが録音されます。また、
[R/リズム]
ドラム・セットと効果音セットなどを選んで演奏
した場合は、この場所に録音されます。
[1 /フル・キー
ボード]
[2 /ベース・伴
奏]
[3 /左手]
[4 /右手] 鍵盤右側での、自分の演奏が録音されます。
その 1 録音の準備をする
ピアノ・スタイル・アレンジャーの状態のとき
(P.74)に、自分の演奏が録音されます。
自動伴奏のベース・パートと伴奏パートの演奏が
録音されます。
自動伴奏を鳴らしながら鍵盤左側で音を鳴らす設
定になっているとき(P.65)に、鍵盤左側での自
分の演奏が録音されます。
ミュージック・スタイルは
5つのパートで構成されて
います。詳しくは「ミュー
ジック・スタイルの構成」
(P.60)
1.
2.
94
[曲]ボタンを押します。
曲リスト画面が表示されます。
fig.04-03.j
ディスプレイ横の<0:>を押して、<0: New Song>を表示さ
せます。
画面に<0: >が表示されていないときは、ディスプレイ下のページ<
>< >を押して画面を切り替えます。

その 2 演奏の準備をする
第 4 章 演奏の録音と保存
3.
4.
5.
6.
7.
その 3 録音を始める
8.
[ワンタッチ・アレンジャー]ボタンを押します。
スタイル・ボタンとディスプレイ横のボタンで、ミュージッ
ク・スタイルを選びます。
[戻る]ボタンを押します。
基本画面が表示されます。
テンポ[−][+]ボタンで、伴奏のテンポを調節します。
テンポ[−][+]ボタンを同時に押すと、選んでいるスタイルの基本テ
ンポに戻すことができます。
録音[ ]ボタンを押します。
録音待機状態になります。
録音を中止したいときは、停止[ ]ボタンを押します。
鍵盤左側でコードを押さえます。
第4章
自動伴奏がスタートして、同時に録音も始まります。
その 4 録音を止める
9.
録音した演奏を聴く
1.
2.
3.
[イントロ/エンディング]ボタンを押します。
エンディングが演奏されてから自動伴奏がストップし、同時に録音も止ま
ります。
曲の頭[ ]ボタンを押します。
曲の先頭から再生するようになります。
再生[ ]ボタンを押します。
録音した演奏が再生されます。
演奏を止めるときは、停止[ ]ボタンを押します。
自動伴奏の演奏を録音する
ときの、録音の止め方を変
えることができます。「録
音の止め方を変える」
(P.98)をご覧ください。
95

第 4 章 演奏の録音と保存
録音をやり直す
録音をやり直すときは、あらかじめ録音し直したいトラック・ボタンを指
定して録音します。
録音済みのトラック・ボタンを選んで録音をやり直すと、録音を始めた位
置から止めた位置までが、新しく録音した演奏に変わります。
以前の演奏をすべて消して
から録音をやり直したいと
きは、「特定のトラック・
ボタンの演奏だけを消す」
(P.97)をご覧ください。
1.
2.
3.
4.
5.
曲の頭[ ]ボタンや早送り[ ]、巻き戻し[ ]ボタ
ンで、録音をやり直す小節に移動します。
録音[ ]ボタンを押します。
録音を中止したいときは、停止[ ]ボタンを押します。
録音をやり直したいトラック・ボタンを押します。
選んだトラック・ボタンのランプが点滅します。
再生[ ]ボタンのランプが点滅して録音待機状態になります。
録音を始めます。
自動伴奏の演奏を録音し直すときは、[シンクロ/リセット]ボタンを押
してボタンのランプを点灯させてからコードを指定するか、[スタート/
ストップ]ボタンを押します。
自動伴奏を使わないときには、再生[ ]ボタンを押します。
録音が始まると、再生[ ]ボタンのランプが点滅から点灯に変わります。
停止[ ]ボタンを押して、録音を止めます。
エンディングも録音し直すときには、[イントロ/エンディング]ボタン
を押します。
最初に録音したテンポで、
曲の「基本テンポ」が決ま
ります。録音をやり直すと
きにテンポを変えて録音し
ても、曲の基本テンポは変
わりません。録音した曲の
テンポを変えたいときは、
「曲の基本テンポを変える」
(P.117)をご覧ください。
96

録音した曲を消す
録音した曲を消すことができます。
第 4 章 演奏の録音と保存
1.
2.
[曲]ボタンを押しながら、録音[ ]ボタンを押します。
次の画面が表示されます。
fig.04-04.j
ディスプレイ下の<はい>を押すと、録音した曲が消えます。
ディスプレイ下の<いいえ>を押すと、録音した曲は消されません。
■ 特定のトラック・ボタンの演奏だけを消す
トラック・ボタンごとに、録音した演奏を消すことができます。
1.
録音した演奏を消したいトラック・ボタンを押しながら、録
音[ ]ボタンを押します。
選んだトラック・ボタンのランプが消灯して、録音した演奏が消えます。
録音した曲の基本テンポや
拍子の設定は消すことはで
きません。
第4章
97
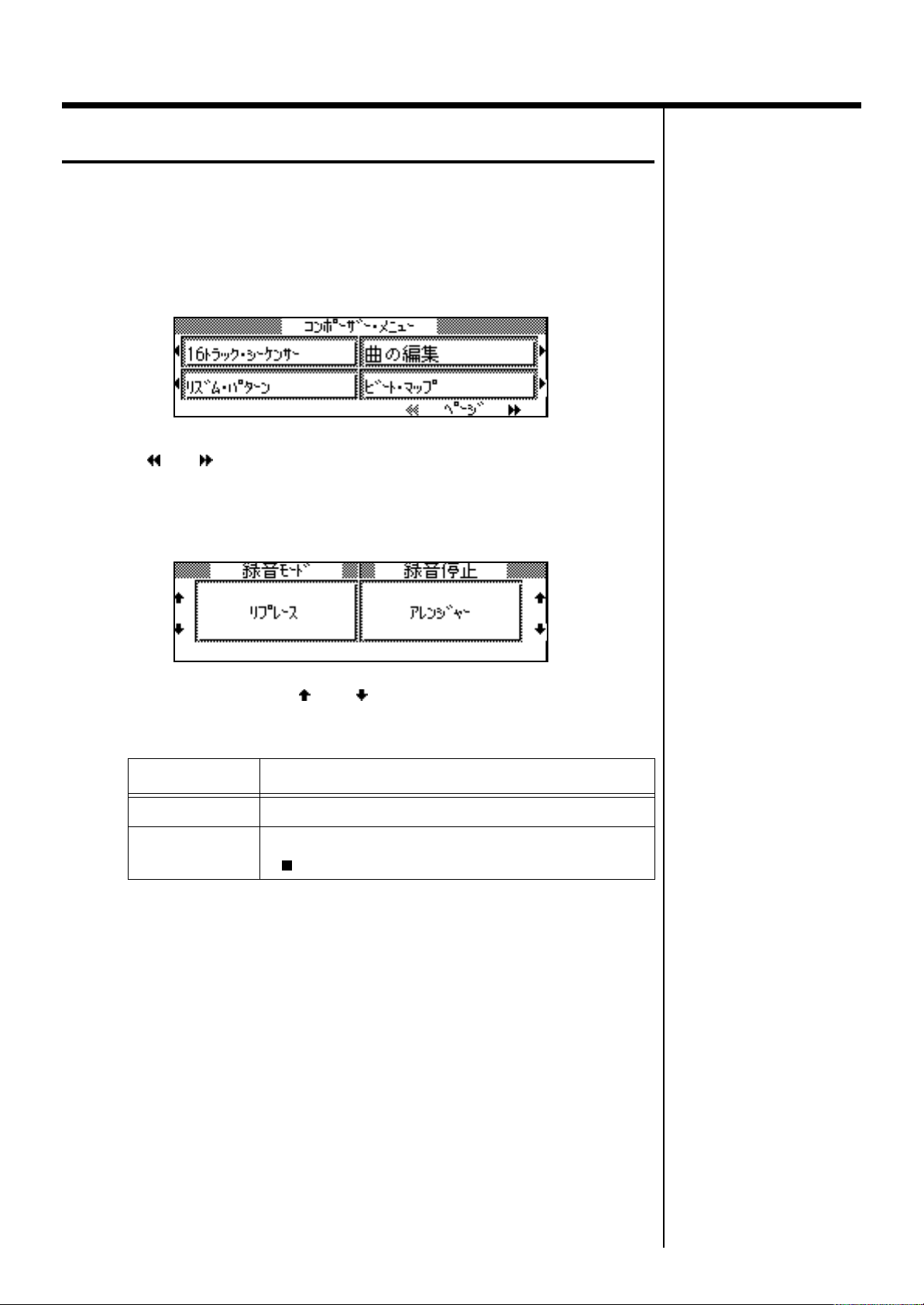
第 4 章 演奏の録音と保存
録音の止め方を変える
自動伴奏の演奏を録音するときの、録音の止め方を変えることができま
す。
1.
2.
3.
[メニュー]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
コンポーザー・メニュー画面が表示されます。
fig.04-08.j
画面に<録音設定>が表示されていないときは、ディスプレイ下のページ
< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ横の<録音設定>を押します。
次の画面が表示されます。
fig.04-09.j
ディスプレイ右の< >< >を押して、<録音停止>の
「アレンジャー」と「コンポーザー」を切り替えます。
表示 解説
アレンジャー 自動伴奏が止まるのと同時に、録音が終わります。
コンポーザー
[戻る]ボタンを押すと、コンポーザー・メニュー画面に戻ります。
自動伴奏が止まっても録音が終わりません。停止
[ ]ボタンを押すと、録音が終わります。
98

弱起の曲を録音する
弱起(アウフタクト)の曲を録音することができます。1拍目以外で始ま
る曲のことを、「弱起の曲」といいます。
第 4 章 演奏の録音と保存
1.
2.
3.
4.
5.
[曲]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
< 0: >を選んで< 0:New Song >を表示させます。
画面に<0: >が表示されていないときは、ディスプレイ下のページ<
>< >を押して画面を切り替えます。
[戻る]ボタンを数回押します。
基本画面のように、右上に小節番号が表示される画面を表示します。
録音[ ]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
録音待機状態になります。
巻戻し[ ]ボタンを 1 回押します。
基本画面右上の小節番号が「PU」に変わります。
fig.04-10.j
第4章
6.
7.
再生[ ]ボタンを押して、録音を始めます。
fig.04-11.j
カウント音
小節番号
-2
PU 1
ここから録音が始まります
録音を止めるときは、停止[ ]ボタンを押します。
〜
99
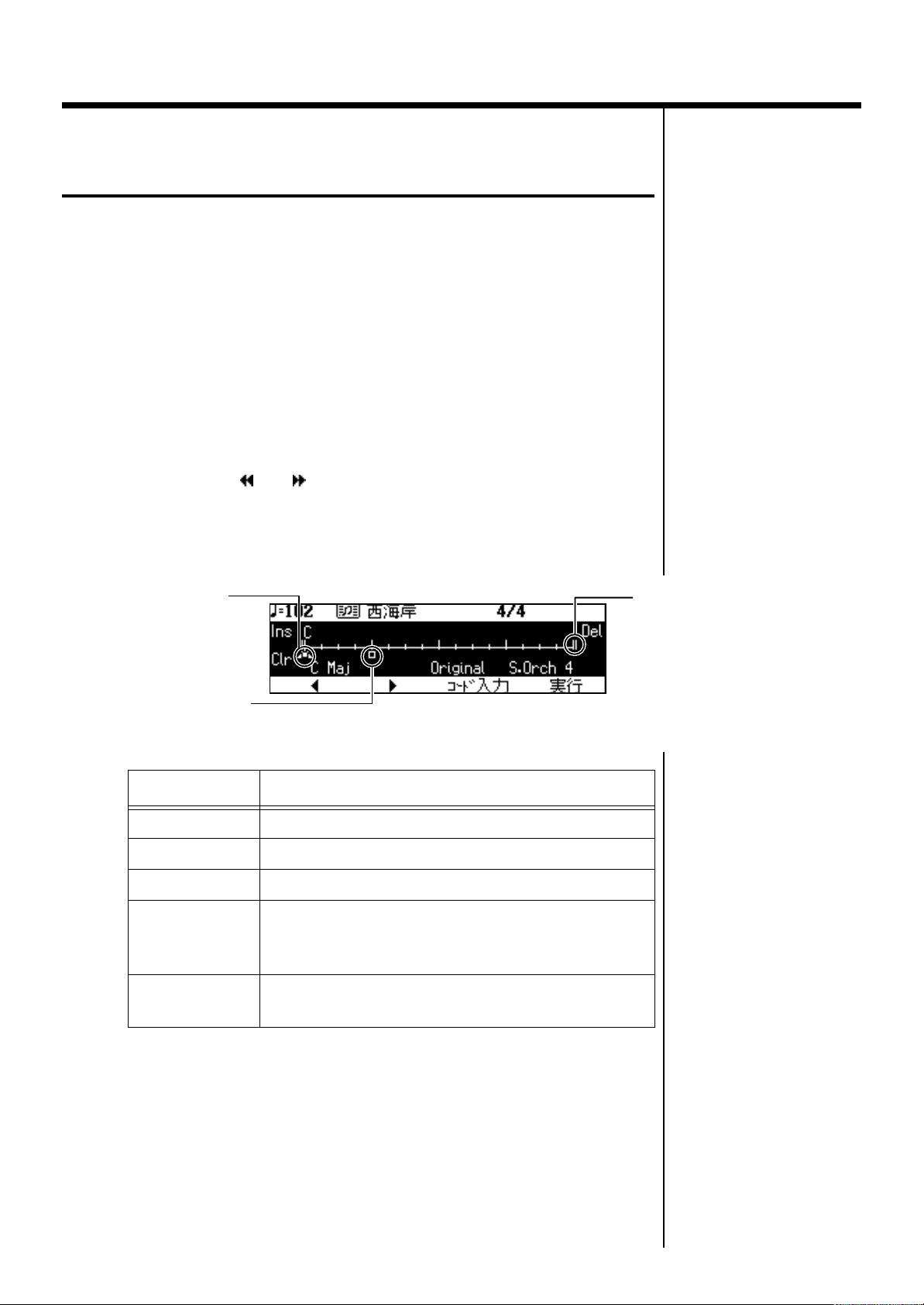
第 4 章 演奏の録音と保存
コードを入力して曲の伴奏を作る
(コード・シーケンサー)
曲のコード進行や伴奏パターンの変わる位置などを入力して、鍵盤で演奏
しなくても、曲の伴奏を作ることができます。この機能を「コード・シー
ケンサー」といいます。
コード・シーケンサーを使うと、あらかじめ伴奏を作っておき、その伴奏
に合わせて右手だけ演奏できますので、より簡単に自動伴奏を楽しむこと
ができます。
1.
2.
入力する位置を表します。
[メニュー]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
コンポーザー・メニュー画面が表示されます。
画面に<コード・シーケンサー>が表示されていないときは、ディスプレ
イ下のページ< >< >を押して画面を切り替えます。
ディスプレイ横の<コード・シーケンサー>を押します。
次のような画面を「コード・シーケンサー画面」といいます。
fig.04-12.j
カーソルといいます。
伴奏パターン(ディビジョ
ン)や、スタイル・オーケ
ストレーターが切り替わる
位置を表します。
表示 解説
< Ins > カーソルのある小節の前に1 小節挿入します。
曲の終わりです。
入力を続けるときは、
[Ins]を押して
小節を挿入します。
3.
4.
100
< Del > カーソルのある小節を削除します。
< Clr > カーソルの位置の設定を消去します。
鍵盤を弾かずにコードを入力することができます。
<コード入力>
<実行>
「鍵盤を弾かずにコードを入力する」(P.102)をご覧
ください。
作った伴奏を曲データにします。すべての入力が終
わったら、このボタンを押します。
スタイル・ボタンとディスプレイ横のボタンを使って、
ミュージック・スタイルを選びます。
[戻る]ボタンを押します。
コード・シーケンサー画面に戻ります。
 Loading...
Loading...